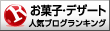那須オルゴール博物館へ行ったときに、こんなものがありました。

「紙腔琴」、国産の手回しオルガンのようです。
明治の中頃、作った人は「戸田 欽堂」という人。(政治小説家でもあったとか)
小学校などで需要があり、5800台も作られたそうです。
大変な人気で「偽物」まで出回ったようで、注意書きがありました。
(その“偽物”も見てみたい!)
浮世絵になっていたのも、似たようなものでしょうか。
(チャルゴロとは?)

今ならピアノが弾けないとCDに頼りますが、
当時はこの「紙腔琴」で歌の練習などしたのでしょうか。
挿しこむ紙の曲の種類も「唱歌」はもちろん、
「長唄」や「軍歌」や「賛美歌」まであり、随分幅広かったようです。

「紙腔琴」、国産の手回しオルガンのようです。
明治の中頃、作った人は「戸田 欽堂」という人。(政治小説家でもあったとか)
小学校などで需要があり、5800台も作られたそうです。
大変な人気で「偽物」まで出回ったようで、注意書きがありました。
(その“偽物”も見てみたい!)
浮世絵になっていたのも、似たようなものでしょうか。
(チャルゴロとは?)

今ならピアノが弾けないとCDに頼りますが、
当時はこの「紙腔琴」で歌の練習などしたのでしょうか。
挿しこむ紙の曲の種類も「唱歌」はもちろん、
「長唄」や「軍歌」や「賛美歌」まであり、随分幅広かったようです。