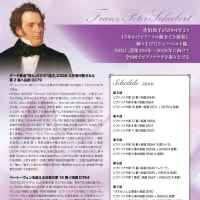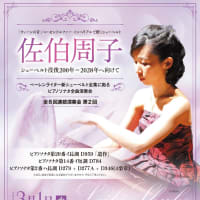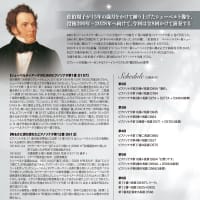真っ先に述べる必要なことがある。
の1人! 演奏会でも頻度高く演奏されるし、ピアノ教育の途上でも多く出会う。また「音楽史」では、重要な作曲家と習う。その割には、何となく印象が定まらない。
まずは魅力から列挙して見たい。
などなど。1曲づつだと、魅力あるのだが、なぜか、「部分評価 = 全体評価」には繋がっていないように思う。私高本なりに理由を考えてみた。
好きな作曲家の1人なので、CDは少なからず所有しているのだが、バルトークCDを延々と聴くと疲れる 事実は否定できない。う~ん。
バルトーク音楽の中心は「ピアノ音楽」である。管弦楽曲も多いし、オペラもあるし、バレエもあるし、声楽曲も、ヴァイオリンソロ曲もあるが、中心は「ピアノ音楽」である。ソロでCD8枚分。協奏曲と室内楽曲がこれに加えられる。
量としては充分である上に、完成度も高いのだが、なぜか「ピアノ音楽」の水準から見た時に「妙な感じ」がする。
ことである。 題名自体が 【小宇宙】 の意味だが、どうも全曲演奏は、弾く方も聴く方も敬遠気味だ。
--------
に集中している。
この期間にバルトークはなぜか、ピアノソロ曲は ミクロコスモスの後半しか作曲していない。
ピアノ作品が 「構想としての規模の不足」が否めないのは、成熟する前の作品の可能性が高い。個々の曲の魅力が高いだけに残念。もしかすると
も少なからずある。 川上敦子 出現以前は、「伊福部昭ピアノ音楽」の評価が低かったので、この可能性は高い。
主要作品 については、近日掲載予定。「バルトーク自作自演CD」から開始の予定。
バルトーク は、全体像を掴み難い作曲家
の1人! 演奏会でも頻度高く演奏されるし、ピアノ教育の途上でも多く出会う。また「音楽史」では、重要な作曲家と習う。その割には、何となく印象が定まらない。
まずは魅力から列挙して見たい。
- 力感が素晴らしい!
- 集中力が卓越しており、完成度が高い(未完成の2作品を除く)
- ハンガリーやルーマニアの「民族音楽」を生かしている
- 教育的な作品の、完成度が高い
などなど。1曲づつだと、魅力あるのだが、なぜか、「部分評価 = 全体評価」には繋がっていないように思う。私高本なりに理由を考えてみた。
- 管弦楽曲は 最後の3作品以外は「演奏会のトリ」を務める作品が無い。
- ピアノ作品は多いが、時間的にまた質感的に短く、「全バルトーク演奏会」以外だと、「トリ」を務める作品が無い(かも知れない)。
- 「心休まる」感触が皆無に近い
好きな作曲家の1人なので、CDは少なからず所有しているのだが、バルトークCDを延々と聴くと疲れる 事実は否定できない。う~ん。
バルトーク音楽の中心は「ピアノ音楽」である。管弦楽曲も多いし、オペラもあるし、バレエもあるし、声楽曲も、ヴァイオリンソロ曲もあるが、中心は「ピアノ音楽」である。ソロでCD8枚分。協奏曲と室内楽曲がこれに加えられる。
量としては充分である上に、完成度も高いのだが、なぜか「ピアノ音楽」の水準から見た時に「妙な感じ」がする。
- 「ミクロコスモス」は 全6巻 153曲 で CD2枚分もの大作!
- しかし バッハ「平均律」や ドビュッシー「前奏曲集」 ラフマニノフ「前奏曲集」 に比べて「全曲演奏会」はほどんどない
ことである。 題名自体が 【小宇宙】 の意味だが、どうも全曲演奏は、弾く方も聴く方も敬遠気味だ。
--------
バルトークの「名作」は 1936年以降
に集中している。
- 弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽(1936)
- 2台のピアノと打楽器のためのソナタ(1937)
- ヴァイオリン協奏曲第2番(1937-1938)
- コントラスト(1938)
- 弦楽器のためのディヴェルティメント(1939)
- 管弦楽のための協奏曲(1943)
- 無伴奏ヴァイオリンソナタ(1944)
この期間にバルトークはなぜか、ピアノソロ曲は ミクロコスモスの後半しか作曲していない。
ピアノ作品が 「構想としての規模の不足」が否めないのは、成熟する前の作品の可能性が高い。個々の曲の魅力が高いだけに残念。もしかすると
卓越した「バルトーク弾き」がまだ出現していないだけの可能性
も少なからずある。 川上敦子 出現以前は、「伊福部昭ピアノ音楽」の評価が低かったので、この可能性は高い。
主要作品 については、近日掲載予定。「バルトーク自作自演CD」から開始の予定。