
歴史が好きな人間として、家康を尊敬している人間として、どうする家康は見ている。リアルタイムで見るのは難しいので、NHKオンデマンドで見ている。これはいい、自分の空いた時間にいつでも見られるからだ。
ところで、このNHKオンデマンドで演技をしている俳優たちのインタビュー集のようなものがある。(現在このインタビューだけは無料で見られる)そのなかに出ている瀬名役の有村架純さんがなにか思い詰めているような一途さ、誠実さを滲ませていて、いままで瀬名にたいして理想に近い女性だと感じていたんだけど、彼女を演じているこの有村さんの話している姿を見て、瀬名とは違う意味で好感を持った。
彼女と共に印象に残ったのは巫女と忍び役を演じている古川琴音さんだ。
なにかシャーマニックな雰囲気を実物の古川さん自身も持っていることを感じたが、(そのためこの役にはぴったりの抜擢だと思った)それよりも印象に残ったのが、かなり知性の高そうな人だということ。
瀬名との会話のシーンで「危うく毒を盛られるところでした」というセリフがあるのだが、そのときに真剣な顔で話そうか少し茶化した感じにしようか迷っていて、それはその時の雰囲気で決めようと思ったと彼女が話していた。それを聞いての感想である。

彼女の経歴を見ると学生時代から演劇部に属していたと知り、あぁなるほどやはり芝居というものを専門にやってきた人だからこその言葉だなと思った。
それと同時に、このドラマの監督の方は役者にかなりの自由裁量を与えているんだなとも思った。というのも、あの世界的な巨匠、小津安二郎監督の場合は演技の非常に細かいところ(非常に微妙な視線や表情、手の変化や動きなど)まで指示して、彼の理想通りの演技になるまで何回も何回もやり直しをさせたという話を聞いていたからだ。当時の女優のインタビューを聞いたことがあるのだが、新人の頃はそれがほんとに怖くて戦々恐々として演技に挑んだといっていた。
まぁ、それはともかく、古川さんという人から放射されている知性というか、感受性というか、そういうものの尋常ではない鋭さが強く印象に残った。僕は普段ドラマや映画をあまり見ない人間なんだけど、この人が出た作品でよさそうなものがあれば見てみようと思いはじめた。
さて、役者の話はこのくらいにして、このドラマについての感想を簡単に書いてみたい。
まず家康像だが、まぁ、こんな家康像も面白いと思った(笑)というか、実際の家康にも人間である以上、こういう側面はあったに違いない。今までは前半生が描かれてきているが、こういう「迷う家康」という部分は逆に僕は彼の後半生に特に現れてきていると感じる。
そう、それは彼が秀吉亡き後の豊臣家との関係をめぐる駆け引きの中ではっきりと現れてきていると僕は感じる。
小牧長久手の後、秀吉との関係を再構築して、たとえ形の上とはいえ秀吉に臣従して以降、ライバルというよりは共に日本統一を目指して戦った「同志」的な立場になった家康。その過程でおそらく家康は人間秀吉というものに触れ、あの人たらしといわれた秀吉に一定の親しみのようなものを持っていったと僕は思う。

この過程の中で、あろうことか(と家康は思ったに違いない)家康と秀吉との間にはなにがしかの情のつながりが生まれたと考えるのが自然である。
幼少期の秀頼の姿なども目にしたこともあるはずだし、さらに秀頼には自分の孫娘まで嫁がせているのだ。
年表を見ると秀吉の死後、大阪夏の陣で豊臣家を完全に滅ぼすまでに実に17年もの歳月が流れている。この長さは豊臣家はあまりに巨大でありそれを滅ぼすにはこれだけの時間がかかったのだ、というとらえ方もできるかもしれないが、それにしてもあまりにも時間をかけすぎている。
僕はこの17年は、その間に彼がたどった葛藤、迷い、情と知の間の揺れ動きの17年であったと思う。僕が感じてきた家康という人物のひととなりというものを思うとき、そう考えるのが一番しっくりとくる。
これが信長や鎌倉政権を作った北条氏であれば、まようことなくできるだけ迅速に最短で滅ぼしたであろうことは容易に想像できる。

彼の全生涯でまさに何度も訪れたであろう「どうする」のなかでも、おそらく最後の「どうする」になったであろうこの豊臣家をどうするか?という迷いは実に17年という歳月を彼をしてかけさせたのだ......
僕が家康という人物をほかの戦国大名と比べて「特異である」とおもうのは、彼からはほかの武将にはほぼ見られないある種の道義性、倫理性とでもいうのだろうか、そういうものを感じずにはいられないからだ。それは彼の人生の非常に重要な場面のいくつかでキラッ、キラッと閃光のように発露している。わかりやすく言えば損得、利害という当時の武将たちのほとんどがそれをベースにして動いていた要素を、超越して動いているところがある。
巷ではこのドラマはあまりにも史実を無視しているという批判があるようだ。しかし、ドラマは歴史研究ではない、それを書いた作家や脚本家の視点や感受性の影響が織り込まれているのは当たり前である。たしかに、家康と瀬名、そして、最も重要な関係である家康と信長の関係性の描き方にぼくも少し違和感は覚える。家康と瀬名のロマンスは僕も史実とはやはり違うと思う。思うがそれはまだいいというか、このドラマの個性としてあっていいと思う。
しかし、信長と家康の関係性はあのような上と下、抑圧者と被抑圧者という単純な関係ではなかったと僕は考えるだけに少し失望しているというのが正直なところである。
この二人の関係性はそれほど単純ではない......と僕は考える。この二人の関係性を間違って捉えることは、それはつまり、信長、そして家康という人物が何者であったか?という視点そのものが狂ってくることを意味する。それほど重要だと僕は思う。
このドラマは創作としてはおもしろい、とくに瀬名と家康の関係の捉え方はとても斬新な挑戦であり、いくら創作とはいっても勇気のある切り込み方だと思う。しかし、人物描写における陰翳、奥行きの浅さ、広がりの狭さから生まれる、短絡、浅薄感、『歴史作品としての』全体的な整合性、統一性の薄さという批判は受けても仕方がないのかな、という気はする。それは偉そうに聞こえるのを許してもらえれば、脚本家のこの時代の歴史というものに対する勉強不足から生まれるものもあると思う。
ただ、それもコインの両面のようなもので、斬新さというものをあそこまで大胆に前面に出せば、後者の側面というものはある程度犠牲にしなければならないのかもしれない。NHKも最近は変な政治家がいろいろとうるさいし、視聴率というものを完全には無視できない以上、こういう楽しませることに重点を置いた作品作りをしてもいい。そういういみでは僕もすごく楽しんでみている。










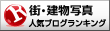
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます