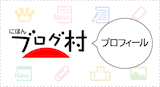2023年4月10日(月)
アケビ Akebia quinata 雄花

20230408 径10mmほど
一昨日、知人たちと地元里山の沢やため池を廻る散歩中に見つけた。
みんな植物は苦手なもので、何の花かわからぬまま記録だけ残すことに。
頂芽辺りに5枚の若葉、そして薄紫色の3枚の萼片と中に6個のコイル状の何かがある花が複数ついていた。

その花たちの根元近くに
アケビ Akebia quinata 雌花

20230408 径30mmほど
同じ3枚の萼片だけれど色が濃く、中に6個の放射状の何かがある花が1つ咲いていた。

最初の花たちより大きくて3倍はある。
いつものように帰宅後調べてみることに。
手元にある『春の野草図鑑』2冊を端から端までめくれど・・・ヒットしない。
当たり前だ。
つる性の木本植物だったのだから。
試行錯誤しながらネット検索中、やまかんで「アケビの花」と入力・・・ビンゴ!
そうかっ!
この花たちはアケビの花だったのか!
雄花のコイル状はおしべ、雌花の放射状はめしべだと知った。
葉が5枚あるからミツバアケビ Akebia trifoliata じゃないことも知った。
幼い頃甘みがうれしくて何度か食べたアケビの実のことはそれなりに知っていたのにね・・・
これまでも見ているのに見えていなかったってこと。
実在する自然は誰でも同じだが、認識している自然は一人一人違うということだ。
本州・四国・九州の日当たりのよい山野に自生。
牧野先生、春『らんまん』ですね!
4/10・9:30追記:ちくしょ~!
今、ゴミ捨てに行ったらステーション横になんぼでも咲いとるではないかっ!

20230410
雄花ばかりで雌花は見つけられなかったけれど。

先日見つけた萼片の薄紫色とは違い、白っぽかったな。
我が家から徒歩100歩、何年も日々通っていても見えてないんだよねえ。
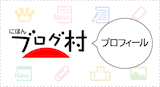
アケビ Akebia quinata 雄花

20230408 径10mmほど
一昨日、知人たちと地元里山の沢やため池を廻る散歩中に見つけた。
みんな植物は苦手なもので、何の花かわからぬまま記録だけ残すことに。
頂芽辺りに5枚の若葉、そして薄紫色の3枚の萼片と中に6個のコイル状の何かがある花が複数ついていた。

その花たちの根元近くに
アケビ Akebia quinata 雌花

20230408 径30mmほど
同じ3枚の萼片だけれど色が濃く、中に6個の放射状の何かがある花が1つ咲いていた。

最初の花たちより大きくて3倍はある。
いつものように帰宅後調べてみることに。
手元にある『春の野草図鑑』2冊を端から端までめくれど・・・ヒットしない。
当たり前だ。
つる性の木本植物だったのだから。
試行錯誤しながらネット検索中、やまかんで「アケビの花」と入力・・・ビンゴ!
そうかっ!
この花たちはアケビの花だったのか!
雄花のコイル状はおしべ、雌花の放射状はめしべだと知った。
葉が5枚あるからミツバアケビ Akebia trifoliata じゃないことも知った。
幼い頃甘みがうれしくて何度か食べたアケビの実のことはそれなりに知っていたのにね・・・
これまでも見ているのに見えていなかったってこと。
実在する自然は誰でも同じだが、認識している自然は一人一人違うということだ。
本州・四国・九州の日当たりのよい山野に自生。
牧野先生、春『らんまん』ですね!
4/10・9:30追記:ちくしょ~!
今、ゴミ捨てに行ったらステーション横になんぼでも咲いとるではないかっ!

20230410
雄花ばかりで雌花は見つけられなかったけれど。

先日見つけた萼片の薄紫色とは違い、白っぽかったな。
我が家から徒歩100歩、何年も日々通っていても見えてないんだよねえ。