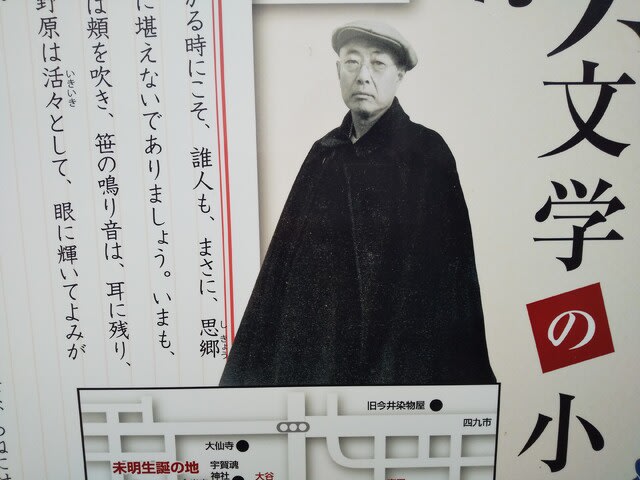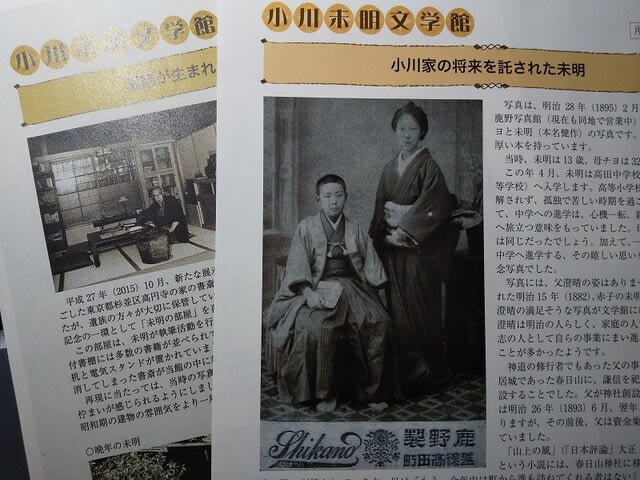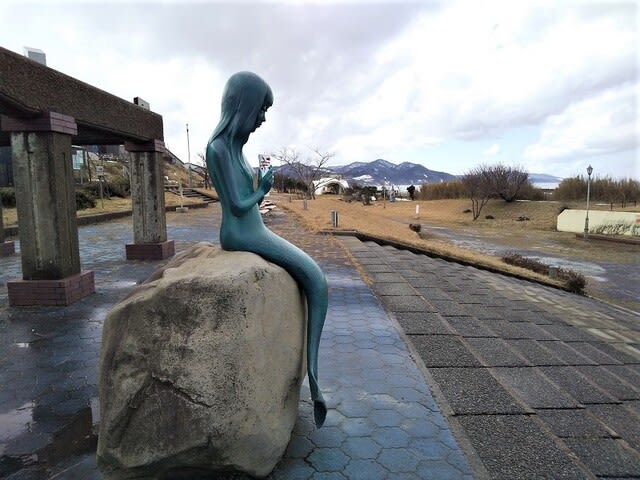「photograph」が発明されたのは今から200年ほど前、19世紀と言われる。
photoは「光の」、graph は「書く、描く」。
日本語では「 光画 」とも訳されるが、一般的に普及しているのは「写真」だろう。
真(まこと)を写すとは、言い得て妙。
確かに写真は「記録」と「伝達」と「表現」を兼ね備えたものだ。
しかし、物事は常に多面的であり、被写体の真実が1つとは限らない。
故に、同じ写真であっても、解釈は観覧者によって異なる場合がある。
また、撮影から時を経た写真は、熟成し「思い出」になると思う。
「時を切り取った記録」は、観覧者が当事者ではなかったとしても、
「あの頃の記憶」を想い起こす触媒になり得るのではないだろうか。
2023年2月現在「津幡ふるさと歴史館 れきしる」では、
企画展「思い出の津幡町~1枚の写真から想う~」を開催中。
今回は、その一部を紹介したい。

【当館が所蔵している写真を中心に、
「学校」「遊び」「記念日」などをテーマに紹介します。
ありきたりの生活の一瞬をとらえた貴重なカットです。
そして、それらの写真にはさまざまな思い出が込められています。
写真を見て、懐かしさに触れてもらえるのではないかと思います。
写真撮影にはカメラなど、映像を残す機材が必要です。
当館所蔵のカメラをはじめ、町内の方からもカメラなどの撮影機材を提供いただきました。
今回展示している懐かしい写真と共に撮影機材にも関心を寄せていただき、
思い出に浸っていただければ幸いです。
また、会場の関係から展示できなかった昔の町並みや、小中学校の校舎、役場庁舎なども
モニターに流すスライドショーとして上映していますので、
時間の許す限りゆっくりとご覧いただければと思います。】
(※上記【 】内、れきしる配布解説文より引用)

<昭和32年(1957年)撮影。
木の棒を振りかざす男の子と同じような自分自身を想い起こす。
昆虫を捕まえたり、チャンバラをしたり、野山は遊び場だった。
彼の背後に写るのは、木造校舎時代の津幡小学校。
今と比べ田園の面積が広いことも見て取れる。
失われた風景の記録として貴重な一枚だ>


<上から順に、昭和42年(1967年)撮影「津幡中学校陸上競技大会 応援合戦」。
昭和44年(1969年)撮影「津幡中学校プール掃除」。
僕もどちらも経験した。
応援の方の記憶は朧気だが、プール掃除はよく覚えている。
掃除前、水を抜いた底には、藻類に混じりヤゴ、水生昆虫が散見できた。
デッキブラシで水垢をこすり落としながら、
生き物たちの生息域をなくすのを申し訳なく思ったものだ。>

<昭和43年(1968年)撮影「津幡小学校体育館での明治100年記念式典」。
ステージ上で歌声を披露しているのは、
向かって左・奥から順に成人女性→中学生→小学生か?
女子児童のスカートは、かなりのミニ。
これも時代なのである。>

前述の解説文にもあったとおり、ガラスケース内には機材も展示されている。
「Camera」の語源はラテン語の「暗い部屋」。
小さな壁穴を通った光が、反対側の壁に外の景色を逆さに写し出す。
ヨーロッパ中世の画家たちは、いわゆる「ピンホールカメラ」の原理を使って、
壁に写った光の跡をなぞりスケッチを描いた。
この装置は「Camera Obscura(カメラ・オブスキュラ)」という。
Cameraは「部屋」、Obscuraは「曖昧な、暗い」の意である。
カメラ・オブスキュラに、銀の化合物を塗った金属板をセットして写し取る技術が生まれ、
金属板はフィルムとなり、フィルムは白黒からカラーへと進化。
被写体をデジタルデータとして定着できるようになったのが、現在だ。


僕は、撮影機材面についての知識は少ない。
典型的な文系脳にとって、カメラは極めてメカニックな印象。
見た目がカッコいいと思う反面、取っ付きにくい対象だった。
だが、今ではスマートフォンの機能の1つに組み込まれ、
気軽に撮影・記録ができるようになり、ありがたいと思っている。
お陰で拙ブログを作ることができるようになった。

今回紹介したのは展示のごく一部。
「津幡ふるさと歴史館 れきしる」の企画展
「思い出の津幡町~1枚の写真から想う~」は、2023年3月12日まで開催。
機会と時間が許せば足を運んでみてはいかがだろうか。
あなたにとっての思い出が見つかるかもしれない。
< 後 記 >
冒頭で、写真は「記録」と「伝達」と「表現」を兼ね備えたものと書いた。
今、トルコ、シリアから伝えられる記録写真は、溜息なしに見ることができない。
理屈として分かっていても、改めて災害(地震)の怖ろしさを実感する。
復興への道のりは長く苦しいものになるだろう。
ともあれ一人でも多くの命が救われることを願って止まない。