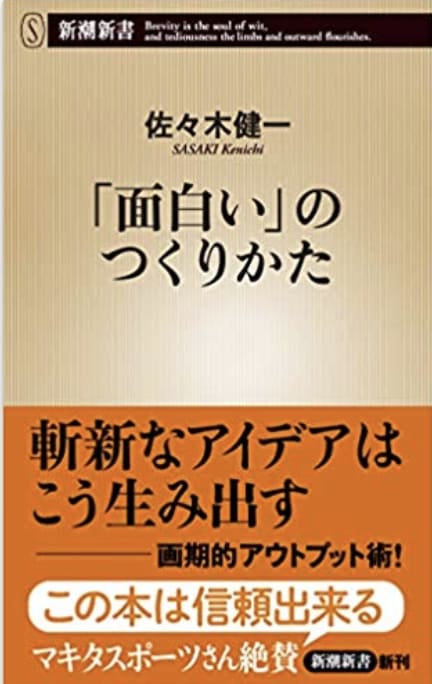@「面白い」の定義、ここでは「差異」と「共感」とある。 人々は現実から離れたギャップを求め、驚き、「なるほどそう言うことか」と思わず言わせることだと感じる。 よく「異文化体験」などと外国人に体験させる日本のギャップ(意外性)はそこにあるのだろう。 「面白い、楽しい」はこれからも多くのアイデア・クリエイティブな発想から生まれ、無尽蔵に開拓できる市場になると確信できる。 人は勉強してこそ、何をするのかを知ることになる。
『面白いの作り方』佐々木健一
ウケるプレゼンをしたい。斬新な企画を考えたい。人の心をつかみたい。誰もがそう思うけれども、そう簡単にはいかないもの。どうすれば「面白い」と思ってもらえるのか。ポイントはどこにあるのか。「安易な共感を狙うな」「アイディアは情報の蓄積から生まれる」「人と会う前に学習せよ」――長年、テレビ番組制作者として、ひたすら「面白い」を追求してきた著者がそのノウハウ、発想法を惜しげもなく披露した、小手先のテクニックを超えた全く新しいアウトプット論。
[Bookデータより出典]
第1章 そもそも面白いって何?
「面白い」とは〝差異〟と〝共感〟の両輪である/人の心を動かすのは〝差異〟である
人々の関心を呼ぶ=差異を感じている「/後追い」では大ヒットは生めない
第2章 アイデアは思いつきの産物ではない
企画は〝組み合わせ〟で生まれる/アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせである
「クリエイティブ」を支えるのは「記憶」である/余裕や遊びがクリエイティブを生む
社内会議で〝斬新なアイデア〟は生まれない/企画会議の常套句「なぜ、今か」?が愚問なワケ 〝今〟に向って石を投げ込む/良いアイデアは「制約」と「必然性」から生まれる
実際には古いものを知らなければ、そう簡単んい斬新なものは生まれない 余裕や遊びが必 過去の蓄積要の上に成り立つもの 似た様な意見や志向を持った人たちが集まると知的生産のクオリティは低下する 「違和感」を大切に
第3章 学び(取材)からすべてが始まる
取材の基本「合わせ鏡の法則」とは?/問われているのは常に〝自分〟である
「取材=話を聞く」ではない/できる仕事人に共通する「地味にスゴイ取材力」
「まず人と会ってみる」が正解ではない/取材なくして物事の〝本質〟はつかめない
〝独学〟こそが成長を育む/根無し草の日々こそ、その後に活きる
「勉強するから、何をしたいかが分かる。勉強しないから、何をしたいか分からない」北野武
第4章 「演出」なくして「面白い」は生まれない
純然たる〝ありのまま〟を伝えることはできない/演出とは〝状況設定〟である
周到な準備で確率を高めるプロの「演出」/「密着すれば人間が描ける」は本当か?
〝前倒し〟が演出のカギを握る「/他者との関係性」は刻々と変化する
第5章 「分かりそうで、分からない」の強烈な吸引力
「分かりやすさ」は万能ではない「/分かりやすそうで、分からない」の威力
第6章 「構成」で面白さは一変する
「ディレクター」とは「構成」する仕事である「/何をどういう順番で配置するか」が根幹
アナログ的手法「ペタペタ」の絶大な威力「/ペタペタ」でプレゼンも魅力的になる
事前に構成を練るのは〝悪〟なのか?/現実が台本通りになることはない
名作に共通する物語の基本構成「三幕構成」/「問題提起」の設定が最も重要
1:2:1 3幕構成=問題提起・問題複雑化・問題解決
第7章 「クオリティ」は受け取る情報量で決まる
作品の「質」の高さは情報量が支えている/ボケ足映像を「美しい」と感じるワケ
なぜ、CGキャラに感情移入するのか/ノーナレが世界で評価される理由
作り手が勝手に情報を限定しない
第8章 現場力を最大限に発揮させる「マネジメント」
知られていない「ディレクター」と「プロデューサー」の違い/署名性がモチベーションを高める人を動かすのはお金より面白さ〝/目利きパトロン〟の重要性/放任主義が生んだ〝世紀の技術革新〟現場を前のめりにさせる「マネジメント」の妙
第9章 妄執こそがクリエイティブの源である
アメリカのドラマがハイクオリティな理由/作り手の権利が確立されることの意味
〝検索社会〟で失うもの〝/偶然の出会い〟を演出するテレビ/作り手の妄執が心に刺さる作品を生む