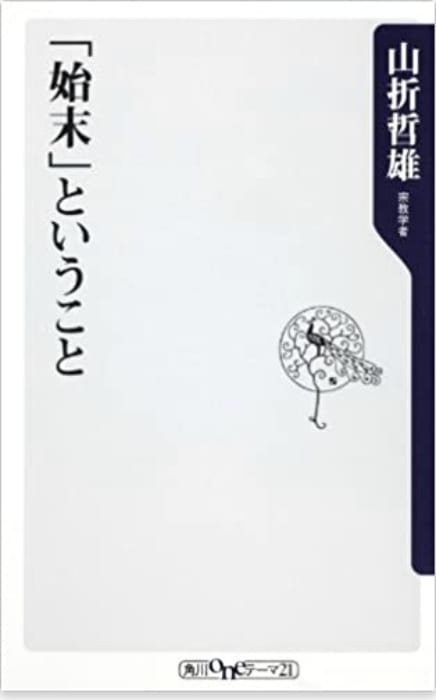@『死後を考える「三無主義」する』とは「自然に還る」を基本に社会環境から他人・親族への迷惑、負担をかけないとする心構えのことである。日本の高齢化社会は今後「葬儀市場」が拡大する。それは墓地、墓石、葬儀一切、お寺供養、遺品整理など家族の負担が大きくなることに繋がる。また、一番厄介なのは今後墓供養は誰がお世話していくのか。現代の墓地巡りをすると「無縁仏」墓も多く、お寺の負担も多くなっている。 自分の最期「始末」はどうあるべきなのか早めに「覚悟」しておくことかもしれない。 ちなみに社会の「三無主義とは無気力、無関心、無責任」を指す。 自粛に対する政府の大幅な遅延決断、いつまで話し合いが続くのか。まるで日本の政治家に見える三無主義だ。
『始末ということ』山折哲雄
「内容」どのように自分の死を迎えるか。そのためにどんなことを覚悟すべきか。日本人の死生観や葬送のあり方から、自らのモノの始末、こころの始末まで、宗教学の第一人者が語る「いのち」の締めくくり方、「終活」の提言。
「始末」とは根性を据えて自分の死と向き合うこと。 現代社会は「無縁社会」「孤独死」から自分の最期に対しての「覚悟」を準備しておく事が必要。自分の死のイメージを深めていくこと。
「葬送」日本の火葬率は99%、その昔は土葬もあり、土葬が少なくなった理由は土地問題、環境衛生問題などから墓埋法が1948年に変わったため。だが火葬以外の方法を禁じているわけではない。日本の火葬は平安時代から始まり一般庶民に広がったのは中世、室町時代とある。火葬場が正式に定められたのは明治8年1875年でその前までは野焼き同然だった。火葬は世界の多数派ではない。
「イスラム教」はすべて土葬、「キリスト教・カソリック教」も土葬が基本、ユダヤ人、中国人、ロシア人も基本的には土葬文化である。
「インド・ヒンズー教」は自然に還ると言う発想から土葬も多い、だたし火葬は、遺灰等を川に流す風習がある。
「三無主義」とは
葬式はしない
墓は作らない
遺骨は残さない
(一握りの散骨=自然葬として自然に還す:自分の旅した場所に散布)
「3つの心得」食べすぎない・飲みすぎない・人に会いすぎない=食事は「足るを知る」心得
「日本人の感情」集団であることで安心する心理が色濃くある、それはみんな同じなんだと言う意識を持って行動できる。また日本人の自然に対する自然観は他の民族との違いを見せる。それは様々な自然の猛威を経験しそれを従順に受け止めた知恵であり、高い需要性の賜物「無常観」を持っているからだ。
「無常」とは仏教言葉であり 「無常三原則」からなる=「あるがまま」
この地上に永遠になるものは一つもない
形あるものは必ず壊れる
人は生きて必ず死ぬ
「ノアの方舟」と「三車火宅」とは
ノアの方舟はサバイバルセオリー、弱者が犠牲になることは止むを得ないこと。選択を間違えないようにすること。選ばれたものだけが生き残る思想から生まれた。
三車火宅とは羊・鹿・牛の車に全ての人々を載せると言う犠牲になるものと生き残りうるものの区別を設けない人間を救うと言う考え方。(人は誰しも必ず死ぬ・永遠なるものは何一つない)
「老齢化社会の役割」社会から何かをしてもらう、与えてもらうことを期待しないこと。価値観を伝えていく役割を持つこと、それは伝統、慣習、価値観など。
「覚悟」を持つ 老いる覚悟・病気になる覚悟・死ぬ覚悟
「整理」身の回りを整理すること、死後多くの私物はゴミとなることで断捨離すること