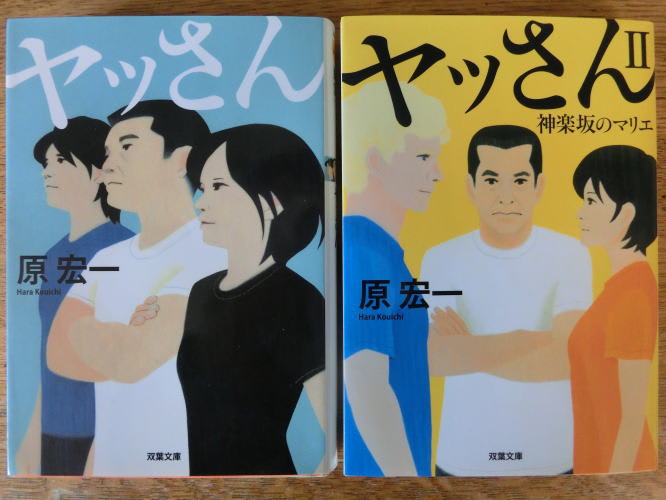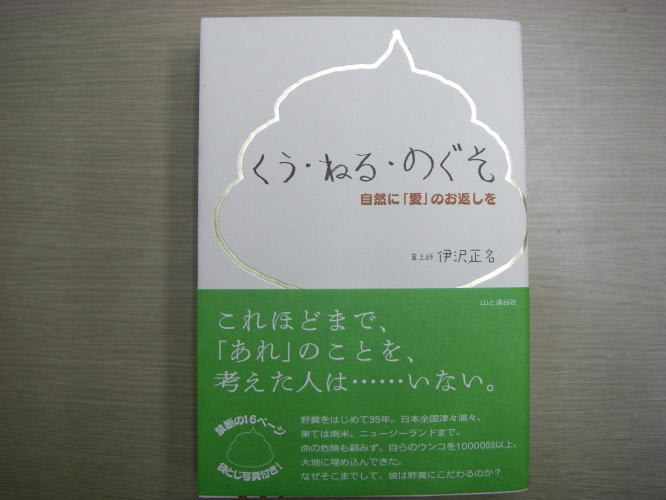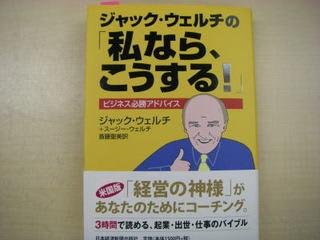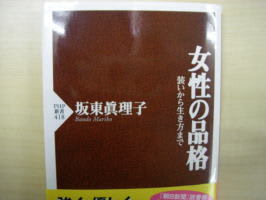2ヶ月ほど前のこと、岩手の友から歌集を出版したという知らせが届いた
彼との出会いは大学3年生の夏、南八つを縦走中の赤岳の頂上であったと記憶している
しばらくはお互いに登った山の写真と手紙をやりとりしていたけれど次第に年賀状の交換だけになった
力強く味のある版画に、岩手の詩人「宮沢賢治」の詩を載せた年賀状は毎年の楽しみの一つになっていた
もしもあの頃、今のようにインタ-ネットが普及していたらもっと深いやりとりができたであろうにと思う

正直に言うと僕は和歌が良く分からない
でも何度が読み返してみると、極くごく身近なことを詠った言葉の一つ一つに
彼らしい人に対する優しさや思いやり、ユーモアをしみじみと感じることができた

あれから47年、二人とも68歳の老境に入ったけれど違う世界でお互いにまだまだ意気盛んである
若き日に赤岳で出逢い、しばらく同じ登山道を歩きながら言葉を交わしただけなのに人と人との縁は不思議なものである
表紙の陽さん人形を見ながら、顔をくしゃくしゃにして笑う彼の笑顔が鮮明に蘇った
彼との出会いは大学3年生の夏、南八つを縦走中の赤岳の頂上であったと記憶している
しばらくはお互いに登った山の写真と手紙をやりとりしていたけれど次第に年賀状の交換だけになった
力強く味のある版画に、岩手の詩人「宮沢賢治」の詩を載せた年賀状は毎年の楽しみの一つになっていた
もしもあの頃、今のようにインタ-ネットが普及していたらもっと深いやりとりができたであろうにと思う

正直に言うと僕は和歌が良く分からない
でも何度が読み返してみると、極くごく身近なことを詠った言葉の一つ一つに
彼らしい人に対する優しさや思いやり、ユーモアをしみじみと感じることができた

あれから47年、二人とも68歳の老境に入ったけれど違う世界でお互いにまだまだ意気盛んである
若き日に赤岳で出逢い、しばらく同じ登山道を歩きながら言葉を交わしただけなのに人と人との縁は不思議なものである
表紙の陽さん人形を見ながら、顔をくしゃくしゃにして笑う彼の笑顔が鮮明に蘇った