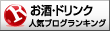利き酒で首位賞と特に印象に残った酒を書いておきます。
吟醸部門
首位 花の舞 バランスよく上質の甘みがあります。
開運 吟醸部門で最も静岡吟醸タイプとしての華やかな香りがあります。味もまるく、欠点がないです。
純米吟醸部門
首位 開運 非常に高い完成度の酒です。吟醸、純米吟醸を合わせてもこれが一番良い酒だと感じました。(個人的には純米吟醸の首位の酒が吟醸の首位の酒よりも良いと感じる年はあまりありません。)
葵天下 個人的に面白い酒質です。酸の質が違う感じです。
磯自慢 ソリッドで味香りとも磯自慢のスタイルがあります。静岡基準でこれを3点法で1点(最高点)以外をつける理由は思い当たりません。
全般 10年前ぐらいの鑑評会と近年の鑑評会を比較した場合、静岡県の出品酒も日本酒度はやや甘くなったのかと思います。また上位の酒のスタイルこそ変わってもレベルはあまり変わっていないが、下位の酒のレベルは上がっていると感じました。
敬称略でございます。ご容赦ください。
志太泉 純米吟醸部門 入賞です。
知事賞 開運
会長賞 正雪 葵天下 英君 磯自慢 天虹 花の舞 高砂 杉錦 志太泉 喜久醉 千代乃峯 若竹 白隠正宗 國香 出世城 萩錦
志太泉吟醸部門入賞です。
知事賞 花の舞
会長賞 正雪 開運 萩錦 磯自慢 杉錦 志太泉 喜久醉 葵天下 高砂 英君 千代乃峯 天虹 出世城 白隠正宗 初亀 若竹
一応PDFにまとめてみました。
http://shidaizumi.com/summary/kanpyoukainagoya2013.11.pdf
こうやって作ってみると、文章の多いまとめというのは、読みたくなくなりますね。
まとめに書かなかった事は
①純米酒部門に出品しなかった理由。
在庫が少ないから。
②本醸造部門でよかった事。
昨年は「特別本醸造」を出品して、入賞しなかったが、考え方を変えて「本醸造」を出品して入賞したこと。
③名古屋での入賞酒の利き酒は結構良い。
というのは、こんなにもたくさんの市販酒を利き酒できる機会はなかなかない。なかなか参考になる。
平成25年度名古屋国税局酒類鑑評会で入賞しました。
この鑑評会について箇条書きで要約すると(厳密性は欠きます)
〇対象となる蔵元は、東海4県(岐阜、静岡、愛知、三重)の日本酒の蔵元です。
〇部門は3部門(本醸造、純米酒、吟醸酒)です。
〇本醸造、純米酒区分は、市販酒を約45度のお燗にて審査を行います。それぞれ1点出品できます。
〇吟醸酒区分は[吟醸酒区分]・[伝統型酵母吟醸酒区分]に分かれます。2点まで出品できます。[吟醸酒区分]・[伝統型酵母吟醸酒区分]で1点ずつ出品することも、同じ部門で2点出品することも可能です。純米吟醸酒の出品も可能です。約18度の酒温で審査します。H24BYに製造した酒が対象です。
〇[吟醸酒区分]は、りんごに似た香り(カプロン酸エチル)が強い酒の事です。
〇[伝統型酵母吟醸酒区分]は、古典的なきょうかい酵母(6号~1501号)、静岡県酵母等を使用した、バナナに似た香り(酢酸イソアミル)が強い酒の事です。
この条件にて、志太泉酒造は、本醸造部門、吟醸酒区分([吟醸酒区分]・[伝統型酵母吟醸酒区分])に出品しました。(純米酒部門は出品しませんでした)
結果は、出品全部門で入賞しました。
名古屋国税局による、公式の鑑評会の情報のサイトは以下の通りです。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/sake/kampyo/62/index.htm
入賞者の名簿は以下の通りです。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/sake/kampyo/62/meibo.htm
(この名簿では、志太泉酒造が両方に入賞していることは確認できませんが、両方入賞しています)
「Internatinal SAKE Challege2013純米大吟醸部門」にて「GOLD MEDAL」を受賞しました。
http://www.sakechallenge.com/results.html
志太泉酒造は、今回「Internatinal SAKE Challege2013」に初出品しました。
初出品であり、また海外審査員の多いという通常とは違う視点の審査で好結果が得られた事をたいへんうれしく思います。
※審査についての詳細は
http://www.sakechallenge.com/challenge.html
全国新酒鑑評会入賞しました。
詳細は、酒類総合研究所のホームページで
http://www.nrib.go.jp/kan/h24by/h24bymoku_top.htm
静岡県は入賞6 金賞0でした。(入賞6の内志太地区は4)
福島県金賞受賞多いです。
http://www.shizuoka-sake.jp/prize/h25_report.html
上記が静岡県清酒鑑評会の結果です。
以下個人的な感想です。(敬称略)
《吟醸部門の印象》
知事賞(1位)の喜久酔のお酒は、精緻さと静謐さのなかに静岡酵母的華やぎがあるすばらしい酒でした。また3位の若竹のお酒も、シャープさと力強さがあり、こういう方向性のお酒も評価されるということは良いことだと思いました。7位の開運は、バランスのよさ、上質な香りがあり、非常に優れたお酒だと思いました。
志太泉のお酒は同着11位でしたが、昨年のお酒と比較するとやや若さや荒さがあったかなと思います。鑑評会の出品戦術としては、もう少し暖かい場所でやや熟成を進めた方がよかったかもしれません。秋には美味しくなると思います。
《純米吟醸部門の印象》
2位の花の舞のお酒は、良い意味での重厚さがある素晴らしいお酒でした。
志太泉(5位)の酒は、以前書いたとおり、まだもっと蔵として良い酒は造れるはずですが、現状で出来ることはだいたい出来ました。
《全体の印象》
今年は、鑑評会的お酒の評価としては各蔵のお酒の差はわずかだったように感じました。その中で各蔵の個性というか技術的芸風が発揮されていたのではないでしょうか。
平成24酒造年度全国新酒鑑評会について開催要項が公表されています。http://www.nrib.go.jp/kan/h24by/info/h24by_info.pdf
上記リンクに追加する情報とすれば、5月22日の東広島の酒類総合研究所の一般公開の前日に、例年どおり講演会が開催されます。
http://www.nrib.go.jp/kou/49kouen.htm
これだけではつまらないので、個人的な推測を書きます。
全国新酒新酒鑑評会の結果を最も気にしているグループは、ベテランの年代の杜氏さんたちかなと推測します。
その次に、気にしているのは、高齢の蔵元さんたちと推測します。
この二つのグループは、ほとんど同じくらい気にしてると思われますが、極めてわずかに杜氏さんたちがより気にしているじゃないでしょうか。
そもそも杜氏さんの酒造りの甲乙などいうのは、客観的に測れないものですが、杜氏として何回金賞を受賞したかというのは、唯一、数字としてくっきり示されるものです。
まったく、同じ事は、蔵元にも当てはまります。
それで、なんで杜氏さんのほうが気にするかと思うかというと、かつて志太泉におられた杜氏さんと、先代の社長を比較すると本当にどちらも全国新酒新酒鑑評会が気になって気になってしかたがなかったでしょうが、微妙に杜氏さんのほうがより気にしていたなという感じがするからです。
だから、ほとんど根拠は無いです。
ベテランの年代の杜氏さんや高齢の蔵元さんじゃない、年齢的に若い杜氏さんや蔵元さんは、一般的には、そこまでこのイベントを気にしていないと思われます。別にデータはないですが多分そうだと思います。
これが仮に正しいとすれば、コンテストが増えたことや酒質の評価の多様化によるものなどが原因でしょう。
結果はこちらです。
http://www.shizuoka-sake.jp/prize/h25_report.html
志太泉は、吟醸部門12位です。
今年も、精米歩合50%で挑戦しました。
昨年(2位)と比較すると、味わいにやわらかさが足りない点がこの結果となったと推測しています。
味わいの中の酸に関しては、同じ酒でも酒にキレとシャープさを与えるプラス評価される場合と酸が不調和というマイナス評価の場合があります。後者の解釈がされたかもしれません。
香りのバランスは、昨年とほぼ同じですが、わずかに地味かもしれません。
純米酒部門は5位です。
質的も、順位的にも、まずまず納得の出来る酒が出来たかと思います。
今年は、各蔵元とも静岡県清酒鑑評会の出品の参考とする静岡県杜氏研究会http://www.shizuoka-sake.jp/topics/120308.html
の利き酒会(一般公開)に出席できませんでした。
そのため、まったく他の蔵元のお酒に関する予断がありません。
一般公開の利き酒が楽しみです。
11月7日に開催されました純米酒大賞2012において、「純米吟醸 兵庫山田錦(精米歩合50%)」と「純米原酒 開龍 朝比奈山田錦(精米歩合70%)」が共に銀賞を受賞しました。
「開龍」は残念ながら完売しております。「純米吟醸」も完売間近となりました。
http://www.fullnet.co.jp/junmaisyu_taisho/2012/index.html
第61回名古屋国税局酒類鑑評会にて
吟醸酒部門にて(伝統型酵母部門、吟醸酒部門)両部門にて入賞しました。
入賞酒名簿はこちら
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/sake/kampyo/61/meibo.htm
名古屋国税局にHPによると伝統型酵母とは
現在ではバイオテクノロジーの進歩により吟醸香を高生産する酵母が開発され、鑑評会で使用される酵母の主流となっていますが、それらの酵母が開発される以前から吟醸酒に使用されていた清酒醸造用優良酵母を指します。現在主流の吟醸酒が、華やかなリンゴ様の香りを主体とし切れの良い味であるのに対し、伝統型酵母を用いた吟醸酒は、落ち着いたバナナ様の香りであり、後味の残らないまろやかな味になります。鑑評会の主目的は酒造技術の進歩・発展でありますが、技術の伝承の観点から、平成21年度より伝統型酵母の区分を設けて品質評価を行っています。
ということです。
いろんな言い方ができますが(雑な表現です。厳密性は欠きます)
①伝統型酵母≒バナナの香りを出す 吟醸香を高生産する酵母≒りんごの香りを出す
②伝統型酵母≒酢酸イソアミルを出す 吟醸香を高生産する酵母≒カプロン酸エチルを出す
③伝統型酵母≒静岡県酵母、昔のきょうかい酵母 吟醸香を高生産する酵母≒カプロン酸エチル高生産酵母(明利酵母、きょうかい1801酵母等)
志太泉酒造では、伝統型酵母(HD-1)と精米歩合50%山田錦で吟醸酒を、吟醸香を高生産する酵母(明利酵母)と精米歩合40%山田錦で大吟醸酒を造っています。今回の鑑評会では、両部門とも入賞することができました。これは、当蔵にとっては初めてとなります。また両部門入賞は、東海4県でも3蔵のみです。
志太泉酒造の酒造りの本流は、伝統型酵母での酒造りだと考えておりますが、吟醸香を高生産する酵母でも一定水準以上の酒造りが出来る事の証明にはなるかと考えております。
但し、良いことばかりではありません。
本醸造部門では、特別本醸造は、入賞しませんでした。
本醸造の審査は45℃でのお燗の審査となります。
こちらが、県別の審査結果です。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/sake/kampyo/61/jokyo.htm
極めて特徴的な事は、静岡県は16点の出品で入賞は1点、愛知県は16点の出品で入賞は10点です。素直に考えれば、愛知県のお燗酒は、静岡県のお燗酒よりはるかに美味しいということとなります。
これは、本醸造の出品されたお燗酒を、利き酒した結果ですが、私の中の、美味しい45℃のお燗酒というのは、審査結果による美味しい酒とは乖離しているようです。もちろん、審査結果の方が、妥当である事は当然の事です。酢酸イソアミルが比較的高いお酒のお燗というのも、私的には、美味しく飲めますが、それは妥当ではないようです。来年以降の出品では、特別本醸造ではなく普通の本醸造を出品する方向で考えております。
結論的に言って全国鑑評会で1位を発表したほうがよいと思う理由は
マスコミに媚びようがなんだろうが、少しでも、日本酒が話題になった方がいいんじゃないかとういう単純なものである。
全国鑑評会において(確率の高い仮定の話として)香りの高い大吟醸「××正宗」が全国1位受賞したとする。
その情報が、ある程度、成人非日本酒飲用者知れたとする。
その情報を受け取った成人非日本酒飲用者の内、①「××正宗」の金賞酒(あるいは大吟醸)、②「××正宗」のどれかの酒、③「日本酒全般」のいずれかを飲んでみよう行動に出るかもしれない。
①「××正宗」の金賞酒(あるいは大吟醸)を飲んだ人が
香りの高い大吟醸(純米大吟醸)を好きになる。
↓
伝統型の大吟醸(純米大吟醸)を好きになる。
↓
業界的な呼び名では中吟クラスを好きになる。
↓ ↓
純米酒を好きになる 本醸造酒を好きになる
↓ ↓
生もと、山廃等を好きになる 普通酒も好きになる
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
最終的に全般的な日本酒フォロワーになる。(極めて楽観的なシナリオ)
別に順路はこうでなくてもかまわない。
②「××正宗」のどれかの酒 ③「日本酒全般」
についても、それなりの順路をたどってかなり確率は少ないが全般的な日本酒フォロワーになる。
まあ、自分で書いていてもナイーブすぎるシナリオである。
次回は、これに対する、きわめてよくある反論について。
全国新酒鑑評会で1位発表されない理由は、発表すれば
発表する主体の酒類総合研究所がDisられる事が確定だからだと思われる。
だれだって(どんな組織)だって批判されるのがみえみえな事はやりたくないだろう。
順当にいくと、全国新酒鑑評会1位のお酒は、
(カプロン酸エチルの高い)華やかな(アルコール添加)大吟醸となるだろう。
そんなお酒が、仮にも全国新酒鑑評会1位のお酒≒日本一の日本酒となることに対して、日本酒の業界内部から多くの批判がおきるだろう。
批判は、主にカプロン酸エチルが高い酒が1位であること。
(伝統型酵母で造った酒こそ1位になるべき)
アルコール添加酒が1位であること。
(純米酒こそ1位になるべき)
という神学論争である。
カプロン酸エチルの高い酒を出品している志太泉が言うのは、きわめて矛盾しているのは承知しているが、志太泉としても、全国新酒鑑評会1位のお酒が、(カプロン酸エチルの高い)華やかな酒となったら正直気分はよくない。
やはり、蔵としての酒質追求のゴールはそれぞれの蔵は違うものと想う者として、仮に全国新酒鑑評会1位の酒という存在が蔵に名誉と注目と売上という実利をもたらすことにより、全国新酒鑑評会酒質への目標の収斂が仮に起きたとしたらいやだなあと思う。
ただ、こんなにも私的にも、Disりたい気持ちは、あるけれど、やはり1位を発表する事で少しでも日本酒に話題になってほしいと思う。
そう思う理由は、また。