8月5日は、名古屋より丸尾氏主催の志太泉蔵見学が開催されました。
愛知大学の日本酒講座の参加者の方がほとんどです。
話があちこち行くようですが、一般論として日本酒というのはかなり酒として汎用性があるので同じ日本酒でも、けっこういろいろな食べ物と合ってしまう面もあります。
たとえば、お寿司にも合うけど、焼き鳥にも合うし、ペペロンチー二にもピザにも合ってしまうような日本酒も世の中にはあります。
この汎用性が強いことは、もちらん日本酒の長所でもあります。しかし、ワインのマーケティングなら、このワインだったらこの食べ物という断言が出来ます。明確なわかりやすい説明ができないという意味では日本酒の短所ともいえます。ソムリエという単語が世間に認知されているにも関わらず、利き酒師という単語を知る人が少ない現実のひとつの要因ではないでしょうか。
どんどん話がそれると、ワインにも汎用性があるという反論も成り立つし、利き酒師というのは、制度的な面からの問題もあるでしょうがやめておきます。
話をもどすと、日本酒である志太泉も食との汎用性のある酒です。
まあ、志太泉にもいろんな種類があり、それぞれの種類の酒にそれぞれの食との相性という意味の機能性は漠然と設定されています。
だから問題設定が根本的におかしいのですが、あえて強引に「志太泉は新鮮な食に合うのか?保存性のある食に酒に合うのか?」という二元論の設問を設定したとすると、「志太泉は新鮮な食に合う酒」です。
今回の蔵見学では、その辺りを考えていたこともあり、蔵見学の直前に、まんさいかん(地元のJAの野菜直売所)に朝行って、朝採りの野菜をそろえて、蔵見学の皆様に、志太泉と一緒に食べて頂きました。
野菜は、きゅうり、フルーツトマト、枝豆、志太梨、じゃがいも、ハウスみかん、オクラなどを用意しました。味はすべてが1級品ではありませんが、すべて地場野菜でとにかく新鮮でした。
まあ、それだけでは、寂しいので、焼津の黒はんぺん、ごぼうまき、桜えび天も準備しました。こちらは足平のものなのでけっこう美味しいと思います。
酒造りの工程では、酒造りそのものがやっていないため、説明は難しいですが、その分ふだんは、みれない部分を見て頂きました。日本酒講座の生徒さんなのでとても熱心に聞いて頂きました。
お酒の種類では、入魂山田錦と愛山純米吟醸が人気でした。ここは名古屋の特徴でもあります。
会の後半の懇親会では、にゃんかっぷTシャツの話で盛り上がりました。
主催の丸尾様、いつもの秋貞様にも大変お世話になりました。
また、参加者の皆様のブログにも、取り上げて頂きました。
http://ameblo.jp/wanosake/entry-11323181181.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kei05192000/38612732.html










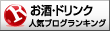
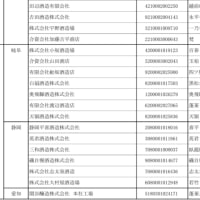

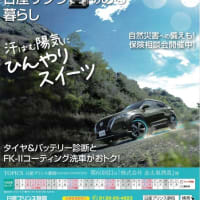

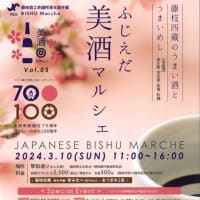
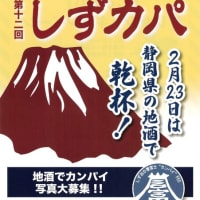

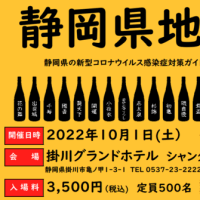







まず、なにをもって利き酒が出来ているかという定義の問題は、それだけでなが~くなってしまいますので、棚上げとするとします。
少しだけこの問題を例示すれば、立場の違う人にとっての利き酒(鑑定官にとっての利き酒、製造者にとっての利き酒と広義のセールスプロモーションをする人にとっての利き酒など)が違うのか同じなのかという現状論。また同じであるべきなのか違うべきなのかというべき論というか理想論)も一つです。
あいまいな定義で判断して私の知る範囲内で、利き酒師が利き酒ができているかといえばできていない方もおられるかもしれません。酒匠の方であれば、できている方もかなりおられると思います。
但し、私個人として、仮に現状の利き酒師の方のほとんどが製造工程を知り、貯蔵中に置ける変化や熟成を知っていた)しても、それは比喩的な意味でのバタフライ効果は期待できるが速効ソムリエより認知されというのは難しいと思います。
私も考えたのですが、利き酒師とソムリエがどちらが社会的に認知されてるという比較は、極めて浅薄極まりないです。ただ浅薄な事も必要だろうというのが暫定的な今の考えです。