奥羽本線(山形新幹線)は、新庄駅を後に、「大石田」-「村山」ー「東根」と最上川に沿い上り、「天童」に着きます。
「山形新幹線」
1991年に奥羽本線改軌工事開始し、1992年に開業。2011年 平成23年、東北地方太平洋沖地震の影響で運休。
3月 福島駅 - 新庄駅間の運転再開。 4月 東北地方太平洋沖地震の余震により再び全線運休。4月には、全線運転再開。
7月 福島駅までの減速運転解消に伴うダイヤ改正により、震災前に戻されている。
山形新幹線車両内から

「天童市」
天童の南北時代、「北畠天童丸」が城を築き、天童氏を称している。中世に舞鶴山(241m)を中心に城下町として栄えた。近世には、
羽州街道の宿場と温泉街で賑わっている。又、全国生産量の95%を占める将棋駒は、天童藩士の内職から始まっていると云う。
天童は、果樹栽培が盛んな地域で、サクランボ・リンゴ、葡萄などがあり、現在山形市のベッドタウンで人口増加率県内一と云う。
北畠天童丸築城跡に舞鶴公園となっている。
新幹線天童駅ホーム

山形県は、飯豊上屋地遺跡・小国東山遺跡の石器時代。縄文の日向洞窟・吹浦遺跡。弥生の東根蟹沢遺跡・山形市の七浦遺跡。古墳高瀬古墳
等が解っている。出羽の陸奥国「最上」と置賜出羽国が712年、721年に出羽・陸奥は、蝦夷使の支配下に置かれている。
880年に、立石寺(山寺)に慈覚大師円仁が建立している。1051~1087は、前9年・後3年の役が起き、1170年藤原秀衝が鎮守府将軍になている。
1189年に源頼朝が奥州征伐で藤原氏を滅ぼしている。1335年「北畠顕家」が陸奥・出羽の兵を率いて「足利尊氏」と戦っている。
1570年「最上義光」が最上家家督を継ぐ。
「閑かさや 岩にしみいる 蝉の声」芭蕉句、東北有数の霊場宝珠山「立石・山寺」1015の石段、今回は廻りません。


国指定史跡 山形城跡「霞城公園」1356年 斯波兼頼「最上家初代」が築城し11代城址義光(57万石)が築いたのが原型と云う。

「最上義光」像
1546-1614 山形城主 義守の子、天童氏・白鳥氏・大江氏討伐して山形を平定させている。
庄内へ勢力拡大、豊臣秀吉に通じ、伊達正宗と争う。山形城に上杉景勝軍引き付けた功で57万石に。
謀略の義光、東北の雄。白鳥長久の娘を息子の嫁にと山形城に誘うが、警戒され、次の手とし、息子成長まで最上氏の後見を頼み系図を
送り、長久は信用し、山形城で謀殺されている。晩年は、家康の覚えめでたい次男の家親に家督をと長男義康を殺害したとも云われている。
東北の雄、最上義光像 上杉景勝重臣直江兼続が攻めて来た時の義光陣頭で向かう姿を再現

「山形城跡・霞城公園」
霞城公園は一辺500mほどの広大な緑地で、山形城址二の丸の堀と石垣などの遺構を中心とした公園と成っている。駅前市のシンボル的な構造物。
山形城址は三の丸まである平城だったが、三の丸の堀は埋められてほとんど面影を残していない。霞城は、山形城の別名である。
面積約35.9ha 、公園一周約2.2km
堀周囲約2.6km二の丸東大手門櫓門・多門櫓・高麗門と土塀をそなえている。史実に従っていると云う。


スポーツ施設 - 野球場、県体育館、県武道館、テニスコート、弓道場など。 文化施設 は、県立博物館、市郷土館(済生館)など
史跡として、山形城の復元が資料に基づいて進められている。東大手門の復元が完了し、幕末当時の風景を再現している。
見どころとして、桜の名所として知られ、石垣に植えられた桜はライトアップされて堀の水面に映り込むと云う。
山形駅から、南門(追手門)・西門(不明門)・北門(不明門)・町に向かって東大手門、霞ケ城公園入口



城が位置したのは扇状地の西端で、その東部を走る羽州街道に沿って七日町、八日町、十日町、旅籠町などの商人町、宿場町が並んだ。
町人町は東方の笹谷街道、北西に向かう六十里越街道に沿って並び、東裏通りと北部には職人町が位置していたと云う。
土塁(土手上には桜並木) 石垣 東大手門(門扉片方1.2t、江戸城・大阪城に匹敵する見事な物)



本丸・二の丸・三の丸の三重の堀と土塁を持ち、輪郭式規模平城の霞城は、全国でも珍しい。
出羽・関ケ原合戦、長谷堂合戦で城郭が霞で隠れたことから「霞ケ城」とも呼ばれていたと云う。
最上家改易後鳥居忠政により大改修されたと伝わる。
本丸修復工事中 園内に古い桜の木が(夏はライトアップされると云う)


東軍と、西軍が戦った、「関ケ原合戦」時、同じくして、山形でも上杉直江兼続軍約2万程の軍勢が、最上軍を討とうと、山形めがけて攻め入って来る。
守る最上軍は7,000余(実際は小野寺義道を牽制するため庄内に出兵していたため、さらに少なく3,000余)でしかなかったが、上杉軍に対して義光は2,000挺もの鉄砲を駆使して抗戦したと云う。
直江軍は、畑谷城を落とし、長谷堂城に、押し寄せ、3回ほど総攻撃をかけたが、落ちません。
激しい戦とうが半月も続きます。「関ケ原合戦では、東軍徳川方が勝ちます」。
上杉軍が、囲みをといて退き出します、それを最上軍が、追撃。これを「長谷堂合戦」「出羽の関ケ原合戦」と云う。
修復工事 隅石の説明


義光の死後、後を継いだ家親は、1617年に急死。このため、家親の子・義俊が後を継いだが、後継者をめぐる抗争が勃発し家中不届きであるとして、義光の死からわずか9年後の1622年に改易となった。
義俊の死後はさらに石高を1万石から5,000石に減らされ、最上家は大名の座から落ちたと云う。
実物の隅石が展示されていた 本丸を囲む土塁



「最上氏改易後」
鳥居氏 (1622 - 1636)、保科氏 (1636 - 1643)、松平家 (1644 - 1648)、奥平氏 (1668 - 1685)、堀田氏 (1700 - 1746) 、
大給松平家 (1746 - 1764)、天領 (1764 - 1767)、 秋元氏 (1767 - 1845)、水野氏 (1845 - 1870)。
近代は、 明治時代、城が売りに出され、市が購入し、陸軍の駐屯地を誘致した。
歩兵三十二連隊の兵営敷地となり、城内の櫓や御殿は破却され、本丸は埋め立てられた。三の丸の堀も埋め立てられている。
歴史館の幟 合戦説明が
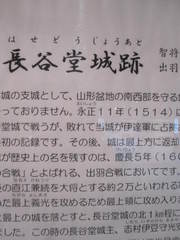


「最上義光歴史館」
城下町の基礎を築いた57万石「最上義光公」の遺品や関連文章等を展示している。兜、合戦図屏風などがある。
歴史館の建物

次回は、山形市内三の丸付近を歩く。
「山形新幹線」
1991年に奥羽本線改軌工事開始し、1992年に開業。2011年 平成23年、東北地方太平洋沖地震の影響で運休。
3月 福島駅 - 新庄駅間の運転再開。 4月 東北地方太平洋沖地震の余震により再び全線運休。4月には、全線運転再開。
7月 福島駅までの減速運転解消に伴うダイヤ改正により、震災前に戻されている。
山形新幹線車両内から

「天童市」
天童の南北時代、「北畠天童丸」が城を築き、天童氏を称している。中世に舞鶴山(241m)を中心に城下町として栄えた。近世には、
羽州街道の宿場と温泉街で賑わっている。又、全国生産量の95%を占める将棋駒は、天童藩士の内職から始まっていると云う。
天童は、果樹栽培が盛んな地域で、サクランボ・リンゴ、葡萄などがあり、現在山形市のベッドタウンで人口増加率県内一と云う。
北畠天童丸築城跡に舞鶴公園となっている。
新幹線天童駅ホーム

山形県は、飯豊上屋地遺跡・小国東山遺跡の石器時代。縄文の日向洞窟・吹浦遺跡。弥生の東根蟹沢遺跡・山形市の七浦遺跡。古墳高瀬古墳
等が解っている。出羽の陸奥国「最上」と置賜出羽国が712年、721年に出羽・陸奥は、蝦夷使の支配下に置かれている。
880年に、立石寺(山寺)に慈覚大師円仁が建立している。1051~1087は、前9年・後3年の役が起き、1170年藤原秀衝が鎮守府将軍になている。
1189年に源頼朝が奥州征伐で藤原氏を滅ぼしている。1335年「北畠顕家」が陸奥・出羽の兵を率いて「足利尊氏」と戦っている。
1570年「最上義光」が最上家家督を継ぐ。
「閑かさや 岩にしみいる 蝉の声」芭蕉句、東北有数の霊場宝珠山「立石・山寺」1015の石段、今回は廻りません。


国指定史跡 山形城跡「霞城公園」1356年 斯波兼頼「最上家初代」が築城し11代城址義光(57万石)が築いたのが原型と云う。

「最上義光」像
1546-1614 山形城主 義守の子、天童氏・白鳥氏・大江氏討伐して山形を平定させている。
庄内へ勢力拡大、豊臣秀吉に通じ、伊達正宗と争う。山形城に上杉景勝軍引き付けた功で57万石に。
謀略の義光、東北の雄。白鳥長久の娘を息子の嫁にと山形城に誘うが、警戒され、次の手とし、息子成長まで最上氏の後見を頼み系図を
送り、長久は信用し、山形城で謀殺されている。晩年は、家康の覚えめでたい次男の家親に家督をと長男義康を殺害したとも云われている。
東北の雄、最上義光像 上杉景勝重臣直江兼続が攻めて来た時の義光陣頭で向かう姿を再現

「山形城跡・霞城公園」
霞城公園は一辺500mほどの広大な緑地で、山形城址二の丸の堀と石垣などの遺構を中心とした公園と成っている。駅前市のシンボル的な構造物。
山形城址は三の丸まである平城だったが、三の丸の堀は埋められてほとんど面影を残していない。霞城は、山形城の別名である。
面積約35.9ha 、公園一周約2.2km
堀周囲約2.6km二の丸東大手門櫓門・多門櫓・高麗門と土塀をそなえている。史実に従っていると云う。


スポーツ施設 - 野球場、県体育館、県武道館、テニスコート、弓道場など。 文化施設 は、県立博物館、市郷土館(済生館)など
史跡として、山形城の復元が資料に基づいて進められている。東大手門の復元が完了し、幕末当時の風景を再現している。
見どころとして、桜の名所として知られ、石垣に植えられた桜はライトアップされて堀の水面に映り込むと云う。
山形駅から、南門(追手門)・西門(不明門)・北門(不明門)・町に向かって東大手門、霞ケ城公園入口



城が位置したのは扇状地の西端で、その東部を走る羽州街道に沿って七日町、八日町、十日町、旅籠町などの商人町、宿場町が並んだ。
町人町は東方の笹谷街道、北西に向かう六十里越街道に沿って並び、東裏通りと北部には職人町が位置していたと云う。
土塁(土手上には桜並木) 石垣 東大手門(門扉片方1.2t、江戸城・大阪城に匹敵する見事な物)



本丸・二の丸・三の丸の三重の堀と土塁を持ち、輪郭式規模平城の霞城は、全国でも珍しい。
出羽・関ケ原合戦、長谷堂合戦で城郭が霞で隠れたことから「霞ケ城」とも呼ばれていたと云う。
最上家改易後鳥居忠政により大改修されたと伝わる。
本丸修復工事中 園内に古い桜の木が(夏はライトアップされると云う)


東軍と、西軍が戦った、「関ケ原合戦」時、同じくして、山形でも上杉直江兼続軍約2万程の軍勢が、最上軍を討とうと、山形めがけて攻め入って来る。
守る最上軍は7,000余(実際は小野寺義道を牽制するため庄内に出兵していたため、さらに少なく3,000余)でしかなかったが、上杉軍に対して義光は2,000挺もの鉄砲を駆使して抗戦したと云う。
直江軍は、畑谷城を落とし、長谷堂城に、押し寄せ、3回ほど総攻撃をかけたが、落ちません。
激しい戦とうが半月も続きます。「関ケ原合戦では、東軍徳川方が勝ちます」。
上杉軍が、囲みをといて退き出します、それを最上軍が、追撃。これを「長谷堂合戦」「出羽の関ケ原合戦」と云う。
修復工事 隅石の説明


義光の死後、後を継いだ家親は、1617年に急死。このため、家親の子・義俊が後を継いだが、後継者をめぐる抗争が勃発し家中不届きであるとして、義光の死からわずか9年後の1622年に改易となった。
義俊の死後はさらに石高を1万石から5,000石に減らされ、最上家は大名の座から落ちたと云う。
実物の隅石が展示されていた 本丸を囲む土塁



「最上氏改易後」
鳥居氏 (1622 - 1636)、保科氏 (1636 - 1643)、松平家 (1644 - 1648)、奥平氏 (1668 - 1685)、堀田氏 (1700 - 1746) 、
大給松平家 (1746 - 1764)、天領 (1764 - 1767)、 秋元氏 (1767 - 1845)、水野氏 (1845 - 1870)。
近代は、 明治時代、城が売りに出され、市が購入し、陸軍の駐屯地を誘致した。
歩兵三十二連隊の兵営敷地となり、城内の櫓や御殿は破却され、本丸は埋め立てられた。三の丸の堀も埋め立てられている。
歴史館の幟 合戦説明が
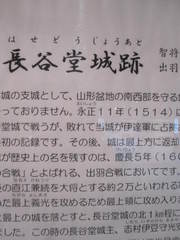


「最上義光歴史館」
城下町の基礎を築いた57万石「最上義光公」の遺品や関連文章等を展示している。兜、合戦図屏風などがある。
歴史館の建物

次回は、山形市内三の丸付近を歩く。









