「源義経」1159-89 義朝の九男、鞍馬寺脱出し、奥州平泉「藤原秀衡」の庇護を受け、頼朝挙兵を知り参加した。
平家討滅の大功をたてるが、頼朝の許可なく任官し怒りをかう。
ここ腰越まで面会を求めたが対立、九州と舟を出さが難破、再び藤原秀衡を頼る。秀衡死後、子泰衡に襲われ自殺した。
義経が屋島を攻めた時、梶原景時が、「関東武士船戦不慣れ、逆櫓を付よ」と進言するが、義経は、暴風を追い風にして一気に四国へ、
景時は、「義経を将の器に非ず」と、見たと云う。
義経平泉から北海道へ逃げた説もある。
「満福寺」鎌倉市腰越、山号ー龍護山、真言宗大覚寺派、本尊ー薬師如来。744年に行基が開いたといわれる古刹である。
札所等ー新四国東国八十八箇所84番。文化財ー義経・腰越状など。
江ノ島電鉄の腰越駅を降りて海岸側に約250メートル行き、踏切を渡った所にある。
満福寺(階段手前が江ノ電踏切)

1185年、義経が兄頼朝に怒りを買い、鎌倉入りを許されず腰越の地に留められた際に、頼朝に心情を訴える腰越状を書いた寺として知られる。寺には弁慶が書いた腰越状の下書きとされる書状が展示、境内には弁慶の腰掛け石や手玉石など、義経・弁慶ゆかりの品々が多数展示されている。有料。
山門 本堂


境内には「義経公慰霊碑」が今も残されている。腰越状は、「吾妻鏡」に全文が残されており、名文としてしられている。
弁慶が水を汲んだといわれる硯の池、腰を下ろしたという腰掛け石や手玉石などがあり、本堂にはこの故事にちなんで義経の生涯を描いた
襖絵がある。襖絵は、鎌倉彫と漆絵の技術を組み合わせたもので32面、
4月中旬に開催される鎌倉まつりでは、義経祭として”静の舞”や慰霊供養も行われます
鐘楼 薬師如来像 境内に


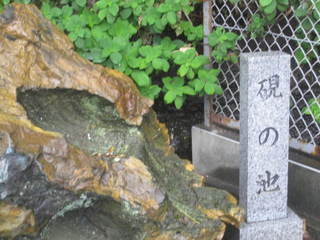
鎌倉が古代から地域政治の中心として栄えていた事や、三浦半島を経由し海路で房総半島へ向かう古代の海道が腰越を走っていたらしい事が考古学の分野から判明しており、「腰越」は、古代から宿駅(腰越駅)として栄えていたと推測。
江戸時代初期、腰越一帯は江戸幕府の代官がおさめる直轄地だったため代官がおかれ、村の政務一般に関する業務は実質的に土地の
土豪島村氏が代わりに取り仕切っていた。
しかし島村氏は苛烈な徴税をはじめ、数々の横暴をおこなったため、多くの村民が島村氏の支配に反発、このため一部の村民が村の分離を幕府に訴えた。
その後1666年に幕府は腰越を村とし、腰越村と津村の二村にわかれたと云う。
龍口寺の三門前

「日蓮」1222-82 日蓮宗開祖、安房「清澄寺」で出家、法華仏教至上とし浄土教を批判、鎌倉へ出て「立正安国論」を書く、北条時頼に
出すが無視、伊豆へ流される。主張を強め他宗からにくまれ佐渡へ流される。
佐渡へ流され前、ここ竜の口で、役人に切られようとした時、雷鳴と稲妻が走り、刀が折れ、命が助けられたと云う。
日像が京都で長年努力し、妙顕寺が勅願寺とされる。日蓮は、湯治途中病で池上で没した。
「龍口寺」は、藤沢市片瀬、山号ー寂光山、日蓮宗、本山・霊跡寺院、本尊ー日蓮聖人像、創建年ー1337年、開基ー日法
札所等ー日蓮上人霊跡。
山門の額 金剛力士像


刑場跡で、1271年に日蓮宗の開祖日蓮が処刑されそうになった。この事件を日蓮宗では「龍ノ口法難」とある。
1337年に日蓮の弟子、日法がこの地を「龍ノ口法難霊蹟」として敷皮堂という堂を建立し、自作の祖師像(日蓮像)と首敷皮を置いたのが
龍口寺の始まりと伝わる。
本格的な寺としての格式を整えたのは、腰越・津 、日蓮宗の信奉篤い島村采女が、1601年に土地を寄進して以来のこととされている。
彫刻は一元流(藤沢彫川)の一元安信。全国的にも数少ない明治期の五重塔だが、近年老朽化が目立つ。


本堂は、1832年竣工。
法難時に日蓮が足元に敷いていた敷皮が安置されているため、敷皮堂ともよぶ。木造欅造り。
本堂

鎌倉での日蓮は、松葉ヶ谷に草庵を結び、小町大路を中心に辻説法を行い、
「念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊」として、他宗を厳しく批判する。
(妙法寺、安国論寺、長勝寺が日蓮の旧跡に建てられたとしているが、その場所は定かではない。)。
1260年「立正安国論」を、時の権力者「北条時頼」に提出。
「立正安国論」では、天変地異や疫病は、法然の念仏宗や禅宗などの邪宗を信仰するからであるとし、法華経を信じなければ、
「他国の侵攻も受ける」などの批判を行っている。
日蓮上人の苦難場所



五重塔 明治43年(1910年)竣工。木造ケヤキ造で五重塔としては神奈川県で唯一。建造には竹中工務店が携わった。
日蓮像 貴重な五重塔



1264年、伊豆流罪を許された日蓮は、一度故郷(千葉県鴨川市)へ帰るが、その際、小松原というところで、
念仏信者である地頭の東条景信に襲われ、額を斬られ、左手を骨折するなどの重傷を負った。
このとき、弟子の鏡忍房日暁と信者の工藤吉隆が殺されている。
龍口寺に隣接 龍口神社無人



次回は、江の島へ。
平家討滅の大功をたてるが、頼朝の許可なく任官し怒りをかう。
ここ腰越まで面会を求めたが対立、九州と舟を出さが難破、再び藤原秀衡を頼る。秀衡死後、子泰衡に襲われ自殺した。
義経が屋島を攻めた時、梶原景時が、「関東武士船戦不慣れ、逆櫓を付よ」と進言するが、義経は、暴風を追い風にして一気に四国へ、
景時は、「義経を将の器に非ず」と、見たと云う。
義経平泉から北海道へ逃げた説もある。
「満福寺」鎌倉市腰越、山号ー龍護山、真言宗大覚寺派、本尊ー薬師如来。744年に行基が開いたといわれる古刹である。
札所等ー新四国東国八十八箇所84番。文化財ー義経・腰越状など。
江ノ島電鉄の腰越駅を降りて海岸側に約250メートル行き、踏切を渡った所にある。
満福寺(階段手前が江ノ電踏切)

1185年、義経が兄頼朝に怒りを買い、鎌倉入りを許されず腰越の地に留められた際に、頼朝に心情を訴える腰越状を書いた寺として知られる。寺には弁慶が書いた腰越状の下書きとされる書状が展示、境内には弁慶の腰掛け石や手玉石など、義経・弁慶ゆかりの品々が多数展示されている。有料。
山門 本堂


境内には「義経公慰霊碑」が今も残されている。腰越状は、「吾妻鏡」に全文が残されており、名文としてしられている。
弁慶が水を汲んだといわれる硯の池、腰を下ろしたという腰掛け石や手玉石などがあり、本堂にはこの故事にちなんで義経の生涯を描いた
襖絵がある。襖絵は、鎌倉彫と漆絵の技術を組み合わせたもので32面、
4月中旬に開催される鎌倉まつりでは、義経祭として”静の舞”や慰霊供養も行われます
鐘楼 薬師如来像 境内に


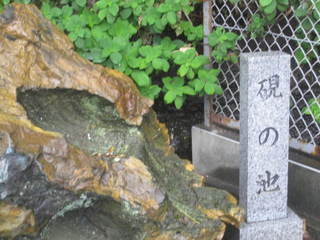
鎌倉が古代から地域政治の中心として栄えていた事や、三浦半島を経由し海路で房総半島へ向かう古代の海道が腰越を走っていたらしい事が考古学の分野から判明しており、「腰越」は、古代から宿駅(腰越駅)として栄えていたと推測。
江戸時代初期、腰越一帯は江戸幕府の代官がおさめる直轄地だったため代官がおかれ、村の政務一般に関する業務は実質的に土地の
土豪島村氏が代わりに取り仕切っていた。
しかし島村氏は苛烈な徴税をはじめ、数々の横暴をおこなったため、多くの村民が島村氏の支配に反発、このため一部の村民が村の分離を幕府に訴えた。
その後1666年に幕府は腰越を村とし、腰越村と津村の二村にわかれたと云う。
龍口寺の三門前

「日蓮」1222-82 日蓮宗開祖、安房「清澄寺」で出家、法華仏教至上とし浄土教を批判、鎌倉へ出て「立正安国論」を書く、北条時頼に
出すが無視、伊豆へ流される。主張を強め他宗からにくまれ佐渡へ流される。
佐渡へ流され前、ここ竜の口で、役人に切られようとした時、雷鳴と稲妻が走り、刀が折れ、命が助けられたと云う。
日像が京都で長年努力し、妙顕寺が勅願寺とされる。日蓮は、湯治途中病で池上で没した。
「龍口寺」は、藤沢市片瀬、山号ー寂光山、日蓮宗、本山・霊跡寺院、本尊ー日蓮聖人像、創建年ー1337年、開基ー日法
札所等ー日蓮上人霊跡。
山門の額 金剛力士像


刑場跡で、1271年に日蓮宗の開祖日蓮が処刑されそうになった。この事件を日蓮宗では「龍ノ口法難」とある。
1337年に日蓮の弟子、日法がこの地を「龍ノ口法難霊蹟」として敷皮堂という堂を建立し、自作の祖師像(日蓮像)と首敷皮を置いたのが
龍口寺の始まりと伝わる。
本格的な寺としての格式を整えたのは、腰越・津 、日蓮宗の信奉篤い島村采女が、1601年に土地を寄進して以来のこととされている。
彫刻は一元流(藤沢彫川)の一元安信。全国的にも数少ない明治期の五重塔だが、近年老朽化が目立つ。


本堂は、1832年竣工。
法難時に日蓮が足元に敷いていた敷皮が安置されているため、敷皮堂ともよぶ。木造欅造り。
本堂

鎌倉での日蓮は、松葉ヶ谷に草庵を結び、小町大路を中心に辻説法を行い、
「念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊」として、他宗を厳しく批判する。
(妙法寺、安国論寺、長勝寺が日蓮の旧跡に建てられたとしているが、その場所は定かではない。)。
1260年「立正安国論」を、時の権力者「北条時頼」に提出。
「立正安国論」では、天変地異や疫病は、法然の念仏宗や禅宗などの邪宗を信仰するからであるとし、法華経を信じなければ、
「他国の侵攻も受ける」などの批判を行っている。
日蓮上人の苦難場所



五重塔 明治43年(1910年)竣工。木造ケヤキ造で五重塔としては神奈川県で唯一。建造には竹中工務店が携わった。
日蓮像 貴重な五重塔



1264年、伊豆流罪を許された日蓮は、一度故郷(千葉県鴨川市)へ帰るが、その際、小松原というところで、
念仏信者である地頭の東条景信に襲われ、額を斬られ、左手を骨折するなどの重傷を負った。
このとき、弟子の鏡忍房日暁と信者の工藤吉隆が殺されている。
龍口寺に隣接 龍口神社無人



次回は、江の島へ。









