江戸時代の川崎は、多摩川の六郷渡し場集落で、東海道五十三次の宿場町、川崎大師「平間寺」の門前町として発展した。
江戸に入る道は東海道と中原街道と大山街道と津久井街道の四つあり、大名行列などで特に賑わった宿場、
江戸初期は幕府の補助金で苦しいようであったが、1659年道中奉行の支配下に編入されて次第に栄えて行ったと云う。
六郷橋が1668年流失し、渡し船で結ばれたが、幕府賄の無賃渡し船であったと云う。
1709年下本陣川崎宿名主「田中丘隅」の献策によって永代渡船権が川崎宿のものとなり財政を潤したと云う。
川崎大師の厄除け・縁起直しの寺として、江戸町民参拝に訪れ、農民・武士の間のも信仰が広まった。
徳川家斉・家慶・家定・家茂と参拝され、格式も高まっていったと云う。1872年新橋ー横浜間鉄道開通で賑わいは今でも続いている。
「天台宗寺院の明長寺」は、恵日山普門院と号し、創建年代は不詳、
静圓法印 1519年寂が、1469―1487年に創建したと伝えられていると云う。
所蔵の葵梶葉文染分辻ヶ花染小袖は、桃山時代に流行した絞り染めの技法といい、国重要文化財。東海三十三観音霊場24番寺。
本尊ー十一面観音立像。
川崎大師仲見世通りに

「辻が花染」は、室町時代後半から桃山時代末にかけて行われたと思われる染色で、絞り染の中に筆で、主に花・鳥などを描いたもの。
短い間にぱっと咲くように流行り、その後、こつ然と消えてしまった幻の染と云われている。
起源は三説ほどある。① つつじの花で染めたので、「つつじが花」がなまった。(色彩説)
② 辻(十字の斜格子に花文)から由来した。(文様形態説)
③ 奈良の木辻で京の染め職人が染めた。(あるいは奈良の木辻で遊女が始めた。)(地名説)
室町・桃山時代の、小袖や胴服などに見られる縫い絞りを主体とした模様染めを、「辻が花」と称していると云う。
寺社仏閣の参道というと、古くは七味唐辛子やお団子店、今ではさまざまな屋台が並んでいるイメージがある。
川崎大師周辺には、それらに加え、独自の「飴」「久寿餅」店が、数多く軒を連ねている。



京急川崎・大師線で三つ目「川崎大師」下車
「川崎大師・平間寺」
真言宗の寺。山号ー金剛山金乗院、1127年源義家の家臣「平間兼乗」が、夢のお告げにより海中から弘法大師木像を得て、寺を興しとのが
始まりと伝える。寺名は、「兼乗」の姓にちなむ。
東国八十八箇所1番・関東三十六不動霊場第7番札所・関東八十八ヵ所霊場特別霊場でもある。
仲見世通り表参道・厄除門 小さな菩薩堂 川崎大師不動門



この時、「兼乗」が42歳の厄年であったことから「厄除け大師」として信仰集めている。
「関東三山と云われる「成田山新勝寺」「高尾山薬王院」とここ「金剛山金乗院」を云う。
大山門

境内の八角五重塔は我が国初。初詣の参拝者数は、毎年首位を争っている。
五重塔(中興塔)は、昭和59年、弘法大師1150年御遠忌に落慶された。
仁王像 八角五重塔 神水舎



崇徳天皇の代1120年頃、平間兼乗という武士が、無実の罪により生国尾張を追われ、諸国を流浪したあげく、 川崎の地に住みつき、
漁猟をなりわいとして、貧しい暮らしを立てていた。
兼乗は深く仏法に帰依し、とくに弘法大師を崇信し、 わが身の不運な回り合せをかえりみ、42歳の厄年に当たり、 日夜厄除けの祈願をした。
ある夜、ひとりの高僧が、兼乗の夢まくらに立ち、「我むかし唐に在りしころ、わが像を刻み、 海上に放ちしことあり。已来未だ有縁の人を得ず。いま、汝速かに網し、これを供養し、功徳を諸人に及ぼさば、汝が災厄変じて福徳となり、諸願もまた満足すべし」と告げられ、
兼乗は、海に出て、光り輝いている場所に網を投じますと一躰の木像が引き揚げられたと云う。
それは、大師の尊いお像でした。
兼乗は随喜してこのお像を浄め、ささやかな草庵をむすんで、朝夕香花を捧げ、供養を続けたと云う。
兼乗は、源頼家(頼朝の長男)の家臣という。
大本堂

残念ながら川崎大師は、第2次大戦の戦禍で建築物など多くの貴重な文化財を失ってしまったため、現在見る事が出来るのは戦後に作られた比較的新しい物が殆ど、八角五重塔。昭和59年の落慶で、ひすいの大日如来像などが安置されていると云う。
鐘楼

「空海」774-835 真言宗の開祖 讃岐国生まれ、四国各地で修行して出家し、入唐し、嵯峨帝より高野山を賜る。
京都東寺を真言密教の道場とする。八十八ケ所巡礼・四国遍路は今も盛んである。庶民学校・著書は、三筆の一人活動範囲広い。
真言宗は、尊、「大日如来」(応化身)と弘法大師で、三宝礼「仏法僧に帰命」、「南無大師遍照金剛」または「南無遍照金剛」を唱える
弘法大師(空海)像
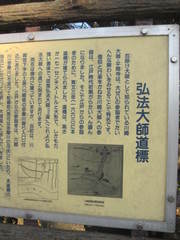


芭蕉の句碑が、「父母のしきりに戀し雉子の聲」1688年春、芭蕉が杜国と高野山を訪れて詠んだ句。芭蕉二百回忌に建立。
境内



虚子の句碑が、「金色の涼しき法の光かな」昭和33年、川崎大師に高浜虚子を招いて句会を。昭和34年虚子85歳で永眠。
種梨遺功碑 竹本細大夫の碑 高浜虚子翁句碑



門楼


次回は、北鎌倉方面へ。
江戸に入る道は東海道と中原街道と大山街道と津久井街道の四つあり、大名行列などで特に賑わった宿場、
江戸初期は幕府の補助金で苦しいようであったが、1659年道中奉行の支配下に編入されて次第に栄えて行ったと云う。
六郷橋が1668年流失し、渡し船で結ばれたが、幕府賄の無賃渡し船であったと云う。
1709年下本陣川崎宿名主「田中丘隅」の献策によって永代渡船権が川崎宿のものとなり財政を潤したと云う。
川崎大師の厄除け・縁起直しの寺として、江戸町民参拝に訪れ、農民・武士の間のも信仰が広まった。
徳川家斉・家慶・家定・家茂と参拝され、格式も高まっていったと云う。1872年新橋ー横浜間鉄道開通で賑わいは今でも続いている。
「天台宗寺院の明長寺」は、恵日山普門院と号し、創建年代は不詳、
静圓法印 1519年寂が、1469―1487年に創建したと伝えられていると云う。
所蔵の葵梶葉文染分辻ヶ花染小袖は、桃山時代に流行した絞り染めの技法といい、国重要文化財。東海三十三観音霊場24番寺。
本尊ー十一面観音立像。
川崎大師仲見世通りに

「辻が花染」は、室町時代後半から桃山時代末にかけて行われたと思われる染色で、絞り染の中に筆で、主に花・鳥などを描いたもの。
短い間にぱっと咲くように流行り、その後、こつ然と消えてしまった幻の染と云われている。
起源は三説ほどある。① つつじの花で染めたので、「つつじが花」がなまった。(色彩説)
② 辻(十字の斜格子に花文)から由来した。(文様形態説)
③ 奈良の木辻で京の染め職人が染めた。(あるいは奈良の木辻で遊女が始めた。)(地名説)
室町・桃山時代の、小袖や胴服などに見られる縫い絞りを主体とした模様染めを、「辻が花」と称していると云う。
寺社仏閣の参道というと、古くは七味唐辛子やお団子店、今ではさまざまな屋台が並んでいるイメージがある。
川崎大師周辺には、それらに加え、独自の「飴」「久寿餅」店が、数多く軒を連ねている。



京急川崎・大師線で三つ目「川崎大師」下車
「川崎大師・平間寺」
真言宗の寺。山号ー金剛山金乗院、1127年源義家の家臣「平間兼乗」が、夢のお告げにより海中から弘法大師木像を得て、寺を興しとのが
始まりと伝える。寺名は、「兼乗」の姓にちなむ。
東国八十八箇所1番・関東三十六不動霊場第7番札所・関東八十八ヵ所霊場特別霊場でもある。
仲見世通り表参道・厄除門 小さな菩薩堂 川崎大師不動門



この時、「兼乗」が42歳の厄年であったことから「厄除け大師」として信仰集めている。
「関東三山と云われる「成田山新勝寺」「高尾山薬王院」とここ「金剛山金乗院」を云う。
大山門

境内の八角五重塔は我が国初。初詣の参拝者数は、毎年首位を争っている。
五重塔(中興塔)は、昭和59年、弘法大師1150年御遠忌に落慶された。
仁王像 八角五重塔 神水舎



崇徳天皇の代1120年頃、平間兼乗という武士が、無実の罪により生国尾張を追われ、諸国を流浪したあげく、 川崎の地に住みつき、
漁猟をなりわいとして、貧しい暮らしを立てていた。
兼乗は深く仏法に帰依し、とくに弘法大師を崇信し、 わが身の不運な回り合せをかえりみ、42歳の厄年に当たり、 日夜厄除けの祈願をした。
ある夜、ひとりの高僧が、兼乗の夢まくらに立ち、「我むかし唐に在りしころ、わが像を刻み、 海上に放ちしことあり。已来未だ有縁の人を得ず。いま、汝速かに網し、これを供養し、功徳を諸人に及ぼさば、汝が災厄変じて福徳となり、諸願もまた満足すべし」と告げられ、
兼乗は、海に出て、光り輝いている場所に網を投じますと一躰の木像が引き揚げられたと云う。
それは、大師の尊いお像でした。
兼乗は随喜してこのお像を浄め、ささやかな草庵をむすんで、朝夕香花を捧げ、供養を続けたと云う。
兼乗は、源頼家(頼朝の長男)の家臣という。
大本堂

残念ながら川崎大師は、第2次大戦の戦禍で建築物など多くの貴重な文化財を失ってしまったため、現在見る事が出来るのは戦後に作られた比較的新しい物が殆ど、八角五重塔。昭和59年の落慶で、ひすいの大日如来像などが安置されていると云う。
鐘楼

「空海」774-835 真言宗の開祖 讃岐国生まれ、四国各地で修行して出家し、入唐し、嵯峨帝より高野山を賜る。
京都東寺を真言密教の道場とする。八十八ケ所巡礼・四国遍路は今も盛んである。庶民学校・著書は、三筆の一人活動範囲広い。
真言宗は、尊、「大日如来」(応化身)と弘法大師で、三宝礼「仏法僧に帰命」、「南無大師遍照金剛」または「南無遍照金剛」を唱える
弘法大師(空海)像
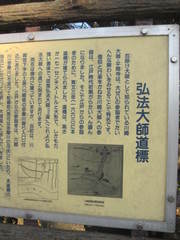


芭蕉の句碑が、「父母のしきりに戀し雉子の聲」1688年春、芭蕉が杜国と高野山を訪れて詠んだ句。芭蕉二百回忌に建立。
境内



虚子の句碑が、「金色の涼しき法の光かな」昭和33年、川崎大師に高浜虚子を招いて句会を。昭和34年虚子85歳で永眠。
種梨遺功碑 竹本細大夫の碑 高浜虚子翁句碑



門楼


次回は、北鎌倉方面へ。









