数日前、一歳年上の兄から小包が届きました。オヤッと思いながら開けましたら中から本と手紙が出て来ました。手紙には、同封の本を最近読み終えたが、大変面白いので贈る、とありました。このことだけ報告すると「お前たち兄弟は“文通の仲か”?」と言われそうですが、そうではありません。晩酌を終えた二人が長々と電話することもしばしばで、世に言う“文通の仲”(最近では、身分等の違いにより電話では失礼になるので、手紙にするという間柄を言うようです)ではありません。そして送られてきた本が一番左のです。

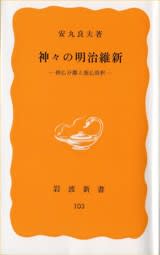

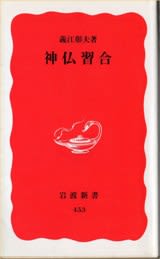
以前にもよく似たことがありました。そのとき兄が薦めた本が立花隆著『天皇と東大』でした。
確か下巻は自分で買って読み、あまりの興味深さに思わず備忘のためのレジュメをつくり兄に贈ったほどでした。『天皇と東大』も十分面白かったですが、今度の本はそれに優るとも劣らぬ面白さです。
半分ほど読んだ頃、犬山の友人から電話がありました。彼は今63歳くらいでしょうか、彼は若いころ、全く偶然の出会いからある期間生活時間を一部共有した仲で、それ以来交流が続いています。
「えりゃあさぶぃが、元気にやっとりゃあすか」
彼の犬山弁はいつも流暢で暖かく瞬時に暫くのご無沙汰を取り消してくれます。一通り世間話のあと、彼が突然話題を変えて「おもしりぇ~本を見つけたでよ、たゃァくつしてらすといかんで、推薦しようと思ってよぉ」と来た。「それは、ありがとう。どういう本?」と聞けば、何と、兄と同じ本を言ったのです。これには私も驚いたが、できるだけ冷静に、落ち着いた声で、「今、読んでます。本当に面白いね」と答えました。
「ほおきゃあ。さすがだなも。よかった、よかった」と彼は電話を切りました。
私は、昔、生活時間の一部を共にした若い友人合うと「最近君が読んだ本で面白かった本がある?」と聞くことにしています。犬山の友人にもよく訊いたのでそれを思い出して電話をくれたのでしょう。有難いことです。ここでこの本の面白さに触れるべきなのでしょうが、それは読もうと思っておられる方々に、浅薄な先入観を与えることになるので、差し控えます。
上の岩波新書3冊も最近読みました。私の師匠が、友人から依頼を受けて、その友人の住む土地の氏神様の社殿の石積みの調査を始められました。拝殿の土台部分の3段石積みの中に「家紋」か「神紋」のような高貴な文様を彫り込んだ大きな石が組み込まれているからです。共同調査を依頼されて「手掛かりは全くありませんが、喜んで協力します」と言って、前例通り私は「文献調査」。鶴舞図書館に出かけ、手当たり次第コピーをとったり、メモしたりでウロウロし、行き着いた先が「幕末から明治にかけて、政治に翻弄された村々の神様や仏様」の様子でした。「廃仏毀釈」という言葉は知っていましたが、中身はさっぱり知らず、今読めばその面白いこと。上の3冊もお薦めです。
写真はありませんが、私の学生時代からの畏友の推薦で、丸谷才一著『恋と女の日本文学』も読みました。これも大変面白い。テーマは「日本の文字文化の師匠である中国文学に全くない恋や愛に関する文学が、我が国では、万葉集から古今・新古今と連綿と開花したのは何故か」でありました。この本は全部旧かなづかいで書かれていて、ちょっと面喰いましたが、私の世代はすぐに慣れました。(わが畏友は、今も旧かなづかいで文章をお書きになります)「英雄は人を欺く」という中国の格言が日本に来るといつの間にか「英雄は色を好む」になるとか。 とにかく面白いです。
最近は見ようと思うテレビ番組が少なくてよく本が読めます。有難いことです。残念なことと言えば最近は感激して読んだ本でも、細部については忘れることが多いということ。以上、雑学・乱読の記でした。









