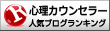私が幹事を務める「G4カウンセリング研究会」の今回の例会は
私が講師役で「自律訓練速習法」をテーマに取り上げました。
自律訓練法は1932年にドイツの精神科医シュルツによって創案
されたもので、心身を効果的にリラクゼーションさせる代表的な
方法です。もともとは心身症の治療として発展したものですが、
ストレスや緊張を和らげる効果があることから、健康増進法と
しても広く一般的に用いられています。
標準練習は次の7つの公式言語(リラックスをつくりだす
決まりの言葉)を使用して行われます。
背景公式「気持ちが落ち着いている」(安静練習)
第1公式「両腕、両脚が重たい」(重感練習)
第2公式「両腕、両脚が温かい」(温感練習)
第3公式「心臓が、静かに打っている」(心臓調整練習)
第4公式「楽に息をしている」(呼吸調整練習)
第5公式「お腹が温かい」(腹部温感練習)
第6公式「額が心地よく涼しい」(額部涼感練習)
リラクゼーションを目的とする場合通常は第2公式までで十分です。
シュルツは「自律訓練法というのは、催眠をかけられたときと同じ
状態になるように、合理的に組み立てられている生理学的訓練法である」
と述べています。自律訓練法はこのように催眠療法をもとに、ヨーガや
禅も取り入れた自己訓練法として確立されました。そこで自己催眠法
あるいは自己弛緩訓練法とも呼ばれています。
さて 「速習法」とはどういうことかといいますと。この自律訓練法は
極めて優れたシステムではありますが。習熟するにはそこそこの期間を要
します。そこでこの習得期間を短縮すべく工夫したものです。習得を困難
にする要因の一つが公式言語が感覚を対象としているためその効果を形と
して捉えにくいという点にあります。すなわち「重たい」「温かい」という
感覚は訓練の初期においては「そのように感じたような感じないような
・・・・」といったいささか心もとないものになりがちです。
そこで 私は背景公式「気持ちが落ち着いている」と第1公式「両腕、
両脚が重たい」の間に観念運動を挿入しました。観念運動とは 運動に結び
付いた観念(身体が揺れる、腕が上がる・下がる等)を心に念ずるとそれを
否定する意志や反対観念が生じない限りその観念が運動に結びつく現象を
いいます。例えば「身体が左右に揺れる」と念じると身体が実際に揺れ始めます。
(もちろん無意識のうちに本人が身体を揺らしている訳ですが) この技法の
良いところは、本人にも周囲にも 目に見えてその効果を捉えられるという点
にあります。
すなわち観念運動が生じていれば第1・第2公式の感覚が生じる可能性が非常に
大きいと視認できるわけです。
この方法により 現役時代に営業教育の一環として 自律訓練法の習得を劇的に
早めた実績があります。
私が講師役で「自律訓練速習法」をテーマに取り上げました。
自律訓練法は1932年にドイツの精神科医シュルツによって創案
されたもので、心身を効果的にリラクゼーションさせる代表的な
方法です。もともとは心身症の治療として発展したものですが、
ストレスや緊張を和らげる効果があることから、健康増進法と
しても広く一般的に用いられています。
標準練習は次の7つの公式言語(リラックスをつくりだす
決まりの言葉)を使用して行われます。
背景公式「気持ちが落ち着いている」(安静練習)
第1公式「両腕、両脚が重たい」(重感練習)
第2公式「両腕、両脚が温かい」(温感練習)
第3公式「心臓が、静かに打っている」(心臓調整練習)
第4公式「楽に息をしている」(呼吸調整練習)
第5公式「お腹が温かい」(腹部温感練習)
第6公式「額が心地よく涼しい」(額部涼感練習)
リラクゼーションを目的とする場合通常は第2公式までで十分です。
シュルツは「自律訓練法というのは、催眠をかけられたときと同じ
状態になるように、合理的に組み立てられている生理学的訓練法である」
と述べています。自律訓練法はこのように催眠療法をもとに、ヨーガや
禅も取り入れた自己訓練法として確立されました。そこで自己催眠法
あるいは自己弛緩訓練法とも呼ばれています。
さて 「速習法」とはどういうことかといいますと。この自律訓練法は
極めて優れたシステムではありますが。習熟するにはそこそこの期間を要
します。そこでこの習得期間を短縮すべく工夫したものです。習得を困難
にする要因の一つが公式言語が感覚を対象としているためその効果を形と
して捉えにくいという点にあります。すなわち「重たい」「温かい」という
感覚は訓練の初期においては「そのように感じたような感じないような
・・・・」といったいささか心もとないものになりがちです。
そこで 私は背景公式「気持ちが落ち着いている」と第1公式「両腕、
両脚が重たい」の間に観念運動を挿入しました。観念運動とは 運動に結び
付いた観念(身体が揺れる、腕が上がる・下がる等)を心に念ずるとそれを
否定する意志や反対観念が生じない限りその観念が運動に結びつく現象を
いいます。例えば「身体が左右に揺れる」と念じると身体が実際に揺れ始めます。
(もちろん無意識のうちに本人が身体を揺らしている訳ですが) この技法の
良いところは、本人にも周囲にも 目に見えてその効果を捉えられるという点
にあります。
すなわち観念運動が生じていれば第1・第2公式の感覚が生じる可能性が非常に
大きいと視認できるわけです。
この方法により 現役時代に営業教育の一環として 自律訓練法の習得を劇的に
早めた実績があります。