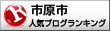昨日、今年最後の市議会定例会が閉会しました。
年4回の定例会で、毎回この瞬間は何とも言えないつかの間の解放感。学生時代のキツい期末テストがようやく終わった時の感じかな(笑)。
この後に行われる議員研修会のために市民会館に移動したところで、森山さんに撮ってもらいました♪

ここでちょっと注目してもらいたいのが、このバッヂ。

最近、このバッヂをつけている首長や国会議員をTVでよく見かけるようになりましたね。
「SDGs」
もうご存知の方も多いと思いますが、 2015年の国連サミットで採択された2030年までの世界共通の目標です。
貧困や飢餓、環境問題のほか、教育やジェンダー、経済成長など17項目が掲げられています。
豊かさを目指しながら地球環境も守る。「社会・環境・経済」のバランスがとれた持続可能で多様性と包摂性のある社会。
「誰一人取り残さない」「全ての人が参加する」がポイントです。
SDGsとは(松山市HP) ぜひクリックしてみてください。
ぜひクリックしてみてください。
市民や市内企業へのメッセージとして、ナマケモノでもできるアクションガイドなど、わかりやすく紹介されています。市の意気込みが伝わってきます!

(松山市のHPからお借りしました)
現在、市原市もSDGsを取り入れた総合計画の改訂版を策定しているところです。
議会での訴えが実って、嬉しいやら有難いやら。
世界中の人々が同じ目標に向かってアクションを起こすって、それだけでもワクワクしませんか?
まさに、地球丸ごとワンチーム!
年4回の定例会で、毎回この瞬間は何とも言えないつかの間の解放感。学生時代のキツい期末テストがようやく終わった時の感じかな(笑)。
この後に行われる議員研修会のために市民会館に移動したところで、森山さんに撮ってもらいました♪

ここでちょっと注目してもらいたいのが、このバッヂ。

最近、このバッヂをつけている首長や国会議員をTVでよく見かけるようになりましたね。
「SDGs」
もうご存知の方も多いと思いますが、 2015年の国連サミットで採択された2030年までの世界共通の目標です。
貧困や飢餓、環境問題のほか、教育やジェンダー、経済成長など17項目が掲げられています。
豊かさを目指しながら地球環境も守る。「社会・環境・経済」のバランスがとれた持続可能で多様性と包摂性のある社会。
「誰一人取り残さない」「全ての人が参加する」がポイントです。
SDGsとは(松山市HP)
 ぜひクリックしてみてください。
ぜひクリックしてみてください。市民や市内企業へのメッセージとして、ナマケモノでもできるアクションガイドなど、わかりやすく紹介されています。市の意気込みが伝わってきます!

(松山市のHPからお借りしました)
現在、市原市もSDGsを取り入れた総合計画の改訂版を策定しているところです。
議会での訴えが実って、嬉しいやら有難いやら。
世界中の人々が同じ目標に向かってアクションを起こすって、それだけでもワクワクしませんか?
まさに、地球丸ごとワンチーム!

























 当事者の申し出
当事者の申し出