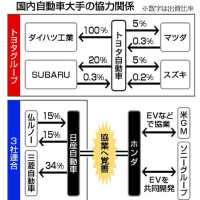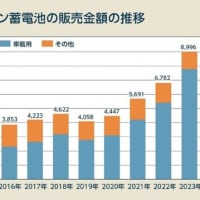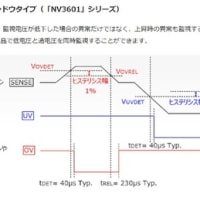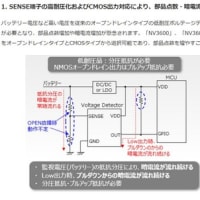【書評】冤罪弁護士(今村核著)
拙人はルポルタージュ(仏語)というジャンルは読み物として好きなジャンルと意識している。だから、図書館を訪れる時は、リポルタージュのジャンルの書棚を見廻し、自分の関心ある仕事だとか経験の本を抜き出し読むことが多い。今回の書評に上げた「冤罪弁護士」がルポルタージュの書棚に分類されていた訳ではないが、一読して思うのは、著者が弁護士活動をやってきて、冤罪事件を無罪として勝ち取ってきた、正にルポルタージュとしてのエッセンスに満ち溢れた本というのが読後感だ。

【著者略歴】
今村核(いまむらかく)略歴 1962年生まれ(60才)
1992年(39)で弁護士登録
旬報法律事務所 所属(弁護士29名)
https://junpo.org/
つまり、過去の担当することになった刑事事件の弁護事案で、当初の当番弁護士(刑事事件として逮捕拘留後に被告の希望があれば初回1回は弁護士会負担で無償で聴取を行う弁護活動)として、被告と触れ合い、これは正に冤罪だと確信すると、人質司法と批判されている長期拘留で挫けそうになる被告人を励ましつつ、事件当初の捜査段階から弁護活動を続けてきた実例と共に、現在日本の司法が置かれたあまりに酷い現状を怒り嘆きつつも、戦ってきたという実情が描かれている。
拙人は世に様々な職種はあれども、非合法な活動をしていない限りにおいては、どんな職種でも社会的な使命というと大げさだが、社会の役に立たない業種はないだろうと思っている。そういう様々な業種において、弁護士という職種はもちろん社会に貢献すべき使命を持っており、そのことは世間一般で云う社会的の権威というか地位は高い職種であるのだろう。一方現実の弁護士を眺めると、営利だけに走ったり、過去にも幾つか事例があるが通称ヤメ検といわれる元検察官上層部(最高検検事正とか特捜部長など)が、大企業の顧問弁護士の顧問を幾つも務めている程度なら許せるが、そのスキルの逆利用でおよそ社会正義を逸脱して自己利益を食んでいる様な犯罪事件を知ると、許せないという思いも込み上げてくる。
ところで、弁護士の活動は、一般社会において訴訟に至らないまでも、様々な法令知識を駆使したりして、適切なアドバイスをしたり、民事賠償事案の示談活動とか民事賠償訴訟を行うことが多いのだろう。つまり、世の訴訟事案は刑事と民事に別れるが、およそ圧倒的に民事専門で、依頼を受ければ消極的には関わるが積極的に刑事弁護に関わる弁護士は少ないと意識している。この理由の一つとして、日本の場合、刑事事件は検察が立証義務を負って起訴した案件を裁判官が妥当かどうかを審査するという仕組みだが、その有罪率は99.9%であることが知られている。実際のところ、小数点第2位までを記せば。99.95%程度の有罪率かもしれない。そんなことが、刑事事件を専門家として弁護活動をやろうとしても、労多くて実入りが少ないということから、刑事弁護に積極的な弁護士を少なくさせているのだろうと想像する。
拙人は過去保険会社の調査員として活動し、それ以後も些少ながら幾らかの争いごとだとか、意見書の作成に関わることがあるが、特に不正事案と云われる保険金詐欺に類するものを排除するには、当事者がどういう説明をしているのかとか、第三者の目撃者の証言というのも無視はできないが、一番の問題は、以下に客観性がある問題としてことを見つめそのことを訴求することが大事かということを感じ続けて来た。ありていに云えば、言葉ではなく物証だとか論理科学的にあり得ないという思考が極めて大事で、直感で疑わしいといいう意見を持ったにしても、そのことをどうやって客観的に説明できるかどうかが勝負どころだと意識してきた。
そういう視点で、この書を読むと、正に著者の思考もその通りで、東大法学部卒で司法試験を取得しているのだから正に文系の方なのだが、ある時は自分で事件現場を歩いたり、事件のアリバイ矛盾を崩すために、移動時間を道路公団の交通状況の記録を探ったり、簡易な実験を自ら行ったり、鑑定を頼んだ火災の燃焼実験に自ら立ち会って、その状況を確認したりと、正に文系というより行動派の工学的実務家という側面を強く感じさせるとことが凄く共感を感じたところでもある。
その上で、法学の知識を充分知った上での、論理という面では、拙人などおよびもしない論理的思考が強く、事件の検察側立証の矛盾として、ここを崩せば検察側の論理は崩壊するという思考の深さというかおそらく正義感に根ざした執着の凄さを感じさせずにいられない、おそらく現状の日本では希有な弁護士ではないかと思える。
以下は、本書の最終章で、著者が述べる論理で大事と思う部分を書き留めた。

1.有罪の論理
検察官が「合理的な疑いを超えた」証明をした場合、有罪判決となる。
最高裁の判例として「犯罪の証明がなされた」とは「高度の必然性」が認められる場合をいう。この必然性とは、「反対事実の存在を許さないほどの確実性を志向した上での「犯罪の証明は十分」であるという確信的な判断に基づくものでなければならない。(最高裁裁決 昭和48.12.13)
これは通常人であれば「誰でも疑いを挟まない程の証明」と云われる。英米の陪審員制度では12名全員一致の評決でなければ有罪にならない。つまり陪審員1人1人の疑義を乗り越えたところに、「合理的な疑いを越えた証明」があるのが本来の陪審員制度と考えられる。
ローマの法の格言に「疑わしきは被告人の利益に」原則がある。このことは「例え10名の犯人を逃そうとも、一人の無辜を罰するなかれ」とも云われる。ところが、日本の職業裁判官に「1人の無辜も処罰してはならばいが、1人の犯人も逃してはならない」と述べる者がいるという。
かつての欧州および日本の裁判では、証拠の証明力を法律で決めていたそうで、これを「法廷証拠主義」というそうだ。その具体的なものとして、「自白がなければ刑罰を課すことはできない」とする考え方が多かったそうだ。そこで、自白を引き出すために、捜査官憲は拷問してでも自白を引き出すことに注力しがちとなり、自白には拷問の影がつきまとったという。
そもそも証拠の証明力とは、案件それぞれにおいて差異があるので法で規定すること自体が困難ということがある。そこで、証拠の証明力の評価を裁判官の理性による判断に委ねる「自由心証主義」に移って来たと云う。現行日本の刑事訴訟法でも「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる(318条)と規定している。
自由心証主義と云っても、裁判官が恣意的な証拠の評価を許すものではない。論理則、経験則に従うことが自由心証主義の内在的制約となる。ここで、この論理則違反とは、判決が論理的に矛盾していることを指す。一方、経験則とは、一般的事象として、こういう状況でこの様な結果にならないというあくまで一般論というものから、物を離せば落下するという物理法則に由来することから、死刑に値する罪で自白はあり得ないだろうという誤った物までがあり得る。
証拠による証明力だが、供述証拠と非供述証拠に分類できる。ここで、供述証拠とは、事件の記録が人の記憶に残されたものであり、非供述証拠とは、事件の痕跡が物に残されたもの、いわゆる物証となる。現実の裁判で、供述証拠と非供述証拠が対立する場合、裁判官が想像を巡らせ、そのそれぞれが両立する可能性に言及する判決がよくあるという。しかし、この両立する可能性を想像するという、ある意味妥協の拡大想像というもので、自由心証主義の限界を示していることが課題と思える。
2.控訴審
一審(地裁)もしくは二審(高裁)での判決に不服がある時は、当該判決から14日以内を期限に控訴ができる。このことは、同判決を受けて14日を越えて控訴しなかった場合は、同判決が確定することを意味する。
この控訴の手続きは、ただ控訴する趣旨の書面を提出すればよく、理由までは必用ない。ただ、この後提出する控訴趣意書に、控訴するについての、様々な言い分を記す。端的なのは無実であるのに有罪判決を受けた時は、事実認定の誤認が控訴理由(趣意)の中心となる。
日本の刑事訴訟法では、被告人が控訴した場合は、原判決より重い刑を課すことはできない。(法402条不利益変更の禁止)ただし、日本の場合は検察にも控訴権があるが、原判決が無罪でも検察控訴の場合は有罪となる場合がある。しかし、英米では検察官の控訴を被告を「二重の危険」にさらすものとして憲法上許されていない。合衆国憲法修正第5条では「何人も同一の犯罪について重ねて生命または身体の危険にさらされることはない」としている。これは日本国憲法39条でも「同一の犯罪について重ねて刑事上の責任は問われない」とう規定があるが、現実には検察官控訴で無罪が有罪になっている現実があるのだが、憲法違反にならないのだという。これについては、最高裁(昭和25.9.27)の判決で「一審、二審、上告審を通じて一度の危険であり、検察官控訴は憲法39条違反に反しない」と結論付けたと云う。この記述を見て、法律の専門家ではない拙人ではあるが、あまりに論理矛盾、経験則から見ても異常で、英米の法解釈と極めて不一致を感じると思うのは多くの方が同意するのではないだろうか。
著者によると、検察官控訴による原判決の破棄は比率は統計上およそ2/3にも達するという。また、一審の無罪判決が検察官控訴により破棄(有罪)となると、一審裁判官は裁判所組織内で冷遇される傾向があると聞く。
3.上告審(最高裁判断)
被告は控訴審(二審)の判断に不服がある時は上告(最高裁)できるが、上告の理由は原則として、憲法違反、最高裁判例違反とされている。(同405条)
ただし、最高裁は「重大な事実誤認」があり、これを破棄しなければ「著しく正義に反する」ときは、原判決を破棄することができるとされている。(同411条)この職権による破棄とは最高裁が最終審であり「裁判所としての最後の頼り」であるために規定されている。しかし、この411条を理由に破棄される事案は近年少なくなり、数年に1回で、ほとんどの上告案件は、405条の適法な上告理由ではないと、上告棄却の三行半の決定が下され続けている。
【今村核を描く参考動画】
BS1スペシャル「ブレイブ 勇敢なる者“えん罪弁護士”完全版」part1 1101 201804152200
2020/11/03(50分)
https://www.youtube.com/watch?v=LuRx_CbbeG8
#冤罪事件 #こういう正義感溢れる弁護士もいる
拙人はルポルタージュ(仏語)というジャンルは読み物として好きなジャンルと意識している。だから、図書館を訪れる時は、リポルタージュのジャンルの書棚を見廻し、自分の関心ある仕事だとか経験の本を抜き出し読むことが多い。今回の書評に上げた「冤罪弁護士」がルポルタージュの書棚に分類されていた訳ではないが、一読して思うのは、著者が弁護士活動をやってきて、冤罪事件を無罪として勝ち取ってきた、正にルポルタージュとしてのエッセンスに満ち溢れた本というのが読後感だ。

【著者略歴】
今村核(いまむらかく)略歴 1962年生まれ(60才)
1992年(39)で弁護士登録
旬報法律事務所 所属(弁護士29名)
https://junpo.org/
つまり、過去の担当することになった刑事事件の弁護事案で、当初の当番弁護士(刑事事件として逮捕拘留後に被告の希望があれば初回1回は弁護士会負担で無償で聴取を行う弁護活動)として、被告と触れ合い、これは正に冤罪だと確信すると、人質司法と批判されている長期拘留で挫けそうになる被告人を励ましつつ、事件当初の捜査段階から弁護活動を続けてきた実例と共に、現在日本の司法が置かれたあまりに酷い現状を怒り嘆きつつも、戦ってきたという実情が描かれている。
拙人は世に様々な職種はあれども、非合法な活動をしていない限りにおいては、どんな職種でも社会的な使命というと大げさだが、社会の役に立たない業種はないだろうと思っている。そういう様々な業種において、弁護士という職種はもちろん社会に貢献すべき使命を持っており、そのことは世間一般で云う社会的の権威というか地位は高い職種であるのだろう。一方現実の弁護士を眺めると、営利だけに走ったり、過去にも幾つか事例があるが通称ヤメ検といわれる元検察官上層部(最高検検事正とか特捜部長など)が、大企業の顧問弁護士の顧問を幾つも務めている程度なら許せるが、そのスキルの逆利用でおよそ社会正義を逸脱して自己利益を食んでいる様な犯罪事件を知ると、許せないという思いも込み上げてくる。
ところで、弁護士の活動は、一般社会において訴訟に至らないまでも、様々な法令知識を駆使したりして、適切なアドバイスをしたり、民事賠償事案の示談活動とか民事賠償訴訟を行うことが多いのだろう。つまり、世の訴訟事案は刑事と民事に別れるが、およそ圧倒的に民事専門で、依頼を受ければ消極的には関わるが積極的に刑事弁護に関わる弁護士は少ないと意識している。この理由の一つとして、日本の場合、刑事事件は検察が立証義務を負って起訴した案件を裁判官が妥当かどうかを審査するという仕組みだが、その有罪率は99.9%であることが知られている。実際のところ、小数点第2位までを記せば。99.95%程度の有罪率かもしれない。そんなことが、刑事事件を専門家として弁護活動をやろうとしても、労多くて実入りが少ないということから、刑事弁護に積極的な弁護士を少なくさせているのだろうと想像する。
拙人は過去保険会社の調査員として活動し、それ以後も些少ながら幾らかの争いごとだとか、意見書の作成に関わることがあるが、特に不正事案と云われる保険金詐欺に類するものを排除するには、当事者がどういう説明をしているのかとか、第三者の目撃者の証言というのも無視はできないが、一番の問題は、以下に客観性がある問題としてことを見つめそのことを訴求することが大事かということを感じ続けて来た。ありていに云えば、言葉ではなく物証だとか論理科学的にあり得ないという思考が極めて大事で、直感で疑わしいといいう意見を持ったにしても、そのことをどうやって客観的に説明できるかどうかが勝負どころだと意識してきた。
そういう視点で、この書を読むと、正に著者の思考もその通りで、東大法学部卒で司法試験を取得しているのだから正に文系の方なのだが、ある時は自分で事件現場を歩いたり、事件のアリバイ矛盾を崩すために、移動時間を道路公団の交通状況の記録を探ったり、簡易な実験を自ら行ったり、鑑定を頼んだ火災の燃焼実験に自ら立ち会って、その状況を確認したりと、正に文系というより行動派の工学的実務家という側面を強く感じさせるとことが凄く共感を感じたところでもある。
その上で、法学の知識を充分知った上での、論理という面では、拙人などおよびもしない論理的思考が強く、事件の検察側立証の矛盾として、ここを崩せば検察側の論理は崩壊するという思考の深さというかおそらく正義感に根ざした執着の凄さを感じさせずにいられない、おそらく現状の日本では希有な弁護士ではないかと思える。
以下は、本書の最終章で、著者が述べる論理で大事と思う部分を書き留めた。

1.有罪の論理
検察官が「合理的な疑いを超えた」証明をした場合、有罪判決となる。
最高裁の判例として「犯罪の証明がなされた」とは「高度の必然性」が認められる場合をいう。この必然性とは、「反対事実の存在を許さないほどの確実性を志向した上での「犯罪の証明は十分」であるという確信的な判断に基づくものでなければならない。(最高裁裁決 昭和48.12.13)
これは通常人であれば「誰でも疑いを挟まない程の証明」と云われる。英米の陪審員制度では12名全員一致の評決でなければ有罪にならない。つまり陪審員1人1人の疑義を乗り越えたところに、「合理的な疑いを越えた証明」があるのが本来の陪審員制度と考えられる。
ローマの法の格言に「疑わしきは被告人の利益に」原則がある。このことは「例え10名の犯人を逃そうとも、一人の無辜を罰するなかれ」とも云われる。ところが、日本の職業裁判官に「1人の無辜も処罰してはならばいが、1人の犯人も逃してはならない」と述べる者がいるという。
かつての欧州および日本の裁判では、証拠の証明力を法律で決めていたそうで、これを「法廷証拠主義」というそうだ。その具体的なものとして、「自白がなければ刑罰を課すことはできない」とする考え方が多かったそうだ。そこで、自白を引き出すために、捜査官憲は拷問してでも自白を引き出すことに注力しがちとなり、自白には拷問の影がつきまとったという。
そもそも証拠の証明力とは、案件それぞれにおいて差異があるので法で規定すること自体が困難ということがある。そこで、証拠の証明力の評価を裁判官の理性による判断に委ねる「自由心証主義」に移って来たと云う。現行日本の刑事訴訟法でも「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる(318条)と規定している。
自由心証主義と云っても、裁判官が恣意的な証拠の評価を許すものではない。論理則、経験則に従うことが自由心証主義の内在的制約となる。ここで、この論理則違反とは、判決が論理的に矛盾していることを指す。一方、経験則とは、一般的事象として、こういう状況でこの様な結果にならないというあくまで一般論というものから、物を離せば落下するという物理法則に由来することから、死刑に値する罪で自白はあり得ないだろうという誤った物までがあり得る。
証拠による証明力だが、供述証拠と非供述証拠に分類できる。ここで、供述証拠とは、事件の記録が人の記憶に残されたものであり、非供述証拠とは、事件の痕跡が物に残されたもの、いわゆる物証となる。現実の裁判で、供述証拠と非供述証拠が対立する場合、裁判官が想像を巡らせ、そのそれぞれが両立する可能性に言及する判決がよくあるという。しかし、この両立する可能性を想像するという、ある意味妥協の拡大想像というもので、自由心証主義の限界を示していることが課題と思える。
2.控訴審
一審(地裁)もしくは二審(高裁)での判決に不服がある時は、当該判決から14日以内を期限に控訴ができる。このことは、同判決を受けて14日を越えて控訴しなかった場合は、同判決が確定することを意味する。
この控訴の手続きは、ただ控訴する趣旨の書面を提出すればよく、理由までは必用ない。ただ、この後提出する控訴趣意書に、控訴するについての、様々な言い分を記す。端的なのは無実であるのに有罪判決を受けた時は、事実認定の誤認が控訴理由(趣意)の中心となる。
日本の刑事訴訟法では、被告人が控訴した場合は、原判決より重い刑を課すことはできない。(法402条不利益変更の禁止)ただし、日本の場合は検察にも控訴権があるが、原判決が無罪でも検察控訴の場合は有罪となる場合がある。しかし、英米では検察官の控訴を被告を「二重の危険」にさらすものとして憲法上許されていない。合衆国憲法修正第5条では「何人も同一の犯罪について重ねて生命または身体の危険にさらされることはない」としている。これは日本国憲法39条でも「同一の犯罪について重ねて刑事上の責任は問われない」とう規定があるが、現実には検察官控訴で無罪が有罪になっている現実があるのだが、憲法違反にならないのだという。これについては、最高裁(昭和25.9.27)の判決で「一審、二審、上告審を通じて一度の危険であり、検察官控訴は憲法39条違反に反しない」と結論付けたと云う。この記述を見て、法律の専門家ではない拙人ではあるが、あまりに論理矛盾、経験則から見ても異常で、英米の法解釈と極めて不一致を感じると思うのは多くの方が同意するのではないだろうか。
著者によると、検察官控訴による原判決の破棄は比率は統計上およそ2/3にも達するという。また、一審の無罪判決が検察官控訴により破棄(有罪)となると、一審裁判官は裁判所組織内で冷遇される傾向があると聞く。
3.上告審(最高裁判断)
被告は控訴審(二審)の判断に不服がある時は上告(最高裁)できるが、上告の理由は原則として、憲法違反、最高裁判例違反とされている。(同405条)
ただし、最高裁は「重大な事実誤認」があり、これを破棄しなければ「著しく正義に反する」ときは、原判決を破棄することができるとされている。(同411条)この職権による破棄とは最高裁が最終審であり「裁判所としての最後の頼り」であるために規定されている。しかし、この411条を理由に破棄される事案は近年少なくなり、数年に1回で、ほとんどの上告案件は、405条の適法な上告理由ではないと、上告棄却の三行半の決定が下され続けている。
【今村核を描く参考動画】
BS1スペシャル「ブレイブ 勇敢なる者“えん罪弁護士”完全版」part1 1101 201804152200
2020/11/03(50分)
https://www.youtube.com/watch?v=LuRx_CbbeG8
#冤罪事件 #こういう正義感溢れる弁護士もいる