指数の話し・基表値の構成・作成法 その1
ここでは、自研センターが企業秘密とか抗弁し、基表を非公表としているが、かつて損保調査人として、知り得た基表値の一端からある程度核心を持てる内容として基表から指数の作り方をレクチャーして見たい。これは、そもそも基表という聞き慣れない言葉の意味を理解していない修理工場や損保調査員に、改めて基表とはなんぞやと云うことを知ってもらうために起草した内容だ。
それには、序章として自研センターの成り立ちとか歴史から、掘り起こして眺めることが大事と意識しつつ以下に記していく。なお、いささか長文となったこともあり、その1およびその2と分割して、今回はその1として序論を記す。
その1 序論
1.自研センターの歴史
そもそも、私こと、損保在職中に自研センターに2年間派遣勤務していたのだが、その期間は1990年4月から1991年3末末までだが、当時の自研センター社長は東京海上出身の横井社長で、初代が島田社長(同じく東海出身)だから2代目の社長だった。
私の自研センターでの所属は研修部であり、当時の研修部長は最初の半年あまりは飯○氏で確か同和火災出身だったと記憶している。その後は、平○という安田火災(現損保ジャパン)の人物だった。これら、自研センターの上層部というのは、いわゆる損保の損調関係者でなく、どちらかと云うと営業もしくはゼネラリストたる本社所属の人物だった。
私は損保調査員時代に、本社勤務が通産9年在籍することになったのだが、付き合いとしては損害調査部たる損調関係者が多数ではあったが、そもそも子会社に移籍してくる上層部人物とか、本社でも様々な人物と触れ合って来たが、端的に云えば生粋の損調部門の生え抜きより、営業とか本社人事部とか総合企画室出身者を比べると、驚くほど人物のスケール格差があり、子会社の損害調査員(アジャスターのこと)は視野が狭く端的に云えばレベルが低いのが通例一般(例外も些少あり)だが、総合職(軍隊で云う将校、官僚で云うキャリア)でも、損調所属はレベルが低い者が多かった(もちろん例外あり)というのが感想だ。
そこ行くと、営業部門でもゴミはいるのだが、本社所属ともなると、人物スケールが異なる人物が多く感じられたものだった。そもそも、損保社長にまで上り詰める損調出身人物は希なるもので、合併以前の大東京火災に僅かに存在したという記憶だ。その大東京も、あいおい社として合併以来、査定優先思考は影を潜め見る影もなくなった。
しかし、当時の自研センターでも、横井社長とか、研修部長クラスになると、ある意味本流から外された左遷とも云える立場で来ているのだが、安田の平〇はときおりそういう憤まんを見せてはいたが、少なくとも横井社長には、そういう思いを感じさせない人物であったという思いだ。
ところで、自研センターという組織だが、役員構成員は当時は現在損保14社(設立時は大合併以前なのでもっと多かった)の共同出資により作られた組織であるが、自研センターに常勤していない社でも、当該社の社長は理事として参加している。
また、その出資率は損保の規模に応じているのだろうが、社長は現在に至るも東京海上日動社(合併以前は東海社)出身者が就任している。なお、最近聞き及ぶところでは、初代とか2代目、3代目くらいまでは、就任した社長は10年程存在したのだが、近年は3年程度で交代している様だ。このことは何を示すかと云えば、要するに自研センターという組織の価値が、相対的に低下してきており、これは想像だが最近の社長となっている東京海上日動出身社長はおそらく日動ルーツの、いわば最後のお勤めを果たしているのが実態だろうと想像できる。
なお、自研センターが設立されたのは1975年(昭和50年)ちょっと前であり、これとほぼ時を同じくして、アジャスター制度という資格制度が生まれているという歴史がある。そして、そもそもアジャスター制度以前には、調査人という資格も何もない、ただ自動車整備とか板金の知識のある者を損保各社は採用して、オール歩合に近い請負たる身分で調査活動(事故車の立会協定のみ)に利用して来ていたのだった。そんな中、当時の損保ガリバーたる社たる東海社では、自社研修施設として現在の自研センターの土地を取得して、建屋の建設工事も始めていたのであった。そんな中1970年代前に、損保各社で欧米の損保事情の視察団というのが構成され、何度か視察を繰り返すということが行われ、特に欧州の損保が経営するリペアリサーチ(作業研究)とか調査員の研修施設が目に止まり、日本でも同様のものを作ろうといういう気運が起きたのだった。そこで、既に建設が始まっていた東海社の研修施設を、そのまま自研センターとして流用しつつ、アジャスター制度を作ろうと云う動きに急速になったのだと伝え聞いている。
ここで、自研センターの事業の核心は以下の2つであるとされた。
➀アジャスター資格制度に関わる研修
②リペアリサーチ活動として作業研究だが、最終目標として料金に結び付く標準作業時間の策定、そしてそれが転じて指数の策定へと移行した。
自研センターの設立に関わる資本金は損保各社の規模に応じた出資金によるが、運営稼働費としては、先の研修費(1人日額25千円程)と指数策定の販売費という構成だ。なお、ここで触れておかなければならないことだが、そもそも指数とかアジャスター制度以前のその昔存在した鑑定人制度(全国で100名程度存在)の管理とかは、現在保険の自由化の中で名称が変更になったが保険料率料率会(現保険料率算定機構)であったことだ。この算定会(現算定機構)というのは、特別立法により組織された機関であり、会社組織ではない団体だ。つまり営利を目的とする法人ではない。それが、現在では、指数はコグニビジョン(旧日本アウダテックス)という営利を目的とする法人に移行していることや、アジャスターの管理は一般社団法人日本損害保険協会に移行している。
さて、私の自研センターでの活動だが、研修部に所属し、主には各アジャスター研修に関わる準備とか、研修の補助的な業務が主で、その他は自由に研究なりしてもよろしいというある意味気軽な立場であった。であるから、自己の研鑽のために、感心を持つ講師の聴講をしたり、自社の問い合わせに答えるための報告書を作成したりという日々が続いていたのだった。そういう中で、当時でも指数策定部には、部外者立ち入り禁止という感じで閉鎖的な様子があったのだが、たまたま席を隣にした関○氏という、いわば定年を過ぎ恩給の形で週3日程度出社する方の隣の席にいることになったのだが、この方は元来保険料率算定会所属で自研センター黎明期という時代に、作業時間の基礎策定に関わった方だったのだ。その方とは種々話しを繰り返したのだが、前職は東京日産サービス部長で、それ以前の戦前戦中の頃は日立に属して水力発電の水車(タービン)設計をしていたという生粋の技術者畑の方だった。今年半年ほど前の人づての話しでは未だご存命だと聞くが、おそらく80代も中頃となるのではないだろうか。
まず、私の現在の指数とか工数を知る序章という面で、この方に聞いた知識はかなり大きなものがあると回想している。ただし、今現在の私の回想としては、この方も学者に良くある視野の狭さというのが内在していて、ある意味権威趣意に毒されており、オープンな思考の広がりには欠けていたという思いを持つところもあるのだが、現在の指数の底流に流れる考え方を知るには極めて参考となる意見を聞けたことは大変参考となった。
なお、自研センターの車両メーカー出身者について補足しておきたいが、そもそも立ち上げ時に、有力ディーラーもしくはメーカーからの転籍もしくは縁故頼りの転入者というのが、私が派遣時にも存在したし、それ以前にも存していた様だ。この中には、リサーチ所属で、当初の標準作業時間から指数に移行するあたりまで筆頭だった長〇〇氏などはTトヨタサービス部長とか、在籍当時は同じくリサーチ部長だった〇野などはTペット出身だった。あと研修部でも、総務的な業務を行なっていた良き年配者には名前を失念したがホンダの技術畑でない人物だったが、時々宗一郎氏の逸話などを聞いたものだった。あと、日産のおそらくサービス部から来ていたと思うが沢〇氏などは、比較的温厚な方だったと回想する。これも半年くらい前に、自研センターの数年前まで部長待遇だった方(これも出身はTトヨタ)に聞いたのだが、最近ではトヨタメーカー出身者が存するそうだが、パワハラまではいかないが、とにかく強気の発言を繰り返し、廻りが白けているということを聞き及ぶ。こういう話は、他でも聞かれ、トヨタ東富士研究所の近くには、ある損保の研修所があるのだが、そこの課長職はトヨタの定席になっているのだが、とにかく威張り倒しているという。そもそもこの棒損保研修所は、損保でそこまで必要性があるのかと思うバリア実験装置まで保有するのだが、噂だがトヨタの下請け的な実験を繰り返しているという。
2.自研センターから本社研修部に戻ってから
自研センターでの2年を過ごし、1992年4月に、研修部に戻った。それからも、97年に研修部を離脱するまでの間、自研センターとは縁あり研修講師を担当するなど自研センターを訪れる機会も続いていた。また、自研センターで巡り合った同じ立場での出向者とか、これはと思う極一部の講師とは、30年余を過ぎる今でも少数だが付き合いは続いている。
ところで、1993年頃から今思えば1996年10月まで、自研センターでは今まで公開していなかった基表の全面公開ではないが、一部の基表値も事例として公開しつつ、基表による指数値の策定方法を徐々に公開し始めていたという歴史があるのだ。このことは、各社当時の本社勤務の調査員にしか知られていないことと思うが、これは当時実体験している者として記録しておきたい。
何故、こういう動きになり、それが96年10月を境に、パッタリ止まったかを、今だから客観的に意識できることとして記しておきたい。
それは1996年10月に公正取引委員会より「社団法人日本損害保険協会に対する警告について」という、いわゆる公取からの警告文書が出されたことに大きな要因はあるのだろう。この警告は、指数に乗ずる対応単価について、県単位で談合に等しい行為を行っていることで、独占禁止法に抵触する恐れがあるとの警告だったのだ。つまり、料金を決める単価についての警告なのだが、料金を決めるもう一つの要素である指数値については触れていないものの、自研センターでは、従来の姿勢が大きく変化をしたということがある。
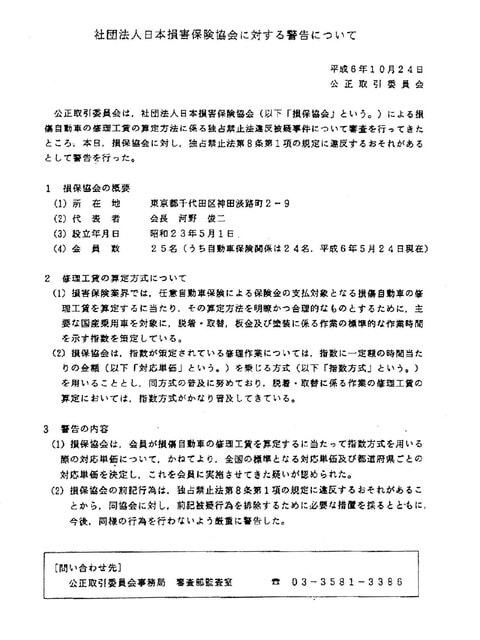
と云うのは、指数とはそもそもその出始めから単位のない無名数という云い方を自研センターではして来たのだが、いくらそういう詭弁を云おうが、それにレバーレートと近似した単価を乗じれば料金となることから、時間値相当であることは誰の目にも明かなことだ。
これについては、自研センターの説明は2転3転しているのはおもしろいところで、当初はこれは純時間ではないという説明(そもそも無名数であるとしながら時間ではないという説明すること事態が矛盾しているのに気が付かない愚かさ)なのだが、それは指数値には車格という純時間に関わらない、これは指数以前の料金工賃表(時間が記されず、料金だけが記載されたもの)との乖離を少なくし、指数を受け入れ易くするために取り入れられた技巧だ。
その後、指数の新型車が拡大しつつ普及するに合わせて、車格要素を払拭したのだろう、指数は科学的な純時間であると云い方を変えた。この時代は、科学的な純時間であり、指数は作業量を把握するモノサシに相当するとも公言していた。
そして、公取警告の後、また変化し、指数は科学的な純時間とかモノサシという言葉や記述はなくなり、自研センターでの数値であり、使う使わないを自研センターとして強要するものではないという表現に変わった。さらに自研センターの無責任さが表れているのは、その後に続く言葉として、扱う損保さんと打ち合わせてくださいと追言するのだ。
そんなことで、自研センターの言に沿い、指数を実運用するする損保に指数の疑問だとかを質問しても、答えは(信頼できる)自研センター策定していますからだけで、指数が何故そうなるのかを説明受けることはできないのだ。それは当然で、自研センターは損保にすら指数の策定根拠を開示していないからなのだ。
また、個別工場が指数を使用しないその他の資料を使うと宣言すると、扱う損保は場合によれば、それは困ったことになるといいつつ、何時まで経ても協定の返事はなくなるのだ。つまり塩漬けにされ、工場からどうすれば良いと譲歩案を出さない限り支払いが受けられなくなる場合も多いのだ。これは事実上の指数使用の強要だと理解しているところなのだ。
ここでは、自研センターが企業秘密とか抗弁し、基表を非公表としているが、かつて損保調査人として、知り得た基表値の一端からある程度核心を持てる内容として基表から指数の作り方をレクチャーして見たい。これは、そもそも基表という聞き慣れない言葉の意味を理解していない修理工場や損保調査員に、改めて基表とはなんぞやと云うことを知ってもらうために起草した内容だ。
それには、序章として自研センターの成り立ちとか歴史から、掘り起こして眺めることが大事と意識しつつ以下に記していく。なお、いささか長文となったこともあり、その1およびその2と分割して、今回はその1として序論を記す。
その1 序論
1.自研センターの歴史
そもそも、私こと、損保在職中に自研センターに2年間派遣勤務していたのだが、その期間は1990年4月から1991年3末末までだが、当時の自研センター社長は東京海上出身の横井社長で、初代が島田社長(同じく東海出身)だから2代目の社長だった。
私の自研センターでの所属は研修部であり、当時の研修部長は最初の半年あまりは飯○氏で確か同和火災出身だったと記憶している。その後は、平○という安田火災(現損保ジャパン)の人物だった。これら、自研センターの上層部というのは、いわゆる損保の損調関係者でなく、どちらかと云うと営業もしくはゼネラリストたる本社所属の人物だった。
私は損保調査員時代に、本社勤務が通産9年在籍することになったのだが、付き合いとしては損害調査部たる損調関係者が多数ではあったが、そもそも子会社に移籍してくる上層部人物とか、本社でも様々な人物と触れ合って来たが、端的に云えば生粋の損調部門の生え抜きより、営業とか本社人事部とか総合企画室出身者を比べると、驚くほど人物のスケール格差があり、子会社の損害調査員(アジャスターのこと)は視野が狭く端的に云えばレベルが低いのが通例一般(例外も些少あり)だが、総合職(軍隊で云う将校、官僚で云うキャリア)でも、損調所属はレベルが低い者が多かった(もちろん例外あり)というのが感想だ。
そこ行くと、営業部門でもゴミはいるのだが、本社所属ともなると、人物スケールが異なる人物が多く感じられたものだった。そもそも、損保社長にまで上り詰める損調出身人物は希なるもので、合併以前の大東京火災に僅かに存在したという記憶だ。その大東京も、あいおい社として合併以来、査定優先思考は影を潜め見る影もなくなった。
しかし、当時の自研センターでも、横井社長とか、研修部長クラスになると、ある意味本流から外された左遷とも云える立場で来ているのだが、安田の平〇はときおりそういう憤まんを見せてはいたが、少なくとも横井社長には、そういう思いを感じさせない人物であったという思いだ。
ところで、自研センターという組織だが、役員構成員は当時は現在損保14社(設立時は大合併以前なのでもっと多かった)の共同出資により作られた組織であるが、自研センターに常勤していない社でも、当該社の社長は理事として参加している。
また、その出資率は損保の規模に応じているのだろうが、社長は現在に至るも東京海上日動社(合併以前は東海社)出身者が就任している。なお、最近聞き及ぶところでは、初代とか2代目、3代目くらいまでは、就任した社長は10年程存在したのだが、近年は3年程度で交代している様だ。このことは何を示すかと云えば、要するに自研センターという組織の価値が、相対的に低下してきており、これは想像だが最近の社長となっている東京海上日動出身社長はおそらく日動ルーツの、いわば最後のお勤めを果たしているのが実態だろうと想像できる。
なお、自研センターが設立されたのは1975年(昭和50年)ちょっと前であり、これとほぼ時を同じくして、アジャスター制度という資格制度が生まれているという歴史がある。そして、そもそもアジャスター制度以前には、調査人という資格も何もない、ただ自動車整備とか板金の知識のある者を損保各社は採用して、オール歩合に近い請負たる身分で調査活動(事故車の立会協定のみ)に利用して来ていたのだった。そんな中、当時の損保ガリバーたる社たる東海社では、自社研修施設として現在の自研センターの土地を取得して、建屋の建設工事も始めていたのであった。そんな中1970年代前に、損保各社で欧米の損保事情の視察団というのが構成され、何度か視察を繰り返すということが行われ、特に欧州の損保が経営するリペアリサーチ(作業研究)とか調査員の研修施設が目に止まり、日本でも同様のものを作ろうといういう気運が起きたのだった。そこで、既に建設が始まっていた東海社の研修施設を、そのまま自研センターとして流用しつつ、アジャスター制度を作ろうと云う動きに急速になったのだと伝え聞いている。
ここで、自研センターの事業の核心は以下の2つであるとされた。
➀アジャスター資格制度に関わる研修
②リペアリサーチ活動として作業研究だが、最終目標として料金に結び付く標準作業時間の策定、そしてそれが転じて指数の策定へと移行した。
自研センターの設立に関わる資本金は損保各社の規模に応じた出資金によるが、運営稼働費としては、先の研修費(1人日額25千円程)と指数策定の販売費という構成だ。なお、ここで触れておかなければならないことだが、そもそも指数とかアジャスター制度以前のその昔存在した鑑定人制度(全国で100名程度存在)の管理とかは、現在保険の自由化の中で名称が変更になったが保険料率料率会(現保険料率算定機構)であったことだ。この算定会(現算定機構)というのは、特別立法により組織された機関であり、会社組織ではない団体だ。つまり営利を目的とする法人ではない。それが、現在では、指数はコグニビジョン(旧日本アウダテックス)という営利を目的とする法人に移行していることや、アジャスターの管理は一般社団法人日本損害保険協会に移行している。
さて、私の自研センターでの活動だが、研修部に所属し、主には各アジャスター研修に関わる準備とか、研修の補助的な業務が主で、その他は自由に研究なりしてもよろしいというある意味気軽な立場であった。であるから、自己の研鑽のために、感心を持つ講師の聴講をしたり、自社の問い合わせに答えるための報告書を作成したりという日々が続いていたのだった。そういう中で、当時でも指数策定部には、部外者立ち入り禁止という感じで閉鎖的な様子があったのだが、たまたま席を隣にした関○氏という、いわば定年を過ぎ恩給の形で週3日程度出社する方の隣の席にいることになったのだが、この方は元来保険料率算定会所属で自研センター黎明期という時代に、作業時間の基礎策定に関わった方だったのだ。その方とは種々話しを繰り返したのだが、前職は東京日産サービス部長で、それ以前の戦前戦中の頃は日立に属して水力発電の水車(タービン)設計をしていたという生粋の技術者畑の方だった。今年半年ほど前の人づての話しでは未だご存命だと聞くが、おそらく80代も中頃となるのではないだろうか。
まず、私の現在の指数とか工数を知る序章という面で、この方に聞いた知識はかなり大きなものがあると回想している。ただし、今現在の私の回想としては、この方も学者に良くある視野の狭さというのが内在していて、ある意味権威趣意に毒されており、オープンな思考の広がりには欠けていたという思いを持つところもあるのだが、現在の指数の底流に流れる考え方を知るには極めて参考となる意見を聞けたことは大変参考となった。
なお、自研センターの車両メーカー出身者について補足しておきたいが、そもそも立ち上げ時に、有力ディーラーもしくはメーカーからの転籍もしくは縁故頼りの転入者というのが、私が派遣時にも存在したし、それ以前にも存していた様だ。この中には、リサーチ所属で、当初の標準作業時間から指数に移行するあたりまで筆頭だった長〇〇氏などはTトヨタサービス部長とか、在籍当時は同じくリサーチ部長だった〇野などはTペット出身だった。あと研修部でも、総務的な業務を行なっていた良き年配者には名前を失念したがホンダの技術畑でない人物だったが、時々宗一郎氏の逸話などを聞いたものだった。あと、日産のおそらくサービス部から来ていたと思うが沢〇氏などは、比較的温厚な方だったと回想する。これも半年くらい前に、自研センターの数年前まで部長待遇だった方(これも出身はTトヨタ)に聞いたのだが、最近ではトヨタメーカー出身者が存するそうだが、パワハラまではいかないが、とにかく強気の発言を繰り返し、廻りが白けているということを聞き及ぶ。こういう話は、他でも聞かれ、トヨタ東富士研究所の近くには、ある損保の研修所があるのだが、そこの課長職はトヨタの定席になっているのだが、とにかく威張り倒しているという。そもそもこの棒損保研修所は、損保でそこまで必要性があるのかと思うバリア実験装置まで保有するのだが、噂だがトヨタの下請け的な実験を繰り返しているという。
2.自研センターから本社研修部に戻ってから
自研センターでの2年を過ごし、1992年4月に、研修部に戻った。それからも、97年に研修部を離脱するまでの間、自研センターとは縁あり研修講師を担当するなど自研センターを訪れる機会も続いていた。また、自研センターで巡り合った同じ立場での出向者とか、これはと思う極一部の講師とは、30年余を過ぎる今でも少数だが付き合いは続いている。
ところで、1993年頃から今思えば1996年10月まで、自研センターでは今まで公開していなかった基表の全面公開ではないが、一部の基表値も事例として公開しつつ、基表による指数値の策定方法を徐々に公開し始めていたという歴史があるのだ。このことは、各社当時の本社勤務の調査員にしか知られていないことと思うが、これは当時実体験している者として記録しておきたい。
何故、こういう動きになり、それが96年10月を境に、パッタリ止まったかを、今だから客観的に意識できることとして記しておきたい。
それは1996年10月に公正取引委員会より「社団法人日本損害保険協会に対する警告について」という、いわゆる公取からの警告文書が出されたことに大きな要因はあるのだろう。この警告は、指数に乗ずる対応単価について、県単位で談合に等しい行為を行っていることで、独占禁止法に抵触する恐れがあるとの警告だったのだ。つまり、料金を決める単価についての警告なのだが、料金を決めるもう一つの要素である指数値については触れていないものの、自研センターでは、従来の姿勢が大きく変化をしたということがある。
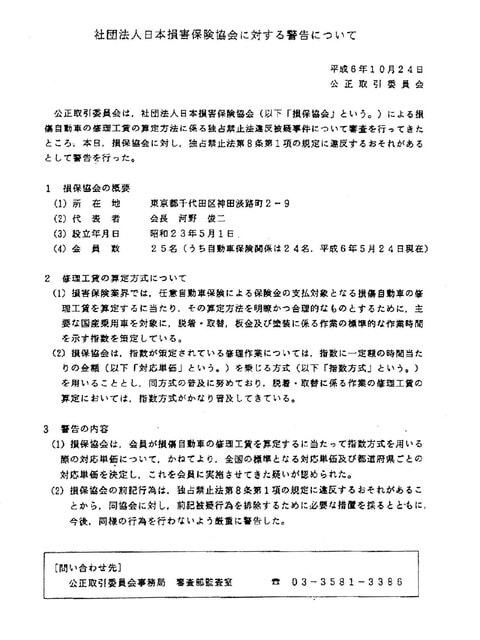
と云うのは、指数とはそもそもその出始めから単位のない無名数という云い方を自研センターではして来たのだが、いくらそういう詭弁を云おうが、それにレバーレートと近似した単価を乗じれば料金となることから、時間値相当であることは誰の目にも明かなことだ。
これについては、自研センターの説明は2転3転しているのはおもしろいところで、当初はこれは純時間ではないという説明(そもそも無名数であるとしながら時間ではないという説明すること事態が矛盾しているのに気が付かない愚かさ)なのだが、それは指数値には車格という純時間に関わらない、これは指数以前の料金工賃表(時間が記されず、料金だけが記載されたもの)との乖離を少なくし、指数を受け入れ易くするために取り入れられた技巧だ。
その後、指数の新型車が拡大しつつ普及するに合わせて、車格要素を払拭したのだろう、指数は科学的な純時間であると云い方を変えた。この時代は、科学的な純時間であり、指数は作業量を把握するモノサシに相当するとも公言していた。
そして、公取警告の後、また変化し、指数は科学的な純時間とかモノサシという言葉や記述はなくなり、自研センターでの数値であり、使う使わないを自研センターとして強要するものではないという表現に変わった。さらに自研センターの無責任さが表れているのは、その後に続く言葉として、扱う損保さんと打ち合わせてくださいと追言するのだ。
そんなことで、自研センターの言に沿い、指数を実運用するする損保に指数の疑問だとかを質問しても、答えは(信頼できる)自研センター策定していますからだけで、指数が何故そうなるのかを説明受けることはできないのだ。それは当然で、自研センターは損保にすら指数の策定根拠を開示していないからなのだ。
また、個別工場が指数を使用しないその他の資料を使うと宣言すると、扱う損保は場合によれば、それは困ったことになるといいつつ、何時まで経ても協定の返事はなくなるのだ。つまり塩漬けにされ、工場からどうすれば良いと譲歩案を出さない限り支払いが受けられなくなる場合も多いのだ。これは事実上の指数使用の強要だと理解しているところなのだ。



















