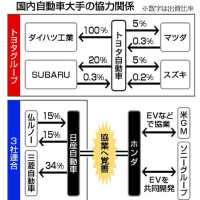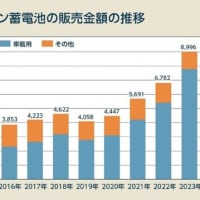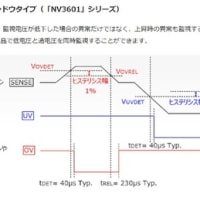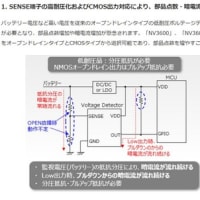【書評】資本主義の終焉と歴史の危機 水野和夫著
現在、私も含め多少なりとも知性を意識する多くの者は、長年の資本主義か共産主義かという人類生き残りの経済論が、一応最適善が自動的に達成される資本主義が肯定されたとはいうものの、富める者と貧しい者の格差が分断を生み、今まで大半の多くが意識していた中流層が欠落した社会としての資本主義の限界を意識しているのだろう。
そんな中、今も政治問題とか社会問題として、資本主義とは云えども、公的支援とか税制の格差是正とか、幾ら資本主義と云っても、いわゆる社会主義の思想を取り入れ、憲法25条に規定される「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を幾らかでも達成しようとしているのだが・・・。
しかし、自分自身の社会人としてのこの40年余りの、生活を振り返ってみても、1980年代と現在の2020年代の40年のあまりの生活環境の差に驚く他ないということがある。つまり、エネルギーとか食品などの生活していくコストは、確実に上昇して来たが、それに対する給与は1990年までは、相応に伸びて、生活の安定度は維持されつつ、誰もが必ずしも100%の満足とまではいかなくても、一応中流を意識できる状態であったのが、2000年以降、確実に給与だけが減りしつつ、相当程度に我慢せざるを得ない、もはや自分が中流だとは意識できない環境に至っていることを意識せざるを得ないことに気づかぬ者が多くを占めるのが40年後の現世だということなのだ。
こういう経済的な困窮の中で、社会も規範とかモラルというものも崩れ始めていることを感じる。このことは、法律論にしてもそうだし、さまざまな事件の判決として下される内容にも感じ続けているのだが、今までだったら法の精神から阻却して裁かれていたのが、法は単なる文章としての規定であって、その法の精神を顧みることなく、上っ面の文面だけで理由付けなされて、ことの決着が下されている様にも思えてしまう。もう少し身近な事例で上げて見ると、さまざまな業種で、マニュアルだとか一応の規定は整備なされているのだが、その文体がとか内容があまりにも表層的もしくは深度の低いものであり、実際例としてマニュアルとやらを見ても、実務にほとんど役立たず、何のためにマニュアルが使用されているかと云えば、何か不祥事が生じた際に、マニュアルの規定に沿っていないとか詰問するためにマニュアルはあるのかと理解できると云う問題を感じてしまう。こんなことを感じるのも、1990年代毎、当時の専門職としてマニュアル化の作成というべき問題に取り組んだことが回想されるのだが、マニュアルとは品質だとか精度を高め時間当りのコストを低減させるという目的が主だったと思えるのだが、自己の専門外も含め現在のマニュアルを概観して思うのだが、そういう根源的な思想が希薄で、品質とか精度を高めると云うより、ある型に納め、持って担当者もしくは作業者の総意工夫を制限しつつ、金太郎飴の如く同じ型に矯正していくと云うべき、思考を持っている様に感じるのは私の思い込みだろうか。

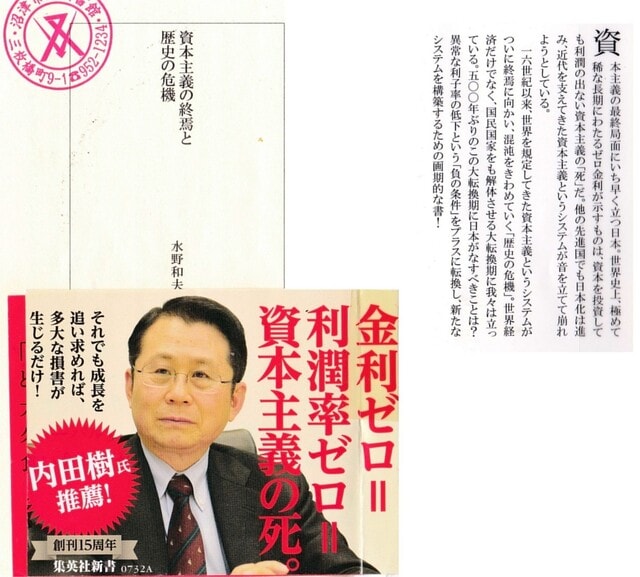
さて、前置きが長くなってしまったのだが、この本はこのところ、その資本主義の行く末が気になりつつ、そのことの危機を極めて判り易く解説する識者として意識しだした水野和夫氏の何冊目かの著作を流し読みした2014年の本だ。本といえば、現在はNet社会になったこともあり、本でなくてもYoutubeだとか中にはマンガとかコミックで、より簡易にと云うか取っつき易く情報に接する機会が多く、本も最新刊で話題(これもマスメディアが作り出す虚像の一つだろう)の本だけが売れると云う傾向がある様だが、本というのは余程科学とかテクノロジーに類するものを除けば、その著作年に関係ない真実を知るメディアの一つだろうと思う。特に、複雑な内容も含め、先の法律論とかマニュアル論と共通するのだが、何の目的を持って、それが記されているのかという根源が大切だと思うし、その根源を意識することがものごとと対峙する時、極めて重要なのではないかと感じる。
この本の表紙裏の序章というべき内容に、日本は資本主義の最終局面に立つのだと著者は記している。それは、既に20年近くも続くゼロ金利政策に現れており、これは資本を投じても利潤のない資本主義の死を表しているのと同意だとしている。そして、この日本が最前線を走る姿は、大同小異あれ世界共通の流れだと断じている。
この本で知る金利(利子率)の歴史を歴史の中で著者は概観しているのが序章だが、非常に興味深い。そもそも資本主義とは、経済成長を前提にしたシステムだが、その成長率と金利とは、相関を持つものだと説く。すなわち。資本主義の利潤率と金利は、ほぼ等価なものだと云う訳である。その金利が、今正にゼロに近づいているのだが、歴史を遡って見ると16世紀から17世紀初めのイタリアジェノバが、やはり金利がゼロに近づいた時代があったというのだ。何故、当時のジェノバで、この様な低金利状態になったかと云えば、その頃の派遣国であるスペインが南米で多くの銀を掘り出し、その多大の銀が取引先のジェノバに集まり、マネーのだぶぶつきを生じたことがある。ところが、そのイタリアでは、ワインの産地であブドウ畑になっており、もう既に投資先がないという状態に陥ったからだと説明しているのだ。
つまり、金利は資本家に投資意欲を湧かせるパラメーターとなるが、新しいフロンティア(投資先)がない状態では、金利は極限まで低下するが、それは資本主義の死を意味しているのだと説く。
著者は、グローバリエーションとは中心と周辺を結び付ける思想だと定義します。そして、もっと云えばとして、グローバリエーションとは、中心と周辺の組み替え作業だと説きます。そもそも北の先進国が中心で南の周辺国から利潤を得ていたのだが、南(BRICS)がそれなりの成長軌道の新興国に転じれば、それが中心として新たね周辺を作る要があります。それが、米で云えばサブプライム層であり、日本で云えば非正規社員であり、EUであればギリシャやキプロスだという訳なのだ。
こうした国境の内側で格差を広げる行為は、民主主義の破壊も生じることになる。つまり民主主義とは価値観を同じにする中間層の存在があって機能するのだが、多くの者の所得が減少する中間層の没落は、民主主義の破壊をすることに他ならない。
それと、著者は1970年以降、製造業の没落に反して電子金融空間業に資本主義の軸足が移行したことを指摘する。そして、電子金融業を駆使する資本家は、バブルの生成と崩壊を繰り返すことになる。バブルの崩壊は、公的資金の投入がなされ、そのツケは広く国民に及ぶ。つまり、バブル崩壊は需要を急減収縮させ、企業は解雇やリストラを断行せざるを得なくなる。今や日本や米国に限らず、あらゆる国で格差が拡大しているのは、グローバル資本主義が必然的にもたらす状況なのだと。
現在、私も含め多少なりとも知性を意識する多くの者は、長年の資本主義か共産主義かという人類生き残りの経済論が、一応最適善が自動的に達成される資本主義が肯定されたとはいうものの、富める者と貧しい者の格差が分断を生み、今まで大半の多くが意識していた中流層が欠落した社会としての資本主義の限界を意識しているのだろう。
そんな中、今も政治問題とか社会問題として、資本主義とは云えども、公的支援とか税制の格差是正とか、幾ら資本主義と云っても、いわゆる社会主義の思想を取り入れ、憲法25条に規定される「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を幾らかでも達成しようとしているのだが・・・。
しかし、自分自身の社会人としてのこの40年余りの、生活を振り返ってみても、1980年代と現在の2020年代の40年のあまりの生活環境の差に驚く他ないということがある。つまり、エネルギーとか食品などの生活していくコストは、確実に上昇して来たが、それに対する給与は1990年までは、相応に伸びて、生活の安定度は維持されつつ、誰もが必ずしも100%の満足とまではいかなくても、一応中流を意識できる状態であったのが、2000年以降、確実に給与だけが減りしつつ、相当程度に我慢せざるを得ない、もはや自分が中流だとは意識できない環境に至っていることを意識せざるを得ないことに気づかぬ者が多くを占めるのが40年後の現世だということなのだ。
こういう経済的な困窮の中で、社会も規範とかモラルというものも崩れ始めていることを感じる。このことは、法律論にしてもそうだし、さまざまな事件の判決として下される内容にも感じ続けているのだが、今までだったら法の精神から阻却して裁かれていたのが、法は単なる文章としての規定であって、その法の精神を顧みることなく、上っ面の文面だけで理由付けなされて、ことの決着が下されている様にも思えてしまう。もう少し身近な事例で上げて見ると、さまざまな業種で、マニュアルだとか一応の規定は整備なされているのだが、その文体がとか内容があまりにも表層的もしくは深度の低いものであり、実際例としてマニュアルとやらを見ても、実務にほとんど役立たず、何のためにマニュアルが使用されているかと云えば、何か不祥事が生じた際に、マニュアルの規定に沿っていないとか詰問するためにマニュアルはあるのかと理解できると云う問題を感じてしまう。こんなことを感じるのも、1990年代毎、当時の専門職としてマニュアル化の作成というべき問題に取り組んだことが回想されるのだが、マニュアルとは品質だとか精度を高め時間当りのコストを低減させるという目的が主だったと思えるのだが、自己の専門外も含め現在のマニュアルを概観して思うのだが、そういう根源的な思想が希薄で、品質とか精度を高めると云うより、ある型に納め、持って担当者もしくは作業者の総意工夫を制限しつつ、金太郎飴の如く同じ型に矯正していくと云うべき、思考を持っている様に感じるのは私の思い込みだろうか。

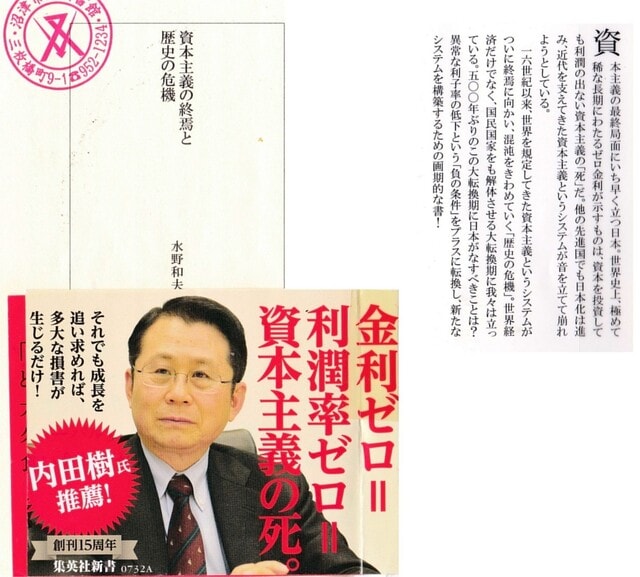
さて、前置きが長くなってしまったのだが、この本はこのところ、その資本主義の行く末が気になりつつ、そのことの危機を極めて判り易く解説する識者として意識しだした水野和夫氏の何冊目かの著作を流し読みした2014年の本だ。本といえば、現在はNet社会になったこともあり、本でなくてもYoutubeだとか中にはマンガとかコミックで、より簡易にと云うか取っつき易く情報に接する機会が多く、本も最新刊で話題(これもマスメディアが作り出す虚像の一つだろう)の本だけが売れると云う傾向がある様だが、本というのは余程科学とかテクノロジーに類するものを除けば、その著作年に関係ない真実を知るメディアの一つだろうと思う。特に、複雑な内容も含め、先の法律論とかマニュアル論と共通するのだが、何の目的を持って、それが記されているのかという根源が大切だと思うし、その根源を意識することがものごとと対峙する時、極めて重要なのではないかと感じる。
この本の表紙裏の序章というべき内容に、日本は資本主義の最終局面に立つのだと著者は記している。それは、既に20年近くも続くゼロ金利政策に現れており、これは資本を投じても利潤のない資本主義の死を表しているのと同意だとしている。そして、この日本が最前線を走る姿は、大同小異あれ世界共通の流れだと断じている。
この本で知る金利(利子率)の歴史を歴史の中で著者は概観しているのが序章だが、非常に興味深い。そもそも資本主義とは、経済成長を前提にしたシステムだが、その成長率と金利とは、相関を持つものだと説く。すなわち。資本主義の利潤率と金利は、ほぼ等価なものだと云う訳である。その金利が、今正にゼロに近づいているのだが、歴史を遡って見ると16世紀から17世紀初めのイタリアジェノバが、やはり金利がゼロに近づいた時代があったというのだ。何故、当時のジェノバで、この様な低金利状態になったかと云えば、その頃の派遣国であるスペインが南米で多くの銀を掘り出し、その多大の銀が取引先のジェノバに集まり、マネーのだぶぶつきを生じたことがある。ところが、そのイタリアでは、ワインの産地であブドウ畑になっており、もう既に投資先がないという状態に陥ったからだと説明しているのだ。
つまり、金利は資本家に投資意欲を湧かせるパラメーターとなるが、新しいフロンティア(投資先)がない状態では、金利は極限まで低下するが、それは資本主義の死を意味しているのだと説く。
著者は、グローバリエーションとは中心と周辺を結び付ける思想だと定義します。そして、もっと云えばとして、グローバリエーションとは、中心と周辺の組み替え作業だと説きます。そもそも北の先進国が中心で南の周辺国から利潤を得ていたのだが、南(BRICS)がそれなりの成長軌道の新興国に転じれば、それが中心として新たね周辺を作る要があります。それが、米で云えばサブプライム層であり、日本で云えば非正規社員であり、EUであればギリシャやキプロスだという訳なのだ。
こうした国境の内側で格差を広げる行為は、民主主義の破壊も生じることになる。つまり民主主義とは価値観を同じにする中間層の存在があって機能するのだが、多くの者の所得が減少する中間層の没落は、民主主義の破壊をすることに他ならない。
それと、著者は1970年以降、製造業の没落に反して電子金融空間業に資本主義の軸足が移行したことを指摘する。そして、電子金融業を駆使する資本家は、バブルの生成と崩壊を繰り返すことになる。バブルの崩壊は、公的資金の投入がなされ、そのツケは広く国民に及ぶ。つまり、バブル崩壊は需要を急減収縮させ、企業は解雇やリストラを断行せざるを得なくなる。今や日本や米国に限らず、あらゆる国で格差が拡大しているのは、グローバル資本主義が必然的にもたらす状況なのだと。