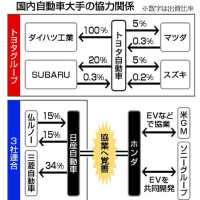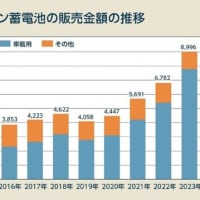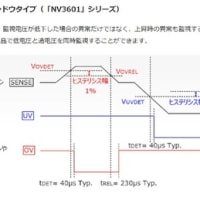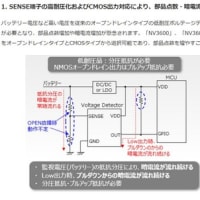相当以前に記した内容だが、クルマに詳しい方は、私以上に既知のことばかりです。興味がある方のみ見て下さい。
最近はオートマチック・トランスミッション(もしくはAMTと云うべき機械式MT+ECU制御)の2ペダルが乗用車が9割を越え、3ペダルのクラッチ付きのマニュアル・トランスミッション車を見ることも、乗る機会も少なくなってしまった。偶にクラッチ付き車に乗ると、新鮮でマニュアルも良いもんだと思うし、自ら選んだギヤで旋回する醍醐味はマニュアルならでは、スポーツカー乗るならマニュアルを選択すべしと思っている。ここで、クラッチのうんちくを、少し記して見たい。
クラッチを日本語に直せば継続機であり動力を切ったり繋いだりできる機構となる。その上で、接続時にダイレクトに繋ぐのでなくスムーズな接続、つまり滑りを伴う半クラッチ状態ができることが市販車には特に求められるのだろう。現在の2ペダルATも、内部に複数のプラネタリギヤセットと、それを切り替えるための複数以上の多板クラッチが使用されている。これらクラッチも継続時は、シフトショックを軽減するため、アキュムレーターなどにより作動油圧の立ち上がり特性を加減したりしているのだ。
昔のクラッチ付きマニュアルトランスミッションでは、運転の仕方でクラッチ板の持ちが随分と違ったものだった。下手な運転者となると、僅か1万キロに満たないでクラッチ板が擦り減り滑り出しすが、上手い運転者は5万キロ以上クラッチが持つこともしばしばだったと思い出す。これは半クラッチ状態の時間長に関係する訳だが、半クラッチ時間が長い運転者がスムーズな運転をし、短い運転者が荒っぽい運転者かというと、そういう訳でもなかったのだ。様は、クラッチ接続時のエンジン回転を低めにし、極短時間の半クラッチ状態で継続完了させているかというテクニックが要求されたのだろう。
なお、市販実用車では、発進時のエンジン低回転での発進を容易にする目的で、フライホイールの慣性力(イナーシャ)を増している。これを、レーシングカーばりに軽量化すると、クラッチ接続時のエンジン回転落ちが激しくエンストし易いため、勢いエンジン回転を上げ気味にして継続するしかなくなる訳であり、クラッチの寿命にも影響してくる。
話は昔のレーシングカーへと移るが、1970年頃のF1グランプリで、いわゆるワークスでないプライベーターは、エンジンはコスワースDFV、ミッションはヒューランド、クラッチはボーク&ベック(現ボルグワーナーに吸収)などと、個別専業パーツメーカーがおのずと決まっていたものだ。そんな、レーシングエンジンでは、フライホイールを含めクランクシャフトなど回転系の回転マスが大きいと、全力加速において加速エネルギーが吸収されてしまうから、なるべく回転系のマス(イナーシャ)を小さく設計している。従って、フライホイールも小径で薄板となり、それに付随して大出力を継続するクラッチも、小径で成立させるために、クラッチ板を複数枚の多板となっているものも多い訳だ。
現在のF1は詳しくないが、クラッチペダルはあるが、これは発進時のみ使用するらしい。走行中はシフトアップもダウンも、クラッチを踏むことなく、パドルシフト操作だけで行っているそうだ。しかし、映画「グラン・プリ」は好きな作品で何度も見るが、1960年代のF1、例えばモナコグランプリでは、「レース中に2,600回を越えるシフト操作が行われる」とナレーションされるが、ドライバーはシフトと操作の都度、クラッチを切り(踏み)シフト操作を繰り返す。特に、シフトダウン時が問題となる。F1のミッションでは常時噛み合いギヤ(市販車も同様)で、シンクロ機構を持たないドグ・クラッチという噛み合い機構で、選択ギヤをメインシャウトにロッキングさせるシンプルなものだから、回転の同期が取れていないシフト操作では、ドグが噛み合いきれずに異音を生じたり、酷くするとミッションの破損に至る訳だ。そのため、1度クラッチを切りニュートラルにして再度クラッチを接続し、アクセルを煽ってミッション内のギヤ(カウンターシャフト)を加速させメインシャフトの選択ギヤとの同期を取って、再度クラッチを切り下位ギヤにシフトするという、いわゆるダブルクラッチ操作が要求されたのだ。しかも、コーナー進入時のブレーキング時にこれを行うため、右足は、つま先でブレーキングし、かかとでアクセルを煽るという、いわゆるヒール&トウというテクニックが繰り返されるのだ。この辺りの状況は、映画「グラン・プリ」で、明瞭に表現されている。

最近はオートマチック・トランスミッション(もしくはAMTと云うべき機械式MT+ECU制御)の2ペダルが乗用車が9割を越え、3ペダルのクラッチ付きのマニュアル・トランスミッション車を見ることも、乗る機会も少なくなってしまった。偶にクラッチ付き車に乗ると、新鮮でマニュアルも良いもんだと思うし、自ら選んだギヤで旋回する醍醐味はマニュアルならでは、スポーツカー乗るならマニュアルを選択すべしと思っている。ここで、クラッチのうんちくを、少し記して見たい。
クラッチを日本語に直せば継続機であり動力を切ったり繋いだりできる機構となる。その上で、接続時にダイレクトに繋ぐのでなくスムーズな接続、つまり滑りを伴う半クラッチ状態ができることが市販車には特に求められるのだろう。現在の2ペダルATも、内部に複数のプラネタリギヤセットと、それを切り替えるための複数以上の多板クラッチが使用されている。これらクラッチも継続時は、シフトショックを軽減するため、アキュムレーターなどにより作動油圧の立ち上がり特性を加減したりしているのだ。
昔のクラッチ付きマニュアルトランスミッションでは、運転の仕方でクラッチ板の持ちが随分と違ったものだった。下手な運転者となると、僅か1万キロに満たないでクラッチ板が擦り減り滑り出しすが、上手い運転者は5万キロ以上クラッチが持つこともしばしばだったと思い出す。これは半クラッチ状態の時間長に関係する訳だが、半クラッチ時間が長い運転者がスムーズな運転をし、短い運転者が荒っぽい運転者かというと、そういう訳でもなかったのだ。様は、クラッチ接続時のエンジン回転を低めにし、極短時間の半クラッチ状態で継続完了させているかというテクニックが要求されたのだろう。
なお、市販実用車では、発進時のエンジン低回転での発進を容易にする目的で、フライホイールの慣性力(イナーシャ)を増している。これを、レーシングカーばりに軽量化すると、クラッチ接続時のエンジン回転落ちが激しくエンストし易いため、勢いエンジン回転を上げ気味にして継続するしかなくなる訳であり、クラッチの寿命にも影響してくる。
話は昔のレーシングカーへと移るが、1970年頃のF1グランプリで、いわゆるワークスでないプライベーターは、エンジンはコスワースDFV、ミッションはヒューランド、クラッチはボーク&ベック(現ボルグワーナーに吸収)などと、個別専業パーツメーカーがおのずと決まっていたものだ。そんな、レーシングエンジンでは、フライホイールを含めクランクシャフトなど回転系の回転マスが大きいと、全力加速において加速エネルギーが吸収されてしまうから、なるべく回転系のマス(イナーシャ)を小さく設計している。従って、フライホイールも小径で薄板となり、それに付随して大出力を継続するクラッチも、小径で成立させるために、クラッチ板を複数枚の多板となっているものも多い訳だ。
現在のF1は詳しくないが、クラッチペダルはあるが、これは発進時のみ使用するらしい。走行中はシフトアップもダウンも、クラッチを踏むことなく、パドルシフト操作だけで行っているそうだ。しかし、映画「グラン・プリ」は好きな作品で何度も見るが、1960年代のF1、例えばモナコグランプリでは、「レース中に2,600回を越えるシフト操作が行われる」とナレーションされるが、ドライバーはシフトと操作の都度、クラッチを切り(踏み)シフト操作を繰り返す。特に、シフトダウン時が問題となる。F1のミッションでは常時噛み合いギヤ(市販車も同様)で、シンクロ機構を持たないドグ・クラッチという噛み合い機構で、選択ギヤをメインシャウトにロッキングさせるシンプルなものだから、回転の同期が取れていないシフト操作では、ドグが噛み合いきれずに異音を生じたり、酷くするとミッションの破損に至る訳だ。そのため、1度クラッチを切りニュートラルにして再度クラッチを接続し、アクセルを煽ってミッション内のギヤ(カウンターシャフト)を加速させメインシャフトの選択ギヤとの同期を取って、再度クラッチを切り下位ギヤにシフトするという、いわゆるダブルクラッチ操作が要求されたのだ。しかも、コーナー進入時のブレーキング時にこれを行うため、右足は、つま先でブレーキングし、かかとでアクセルを煽るという、いわゆるヒール&トウというテクニックが繰り返されるのだ。この辺りの状況は、映画「グラン・プリ」で、明瞭に表現されている。