平成27年2月3日(曇り)岩手路 第二弾
ということで、後日掲載ですが、農業者として勉強になったんで掲載します。
味噌作り体験の後、2時間程の時間の余裕があったので近くの農家さんを回ってみました。この冬場に岩手の農家さんは何してんのかな?という思いで!
近くを流していたら作業していそうなハウスを見つけたんでいつものパターンで突撃で話を聞いてみました。
キノコ農家(この時はカメラを持っていかなかったので写真は有りませんが取材はバッチリデスよ!)
ハウスの中でキノコを栽培しているそうで、キノコはシイタケとひら茸というキノコだそうです。見せていただいたらひら茸はとても立派で冬場でもこんな立派なキノコができるんだと感心してしまいました。
そこでオーナーさんにいろいろ聞いてみましたが、驚くことに、キノコは菌床が凍らなければ成長するそうで凍らない様にしておけばいいそうです。
ここは60坪位のハウスに薪ストーブ1台で室内温度を維持しているそうです。マキは間伐材を使っているので材料費はかからないが、山から切り出してくるのが労力的に大変でそれがコストかなと言っていました。
あ!対応していただいた人は、80歳位のお爺さんです、隣の建物では50歳位の息子さんが何か仕事していましたが、売店兼作業所に先ず入れということで薪ストーブに火を入れてくれて暫し、話をしていましたね。近所の仲間と話しているような感じで初対面な自分を疑いもせずいろいろと話してくれました。
話を聞くと市場は遠くて出荷できないし、何故かJAが嫌いだそうで、道路に面した自宅を改造して売店を作ってあってそこで売っているそうです。余ったものは乾燥して販売しているそうです。
自分も過去に前を通った時にお客さんが沢山並んでいて盛況だったんで、更に夏場はキューリも箱売りしていて飛ぶように売れていて、いつかは入って見ようかなと思っていたんです。
ここでは菌床は自分で作っているそうなんで、キノコ用のハウスを作るか、今のハウスを一部キノコ用にしたら菌床を買いに行こうと思います。冬場に出荷できるし、岩手より秋田の方がキノコを食べる文化があるんでいけるかな?
次は花農家さんです。
立派なハウスに雪かきした道路があって人が居そうだったんで、突撃取材です。

入って見たら70歳前後のお婆さんが居て仕事を止めて対応してくれましたよ。
今は「ラナンキュラス]の花を作って出荷しているそうです。この花は寒さに強く、加温のコストは極端に少ないそうです。

岩手の人は本当に突撃で見知らぬ人が入って行っても対応してくれるんで凄く良い県民性ですね。まあ、2年前までは自分も岩手県民でしたけどね。
自分は今のところ花はやらないけど話を聞くのは好きなんで暫く話込んでしまいましたね。
ここで聞いた話をまとめておきます。
ここのオーナーは息子さん(42歳)でそれをお父さんとお母さん(対応者)がサポートしているということでした。
息子さんのお嫁さんは勤めていて農業には参画していないです。お父さんは冬場は土建関係のアルバイトに行ってるそうです。お婆さんはハウスの温度管理等サポートしているんだけど、お孫さんの登校の送り迎えなどをしていて結構忙しいということでした。
息子さんは首都圏などの花屋さん等を回って営業しているそうで、今週は九州を回っているということで本日は不在でしたね。直接花屋さんに行くと、お客のニーズが判って栽培の参考になるからと毎年、全国を飛び回っているということでした。契約も取ってきてほとんど契約栽培だと言っていました。オーナーさんから話を聞きたかったですけど残念。
自分が知りたいのは家族の動向では無いし農業について聴きたかったんで、話を農業に戻していろいろ聞いてみました。初対面で家族構成から家族の動向まで普通言うか?あり得ない!
この花は低温栽培の花で温度を上げるとつぼみの茎がヒョロ長になり、茎が曲がってしまって商品価値が落ちるので室温は10度以下に維持しなければならないらしい。このハウスは自動温度管理システムが入っていて室温が13度になるとルーフが自動的に解放されて、温度調整します。素晴らしいシステムが入っています。


今はこの花をビニールハウス3棟で栽培して雪が溶けたら路地でも栽培する。その他に鉢植えリンドウもやってるらしい。
この花は球根から栽培していて、花を切って出荷してもどんどん花芽が出てくるので、良い製品が出来れば結構な収入はあるとのこと。

田んぼを1ha持っているらしいが、花の管理等が忙しくて稲は栽培していないそうです。家族全員分のお米を購入しても年額10万円程度だから、水稲をやる気がしないし、田んぼにはかまっていられないので耕作放棄だそうです。
次はイチゴ農家ハウスです。
100坪クラスのハウスが6棟程あって、中はイチゴ栽培していました。土耕が3棟と高設栽培が3棟とかなりの規模です。入り口の隙間から見たら実を沢山付けていましたね。
作業員が若い人が2名いましたが、時間が無くなりインタビューは止めました。

それにしても10km圏内でこんなにも多く農家さんが冬でも活動していて素晴らしいですね。
かってな個人視察研修成功です。
さあ、これから温泉と宴会だぞ!あっ!その前に総会があるんだった。
頑張っているんで、プチットお願います。
↓↓↓
百姓の場合はこちら

登山の場合はこちら
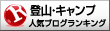
ということで、後日掲載ですが、農業者として勉強になったんで掲載します。
味噌作り体験の後、2時間程の時間の余裕があったので近くの農家さんを回ってみました。この冬場に岩手の農家さんは何してんのかな?という思いで!
近くを流していたら作業していそうなハウスを見つけたんでいつものパターンで突撃で話を聞いてみました。
キノコ農家(この時はカメラを持っていかなかったので写真は有りませんが取材はバッチリデスよ!)
ハウスの中でキノコを栽培しているそうで、キノコはシイタケとひら茸というキノコだそうです。見せていただいたらひら茸はとても立派で冬場でもこんな立派なキノコができるんだと感心してしまいました。
そこでオーナーさんにいろいろ聞いてみましたが、驚くことに、キノコは菌床が凍らなければ成長するそうで凍らない様にしておけばいいそうです。
ここは60坪位のハウスに薪ストーブ1台で室内温度を維持しているそうです。マキは間伐材を使っているので材料費はかからないが、山から切り出してくるのが労力的に大変でそれがコストかなと言っていました。
あ!対応していただいた人は、80歳位のお爺さんです、隣の建物では50歳位の息子さんが何か仕事していましたが、売店兼作業所に先ず入れということで薪ストーブに火を入れてくれて暫し、話をしていましたね。近所の仲間と話しているような感じで初対面な自分を疑いもせずいろいろと話してくれました。
話を聞くと市場は遠くて出荷できないし、何故かJAが嫌いだそうで、道路に面した自宅を改造して売店を作ってあってそこで売っているそうです。余ったものは乾燥して販売しているそうです。
自分も過去に前を通った時にお客さんが沢山並んでいて盛況だったんで、更に夏場はキューリも箱売りしていて飛ぶように売れていて、いつかは入って見ようかなと思っていたんです。
ここでは菌床は自分で作っているそうなんで、キノコ用のハウスを作るか、今のハウスを一部キノコ用にしたら菌床を買いに行こうと思います。冬場に出荷できるし、岩手より秋田の方がキノコを食べる文化があるんでいけるかな?
次は花農家さんです。
立派なハウスに雪かきした道路があって人が居そうだったんで、突撃取材です。

入って見たら70歳前後のお婆さんが居て仕事を止めて対応してくれましたよ。
今は「ラナンキュラス]の花を作って出荷しているそうです。この花は寒さに強く、加温のコストは極端に少ないそうです。

岩手の人は本当に突撃で見知らぬ人が入って行っても対応してくれるんで凄く良い県民性ですね。まあ、2年前までは自分も岩手県民でしたけどね。
自分は今のところ花はやらないけど話を聞くのは好きなんで暫く話込んでしまいましたね。
ここで聞いた話をまとめておきます。
ここのオーナーは息子さん(42歳)でそれをお父さんとお母さん(対応者)がサポートしているということでした。
息子さんのお嫁さんは勤めていて農業には参画していないです。お父さんは冬場は土建関係のアルバイトに行ってるそうです。お婆さんはハウスの温度管理等サポートしているんだけど、お孫さんの登校の送り迎えなどをしていて結構忙しいということでした。
息子さんは首都圏などの花屋さん等を回って営業しているそうで、今週は九州を回っているということで本日は不在でしたね。直接花屋さんに行くと、お客のニーズが判って栽培の参考になるからと毎年、全国を飛び回っているということでした。契約も取ってきてほとんど契約栽培だと言っていました。オーナーさんから話を聞きたかったですけど残念。
自分が知りたいのは家族の動向では無いし農業について聴きたかったんで、話を農業に戻していろいろ聞いてみました。初対面で家族構成から家族の動向まで普通言うか?あり得ない!
この花は低温栽培の花で温度を上げるとつぼみの茎がヒョロ長になり、茎が曲がってしまって商品価値が落ちるので室温は10度以下に維持しなければならないらしい。このハウスは自動温度管理システムが入っていて室温が13度になるとルーフが自動的に解放されて、温度調整します。素晴らしいシステムが入っています。


今はこの花をビニールハウス3棟で栽培して雪が溶けたら路地でも栽培する。その他に鉢植えリンドウもやってるらしい。
この花は球根から栽培していて、花を切って出荷してもどんどん花芽が出てくるので、良い製品が出来れば結構な収入はあるとのこと。

田んぼを1ha持っているらしいが、花の管理等が忙しくて稲は栽培していないそうです。家族全員分のお米を購入しても年額10万円程度だから、水稲をやる気がしないし、田んぼにはかまっていられないので耕作放棄だそうです。
次はイチゴ農家ハウスです。
100坪クラスのハウスが6棟程あって、中はイチゴ栽培していました。土耕が3棟と高設栽培が3棟とかなりの規模です。入り口の隙間から見たら実を沢山付けていましたね。
作業員が若い人が2名いましたが、時間が無くなりインタビューは止めました。

それにしても10km圏内でこんなにも多く農家さんが冬でも活動していて素晴らしいですね。
かってな個人視察研修成功です。
さあ、これから温泉と宴会だぞ!あっ!その前に総会があるんだった。
頑張っているんで、プチットお願います。
↓↓↓
百姓の場合はこちら
登山の場合はこちら



























