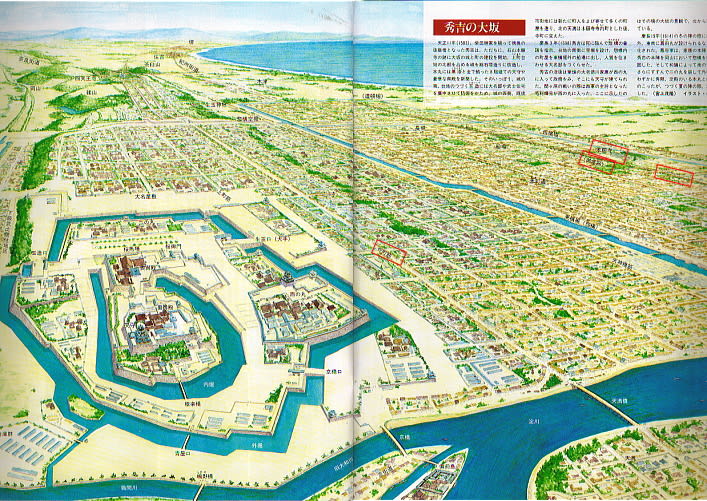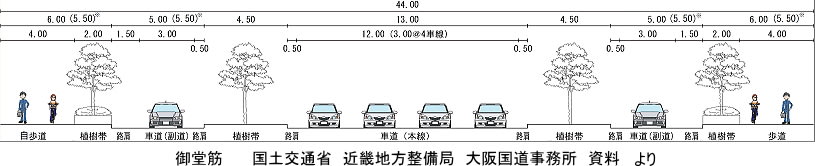朝日小学生新聞に連載の、漫画家・やなせたかしさんの「メルヘン絵本」(※1)で、「ヒョロ松さん」と呼ばれる一本松が、枝をふるわせて歌っている絵が掲載されたのは今からちょうど2年前(2011年)の今日・5月30日のことであった。
(冒頭の画像が、2011年5月30日付朝日小学生新聞に掲載されたやなせたかしさんの連載「メルヘン絵本」の絵。6月14日付朝日新聞朝刊掲載分を借用)。
このヒョロ松さんが歌っていたのが、やなせたかしさん自身の作詞、作曲による「陸前高田の松の木」であった。
(一番)
陸前高田の松林
うす桃色のかにの子は
ハサミふりふり歌うのさ
ここで生まれたいのちなら
陸前高田の松の木は
みんなのいのちの友だちだ
★ぼくらは生きる
負けずに生きる
生きてゆくんだ
オー オー オー
(4番まである★は繰り返し)
アンパンマンの原作者やなせたかしさん(当時92歳)が、2011(平成23)年3月11日(金)に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による津波で、岩手県陸前高田市の名勝・高田松原に1本だけ残った松の木を見て歌を作ったもの。
高田松原には震災前、海岸沿いに約7万本の松の木があった。だが津波に襲われ、残ったのは1本だけ。大切なものを失った被災者のあいだで、いつしか「奇跡の一本松」と言われるようになった。

●(上掲の画象は、「奇跡の一本松」として復興のシンボルになった1本の松。背後に見えるのは被災した陸前高田ユースホステルの建物。2011年5月6日撮影。Wikipediaより)
今にも倒れそうな一本松。やなせさん自身も当時92歳になり、学校の同級生は2人しか残っていない。「あとは全部死んでしまった。漫画家の仲間もほとんどいなくなった。わずかに3歳下の水木しげるがいるだけ。僕自身も病気が多く余命はわずかだと思う」。生き残った松が、自分自身と重なったという。
そういえば、NHK総合テレビ『爆笑問題のニッポンの教養』に出演したやなせたかしさんが、ぬいぐるみで埋め尽くされたアンパンマン部屋を訪ねてきた爆笑問題(太田光・田中裕二)を相手に、「奇跡の一本松」の応援歌ともいうべき「陸前高田の松の木」を大きな声で熱唱していたのを思い出した(放送日:2011年12月1日[木)]22:55~23:25.。2011年9月1日放送分のアンコール放送分)。以下でそのシーンが見られるが、4番の歌詞を歌っている。
「陸前高田の松ノ木」やなせたかしSings~IMG
太田や田中が言っていたように、やなせの作品が常に「生きていく」ということをテーマにしていること、また、やなせも作品を作る理由は、人を喜ばせると自分がうれしいからだと語っていたが、それが、彼の作品が子供達だけでなく誰からも、愛し続けられている秘訣なのだろう。
私の地元、神戸ハーバーランドにも先月神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール(※3参照)がオープンしたがちびっ子たちで大賑わいであった。
高田松原の約7万本の松の中で震災の津波に耐え唯一流されずに残り、震災で何もかもなくした同じ境地の地域の人々の祈りや希望を込め、「奇跡の一本松」と名付けられた松の現状は地盤沈下により根元は塩水に侵され厳しい状況にあった。そして、葉の緑も日増しに薄くなり、赤茶けていく。保存を望む地元の人たちは、「なんとか生き抜いてもらいたい」と木の周りに防潮柵を作ったり、活性剤を与えたりと、いろいろ努力をしたようであるが、哀しいかな立ち枯れてしまったようである。
これに対し、陸前高田市は復興のシンボルにしようと長期保存を決定。昨・2012(平成24)年9月から根元と幹、枝葉に切り分けて、復元が進められていた。
作業では、高さが27メートルもある一本松を根元から切り倒し、幹を5分割にして、その芯をくり抜く。そして、防腐処理をしたうえで、金属製の心棒を幹に通してモニュメントにするといったもので、震災2周年の節目になる今年・2013(平成25)年3月11日には、元の場所でお披露目したいとの考えだったようだ。
しかし、3月6日に復元で、特殊な樹脂を使って再現した枝葉のレプリカを取り付けが行われたが、市民から「立ち姿が以前と違うのではないか」と指摘があり、取り付けミスが発覚、接続部の特殊な金具は再利用できないため、新たに作り直すことになったが、22日に現地で予定していた完成式典には間に合わず完成は6月末になるとの発表があった(3月21日、※4参照)。
この「奇跡の一本松」の保存工事には、1億5000万円もかかるらしく、このような費用をかけて保存工事をすることには、当初より地元住民の間でもいろいろと賛否が分かれ、論議されていたようである(※5参照)。
私の地元神戸も兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)に見舞われ街の大半が崩壊した。そして、神戸のシンボルでもある港が破壊されたが、メリケンパークには神戸港の復旧・復興に努めた様子を後世に伝えようと、メリケンパークの岸壁の一部・約60メートルを被災当時のままの状態で保存した「神戸港震災メモリアルパーク」などが設けられている(ここ参照)。
このような災害についてのメモリアルをどのような形で後世に伝えていくかはに関しては、私達部外者(県外の者)が、とやかくと意見を挟むことではないので、その有益性などについては、地元住民の間十分に話し合って決めるべきことだろう。
岩手県陸前高田市は、今年3月27日の記者会見で、修復作業が進められている「希跡の一本松」を顕微鏡で調べた結果樹齢173年と判明したと発表している。この一本松は1896(明治29)年の明治三陸地震、1933(昭和8)年の昭和三陸地震の2度の大津波に遭いながら、生き抜いた古木。樹齢の判定は難しく、173年より数年古い可能性もあるといい、再鑑定を進めているようだ。地元の市民団体などには260年とする説もあるようだが、これは見間違いによるもののようだ(※6参照)。
いずれにしてもこの「一本松」は陸前高田の地にあって、度重なる震災と津波を経験しそれを乗り越えてきた松であることに間違いはない。
岩手県陸前高田市は、太平洋に面した三陸海岸の南寄りに位置する。旧陸前国・気仙郡に属し、隣接する同県大船渡市や宮城県気仙沼市とともに陸前海岸北部の中核を成す都市である。
かつてこの地に存在していた松原(「高田松原」)が広がっていた地域は、旧高田村(高田町)と旧今泉村(現:気仙町)にまたがっており、もともとは木一本ない砂原で、潮風が巻き上げる砂塵と高潮とにさらされ、背後にある農地は収穫のない年もしばしばという有様であったようだ(※7参照)。
それを、江戸時代の寛文年間に高田の豪商・菅野杢之助が私財を投じて植林し、その後、享保年間には松坂新右衛門による私財を投じての増林が行われ、以来、クロマツとアカマツからなる合計7万本もの松林は、仙台藩・岩手県を代表する防潮林となり、また、その白砂青松の景観は世に広く評価され、
「東北地方稀ニ見ル壯大優美ナル松原ニシテ前ニ廣田灣ヲ控ヘ後ニ氷上山、雷神山等ノ翠巒ヲ繞ラシ山紫水明ノ一勝區ヲ成セリ樹種ハ黒松ヲ主トシ林相整美樹下荊棘ノ繁茂スルモノナク境地清淨ニシテ林内ノ逍遙ニ適ス 」・・と、史蹟名勝天然紀念物保存法による天然記念物に指定されていた(※8参照)。

●(上掲の画象は、震災被害を受ける前の高田松原(2007年6月3日撮影。Wikipediaより)
高田松原の防潮林はたびたび津波に見舞われ、同時に津波被害を防いできた。
近代以降で代表的なものとしては、1896(明治29)年6月15日の明治三陸津波、1933(昭和8)年3月3日の昭和三陸津波、1960(昭和35)年5月24日のチリ地震津波がある。
しかし、2011(平成23)年3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で、高田松原は10メートルを超える大津波に呑み込まれ、ほぼ全ての松がなぎ倒され壊滅した。
『宮城県昭和震嘯(しんしょう)誌』(※9参照)から三陸地方の津波の歴史を詳しく解析しているものがある。それが以下の論文だ。
三陸地方の津波の歴史 その1 首藤伸夫
三陸地方の津波の歴史 その2

●(上掲の画象は、昭和8(1933)年3月3日午前2時30分岩手県東方沖でマグニチュード8.1の地震が起こり、三陸海岸を中心に最高28,7mの津波を起こした「昭和三陸津波」は、1896(明治29)年の「明治三陸津波」以来の37年ぶりの大惨事となった。写真は岩手県宮古町。『朝日クロニクル週刊20世紀』1933-34年号より借用。)
『宮城県昭和震嘯誌』には、三陸地方の津波の歴史(原文)について以下のように記されているそうだ。([ ]内の数字は西暦年)
「三陸沿岸」に於て、從來、記録又は據(よ)るべき口碑(石碑のようにながく後世にのこる意。古くからの言い伝え。)により、「地震に伴ふ津浪」の起りしものを次に列擧せん。(備考)括弧内の年代は昭和八年よりの逆算數なり。
(一)貞觀十一年五月二十六日[869](一千六十四年前)三代實録陸奥國大地震家屋倒潰、壓死者多く、津浪は城下(多賀城か)に追つて溺死者千人餘資産苗稼流失す。
(二)天正十三年五月十四日[1585](三百四十八年前)(口碑)宮城縣本吉郡戸倉村の口碑に海嘯ありしを傳ふ。(参考 同年十一月二十九日、畿内・東海・東山・北陸に大震ありて死者多し。)
(三)慶長十六年十月二十八日[1611](三百二十二年前)御三代御書上陸奥國地震後大津浪あり。伊達領内にて男女一千七百八十三人、牛馬八十五頭溺死す。又現在の陸中山田町附近・鵜住居村・大槌町・津輕石村等にも被害多し。
(四)元和二年七月二十八日[1616](三百十七年前)「三陸地方」強震後大津浪あり。
(五)慶安四年[1651](二百八十二年前)宮城縣亘理郡東裏迄海嘯襲來す。(口碑)
(六)延寳四年十月[1676](二百五十七年前)常陸國水戸、陸奥國磐城の海邊に津浪ありて人畜溺死し、屋舎流失す。
(七)延寳五年三月十二日[1677](二百五十六年前)(口碑)陸中國南部領に數十回の地震あり、地震直接の被害なきも、津浪ありし宮古、鍬ケ崎、大槌浦等に家屋流失あり。
(八)貞享四年九月十七日[1687](二百四十六年前)宮城縣内、鹽釜をはじめ宮城郡沿岸に海嘯あり、その高さ地上一尺五、六寸にして、十二、三度進退す。
(九)元祿二年[1689](二百四十四年前)陸中國に津浪あり。(口碑)
(十)元祿九年十一月一日[1693](二百三十七年前)宮城縣北上川口に高浪襲來、船三百隻を流し、溺死者多し。《首藤註:高潮か?》
(十一)享保年間[1716~1735](二百十七年、百九十八年前)海嘯あり、田畑を害せしが、民家・人畜を害ふに至らず。
(十二)寳暦元年四月二十六日[1751](百八十二年前)高田大地震の餘波として、陸中國に津浪あり。
(十三)天明年間[1781~1788](百五十二年 - 百四十五年前)海嘯あり。
(十四)寛政年間[1793-](凡百四十年前)「三陸沿岸」に地震・津浪あり、宮城縣桃生郡十五濱村雄勝にて床上浸水二尺。
(十五)天保七年六月二十五日[1836](九十七年前)東藩史稿仙臺地方大震ありて、牙城の石垣崩れ、海水溢れ、民家數百を破りて溺死者多し。
(十六)安政三年七月二十三日[1856](七十七年前)宮城縣桃生郡十五濱村雄勝「先祖代々記」正午頃「三陸地方」に地震あり、次いで大津浪起り、現在の宮城縣桃生郡十五濱村雄勝にて床上浸水三尺、午後十時頃迄に十四、五度押寄す。人畜の死傷は凡んどなかりしが、北海道南部にては、かなりの被害ありしものの如し。
(十七)明治元年六月[1867](六十六年前)宮城縣本吉郡地方津浪あり。
(十八)明治二十七年三月二十二日[1894](三十九年前)午後八時二十分頃岩手縣沿岸に小津浪あり。
(十九)明治二十九年六月十五日[1896](三十七年前)午後七時半起れる海底地震によりて、「三陸沿岸」は、午後八時十分頃より八時三十分頃迄に於て大津浪襲來し死者二萬千九百五十三人、傷者四千三百九十八人、流矢家屋一萬三百七十棟、内、宮城縣死者三千四百五十二人、傷者千二百四十一人、流失家屋九百八十五戸
(二十)大正四年十一月一日[1915](十八年前)「三陸沖地震」によるものにして宮城縣志津川灣に小津浪あり。
(廿一)昭和八年三月三日[1933]午前二時半頃起れる外側帶性地震は、約三十分後、「三陸」及北海道日高國の沿岸に津浪を伴ひ、そのため、六十七町村は被害をうけ、死者千五百二十九人、行方不明者千四百二十一人、負傷者千二百五十八人を出し、流失・倒潰家屋七千二百六十三戸を生ぜり。・・・と。
海嘯(かいしょう)とは、河口に入る潮波が垂直壁となって河を逆流する現象であり、潮津波(しおつなみ)とも呼ばれる。昭和初期までは地震津波も海嘯と呼ばれていたようだ。
「三陸地方に於ける既往の震嘯は、前述の如くなるが、その中、代表的のものを次に掲げん。」・・・として、
(一) 貞觀十一年の震嘯陸奥國地大震動。(二) 慶長十六年の震嘯。(三) 安政三年の震嘯。それに、 (四) 明治二十九年の震嘯・・・を挙げている。この津波の内容や被害の詳細等は上記論文参照。
「三陸地方」とは、東北地方の太平洋岸の名称であり、この地域は地理学的にはその成立に複雑な歴史が絡んでいるが、通常3つの陸の付いた国陸奥・陸中・陸前の3国全域を指すことよりも、この3つの令制国にまたがる海岸三陸海岸地域を指すことが多い(詳しくは、Wikipediaの三陸海岸また、参考の※10を参照)
当海岸は1896(明治29)年6月15日に発生した地震に伴って、本州における当時の観測史上最高の遡上高(そじょうこう。※11参照)である海抜38.2mを記録する津波(明治三陸地震参照)が発生し、甚大な被害を与えた。
しかし、当海岸全体を指す言葉が無かったため、この地震・津波の報道では当初様々な呼称が用いられていたが、やがて「三陸」という言葉が用いられるようになり、当海岸は以降「三陸海岸」と呼ばれるようになったという(※10を参照)。
よって、一般的には、北上山地が太平洋と接する海岸線を指す。すなわち、青森県南東部の鮫角から岩手県沿岸を経て宮城県東部の万石浦まで、総延長600km余りの海岸を言うそうだ。
海岸中部の岩手県宮古市には本州最東端の魹ヶ崎があり、同市を境に北部は海岸段丘が発達し港に適した場所が少ないため、農業・牧畜などが盛んである。
一方宮古市よりも南では、隆起速度を上回る海面上昇により相対的に沈水し、リアス式海岸となっている。そのため、水深の深い入り江が多く、天然の良港となって漁業が盛んである。世界三大漁場「三陸沖」には、この南部の漁港から主に出漁する。
海岸沿いには国道45号、八戸線、三陸鉄道北リアス線・南リアス線、山田線、大船渡線、気仙沼線が通っている。海岸沿いには多数の景勝地があり、遊覧船が就航されている所もあり、観光地としても知られている。
1933(昭和8)年の昭和三陸地震からは、78年後の2011(平成23)年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震。それから、2年を経過した今年、NHK連続テレビ小説・第88シリーズ「あまちゃん」は、前半の「故郷編」では東北地方・三陸海岸にある架空の町・岩手県北三陸市が舞台となっている。
時代は2008年の夏休み。引きこもりがちな都内の女子高生(ヒロイン・アキ)が夏休みに母の故郷である北三陸母に連れてこらて祖母と出会う。現役の海女を続ける祖母は、人生で初めて出会った「カッコいい!」と思える女性だった。
厳しく切り立ったリアス式海岸の海に、恐れもせず潜っていく祖母の姿に衝撃を受け「私、海女になりたいかも・・・と海女にチャレンジ」。やがてアキは地元アイドルとして町おこしのシンボルになっていくらしい。
同じ東北(宮城県)出身の脚本家宮藤官九郎は、「小さな田舎の、地元アイドルによる村おこし」をテーマーに書こうと思ってい居る中で岩手県久慈市・小袖海岸の「北限の海女」や、三陸鉄道北リアス線(岩手県宮古市の宮古駅と久慈市の久慈駅とを結ぶ)を使った町おこしなどの存在を知り、これらをストーリーの軸に決めたという。
最終盤では、劇中劇として2011年(平成23年)3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)発生の場面を盛り込むそうだが、当初より、NHKや宮藤の頭の中には、2年前の3月11日の地震と津波による災害からの復興への応援歌として作ろう・・・との考えがあったのだろうと思われる。舞台となっている小袖海岸の風景は実に美しい。以下で見れる。
あまちゃん ロケ地 小袖海岸YouTube
また、過去に津波の被害を受けた三陸沿いの津々浦々には約200基もの津波に対する備えや警告の石碑(災害記念碑)がさまざまな形で建てられ、今も多く残っている。その一部は、以下でも見ることができる。
It happened that | 大震嘯災記念A
http://happenlog.blog73.fc2.com/blog-entry-290.html
It happened that |大震嘯災記念B
http://happenlog.blog73.fc2.com/blog-entry-894.html
未曾有の大災害を引き起こした津波の恐ろしさを未来に残そうとした先人達の教訓・・・。
約3千人の犠牲者が出た1933年3月3日の昭和三陸沖地震から数えて78年後の2011年3月の東北地方太平洋沖地震ではどれだけの人たちに先人の教えが守られたのだろうか。これら先人の記念碑は、海の景色に溶け込む単なるオブジェであったのか・・・。
それから2年経った、今年3月で、昭和三陸沖地震から80年目になる。今一度、昭和三陸沖地震の結果を振り返り、何が問題であったのかを反省しなければ、また同じことを繰り返すことになるだろう。
上記論文に見られるように、昭和三陸地震は、岩手県上閉伊郡・釜石町(現・釜石市)の東方沖約 200 kmを震源として発生した地震であり、気象庁の推定による地震の規模はM8.1(※12の過去の地震・津波被害
参照)。金森博雄の推測はMw8.4で、アメリカ地質調査所 (USGS) もこれを採用しているという。
震源は日本海溝を隔てた太平洋側であり、三陸海岸まで200km以上距離があったため三陸海岸は軒並み震度5の強い揺れを記録したが、明治三陸地震の時と同じく地震規模に比べて地震による直接の被害は少なかった。その一方で、強い上下動によって発生した大津波が襲来し被害は甚大となった。
最大遡上高は、岩手県気仙郡綾里村(現・大船渡市三陸町の一部)で、海抜28.7mを記録した。 第一波は、地震から約30分で到達したと考えられる(上掲1の論文Page 5には明治と昭和の津波について、各地の遡上高比較も記載されているので参考にされるとよい)。
この地震による被害は、死者1522名、行方不明者1542名、負傷者1万2053名、家屋全壊7009戸、流出4885戸、浸水4147戸、焼失294戸に及んだ。行方不明者が多かったのは、津波の引き波により海中にさらわれた人が多かった事を意味する。
特に被害が激しかったのは、岩手県の下閉伊郡田老村(現・宮古市の一部)で、人口の42%に当たる763人が亡くなり(当時の村内の人口は1798人)、家屋も98%に当たる358戸が全壊した。津波が襲来した後の田老村は、家がほとんどない更地同然の姿となっていた。
震災から約4ヶ月後の同年6月30日、宮城県は「海嘯罹災地建築取締規則(昭和八年六月三十日宮城縣令第三十三號)を公布・施行した(※13参照)。
当条例は、津波被害の可能性がある地区内に建築物を設置することを原則禁止しており、住宅を建てる場合には知事の認可を必要とし、工場や倉庫を建てる場合には「非住家 ココニスンデハ キケンデス」の表示を義務付けた。違反者は拘留あるいは科料に処すとの罰則も規定された。
1950(昭和25)年に建築基準法が施行され、災害危険区域を指定して住宅建築を制限する主体は市町村となったため、当条例は既に存在していないとの説があるものの、廃止された記録もないため、現行法上の有効性は不明。なお、県内では現行法に基いて仙台市・南三陸町・丸森町が災害危険区域を条例で指定しており、沿岸自治体の仙台・南三陸の2市町のみが県の当条例を一部引き継いでいるとも見なせるが、現行法で認める違反者への50万円以下の罰金が3市町の条例ではいずれも規定しておらず、罰則規定については引き継がれなかったと言える。・・・と指摘している。
また、1964(昭和39)年の新潟地震を契機として、1972(昭和47)年に防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(※14)が公布・施行され、災害危険区域からの防災集団移転促進事業(※15)の財政的な裏付けがなされた。
ただし、同事業における補助金は事業費の3/4の充当であるため、事業主体の地方公共団体が事業費の1/4を負担しなくてはならないこと、平時において移転促進区域内の住民の同意を得て全住居の移転を達成しなくてはらないことなど実施にはハードルが高く、2011年(平成23年)3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)以前に県内で同事業が実施されたのは、1978(昭和53)年6月12日の宮城県沖地震後に仙台市の27戸が移転した例のみに留まっている(※16)という。・・・「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということか。
また、津波の襲来により多くの死者を出し、家がほとんどなくなった田老村では、1982(昭和57)年までに海抜10m 、総延長2433mの巨大な防潮堤が築かれた。そして、1958(昭和33)年に完成した1期工事の防潮堤は、1960年(昭和35年)5月23日に発生・来襲したチリ地震津波の被害を最小限に食い止める事に成功した。これにより、田老の巨大防潮堤は全世界に知れ渡った。
この巨大防潮堤は田老の防災の象徴ともなっていたが、自然の及ぼす力は人智を超えている。今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)では「想定外」の大津波となってこの防潮堤を越えて町内を襲い、全域を壊滅状態にしてしまった・・・・。
このような立派な堤防で津波に抵抗しても津波は防げなかった。今後、どれだけ巨大なものを作るのだろうか。今回の津波以上のものを防止しようとするともう、箱の中に閉じこもったような生活をしなければならないだろう。まずは、高台へ移転するのが優先されるべきなのだろうが・・・。
しかも、今回の地震と津波は福島第一原発の炉心溶融と建屋爆発事故も発生させ、その放射能汚染が、2重の災害(被害)をもたらすことになった(詳しくは福島第一原子力発電所事故を参照)。
「海辺に住むな」「高台に逃げろ」「此処(ここ)より下に家を建てるな」という先人たちの残した警告や教訓。中には、不便を承知で本気で高台へ移転した人たちも多くいた。また、当時は、海岸近くに住宅は建てず、高台に家を構えた人もいたが、代替わりするうちに堤防の与える安心感や、漁など海に近いところの利便性を求めて低地へ移る人も増え、前段でも挙げたようなな法律も形骸化し、結果として、東日本大震災では約1万9000人もの人たちが死亡したり行方不明になったりしてしまったが、先人の警告や守り続けた人たちは、助かり明と暗に分かれることになっている。
先人たちが残したものは石碑だけではない。以下参考に記載の「※17:記者の目:震災1年 風化繰り返した過去の悲劇」には以下のように書かれている。
1933(昭和8)年の昭和三陸津波の後、宮城県では、震災を永久に記録しようと、全国から寄せられた義援金をもとに、県内32カ所に復興記念館が建てられ、震災資料の展示や記念行事を行うほか、講演や教育の場としても地域住民が利用できた。だが老朽化による取り壊しで、2011年3月の震災前に残っていたのは5館のみであったという。
この記念館の現状を調査した気仙沼市の白幡勝美教育長は「(教訓の)風化の早さを物語っている」と残念がる。そして、震災で今は1館を残すだけであり、その最後の1館も、津波の常襲地帯、唐桑(からくわ)半島にある宿(しゅく)集会所であり、老朽化した集会所で取材をした毎日新聞の記者が驚いたのは、震災資料が一切残されていないことだという。戦後、家政学校や商工会事務所として利用され、いつまで展示されていたのかすら定かではない。取り壊されなかったのは、代わりの集会所がなかったからだからという。・・・と。これを読んで私も、地元民の、防災意識の欠如の驚かされるばかりである。
こうした事例から、失敗学を提唱する畑村洋太郎は、「失敗は人に伝わりにくい」「失敗は伝達されていく中で減衰していく」という、失敗情報の持つ性質を見出している(※18、※19参照)。
昨年の1月、このブログ辰年に思うでも書いたので、詳しくは書かないが、防災に関する文章などによく用いられる物理学者(地震研究者)にして随筆家であった寺田寅彦も、「災害は忘れた頃にやって来る」との明言を吐いたとされるが、人の記憶は時の経過とともに忘れ去られる。
四季に恵まれた日本ではあるが、日本列島の生い立ちから地核変動による、地震が多く、地震大国とも言われる。そして、ここのところ、周期的大地震が頻繁しているのであるが、10年、50年が過ぎれば、先にも書いたように、悲惨な惨事についての伝承、語り伝えも途絶え、曖昧になり、忘却の彼方に遠ざけられてゆくことになる。
いくら先人が警告のための記念碑を建てても、人は時と共に語り伝えることを止め、そのうち記憶は薄れ、かって先人が味わった苦悩や苦痛、悲しみを忘れて、同じ事を何度でも繰り返す。自分たちのご先祖達にも津波によって家屋を破壊され、生命を失った者がいたはずだろうに・・・・。
同じ過ちを繰り返す、愚かな人間の業ともいうべきか・・・。
1995年(平成7年)1月17日(火)に、私が経験した阪神淡路大震災のような直下型地震は、繰り返し周期が1000年から10000万年という長期に及ぶものが多く、将来の発生を予測するのはほとんど不可能だそうである。一方、東北地方太平洋沖地震のような海溝型地震は、繰り返し周期も短く、最短で10年、長い場合でも500年であるという。
また、阪神淡路大震災はキラーパルス(※20参照)が卓越していたため家屋の倒壊による甚大な被害を出した。逆に、東北地方太平洋沖地震はキラーパルスはあまり含まれていなかったため、阪神淡路大震災のような建物の倒壊による圧死は少なかったが、地震動の長さ、余震、津波により甚大な被害を出した。V字型の湾や岬の突端、リアス式海岸などの複雑な地形などでも波が高くなる。また川を遡上して内陸数kmまで到達する場合もある。2011年の東北地方太平洋沖地震が津波被害の典型的な事例であるという。(全体のことは、※21:「地震の基礎」を参照)。
三陸海岸は津波の発生し易い地形であり、それは歴史が証明していることである。津波対策こそ重要ということだろう。今度こそ、震災の悲劇と、その教訓を忘れないで、備えを十分に立てておくべきではないか。
政府の地震調査研究推進本部の予測によると、2010年1月1日からの発生確率は30年以内で 60 - 70 % 、50年以内で 90 % 程度以上とされていると発表されていた。
また、政府の地震調査委員会は今年3月11日、日本周辺で起きる地震の発生確率を、今年1月1日を基準として計算した結果を発表、東南海地震の今後30年以内の発生確率が、昨年の「70%程度」から「70~80%」に上昇するなど、一部地域でわずかに上昇した。また南海地震(30年以内)は「60%程度」で変わらなないといわれていた(※22参照)。
しかし、南海トラフ巨大地震の対策を検討していた国の有識者会議は、今月28日、地震予知が現状では困難と認め、備えの重要性を指摘する最終報告をまとめたと、昨日・5月29日にマスコミは一斉に報じていた(※23参照)。
そして、家庭用備蓄を「一週間以上」とすることや、巨大津波への対応を求めている。古谷圭司・防災相は今年度中に国の対策大綱をまとめるとの方針も示した。
もともと地震予知の手がかりとなる前兆を確実に観測できた例が過去に一つもないところに、今回の東日本大震災が起きている。歴史的な事実からある程度の地震の周期的なことは推測できたとしても、地震が発生する数時間から数日前に起きる前触れ的なプレートの動きをとらえた確度の高い余地は「困難なこと」であった。
東海地震の予知のために24時間体制の監視などをしていたが、阪神淡路大震災、その他東日本大震災発生までに大きな地震が数多く起こっている。そんなこともあり、研究が進めば進むほど予知の難しさがわかったという。
●(上掲の画像は、内閣府の有識者会議の試算結果から示された被害者数等の状況。都府県別のそれぞれの最悪のケース。全体値は合計が最悪になるケース。画像は5月29日朝日新聞朝刊より。)
たかじんのそこまで言って委員会に出演していた地震学者であり、東大教授のロバート・ゲラー氏は、「地震は、予測できるものではない」。「大地震の前には前兆現象が起きるという仮説のもとに予知の研究は行われてきた。だが、100年探しても前兆現象は見つかっていないのだから、地震学者は地震予知という幻想を捨てて、本来の基礎研究を行うべきだ。」・・・・と、前々から言っていたよ。今更政府がそんな当たり前のことを発表するなんて相当遅れているということだ。
もし。今回言っている南海トラフ巨大地震が明日にも来るなどと言われると、どう対処すればよいのだ。それこそパニックを引き起こし大騒ぎになるだけでなくいろんな問題が生じるだろう。
地震大国に居住している以上、地震との遭遇は、避けられないものと覚悟をし、インフラなどは国や地方がやるとしても、一週間ぐらい生き延びれるだけの食料や防災用品の準備、避難場所の確保等は各人がそれぞれの責任で用意しておかなければいけないだろう。
2年前の東北の地震にしても、それまでに、阪神淡路大震災や新潟県中越地震など大きな地震が発生し、大きな被害が出ているにかかわらず、数日分の飲料水の準備さえしておらず困った困ったといっている人を、テレビの報道などで見たが、まるで、よその地で起こった震災の被害等は、対岸の火事のように見ていたのだろう。
被害にあえば、困った困ったと泣き言を言いながら肝心の予防はしない。そんな人は、今度の震災でひどい目にあうだろう。肝に命じておかなければいけないと思う。
同じ1年と言っても、自然界におけえる時の間隔は我々人間の1年とは全然違う。30年以内といっても極端に言えばもう明日のことかもしれない。本当に30年後なら、おそらく私は生きてはいないので関係はない。もう、先の短い私の年代になると、30年以上も住んでいる家が倒壊しようが、倒壊した家で圧死しようがいずれ死ぬ身、どちらでもよいと思っている。
仏教では、今は末法の時代だという。世の中も荒んできたし、資本主義経済も行き着くところへ来たようで、住みにくい世の中になってしまった。私だけのことなら、なるがままに任せようと思う。
しかし、災害に遭っても不幸にして助かってしまったり、私が大けがをして、歳とった家内に世話をかけるのは心苦しい。そのために、住まいの防災対策についても最低限は講じてある。
わが身のことについては来るなら来いという感じなのであるが、息子や孫の行く末を考えると可愛そうだ。そのため毎日ご先祖様のご加護をお祈りはしているのだが・・・・。
(冒頭の画像が、2011年5月30日付朝日小学生新聞に掲載されたやなせたかしさんの連載「メルヘン絵本」の絵。6月14日付朝日新聞朝刊掲載分を借用)。
このヒョロ松さんが歌っていたのが、やなせたかしさん自身の作詞、作曲による「陸前高田の松の木」であった。
(一番)
陸前高田の松林
うす桃色のかにの子は
ハサミふりふり歌うのさ
ここで生まれたいのちなら
陸前高田の松の木は
みんなのいのちの友だちだ
★ぼくらは生きる
負けずに生きる
生きてゆくんだ
オー オー オー
(4番まである★は繰り返し)
アンパンマンの原作者やなせたかしさん(当時92歳)が、2011(平成23)年3月11日(金)に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による津波で、岩手県陸前高田市の名勝・高田松原に1本だけ残った松の木を見て歌を作ったもの。
高田松原には震災前、海岸沿いに約7万本の松の木があった。だが津波に襲われ、残ったのは1本だけ。大切なものを失った被災者のあいだで、いつしか「奇跡の一本松」と言われるようになった。

●(上掲の画象は、「奇跡の一本松」として復興のシンボルになった1本の松。背後に見えるのは被災した陸前高田ユースホステルの建物。2011年5月6日撮影。Wikipediaより)
今にも倒れそうな一本松。やなせさん自身も当時92歳になり、学校の同級生は2人しか残っていない。「あとは全部死んでしまった。漫画家の仲間もほとんどいなくなった。わずかに3歳下の水木しげるがいるだけ。僕自身も病気が多く余命はわずかだと思う」。生き残った松が、自分自身と重なったという。
そういえば、NHK総合テレビ『爆笑問題のニッポンの教養』に出演したやなせたかしさんが、ぬいぐるみで埋め尽くされたアンパンマン部屋を訪ねてきた爆笑問題(太田光・田中裕二)を相手に、「奇跡の一本松」の応援歌ともいうべき「陸前高田の松の木」を大きな声で熱唱していたのを思い出した(放送日:2011年12月1日[木)]22:55~23:25.。2011年9月1日放送分のアンコール放送分)。以下でそのシーンが見られるが、4番の歌詞を歌っている。
「陸前高田の松ノ木」やなせたかしSings~IMG
太田や田中が言っていたように、やなせの作品が常に「生きていく」ということをテーマにしていること、また、やなせも作品を作る理由は、人を喜ばせると自分がうれしいからだと語っていたが、それが、彼の作品が子供達だけでなく誰からも、愛し続けられている秘訣なのだろう。
私の地元、神戸ハーバーランドにも先月神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール(※3参照)がオープンしたがちびっ子たちで大賑わいであった。
高田松原の約7万本の松の中で震災の津波に耐え唯一流されずに残り、震災で何もかもなくした同じ境地の地域の人々の祈りや希望を込め、「奇跡の一本松」と名付けられた松の現状は地盤沈下により根元は塩水に侵され厳しい状況にあった。そして、葉の緑も日増しに薄くなり、赤茶けていく。保存を望む地元の人たちは、「なんとか生き抜いてもらいたい」と木の周りに防潮柵を作ったり、活性剤を与えたりと、いろいろ努力をしたようであるが、哀しいかな立ち枯れてしまったようである。
これに対し、陸前高田市は復興のシンボルにしようと長期保存を決定。昨・2012(平成24)年9月から根元と幹、枝葉に切り分けて、復元が進められていた。
作業では、高さが27メートルもある一本松を根元から切り倒し、幹を5分割にして、その芯をくり抜く。そして、防腐処理をしたうえで、金属製の心棒を幹に通してモニュメントにするといったもので、震災2周年の節目になる今年・2013(平成25)年3月11日には、元の場所でお披露目したいとの考えだったようだ。
しかし、3月6日に復元で、特殊な樹脂を使って再現した枝葉のレプリカを取り付けが行われたが、市民から「立ち姿が以前と違うのではないか」と指摘があり、取り付けミスが発覚、接続部の特殊な金具は再利用できないため、新たに作り直すことになったが、22日に現地で予定していた完成式典には間に合わず完成は6月末になるとの発表があった(3月21日、※4参照)。
この「奇跡の一本松」の保存工事には、1億5000万円もかかるらしく、このような費用をかけて保存工事をすることには、当初より地元住民の間でもいろいろと賛否が分かれ、論議されていたようである(※5参照)。
私の地元神戸も兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)に見舞われ街の大半が崩壊した。そして、神戸のシンボルでもある港が破壊されたが、メリケンパークには神戸港の復旧・復興に努めた様子を後世に伝えようと、メリケンパークの岸壁の一部・約60メートルを被災当時のままの状態で保存した「神戸港震災メモリアルパーク」などが設けられている(ここ参照)。
このような災害についてのメモリアルをどのような形で後世に伝えていくかはに関しては、私達部外者(県外の者)が、とやかくと意見を挟むことではないので、その有益性などについては、地元住民の間十分に話し合って決めるべきことだろう。
岩手県陸前高田市は、今年3月27日の記者会見で、修復作業が進められている「希跡の一本松」を顕微鏡で調べた結果樹齢173年と判明したと発表している。この一本松は1896(明治29)年の明治三陸地震、1933(昭和8)年の昭和三陸地震の2度の大津波に遭いながら、生き抜いた古木。樹齢の判定は難しく、173年より数年古い可能性もあるといい、再鑑定を進めているようだ。地元の市民団体などには260年とする説もあるようだが、これは見間違いによるもののようだ(※6参照)。
いずれにしてもこの「一本松」は陸前高田の地にあって、度重なる震災と津波を経験しそれを乗り越えてきた松であることに間違いはない。
岩手県陸前高田市は、太平洋に面した三陸海岸の南寄りに位置する。旧陸前国・気仙郡に属し、隣接する同県大船渡市や宮城県気仙沼市とともに陸前海岸北部の中核を成す都市である。
かつてこの地に存在していた松原(「高田松原」)が広がっていた地域は、旧高田村(高田町)と旧今泉村(現:気仙町)にまたがっており、もともとは木一本ない砂原で、潮風が巻き上げる砂塵と高潮とにさらされ、背後にある農地は収穫のない年もしばしばという有様であったようだ(※7参照)。
それを、江戸時代の寛文年間に高田の豪商・菅野杢之助が私財を投じて植林し、その後、享保年間には松坂新右衛門による私財を投じての増林が行われ、以来、クロマツとアカマツからなる合計7万本もの松林は、仙台藩・岩手県を代表する防潮林となり、また、その白砂青松の景観は世に広く評価され、
「東北地方稀ニ見ル壯大優美ナル松原ニシテ前ニ廣田灣ヲ控ヘ後ニ氷上山、雷神山等ノ翠巒ヲ繞ラシ山紫水明ノ一勝區ヲ成セリ樹種ハ黒松ヲ主トシ林相整美樹下荊棘ノ繁茂スルモノナク境地清淨ニシテ林内ノ逍遙ニ適ス 」・・と、史蹟名勝天然紀念物保存法による天然記念物に指定されていた(※8参照)。

●(上掲の画象は、震災被害を受ける前の高田松原(2007年6月3日撮影。Wikipediaより)
高田松原の防潮林はたびたび津波に見舞われ、同時に津波被害を防いできた。
近代以降で代表的なものとしては、1896(明治29)年6月15日の明治三陸津波、1933(昭和8)年3月3日の昭和三陸津波、1960(昭和35)年5月24日のチリ地震津波がある。
しかし、2011(平成23)年3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で、高田松原は10メートルを超える大津波に呑み込まれ、ほぼ全ての松がなぎ倒され壊滅した。
『宮城県昭和震嘯(しんしょう)誌』(※9参照)から三陸地方の津波の歴史を詳しく解析しているものがある。それが以下の論文だ。
三陸地方の津波の歴史 その1 首藤伸夫
三陸地方の津波の歴史 その2

●(上掲の画象は、昭和8(1933)年3月3日午前2時30分岩手県東方沖でマグニチュード8.1の地震が起こり、三陸海岸を中心に最高28,7mの津波を起こした「昭和三陸津波」は、1896(明治29)年の「明治三陸津波」以来の37年ぶりの大惨事となった。写真は岩手県宮古町。『朝日クロニクル週刊20世紀』1933-34年号より借用。)
『宮城県昭和震嘯誌』には、三陸地方の津波の歴史(原文)について以下のように記されているそうだ。([ ]内の数字は西暦年)
「三陸沿岸」に於て、從來、記録又は據(よ)るべき口碑(石碑のようにながく後世にのこる意。古くからの言い伝え。)により、「地震に伴ふ津浪」の起りしものを次に列擧せん。(備考)括弧内の年代は昭和八年よりの逆算數なり。
(一)貞觀十一年五月二十六日[869](一千六十四年前)三代實録陸奥國大地震家屋倒潰、壓死者多く、津浪は城下(多賀城か)に追つて溺死者千人餘資産苗稼流失す。
(二)天正十三年五月十四日[1585](三百四十八年前)(口碑)宮城縣本吉郡戸倉村の口碑に海嘯ありしを傳ふ。(参考 同年十一月二十九日、畿内・東海・東山・北陸に大震ありて死者多し。)
(三)慶長十六年十月二十八日[1611](三百二十二年前)御三代御書上陸奥國地震後大津浪あり。伊達領内にて男女一千七百八十三人、牛馬八十五頭溺死す。又現在の陸中山田町附近・鵜住居村・大槌町・津輕石村等にも被害多し。
(四)元和二年七月二十八日[1616](三百十七年前)「三陸地方」強震後大津浪あり。
(五)慶安四年[1651](二百八十二年前)宮城縣亘理郡東裏迄海嘯襲來す。(口碑)
(六)延寳四年十月[1676](二百五十七年前)常陸國水戸、陸奥國磐城の海邊に津浪ありて人畜溺死し、屋舎流失す。
(七)延寳五年三月十二日[1677](二百五十六年前)(口碑)陸中國南部領に數十回の地震あり、地震直接の被害なきも、津浪ありし宮古、鍬ケ崎、大槌浦等に家屋流失あり。
(八)貞享四年九月十七日[1687](二百四十六年前)宮城縣内、鹽釜をはじめ宮城郡沿岸に海嘯あり、その高さ地上一尺五、六寸にして、十二、三度進退す。
(九)元祿二年[1689](二百四十四年前)陸中國に津浪あり。(口碑)
(十)元祿九年十一月一日[1693](二百三十七年前)宮城縣北上川口に高浪襲來、船三百隻を流し、溺死者多し。《首藤註:高潮か?》
(十一)享保年間[1716~1735](二百十七年、百九十八年前)海嘯あり、田畑を害せしが、民家・人畜を害ふに至らず。
(十二)寳暦元年四月二十六日[1751](百八十二年前)高田大地震の餘波として、陸中國に津浪あり。
(十三)天明年間[1781~1788](百五十二年 - 百四十五年前)海嘯あり。
(十四)寛政年間[1793-](凡百四十年前)「三陸沿岸」に地震・津浪あり、宮城縣桃生郡十五濱村雄勝にて床上浸水二尺。
(十五)天保七年六月二十五日[1836](九十七年前)東藩史稿仙臺地方大震ありて、牙城の石垣崩れ、海水溢れ、民家數百を破りて溺死者多し。
(十六)安政三年七月二十三日[1856](七十七年前)宮城縣桃生郡十五濱村雄勝「先祖代々記」正午頃「三陸地方」に地震あり、次いで大津浪起り、現在の宮城縣桃生郡十五濱村雄勝にて床上浸水三尺、午後十時頃迄に十四、五度押寄す。人畜の死傷は凡んどなかりしが、北海道南部にては、かなりの被害ありしものの如し。
(十七)明治元年六月[1867](六十六年前)宮城縣本吉郡地方津浪あり。
(十八)明治二十七年三月二十二日[1894](三十九年前)午後八時二十分頃岩手縣沿岸に小津浪あり。
(十九)明治二十九年六月十五日[1896](三十七年前)午後七時半起れる海底地震によりて、「三陸沿岸」は、午後八時十分頃より八時三十分頃迄に於て大津浪襲來し死者二萬千九百五十三人、傷者四千三百九十八人、流矢家屋一萬三百七十棟、内、宮城縣死者三千四百五十二人、傷者千二百四十一人、流失家屋九百八十五戸
(二十)大正四年十一月一日[1915](十八年前)「三陸沖地震」によるものにして宮城縣志津川灣に小津浪あり。
(廿一)昭和八年三月三日[1933]午前二時半頃起れる外側帶性地震は、約三十分後、「三陸」及北海道日高國の沿岸に津浪を伴ひ、そのため、六十七町村は被害をうけ、死者千五百二十九人、行方不明者千四百二十一人、負傷者千二百五十八人を出し、流失・倒潰家屋七千二百六十三戸を生ぜり。・・・と。
海嘯(かいしょう)とは、河口に入る潮波が垂直壁となって河を逆流する現象であり、潮津波(しおつなみ)とも呼ばれる。昭和初期までは地震津波も海嘯と呼ばれていたようだ。
「三陸地方に於ける既往の震嘯は、前述の如くなるが、その中、代表的のものを次に掲げん。」・・・として、
(一) 貞觀十一年の震嘯陸奥國地大震動。(二) 慶長十六年の震嘯。(三) 安政三年の震嘯。それに、 (四) 明治二十九年の震嘯・・・を挙げている。この津波の内容や被害の詳細等は上記論文参照。
「三陸地方」とは、東北地方の太平洋岸の名称であり、この地域は地理学的にはその成立に複雑な歴史が絡んでいるが、通常3つの陸の付いた国陸奥・陸中・陸前の3国全域を指すことよりも、この3つの令制国にまたがる海岸三陸海岸地域を指すことが多い(詳しくは、Wikipediaの三陸海岸また、参考の※10を参照)
当海岸は1896(明治29)年6月15日に発生した地震に伴って、本州における当時の観測史上最高の遡上高(そじょうこう。※11参照)である海抜38.2mを記録する津波(明治三陸地震参照)が発生し、甚大な被害を与えた。
しかし、当海岸全体を指す言葉が無かったため、この地震・津波の報道では当初様々な呼称が用いられていたが、やがて「三陸」という言葉が用いられるようになり、当海岸は以降「三陸海岸」と呼ばれるようになったという(※10を参照)。
よって、一般的には、北上山地が太平洋と接する海岸線を指す。すなわち、青森県南東部の鮫角から岩手県沿岸を経て宮城県東部の万石浦まで、総延長600km余りの海岸を言うそうだ。
海岸中部の岩手県宮古市には本州最東端の魹ヶ崎があり、同市を境に北部は海岸段丘が発達し港に適した場所が少ないため、農業・牧畜などが盛んである。
一方宮古市よりも南では、隆起速度を上回る海面上昇により相対的に沈水し、リアス式海岸となっている。そのため、水深の深い入り江が多く、天然の良港となって漁業が盛んである。世界三大漁場「三陸沖」には、この南部の漁港から主に出漁する。
海岸沿いには国道45号、八戸線、三陸鉄道北リアス線・南リアス線、山田線、大船渡線、気仙沼線が通っている。海岸沿いには多数の景勝地があり、遊覧船が就航されている所もあり、観光地としても知られている。
1933(昭和8)年の昭和三陸地震からは、78年後の2011(平成23)年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震。それから、2年を経過した今年、NHK連続テレビ小説・第88シリーズ「あまちゃん」は、前半の「故郷編」では東北地方・三陸海岸にある架空の町・岩手県北三陸市が舞台となっている。
時代は2008年の夏休み。引きこもりがちな都内の女子高生(ヒロイン・アキ)が夏休みに母の故郷である北三陸母に連れてこらて祖母と出会う。現役の海女を続ける祖母は、人生で初めて出会った「カッコいい!」と思える女性だった。
厳しく切り立ったリアス式海岸の海に、恐れもせず潜っていく祖母の姿に衝撃を受け「私、海女になりたいかも・・・と海女にチャレンジ」。やがてアキは地元アイドルとして町おこしのシンボルになっていくらしい。
同じ東北(宮城県)出身の脚本家宮藤官九郎は、「小さな田舎の、地元アイドルによる村おこし」をテーマーに書こうと思ってい居る中で岩手県久慈市・小袖海岸の「北限の海女」や、三陸鉄道北リアス線(岩手県宮古市の宮古駅と久慈市の久慈駅とを結ぶ)を使った町おこしなどの存在を知り、これらをストーリーの軸に決めたという。
最終盤では、劇中劇として2011年(平成23年)3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)発生の場面を盛り込むそうだが、当初より、NHKや宮藤の頭の中には、2年前の3月11日の地震と津波による災害からの復興への応援歌として作ろう・・・との考えがあったのだろうと思われる。舞台となっている小袖海岸の風景は実に美しい。以下で見れる。
あまちゃん ロケ地 小袖海岸YouTube
また、過去に津波の被害を受けた三陸沿いの津々浦々には約200基もの津波に対する備えや警告の石碑(災害記念碑)がさまざまな形で建てられ、今も多く残っている。その一部は、以下でも見ることができる。
It happened that | 大震嘯災記念A
http://happenlog.blog73.fc2.com/blog-entry-290.html
It happened that |大震嘯災記念B
http://happenlog.blog73.fc2.com/blog-entry-894.html
未曾有の大災害を引き起こした津波の恐ろしさを未来に残そうとした先人達の教訓・・・。
約3千人の犠牲者が出た1933年3月3日の昭和三陸沖地震から数えて78年後の2011年3月の東北地方太平洋沖地震ではどれだけの人たちに先人の教えが守られたのだろうか。これら先人の記念碑は、海の景色に溶け込む単なるオブジェであったのか・・・。
それから2年経った、今年3月で、昭和三陸沖地震から80年目になる。今一度、昭和三陸沖地震の結果を振り返り、何が問題であったのかを反省しなければ、また同じことを繰り返すことになるだろう。
上記論文に見られるように、昭和三陸地震は、岩手県上閉伊郡・釜石町(現・釜石市)の東方沖約 200 kmを震源として発生した地震であり、気象庁の推定による地震の規模はM8.1(※12の過去の地震・津波被害
参照)。金森博雄の推測はMw8.4で、アメリカ地質調査所 (USGS) もこれを採用しているという。
震源は日本海溝を隔てた太平洋側であり、三陸海岸まで200km以上距離があったため三陸海岸は軒並み震度5の強い揺れを記録したが、明治三陸地震の時と同じく地震規模に比べて地震による直接の被害は少なかった。その一方で、強い上下動によって発生した大津波が襲来し被害は甚大となった。
最大遡上高は、岩手県気仙郡綾里村(現・大船渡市三陸町の一部)で、海抜28.7mを記録した。 第一波は、地震から約30分で到達したと考えられる(上掲1の論文Page 5には明治と昭和の津波について、各地の遡上高比較も記載されているので参考にされるとよい)。
この地震による被害は、死者1522名、行方不明者1542名、負傷者1万2053名、家屋全壊7009戸、流出4885戸、浸水4147戸、焼失294戸に及んだ。行方不明者が多かったのは、津波の引き波により海中にさらわれた人が多かった事を意味する。
特に被害が激しかったのは、岩手県の下閉伊郡田老村(現・宮古市の一部)で、人口の42%に当たる763人が亡くなり(当時の村内の人口は1798人)、家屋も98%に当たる358戸が全壊した。津波が襲来した後の田老村は、家がほとんどない更地同然の姿となっていた。
震災から約4ヶ月後の同年6月30日、宮城県は「海嘯罹災地建築取締規則(昭和八年六月三十日宮城縣令第三十三號)を公布・施行した(※13参照)。
当条例は、津波被害の可能性がある地区内に建築物を設置することを原則禁止しており、住宅を建てる場合には知事の認可を必要とし、工場や倉庫を建てる場合には「非住家 ココニスンデハ キケンデス」の表示を義務付けた。違反者は拘留あるいは科料に処すとの罰則も規定された。
1950(昭和25)年に建築基準法が施行され、災害危険区域を指定して住宅建築を制限する主体は市町村となったため、当条例は既に存在していないとの説があるものの、廃止された記録もないため、現行法上の有効性は不明。なお、県内では現行法に基いて仙台市・南三陸町・丸森町が災害危険区域を条例で指定しており、沿岸自治体の仙台・南三陸の2市町のみが県の当条例を一部引き継いでいるとも見なせるが、現行法で認める違反者への50万円以下の罰金が3市町の条例ではいずれも規定しておらず、罰則規定については引き継がれなかったと言える。・・・と指摘している。
また、1964(昭和39)年の新潟地震を契機として、1972(昭和47)年に防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(※14)が公布・施行され、災害危険区域からの防災集団移転促進事業(※15)の財政的な裏付けがなされた。
ただし、同事業における補助金は事業費の3/4の充当であるため、事業主体の地方公共団体が事業費の1/4を負担しなくてはならないこと、平時において移転促進区域内の住民の同意を得て全住居の移転を達成しなくてはらないことなど実施にはハードルが高く、2011年(平成23年)3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)以前に県内で同事業が実施されたのは、1978(昭和53)年6月12日の宮城県沖地震後に仙台市の27戸が移転した例のみに留まっている(※16)という。・・・「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということか。
また、津波の襲来により多くの死者を出し、家がほとんどなくなった田老村では、1982(昭和57)年までに海抜10m 、総延長2433mの巨大な防潮堤が築かれた。そして、1958(昭和33)年に完成した1期工事の防潮堤は、1960年(昭和35年)5月23日に発生・来襲したチリ地震津波の被害を最小限に食い止める事に成功した。これにより、田老の巨大防潮堤は全世界に知れ渡った。
この巨大防潮堤は田老の防災の象徴ともなっていたが、自然の及ぼす力は人智を超えている。今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)では「想定外」の大津波となってこの防潮堤を越えて町内を襲い、全域を壊滅状態にしてしまった・・・・。
このような立派な堤防で津波に抵抗しても津波は防げなかった。今後、どれだけ巨大なものを作るのだろうか。今回の津波以上のものを防止しようとするともう、箱の中に閉じこもったような生活をしなければならないだろう。まずは、高台へ移転するのが優先されるべきなのだろうが・・・。
しかも、今回の地震と津波は福島第一原発の炉心溶融と建屋爆発事故も発生させ、その放射能汚染が、2重の災害(被害)をもたらすことになった(詳しくは福島第一原子力発電所事故を参照)。
「海辺に住むな」「高台に逃げろ」「此処(ここ)より下に家を建てるな」という先人たちの残した警告や教訓。中には、不便を承知で本気で高台へ移転した人たちも多くいた。また、当時は、海岸近くに住宅は建てず、高台に家を構えた人もいたが、代替わりするうちに堤防の与える安心感や、漁など海に近いところの利便性を求めて低地へ移る人も増え、前段でも挙げたようなな法律も形骸化し、結果として、東日本大震災では約1万9000人もの人たちが死亡したり行方不明になったりしてしまったが、先人の警告や守り続けた人たちは、助かり明と暗に分かれることになっている。
先人たちが残したものは石碑だけではない。以下参考に記載の「※17:記者の目:震災1年 風化繰り返した過去の悲劇」には以下のように書かれている。
1933(昭和8)年の昭和三陸津波の後、宮城県では、震災を永久に記録しようと、全国から寄せられた義援金をもとに、県内32カ所に復興記念館が建てられ、震災資料の展示や記念行事を行うほか、講演や教育の場としても地域住民が利用できた。だが老朽化による取り壊しで、2011年3月の震災前に残っていたのは5館のみであったという。
この記念館の現状を調査した気仙沼市の白幡勝美教育長は「(教訓の)風化の早さを物語っている」と残念がる。そして、震災で今は1館を残すだけであり、その最後の1館も、津波の常襲地帯、唐桑(からくわ)半島にある宿(しゅく)集会所であり、老朽化した集会所で取材をした毎日新聞の記者が驚いたのは、震災資料が一切残されていないことだという。戦後、家政学校や商工会事務所として利用され、いつまで展示されていたのかすら定かではない。取り壊されなかったのは、代わりの集会所がなかったからだからという。・・・と。これを読んで私も、地元民の、防災意識の欠如の驚かされるばかりである。
こうした事例から、失敗学を提唱する畑村洋太郎は、「失敗は人に伝わりにくい」「失敗は伝達されていく中で減衰していく」という、失敗情報の持つ性質を見出している(※18、※19参照)。
昨年の1月、このブログ辰年に思うでも書いたので、詳しくは書かないが、防災に関する文章などによく用いられる物理学者(地震研究者)にして随筆家であった寺田寅彦も、「災害は忘れた頃にやって来る」との明言を吐いたとされるが、人の記憶は時の経過とともに忘れ去られる。
四季に恵まれた日本ではあるが、日本列島の生い立ちから地核変動による、地震が多く、地震大国とも言われる。そして、ここのところ、周期的大地震が頻繁しているのであるが、10年、50年が過ぎれば、先にも書いたように、悲惨な惨事についての伝承、語り伝えも途絶え、曖昧になり、忘却の彼方に遠ざけられてゆくことになる。
いくら先人が警告のための記念碑を建てても、人は時と共に語り伝えることを止め、そのうち記憶は薄れ、かって先人が味わった苦悩や苦痛、悲しみを忘れて、同じ事を何度でも繰り返す。自分たちのご先祖達にも津波によって家屋を破壊され、生命を失った者がいたはずだろうに・・・・。
同じ過ちを繰り返す、愚かな人間の業ともいうべきか・・・。
1995年(平成7年)1月17日(火)に、私が経験した阪神淡路大震災のような直下型地震は、繰り返し周期が1000年から10000万年という長期に及ぶものが多く、将来の発生を予測するのはほとんど不可能だそうである。一方、東北地方太平洋沖地震のような海溝型地震は、繰り返し周期も短く、最短で10年、長い場合でも500年であるという。
また、阪神淡路大震災はキラーパルス(※20参照)が卓越していたため家屋の倒壊による甚大な被害を出した。逆に、東北地方太平洋沖地震はキラーパルスはあまり含まれていなかったため、阪神淡路大震災のような建物の倒壊による圧死は少なかったが、地震動の長さ、余震、津波により甚大な被害を出した。V字型の湾や岬の突端、リアス式海岸などの複雑な地形などでも波が高くなる。また川を遡上して内陸数kmまで到達する場合もある。2011年の東北地方太平洋沖地震が津波被害の典型的な事例であるという。(全体のことは、※21:「地震の基礎」を参照)。
三陸海岸は津波の発生し易い地形であり、それは歴史が証明していることである。津波対策こそ重要ということだろう。今度こそ、震災の悲劇と、その教訓を忘れないで、備えを十分に立てておくべきではないか。
政府の地震調査研究推進本部の予測によると、2010年1月1日からの発生確率は30年以内で 60 - 70 % 、50年以内で 90 % 程度以上とされていると発表されていた。
また、政府の地震調査委員会は今年3月11日、日本周辺で起きる地震の発生確率を、今年1月1日を基準として計算した結果を発表、東南海地震の今後30年以内の発生確率が、昨年の「70%程度」から「70~80%」に上昇するなど、一部地域でわずかに上昇した。また南海地震(30年以内)は「60%程度」で変わらなないといわれていた(※22参照)。
しかし、南海トラフ巨大地震の対策を検討していた国の有識者会議は、今月28日、地震予知が現状では困難と認め、備えの重要性を指摘する最終報告をまとめたと、昨日・5月29日にマスコミは一斉に報じていた(※23参照)。
そして、家庭用備蓄を「一週間以上」とすることや、巨大津波への対応を求めている。古谷圭司・防災相は今年度中に国の対策大綱をまとめるとの方針も示した。
もともと地震予知の手がかりとなる前兆を確実に観測できた例が過去に一つもないところに、今回の東日本大震災が起きている。歴史的な事実からある程度の地震の周期的なことは推測できたとしても、地震が発生する数時間から数日前に起きる前触れ的なプレートの動きをとらえた確度の高い余地は「困難なこと」であった。
東海地震の予知のために24時間体制の監視などをしていたが、阪神淡路大震災、その他東日本大震災発生までに大きな地震が数多く起こっている。そんなこともあり、研究が進めば進むほど予知の難しさがわかったという。
●(上掲の画像は、内閣府の有識者会議の試算結果から示された被害者数等の状況。都府県別のそれぞれの最悪のケース。全体値は合計が最悪になるケース。画像は5月29日朝日新聞朝刊より。)
たかじんのそこまで言って委員会に出演していた地震学者であり、東大教授のロバート・ゲラー氏は、「地震は、予測できるものではない」。「大地震の前には前兆現象が起きるという仮説のもとに予知の研究は行われてきた。だが、100年探しても前兆現象は見つかっていないのだから、地震学者は地震予知という幻想を捨てて、本来の基礎研究を行うべきだ。」・・・・と、前々から言っていたよ。今更政府がそんな当たり前のことを発表するなんて相当遅れているということだ。
もし。今回言っている南海トラフ巨大地震が明日にも来るなどと言われると、どう対処すればよいのだ。それこそパニックを引き起こし大騒ぎになるだけでなくいろんな問題が生じるだろう。
地震大国に居住している以上、地震との遭遇は、避けられないものと覚悟をし、インフラなどは国や地方がやるとしても、一週間ぐらい生き延びれるだけの食料や防災用品の準備、避難場所の確保等は各人がそれぞれの責任で用意しておかなければいけないだろう。
2年前の東北の地震にしても、それまでに、阪神淡路大震災や新潟県中越地震など大きな地震が発生し、大きな被害が出ているにかかわらず、数日分の飲料水の準備さえしておらず困った困ったといっている人を、テレビの報道などで見たが、まるで、よその地で起こった震災の被害等は、対岸の火事のように見ていたのだろう。
被害にあえば、困った困ったと泣き言を言いながら肝心の予防はしない。そんな人は、今度の震災でひどい目にあうだろう。肝に命じておかなければいけないと思う。
同じ1年と言っても、自然界におけえる時の間隔は我々人間の1年とは全然違う。30年以内といっても極端に言えばもう明日のことかもしれない。本当に30年後なら、おそらく私は生きてはいないので関係はない。もう、先の短い私の年代になると、30年以上も住んでいる家が倒壊しようが、倒壊した家で圧死しようがいずれ死ぬ身、どちらでもよいと思っている。
仏教では、今は末法の時代だという。世の中も荒んできたし、資本主義経済も行き着くところへ来たようで、住みにくい世の中になってしまった。私だけのことなら、なるがままに任せようと思う。
しかし、災害に遭っても不幸にして助かってしまったり、私が大けがをして、歳とった家内に世話をかけるのは心苦しい。そのために、住まいの防災対策についても最低限は講じてある。
わが身のことについては来るなら来いという感じなのであるが、息子や孫の行く末を考えると可愛そうだ。そのため毎日ご先祖様のご加護をお祈りはしているのだが・・・・。