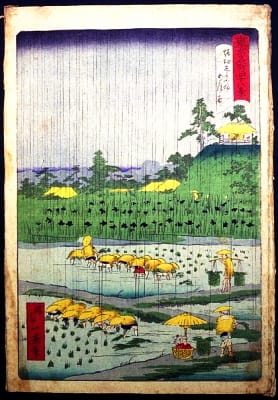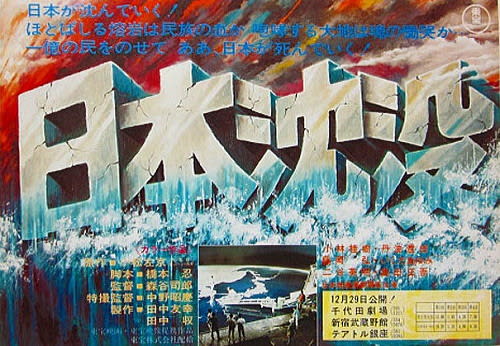1979(昭和54年)年6月28日から29日まで日本で第5回先進国首脳会議(通称:東京サミット)が開催された。これは、日本で開催された初めての主要国首脳会議(サミット)である。
冷戦下の1970年代に入り、ニクソン・ショック(ドルの切り下げ)や第1次石油危機(オイルショック参照)などの諸問題に直面した先進国の間では、世界経済問題(マクロ経済、通貨、貿易、エネルギーなど)に対する政策協調について首脳レベルで総合的に議論する場が必要であるとの認識が生まれた。
このような背景の下、ジスカール・デスタン仏大統領(当時)の提案により、1975年11月、パリ郊外のランブイエ城において、日、米、英、仏、独、伊の6か国による第1回首脳会議が開催された。
第2回目の1976年のプエルトリコ会議からはカナダが参加し、1977年の第3回ロンドン会議からは欧州共同体(EC)(現在は欧州連合【EU】)の欧州委員会委員長が参加するようになった。
そして、1978年ボン会議(サミット)(西ドイツ)に続いて、1979年、東京都港区赤坂の迎賓館で第5回東京会議(サミット)が開催された。
第2次石油危機のさなかに開催されたこのサミットでは主要な議題は石油・エネルギーの問題であった。エネルギーの節約、輸入抑制や方法が論議されたが、最終的に各国の輸入制限目標が決められ、日本の場合は、輸入総量を630万バレルから690万バレルの間に抑える(国内からの要求量は700万バレル)、という案で合意した。
インドシナ難民(※3参照)に関する特別声明もだされた。(過去から現代までのサミットでの会議の概要、参加国、関連文書等は以下参考の※1:「外務省HPG7 / G8」の過去のサミット一覧表および※2:「主要国首脳会議関連文書 - 東京大学東洋文化研究所」を参照れるとよい)
ところで、この会議で討議されたたことの背景を知るために、前年の第4回・ボン・サミット(7月16日から17日) 以降、東京サミットが開催された1979年の6月まで1年間に起こった世界的に大きな出来事(国際的問題)等を少し振り返ええりながら、現代の状況がどうなっているを見てみたい。
出来事(1)
1978年(昭和53年)8月12日、日本の園田直外相と、中国(とう) 小平副首相との会談で「尖閣列島(尖閣諸島)」「中ソ関係」に合意が得られ北京で日中平和友好条約の調印式が行われた。(1972年の日中共同声明を踏まえてのもの.。国会承認:10月16日、効力発生:10月23日)。
日本政府は尖閣諸島は日本固有の領土であるとして実効支配をしている。これに対して、1968年に地下資源が発見された頃から、中国と台湾などが領有権を主張しはじめた(南シナ海の領有権問題 参照)。
しかし、尖閣諸島問題は日中共同声明及びその6年後の日中平和友好条約締結(園田外相、(とう)小平)の際にも、「その解決は将来の世代の知恵に待つ」(小平)として「先送り」されて来た。
この時、園田外相が尖閣問題を切出すと、小平は「ああいう事件を再び起こさない」と確約したという。それを信じてこの問題には双方が触れないということで条約を締結したのだが・・・(※3参照)。
今でも日米安保の下、米国に従属している日本。軍事大国化し、ますます覇権主義となりつつある中国。そこに起こっている尖閣諸島問題。
領土問題は今日では、資源問題でもある。かって、は、このような問題は往々にして戦争 (局地的な戦争も含め) によって解決されたものだが・・・。これからどう解決してゆくのだろうか。
日中平和友好条約締結直後の10月25日に来日した折にも、当時の中国の最高実力者小平は記者会見に応じ、その中で、中日友好条約が覇権反対の原則を明確に規定したことの意義を述べており、「中国が将来四つの現代化を実現した強大な国になったときも、決して覇を唱えない。これは毛沢東首席が生前私たちのために定めた国策であり、既に明確に憲法に記入されている」・・・と述べているのだが・・・(※4:「特記すべき記者会見 | 日本記者クラブ」の“小平中国副首相記者会見 1978年10月25日”を参照)。
日中国交回復から35年、経済関係の目覚しい発展にもかかわらず、政治面では摩擦が絶えず、最近は、両国間に相互不信はかつてなく深刻な状況になっている。
出来事(2)
1978年 11月1日、当時、貿易収支の大幅な赤字によって経常収支が赤字に転落し、インフレが加速していた中、米国のカーター大統領はドル下落に歯止めをかけるため、独・日 ・スイスの3カ国と個別に外国為替市場に協調介入することと、公定歩合の1%引き上げと預金準備率引き上げのドル防衛策を発表。
これを受けて翌日ドルは大幅に(1日で10円以上)上昇(逆に円安)。その後も円安・ドル高傾向は続いた(※5参照)‘77年から’78年にかけては第一次の円高時期であった。
日本は、今アベノミクスで、物価下落と不況のデフレ・スパイラルを断ち切るためにインフレ目標(インフレターゲット)を設定し、大胆な金融緩和措置を講じることを掲げ、昨年末より、これを好感し円安、株高に転じていたが、5月23日場中につけた日経平均株価の最高値を境に、急激な円高株安に転じた。
理由は、アベノミクスの「第3の矢」とされる「成長戦略」が事前に報道された内容に留まった上、実現への具体策も乏しいと市場に受け止められ、失望売りが膨らんだとみられた他、アメリカの金融緩和が縮小されるとの観測が広がったこともこの流れを後押ししていた(※6参照)。
市場の予想通り、6月19日、FOMC(米国連邦公開市場委員会)後の記者会見でFRB(米国連邦準備制度理事会)のバーナンキ議長は「QE3(月850億ドルの証券購入策)の縮小を年内に開始し、来年半ばには停止するであろう」と発表した(※7参照)。
今回のバーナンキ議長の発表によって、米国の金融政策の変更がほぼ間違いないことが明確になり、長期金利の上昇傾向が鮮明化した。それをきかっけに、新興国の株式市場が不安定化すると共に、当該国の通貨が軒並み弱含みの状況になっている。
日本にとって重要なことは、安倍首相が明確な成長戦略を打ち出せるか否かであり、それができなければ、期待が失望に変わり、アベノミクスで加速した相場は終焉することになる。しかし、余り具体的な、戦略は見えてこないのだが・・・。
もともと、英国やオーストラリアなどでもインフレ目標を導入しているが、いずれもインフレ抑制のためであり、デフレ対応として導入している国はないという。
インフレ目標を導入し、人為的にインフレを起こした場合に、物価だけが上昇し景気が回復しない(失業率が下がらない)、というスタグフレーション(stagflation)を心配する見方もある。これから先どうなるか楽観はできない。インフレターゲット論への疑問の声も知っておいたほうがよい(※8参照)。
アメリカの金融緩和縮小政策発表により、世界の投資資金が新興国から逃げ出しているとも聞く。世界経済に及ぼす影響も心配である・・・。
出来事(3)
1978年11月2日、東京電力の福島第一原子力発電所3号機で制御棒の脱落による日本最初の臨界事故が発生していたことが後ほどわかったようだ。(【2007年3月まで隠蔽】※9参照)
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による地震動と津波の影響による福島第一原子力発電所で発生した炉心溶融など一連の放射性物質の放出を伴った原子力事故(福島第一原子力発電所事故)は、日本にとって戦後最大の危機であった。
それは日本という国家が成り立つかどうかの瀬戸際の危機だったわけであるが、この東京電力福島第一原発の事故は、孤立した事象ではなく、過去の原発事故の多くが隠蔽されていたのだという。
先に挙げた1978年の臨界事故のような事故ですら、長期間隠蔽されてきた。そして、その結果、事故情報が共有されず、防げたはずの事故が起きている。多くの事故は、取るべき安全対策が取られなかった結果、起きてしまった。まさに人災ともいうべき事故が並んでいる。それでも、原発は安全だという「安全神話」を、原子力村は強引に押し通してきた。これまでのいい加減な対応を見ていると、東京電力福島第一原発のような事故は、遅かれ早かれどこかで起こらざるを得なかったのではないでしょうか。・・・と、自民党の河野太郎氏は自身の公式サイト(※10)で述べている。
そして、これを繰り返さないためには、経営体質の抜本改革が必要です。再稼働するならば経営陣の総退陣と社外取締役のきちんとした選任が必要です。経産大臣に、それができるでしょうか。総理に、それを指示する勇気があるでしょうか。・・・として、過去の事故例等(※9も参照)を挙げ、最後に「総理、あなたは国民を守るのですか、それとも電力会社を守るのですか。」と結んでいるが・・・(※11も参照)。
阿部自民党政権では基本的に原子力発電所は再稼働の方針のようであり、首相自らが率先して経済外交を行い、アラブ首長国連邦やトルコなどへ原発の売り込みなどをしているのだが・・・。
出来事(4)
1979年1月1日 、アメリカ合衆国と中華人民共和国(通称中国)が国交を樹立。このことは最後に述べる。
出来事(5)
1979年2月11日、カリスマ的宗教指導者ホメイニーによるイスラム革命評議会がパーレヴィー(パフラヴィー)皇帝時代の政府(パフラビー王朝)から政権を奪取し、イランが共和国として再生した。(イランにおけるイスラム革命=イラン革命)。
それによる混乱からイランの石油輸出が停滞し、国際需給が逼迫、石油消費国はエネルギー危機(第2次オイルショック)に見舞われることになる。(※5参照)。
この緊迫の度を増した石油情勢についての議論が第5回の東京サミットの最重要課題として行われ、各国が原油輸入の抑制を行うことで一致し, 日本においても、原油輸入抑制を行うとともに、イラン減産分をサウジアラビアを始めとする他の石油輸出国からの輸入で代替するなどの措置をとることで、原油価格は上昇したものの、第一次石油危機時のような消費者による買い占めパニックといった大きな混乱は免れた。
ただこの東京サミットでの経済宣言の中で、以下のように石油の代替えエネルギーとして核燃料の推進が宣言、確認されている。
「われわれは,代替エネルギー源,とりわけ,一層の汚染,特に大気中の二酸化炭素及び硫黄酸化物の増大を防止することに役立つ代替エネルギー源を拡大する必要がある。
今後数十年において原子力発電能力が拡大しなければ,経済成長及び高水準の雇用の達成は困難となろう。これは国民の安全を保障する条件の下に行われなければならない。われわれはこの目的のために協力する。この点に関して、国際原子力機関(IAEA) は中心的役割を果しうる。
われわれは,核燃料の安定供給と核拡散の危険性の極小化に関するボン・サミットにおいて達せられた了解を再確認する。」・・・と。(※2の第5回主要国首脳会議における宣言【経済宣言】を参照)。
この件に関して、私も以前より関心のあったことが、以下参考の※13:「知らないのは日本人だけ? 世界の原発保有国の語られざる本音」に書かれていたので、その要約を以下まとめてみよう。
「2011年5月時点で31カ国が原発を所有していたという。
原発による発電量が最も多い国は米国、フランス、日本、ロシア、韓国、ドイツ、カナダの順であり、この時点で日本は世界で3位となっている。その他を見ると、意外にも旧共産圏に多い。
旧共産圏以外では、トップが中国で1780万トン、これは日本の6730万トンの26,4%である。環境問題に関心が深いとされるスウェーデンが意外にも1670万トンと原発大国になっている反面イギリスが1370万トンと少ない。以外にもG7の一員であるイタリアには原発がない。イタリアはチェルノブイリ原発事故の後に国民投票を行い、原発を廃止したからである。
また、ドイツも緑の党などが強く反対するために、福島原発の事故を受けて、原発の保有が大きな岐路に立たされている。
ある国が原発を所有する理由を明確に知ることは難しいが、原発を持っている国名を列記してみると、その理由がおぼろげながら見えてくるが、原発は国家の安全保障政策に関係しているようだという。
つまり、原子力による発電は原子力の平和利用であるが、ウランを燃焼させることにより生じるプルトニウムは原子爆弾の原料になる。
また、原発を製造しそれを維持する技術は、原爆を製造する技術につながる。原発を持っている国は、何かの際に短時間で原爆を作ることができる。
北朝鮮が原爆の所有にこだわり、それを手にした結果、米国に対して強い立場で交渉できる。この事実は広く知られている。そのために、イランも原爆を欲しがっている。
日本における原発に関する議論にはこの点が取り上げられないことに疑問を感じられる。福島の事故を受けて、今後のエネルギー政策を考える際には、ぜひ、タブーを取り除いて議論すべきであろう。」・・・と。
確かにその面はあるだろう。しかし、ここで述べている環境問題に関心が深いとされるイギリスなどもその後、市場原理重視から原子力推進に転換し、推進の立場を変えてはいないようだが、各国同様の傾向にあるようだ(※14参照)。
日本は、東日本大震災に伴う原発事故によって、電力不足の問題が起こっている。そのため、原発に代わる太陽光や風力などの再生可能な代替エネルギーへの関心が高まっているが、今、アメリカは、次世代エネルギーとして頁岩(シェール)層から採取される天然ガスシェールガスの生産が進み、雇用も生んでいることから、「シェールガス革命」という言葉も飛び交っている(※15参照)。
中東・中南米・中国のほか、これまでロシア(ガスプロム)にLNGを依存してきた欧州でも、大量の埋蔵が確認されており、シェールガスは世界の資源地図を塗り替えるという声もある。
日本でもメタンハイドレートからガスを取り出すことに成功しており、2008年現在、日本近海は世界有数のメタンハイドレート埋蔵量を持つとされており、シェールガス革命がアメリカを再生させたように、メタンハイドレートが衰え気味の日本を再び繁栄させるかもしれない(※16参照)。
一昨日・6月26日の株主総会では原発を持つ9電力会社が原発再稼働を急ぐ姿勢を鮮明にしている。安倍政権が成長戦略で「原発の活用」を打ち出したのを背景に、原発を再び経営の柱に据えようとしているのである。原発への不安を抱えながら「原発依存」をしようとする経営体質の危うさ・・・。
新エネルギーの実用化までには相当な年数を要するだろうが、何時になったら方向転換できるのだろう・・・。
出来事(6)
1979年2月、ベトナム戦争(1965年 - 1975年)が終わり、平和が訪れたかに見えたインドシナに再び戦火が上がった。大量虐殺で知られるカンボジアのポル・ポト政権は1979年の正月早々に、ベトナムの侵攻で打倒され、ポル・ポト体制はベトナム軍の手で解体された。
だが、国連は1979年2月、米中両国の主導でベトナムに侵略者の烙印を押し、全面的な対越制裁を決議、カンボジアを支援していた中国は、2月17日 、ベトナム北部へ軍事侵攻し、国境の都市をあらかた破壊した(中越戦争の勃発)。
折しも、前年ぐらいから華人を中心に急増していたインドシナ難民(海上難民は、ボートピープルと呼ばれる。)がこの戦争を機にピークに達し国際的な問題となっていた(※3も参照)。
社会主義化に伴う資産制限・国有化、また中越戦争による民族的緊張により、1978年前後をピークに大量の華人が移民もしくはボートピープルとしてベトナムから国外に流出した。
こうした大量のベトナム系中国人が国外に脱出した背景には、中越関係悪化の中、ベトナムの経済や流通の中枢を華僑がおさえていたことに対して新政府が危機感をつのらせ、組織的にこれを追放したことがあるからだという。
インドシナ難民問題に関しては、東京サミットで特別声明が出され、 ドイモイ以後、ベトナムに帰還する華人も増え、華人人口は復調傾向にあるようだ。
しかし、万一、核兵器を持ち独裁体制を敷いている北朝鮮が崩壊し、大勢の難民が溢れたとき、日本はじめ周辺国の難民受け入れ体制は十分に、出来ているのであろうか?余り、現実的ではない話であるとは思うが、その危険性をはらんでいる国であることには違いない。
出来事(7)
1979年3月28日、アメリカペンシルベニア州のスリーマイル島(TMI)原子力発電所事故で想定された事故の規模を上回る原子力事故が発生。

●上掲の画像は、スリーマイル島原子力発電所。中央手前の二つのドームが原子炉建屋で、その左隣の白い建物が制御室を含むタービン建屋である。奥に見える二基の塔状構造物は放熱塔(Wikipediaより)
原子炉から1次冷却水が失われ、水面上に露出した炉心が過熱して溶融(炉心溶融)したきわめて深刻な放射能漏れ事故であった(事故の種類としては原子炉冷却材喪失事故 (Loss Of Coolant Accident, LOCA) に分類)。
これは、想定された事故の規模を上回る過酷事故 (Severe Accident) であり、国際原子力事象評価尺度 (INES) におけるレベル5の事例である。
以下参考に記載の※17:「チェルノブイリ・スリーマイル・福島の比較」をみると、
スリーマイル (TMI)は、作業員が非常用冷却系統を誤操作により停止してしまったのが原因(計画自体に不備・実験等の違反)。チェルノブイリの場合は違反した動作試験が行われていた為予期しない運転出力の急上昇により蒸気爆発を起こしたのが原因(人為的な操作ミス【機器の欠陥が事故の発端】)と言われているのに対し、福島原発は想像を超す自然災害(東日本大震災)が原因であったとしている。
しかし、実際には、出来事(3)で書いたように、過去数多くの事故の隠蔽が行われていたようであり中には人為的な操作ミスも含まれている。
つまり、この事故は、原発に対するそれまでの「安全神話」を覆し、アメリカ国内に反原発の機運が高まるきっかけになったばかりでなく、多重安全(日本の場合は多重防護と呼ぶ)設計を施した巨大システムが、ちょっとしたヒューマン・エラーから呆気なく崩壊していくことを示す格好の事例であった(※18参照)。
TMI原発の1つの特徴は、原子炉から4kmの地点にハリスバーグ国際空港があり、飛行機が原子炉に墜落する確率が1年に 10-6を越える点であり、アメリカの基準では、10-6/年以上の確率(「原子炉一基,一年あたり百万分の一回程度の確率」※18参照)を持つ危険性に対しては安全対策を講じることが必要だとされているので、TMI原発は、大型旅客機が墜落しても大丈夫なように、きわめて強固なコンクリート製の原子炉格納容器を有しており、この格納容器が、事故の規模を小さくする上で多少の効果があったとされている。
それに対して、地震大国日本の格納容器はどうなっている・・・?いずれにしても怖い話だ。
さて最後に、出来事(4)の1979年1月の、アメリカと中国の国交を樹立の件である。
第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造である冷戦は、周辺のアジアにも強い影響を与えたが1950年代初頭には、アメリカは共産主義の封じ込みを図っていた。
この1950年代のアメリカの総生産は世界の約4割、金と外貨の保有は約5割に上り、名実共に世界の盟主となっていた。このようなアメリカを中心とするアジア・太平洋の同盟は、戦禍を蒙らずに一人勝ちできたアメリカ経済によって支えられていたといえる。
1953年、スターリンが死去し、冷戦状態が緩和する兆しが見え始めた。同年に朝鮮戦争の休戦が合意され、1955年にはNATOに対抗するワルシャワ条約機構が結成、オーストリアは永世中立が宣言されて東西の緩衝帯となり、連合国軍が撤退した。
またジュネーヴで米ソ英仏の首脳が会談し、ソ連と西ドイツが国交樹立、ソ連は翌1956年に日本とも国交を回復(日ソ共同宣言参照)し、1959年にはフルシチョフがアメリカを訪問するなど、冷戦の「雪どけ」ムードを演出した。
この時期、東側陣営ではソ連の覇権が揺らぎつつあった。フルシチョフは、1956年の第20回ソ連共産党大会でスターリン批判を行ったが、この演説の反響は大きく、ソ連の衛星諸国に大きな衝撃をもたらし、東欧各地で反ソ暴動が起きた。一方、中華人民共和国はスターリン批判に反発した。
1960年代にはキューバ危機や部分的核実験禁止条約でしばしば対立、ダマンスキー島事件などの国境紛争を起こすに至った。
1958年から1962年は、危機の時代であり、米ソは互いを常に「仮想敵国」と想定し、仮想敵国と戦争になった場合の勝利を保障しようと、両国共に勢力の拡大を競い合い、軍備拡張が続いた。
この象徴的な存在が、核兵器開発と宇宙開発競争であった。しかし、ソ連とアメリカの直接衝突は、皮肉にも核の脅威による牽制で発生しなかった。
その一方、第三世界の諸国では、各陣営の支援の元で実際の戦火が上がった。これは、二つの大国の熱い戦争を肩代わりする「、代理戦争」と呼ばれた。
キューバ危機によって核戦争寸前の状況を経験した米ソ両国は、核戦争を回避するという点において共通利益を見出した。この結果、米英ソ3国間で部分的核実験禁止条約、ホットライン協定などが締結された。
しかし、部分的核実験禁止条約には核開発で後れを取っていた中国・フランスが反対し、十数カ国は調印しなかった。
東西共に一枚岩でないことが明白となった。また、地下での核実験は除外されていたため、大国の核開発を抑止する効果は限定的だった。
フランスは1960年2月にサハラ砂漠で最初の核実験を行い、この条約の後の1966年にNATO(北大西洋条約機構)の軍事機構を脱退し、アメリカ・イギリスなどと一定の距離を置く独自の路線を歩むことになった。
また、共産圏の中国も当時、中ソ対立でソ連との対立が深まりつつあり、独自の核開発路線へと向かい、1964年10月に中国初の原爆実験を行った。
この時期、米ソ両国の軍拡競争が進行し、ベトナム戦争を契機とする反戦運動、黒人の公民権運動とそれに対抗する人種差別主義者の対立などによってアメリカ国内は混乱、マーティン・ルーサー・キング牧師やロバート・ケネディなどの要人の暗殺が横行して社会不安に陥った。
第二次世界大戦終結時はアメリカ以外の主要な交戦国は戦災で著しく疲弊していたので、世界の経済規模に対するアメリカの経済規模の比率は突出して大きかったが、戦災から復興した日本や西ドイツが未曾有の経済成長を遂げ、西欧が経済的に復活する中で、世界の経済規模に対するアメリカ合衆国の経済規模の比率は相対的に減少した。
チェコスロバキアはプラハの春と呼ばれる民主化、改革路線を取ったが、ソ連は制限主権論に基づきワルシャワ条約機構軍による軍事介入を行い武力でこれを弾圧した。
アルバニアはスターリン批判以来、中華人民共和国寄りの姿勢を貫いてワルシャワ条約機構を離れ、中華人民共和国はアメリカに近づいてソ連と決別、北朝鮮は主体思想を掲げてソ連から離反するなど、1963年~1968年には冷戦の変容が見られた。
1960年代末からは緊張緩和、いわゆるデタントの時代に突入した。米ソ間で戦略兵器制限交渉 (SALT) を開始、1972年の協定で核兵器の量的削減が行われ、緊張緩和を世界が感じることができた。
このころ、日本では、佐藤栄作内閣が「沖縄返還」を錦の御旗に自衛隊を増強し、非核三原則の拡大解釈や日本国内へのアメリカ軍の各種核兵器の一時的な国内への持ち込みに関する秘密協定など、冷戦下で東側諸国との対峙を続けるアメリカの要求を尊重した政策を遂行し、アジアにおけるアメリカの肩代わりと中国敵視政策でせっせとアメリカの点数稼ぎに懸命であった。
一方、アメリカは、ソ連を牽制すると同時に、密かに水面下で中国との接近を進めていたのである。
1968年アメリカ大統領に当選したニクソン大統領は、大統領補佐官に任命したキッシンジャーと図って、新たな世界戦略をうち建ててベトナム戦争の泥沼から抜け出す道を求めていた。
そして、1972年2月にニクソン大統領が北京を訪問し毛沢東主席と会談した。これは1949年に共産政府が成立して以降、アメリカ大統領の中華人民共和国訪問はこれが最初であった。
アメリカはそれまで蒋介石率いる中華民国を中国大陸を統治する正統な政府として、中国共産党政府を承認していなかったが、この訪問で米中共同宣言を発表し、中国共産党政府を事実上承認し、東アジアにおける冷戦の対立軸であった米中関係が改善するが、国際社会の反応は様々だった。
ソ連は米中和解に深い懸念を示し、新しい世界秩序は米ソデタントに大きく貢献した。また、1973年に北ベトナムとアメリカは和平協定に調印し、アメリカ軍はベトナムから撤退したが、アメリカは建国以来初の敗北を味わうことになった。
その後、ジミー・カーター政権時代の1979年1月にアメリカと中華人民共和国の間で国交が樹立された。
しかし、この米中共同宣言に先立つ1971年7月にニクソン大統領が中華人民共和国訪問を表明した際には、余りにも電撃的な発表であったため世界中があっと驚かされた。
欧州の同盟国の多くとカナダは既に中国を承認していたため歓迎の意向を示した。しかし、アジアの反応はもっと複雑だった。特に日本は発表の内容を直前まで知らされておらず、米国が日本よりも中国を重視することを怖れて非常に強い不快感を示し、日本の政界は対中政策を巡って大混乱に陥る第一次ニクソン・ショックに見舞われた。
ただ日中国交樹立の客観的条件が熟してきたその時に、日中友好を主張する田中角栄内閣が佐藤内閣の総辞職後登場したことは幸いであった。
キッシンジャーが東アジア新秩序構想において日本抜きで事を運ぼうとしていることを察知した日本政府及び田中角栄は、でき得る限り早く日中国交正常化を果たすことを決断。そしてニクソン訪中宣言からわずか1年2ヶ月という異例の早さで田中首相は大平正芳外相とともに北京を訪れ周恩来首相ら中国側と会談し1972年9月29日、日中共同声明(「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」)に持ち込んだ。そして、日中共同声明に基づき、日本はそれまで国交のあった中華民国には断交を通告したのだが・・・。。
ただ、スムーズにいくかと思われたこの会談での交渉は難航したようだ。それは、中国側が共同声明第7項の「反覇権条項」を条約草案に盛り込むことを主張したが、日本側はこれに異議を唱え、以後、「反覇権条項」の取扱いが双方の交渉の対立点となったという(以下参考の※19:「中国と日本」を参照)。
日本は共同声明の第7項では覇権主義反対を書くことに同意しておきながら、なぜ平和友好条約では反覇権条項を入れることに躊躇するのか。それはソ連が日本に圧力をかけ、牽制していることと関係していた。中ソ対立が激しい当時、ソ連は日本が中国と友好関係になるのを恐れた。ソ連は日中両国が反覇権を明記した条約を締結するならば、これに対応する措置として、ソ連は「対日政策を見直すことになろう」と述べたり、海軍を日本近海に出動させて武力威嚇を行ったりしてきた。日本は「日本が中ソ対立に巻き込まれれば、アジアの不安定化と緊張をもたらす」と考え、条約交渉を中断させた。・・・のだという。
福田赳夫政権の下で正式に「日中平和友好条約」が調印されたのは6 年後の1978年8月のことであった。これは、1979年1月にアメリカと中国の間で国交が樹立されるより1年以上も前のことであった。
しかし、今日ある尖閣諸島にかかわる領有権問題は、「日中共同声明」、「平和友好条約」ではっきりさせてこなかったことのつけであり、 また、当時より力を付け世界第2の経済大国であり、また軍事大国となった中国の漁船などが領海侵犯を繰り返してくるのは、「反覇権条項」を「平和友好条約」の中へ入れてこなかったことも大きな要因であるようだ。
そして、今ではアメリカにとって経済力の落ちてきた日本よりも中国の重要性の方が増してきており、尖閣諸島についてアメリカは関知しない、「日中両国の二国間で解決すべき問題」との態度を取り始めた。これから日本はどうするつもりであろう。
この様に、第4回~第5回サミットの期間に発生していた問題などは、その当時から34年経過した現在の日本にとっても、未解決の重要課題が多く関連している事と思いませんか・・・。
(冒頭の画像は1979年6月28日、東京サミットで赤坂の迎賓館の庭を散歩する各国首脳。向かって左から4人目大平首相その隣ジミー・カーター米国大統領。向かって右から2人目マーガレット・サッチャーイギリス首相。Gazouha ,『朝日クロニクル週刊20世紀』1980年号より借用。)
日本で初めて先進国首脳会議(東京サミット)が開催された日:参考へ
冷戦下の1970年代に入り、ニクソン・ショック(ドルの切り下げ)や第1次石油危機(オイルショック参照)などの諸問題に直面した先進国の間では、世界経済問題(マクロ経済、通貨、貿易、エネルギーなど)に対する政策協調について首脳レベルで総合的に議論する場が必要であるとの認識が生まれた。
このような背景の下、ジスカール・デスタン仏大統領(当時)の提案により、1975年11月、パリ郊外のランブイエ城において、日、米、英、仏、独、伊の6か国による第1回首脳会議が開催された。
第2回目の1976年のプエルトリコ会議からはカナダが参加し、1977年の第3回ロンドン会議からは欧州共同体(EC)(現在は欧州連合【EU】)の欧州委員会委員長が参加するようになった。
そして、1978年ボン会議(サミット)(西ドイツ)に続いて、1979年、東京都港区赤坂の迎賓館で第5回東京会議(サミット)が開催された。
第2次石油危機のさなかに開催されたこのサミットでは主要な議題は石油・エネルギーの問題であった。エネルギーの節約、輸入抑制や方法が論議されたが、最終的に各国の輸入制限目標が決められ、日本の場合は、輸入総量を630万バレルから690万バレルの間に抑える(国内からの要求量は700万バレル)、という案で合意した。
インドシナ難民(※3参照)に関する特別声明もだされた。(過去から現代までのサミットでの会議の概要、参加国、関連文書等は以下参考の※1:「外務省HPG7 / G8」の過去のサミット一覧表および※2:「主要国首脳会議関連文書 - 東京大学東洋文化研究所」を参照れるとよい)
ところで、この会議で討議されたたことの背景を知るために、前年の第4回・ボン・サミット(7月16日から17日) 以降、東京サミットが開催された1979年の6月まで1年間に起こった世界的に大きな出来事(国際的問題)等を少し振り返ええりながら、現代の状況がどうなっているを見てみたい。
出来事(1)
1978年(昭和53年)8月12日、日本の園田直外相と、中国(とう) 小平副首相との会談で「尖閣列島(尖閣諸島)」「中ソ関係」に合意が得られ北京で日中平和友好条約の調印式が行われた。(1972年の日中共同声明を踏まえてのもの.。国会承認:10月16日、効力発生:10月23日)。
日本政府は尖閣諸島は日本固有の領土であるとして実効支配をしている。これに対して、1968年に地下資源が発見された頃から、中国と台湾などが領有権を主張しはじめた(南シナ海の領有権問題 参照)。
しかし、尖閣諸島問題は日中共同声明及びその6年後の日中平和友好条約締結(園田外相、(とう)小平)の際にも、「その解決は将来の世代の知恵に待つ」(小平)として「先送り」されて来た。
この時、園田外相が尖閣問題を切出すと、小平は「ああいう事件を再び起こさない」と確約したという。それを信じてこの問題には双方が触れないということで条約を締結したのだが・・・(※3参照)。
今でも日米安保の下、米国に従属している日本。軍事大国化し、ますます覇権主義となりつつある中国。そこに起こっている尖閣諸島問題。
領土問題は今日では、資源問題でもある。かって、は、このような問題は往々にして戦争 (局地的な戦争も含め) によって解決されたものだが・・・。これからどう解決してゆくのだろうか。
日中平和友好条約締結直後の10月25日に来日した折にも、当時の中国の最高実力者小平は記者会見に応じ、その中で、中日友好条約が覇権反対の原則を明確に規定したことの意義を述べており、「中国が将来四つの現代化を実現した強大な国になったときも、決して覇を唱えない。これは毛沢東首席が生前私たちのために定めた国策であり、既に明確に憲法に記入されている」・・・と述べているのだが・・・(※4:「特記すべき記者会見 | 日本記者クラブ」の“小平中国副首相記者会見 1978年10月25日”を参照)。
日中国交回復から35年、経済関係の目覚しい発展にもかかわらず、政治面では摩擦が絶えず、最近は、両国間に相互不信はかつてなく深刻な状況になっている。
出来事(2)
1978年 11月1日、当時、貿易収支の大幅な赤字によって経常収支が赤字に転落し、インフレが加速していた中、米国のカーター大統領はドル下落に歯止めをかけるため、独・日 ・スイスの3カ国と個別に外国為替市場に協調介入することと、公定歩合の1%引き上げと預金準備率引き上げのドル防衛策を発表。
これを受けて翌日ドルは大幅に(1日で10円以上)上昇(逆に円安)。その後も円安・ドル高傾向は続いた(※5参照)‘77年から’78年にかけては第一次の円高時期であった。
日本は、今アベノミクスで、物価下落と不況のデフレ・スパイラルを断ち切るためにインフレ目標(インフレターゲット)を設定し、大胆な金融緩和措置を講じることを掲げ、昨年末より、これを好感し円安、株高に転じていたが、5月23日場中につけた日経平均株価の最高値を境に、急激な円高株安に転じた。
理由は、アベノミクスの「第3の矢」とされる「成長戦略」が事前に報道された内容に留まった上、実現への具体策も乏しいと市場に受け止められ、失望売りが膨らんだとみられた他、アメリカの金融緩和が縮小されるとの観測が広がったこともこの流れを後押ししていた(※6参照)。
市場の予想通り、6月19日、FOMC(米国連邦公開市場委員会)後の記者会見でFRB(米国連邦準備制度理事会)のバーナンキ議長は「QE3(月850億ドルの証券購入策)の縮小を年内に開始し、来年半ばには停止するであろう」と発表した(※7参照)。
今回のバーナンキ議長の発表によって、米国の金融政策の変更がほぼ間違いないことが明確になり、長期金利の上昇傾向が鮮明化した。それをきかっけに、新興国の株式市場が不安定化すると共に、当該国の通貨が軒並み弱含みの状況になっている。
日本にとって重要なことは、安倍首相が明確な成長戦略を打ち出せるか否かであり、それができなければ、期待が失望に変わり、アベノミクスで加速した相場は終焉することになる。しかし、余り具体的な、戦略は見えてこないのだが・・・。
もともと、英国やオーストラリアなどでもインフレ目標を導入しているが、いずれもインフレ抑制のためであり、デフレ対応として導入している国はないという。
インフレ目標を導入し、人為的にインフレを起こした場合に、物価だけが上昇し景気が回復しない(失業率が下がらない)、というスタグフレーション(stagflation)を心配する見方もある。これから先どうなるか楽観はできない。インフレターゲット論への疑問の声も知っておいたほうがよい(※8参照)。
アメリカの金融緩和縮小政策発表により、世界の投資資金が新興国から逃げ出しているとも聞く。世界経済に及ぼす影響も心配である・・・。
出来事(3)
1978年11月2日、東京電力の福島第一原子力発電所3号機で制御棒の脱落による日本最初の臨界事故が発生していたことが後ほどわかったようだ。(【2007年3月まで隠蔽】※9参照)
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による地震動と津波の影響による福島第一原子力発電所で発生した炉心溶融など一連の放射性物質の放出を伴った原子力事故(福島第一原子力発電所事故)は、日本にとって戦後最大の危機であった。
それは日本という国家が成り立つかどうかの瀬戸際の危機だったわけであるが、この東京電力福島第一原発の事故は、孤立した事象ではなく、過去の原発事故の多くが隠蔽されていたのだという。
先に挙げた1978年の臨界事故のような事故ですら、長期間隠蔽されてきた。そして、その結果、事故情報が共有されず、防げたはずの事故が起きている。多くの事故は、取るべき安全対策が取られなかった結果、起きてしまった。まさに人災ともいうべき事故が並んでいる。それでも、原発は安全だという「安全神話」を、原子力村は強引に押し通してきた。これまでのいい加減な対応を見ていると、東京電力福島第一原発のような事故は、遅かれ早かれどこかで起こらざるを得なかったのではないでしょうか。・・・と、自民党の河野太郎氏は自身の公式サイト(※10)で述べている。
そして、これを繰り返さないためには、経営体質の抜本改革が必要です。再稼働するならば経営陣の総退陣と社外取締役のきちんとした選任が必要です。経産大臣に、それができるでしょうか。総理に、それを指示する勇気があるでしょうか。・・・として、過去の事故例等(※9も参照)を挙げ、最後に「総理、あなたは国民を守るのですか、それとも電力会社を守るのですか。」と結んでいるが・・・(※11も参照)。
阿部自民党政権では基本的に原子力発電所は再稼働の方針のようであり、首相自らが率先して経済外交を行い、アラブ首長国連邦やトルコなどへ原発の売り込みなどをしているのだが・・・。
出来事(4)
1979年1月1日 、アメリカ合衆国と中華人民共和国(通称中国)が国交を樹立。このことは最後に述べる。
出来事(5)
1979年2月11日、カリスマ的宗教指導者ホメイニーによるイスラム革命評議会がパーレヴィー(パフラヴィー)皇帝時代の政府(パフラビー王朝)から政権を奪取し、イランが共和国として再生した。(イランにおけるイスラム革命=イラン革命)。
それによる混乱からイランの石油輸出が停滞し、国際需給が逼迫、石油消費国はエネルギー危機(第2次オイルショック)に見舞われることになる。(※5参照)。
この緊迫の度を増した石油情勢についての議論が第5回の東京サミットの最重要課題として行われ、各国が原油輸入の抑制を行うことで一致し, 日本においても、原油輸入抑制を行うとともに、イラン減産分をサウジアラビアを始めとする他の石油輸出国からの輸入で代替するなどの措置をとることで、原油価格は上昇したものの、第一次石油危機時のような消費者による買い占めパニックといった大きな混乱は免れた。
ただこの東京サミットでの経済宣言の中で、以下のように石油の代替えエネルギーとして核燃料の推進が宣言、確認されている。
「われわれは,代替エネルギー源,とりわけ,一層の汚染,特に大気中の二酸化炭素及び硫黄酸化物の増大を防止することに役立つ代替エネルギー源を拡大する必要がある。
今後数十年において原子力発電能力が拡大しなければ,経済成長及び高水準の雇用の達成は困難となろう。これは国民の安全を保障する条件の下に行われなければならない。われわれはこの目的のために協力する。この点に関して、国際原子力機関(IAEA) は中心的役割を果しうる。
われわれは,核燃料の安定供給と核拡散の危険性の極小化に関するボン・サミットにおいて達せられた了解を再確認する。」・・・と。(※2の第5回主要国首脳会議における宣言【経済宣言】を参照)。
この件に関して、私も以前より関心のあったことが、以下参考の※13:「知らないのは日本人だけ? 世界の原発保有国の語られざる本音」に書かれていたので、その要約を以下まとめてみよう。
「2011年5月時点で31カ国が原発を所有していたという。
原発による発電量が最も多い国は米国、フランス、日本、ロシア、韓国、ドイツ、カナダの順であり、この時点で日本は世界で3位となっている。その他を見ると、意外にも旧共産圏に多い。
旧共産圏以外では、トップが中国で1780万トン、これは日本の6730万トンの26,4%である。環境問題に関心が深いとされるスウェーデンが意外にも1670万トンと原発大国になっている反面イギリスが1370万トンと少ない。以外にもG7の一員であるイタリアには原発がない。イタリアはチェルノブイリ原発事故の後に国民投票を行い、原発を廃止したからである。
また、ドイツも緑の党などが強く反対するために、福島原発の事故を受けて、原発の保有が大きな岐路に立たされている。
ある国が原発を所有する理由を明確に知ることは難しいが、原発を持っている国名を列記してみると、その理由がおぼろげながら見えてくるが、原発は国家の安全保障政策に関係しているようだという。
つまり、原子力による発電は原子力の平和利用であるが、ウランを燃焼させることにより生じるプルトニウムは原子爆弾の原料になる。
また、原発を製造しそれを維持する技術は、原爆を製造する技術につながる。原発を持っている国は、何かの際に短時間で原爆を作ることができる。
北朝鮮が原爆の所有にこだわり、それを手にした結果、米国に対して強い立場で交渉できる。この事実は広く知られている。そのために、イランも原爆を欲しがっている。
日本における原発に関する議論にはこの点が取り上げられないことに疑問を感じられる。福島の事故を受けて、今後のエネルギー政策を考える際には、ぜひ、タブーを取り除いて議論すべきであろう。」・・・と。
確かにその面はあるだろう。しかし、ここで述べている環境問題に関心が深いとされるイギリスなどもその後、市場原理重視から原子力推進に転換し、推進の立場を変えてはいないようだが、各国同様の傾向にあるようだ(※14参照)。
日本は、東日本大震災に伴う原発事故によって、電力不足の問題が起こっている。そのため、原発に代わる太陽光や風力などの再生可能な代替エネルギーへの関心が高まっているが、今、アメリカは、次世代エネルギーとして頁岩(シェール)層から採取される天然ガスシェールガスの生産が進み、雇用も生んでいることから、「シェールガス革命」という言葉も飛び交っている(※15参照)。
中東・中南米・中国のほか、これまでロシア(ガスプロム)にLNGを依存してきた欧州でも、大量の埋蔵が確認されており、シェールガスは世界の資源地図を塗り替えるという声もある。
日本でもメタンハイドレートからガスを取り出すことに成功しており、2008年現在、日本近海は世界有数のメタンハイドレート埋蔵量を持つとされており、シェールガス革命がアメリカを再生させたように、メタンハイドレートが衰え気味の日本を再び繁栄させるかもしれない(※16参照)。
一昨日・6月26日の株主総会では原発を持つ9電力会社が原発再稼働を急ぐ姿勢を鮮明にしている。安倍政権が成長戦略で「原発の活用」を打ち出したのを背景に、原発を再び経営の柱に据えようとしているのである。原発への不安を抱えながら「原発依存」をしようとする経営体質の危うさ・・・。
新エネルギーの実用化までには相当な年数を要するだろうが、何時になったら方向転換できるのだろう・・・。
出来事(6)
1979年2月、ベトナム戦争(1965年 - 1975年)が終わり、平和が訪れたかに見えたインドシナに再び戦火が上がった。大量虐殺で知られるカンボジアのポル・ポト政権は1979年の正月早々に、ベトナムの侵攻で打倒され、ポル・ポト体制はベトナム軍の手で解体された。
だが、国連は1979年2月、米中両国の主導でベトナムに侵略者の烙印を押し、全面的な対越制裁を決議、カンボジアを支援していた中国は、2月17日 、ベトナム北部へ軍事侵攻し、国境の都市をあらかた破壊した(中越戦争の勃発)。
折しも、前年ぐらいから華人を中心に急増していたインドシナ難民(海上難民は、ボートピープルと呼ばれる。)がこの戦争を機にピークに達し国際的な問題となっていた(※3も参照)。
社会主義化に伴う資産制限・国有化、また中越戦争による民族的緊張により、1978年前後をピークに大量の華人が移民もしくはボートピープルとしてベトナムから国外に流出した。
こうした大量のベトナム系中国人が国外に脱出した背景には、中越関係悪化の中、ベトナムの経済や流通の中枢を華僑がおさえていたことに対して新政府が危機感をつのらせ、組織的にこれを追放したことがあるからだという。
インドシナ難民問題に関しては、東京サミットで特別声明が出され、 ドイモイ以後、ベトナムに帰還する華人も増え、華人人口は復調傾向にあるようだ。
しかし、万一、核兵器を持ち独裁体制を敷いている北朝鮮が崩壊し、大勢の難民が溢れたとき、日本はじめ周辺国の難民受け入れ体制は十分に、出来ているのであろうか?余り、現実的ではない話であるとは思うが、その危険性をはらんでいる国であることには違いない。
出来事(7)
1979年3月28日、アメリカペンシルベニア州のスリーマイル島(TMI)原子力発電所事故で想定された事故の規模を上回る原子力事故が発生。

●上掲の画像は、スリーマイル島原子力発電所。中央手前の二つのドームが原子炉建屋で、その左隣の白い建物が制御室を含むタービン建屋である。奥に見える二基の塔状構造物は放熱塔(Wikipediaより)
原子炉から1次冷却水が失われ、水面上に露出した炉心が過熱して溶融(炉心溶融)したきわめて深刻な放射能漏れ事故であった(事故の種類としては原子炉冷却材喪失事故 (Loss Of Coolant Accident, LOCA) に分類)。
これは、想定された事故の規模を上回る過酷事故 (Severe Accident) であり、国際原子力事象評価尺度 (INES) におけるレベル5の事例である。
以下参考に記載の※17:「チェルノブイリ・スリーマイル・福島の比較」をみると、
スリーマイル (TMI)は、作業員が非常用冷却系統を誤操作により停止してしまったのが原因(計画自体に不備・実験等の違反)。チェルノブイリの場合は違反した動作試験が行われていた為予期しない運転出力の急上昇により蒸気爆発を起こしたのが原因(人為的な操作ミス【機器の欠陥が事故の発端】)と言われているのに対し、福島原発は想像を超す自然災害(東日本大震災)が原因であったとしている。
しかし、実際には、出来事(3)で書いたように、過去数多くの事故の隠蔽が行われていたようであり中には人為的な操作ミスも含まれている。
つまり、この事故は、原発に対するそれまでの「安全神話」を覆し、アメリカ国内に反原発の機運が高まるきっかけになったばかりでなく、多重安全(日本の場合は多重防護と呼ぶ)設計を施した巨大システムが、ちょっとしたヒューマン・エラーから呆気なく崩壊していくことを示す格好の事例であった(※18参照)。
TMI原発の1つの特徴は、原子炉から4kmの地点にハリスバーグ国際空港があり、飛行機が原子炉に墜落する確率が1年に 10-6を越える点であり、アメリカの基準では、10-6/年以上の確率(「原子炉一基,一年あたり百万分の一回程度の確率」※18参照)を持つ危険性に対しては安全対策を講じることが必要だとされているので、TMI原発は、大型旅客機が墜落しても大丈夫なように、きわめて強固なコンクリート製の原子炉格納容器を有しており、この格納容器が、事故の規模を小さくする上で多少の効果があったとされている。
それに対して、地震大国日本の格納容器はどうなっている・・・?いずれにしても怖い話だ。
さて最後に、出来事(4)の1979年1月の、アメリカと中国の国交を樹立の件である。
第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造である冷戦は、周辺のアジアにも強い影響を与えたが1950年代初頭には、アメリカは共産主義の封じ込みを図っていた。
この1950年代のアメリカの総生産は世界の約4割、金と外貨の保有は約5割に上り、名実共に世界の盟主となっていた。このようなアメリカを中心とするアジア・太平洋の同盟は、戦禍を蒙らずに一人勝ちできたアメリカ経済によって支えられていたといえる。
1953年、スターリンが死去し、冷戦状態が緩和する兆しが見え始めた。同年に朝鮮戦争の休戦が合意され、1955年にはNATOに対抗するワルシャワ条約機構が結成、オーストリアは永世中立が宣言されて東西の緩衝帯となり、連合国軍が撤退した。
またジュネーヴで米ソ英仏の首脳が会談し、ソ連と西ドイツが国交樹立、ソ連は翌1956年に日本とも国交を回復(日ソ共同宣言参照)し、1959年にはフルシチョフがアメリカを訪問するなど、冷戦の「雪どけ」ムードを演出した。
この時期、東側陣営ではソ連の覇権が揺らぎつつあった。フルシチョフは、1956年の第20回ソ連共産党大会でスターリン批判を行ったが、この演説の反響は大きく、ソ連の衛星諸国に大きな衝撃をもたらし、東欧各地で反ソ暴動が起きた。一方、中華人民共和国はスターリン批判に反発した。
1960年代にはキューバ危機や部分的核実験禁止条約でしばしば対立、ダマンスキー島事件などの国境紛争を起こすに至った。
1958年から1962年は、危機の時代であり、米ソは互いを常に「仮想敵国」と想定し、仮想敵国と戦争になった場合の勝利を保障しようと、両国共に勢力の拡大を競い合い、軍備拡張が続いた。
この象徴的な存在が、核兵器開発と宇宙開発競争であった。しかし、ソ連とアメリカの直接衝突は、皮肉にも核の脅威による牽制で発生しなかった。
その一方、第三世界の諸国では、各陣営の支援の元で実際の戦火が上がった。これは、二つの大国の熱い戦争を肩代わりする「、代理戦争」と呼ばれた。
キューバ危機によって核戦争寸前の状況を経験した米ソ両国は、核戦争を回避するという点において共通利益を見出した。この結果、米英ソ3国間で部分的核実験禁止条約、ホットライン協定などが締結された。
しかし、部分的核実験禁止条約には核開発で後れを取っていた中国・フランスが反対し、十数カ国は調印しなかった。
東西共に一枚岩でないことが明白となった。また、地下での核実験は除外されていたため、大国の核開発を抑止する効果は限定的だった。
フランスは1960年2月にサハラ砂漠で最初の核実験を行い、この条約の後の1966年にNATO(北大西洋条約機構)の軍事機構を脱退し、アメリカ・イギリスなどと一定の距離を置く独自の路線を歩むことになった。
また、共産圏の中国も当時、中ソ対立でソ連との対立が深まりつつあり、独自の核開発路線へと向かい、1964年10月に中国初の原爆実験を行った。
この時期、米ソ両国の軍拡競争が進行し、ベトナム戦争を契機とする反戦運動、黒人の公民権運動とそれに対抗する人種差別主義者の対立などによってアメリカ国内は混乱、マーティン・ルーサー・キング牧師やロバート・ケネディなどの要人の暗殺が横行して社会不安に陥った。
第二次世界大戦終結時はアメリカ以外の主要な交戦国は戦災で著しく疲弊していたので、世界の経済規模に対するアメリカの経済規模の比率は突出して大きかったが、戦災から復興した日本や西ドイツが未曾有の経済成長を遂げ、西欧が経済的に復活する中で、世界の経済規模に対するアメリカ合衆国の経済規模の比率は相対的に減少した。
チェコスロバキアはプラハの春と呼ばれる民主化、改革路線を取ったが、ソ連は制限主権論に基づきワルシャワ条約機構軍による軍事介入を行い武力でこれを弾圧した。
アルバニアはスターリン批判以来、中華人民共和国寄りの姿勢を貫いてワルシャワ条約機構を離れ、中華人民共和国はアメリカに近づいてソ連と決別、北朝鮮は主体思想を掲げてソ連から離反するなど、1963年~1968年には冷戦の変容が見られた。
1960年代末からは緊張緩和、いわゆるデタントの時代に突入した。米ソ間で戦略兵器制限交渉 (SALT) を開始、1972年の協定で核兵器の量的削減が行われ、緊張緩和を世界が感じることができた。
このころ、日本では、佐藤栄作内閣が「沖縄返還」を錦の御旗に自衛隊を増強し、非核三原則の拡大解釈や日本国内へのアメリカ軍の各種核兵器の一時的な国内への持ち込みに関する秘密協定など、冷戦下で東側諸国との対峙を続けるアメリカの要求を尊重した政策を遂行し、アジアにおけるアメリカの肩代わりと中国敵視政策でせっせとアメリカの点数稼ぎに懸命であった。
一方、アメリカは、ソ連を牽制すると同時に、密かに水面下で中国との接近を進めていたのである。
1968年アメリカ大統領に当選したニクソン大統領は、大統領補佐官に任命したキッシンジャーと図って、新たな世界戦略をうち建ててベトナム戦争の泥沼から抜け出す道を求めていた。
そして、1972年2月にニクソン大統領が北京を訪問し毛沢東主席と会談した。これは1949年に共産政府が成立して以降、アメリカ大統領の中華人民共和国訪問はこれが最初であった。
アメリカはそれまで蒋介石率いる中華民国を中国大陸を統治する正統な政府として、中国共産党政府を承認していなかったが、この訪問で米中共同宣言を発表し、中国共産党政府を事実上承認し、東アジアにおける冷戦の対立軸であった米中関係が改善するが、国際社会の反応は様々だった。
ソ連は米中和解に深い懸念を示し、新しい世界秩序は米ソデタントに大きく貢献した。また、1973年に北ベトナムとアメリカは和平協定に調印し、アメリカ軍はベトナムから撤退したが、アメリカは建国以来初の敗北を味わうことになった。
その後、ジミー・カーター政権時代の1979年1月にアメリカと中華人民共和国の間で国交が樹立された。
しかし、この米中共同宣言に先立つ1971年7月にニクソン大統領が中華人民共和国訪問を表明した際には、余りにも電撃的な発表であったため世界中があっと驚かされた。
欧州の同盟国の多くとカナダは既に中国を承認していたため歓迎の意向を示した。しかし、アジアの反応はもっと複雑だった。特に日本は発表の内容を直前まで知らされておらず、米国が日本よりも中国を重視することを怖れて非常に強い不快感を示し、日本の政界は対中政策を巡って大混乱に陥る第一次ニクソン・ショックに見舞われた。
ただ日中国交樹立の客観的条件が熟してきたその時に、日中友好を主張する田中角栄内閣が佐藤内閣の総辞職後登場したことは幸いであった。
キッシンジャーが東アジア新秩序構想において日本抜きで事を運ぼうとしていることを察知した日本政府及び田中角栄は、でき得る限り早く日中国交正常化を果たすことを決断。そしてニクソン訪中宣言からわずか1年2ヶ月という異例の早さで田中首相は大平正芳外相とともに北京を訪れ周恩来首相ら中国側と会談し1972年9月29日、日中共同声明(「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」)に持ち込んだ。そして、日中共同声明に基づき、日本はそれまで国交のあった中華民国には断交を通告したのだが・・・。。
ただ、スムーズにいくかと思われたこの会談での交渉は難航したようだ。それは、中国側が共同声明第7項の「反覇権条項」を条約草案に盛り込むことを主張したが、日本側はこれに異議を唱え、以後、「反覇権条項」の取扱いが双方の交渉の対立点となったという(以下参考の※19:「中国と日本」を参照)。
日本は共同声明の第7項では覇権主義反対を書くことに同意しておきながら、なぜ平和友好条約では反覇権条項を入れることに躊躇するのか。それはソ連が日本に圧力をかけ、牽制していることと関係していた。中ソ対立が激しい当時、ソ連は日本が中国と友好関係になるのを恐れた。ソ連は日中両国が反覇権を明記した条約を締結するならば、これに対応する措置として、ソ連は「対日政策を見直すことになろう」と述べたり、海軍を日本近海に出動させて武力威嚇を行ったりしてきた。日本は「日本が中ソ対立に巻き込まれれば、アジアの不安定化と緊張をもたらす」と考え、条約交渉を中断させた。・・・のだという。
福田赳夫政権の下で正式に「日中平和友好条約」が調印されたのは6 年後の1978年8月のことであった。これは、1979年1月にアメリカと中国の間で国交が樹立されるより1年以上も前のことであった。
しかし、今日ある尖閣諸島にかかわる領有権問題は、「日中共同声明」、「平和友好条約」ではっきりさせてこなかったことのつけであり、 また、当時より力を付け世界第2の経済大国であり、また軍事大国となった中国の漁船などが領海侵犯を繰り返してくるのは、「反覇権条項」を「平和友好条約」の中へ入れてこなかったことも大きな要因であるようだ。
そして、今ではアメリカにとって経済力の落ちてきた日本よりも中国の重要性の方が増してきており、尖閣諸島についてアメリカは関知しない、「日中両国の二国間で解決すべき問題」との態度を取り始めた。これから日本はどうするつもりであろう。
この様に、第4回~第5回サミットの期間に発生していた問題などは、その当時から34年経過した現在の日本にとっても、未解決の重要課題が多く関連している事と思いませんか・・・。
(冒頭の画像は1979年6月28日、東京サミットで赤坂の迎賓館の庭を散歩する各国首脳。向かって左から4人目大平首相その隣ジミー・カーター米国大統領。向かって右から2人目マーガレット・サッチャーイギリス首相。Gazouha ,『朝日クロニクル週刊20世紀』1980年号より借用。)
日本で初めて先進国首脳会議(東京サミット)が開催された日:参考へ