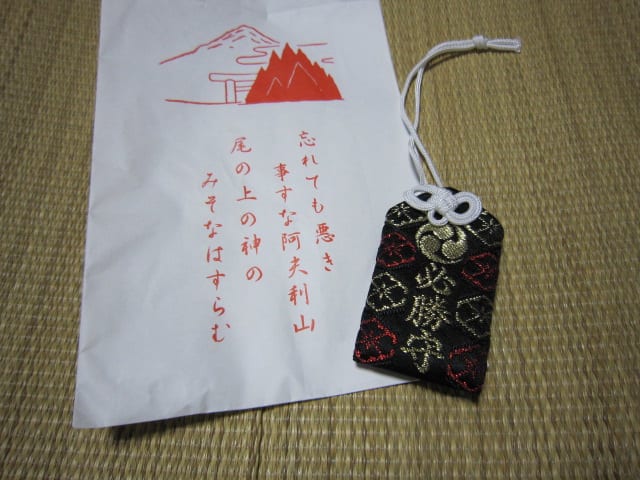最近のニュースから。
今の首相といい、前の首相といい・・・・・。
「何かあたらしいことを」
「今までとは違った考え・行動を」
「今までの慣習・既得権益をなくさねば」
「マニフェストの存在」
などなど、なにか“呪縛霊”みたいなものにかかっているように思える。
「いま何をするか」
「いま何をしなければならないか」
考えてはいるのだろうけど、踏み出せない。踏み出そうとしない。
見えないプレッシャーが、世間というバッシングを警戒するあまりに、特に「痛み」をともなう主義・思想・行動をふさいでしまっている。(もっとのびのびやればいいのに・・・・)
そんな時。
「俺はまだ隠居しないよ」と言わんばかりに“おざわ”さんが、いったん退いていたのに表舞台に出てきた。
おいおいこんな時期にまたまた「政争」かよ。いいかげんに・・・・・・。
しかし、コロコロ変わる「首相」には“ただあきれる”ばかりだが、“おざわ”さんが「もしかしたら・・・・・・・」と思わせるくらい今の政治をなんとかせねばと期待したくなる気もある。
むかし「列島改造論」をぶちかました「コンピューター付きブルトーザー」こと“たなかかくえい”首相が、高度成長著しい日本をさらにさらに押し上げる政策を打って出た。
金権・権力を手玉に・・・・とかダークな部分は残るが、当時の日本に“おおきなチカラ”を与え、その実行力、国を代表してのリーダーシップ、国民からの求心力、魅力あふれるキャラクター・・・・・・・いずれもがいずれもが「今の日本」に必要なものなのではないかと思う。
“たなかかくえい”擁護ではないが、でもすこしでも“すがりたい”くらいに日本は衰退しているような雰囲気・焦燥に包まれている。
この国の行く末がどうなるかの「岐路」にいまたたされている。
「いま何かをしなければ」
「いま何かをしておけば」
だからこそ、日本に“活”をいれる存在感ある人物・起爆剤が必要なのではないだろうか。
ただ、「政争」は早めに切り上げないとすっぽかされるよ。
今の首相といい、前の首相といい・・・・・。
「何かあたらしいことを」
「今までとは違った考え・行動を」
「今までの慣習・既得権益をなくさねば」
「マニフェストの存在」
などなど、なにか“呪縛霊”みたいなものにかかっているように思える。
「いま何をするか」
「いま何をしなければならないか」
考えてはいるのだろうけど、踏み出せない。踏み出そうとしない。
見えないプレッシャーが、世間というバッシングを警戒するあまりに、特に「痛み」をともなう主義・思想・行動をふさいでしまっている。(もっとのびのびやればいいのに・・・・)
そんな時。
「俺はまだ隠居しないよ」と言わんばかりに“おざわ”さんが、いったん退いていたのに表舞台に出てきた。
おいおいこんな時期にまたまた「政争」かよ。いいかげんに・・・・・・。
しかし、コロコロ変わる「首相」には“ただあきれる”ばかりだが、“おざわ”さんが「もしかしたら・・・・・・・」と思わせるくらい今の政治をなんとかせねばと期待したくなる気もある。
むかし「列島改造論」をぶちかました「コンピューター付きブルトーザー」こと“たなかかくえい”首相が、高度成長著しい日本をさらにさらに押し上げる政策を打って出た。
金権・権力を手玉に・・・・とかダークな部分は残るが、当時の日本に“おおきなチカラ”を与え、その実行力、国を代表してのリーダーシップ、国民からの求心力、魅力あふれるキャラクター・・・・・・・いずれもがいずれもが「今の日本」に必要なものなのではないかと思う。
“たなかかくえい”擁護ではないが、でもすこしでも“すがりたい”くらいに日本は衰退しているような雰囲気・焦燥に包まれている。
この国の行く末がどうなるかの「岐路」にいまたたされている。
「いま何かをしなければ」
「いま何かをしておけば」
だからこそ、日本に“活”をいれる存在感ある人物・起爆剤が必要なのではないだろうか。
ただ、「政争」は早めに切り上げないとすっぽかされるよ。