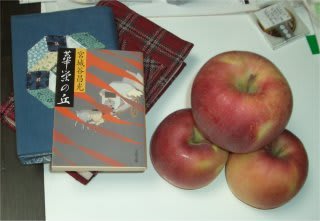かつて大国であった国が、滅亡の淵から小国を立てる。商(殷)が暴虐の王とともに滅び、残された民が立てた国が宋である。強大な二つの国、楚と晋との間にあり、宋王・昭公の死により即位した文公は、襄王夫人の推挙により、華元を右師(右大臣)に任命する。出目で太鼓腹の巨躯を持つ華元は、争いを好まない。先手を打ち勝ちを狙うことをせず、相手に攻めさせて大義を得ることを重視し、見事に防ぎきるタイプだ。乱世とはいえ、戦で何万人も殺すことを常とする将軍や王を主人公とした物語を読んでいると、なんだか殺伐とした気持ちになる。だが、争わず勝とうとせず、義において負けないことを主題とした王と宰相の物語は、いっぷう変わった味わいがある。
文公と華元の信頼関係は、心を打つものがある。華元がとらえられたとき、文公は「わが庫が空になろうとも」華元を救えと命じた。無残な戦国の時代に、こういう話は心洗われるようだ。何度か読み返してなお後味の良い中編である。
剣道や柔道とは異なり、弓道の試合は相手が強いから負けるのではない。相手がいかに強かろうと関係がない。外すのは自分である。勝とうとして勝てるわけではない。淡々として的を外さなければよい、つまり負けなければよいのである。華元の流儀に、ふとそんなことを思った。
自己に苦しみ、徳の薄さを哀しむ士仲に対し、華元は言う。
「徳は、生まれつき、そなわっているものではない。積むものだ。足もとに落ちている塵をだまってひろえ。それでひとつ徳を積んだことになる」
20世紀、道端のゴミ集積所から、ゴミ袋が一つ、邪魔っけに道路に転がっていた。若者は足で道路の端に蹴り寄せる。通り過ぎた後、すれ違ったいきつけの床屋のじいさんが、どっこいしょとそのゴミ袋をあるべき場所に抱え上げていた。四十年前の光景を思い出し、中年となったかつての若者はただ恥じいるばかりである。
文公と華元の信頼関係は、心を打つものがある。華元がとらえられたとき、文公は「わが庫が空になろうとも」華元を救えと命じた。無残な戦国の時代に、こういう話は心洗われるようだ。何度か読み返してなお後味の良い中編である。
剣道や柔道とは異なり、弓道の試合は相手が強いから負けるのではない。相手がいかに強かろうと関係がない。外すのは自分である。勝とうとして勝てるわけではない。淡々として的を外さなければよい、つまり負けなければよいのである。華元の流儀に、ふとそんなことを思った。
自己に苦しみ、徳の薄さを哀しむ士仲に対し、華元は言う。
「徳は、生まれつき、そなわっているものではない。積むものだ。足もとに落ちている塵をだまってひろえ。それでひとつ徳を積んだことになる」
20世紀、道端のゴミ集積所から、ゴミ袋が一つ、邪魔っけに道路に転がっていた。若者は足で道路の端に蹴り寄せる。通り過ぎた後、すれ違ったいきつけの床屋のじいさんが、どっこいしょとそのゴミ袋をあるべき場所に抱え上げていた。四十年前の光景を思い出し、中年となったかつての若者はただ恥じいるばかりである。