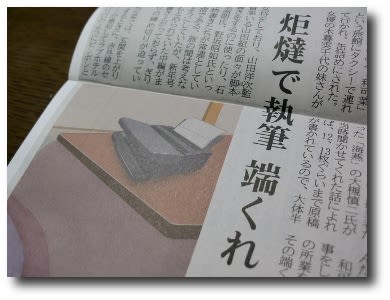先日、26日付けの山形新聞に、佐伯一麦さんの連載記事「Nさんの机で~ものをめぐる文学的自叙伝」の「ワープロとパソコン(4)」が掲載されました。
1992年に新進作家として訪中した帰りに、待ち構えた雑誌の編集者によって、羽田空港からまっすぐ旅館に連れていかれ、カンヅメにされて原稿の完成まで呻吟するという内容です。
ここでもワープロの話題が登場します。縦書き表示ができないために、印刷して様子を確認しなければならないこと、インクリボン代の節約のために感熱紙を使ったことなど、「ああ、そうだった」と懐かしく思い出す方も少なくないことでしょう。
ただし、私が注目したのは、この記事の最後の一節でした。
ふーむ。すると、編集者の石坂氏が用意してくれた同型のワープロには、カットシートフィーダが備わっていた、ということになります。
○
1992年当時、専用ワープロ機にはまだカットシートフィーダは標準装備ではなかったはず。おそらく別売りのものを装着していたのでしょう。当時は、パソコンでも、15インチあるいは11インチの連続用紙にジージーうるさい音をたてて印刷するドットインパクトプリンタがまだ多く使われており、キャノンが発売したバブルジェットの普及タイプ BJ-10v が一般個人にも普及してきた頃でした。私も、これのOEM製品を通じて、カットシートフィーダを導入し、連続用紙とおさらばしたのでした。
さらに数年後には、インクジェットプリンタのスピードに限界を感じ、レーザープリンタの導入に至るわけですが、この頃は、たしかに連続用紙からA4の普通紙へ切り替わっていった時期が、反映していたのかもしれません。
1992年に新進作家として訪中した帰りに、待ち構えた雑誌の編集者によって、羽田空港からまっすぐ旅館に連れていかれ、カンヅメにされて原稿の完成まで呻吟するという内容です。
ここでもワープロの話題が登場します。縦書き表示ができないために、印刷して様子を確認しなければならないこと、インクリボン代の節約のために感熱紙を使ったことなど、「ああ、そうだった」と懐かしく思い出す方も少なくないことでしょう。
ただし、私が注目したのは、この記事の最後の一節でした。
妻子と別居している身の上に触れた「ある帰宅」という作品をどうにか書き上げ、のんびりとプリントアウトしているのを尻目に、石坂氏と近くのうなぎ屋で打ち上げを兼ねた食事をして戻って来ると、ワープロはまだ音を立てて印字を続けているところだった。
ふーむ。すると、編集者の石坂氏が用意してくれた同型のワープロには、カットシートフィーダが備わっていた、ということになります。
○
1992年当時、専用ワープロ機にはまだカットシートフィーダは標準装備ではなかったはず。おそらく別売りのものを装着していたのでしょう。当時は、パソコンでも、15インチあるいは11インチの連続用紙にジージーうるさい音をたてて印刷するドットインパクトプリンタがまだ多く使われており、キャノンが発売したバブルジェットの普及タイプ BJ-10v が一般個人にも普及してきた頃でした。私も、これのOEM製品を通じて、カットシートフィーダを導入し、連続用紙とおさらばしたのでした。
さらに数年後には、インクジェットプリンタのスピードに限界を感じ、レーザープリンタの導入に至るわけですが、この頃は、たしかに連続用紙からA4の普通紙へ切り替わっていった時期が、反映していたのかもしれません。