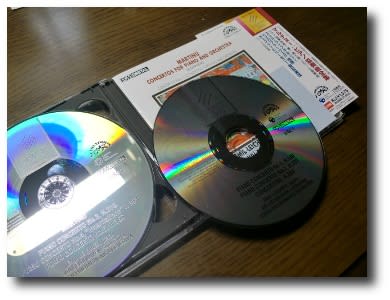作曲家の若い時代の作品は、中期や晩年の代表作と比較すれば、軽く見られがちではありますが、逆にその人らしさを端的に表している場合があります。しばらく前に購入していたCDで、「望郷の作曲家」マルティヌーの若い時代、といっても1890年生まれのマルティヌーが35歳となる1925年の作品、ピアノ協奏曲第1番を聴き、意外なほどの明るさ、新鮮さに驚かされました。
CDは、エミル・ライフネル(Pf)、ビエロフラーヴェク指揮チェコフィルハーモニー管弦楽団の演奏による2枚組で、この曲は1987年の3月に、プラハのルドルフィヌム(芸術家の家)でデジタル録音されたもの(DENON COCO-73026-7)です。
添付リーフレットの解説によれば、1923年に33歳でパリに出たマルティヌーは、故郷のポリチカで夏をすごし、1925年の8月~9月にかけて、この曲を作曲します。1926年に初演されますが、成功を収めたのは、1928年の冬、ルセット・デカーヴのピアノ、ピエルネ指揮コロンヌ交響楽団によるシャルトレ座での演奏会だったそうです。この時以来、たいそうな人気を博し、師匠のルーセルにもほめられたのだとか。たしかに、古典とロマン派と近代とが融合したような作品で、耳に快く、当方のような素人音楽愛好家にもたいへん楽しめるものです。
楽器編成は、Fl(2),Ob(2),Cl(2),Fg(2),Hrn(2),Tp(2),Tb(2),弦楽5部というもので、これなら当地の山響でも演奏可能な規模でしょう。
第1楽章:アレグロ・モデラート、ニ長調、4分の2拍子。この始まりが、剽軽で実に楽しい。ピアノが登場すると、近代的で幻想的な響きをまき散らしながら、自由でリズミカルで気まぐれな動きを見せてくれます。こういう音楽、好きだなあ(^o^)/
第2楽章:アンダンテ、ト短調、8分の6拍子。ピアノソロがたっぷり聴ける緩徐楽章です。メランコリックな面や悲壮な調子もありますが、それよりもむしろ、見事なピアノソロの印象が強い音楽です。
第3楽章:アレグロ、ニ長調、4分の3拍子。どこかにスメタナの「モルダウ」をアレンジしたみたいな旋律が聞こえます。添付リーフレットの解説やWikipediaの解説(*1)には、第2主題がドヴォルザークの歌劇「ルサルカ」の旋律からとられているとありますが、そもそも「ルサルカ」をまともに観て(聴いて)いないのですから何とも言えません。でも、ずいぶん特徴的な、「あれっ」と思う旋律です。もう一つ、カデンツァの見事さにも、一言触れておきましょう。
よく耳になじんだ曲ばかりを聴いてしまいがちな年齢になって、こういう新しいレパートリーを開拓できるのは嬉しい限りです。若さと活力にあふれた音楽を繰り返し聴いていると、思わず自分の年齢を忘れてしまいます(^o^)/
マルティヌーのピアノ協奏曲第1番、なかなかいい曲です。できれば、実演でも一度は聴いてみたいものです。
(*1):マルティヌー「ピアノ協奏曲第1番」~Wikipediaの解説より
(*2):YouTube にもこの曲が upload されていましたが、どうも権利処理が怪しいので、ご紹介はいたしません。

CDは、エミル・ライフネル(Pf)、ビエロフラーヴェク指揮チェコフィルハーモニー管弦楽団の演奏による2枚組で、この曲は1987年の3月に、プラハのルドルフィヌム(芸術家の家)でデジタル録音されたもの(DENON COCO-73026-7)です。
添付リーフレットの解説によれば、1923年に33歳でパリに出たマルティヌーは、故郷のポリチカで夏をすごし、1925年の8月~9月にかけて、この曲を作曲します。1926年に初演されますが、成功を収めたのは、1928年の冬、ルセット・デカーヴのピアノ、ピエルネ指揮コロンヌ交響楽団によるシャルトレ座での演奏会だったそうです。この時以来、たいそうな人気を博し、師匠のルーセルにもほめられたのだとか。たしかに、古典とロマン派と近代とが融合したような作品で、耳に快く、当方のような素人音楽愛好家にもたいへん楽しめるものです。
楽器編成は、Fl(2),Ob(2),Cl(2),Fg(2),Hrn(2),Tp(2),Tb(2),弦楽5部というもので、これなら当地の山響でも演奏可能な規模でしょう。
第1楽章:アレグロ・モデラート、ニ長調、4分の2拍子。この始まりが、剽軽で実に楽しい。ピアノが登場すると、近代的で幻想的な響きをまき散らしながら、自由でリズミカルで気まぐれな動きを見せてくれます。こういう音楽、好きだなあ(^o^)/
第2楽章:アンダンテ、ト短調、8分の6拍子。ピアノソロがたっぷり聴ける緩徐楽章です。メランコリックな面や悲壮な調子もありますが、それよりもむしろ、見事なピアノソロの印象が強い音楽です。
第3楽章:アレグロ、ニ長調、4分の3拍子。どこかにスメタナの「モルダウ」をアレンジしたみたいな旋律が聞こえます。添付リーフレットの解説やWikipediaの解説(*1)には、第2主題がドヴォルザークの歌劇「ルサルカ」の旋律からとられているとありますが、そもそも「ルサルカ」をまともに観て(聴いて)いないのですから何とも言えません。でも、ずいぶん特徴的な、「あれっ」と思う旋律です。もう一つ、カデンツァの見事さにも、一言触れておきましょう。
よく耳になじんだ曲ばかりを聴いてしまいがちな年齢になって、こういう新しいレパートリーを開拓できるのは嬉しい限りです。若さと活力にあふれた音楽を繰り返し聴いていると、思わず自分の年齢を忘れてしまいます(^o^)/
マルティヌーのピアノ協奏曲第1番、なかなかいい曲です。できれば、実演でも一度は聴いてみたいものです。
(*1):マルティヌー「ピアノ協奏曲第1番」~Wikipediaの解説より
(*2):YouTube にもこの曲が upload されていましたが、どうも権利処理が怪しいので、ご紹介はいたしません。