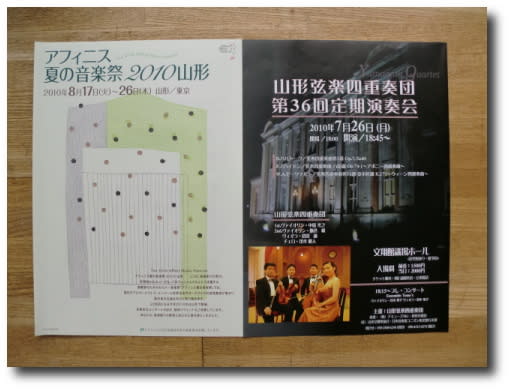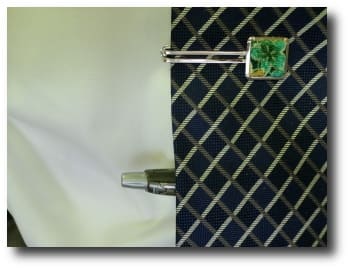作家・藤沢周平の没後十年を機に、故郷の山形新聞社で連載した特集は、たいへん充実したもので、後に単行本としてまとめられました。当ブログでも、すでに記事(*)にしておりますが、このときの筆者陣の一人である蒲生芳郎氏の書き下ろしで、小学館文庫『藤沢周平「海坂藩」の原郷」と題した文庫があることを知りました。著者は、山形師範学校時代の同人雑誌の仲間であり、長く親交のあった友人であるというだけでなく、作家の身近でその半生を知る、深い読み手でもあります。さっそく購入し、先ごろ読み終えましたが、たいへんに充実した、藤沢ファンには必読の書の一つと思います。
本書は、次のような構成からなっています。
I 面影を偲ぶ
1. 藤沢さんの思い出~小菅君の頃から晩年まで
2. 二つの遺墨のあいだ~感性の原点とその回路
II 作品を読む
1. 暗い情念の淵から~初期作品を読む
2. <やさしさ>の泉のようなもの~<癒し>への道筋
3. 「転機の作物」前後~『用心棒日月抄』その他
4. 生活感という真実らしさ~『隠し剣』シリーズと『たそがれ清兵衛』
5. 市井小説の傑作・中年の恋の物語~『海鳴り』を読む
6. 練達の技法と底流する詩情と~『蝉しぐれ』を読む
7. 権力をめぐる光と影~『風の果て』を読む
8. 残照の風景ーその夕映えと陰翳と~『三屋清左衛門残日録』を読む
9. 歴史小説の系譜~『又蔵の火』から『市塵』『白き瓶』を読む
10.『漆の実のみのる国』という美しい幻~『漆の実のみのる国』を読む
著者の本領はどこにあるのかといえば、
(1) 師範学校時代の同人誌『砕氷船』に寄せた、作家の若き日の詩二篇を紹介しつつ、私信に触れながら創作の状況を垣間見せ、
(2) 結核発病により途絶えざるを得なかった愛の存在と再会の悲哀をも教えつつ、
(3) そういう作家の半生を身近に承知しながら読み込まれた作品の理解と紹介、
にあると言えましょう。ここで紹介された代表作を再読するとき、本筋のストーリーとはまた別に、様々なエピソードや表現に気づかされるところが多くあります。藤沢周平作品の入門というよりはむしろ、作家の人間性への理解を深めてくれる最良のガイドの一つというべきでしょう。
(*):『没後十年 藤沢周平読本』を読む~「電網郊外散歩道」2008年8月
本書は、次のような構成からなっています。
I 面影を偲ぶ
1. 藤沢さんの思い出~小菅君の頃から晩年まで
2. 二つの遺墨のあいだ~感性の原点とその回路
II 作品を読む
1. 暗い情念の淵から~初期作品を読む
2. <やさしさ>の泉のようなもの~<癒し>への道筋
3. 「転機の作物」前後~『用心棒日月抄』その他
4. 生活感という真実らしさ~『隠し剣』シリーズと『たそがれ清兵衛』
5. 市井小説の傑作・中年の恋の物語~『海鳴り』を読む
6. 練達の技法と底流する詩情と~『蝉しぐれ』を読む
7. 権力をめぐる光と影~『風の果て』を読む
8. 残照の風景ーその夕映えと陰翳と~『三屋清左衛門残日録』を読む
9. 歴史小説の系譜~『又蔵の火』から『市塵』『白き瓶』を読む
10.『漆の実のみのる国』という美しい幻~『漆の実のみのる国』を読む
著者の本領はどこにあるのかといえば、
(1) 師範学校時代の同人誌『砕氷船』に寄せた、作家の若き日の詩二篇を紹介しつつ、私信に触れながら創作の状況を垣間見せ、
(2) 結核発病により途絶えざるを得なかった愛の存在と再会の悲哀をも教えつつ、
(3) そういう作家の半生を身近に承知しながら読み込まれた作品の理解と紹介、
にあると言えましょう。ここで紹介された代表作を再読するとき、本筋のストーリーとはまた別に、様々なエピソードや表現に気づかされるところが多くあります。藤沢周平作品の入門というよりはむしろ、作家の人間性への理解を深めてくれる最良のガイドの一つというべきでしょう。
(*):『没後十年 藤沢周平読本』を読む~「電網郊外散歩道」2008年8月