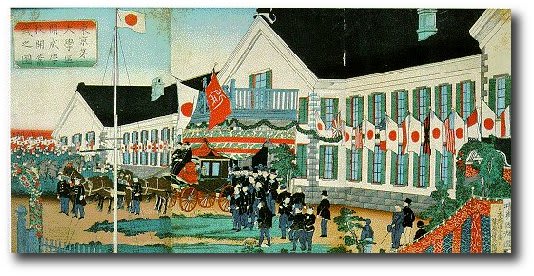三連休の真ん中にあたる日曜日、午前中に剪定枝の処理と「つがる」リンゴの収穫をしてから、午後には天童市の市民プラザ(パルテ3F)の多目的ホールで「初秋を彩るプラザコンサート」を聴きました。山形交響楽団所属の演奏家を中心とする室内楽コンサートです。
プログラムは前半と後半の二部に分かれています。
最初は、フンメルの弦楽三重奏曲第2番ト長調から第1楽章を、蜂谷ゆかり(Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)のトリオで。藤色のドレスでマイクを持った蜂谷さんのお話では、この曲のCDは出ていないのだとか。へぇ~、貴重な機会だったわけですねっ(^o^)/
このあとは、「楽器の彩り」と題して、各奏者がそれぞれの楽器の持ち味を生かした小品を演奏します。
ビゼー:歌劇「アルルの女」より「メヌエット」、山田耕筰:「赤とんぼ」、足達祥治(Fl)、小林路子(Pf)
シューマン:「幻想小曲集」Op.73 第1楽章、渡邊研多郎(Vc)、小林路子(Pf)
ドヴォルザーク:「ユーモレスク」、蜂谷ゆかり(Vn)、小林路子(Pf)
ブルッフ:「ロマンス」、井戸健治(Vla)、小林路子(Pf)
ドビュッシー:「ヒースの茂る荒地」・「雨の庭」、小林路子(Pf)
ビゼーの「メヌエット」は、ふだんはオーケストラの曲として聞きなれていますが、こうしてピアノ伴奏で聴いてみると、フルートの魅力がクローズアップされるようです。
チェロで聴くシューマンは、いいですね~。「ユーモレスク」は軽すぎたかな? と蜂谷さんが懸念していましたが、いえいえ、そんなことはありません。ブルッフはヴィオラ・オリジナルな曲だそうで、いい曲ですね~。もう一つ、マイクを持った井戸さんの声、実はいい声なのですね~。二曲のドビュッシー、大いに楽しみました。

15分の休憩の後、後半は前半で紹介した楽器を組み合わせたプログラムです。
モーツァルト:ピアノ四重奏曲第2番、変ホ長調、第1楽章
小林路子(Pf)、蜂谷ゆかり(Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)。
ピアノがコロコロと明るく活発に。
旬の楽曲の彩り「花は咲く」、「Let It Go」
足達祥治(Fl)、蜂谷ゆかり(Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)。
「花は咲く」はヴィオラの印象的な出だしです。足達さん、実は「アナと雪の女王」をまだ観ていないのだそうで、ちょいと驚きでした(^o^)/
モーツァルト:フルート四重奏曲第1番、ニ長調
足達祥治(Fl)、蜂谷ゆかり(Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)。
明るく活発な第1楽章と、VnとVlaをマンドリンのようにかかえてピツィカートする少々悲しげな第2楽章、そして唐突に明るい調子に戻る第3楽章の組み合わせが不思議な曲だなと思っていましたが、第2楽章は「見込みの薄い」セレナードなのですね(^o^)/
アンコールは、五人そろって「秋の夕日に照る山もみじ~」でした。
○
会場の「パルテ」は、今回初めて行きましたが、駐車場の入り口がわかりにくくて困りました。天童駅隣接のビルなので、本当は電車で行けば便利なのでしょうが、1時間に1本の頻度ではなあ(^o^;)>poripori
プログラムは前半と後半の二部に分かれています。
最初は、フンメルの弦楽三重奏曲第2番ト長調から第1楽章を、蜂谷ゆかり(Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)のトリオで。藤色のドレスでマイクを持った蜂谷さんのお話では、この曲のCDは出ていないのだとか。へぇ~、貴重な機会だったわけですねっ(^o^)/
このあとは、「楽器の彩り」と題して、各奏者がそれぞれの楽器の持ち味を生かした小品を演奏します。
ビゼーの「メヌエット」は、ふだんはオーケストラの曲として聞きなれていますが、こうしてピアノ伴奏で聴いてみると、フルートの魅力がクローズアップされるようです。
チェロで聴くシューマンは、いいですね~。「ユーモレスク」は軽すぎたかな? と蜂谷さんが懸念していましたが、いえいえ、そんなことはありません。ブルッフはヴィオラ・オリジナルな曲だそうで、いい曲ですね~。もう一つ、マイクを持った井戸さんの声、実はいい声なのですね~。二曲のドビュッシー、大いに楽しみました。

15分の休憩の後、後半は前半で紹介した楽器を組み合わせたプログラムです。
小林路子(Pf)、蜂谷ゆかり(Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)。
ピアノがコロコロと明るく活発に。
足達祥治(Fl)、蜂谷ゆかり(Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)。
「花は咲く」はヴィオラの印象的な出だしです。足達さん、実は「アナと雪の女王」をまだ観ていないのだそうで、ちょいと驚きでした(^o^)/
足達祥治(Fl)、蜂谷ゆかり(Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)。
明るく活発な第1楽章と、VnとVlaをマンドリンのようにかかえてピツィカートする少々悲しげな第2楽章、そして唐突に明るい調子に戻る第3楽章の組み合わせが不思議な曲だなと思っていましたが、第2楽章は「見込みの薄い」セレナードなのですね(^o^)/
アンコールは、五人そろって「秋の夕日に照る山もみじ~」でした。
○
会場の「パルテ」は、今回初めて行きましたが、駐車場の入り口がわかりにくくて困りました。天童駅隣接のビルなので、本当は電車で行けば便利なのでしょうが、1時間に1本の頻度ではなあ(^o^;)>poripori