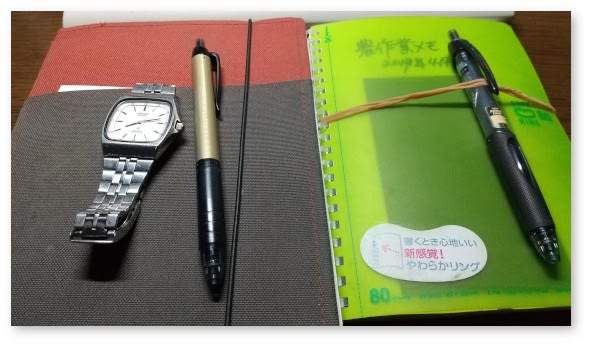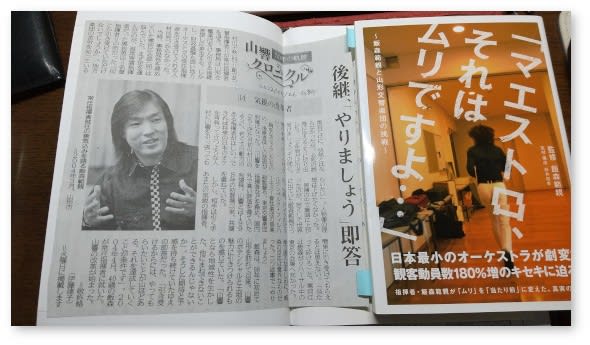私にとっては万年筆・ボールペン・シャープペンシルが筆記具の三大ヒーローで、どれかを持ち歩かないと安心できないほうですが、世の中にはふだん筆記具を持たない人はかなりいるようです。たしかに、役所やお店で申込み書類等にサインをしなければいけないときなど、もともとボールペンが置いてあることがほとんどです。宅配便を受け取るときにも、宅配の人が受け取りサイン用にボールペンを渡してくれます。銀行や郵便局でも、窓口にはボールペンと印肉が置いてあるのが普通でしょう。日常生活で、自分のメモ等の用途がなければ、たしかに筆記具を持たない生活は可能です。別の面から、つまりデジタル化という面からも、メモするよりはスマホのカメラで撮影する流儀の人も少なくないのかもしれません。とすれば、メモ用の筆記具すら必要としていないのかも。
では筆記具の生産量は減少の一途をたどっているのかというと、資料によれば(*1)どうもそうではなさそうで、ボールペン全体としては増えているようなのです。減っているのは、シャープペンシル。これは少子化の影響を受けているのでしょうか。内訳として油性ボールペンは減少気味、またマーカーペンは増加気味のようです。
おそらく、外出時には必ずしも筆記具を持たないけれど、帰宅すると身の回りにはけっこうな数の筆記具がある、というのが実情なのでしょう。あれば、使う。手頃なものとして、ゲル・インクのボールペンが主流になっているのでしょう。
(*1): 筆記具生産量の推移〜日本筆記具工業会
では筆記具の生産量は減少の一途をたどっているのかというと、資料によれば(*1)どうもそうではなさそうで、ボールペン全体としては増えているようなのです。減っているのは、シャープペンシル。これは少子化の影響を受けているのでしょうか。内訳として油性ボールペンは減少気味、またマーカーペンは増加気味のようです。
おそらく、外出時には必ずしも筆記具を持たないけれど、帰宅すると身の回りにはけっこうな数の筆記具がある、というのが実情なのでしょう。あれば、使う。手頃なものとして、ゲル・インクのボールペンが主流になっているのでしょう。
(*1): 筆記具生産量の推移〜日本筆記具工業会