●中三が
昨日、青森市に本社のある百貨店「中三(なかさん)」が30日付で民事再生手続きに入ったことが分かった。負債総額は122億5千万円。
昨日から休業しており、1週間程度で営業を再開するが、4月末で全従業員を解雇。スポンサーの支援を得て、営業再開したい方針。
中三は、1896(明治29)年、現在の五所川原市で創業。(創業地の五所川原店は2006年に閉店)
現在は青森市の本店、弘前店、岩手県の盛岡店の3店舗が、それぞれの中心市街地にある。
一時期イオンと提携しており、その際に秋田市郊外のイオン秋田ショッピングセンター(現イオンモール秋田)に秋田店を出店(1997年)したが、2008年に閉店・撤退している。
商品仕入れは三越と提携しているそうだ。
現在、盛岡店は3月14日に発生した爆発事故を受けて休業中だが、盛岡店も含めた3店舗すべてを存続したい方針。
青森の地場百貨店で現在も残るのは、中三だけ。(「さくら野」も地元百貨店の流れを汲んではいる)
そして老舗だけに、地元の人の信頼や親近感は強い。今日の陸奥新報によれば「津軽地域の住民には「手土産は中三の包装紙かどうかで違う」と言われるほど老舗百貨店として別格の存在。」。(秋田で「木内」の包装でないと…と言われたのと同じだ)
秋田店の撤退などから分かるように以前から中三の経営は思わしくなかったのだろうし、そこに爆発事故と大震災による消費低迷が打撃を与えたようだ。
僕は中三については、弘前市下土手町にある弘前店しか知らない。(秋田店にも行ったことなかった)
土手町は大正時代に東北地方で初めて百貨店ができた街であり、戦後には中三を含めて3つの百貨店があった(中三は1962年開店)という。2つは後に閉店や移転し、土手町に残ったのは中三だけだった。
 毛綱毅曠(もづなきこう)設計の現店舗は1995年完成
毛綱毅曠(もづなきこう)設計の現店舗は1995年完成
土手町のみならず弘前市中心市街地の核となる店舗だから、弘前市民や商工界のショックは大きいだろう。
営業を再開する方針であるのが救いだ。
・「苦して」?
陸奥新報サイトでは、このニュースを知った買い物客の声として「「つぶれればどうするべと苦して来た」」とあるが、「苦して」ってどういう意味?
そんな方言は聞いたことないし、「苦労して」とか「苦しくて」とかの間違いだとしても意味が通らない。どなたか分かりませんか?
【4月2日追記】「苦して」について、皆様からコメントで教えていただきました(コメント欄をご覧ください)。ありがとうございました。
※続きはこちら
●ハイローザ跡地が
中三弘前店の近く、下土手町と一番町付近に、「ドテヒロ」という空き地がある。感覚的には中三のはす向かいかな(実際は離れている)。スクランブル交差点に面した角地で前にバス停がある。
元は上記、東北初の百貨店「かくは宮川」があり(1978年閉店)、1980年から1998年まで「ハイローザ」というファッションビル(?)があった。
ハイローザは閉店後解体されて、弘前商工会議所所有の空き地になり、屋台村のイベントなどが開催されていた。(秋田市の産業会館跡地と同じようなもんだ)
「ドテヒロ」は、その空き地の愛称。
そのドテヒロが、5月にマンション開発業者に売却される見通しであることが先日分かった。29日の陸奥新報によれば「業者は購入した土地に分譲マンションを建設する意向だという。」。
あそこもマンションになってしまうのか。
秋田市広小路の「協働社」跡地がマンションになった時、街の性格が変わってしまったように思え、かつての賑わいはもう戻らない気がした。
ハイローザ跡地もそれと同じようになってしまわないだろうか。
空き地にしておくよりはいいのかもしれないが、土手町と弘前公園の間のあの場所をマンションにしてしまうのはもったいない。
弘前駅前の「ジョッパル(旧ダイエー)」が経営破綻し買い手がつかずに空き屋になっているし、弘前も秋田市中心市街地と同じように、衰退に拍車がかかってしまうのではないかと気がかりだ。
※続きはこちら
昨日、青森市に本社のある百貨店「中三(なかさん)」が30日付で民事再生手続きに入ったことが分かった。負債総額は122億5千万円。
昨日から休業しており、1週間程度で営業を再開するが、4月末で全従業員を解雇。スポンサーの支援を得て、営業再開したい方針。
中三は、1896(明治29)年、現在の五所川原市で創業。(創業地の五所川原店は2006年に閉店)
現在は青森市の本店、弘前店、岩手県の盛岡店の3店舗が、それぞれの中心市街地にある。
一時期イオンと提携しており、その際に秋田市郊外のイオン秋田ショッピングセンター(現イオンモール秋田)に秋田店を出店(1997年)したが、2008年に閉店・撤退している。
商品仕入れは三越と提携しているそうだ。
現在、盛岡店は3月14日に発生した爆発事故を受けて休業中だが、盛岡店も含めた3店舗すべてを存続したい方針。
青森の地場百貨店で現在も残るのは、中三だけ。(「さくら野」も地元百貨店の流れを汲んではいる)
そして老舗だけに、地元の人の信頼や親近感は強い。今日の陸奥新報によれば「津軽地域の住民には「手土産は中三の包装紙かどうかで違う」と言われるほど老舗百貨店として別格の存在。」。(秋田で「木内」の包装でないと…と言われたのと同じだ)
秋田店の撤退などから分かるように以前から中三の経営は思わしくなかったのだろうし、そこに爆発事故と大震災による消費低迷が打撃を与えたようだ。
僕は中三については、弘前市下土手町にある弘前店しか知らない。(秋田店にも行ったことなかった)
土手町は大正時代に東北地方で初めて百貨店ができた街であり、戦後には中三を含めて3つの百貨店があった(中三は1962年開店)という。2つは後に閉店や移転し、土手町に残ったのは中三だけだった。
 毛綱毅曠(もづなきこう)設計の現店舗は1995年完成
毛綱毅曠(もづなきこう)設計の現店舗は1995年完成土手町のみならず弘前市中心市街地の核となる店舗だから、弘前市民や商工界のショックは大きいだろう。
営業を再開する方針であるのが救いだ。
・「苦して」?
陸奥新報サイトでは、このニュースを知った買い物客の声として「「つぶれればどうするべと苦して来た」」とあるが、「苦して」ってどういう意味?
【4月2日追記】「苦して」について、皆様からコメントで教えていただきました(コメント欄をご覧ください)。ありがとうございました。
※続きはこちら
●ハイローザ跡地が
中三弘前店の近く、下土手町と一番町付近に、「ドテヒロ」という空き地がある。感覚的には中三のはす向かいかな(実際は離れている)。スクランブル交差点に面した角地で前にバス停がある。
元は上記、東北初の百貨店「かくは宮川」があり(1978年閉店)、1980年から1998年まで「ハイローザ」というファッションビル(?)があった。
ハイローザは閉店後解体されて、弘前商工会議所所有の空き地になり、屋台村のイベントなどが開催されていた。(秋田市の産業会館跡地と同じようなもんだ)
「ドテヒロ」は、その空き地の愛称。
そのドテヒロが、5月にマンション開発業者に売却される見通しであることが先日分かった。29日の陸奥新報によれば「業者は購入した土地に分譲マンションを建設する意向だという。」。
あそこもマンションになってしまうのか。
秋田市広小路の「協働社」跡地がマンションになった時、街の性格が変わってしまったように思え、かつての賑わいはもう戻らない気がした。
ハイローザ跡地もそれと同じようになってしまわないだろうか。
空き地にしておくよりはいいのかもしれないが、土手町と弘前公園の間のあの場所をマンションにしてしまうのはもったいない。
弘前駅前の「ジョッパル(旧ダイエー)」が経営破綻し買い手がつかずに空き屋になっているし、弘前も秋田市中心市街地と同じように、衰退に拍車がかかってしまうのではないかと気がかりだ。
※続きはこちら










 NHKのサイトより。実際には上の赤いのが先に出る
NHKのサイトより。実際には上の赤いのが先に出る お墓の上でくつろいでいるところに声をかけたら…
お墓の上でくつろいでいるところに声をかけたら… 「ニャんだお前?」
「ニャんだお前?」 左のサバトラさんに、右からキジトラさんが接近。
左のサバトラさんに、右からキジトラさんが接近。 「ちょっと前を失礼しますよ」
「ちょっと前を失礼しますよ」 「このカシャカシャいうヤツは何だべ?」
「このカシャカシャいうヤツは何だべ?」 「なんなんだコレ」
「なんなんだコレ」 歓楽街“川反(かわばた)”周辺にも
歓楽街“川反(かわばた)”周辺にも 水かきにうっすら雪が積もる
水かきにうっすら雪が積もる 正面のお顔
正面のお顔 断面が円のパイプにも、上手に止まっている
断面が円のパイプにも、上手に止まっている また雪が積もった
また雪が積もった 今回は先の方から少し開花していた
今回は先の方から少し開花していた つぼみの頃の方がきれいだった?
つぼみの頃の方がきれいだった? これ
これ 板ごとに色合いがかなり違う
板ごとに色合いがかなり違う 既にちょっとめくれてます
既にちょっとめくれてます 「設置番号3-31」
「設置番号3-31」 脚は7本
脚は7本 状況によって脚を短縮することも
状況によって脚を短縮することも ある公園の入口
ある公園の入口
 90メートルほど先の向かい側にも
90メートルほど先の向かい側にも 「秋田県議会議員一般選挙」の上の線に注目
「秋田県議会議員一般選挙」の上の線に注目 こちらはインクが隣の板に少し移ってしまっている
こちらはインクが隣の板に少し移ってしまっている 縦線がない
縦線がない この掲示場
この掲示場


 参考までにイトーヨーカドー時代
参考までにイトーヨーカドー時代 現在
現在 南東側から
南東側から 後ろ姿。塗り直したものだけどピカピカ
後ろ姿。塗り直したものだけどピカピカ リラガラス右上!
リラガラス右上! 「NB/社団法人日本バフ/会員」?
「NB/社団法人日本バフ/会員」? 羽後交通本荘営業所のバス
羽後交通本荘営業所のバス 中央交通のバスにも、同じものが貼られている
中央交通のバスにも、同じものが貼られている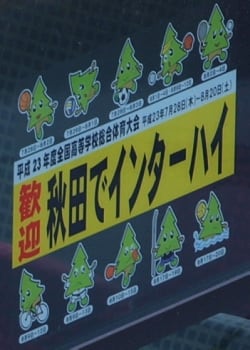 「歓迎 秋田でインターハイ」
「歓迎 秋田でインターハイ」 真っ白
真っ白 歩道橋の階段にも積雪
歩道橋の階段にも積雪 「OK」(本当の送信アンテナはこんな形ではないらしいです)
「OK」(本当の送信アンテナはこんな形ではないらしいです) 「W」
「W」 こんな感じ(午前の遅い時間帯)
こんな感じ(午前の遅い時間帯) 雪があった!
雪があった! !
!
 秋田市立中央図書館「明徳館」
秋田市立中央図書館「明徳館」 正面玄関
正面玄関 「危険 地面が陥没しています」
「危険 地面が陥没しています」

 側面から
側面から 予定なし
予定なし お休み中
お休み中 外から見た限りでは以前と変りない
外から見た限りでは以前と変りない 「地震の為3月31日まで休業させていただきます」
「地震の為3月31日まで休業させていただきます」 3月14日、東側(秋田駅側)
3月14日、東側(秋田駅側) 北側のぽぽろーど側には壁面に表示がある
北側のぽぽろーど側には壁面に表示がある 秋田駅から見るとこうなる
秋田駅から見るとこうなる 南側と東側
南側と東側 分かりづらいですが北側と西側
分かりづらいですが北側と西側 JR東日本秋田支社前 屋内は停電し、2階の窓が開いている
JR東日本秋田支社前 屋内は停電し、2階の窓が開いている 「アルス」前
「アルス」前 「トピコ」2階のぽぽろーど側入口
「トピコ」2階のぽぽろーど側入口 復旧作業中の様子(14日の記事の再掲)
復旧作業中の様子(14日の記事の再掲) ぽぽろーどのつなぎ目も
ぽぽろーどのつなぎ目も 大屋根下。左がフォンテ、右奥が西武
大屋根下。左がフォンテ、右奥が西武 整列
整列 ゆうちょ銀行秋田支店前
ゆうちょ銀行秋田支店前 この箱の中に発電機
この箱の中に発電機



