【2020年9月17日訂正・この記事で取り上げる2つの標識について、誤解がありました。2つは規制内容が異なる点もあり、同一視はできません。以下、初回アップ時のままの内容ですので、こちらの記事を併せてご覧ください。】
約10年前、2010年末の記事で、「歩行者専用」の規制標識を取り上げた。
秋田ではほとんど見ない標識で、その新品に近いもので、しかも若干の矛盾がある設置方法であった。
当時は場所を明言しなかったようだが、仲小路の西端、みずほ銀行と産業会館跡地の間に設置されている。現在も状況は変わっていない。
 現在の姿。若干汚れているが破損などはない
現在の姿。若干汚れているが破損などはない
県によってはそうでないデザインのものもあるが、標準的なクネクネっとしたラインの親子のシルエット。
下には「自転車を除く」の補助標識。だったら「自転車及び歩行者専用」の標識を設置すればいいのではと思ってしまうが、これは歩行者が最優先であり、自転車は気をつけて通ってほしいという意図【29日補足・例外的に通行を認めているような意味合い】があるのだと考えられる。秋田県外ではアーケード商店街などで同様の設置例がある。
ここでおかしかったのは、これが設置されているのが道路左側で、その右側(宝くじ売り場付近)には「自転車及び歩行者専用」標識が設置されていることだった。
言っていることはほぼ同じだが、図柄が違うのは混乱を招くし、厳密には自転車以外の軽車両が通れなかったり/通れたりして矛盾している。
※道路交通法における「自転車で通れる/通れない」は、「自転車に乗って」通行することを指すので、以下それに従います。自転車を降りて押して通る場合は歩行者扱いです。
右側の「自転車及び歩行者専用」は、仲小路が昭和末に整備された時、県警が設置したもので、この逆側にも設置されている。
一方、「歩行者専用」は、見るからに新しく、ここ1か所にしか設置されていなかった。管理者を示すシールなどはなかった(今回再確認済み)。
そして、この標識は、警察も道路管理者(ここの場合秋田市)もどちらでも設置できることになっている。憶測だが、「歩行者専用」は秋田市が設置したもので、警察側と連携が取れていないのかなと考えていた。
秋田市内でここ以外で知る「歩行者専用」は、広面(と柳田)の秋田大学医学部向かいだけだった。古そうなものが複数枚あり、これは県警設置。
ただ、これは秋田県警でよく見られるのだが、一本道のこちら端とあちら端で、設置されている標識や補助標識が統一されておらず、厳密に従えば片方向は自転車で通れるのに、逆方向はダメというものだった。
【29日追記】記事にしたのにもう1か所あったのを忘れていた。八橋運動公園を抜ける市道の、歩道を自転車が通行できる旨の標識で、2012年の県警設置と思われるもの。片方向・1枚のみ。
以上を踏まえて。
高陽青柳町は、秋田市中央部、新国道と八橋の間にある住宅街。細い道路が碁盤の目のように(等間隔でなく、行き止まりもあるけど)張り巡らされている。その1つ。
 「歩行者専用」発見!
「歩行者専用」発見!
この辺りの道路の中には「自転車及び歩行者専用」規制はいくつもあったはずだけど、歩行者専用はあったっけ? 見た感じ標識本体も支柱も新しそう。
 ピカピカ
ピカピカ
図柄や反射材は、仲小路と同一と思われる。
補助標識は「規制区間内住民の関係車両を除く」。補助標識のフォントは異なり「自転車を除く」は写研ナール、こちらは平成丸ゴシック体かな?
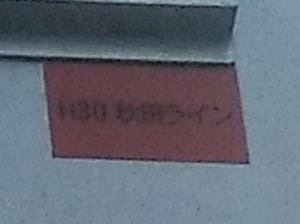 裏面。分かりづらいですが「H30」
裏面。分かりづらいですが「H30」
このシールが貼ってあると警察発注の可能性が高い。2018年設置だ。
以前はどうだったか、Googleストリートビューで確認。
 左が2018年7月、右が2017年4月
左が2018年7月、右が2017年4月
以前は補助標識なしの「自転車及び歩行者専用」。警察管轄で間違いないと思う(以下、それで話を進めます)。
2018年7月の画像では、民家の植木に倒れかかっているようなので、交換されたのだろう。
なお、ストリートビュー撮影車は、標識に従って道路内には進入していなかった。
標識と補助標識を厳格に守れば、以前は住民であっても車では一切通れなかったことになるし、交換後現在は住民以外は自転車で通行できないことになる。これらは常識的にあり得ない。【29日追記・旧標識時代も当初は「区間内住民を除く」の補助標識があったのに、なくなってしまった可能性がある。現在のものは、本標識の内容が変わったのにも関わらず、その補助標識は以前と同じものにしてしまったのだと考えられる。】
そして、ここは細い道路といえば細いが、近くの他の道も似たようなもんだし、特段主要な通学路とかいうわけでもないだろう(ここは学区のほぼ端)。どうして歩行者専用に変わったのか。
秋田市内では古い「自転車及び歩行者専用」の交換はほぼまったく実施されていない。久々に更新の必要が生じたのを機に、より歩行者を守るために変えたのだろうか。【29日補足・そしてその際に、補助標識の文言の見直しが不十分であったことになろう。】
この道は一方通行ではない。では、この区間の反対側の端はどうなっているか?
たどってみると、先日の秋田スズキのお隣、新国道モール(いとく)の駐車場の裏面に突き当たる。駐車場の出入り口側も微妙ながら公道の扱いらしく、小さな十字路になっている。
 何もない!
何もない!
ストリートビューでは、
 2018年7月
2018年7月
今は空き地のところに「売物件」の家があり、その塀際というかその民家の敷地内に「規制区間内住民の関係車両を除く」補助標識付きの「自転車及び歩行者専用」が立っていた。
おそらく、民家の解体に合わせて撤去され、後で設置するつもりが…なのだろう(秋田県警なのか秋田中央警察署なのか、こういうのがままある)。
そして、どちら方向に進む時でも同じ規制が適用されているはずなのに、以前と現在を比べても、反対側と比べても、一致していない問題がある。
【29日補足】標識に厳密に従うと、車両の種類ごとに以前/現状では、
自転車:両方向通行可/西進のみ可(東進は住民のみ)、規制区間内住民の車:西進のみ可/両方向通行可、よそ者の車:通行不可/西進は可能
となる。本来は、自動車は地域住民だけ通らせ、歩行者自転車に開放させたくて実施した規制[自転車:両方向可、住民の車:両方向可、よそ者車:不可]のはずだが、以前も現在も、標識の不備のせいで意味が分からなくなっている。(以上追記)
現状では、スズキ裏側から来て右折しようとする車向けには、指定方向外進行禁止の標識があってかろうじて伝わるが、いとく駐車場から直進、旧国道側から左折する車向けには、その類の標識がないので、この区間に進入してもとがめることはできない。通り放題。
これで万一事故になったら…
・新国道(いとく裏)側入口への標識設置(仮設ででも)。
・「歩行者専用」側に、自転車は通れる旨の補助標識が必要ではないか。
は提案したほうがいいと思うのだが、あえてここを選んで通る人も車も少ないと思われる道だし、明らかな危険は少なそう(むしろ近くの幼稚園前とかのほうが怖い)。僕も、もしかしたら今回初めて通ったかもしれない。本当に危ないなら、町内会が要望したり立て看板を置いたりしそうだし、よそ者がとやかく言うのもはばかられてしまう【6月2日補足・つまり、矛盾していたとしても、地元の人たちはそれが暗黙の了解で合意形成されている、みたいなことになっていたとしたら、それをよそ者が壊すことになる】。
ここ以外の各所で統一されていない補助標識の見直しを進めるべきだとも思うが、秋田県警はそのことは把握しているのか、必要性を感じているのか。
※2021年になって、矛盾は解消した。
約10年前、2010年末の記事で、「歩行者専用」の規制標識を取り上げた。
秋田ではほとんど見ない標識で、その新品に近いもので、しかも若干の矛盾がある設置方法であった。
当時は場所を明言しなかったようだが、仲小路の西端、みずほ銀行と産業会館跡地の間に設置されている。現在も状況は変わっていない。
 現在の姿。若干汚れているが破損などはない
現在の姿。若干汚れているが破損などはない県によってはそうでないデザインのものもあるが、標準的なクネクネっとしたラインの親子のシルエット。
下には「自転車を除く」の補助標識。だったら「自転車及び歩行者専用」の標識を設置すればいいのではと思ってしまうが、これは歩行者が最優先であり、自転車は気をつけて通ってほしいという意図【29日補足・例外的に通行を認めているような意味合い】があるのだと考えられる。秋田県外ではアーケード商店街などで同様の設置例がある。
ここでおかしかったのは、これが設置されているのが道路左側で、その右側(宝くじ売り場付近)には「自転車及び歩行者専用」標識が設置されていることだった。
言っていることはほぼ同じだが、図柄が違うのは混乱を招くし、厳密には自転車以外の軽車両が通れなかったり/通れたりして矛盾している。
※道路交通法における「自転車で通れる/通れない」は、「自転車に乗って」通行することを指すので、以下それに従います。自転車を降りて押して通る場合は歩行者扱いです。
右側の「自転車及び歩行者専用」は、仲小路が昭和末に整備された時、県警が設置したもので、この逆側にも設置されている。
一方、「歩行者専用」は、見るからに新しく、ここ1か所にしか設置されていなかった。管理者を示すシールなどはなかった(今回再確認済み)。
そして、この標識は、警察も道路管理者(ここの場合秋田市)もどちらでも設置できることになっている。憶測だが、「歩行者専用」は秋田市が設置したもので、警察側と連携が取れていないのかなと考えていた。
秋田市内でここ以外で知る「歩行者専用」は、広面(と柳田)の秋田大学医学部向かいだけだった。古そうなものが複数枚あり、これは県警設置。
ただ、これは秋田県警でよく見られるのだが、一本道のこちら端とあちら端で、設置されている標識や補助標識が統一されておらず、厳密に従えば片方向は自転車で通れるのに、逆方向はダメというものだった。
【29日追記】記事にしたのにもう1か所あったのを忘れていた。八橋運動公園を抜ける市道の、歩道を自転車が通行できる旨の標識で、2012年の県警設置と思われるもの。片方向・1枚のみ。
以上を踏まえて。
高陽青柳町は、秋田市中央部、新国道と八橋の間にある住宅街。細い道路が碁盤の目のように(等間隔でなく、行き止まりもあるけど)張り巡らされている。その1つ。
 「歩行者専用」発見!
「歩行者専用」発見!この辺りの道路の中には「自転車及び歩行者専用」規制はいくつもあったはずだけど、歩行者専用はあったっけ? 見た感じ標識本体も支柱も新しそう。
 ピカピカ
ピカピカ図柄や反射材は、仲小路と同一と思われる。
補助標識は「規制区間内住民の関係車両を除く」。補助標識のフォントは異なり「自転車を除く」は写研ナール、こちらは平成丸ゴシック体かな?
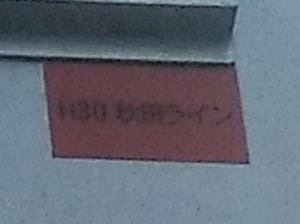 裏面。分かりづらいですが「H30」
裏面。分かりづらいですが「H30」このシールが貼ってあると警察発注の可能性が高い。2018年設置だ。
以前はどうだったか、Googleストリートビューで確認。
 左が2018年7月、右が2017年4月
左が2018年7月、右が2017年4月以前は補助標識なしの「自転車及び歩行者専用」。警察管轄で間違いないと思う(以下、それで話を進めます)。
2018年7月の画像では、民家の植木に倒れかかっているようなので、交換されたのだろう。
なお、ストリートビュー撮影車は、標識に従って道路内には進入していなかった。
標識と補助標識を厳格に守れば、以前は住民であっても車では一切通れなかったことになるし、交換後現在は住民以外は自転車で通行できないことになる。これらは常識的にあり得ない。【29日追記・旧標識時代も当初は「区間内住民を除く」の補助標識があったのに、なくなってしまった可能性がある。現在のものは、本標識の内容が変わったのにも関わらず、その補助標識は以前と同じものにしてしまったのだと考えられる。】
そして、ここは細い道路といえば細いが、近くの他の道も似たようなもんだし、特段主要な通学路とかいうわけでもないだろう(ここは学区のほぼ端)。どうして歩行者専用に変わったのか。
秋田市内では古い「自転車及び歩行者専用」の交換はほぼまったく実施されていない。久々に更新の必要が生じたのを機に、より歩行者を守るために変えたのだろうか。【29日補足・そしてその際に、補助標識の文言の見直しが不十分であったことになろう。】
この道は一方通行ではない。では、この区間の反対側の端はどうなっているか?
たどってみると、先日の秋田スズキのお隣、新国道モール(いとく)の駐車場の裏面に突き当たる。駐車場の出入り口側も微妙ながら公道の扱いらしく、小さな十字路になっている。
 何もない!
何もない!ストリートビューでは、
 2018年7月
2018年7月今は空き地のところに「売物件」の家があり、その塀際というかその民家の敷地内に「規制区間内住民の関係車両を除く」補助標識付きの「自転車及び歩行者専用」が立っていた。
おそらく、民家の解体に合わせて撤去され、後で設置するつもりが…なのだろう(秋田県警なのか秋田中央警察署なのか、こういうのがままある)。
そして、どちら方向に進む時でも同じ規制が適用されているはずなのに、以前と現在を比べても、反対側と比べても、一致していない問題がある。
【29日補足】標識に厳密に従うと、車両の種類ごとに以前/現状では、
自転車:両方向通行可/西進のみ可(東進は住民のみ)、規制区間内住民の車:西進のみ可/両方向通行可、よそ者の車:通行不可/西進は可能
となる。本来は、自動車は地域住民だけ通らせ、歩行者自転車に開放させたくて実施した規制[自転車:両方向可、住民の車:両方向可、よそ者車:不可]のはずだが、以前も現在も、標識の不備のせいで意味が分からなくなっている。(以上追記)
現状では、スズキ裏側から来て右折しようとする車向けには、指定方向外進行禁止の標識があってかろうじて伝わるが、いとく駐車場から直進、旧国道側から左折する車向けには、その類の標識がないので、この区間に進入してもとがめることはできない。通り放題。
これで万一事故になったら…
・新国道(いとく裏)側入口への標識設置(仮設ででも)。
・「歩行者専用」側に、自転車は通れる旨の補助標識が必要ではないか。
は提案したほうがいいと思うのだが、あえてここを選んで通る人も車も少ないと思われる道だし、明らかな危険は少なそう(むしろ近くの幼稚園前とかのほうが怖い)。僕も、もしかしたら今回初めて通ったかもしれない。本当に危ないなら、町内会が要望したり立て看板を置いたりしそうだし、よそ者がとやかく言うのもはばかられてしまう【6月2日補足・つまり、矛盾していたとしても、地元の人たちはそれが暗黙の了解で合意形成されている、みたいなことになっていたとしたら、それをよそ者が壊すことになる】。
ここ以外の各所で統一されていない補助標識の見直しを進めるべきだとも思うが、秋田県警はそのことは把握しているのか、必要性を感じているのか。
※2021年になって、矛盾は解消した。










 いとく側から。奥が土崎方向
いとく側から。奥が土崎方向 2017年8月撮影Googleストリートビューより。上の写真と同じ方向
2017年8月撮影Googleストリートビューより。上の写真と同じ方向 2017年8月ストリートビューより。北側から
2017年8月ストリートビューより。北側から 交差点越しに
交差点越しに 2019年12月。北側角に建物が建っている
2019年12月。北側角に建物が建っている 新国道に対して斜めに建つ
新国道に対して斜めに建つ 「仮店舗営業中」とあるがプレオープン直前で引っ越し済み
「仮店舗営業中」とあるがプレオープン直前で引っ越し済み 解体に入る直前
解体に入る直前

 2種類 ※ラップ越しですみません
2種類 ※ラップ越しですみません

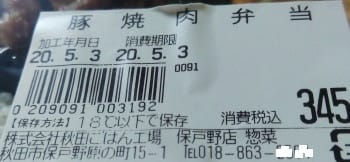
 4月中旬、通過する列車後部から撮影。左が謎の建物、奥が土崎方向
4月中旬、通過する列車後部から撮影。左が謎の建物、奥が土崎方向 上の写真とは逆・土崎側から
上の写真とは逆・土崎側から 秋田寄り。ここが端?
秋田寄り。ここが端? こちらは基礎だけで床はまだ
こちらは基礎だけで床はまだ 外旭川側。奥左右が歩行者自転車道と線路
外旭川側。奥左右が歩行者自転車道と線路 2019年12月末
2019年12月末 現在。向こうに上りホームが見える
現在。向こうに上りホームが見える 2019年12月初め
2019年12月初め 1月上旬。地下道の壁を撤去して穴を広げて、順次、鉄骨を入れて、
1月上旬。地下道の壁を撤去して穴を広げて、順次、鉄骨を入れて、 2月上旬。地中に足場が組まれた
2月上旬。地中に足場が組まれた 現在
現在
 地上に出っ張り。向こうに下りホーム
地上に出っ張り。向こうに下りホーム 背後が線路
背後が線路 泉ハイタウン線バス通りの押しボタン信号付近から。左はスーパードラッグアサヒの裏面
泉ハイタウン線バス通りの押しボタン信号付近から。左はスーパードラッグアサヒの裏面 スナックサンド 秋田名物いぶりがっこ 1個108kcal 食塩相当量0.68g
スナックサンド 秋田名物いぶりがっこ 1個108kcal 食塩相当量0.68g いぶりがっこは細かめに刻まれている
いぶりがっこは細かめに刻まれている (再掲)城バス停
(再掲)城バス停 (再掲)共用タイプになった。広告はバスロケもどきに移設
(再掲)共用タイプになった。広告はバスロケもどきに移設 円形表示板に
円形表示板に
 (いずれも再掲)
(いずれも再掲)

 中通二丁目、影のほうが分かりやすいかも
中通二丁目、影のほうが分かりやすいかも かおる堂 アマビエ練り切り
かおる堂 アマビエ練り切り 横からだと髪が分かるが、アマビエにしては毛量少なめ?
横からだと髪が分かるが、アマビエにしては毛量少なめ? ラベルの商品名は「妖怪アマビエ」
ラベルの商品名は「妖怪アマビエ」 アマビエ諸越(もろこし) ※こちらの商品には「妖怪」なし
アマビエ諸越(もろこし) ※こちらの商品には「妖怪」なし もろこしと練り切り
もろこしと練り切り アマビエシールの大福?
アマビエシールの大福? 「アマビエ 力餅」 ※カタカナのカじゃなくて「アマビエちからもち」
「アマビエ 力餅」 ※カタカナのカじゃなくて「アマビエちからもち」 いかにもCGのアマビエの横顔。紫色印刷なのは意味があるのか?
いかにもCGのアマビエの横顔。紫色印刷なのは意味があるのか? 正門~グラウンドの横にかけてハクモクレン並木
正門~グラウンドの横にかけてハクモクレン並木 逆光です
逆光です たわわに咲く
たわわに咲く 枝垂れ桜が咲き乱れる一角
枝垂れ桜が咲き乱れる一角 その向こうがハクモクレン並木
その向こうがハクモクレン並木 赤紫色の花が遅れて咲いた
赤紫色の花が遅れて咲いた この木もやや不格好で、中ほどの枝が枯れている
この木もやや不格好で、中ほどの枝が枯れている 奥がハミングロードの枝垂れ桜エリア。ほぼ葉桜
奥がハミングロードの枝垂れ桜エリア。ほぼ葉桜
 (再掲)LEDは点灯しなくなった。フォントはどちらもスーラ?
(再掲)LEDは点灯しなくなった。フォントはどちらもスーラ?
 2019年10月撮影。下り側
2019年10月撮影。下り側 共用タイプ
共用タイプ 交換後の上り側。こちらは元バスロケで通風口がある
交換後の上り側。こちらは元バスロケで通風口がある 上り側西面
上り側西面 下り側東面
下り側東面 2010年頃撮影
2010年頃撮影 上り側。更新前
上り側。更新前 2010年撮影
2010年撮影 (再掲)信号機の地点名表示はナール。ただし「王」を上下逆に貼っている
(再掲)信号機の地点名表示はナール。ただし「王」を上下逆に貼っている これは下り側
これは下り側 (再掲)上り側
(再掲)上り側 2010年頃撮影。分かりにくいがバスロケは一般的なタイプ
2010年頃撮影。分かりにくいがバスロケは一般的なタイプ 台座・支柱も新しそう
台座・支柱も新しそう 細い
細い 「秋操駅(あきそうえき)入口」!
「秋操駅(あきそうえき)入口」! ここは今回更新の表示板
ここは今回更新の表示板 緑色のシール
緑色のシール 2008年8月撮影。現在は電光掲示板がなくなった以外、さほど変わっていない
2008年8月撮影。現在は電光掲示板がなくなった以外、さほど変わっていない 開通間もない新しい道路側から。左が弘大・右が土手町方向
開通間もない新しい道路側から。左が弘大・右が土手町方向 マルエス倒産直後2008年7月末の貴重な写真
マルエス倒産直後2008年7月末の貴重な写真 大学方向を背に
大学方向を背に フェンス越し
フェンス越し

 白い桜の数本先、照明柱付近にまだ咲かない桜
白い桜の数本先、照明柱付近にまだ咲かない桜 路面に花びらが
路面に花びらが つぼみが開き始めていた
つぼみが開き始めていた 葉桜の中に満開の桜
葉桜の中に満開の桜 遅咲き桜の花
遅咲き桜の花 天気が悪いですが
天気が悪いですが また違う桜が!
また違う桜が! 白い八重桜
白い八重桜 完全に枯れてしまった桜も2本
完全に枯れてしまった桜も2本 自由通路から北方向
自由通路から北方向 上のすぐ東隣
上のすぐ東隣 反対側、自由通路から南方向
反対側、自由通路から南方向 いつの間にかケヤキが芽吹く季節。車2
いつの間にかケヤキが芽吹く季節。車2 まだ通れる?
まだ通れる? 日付が「5月7日」に上手に修正
日付が「5月7日」に上手に修正



