久しぶりにパンの話。
たけや製パンでは、昨年秋に秋田県産リンゴを使ったパンをいくつか発売していた。
その後も、リンゴ入り新商品が出ている。
12月には、アベックトースト派生商品の第4弾となる「アベックトースト りんごジャム&マーガリン」が発売された。(第3弾「山ぶどうジャム」では、使っているのに商品名から抜けていた「&マーガリン」が復活した)
ほかにも、
 りんごのシュクレ リンゴダイス入り 463kcal
りんごのシュクレ リンゴダイス入り 463kcal
「菓子パン」扱い。
「秋田県産りんごのプレザーブとダマンド生地を包みシュガーマーガリンをトッピング」したそうだけど、「シュクレ」って何?(こういうお菓子のことなんでしょうけど)

しっとりしたパイみたいな感じで、悪くない。
次は1月発売。
 秋田のりんごパン 5個431kcal
秋田のりんごパン 5個431kcal
プロバスケットボールチーム「秋田ノーザンハピネッツ」とのタイアップ商品のようで、チームマスコット「Bicky(ビッキー)」が描かれ、売上の一部がチーム活動資金になるとのこと。
パッケージ左上には緑色の文字で「誇れる」と書かれているので、「誇れる秋田のりんごパン」という商品名かと思ったが、パッケージ裏のバーコード付近の表示やホームページでは「秋田のりんごパン」としか記載されていない。(ヤマザキ系列では、バーコードそばには商品名を細かく・詳しく表示するのだが)
上部中央にハピネッツのロゴが入っているから、もしかしたら「誇れるハピネッツ」という賛辞を表示しているに過ぎないのだろうか?
 5個入り
5個入り
ヤマザキで発売している「ミニパンシリーズ・薄皮○○」にそっくり。(たけやで一部の製造を受託している)
「秋田県産りんごを使ったジャムとカスタードを合わせたりんごカスタードを包みました。」とあるけれど、中に入っているのは、見た感じは普通のクリームパンのクリーム。
食べてみると、パン生地の食感は「薄皮」と同じ。クリームは、リンゴの味が強すぎず弱すぎずで、おいしい。果肉の食感もある。
青森の工藤パンでもリンゴを使ったものがいくつかあって、紹介してきたけれど、酸っぱすぎるものもあった。それらと比べても、これはおいしいと思う。
薄皮シリーズでも同じなんだけど、5個入りというのは中途半端じゃないでしょうか。
1人で1度に5個食べる人はあまりいないだろうし、分けにくい数。4個入りのほうがうれしい人が多いのでは?
【3月7日追記】2月から、ヤマザキのミニパンシリーズ で「薄皮りんごクリームパン」というのが出ており、秋田でもたまに売っている。1個あたり110kcal(=1袋550kcal)なので、たけやのりんごパンとは別物のようだ。
【4月10日追記】4月にはたけやからこんなものも発売された。
ここで工藤パンのイギリストースト。
ここ数年は秋田県内の一部スーパー等で買えるようになったとはいえ通常版。派生・期間限定商品はほぼ入手困難だった。
今月、マックスバリュ東北の広面店に行ったら、通常版とともに、
 イギリストースト 生チョコ入りチョコクリーム 345kcal
イギリストースト 生チョコ入りチョコクリーム 345kcal
12月発売のこれが売られていた。セールなどでなく、他の菓子パンと並んで普通に。
イギリストーストでは、チョコクリームを使ったものを微妙に変えて幾度も出していて、昨年夏にもあったが、今回は生チョコ入りで出た。
見た目は従来と違わないペースト状のチョコクリームで、どこが生チョコなのかよく分からないけれど、おいしいことはおいしかった。(イギリストーストのチョコクリームはどれもおいしいと思う)
2月以降は他のイギリストーストも売ってくれないだろうか? マックスバリュ広面店に期待。(茨島店や港北店では扱っていない模様)
工藤パンホームページによれば、1月からは「青森県産スチューベンホイップ」のイギリストーストが出ている。ブドウのホイップクリームだそうで、珍しい。→それを秋田で購入できた
秋田には来ないだろうけど、タマゴやツナサラダをイギリストーストのパンに挟んだ「イギリスサンド」なる惣菜パン(?)も発売されている。
最後に、昨秋やっと開設されたたけや製パンのホームページ。
1月の新商品を12月末の段階でアップする(更新日は元日になっているけど)など、精力的な面もあるけれど、紹介されている新商品は5種類だけで、アベックトーストのことは一切紹介していないなど、まだまだがんばってほしい点もある。
秋の時点では、Googleで「たけや製パン」と検索すると、検索結果のトップはWikipediaの項目。2番目が公式ホームページ。
公式ホームページが1番目になれば、公式ホームページとして認知されたと胸を張れるはず。その日はいつになるかと思っていた。
正月(1月3日)に検索してみると…
 公式ページが最上位になっている!
公式ページが最上位になっている!
ついにトップに来たかと喜んだ(当事者じゃないけど)のもつかの間、1月4日には…
 以前と同じく、2番目に?!
以前と同じく、2番目に?!
その後、ずっと同じ。
なぜかお正月だけの首位だったようだ。
いずれはトップになるとは思うが、それはいつになるだろう。※2014年4月25日時点では2番目のまま。
※2014年4月30日には、ついにGoogle検索結果の最上位に表示されるようになった!(一方、今までなら前の月末にアップされていた、翌月の新商品紹介は、アップされなかった。→5月1日にアップ)
※と思ったら、5月1日にはまた2番目に。Wikipediaとし烈な1位争いをしているようだ。
【31日追記】2月の新商品の紹介は、1月31日にアップされた。1月のページはなくなって(上書きされて)、その月分しか紹介しない方針らしい。
新商品紹介ページの下部には、いくつかの商品の画像が入れ替わりで表示される。それには1月の新商品だったものもあるが、見たことがない商品も混ざっていて、「アベックトースト コーヒー&ホイップ」という包装が確認できる。
 クリックしても何も起こらない
クリックしても何も起こらない
隣にあるチョコデニッシュは新商品として紹介されているので、これも2月の新商品かと推測される。とすれば、初のマーガリンではなくホイップを使ったアベックトーストということになる。
だったら、小さな画像だけでなくちゃんと文字で紹介してよ!
たけや製パンでは、昨年秋に秋田県産リンゴを使ったパンをいくつか発売していた。
その後も、リンゴ入り新商品が出ている。
12月には、アベックトースト派生商品の第4弾となる「アベックトースト りんごジャム&マーガリン」が発売された。(第3弾「山ぶどうジャム」では、使っているのに商品名から抜けていた「&マーガリン」が復活した)
ほかにも、
 りんごのシュクレ リンゴダイス入り 463kcal
りんごのシュクレ リンゴダイス入り 463kcal「菓子パン」扱い。
「秋田県産りんごのプレザーブとダマンド生地を包みシュガーマーガリンをトッピング」したそうだけど、「シュクレ」って何?(こういうお菓子のことなんでしょうけど)

しっとりしたパイみたいな感じで、悪くない。
次は1月発売。
 秋田のりんごパン 5個431kcal
秋田のりんごパン 5個431kcalプロバスケットボールチーム「秋田ノーザンハピネッツ」とのタイアップ商品のようで、チームマスコット「Bicky(ビッキー)」が描かれ、売上の一部がチーム活動資金になるとのこと。
パッケージ左上には緑色の文字で「誇れる」と書かれているので、「誇れる秋田のりんごパン」という商品名かと思ったが、パッケージ裏のバーコード付近の表示やホームページでは「秋田のりんごパン」としか記載されていない。(ヤマザキ系列では、バーコードそばには商品名を細かく・詳しく表示するのだが)
上部中央にハピネッツのロゴが入っているから、もしかしたら「誇れるハピネッツ」という賛辞を表示しているに過ぎないのだろうか?
 5個入り
5個入りヤマザキで発売している「ミニパンシリーズ・薄皮○○」にそっくり。(たけやで一部の製造を受託している)
「秋田県産りんごを使ったジャムとカスタードを合わせたりんごカスタードを包みました。」とあるけれど、中に入っているのは、見た感じは普通のクリームパンのクリーム。
食べてみると、パン生地の食感は「薄皮」と同じ。クリームは、リンゴの味が強すぎず弱すぎずで、おいしい。果肉の食感もある。
青森の工藤パンでもリンゴを使ったものがいくつかあって、紹介してきたけれど、酸っぱすぎるものもあった。それらと比べても、これはおいしいと思う。
薄皮シリーズでも同じなんだけど、5個入りというのは中途半端じゃないでしょうか。
1人で1度に5個食べる人はあまりいないだろうし、分けにくい数。4個入りのほうがうれしい人が多いのでは?
【3月7日追記】2月から、ヤマザキのミニパンシリーズ で「薄皮りんごクリームパン」というのが出ており、秋田でもたまに売っている。1個あたり110kcal(=1袋550kcal)なので、たけやのりんごパンとは別物のようだ。
【4月10日追記】4月にはたけやからこんなものも発売された。
ここで工藤パンのイギリストースト。
ここ数年は秋田県内の一部スーパー等で買えるようになったとはいえ通常版。派生・期間限定商品はほぼ入手困難だった。
今月、マックスバリュ東北の広面店に行ったら、通常版とともに、
 イギリストースト 生チョコ入りチョコクリーム 345kcal
イギリストースト 生チョコ入りチョコクリーム 345kcal12月発売のこれが売られていた。セールなどでなく、他の菓子パンと並んで普通に。
イギリストーストでは、チョコクリームを使ったものを微妙に変えて幾度も出していて、昨年夏にもあったが、今回は生チョコ入りで出た。
見た目は従来と違わないペースト状のチョコクリームで、どこが生チョコなのかよく分からないけれど、おいしいことはおいしかった。(イギリストーストのチョコクリームはどれもおいしいと思う)
2月以降は他のイギリストーストも売ってくれないだろうか? マックスバリュ広面店に期待。(茨島店や港北店では扱っていない模様)
工藤パンホームページによれば、1月からは「青森県産スチューベンホイップ」のイギリストーストが出ている。ブドウのホイップクリームだそうで、珍しい。→それを秋田で購入できた
秋田には来ないだろうけど、タマゴやツナサラダをイギリストーストのパンに挟んだ「イギリスサンド」なる惣菜パン(?)も発売されている。
最後に、昨秋やっと開設されたたけや製パンのホームページ。
1月の新商品を12月末の段階でアップする(更新日は元日になっているけど)など、精力的な面もあるけれど、紹介されている新商品は5種類だけで、アベックトーストのことは一切紹介していないなど、まだまだがんばってほしい点もある。
秋の時点では、Googleで「たけや製パン」と検索すると、検索結果のトップはWikipediaの項目。2番目が公式ホームページ。
公式ホームページが1番目になれば、公式ホームページとして認知されたと胸を張れるはず。その日はいつになるかと思っていた。
正月(1月3日)に検索してみると…
 公式ページが最上位になっている!
公式ページが最上位になっている!ついにトップに来たかと喜んだ(当事者じゃないけど)のもつかの間、1月4日には…
 以前と同じく、2番目に?!
以前と同じく、2番目に?!その後、ずっと同じ。
なぜかお正月だけの首位だったようだ。
いずれはトップになるとは思うが、それはいつになるだろう。※2014年4月25日時点では2番目のまま。
※2014年4月30日には、ついにGoogle検索結果の最上位に表示されるようになった!(一方、今までなら前の月末にアップされていた、翌月の新商品紹介は、アップされなかった。→5月1日にアップ)
※と思ったら、5月1日にはまた2番目に。Wikipediaとし烈な1位争いをしているようだ。
【31日追記】2月の新商品の紹介は、1月31日にアップされた。1月のページはなくなって(上書きされて)、その月分しか紹介しない方針らしい。
新商品紹介ページの下部には、いくつかの商品の画像が入れ替わりで表示される。それには1月の新商品だったものもあるが、見たことがない商品も混ざっていて、「アベックトースト コーヒー&ホイップ」という包装が確認できる。
 クリックしても何も起こらない
クリックしても何も起こらない隣にあるチョコデニッシュは新商品として紹介されているので、これも2月の新商品かと推測される。とすれば、初のマーガリンではなくホイップを使ったアベックトーストということになる。
だったら、小さな画像だけでなくちゃんと文字で紹介してよ!











 701系電車。赤丸がドアボタン
701系電車。赤丸がドアボタン
 車外側
車外側 車内側
車内側
 丸ゴシック体と手書き風書体
丸ゴシック体と手書き風書体 N32編成にやっと巡り会えた
N32編成にやっと巡り会えた


 デカい!
デカい!
 ブルボンホームページより
ブルボンホームページより 後ろのコンテナには本当に「プチ」が積み込まれていたりして?!
後ろのコンテナには本当に「プチ」が積み込まれていたりして?! 美大正門の看板代わりの雪像も恒例となった
美大正門の看板代わりの雪像も恒例となった けっこうにぎやか
けっこうにぎやか 今年も右側のレストハウス(学食)が開放されて灯りが点いている
今年も右側のレストハウス(学食)が開放されて灯りが点いている
 今年は「午」年
今年は「午」年

 倉庫棟付近から遊歩道にかけてはいつものミニかまくらが並ぶ
倉庫棟付近から遊歩道にかけてはいつものミニかまくらが並ぶ 明るめに補正
明るめに補正

 巨大な雪山
巨大な雪山 避難場所の看板は美大に替わっている
避難場所の看板は美大に替わっている 学長名のこの看板は「短期大学」のまま ※その後の変化は、この記事末尾のリンクから2015年の記事参照
学長名のこの看板は「短期大学」のまま ※その後の変化は、この記事末尾のリンクから2015年の記事参照 上屋が設置されていた!
上屋が設置されていた! 【25日画像追加】(再掲)国道13号線沿いの秋田南高校
【25日画像追加】(再掲)国道13号線沿いの秋田南高校 秋田駅を通らない新港線の運賃も分かる
秋田駅を通らない新港線の運賃も分かる 複数経路がある区間では、時刻だけでなく運賃でも比較できる
複数経路がある区間では、時刻だけでなく運賃でも比較できる 最後のシーンは岩手銀行中ノ橋支店前
最後のシーンは岩手銀行中ノ橋支店前 橋を渡るバスは、富士重工ボディ・国際興業新塗装の車両(岩手銀行前の車両も同じ形かな)
橋を渡るバスは、富士重工ボディ・国際興業新塗装の車両(岩手銀行前の車両も同じ形かな) 車内ではハンドルに「NISSAN DIESEL」と表記がある
車内ではハンドルに「NISSAN DIESEL」と表記がある なかいち方向。横断歩道は手前の南北と右の長い東西の2か所
なかいち方向。横断歩道は手前の南北と右の長い東西の2か所 なかいち側から
なかいち側から 正面の信号機が撤去された
正面の信号機が撤去された
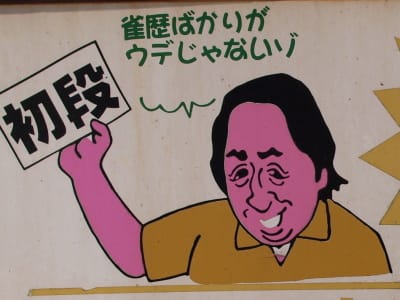
 クリニックの広告看板
クリニックの広告看板 「あなたも小島武夫の店で…」
「あなたも小島武夫の店で…」 ストリートビューより
ストリートビューより 放送大学の看板
放送大学の看板 「月曜・祝日除く」の「曜」だけフォントが違う
「月曜・祝日除く」の「曜」だけフォントが違う (再掲)
(再掲) こうなりました
こうなりました 柱・アームは従来のものを引き続き使っている
柱・アームは従来のものを引き続き使っている (再掲)更新前
(再掲)更新前  更新後
更新後 ケーブルが余ってぐるぐる巻かれてる?
ケーブルが余ってぐるぐる巻かれてる? 新国道を山王方向に進む時に正面になる信号(写真で青になっているもの)
新国道を山王方向に進む時に正面になる信号(写真で青になっているもの)

 県庁方向車線の正面
県庁方向車線の正面
 真横から
真横から (
( 信号機本体に注目
信号機本体に注目

 上が黄灯、下が青灯
上が黄灯、下が青灯 手前右は短いフードの従来型LED
手前右は短いフードの従来型LED 旭川は手前から右へ流れる。左から太平川が合流。左奥が大森山
旭川は手前から右へ流れる。左から太平川が合流。左奥が大森山 約50羽
約50羽 自転車が1台
自転車が1台
 (再掲)
(再掲) 「10周年記念」の文字(別の日に撮影)
「10周年記念」の文字(別の日に撮影) 南東側の総社通りから。左が刑務所、奥が若葉町交差点、右折すれば川尻小へ
南東側の総社通りから。左が刑務所、奥が若葉町交差点、右折すれば川尻小へ 北西側の裏道から。右が国道方向
北西側の裏道から。右が国道方向 東側の市道から。駐車場は使われている模様
東側の市道から。駐車場は使われている模様 「八橋鯲沼町」交差点角。右側奥のほうがCNA部分らしい
「八橋鯲沼町」交差点角。右側奥のほうがCNA部分らしい 交差点(南)寄りから北都銀行、郵便局、CNA、日産ラ・カージュ店。郵便局の上に道路情報Live用のカメラが見える
交差点(南)寄りから北都銀行、郵便局、CNA、日産ラ・カージュ店。郵便局の上に道路情報Live用のカメラが見える ストリートビューで北側から。ABSのラジPALが走っている
ストリートビューで北側から。ABSのラジPALが走っている 日産コンプレックス南西側の市道から。裏手にも車がびっしりで手狭そう
日産コンプレックス南西側の市道から。裏手にも車がびっしりで手狭そう このアンテナ群も移転かな
このアンテナ群も移転かな
 最初に気付いた場面以外でも、同じ「信」
最初に気付いた場面以外でも、同じ「信」





 違和感のない「信」「飼」
違和感のない「信」「飼」 しんにょうの点が1つの「辺」と2つの「道」な上、「辺」が細い
しんにょうの点が1つの「辺」と2つの「道」な上、「辺」が細い 「満」が細い
「満」が細い 「国」と「厳」が細い
「国」と「厳」が細い

 (再掲)
(再掲) (再掲)ロマントピア行きは必ず小型バスで運行かな?
(再掲)ロマントピア行きは必ず小型バスで運行かな? シンプルな「相 馬」の行き先表示も見納めか?【9月17日追記】→短縮後も「相馬」のまま
シンプルな「相 馬」の行き先表示も見納めか?【9月17日追記】→短縮後も「相馬」のまま (再掲)運賃は遠回りしても近回りと同額が適用されるらしい
(再掲)運賃は遠回りしても近回りと同額が適用されるらしい (再掲)特に分かりづらいLED表示
(再掲)特に分かりづらいLED表示 (再掲)「弘前駅前」「四中校」、「大学病院」は黒文字
(再掲)「弘前駅前」「四中校」、「大学病院」は黒文字 2005年撮影。「弘前駅前」「四中(校がない)」、「大学病院」は黒文字カッコ付き
2005年撮影。「弘前駅前」「四中(校がない)」、「大学病院」は黒文字カッコ付き 弘前市公共交通マップより現在の路線網。青が茂森線など、太いピンクが桜ヶ丘線・久渡寺線
弘前市公共交通マップより現在の路線網。青が茂森線など、太いピンクが桜ヶ丘線・久渡寺線 (
( 以前の久渡寺線「桔梗野 久渡寺」という表示も、経路変更後は変わることだろう
以前の久渡寺線「桔梗野 久渡寺」という表示も、経路変更後は変わることだろう



