昨年12月15日、JR各社から春(3月17日)のダイヤ改正の内容が発表された。
いつものように、本社と各支社の資料をざっと見て興味を持った点をまとめておく。
※今後変更される可能性もあります。利用の際は、各自、公式な時刻表等で確認してください。
昨2017年の改正もそうだったけれど、今回の改正も、新路線開業など目玉となるポイントはなく、どちらかと言えば小規模。
まず、東日本以外。
●JR北海道 特急「北斗」がすべて「スーパー北斗」に
函館-札幌間の特急12往復のうち、旧型車(キハ183系)による特急「北斗」として残っていた3往復にも新型車両を投入して「スーパー北斗」化。1994年の登場から24年を経て、全列車がスーパー北斗になる。(スーパーこまちの時のように「スーパー」を取るわけではない)
キハ183系北斗には、何度か乗ったことがある。速さと快適さではスーパー北斗に劣るけれど、国鉄の雰囲気を漂わせ、ちょっと無理していそうに高速走行するのもまた趣き(?)があった。だから不具合が頻発したんでしょうけど。
乗ったことはないけれど、かつてはハイデッカーグリーン車やお座敷車両が連結された183系北斗もあった。

最後まで使われているのはこの高速対応タイプかな。稚内駅にて
改正後もわずかにキハ183系が残るのは、網走方面だけらしい。
●JR東海・小田急電鉄 特急「あさぎり」を「ふじさん」に改称
小田急線からJR東海・御殿場線へ乗り入れて、小田急新宿-御殿場間を結ぶ特急の列車名が変わる。※
2012年に乗った
世界遺産登録による富士山ブームと外国人観光客増加を意識してのことだろうか。
昔は「富士」という特急(「さくら」とともに日本初の名前付き列車)があり、2009年まで九州方面の寝台特急として走っていた。だから、ありそうでなかった「富士山」という列車名が現実になる。山梨県側の富士急行の「フジサン特急」とちょっとまぎらわしい。
「あさぎり」は富士宮の朝霧高原(小田急経営のキャンプ場の宣伝も兼ねていたらしい)にちなむもので、1959年に「朝霧」として登場。歴史ある列車名が消えることになる。
それでは、JR東日本エリアへ。まずは遠方のトピックス。
●特急「スーパーあずさ」E353系に統一
1993年に、初代スーパーあずさ用として登場したE351系が撤退。JR東日本の車両形式名で初めて頭に「E」が付いた形式であり、車体が大きく傾く振り子式車両のため独特のスタイルの車だった。
後継車両の試作車ができたものの、なかなか本格導入されないなと思っていたら、昨年から増備が始まっていたのだった。

E351系。上諏訪駅にて
引退後のE351系は、他線区に転用されず廃車になるとのこと。3回くらいしか乗れなったけれど、もっと乗っておきたかった。
●快速「エアポート成田」名称廃止
横須賀線・総武線の快速電車のうち、成田空港へ行く列車の愛称「エアポート成田」がなくなり、無名快速になる。
1991年の成田空港駅開業時(CMで小泉今日子が「ジャンジャカジャーン。空港の真下まで乗り入れマシタ」と言っていた時かな)からこの愛称で、当初は空港始発も同じ愛称。2002年から空港発は無名、空港行きだけに名前があったそうだ。
たしかに、昔、初めて横須賀線に乗った時にエアポート成田が来て、「成田空港行き」にただでさえ戸惑う上、「エアポート成田」なんて名前が付いていたら、空港に行く人しか乗れない列車ではないかと、一瞬悩んだ。特急「成田エクスプレス」ともちょっとまぎらわしい。
でも、名前があったほうがどちら方面行きか分かりやすいという反対の見方もできる。秋田支社のような無名快速ばかりでは味気ないし、首都圏でも「アクティー」「ラビット」があるし。
●八戸線E130系気動車で統一(と3セク乗り入れ減)
以前少し触れた、公募調達により八戸線に導入される新型車両として、E130系気動車が製造され、昨年から順次投入中。スーパーあずさ同様、気づけば定期普通列車全車両が更新される。
その結果ということか、第3セクター・青い森鉄道から八戸線への乗り入れが廃止(朝の三戸発鮫行き2本)。
ところで、新潟県では、JR信越本線から第3セクター・えちごトキめき鉄道(妙高はねうまライン)に乗り入れる、新潟-新井間の快速列車2往復4本のうち、改正後は3本が直江津駅で分断される。直通列車(特急しらゆきは別)は1本だけになるようだ。
これも、今は115系電車で運行されているものが、E129系の増備により車両変更されることが関係していそう。
3セク側で新形式を受け入れるのが手間なのか、金銭面や利用実態も絡む複雑な事情があるのかもしれないけれど、新幹線開業により3セク化されていなければ、こんな事態にはならなかっただろう。同じ県内なのだし通しで乗りたい客はいなくもないと思うから、これも新幹線開業の影の部分と言えそう。
○そういえばGV-E400系
上の八戸線新車両の記事のメインだったのが、新潟地区と秋田地区(五能線・津軽線)に導入される電気式気動車(ハイブリッドではない)GV-E400系。先に新潟地区に導入され、秋田へは2020年度の予定。
新潟向けの最初の車両がこのほど落成し、まさに今、神戸の川崎重工から新潟へ甲種輸送されているとのこと。
新潟支社のダイヤ改正の資料には、このことは出てこないから、今春時点では本格的な営業運行はまだ行わないということでしょう。

昨年末撮影。右奥の秋田総合車両センター(旧・土崎工場)内の赤い車両に注目
八戸線で使われていた車両は、男鹿線・五能線と同じキハ40系であったが、冷房設置やエンジン換装は未施工の原型により近いものだった。
うち2両だけは、塗装を変えて座席をリクライニングシートに交換し、「うみねこ」の名前で運行されていた。別に「リゾートうみねこ」編成ができたり、東日本大震災のせいもあったのか、この車両は「キハ48 リクライニング車」と呼ばれるようになって、大湊線の臨時列車(快速「まさかり」など)などに使われていた。
それも運行されなくなり、昨年末には秋田総合車両センターの構内に留置されていた。おそらく他の八戸線の旧車両より先立って、廃車されるのだろう。
次に、秋田県周辺で、少し秋田にも関係する変更点。
●新潟駅在来線ホーム高架化(4月予定)
高架化工事が進む新潟駅。在来線ホーム(の一部?)の高架化も完成するらしい。
うち1つのホームでは、上越新幹線と在来線が向かい合う(隣り合う)構造となり、新幹線と特急いなほ(一部を除く)が、階段を使わず同じホームで乗り換え(対面乗り換え)可能になる。
九州新幹線博多開業前の新八代駅のような構造になるようだ。【12日訂正・コメント欄でご指摘いたいだたとおり、新八代駅とは少し違う構造になる模様】
新八代駅で接続する特急(博多方面)と新幹線(鹿児島中央方面)の指定席券を同時に購入すれば、両列車で同じ号車(席番も同じだったか?)の席が確保され、ホームを極力歩かなくて済むように配慮されていたのだが、新潟駅ではどうなるだろうか。
ごくまれに新潟駅で乗り換える者としては、ラインナップが豊富な駅弁やお土産を物色する時間がなくなってしまうだろうから、あまり使いたくない(新幹線を1本ずらしたい)。
あと、
新幹線を利用せず「いなほ」に乗るだけでも、新幹線改札を通る必要も生じる。【12日訂正・予想図ではホーム上に自動改札機が設置されているので、いなほに乗るだけでは新幹線改札は無関係になる。ただ、その構造では新幹線との乗り換え客がホームを歩く距離は長くなるし、集中して流れが滞りそうだ。階段上下よりはましだろうけど】【3月26日追記・ホーム上の乗り換え改札は2か所設置されるとのこと】
●津軽線の編成両数見直し
津軽線は、青森から蟹田までは電化されていて、先の三厩までは非電化なので、電車と気動車の2種が走る。電車は秋田支社の701系電車。
今まで触れそこねていたけれど、2016年の北海道新幹線開業時からは、気動車も盛岡支社から秋田支社へ担当が替わっていて、五能線と共通運用になっているとのこと。
線路は盛岡支社管轄なのに、走る車両はすべて秋田支社というちょっと変わったことになった。
で、盛岡支社の資料は見出し程度なので詳細不明。どこをどう見直すのかは分からないけれど、増やすよりは減らすのでしょう。気動車はキハ40の単行(1両編成)が多かったはずで、これ以上減らしようがなさそう。
一方、701系は、3両編成が多かった印象がある。もしかしたら、それを2両編成に替えるのかもしれない。
※告知されなかったが、701系の3両編成の一部が2両編成化され、奥羽本線側でも編成が短縮される列車が出た。
この記事など参照。
●羽越本線 酒田-鶴岡1往復廃止
新潟支社管内山形県庄内での短距離列車の減便。酒田8時18分発鶴岡行きと折り返し鶴岡9時29分発酒田行きがなくなる。
この運用は、秋田支社の701系電車(たしか2両編成)が受け持っていた。酒田以南では唯一の701系運用。
単純に701系がこの区間から撤退するとすれば、701系の運用区間が酒田までと、少し狭くなる。(他の鶴岡止まりの便が701系運用に替わる可能性もなくはないけれど。)

【12日画像追加】701系側面幕「快速 鶴岡」。LED化される前、幕を回しているところを撮影。このコマを使う機会はなかったことだろう
【2020年7月21日追記】上記の通り、2018年春改正では701系の鶴岡乗り入れがなくなった。しかし、2年後の2020年春改正で、昼前後の酒田-鶴岡1往復が気動車から701系2両編成に変更。再び701系が鶴岡に現れるようになった。
いよいよ、秋田県内へ。
●北上線さらに1本減
改正のたびに寂れていくように感じられる、岩手県北上と秋田県横手を結ぶ北上線。
昨年の改正では全線通し運行の下り8本、上り6本のうち、下り4本、上り2本を3駅だけ通過する快速化していた。
今回は、下り始発(北上5時31分)の快速1本が廃止される。
現在の2番列車に当たる6時10分発(現・6時13分)普通が始発となる。
言われてみれば、始発とその次で間隔が詰まっているし、横手に6時48分に着く早朝の下りでは、あまり利用者もいなさそう。
○横手発一ノ関行き廃止
いつの頃からかは知らないが、北上線から東北本線へ直通する上り列車があった。
横手10時43分発一ノ関行きで、北上線内は快速。北上12時00分着/12時10分発、一ノ関12時54分着。
これが
横手【14日訂正】北上止まりになり、横手発はすべて北上行きになる。(一ノ関方面へは既存ダイヤを調整して接続あり)
直通だったのは、車両が所属基地の一ノ関へ戻る回送を兼ねていたという、運行上の都合だと思われる。
改正後は、北上始発8時41分発一ノ関行きというのが新設され、これが同じ役目を果たすようだ。
東北本線では、701系は110km/hで走れるのに対し、北上線のキハ100形は100km/hだから、北上から一ノ関までの所要時間は5分ほど余計にかかる。
でも、701系の15分後だからそんなに混雑しなかっただろうし、座席はボックスシート、しかも北上線から乗換なし。本線の線路を小柄で強力なキハ100が飛ばすのに乗ってみたかった(今後も北上に8時41分に行けば乗れるけど)。
●花輪線は特になし?
盛岡支社の資料に登場しないことから、今回は特になさそう。
やっと、秋田支社管内。
こまごまとしたことながら、いろいろあって、秋田支社のプレスリリースは9ページもある。今改正の中では、秋田支社がいちばん変更点が多いかもしれない。
また、多くの項目で「~のため」と改正の理由を記してくれているのが、律儀。
●「いなほ8号」時刻移動
羽越本線の上り特急の1番列車が、1時間以上時刻が繰り下がる。
現在秋田9時15分→新潟12時57分なのが、秋田10時35分→新潟14時05分となる。
上記、新潟駅での対面乗り換えの効果もあって、東京までの所要時間は48分短縮(あくまでかかる時間。到着時刻は、もちろん新幹線1本分後・約30分後になる)。
今は直前に秋田9時03分発の酒田行き普通列車があり、その次の酒田行きは12時08分。
いなほとしても、8号が午前中最後の便で、次の10号は秋田を13時前の出発(酒田以南の区間便も定期ではない)。
8号の繰り下げによって、運行間隔の分散にはなる。
ところで、この8号は、かつての大阪行き「白鳥」の流れを汲むダイヤであった(
関連記事)。多少の時刻移動はあっても、秋田駅を8時台、最後の20年以上(?)は8時40分頃に発着というのになじんでいたものだが、それが2時間も遅くなると思えば、感慨深い。
●「つがる」浪岡駅停車
青森県津軽エリア。秋田支社のリリースのトップ項目、本社のリリースにも少し出ている。
秋田と青森を結ぶ特急「つがる」が、弘前と新青森の間の浪岡駅にも停車するようになる。
秋田支社リリースでは「要望があったため」としており、新青森での新幹線乗り継ぎの便を図るようだ。
浪岡は、現在は青森市だが、弘前とも一定の結びつきがあり、普通列車では、上下とも乗る客も降りる客も多い駅。
また、かつて弘前-八戸を走っていた頃の「つがる」は一部が停車していた(2002年~2010年)。
浪岡-新青森はわずか18.5キロ。自由席特急券は510円で、新幹線に乗り継げば半額になる。旅行商品では追加料金なしで特急に乗れるものもあるだろうから、それなりに利用者はいるかな。
【11日追記】国鉄時代の急行列車は、一部列車が浪岡に停車していたそうだ。上野-青森の「津軽」は通過。感覚としては秋田市の土崎駅レベルってとこか。
●男鹿線EV-E801系の1往復増
昨年導入の蓄電池式電車EV-E801系は順調・好評(ただし、オールロングシートで2両だけという点ではどうでしょう?)で、1日2往復から3往復に。車両を増備するのではなく、運用を変更して対応。※予備車両がないので、従来の気動車代走の場合もあり得る。
現在は、午前午後1往復ずつなのが、午前はそのまま1往復、午後の充当ダイヤを変更して2往復となる。
現在EV-E801系が走っている秋田発13時台・折り返し男鹿発15時台が再びキハ40系に戻り、その前後の1往復ずつ(秋田発12・15時台、男鹿発13・16時台)がEV-E801系化。
最後、18時前に秋田に戻ってくる列車は、現在は3両編成で運行。以前見た限りでは、それほど混雑するわけでもないようだけど、帰宅時間帯に1両減かつワンマン化(でしょうね)で大丈夫だろうか。
【28日追記】男鹿発13時台の上り秋田行きは、現在も2両編成(車掌乗務あり)で、何度か乗ったことがあるが定員としては問題なさそう。土崎駅では珍しく2番線に入るのだが、改正後はどうなるか。
●奥羽北線快速 上飯島、羽後飯塚に停車
秋田より北の奥羽本線の快速4本(朝の大館発、弘前発、夜の弘前行き、大館行き)が新たに秋田市近郊2駅に停車。
羽後飯塚駅は隣の井川さくら駅と1.4キロしか離れておらず、1995年の井川さくら駅開業直後は、普通列車でも羽後飯塚を通過するものがあったはず。
上飯島駅は、ホームだけの無人駅で、やはり1990年代後半頃までは、一部普通列車が通過していた。
そんな両駅に快速が停まる日が来るとは!
っていうか、これによって秋田-八郎潟の間の6駅すべてに快速が停車することになり、実質的に普通列車化も同然だ。
701系導入後の20年ほど前の快速「しらかみ」→「しらゆき」は、秋田-八郎潟間はノンストップだったのに…
秋田支社のプレスリリースでは、「羽後飯塚駅に快速列車を停車してほしいとお客さま及び自治体からの要望があったことや上飯島駅のご利用人員が増加しているため」「通勤通学の利便性向上」としている。
文面通り受け取れば、羽後飯塚については潟上市(と客)から要望があって、上飯島については別に秋田市(と客)から要望はなかったということになる。
こう停まったり停まらなかったり変化が激しければ、客もJRも混乱しそう。全駅停車にすれば、それもなくなるかな。
と思っていた矢先の1月9日。大館発の快速が、(通過する羽後飯塚の次駅である)大久保駅での停車を失念し、車掌が非常ブレーキをかけるもオーバーランする事案が発生した。
報道によれば、運転士が大久保駅を羽後飯塚だと勘違いしたとのこと。直前に通過済みの羽後飯塚を、また通過すると思いこんでしまうとは、なんだかなという気もしてしまう(線路際に注意喚起の標識もあるはずだし、指差喚呼していれば起こらないのでは)けれど、羽後飯塚にも停車するようになれば、そんなこともなくなりますね… あ、慣れるまでは上飯島と羽後飯塚を通過してしまう危険はあるか…
●奥羽本線 津軽湯の沢駅 上り2本通過
秋田県から青森県へ入って最初の津軽湯の沢駅。
普通列車だけが停車するが、「ご利用状況にあわせて一部の上り列車を通過とします。」。
上りの終電とその1つ前、現ダイヤの時刻で21時22分、22時54分のいずれも大館行きが通過することに。これにより20時前の秋田行きが最終となる。
【13日追記】津軽湯の沢駅の利用者は、弘前方面との行き来が多いはず。といっても数は多くなく、乗降ゼロのことも珍しくない。夕方の上りではそれなりに降りるけれど、21時以降ではきわめて少ないのは想像がつく。

【11日画像追加】(
再掲)2009年の津軽湯の沢駅
現段階では、下りのほうは2本が通過している。
17時台の秋田発青森行きと、最終の21時台の大館発青森行き。
昔はどうだったか忘れたけれど、そう言われれば、20年前に花輪線の車両が使われていた弘前行き下り最終は通過していたような気がする。
改正後は、上下とも1日8本が停車することになる。
【11月19日追記】その後、2018年以降は毎年12月1日から翌年3月31日までの
冬期間、全列車が津軽湯の沢駅を通過することになった。
●羽越本線 新屋発始発が始発こまちに接続
「羽越本線から秋田新幹線「こまち6号」に接続列車がほしいとお客さまからの要望があり」、新屋発6時02分を5時55分発に。
わずか2駅の短距離列車を、たった7分繰り上げるだけで接続できるのに、どうして今までやらなかったんだろう。
羽越本線といっても秋田市内2駅だけだけど、少し便利になりそう。
●五能線の輸送体系変更
単なる減便でなく、定期快速の新設など、けっこう手が入るようだ。
リゾートしらかみと合わせて、後日
別記事にて。
とりあえず以上。
秋田地区の五能線以外の普通列車については、改正後のダイヤは分からない。部分的に見る限り、男鹿線の上り14時台が30分ほど繰り上がっているので、ほかにもその程度の変更があるかもしれない。
昨年から横手-秋田-追分間を1往復だけ走り始めた719系電車については特に触れていない(転入したこと自体、公式に発表されていないけど)。
※
翌2019年の改正について。
 (再掲)2015年撮影
(再掲)2015年撮影 「大学構内につき無用の立入禁止」
「大学構内につき無用の立入禁止」 首を細くすれば?
首を細くすれば? (再掲)2015年撮影
(再掲)2015年撮影 「大学構内につき無用の立入禁止」
「大学構内につき無用の立入禁止」 首を細くすれば?
首を細くすれば?









 秋田大橋下流・右岸(茨島側)から
秋田大橋下流・右岸(茨島側)から 秋田運河入口・新屋水門の上から。左から流れる水の一部がこの水門へ分かれる
秋田運河入口・新屋水門の上から。左から流れる水の一部がこの水門へ分かれる こちらは右岸の氷が少なく、左岸側も凍っている
こちらは右岸の氷が少なく、左岸側も凍っている
 秋田大橋の上から上流方向。向こうの橋は羽越本線
秋田大橋の上から上流方向。向こうの橋は羽越本線 写真があった
写真があった 橋の上から。今年の写真よりも川の中央部寄りで撮影したはず
橋の上から。今年の写真よりも川の中央部寄りで撮影したはず 恒例のミニかまくらを積み上げた表示
恒例のミニかまくらを積み上げた表示 オブジェ風のもの
オブジェ風のもの 少し霞んだ美大正面「サークルプラザ」
少し霞んだ美大正面「サークルプラザ」 覆われたシンボルタワー
覆われたシンボルタワー

 こんなのが多かった
こんなのが多かった 前のめり
前のめり こんなに傾いてしまった
こんなに傾いてしまった 25日。通町橋から旭川下流
25日。通町橋から旭川下流 道路はこの程度の積雪
道路はこの程度の積雪 昨年12月下旬
昨年12月下旬 昨年12月中旬
昨年12月中旬 つるつる
つるつる 拡大
拡大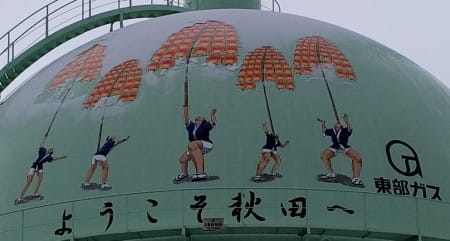 1月中旬
1月中旬 昨年末売られていた2種
昨年末売られていた2種
 昨年秋、秋田市北部で発見した細長い柿。渋柿なんだろうけど初めて見たタイプ
昨年秋、秋田市北部で発見した細長い柿。渋柿なんだろうけど初めて見たタイプ 秋田大橋上流側から新屋方向。正面が大森山
秋田大橋上流側から新屋方向。正面が大森山 少し上流側へ移動して、ズーム
少し上流側へ移動して、ズーム さらに上流側からシンボルタワーの裏側。奥は大森山のテレビ塔
さらに上流側からシンボルタワーの裏側。奥は大森山のテレビ塔 2017年1月撮影
2017年1月撮影 2009年撮影。新屋側
2009年撮影。新屋側 2013年撮影
2013年撮影 だいぶ薄れているけれど
だいぶ薄れているけれど 1枚だけこんなのも
1枚だけこんなのも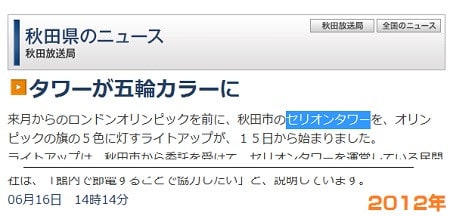 2012年6月16日更新のNHKニュースサイトより。一部省略
2012年6月16日更新のNHKニュースサイトより。一部省略 公式サイト「新店一覧」より
公式サイト「新店一覧」より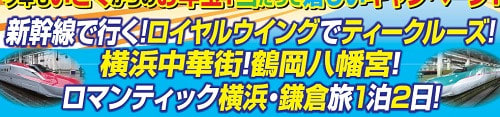 ホームページ掲載のチラシより
ホームページ掲載のチラシより
 封鎖された正門から
封鎖された正門から
 正門の左方から。全体に白っぽい建物で雪と同化しそう
正門の左方から。全体に白っぽい建物で雪と同化しそう 旧正門から
旧正門から 正門左方から見ると、ちょっと不格好。1階にはコカコーラの自販機?
正門左方から見ると、ちょっと不格好。1階にはコカコーラの自販機? 最後まで使われているのはこの高速対応タイプかな。稚内駅にて
最後まで使われているのはこの高速対応タイプかな。稚内駅にて E351系。上諏訪駅にて
E351系。上諏訪駅にて 昨年末撮影。右奥の秋田総合車両センター(旧・土崎工場)内の赤い車両に注目
昨年末撮影。右奥の秋田総合車両センター(旧・土崎工場)内の赤い車両に注目 【12日画像追加】701系側面幕「快速 鶴岡」。LED化される前、幕を回しているところを撮影。このコマを使う機会はなかったことだろう
【12日画像追加】701系側面幕「快速 鶴岡」。LED化される前、幕を回しているところを撮影。このコマを使う機会はなかったことだろう 【11日画像追加】(
【11日画像追加】( やわらかもちケーキ りんご 296kcal 要冷蔵
やわらかもちケーキ りんご 296kcal 要冷蔵

 保戸野金砂町と千秋中島町の間から、旭川と太平山。橋は工事中で板で囲われている
保戸野金砂町と千秋中島町の間から、旭川と太平山。橋は工事中で板で囲われている 少し上流側・旭川橋梁を渡るEV-E801系(今回は軽く
少し上流側・旭川橋梁を渡るEV-E801系(今回は軽く (再掲)秋田市営バスの広告(2001年)【1月7日追記】ここでは「“秋田市・”共通ポイントカード」とある。「みるみるたまってとるとる特典」というフレーズはたまに目にしたか
(再掲)秋田市営バスの広告(2001年)【1月7日追記】ここでは「“秋田市・”共通ポイントカード」とある。「みるみるたまってとるとる特典」というフレーズはたまに目にしたか



