関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
洋楽と邦楽の境界
2020/10/31 更新UP
さきほど放送していたNHKの「筒美京平からの贈りもの ~天才作曲家の素顔~」、面白かった。
このなかで、筒美京平氏は「『ペンタトニック』に『メジャーセブンス(四和音)』系の音を加えていった」という内容があった。
音楽理論も楽器の演奏もまったくのトーシロなんでよくはわからんが、おそらく「ペンタトニック」を日本固有の五音音階(ヨナ抜き音階やニロ抜き音階)の意味で使っていた気がする。
(端折っていうと「ド・レ・ミ・ソ・ラ」だけでつくられたような曲。)
これに洋楽の音階である、四和音(セブンス・コード)が入ってくると音数がふえて多彩な響きになる。
(端折っていうと「お洒落感」がでる。)
比較として適切かわからんけど、「ヨナ抜き音階」でつくられているといわれる米津玄師 の『パプリカ』。
これに対して、四和音(メジャーセブンス)にマニアックなコードばりばり盛り込んだ山下達郎の『SPARKLE』。
個人的には、シティーポップのなかでも、もっともメジャーセブンス系のグルーヴが効いた曲だと思っている。
わかりやすいコードの解説も出てる → こちら
4:38~のコード進行、解説きいてみるとディミニッシュやオーギュメント使ってのクリシェ(コードの1音を上下してコード(メロディ)を遷移させていくこと)ばりばりじゃん!
この前の関ジャムの「矢沢永吉」特集でも、永ちゃん自身が「自然に不安定な(テンションコード的な)コードが湧いてきた。」的なコメントしてたけど、ここらへん(=五音音階に四和音メジャーセブンスが加わって、ほどよい練り具合で曲がつくられていたこと)が1970年代中盤~1980年代中盤の音楽のキモなのかもしれない。
それにしても、↑の3曲聴き比べてみて、最近圧倒的に上(パプリカ)のパターンが増えてきているという見方は、うがちすぎか?
〔 関連記事 〕
■ グルーヴ&ハイトーン (グルーヴってなに・・・?)
---------------------------------
2020/10/22 更新UP
↓ この記事、けっこうアクセスいただいてるので、リンク切れした動画入れ替えて更新UPします。
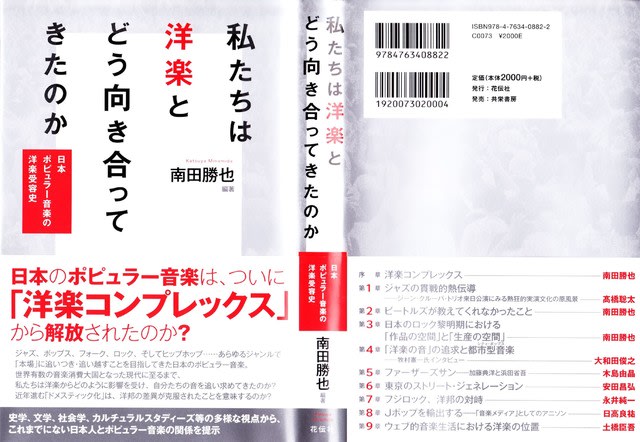
2020/01/05 UP
「私たちは洋楽とどう向き合ってきたのか」(南田勝也編著/花伝社2019.3初版)に関連して、引きつづき書いてみます。
今回は、日本の1970~80年代の「シティポップス」が近年海外で人気の理由について。
本書(P10-12)には、
・「多くの国では自国のミュージシャンの音楽よりも英米のミュージシャンや全米トップ40の音楽が優勢であり、チャートにもそれが反映される。『世界的に大ヒット』とされたミュージシャンは、真に世界中でヒットしているのであり、『ただし日本をのぞく』のである。」
・「ほとんど輸出されることのない音楽が、しかし国内だけで巨大に発達してマーケットを構成し、文化の系譜を積層している。」
という記述がある。
これは事実だが、そうなるとシティポップは、洋楽とは別個に発達したガラパゴス的な音楽なのか?
違うと思う。
シティポップは、アメリカのウェストコーストサウンドやAORとほぼ同時期に名作を輩出したが(70年代後半~80年代中盤)、わたしは、この時期どちらも並行して聴き込んでいた。
だから絶対違うと言い切る自信がある。
もし、シティポップが日本固有のガラパゴス的なPOP MUSICだとしたら、そのリズムは裏拍(アップビート)ではなく表拍(ダウンビート)になる筈であり、コードはメジャーセブンス系ではなくマイナー系になる筈だ。
ところが、シティポップの楽曲は例外なく、メジャーセブンス系裏拍(アップビート)であり、そこへのこだわりは世界のPOP MUSIC史でも稀なくらいに徹底している。
(この「(日本人特有の細部へのこだわりやワザをもって本家の魅力を)意識的に高めている。」という視点はこちらの記事でも指摘されています。)
ウェストコーストサウンドは、ブライトなメロディとこ洒落たハーモニー、そして独特の弾むリズムが魅力だと思っているが、今、海外で人気とされるシティポップ曲を聴くと、例外なくこれらの要素を備えている。
これらが重なると、耳(というか全身)に自然に入ってくる、きわめて「聴き心地のよい音楽」となる。そして聴き手にポジティブな高揚感をもたらす。
当時はさほど意識していなかったが、いま聴き直してみるとシティポップではこれらの要素(とくに弾むリズム)をウェストコーストサウンドよりも意識的にデフォルメしている感じがある。
だからシティポップの「聴き心地のよさ」は、ウェストコーストサウンドを凌駕しているのでは。
シティポップ海外人気の理由をYouTubeの普及やヴェイパーウェイヴ(Vaporwave)・フューチャーファンク(Future Funk)('70~'80年代のとくに日本の音源をエフェクトを重ねて表現する手法・またはジャンル)に求める意見は多いが、これらはアクセスの手段ではあっても本質ではない。
簡単にアクセスできたり、耳に触れる機会が増えても、共感や評価が得られなければけっして人気は出ないから・・・。
かつて彼らが生み出したウェストコーストサウンドやAOR(AC)が、より進化した形で日本で生み出されていたことに対するおどろきと、有無をいわさぬ「聴き心地のよさ」、そしていまの社会環境(時代の気分)では、もはや創りだすことが難しくなった「高揚感」がシティポップ人気の本質ではないか。
だから、シティポップ海外人気は、アーティストに拠る「アーティスト・オリエンテッド」ではなく、楽曲そのものの魅力に向かう「ソング・オリエンテッド」な動きなのだと思う。(=曲がよければアーティストは誰でもよい。)
----------------
ここからはさらに個人的な憶測です。(なんの根拠もありません(笑))
音楽でも芸術でも、ある一定の時代に「黄金期」というものがあって名作が輩出している。
後年、技法や技術は飛躍的に進歩を遂げたが、結局は「黄金期」の伝承、模倣や亜流にとどまり、「黄金期」を超える作品は後世ではほとんど創り出せていない。
バロック、クラシック、陶芸、仏像製作など思い当たる分野が多々ある。
これは「黄金期」の作品が、その分野で人々の感性に訴えるもっとも最適化した「解」を出してしまったので、後世でいくら技法やテクニックを駆使しても「黄金期」の作品を超える(人々の感性により強く訴える)ものが創り出せないためではないか。
1984年から洋楽の質は一気に変容し、アグレッシブでリズム(ピッチ)主体の曲がメインとなっていった。
(理由はこちらをみてね。)
それらは時代性や商業性は備えていたものの、「聴き心地のよさ」からは離れていった感じが強い。
そして、現在に至るまでカバー、サンプリング、リミックスがあたりまえの時代がつづく。
それに併せて打ち出されるコピーはいつもきまって「トリビュート」や「リスペクト」。
「トリビュート」や「リスペクト」される側のメジャーアーティストだって、アンセム志向(過去の名曲に人気が集まりやすいこと)は強まる一方だ。
本当は「演っていて気持ちのいい音楽」「聴き心地のいい音楽」を創り出したいのだけど、どうやっても「黄金期」('70~'80年代)のレベルには迫れないからカバー、サンプリング系でかわす。
でも、厳しい言い方になるが、本家に迫れないカバー、サンプリングは単なる「パクリ」でしかなく、(元歌を広める効果以外は)ほとんど無価値だ。
------
※カラバトU-18の「黄金の世代」が歌っているのはほとんどカバー曲だが、彼女たちは、元歌を自身のオリジナルな唱法で歌いこなし、元歌から別の魅力を引き出している。
そういうことをできる歌い手はそうそういないが、そんな才能がかたまって輩出しているので、おどろきをこめて「黄金の世代」として紹介しています。
また、ONE OK ROCKは、(個人的には)'70~'80年代のブリティッシュロック(黄金期)の系譜を継いでいると思うが、彼らの凄いところは、それをオリジナル曲で、しかも「黄金期」を凌ぐレベルで体現している感じがあるところ。
これはおそらく世界的にもレアケースで、だから海外での人気が高いのだと思う。
------
それでは、POP MUSICは終わったのかというと、ぜんぜんそんなことはないと思う。
'70~'80年代に「黄金期」を迎えたというのはあくまでも既成の洋楽であって、あたらしい切り口はいくつもある。
わかりやすいのは'70~'80年代に「シーンとして(ほぼ)存在していなかった」フォーマット。
たとえば、クラシカル・クロスオーバー、ヒーリングミュージック、ボカロ曲、アニソンなどで、これらはいま「黄金期」にあるか、これから「黄金期」に向かう可能性が高い。
そして、それらのジャンルは日本にアドバンテージのあるものが多い。
こうしてみると、海外でのシティポップ人気とアニソン人気はその性質が異なる(とみられる)が、日本が「音楽の宝の山」として注目を高める傾向はこれからますます強まっていくと思う。
2020年の日本の音楽シーンに期待したいところです。
■ 名曲であふれていた1970年代後半~1980年代前半 ↓
【cover】荒井由実 - ベルベット・イースター
どうやったら、こういう曲が生み出せるんだろう。
初期のユーミンならではの透明感あふれる名曲。
角松敏生 - Crescent Aventure
個人的には、角松といったらやっぱりこの曲かな。
当山ひとみ - Anytime Anyplace
シティポップのなかでも、グルーヴのききはピカ一のアーティストだと思う。
【cover】サザンオールスターズ - 素顔で踊らせて
キレ味鋭い洒落っ気のあった、初期のサザン。
【high_note Music Lounge】小林明子 - 恋におちて -Fall in love-
1985年秋、日本国中を不倫ブーム?に巻き込んだ『金妻 III』の主題歌。
捨て音いっさいなしの神曲! イントロのインパクトからしてただごとじゃない。
杏里 - Just Be Yourself
こういう、グルーヴのきいたミディアム曲って、1990年代以降ほんとにつくられなくなった。
山下達郎 - メロディー,君の為に (Melody For You)
達郎のリズム、達郎のメロディ。
山下達郎 - YOUR EYES
1982年の夏を象徴する名曲。
杉山清貴 - 空から降りてくるLONELINESS
これは1989年5月リリースの名曲。
1989年(平成元年)12月29日、株式市場大納会まであと半年。
1980年代前半のはじけるような高揚感は、もはやここにはない。
---------------------------------
2020/01/03 UP
「私たちは洋楽とどう向き合ってきたのか」(南田勝也編著/花伝社2019.3初版)、買ってみました。
まだ拾い読みですが、前々から勝手に唱えている1983年洋楽ピーク説とけっこう重なる内容があったので、とりあえずUPしてみます。
(個人的には、POP MUSICを語るにはいささか論理的構成にすぎる(=文章がかたすぎる)感なきにしもあらずですが、バックデータが豊富だし、正鵠を射ている内容が多いと思います。)
本書では、「一方で80年代は人びとと洋楽の距離が急接近する『洋楽の黄金期』だったが」(本書P.145より)とし、この時代の洋楽のポジションを明確にしている。
この時期、邦楽が洋楽とほとんど遜色ないレベルにあった感じがしているが、その点は本書では大滝詠一の「分母分子論」を用いて説明されている。
「分母分子論」は1983年の発表。
Artistサイドからしても、1983年時点の邦楽がもはや洋楽アドバンテージから脱却していたことがわかる。
最近の、とくに若い世代の「洋楽離れ」については、”情報が多すぎてよくわからない。”、”洋楽は(邦楽とちがって)LIVEをリアルに楽しめない。”、”決定的なヒット曲の欠如”などの背景があるように思うが、ひょっとして、「邦楽が洋楽のレベルを上回ってきていて、国内のリスナーがもはや洋楽を聴く意味がなくなってきている。」ということもあるのかもしれない。
これは女性ボーカル(とくに若手/女神系歌姫)の分野ではかなり前から感じていたが、グループ系についてもONE OK ROCKの出現により決定的になった感じがある。
「洋楽離れ」は、本書で指摘している「YouTubeやTwitterでの偶発的な出会い」や「音のみによる判断」が背景にあるのは確かだと思うし、この傾向はこれからさらに強まっていくのでは。
そうなると、洋楽・邦楽の境界はますますあいまいになり、これは逆にみると、J-POPが海外のリスナーに受け入れられやすくなることを意味する。
ONE OK ROCKはそのいい例だと思う。(海外ではYouTubeから火がついたとされる。)
ONE OK ROCK - Clock Strikes 35xxxv Japan Tour 2015
これ日本か? これほどの若いオーディエンスが日本で育っているとは・・・。正直おどろき。
海外の音楽好きのあいだでこのところ再ブレーク↓ (やはり発端はYouTubeとされる。)
Plastic Love - 竹内 まりや(1984年)
読み込んだら、もう少しカキコしてみます。
1977年~1980年頃の個人的な音楽体験
1980年~1982年頃の個人的な音楽体験
1983年~1986年頃の個人的な音楽体験
1986年~現在までの個人的な音楽体験
さきほど放送していたNHKの「筒美京平からの贈りもの ~天才作曲家の素顔~」、面白かった。
このなかで、筒美京平氏は「『ペンタトニック』に『メジャーセブンス(四和音)』系の音を加えていった」という内容があった。
音楽理論も楽器の演奏もまったくのトーシロなんでよくはわからんが、おそらく「ペンタトニック」を日本固有の五音音階(ヨナ抜き音階やニロ抜き音階)の意味で使っていた気がする。
(端折っていうと「ド・レ・ミ・ソ・ラ」だけでつくられたような曲。)
これに洋楽の音階である、四和音(セブンス・コード)が入ってくると音数がふえて多彩な響きになる。
(端折っていうと「お洒落感」がでる。)
比較として適切かわからんけど、「ヨナ抜き音階」でつくられているといわれる米津玄師 の『パプリカ』。
これに対して、四和音(メジャーセブンス)にマニアックなコードばりばり盛り込んだ山下達郎の『SPARKLE』。
個人的には、シティーポップのなかでも、もっともメジャーセブンス系のグルーヴが効いた曲だと思っている。
わかりやすいコードの解説も出てる → こちら
4:38~のコード進行、解説きいてみるとディミニッシュやオーギュメント使ってのクリシェ(コードの1音を上下してコード(メロディ)を遷移させていくこと)ばりばりじゃん!
この前の関ジャムの「矢沢永吉」特集でも、永ちゃん自身が「自然に不安定な(テンションコード的な)コードが湧いてきた。」的なコメントしてたけど、ここらへん(=五音音階に四和音メジャーセブンスが加わって、ほどよい練り具合で曲がつくられていたこと)が1970年代中盤~1980年代中盤の音楽のキモなのかもしれない。
それにしても、↑の3曲聴き比べてみて、最近圧倒的に上(パプリカ)のパターンが増えてきているという見方は、うがちすぎか?
〔 関連記事 〕
■ グルーヴ&ハイトーン (グルーヴってなに・・・?)
---------------------------------
2020/10/22 更新UP
↓ この記事、けっこうアクセスいただいてるので、リンク切れした動画入れ替えて更新UPします。
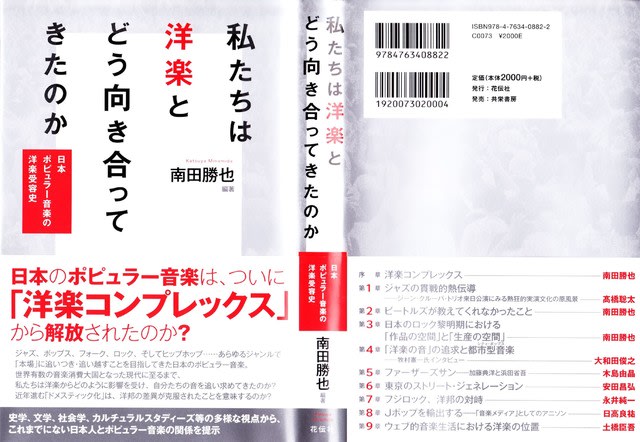
2020/01/05 UP
「私たちは洋楽とどう向き合ってきたのか」(南田勝也編著/花伝社2019.3初版)に関連して、引きつづき書いてみます。
今回は、日本の1970~80年代の「シティポップス」が近年海外で人気の理由について。
本書(P10-12)には、
・「多くの国では自国のミュージシャンの音楽よりも英米のミュージシャンや全米トップ40の音楽が優勢であり、チャートにもそれが反映される。『世界的に大ヒット』とされたミュージシャンは、真に世界中でヒットしているのであり、『ただし日本をのぞく』のである。」
・「ほとんど輸出されることのない音楽が、しかし国内だけで巨大に発達してマーケットを構成し、文化の系譜を積層している。」
という記述がある。
これは事実だが、そうなるとシティポップは、洋楽とは別個に発達したガラパゴス的な音楽なのか?
違うと思う。
シティポップは、アメリカのウェストコーストサウンドやAORとほぼ同時期に名作を輩出したが(70年代後半~80年代中盤)、わたしは、この時期どちらも並行して聴き込んでいた。
だから絶対違うと言い切る自信がある。
もし、シティポップが日本固有のガラパゴス的なPOP MUSICだとしたら、そのリズムは裏拍(アップビート)ではなく表拍(ダウンビート)になる筈であり、コードはメジャーセブンス系ではなくマイナー系になる筈だ。
ところが、シティポップの楽曲は例外なく、メジャーセブンス系裏拍(アップビート)であり、そこへのこだわりは世界のPOP MUSIC史でも稀なくらいに徹底している。
(この「(日本人特有の細部へのこだわりやワザをもって本家の魅力を)意識的に高めている。」という視点はこちらの記事でも指摘されています。)
ウェストコーストサウンドは、ブライトなメロディとこ洒落たハーモニー、そして独特の弾むリズムが魅力だと思っているが、今、海外で人気とされるシティポップ曲を聴くと、例外なくこれらの要素を備えている。
これらが重なると、耳(というか全身)に自然に入ってくる、きわめて「聴き心地のよい音楽」となる。そして聴き手にポジティブな高揚感をもたらす。
当時はさほど意識していなかったが、いま聴き直してみるとシティポップではこれらの要素(とくに弾むリズム)をウェストコーストサウンドよりも意識的にデフォルメしている感じがある。
だからシティポップの「聴き心地のよさ」は、ウェストコーストサウンドを凌駕しているのでは。
シティポップ海外人気の理由をYouTubeの普及やヴェイパーウェイヴ(Vaporwave)・フューチャーファンク(Future Funk)('70~'80年代のとくに日本の音源をエフェクトを重ねて表現する手法・またはジャンル)に求める意見は多いが、これらはアクセスの手段ではあっても本質ではない。
簡単にアクセスできたり、耳に触れる機会が増えても、共感や評価が得られなければけっして人気は出ないから・・・。
かつて彼らが生み出したウェストコーストサウンドやAOR(AC)が、より進化した形で日本で生み出されていたことに対するおどろきと、有無をいわさぬ「聴き心地のよさ」、そしていまの社会環境(時代の気分)では、もはや創りだすことが難しくなった「高揚感」がシティポップ人気の本質ではないか。
だから、シティポップ海外人気は、アーティストに拠る「アーティスト・オリエンテッド」ではなく、楽曲そのものの魅力に向かう「ソング・オリエンテッド」な動きなのだと思う。(=曲がよければアーティストは誰でもよい。)
----------------
ここからはさらに個人的な憶測です。(なんの根拠もありません(笑))
音楽でも芸術でも、ある一定の時代に「黄金期」というものがあって名作が輩出している。
後年、技法や技術は飛躍的に進歩を遂げたが、結局は「黄金期」の伝承、模倣や亜流にとどまり、「黄金期」を超える作品は後世ではほとんど創り出せていない。
バロック、クラシック、陶芸、仏像製作など思い当たる分野が多々ある。
これは「黄金期」の作品が、その分野で人々の感性に訴えるもっとも最適化した「解」を出してしまったので、後世でいくら技法やテクニックを駆使しても「黄金期」の作品を超える(人々の感性により強く訴える)ものが創り出せないためではないか。
1984年から洋楽の質は一気に変容し、アグレッシブでリズム(ピッチ)主体の曲がメインとなっていった。
(理由はこちらをみてね。)
それらは時代性や商業性は備えていたものの、「聴き心地のよさ」からは離れていった感じが強い。
そして、現在に至るまでカバー、サンプリング、リミックスがあたりまえの時代がつづく。
それに併せて打ち出されるコピーはいつもきまって「トリビュート」や「リスペクト」。
「トリビュート」や「リスペクト」される側のメジャーアーティストだって、アンセム志向(過去の名曲に人気が集まりやすいこと)は強まる一方だ。
本当は「演っていて気持ちのいい音楽」「聴き心地のいい音楽」を創り出したいのだけど、どうやっても「黄金期」('70~'80年代)のレベルには迫れないからカバー、サンプリング系でかわす。
でも、厳しい言い方になるが、本家に迫れないカバー、サンプリングは単なる「パクリ」でしかなく、(元歌を広める効果以外は)ほとんど無価値だ。
------
※カラバトU-18の「黄金の世代」が歌っているのはほとんどカバー曲だが、彼女たちは、元歌を自身のオリジナルな唱法で歌いこなし、元歌から別の魅力を引き出している。
そういうことをできる歌い手はそうそういないが、そんな才能がかたまって輩出しているので、おどろきをこめて「黄金の世代」として紹介しています。
また、ONE OK ROCKは、(個人的には)'70~'80年代のブリティッシュロック(黄金期)の系譜を継いでいると思うが、彼らの凄いところは、それをオリジナル曲で、しかも「黄金期」を凌ぐレベルで体現している感じがあるところ。
これはおそらく世界的にもレアケースで、だから海外での人気が高いのだと思う。
------
それでは、POP MUSICは終わったのかというと、ぜんぜんそんなことはないと思う。
'70~'80年代に「黄金期」を迎えたというのはあくまでも既成の洋楽であって、あたらしい切り口はいくつもある。
わかりやすいのは'70~'80年代に「シーンとして(ほぼ)存在していなかった」フォーマット。
たとえば、クラシカル・クロスオーバー、ヒーリングミュージック、ボカロ曲、アニソンなどで、これらはいま「黄金期」にあるか、これから「黄金期」に向かう可能性が高い。
そして、それらのジャンルは日本にアドバンテージのあるものが多い。
こうしてみると、海外でのシティポップ人気とアニソン人気はその性質が異なる(とみられる)が、日本が「音楽の宝の山」として注目を高める傾向はこれからますます強まっていくと思う。
2020年の日本の音楽シーンに期待したいところです。
■ 名曲であふれていた1970年代後半~1980年代前半 ↓
【cover】荒井由実 - ベルベット・イースター
どうやったら、こういう曲が生み出せるんだろう。
初期のユーミンならではの透明感あふれる名曲。
角松敏生 - Crescent Aventure
個人的には、角松といったらやっぱりこの曲かな。
当山ひとみ - Anytime Anyplace
シティポップのなかでも、グルーヴのききはピカ一のアーティストだと思う。
【cover】サザンオールスターズ - 素顔で踊らせて
キレ味鋭い洒落っ気のあった、初期のサザン。
【high_note Music Lounge】小林明子 - 恋におちて -Fall in love-
1985年秋、日本国中を不倫ブーム?に巻き込んだ『金妻 III』の主題歌。
捨て音いっさいなしの神曲! イントロのインパクトからしてただごとじゃない。
杏里 - Just Be Yourself
こういう、グルーヴのきいたミディアム曲って、1990年代以降ほんとにつくられなくなった。
山下達郎 - メロディー,君の為に (Melody For You)
達郎のリズム、達郎のメロディ。
山下達郎 - YOUR EYES
1982年の夏を象徴する名曲。
杉山清貴 - 空から降りてくるLONELINESS
これは1989年5月リリースの名曲。
1989年(平成元年)12月29日、株式市場大納会まであと半年。
1980年代前半のはじけるような高揚感は、もはやここにはない。
---------------------------------
2020/01/03 UP
「私たちは洋楽とどう向き合ってきたのか」(南田勝也編著/花伝社2019.3初版)、買ってみました。
まだ拾い読みですが、前々から勝手に唱えている1983年洋楽ピーク説とけっこう重なる内容があったので、とりあえずUPしてみます。
(個人的には、POP MUSICを語るにはいささか論理的構成にすぎる(=文章がかたすぎる)感なきにしもあらずですが、バックデータが豊富だし、正鵠を射ている内容が多いと思います。)
本書では、「一方で80年代は人びとと洋楽の距離が急接近する『洋楽の黄金期』だったが」(本書P.145より)とし、この時代の洋楽のポジションを明確にしている。
この時期、邦楽が洋楽とほとんど遜色ないレベルにあった感じがしているが、その点は本書では大滝詠一の「分母分子論」を用いて説明されている。
「分母分子論」は1983年の発表。
Artistサイドからしても、1983年時点の邦楽がもはや洋楽アドバンテージから脱却していたことがわかる。
最近の、とくに若い世代の「洋楽離れ」については、”情報が多すぎてよくわからない。”、”洋楽は(邦楽とちがって)LIVEをリアルに楽しめない。”、”決定的なヒット曲の欠如”などの背景があるように思うが、ひょっとして、「邦楽が洋楽のレベルを上回ってきていて、国内のリスナーがもはや洋楽を聴く意味がなくなってきている。」ということもあるのかもしれない。
これは女性ボーカル(とくに若手/女神系歌姫)の分野ではかなり前から感じていたが、グループ系についてもONE OK ROCKの出現により決定的になった感じがある。
「洋楽離れ」は、本書で指摘している「YouTubeやTwitterでの偶発的な出会い」や「音のみによる判断」が背景にあるのは確かだと思うし、この傾向はこれからさらに強まっていくのでは。
そうなると、洋楽・邦楽の境界はますますあいまいになり、これは逆にみると、J-POPが海外のリスナーに受け入れられやすくなることを意味する。
ONE OK ROCKはそのいい例だと思う。(海外ではYouTubeから火がついたとされる。)
ONE OK ROCK - Clock Strikes 35xxxv Japan Tour 2015
これ日本か? これほどの若いオーディエンスが日本で育っているとは・・・。正直おどろき。
海外の音楽好きのあいだでこのところ再ブレーク↓ (やはり発端はYouTubeとされる。)
Plastic Love - 竹内 まりや(1984年)
読み込んだら、もう少しカキコしてみます。
1977年~1980年頃の個人的な音楽体験
1980年~1982年頃の個人的な音楽体験
1983年~1986年頃の個人的な音楽体験
1986年~現在までの個人的な音楽体験
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )





