関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 「カナリア曲」&「鳩曲」
冷え込み、凋落、分断、閉塞感・・・、そんな言葉ばかりが目につくこの頃。
この一年は、ここ数十年そこはかとなく感じていた日本の凋落を、多くの人々が逃れられない現実として実感した年ではなかったでしょうか。
でも、まだまだ日本の底力は尽きていない。(と思いたい)
先人が残してくれた数々の文化や資産、”相身互い”の国民性、そしてゆたかで変化に富んだ自然・・・。
どれもこれも世界に誇れるものです。
---------------------------
音楽は「炭鉱のカナリア」ともいわれます。
これから向かう時代の空気感を、いちはやく曲調であらわすというのです。
確かに、思い当たるフシはあります。
■ 最後のニュース - 井上陽水
1989年12月21日、バブル崩壊直前のリリース。
■ CAN YOU CELEBRATE? - 安室奈美恵
1997年2月19日、緊縮財政元年ともいわれる年のはじめにリリースして大ヒット。
■ 絢香 - 三日月
リーマンショック(2008年9月)を2年後に控えた2006年9月27日リリース。
この頃から「つながる」というワードが歌詞に多く出てくるようになる。
■ 遠くても - 西野カナfeat.WISE
リーマンショック後、東日本大震災前の2009年3月18日リリースのセツナ系。
■ ハロ/ハワユ - リツカ(歌ってみた)
2010年10月11日歌ってみた投稿。
私的な内面(日々の悩み)に向かう曲が増えてきている。
時代はこの頃よりさらに苛烈になっていると思うが・・・。
■ SUPER MOON - 藤田麻衣子
東日本大震災がもたらしたものは、やっぱり重すぎる。
震災後の2011年3月20日に現れたスーパームーンを歌った曲。
ここでも「つながる」がキーワードになっている。
■ 潮見表 - 遊佐未森
2013年10月27日東京・渋谷公会堂でのLIVE。
■ 夜空。- miwa feat. ハジ→
2015年8月19日リリース。
2008年頃の”セツナ系”よりセツナさを増している。
そしてどうしようもない閉塞感。
■ 空奏列車 - めありー(歌ってみた)
2015年2月Web公開とみられるボカロ曲。
不確実、不安定、先の見えない世界。
---------------------------
でも2007年頃~、”セツナ系”の隆盛と歩調を合わせるように、聴き手が前向きになれるような曲も少しづつ出てきていた。
■ Again - アンジェラ・アキ (2007年)
梶浦由記さんと歌姫たちが生み出すテイクは、壮大で高揚感あふれていた。
それは1980年代のシティ・ポップとはあきらかに異なる質感をもっていた。
■ Everlasting Song - FictionJunction (2009年7月12日のLIVE)
■ 未来 - Kalafina (2013年)
■ I Will Be There With You - 杏里/Anri(JAL 企業PV/2011年)
1980年代の杏里にはなかった旋律。
■ ここにあること - 桜ほたる(歌ってみた)
2011年秋、震災後のWeb公開とみられるボカロ曲。
思いっきりはじけた感じがする名曲。
■ ヒカリヘ - miwa (2013年)
どちらかというと、いまの時代にアジャストしている曲のような気がする。
時代を先取りしすぎたか?
■ Hero - 安室奈美恵
2016年7月27日リリース。
J-POPの質感が変わったか? と感じた曲。
この名曲でもオリコン最高位6位。五輪のテーマソングとしてはよく流されたが、時代の空気にはそぐわなかった?
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
2016年11月23日リリース。
閉塞状況から花開いていく感じの曲。これも早すぎたか。
■ YOASOBI「群青」 from 初有観客ライブ『NICE TO MEET YOU』2021.12.04@日本武道館
2020年9月1日リリース。
一聴”応援ソング”っぽいけど、歌詞を聴き込むと、巷にあふれる”自助的応援ソング(がんばろうソング)”とは明らかに一線を画していることがわかる。
『Just The Two Of Us進行』的なコードも、1980年代のお洒落感とはちがう解釈ではまってる。
「本当に変わっていくかも」と感じた1曲。
■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」
アニソン系でもはじけるブライト感をもつ曲が増えてきた。
■ One Reason - milet
2021年9月10日リリース。これまでのJ-POPとは明らかにスケール感がちがう。
■ キャラクター - 緑黄色社会
2022年1月26日リリース。ひさびさに聴いたヨコノリ含みのグルーヴ曲。
こういう曲が出てくるということは・・・。
■ おもかげ - milet×Aimer×幾田りら (produced by Vaundy)
2021年12月17日リリース。
あたらしいJ-POPを象徴する3人のコーラス。これは来たと思った(笑)
Vaundyのような才能が出てきて正当に評価されるのも時代の流れの必然では?
■ Hallelujah - 加藤礼愛(カトレア/Leia Kato/12yrs/中1) @東京ミッドタウン 2022.5.5日比谷フェスティバル まちなか劇場
2022年5月5日のライブテイク。
こういうワールドワイドな才能が出てくることも、日本の復活を暗示しているのかも。
↑ こういう「聴き手のきもちを前向きにする」曲はあきらかにここ数年で増えてきていると思う。
これを吉兆とするならば、吉兆の鳥・八幡神のおつかいの鳩ですね。なので「鳩曲」。
こうした「鳩曲」たちが先駆けとなって、時代がすこしでも前向きに、明るくなるといいですね。
この一年は、ここ数十年そこはかとなく感じていた日本の凋落を、多くの人々が逃れられない現実として実感した年ではなかったでしょうか。
でも、まだまだ日本の底力は尽きていない。(と思いたい)
先人が残してくれた数々の文化や資産、”相身互い”の国民性、そしてゆたかで変化に富んだ自然・・・。
どれもこれも世界に誇れるものです。
---------------------------
音楽は「炭鉱のカナリア」ともいわれます。
これから向かう時代の空気感を、いちはやく曲調であらわすというのです。
確かに、思い当たるフシはあります。
■ 最後のニュース - 井上陽水
1989年12月21日、バブル崩壊直前のリリース。
■ CAN YOU CELEBRATE? - 安室奈美恵
1997年2月19日、緊縮財政元年ともいわれる年のはじめにリリースして大ヒット。
■ 絢香 - 三日月
リーマンショック(2008年9月)を2年後に控えた2006年9月27日リリース。
この頃から「つながる」というワードが歌詞に多く出てくるようになる。
■ 遠くても - 西野カナfeat.WISE
リーマンショック後、東日本大震災前の2009年3月18日リリースのセツナ系。
■ ハロ/ハワユ - リツカ(歌ってみた)
2010年10月11日歌ってみた投稿。
私的な内面(日々の悩み)に向かう曲が増えてきている。
時代はこの頃よりさらに苛烈になっていると思うが・・・。
■ SUPER MOON - 藤田麻衣子
東日本大震災がもたらしたものは、やっぱり重すぎる。
震災後の2011年3月20日に現れたスーパームーンを歌った曲。
ここでも「つながる」がキーワードになっている。
■ 潮見表 - 遊佐未森
2013年10月27日東京・渋谷公会堂でのLIVE。
■ 夜空。- miwa feat. ハジ→
2015年8月19日リリース。
2008年頃の”セツナ系”よりセツナさを増している。
そしてどうしようもない閉塞感。
■ 空奏列車 - めありー(歌ってみた)
2015年2月Web公開とみられるボカロ曲。
不確実、不安定、先の見えない世界。
---------------------------
でも2007年頃~、”セツナ系”の隆盛と歩調を合わせるように、聴き手が前向きになれるような曲も少しづつ出てきていた。
■ Again - アンジェラ・アキ (2007年)
梶浦由記さんと歌姫たちが生み出すテイクは、壮大で高揚感あふれていた。
それは1980年代のシティ・ポップとはあきらかに異なる質感をもっていた。
■ Everlasting Song - FictionJunction (2009年7月12日のLIVE)
■ 未来 - Kalafina (2013年)
■ I Will Be There With You - 杏里/Anri(JAL 企業PV/2011年)
1980年代の杏里にはなかった旋律。
■ ここにあること - 桜ほたる(歌ってみた)
2011年秋、震災後のWeb公開とみられるボカロ曲。
思いっきりはじけた感じがする名曲。
■ ヒカリヘ - miwa (2013年)
どちらかというと、いまの時代にアジャストしている曲のような気がする。
時代を先取りしすぎたか?
■ Hero - 安室奈美恵
2016年7月27日リリース。
J-POPの質感が変わったか? と感じた曲。
この名曲でもオリコン最高位6位。五輪のテーマソングとしてはよく流されたが、時代の空気にはそぐわなかった?
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
2016年11月23日リリース。
閉塞状況から花開いていく感じの曲。これも早すぎたか。
■ YOASOBI「群青」 from 初有観客ライブ『NICE TO MEET YOU』2021.12.04@日本武道館
2020年9月1日リリース。
一聴”応援ソング”っぽいけど、歌詞を聴き込むと、巷にあふれる”自助的応援ソング(がんばろうソング)”とは明らかに一線を画していることがわかる。
『Just The Two Of Us進行』的なコードも、1980年代のお洒落感とはちがう解釈ではまってる。
「本当に変わっていくかも」と感じた1曲。
■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」
アニソン系でもはじけるブライト感をもつ曲が増えてきた。
■ One Reason - milet
2021年9月10日リリース。これまでのJ-POPとは明らかにスケール感がちがう。
■ キャラクター - 緑黄色社会
2022年1月26日リリース。ひさびさに聴いたヨコノリ含みのグルーヴ曲。
こういう曲が出てくるということは・・・。
■ おもかげ - milet×Aimer×幾田りら (produced by Vaundy)
2021年12月17日リリース。
あたらしいJ-POPを象徴する3人のコーラス。これは来たと思った(笑)
Vaundyのような才能が出てきて正当に評価されるのも時代の流れの必然では?
■ Hallelujah - 加藤礼愛(カトレア/Leia Kato/12yrs/中1) @東京ミッドタウン 2022.5.5日比谷フェスティバル まちなか劇場
2022年5月5日のライブテイク。
こういうワールドワイドな才能が出てくることも、日本の復活を暗示しているのかも。
↑ こういう「聴き手のきもちを前向きにする」曲はあきらかにここ数年で増えてきていると思う。
これを吉兆とするならば、吉兆の鳥・八幡神のおつかいの鳩ですね。なので「鳩曲」。
こうした「鳩曲」たちが先駆けとなって、時代がすこしでも前向きに、明るくなるといいですね。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ サザンのセブンス曲
「歌詞が刺さる」って最近よく聞くけど。(TVで特集すらやっている)
ふつうに歌詞がわかりやすいから刺さるのでは?
サザンに限らず、1980年代あたりの邦楽は「歌詞が刺さる」というより「風景が広がる」とか「イメージがふくらむ」とか「雰囲気をつくれる」(←これ重要)とか、そういう聴き方だったと思う。
隠喩や倒置やライムを多用する初期サザンの歌詞がストレートに「刺さる」としたら、その人はすでに詩人の域では(笑)
サウンドにしてもこんな感じか ↓ (■ 「シティ・ポップ」って?からひっぱってきました。)
多くの日本人は、根っこにヨナ抜き音階(ペンタトニック)やダウンビートが入っているので、コンスタントに洋楽を意識する局面がないと、どうしてもセブンス(四和音)やアップビートから遠ざかっていく。
それに、最近では洋楽も急速にペンタ化やダウンビート化(というか4つ打ち化)が進みつつあるし、70~80年代に洋楽の影響を受けた多才なアーティストたちも第一線を退きつつある。
ここ数年(とくにこの5年)、日本でペンタ化・4つ打ち化(ほぼフォークソング化)が進んだこと、そして海外からのシティ・ポップの評価が進んだ背景には、こんな要素もあると思う。
■『ロックの子』/桑田佳祐氏著(昭和62年(1987年)初版)

から引用させていただきます。(萩原健太氏との対談形式)
「そういう意識で来てるじゃない、ずっと。学生のころから。渋谷で友だちに会えばどこそこの輸入盤屋より・・・・ディスクなんとかよりもシスコのほうがいいもん売ってるとか、やっぱ向こうの、こう、ジェフ・ベックの海賊盤ほしいとか」
「ね。そういうふうにやってきたわけじゃない、俺たち。どれだけ向こうのディテールにくいこめるか、と」
「ディテールね」
「そういうことでしょ」
「うん」
「そういうバンドだと思うんだ、だから、俺たちも」
「宿命的に」
「そう。宿命的にね。うん」
↑
この時代、宿命的に先を走る良質な洋楽があったから、この環境が「シティ・ポップ」を生み出す大きな契機になったのだと思う。
それに「シティ・ポップ」は、音の ”ディテール” にこだわらないと創り出せないから・・・。
この”ディテール” にこだわったテイクの代表格が、サザンのセブンス曲では?
2022/10/21 UP
2022/03/04 UP
2022/01/22 UP
このところ、CMでやたらにサザンを聴く。
新型コロナ禍継続、ウクライナ侵攻、そして円安物価高と先がみえない状況だけど。
こんなときこそ、サザンのセブンス曲!
■ 海
→ 「海」のコード
イントロのフレーズ。リバーブの効いたドラムス。複雑なカウンター・メロディ。
むせぶSaxophone、そして桑田さんの色気ただようスキャット。
文句なしの名曲!
■ 素顔で踊らせて
→ コード
なかなか地上に降りてこない、メジャー・セブンスならではの浮遊感。
---------------------------------
2021/05/24 UP
さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」で「桑田さんのマイナーセブンス曲」として ↓ をとりあげてた。
■ ONE DAY - Kuwata Band
コード
中~後期のサザンでよく聴くメロ&コード展開。
とても聴きやすいけど、やっぱり個人的には ↓ のような意表をつく桑田節に惹かれます。
■ Oh! クラウディア - サザンオールスターズ
コード
いつまでも この胸に(Bm F#aug Bm/A)
オーギュメント→オンコード
■ 旅姿六人衆 - サザンオールスターズ
コード
ベースはF G Em Am(4536)の王道進行ながら、
ステキな今宵を分け合えりゃ Dm A# C (261)の切り返し(斬新)感がハンパじゃない。
神テイクすぎるにもほどがある!
いい音楽を生み出すのに、これ以上なにが要るというの?
■ シャララ - サザンオールスターズ
→ コード
不思議な 期待など もてる このごろ (Bm7 E7 Am7 E♭dim)
このごろ(E♭dim)の使い方が神ってる。
■ 涙のアベニュー - サザンオールスターズ
→ コード
ほんとにおサレじゃわ。初期のサザン。
言葉がとぎれて さめざめしい(Amaj7 G#m7 Gm7)のAmaj7のかまし。
1980年代初頭の横浜を歌ったバラッドといわれる。
-----------------------
2021/05/11 UP
このところ、初期サザンを聴く機会がけっこうあった。
初期のサザンって、どうしてこんなにお洒落だったんかな? と考えたらやっぱりセブンス系のコードしこたま使ってたりする。
そこで、初期サザンのセブンス曲と思われる(ちがうかも・・・(笑))ナンバーをいくつかあげてみました。
本来、セブンス系の曲の繊細な響きを語るには、オンコード、代理コード、テンション・ノートなどはおそらく外せないと思うのですが、やたら複雑になります。(筆者もよくわかっていない(笑))
なので、まずは三和音+7度≒セブンスとして捉えた方がわかりやすいと思います。
超安直な方法として、↓のようなコードが頻繁に入ってくると、たいていセブンス系の曲のような感じがしています。
●maj7、●7、●m7、●mM7、●M7aug、●m7-5、●dim7、●7sus4、●add9、●/●(●Con●)
↓ のコードでさがしてみてね。
01.C調言葉に御用心
→ コード
02.Just A Little Bit - cover by サザンヴィンテージーズバンド
→ コード
03.Tiny Bubbles(type-B)
いい動画がみつかりません。こっちで聴いてね。
→ コード
04.ふたりだけのパーティー - cover by サザンヴィンテージーズバンド
→ コード
05.海 ~ 栞のテーマ - サザンオールスターズ
→ 「栞のテーマ」のコード
↓ とりあえずまとめてみました。トーシロなんで間違いあるかも(笑)
〔三和音/トライアド〕
・三和音には4種類。(例はルート音がド(C)の場合)
1.メジャー・トライアド 【C】(長三和音):
ド、ミ、ソ / C、E、G / ルート+長3度+完全5度
2.マイナー・トライアド 【Cm】(短三和音):
ド、ミ♭、ソ /C、E♭、G / ルート+短3度+完全5度
3.オーギュメント・トライアド 【Caug、C+】(増三和音):
ド、ミ、ソ# /C、E、G# / ルート+長3度+増5度
4.ディミニッシュ・トライアド 【Cdim、Cº】(減三和音):
ド、ミ♭、ソ♭ / C、E♭、G♭ / ルート+短3度+減5度
・3度は音の明暗を決めるので、ここに長短がつくことでメジャー・マイナーに分かれる。
・5度は音の安定度を決めるので、ここに増減がつくことで不安定感が出る。(だからaug(増5)やdim(減5)は不安定感のあるコードとされる。)
・完全系の音程は1、4、5、8度でふつう完全、増、減であらわす。長短系の音程は2、3、6、7度で、ふつう長、短であらわす。(減7度など例外あり)
・絶対協和音程は完全1度と完全8度。協和音程は完全5度と完全4度。不完全協和音程は長3度、短3度、長6度、短6度。それ以外は不協和音程。
〔四和音/セブンス〕 (例はルート音がド(C)の場合)
・三和音(1度(ルート)、3度、5度/トライアド)+1音(7度の音)=四和音(1度(ルート)、3度、5度、7度)≒セブンス
1.メジャー・セブンス 【Cmaj7、CM7、C△7】(長七の和音):
ド、ミ、ソ、シ / C、E、G、B / ルート+長3度+完全5度+長7度
(メジャー・トライアド + ルートの半音下の音(長7度(M7)))
2.(ドミナント・)セブンス 【C7】(属七の和音):
ド、ミ、ソ、シ♭ / C、E、G、B♭ / ルート+長3度+完全5度+短7度
(メジャー・トライアド + ルート短7度(m7))
3.マイナー・メジャーセブンス 【CmM7、Cm△7】:
ド、ミ♭、ソ、シ / C、E♭、G、B / ルート+短3度+完全5度+長7度
(マイナー・トライアド + ルート長7度(M7))※ラインクリシェに重用
4.マイナー・セブンス 【Cm7】(短七の和音):
ド、ミ♭、ソ、シ♭ / C、E♭、G、B♭ / ルート+短3度+完全5度+短7度
(マイナー・トライアド + ルート短7度(m7)、)
5.メジャーセブンス・オーギュメント 【CM7aug、C△7+】:
ド、ミ、ソ#、シ / C、E、G#、B / ルート+長3度+増5度+長7度
(オーギュメント・トライアド + ルート長7度(M7))
6.セブンス・オーギュメント 【C7aug、C7+】:
ド、ミ、ソ#、シ♭ / C、E、G#、B♭ / ルート+長3度+増5度+短7度
(オーギュメント・トライアド + ルート短7度(m7))
7.マイナー・セブンス・フラット・ファイブ/ハーフディミニッシュ 【Cm7(b5)、Cm7-5】(減五短七の和音)
ド、ミ♭、ソ♭、シ♭ / C、E♭、G♭、B♭ / ルート+短3度+減5度+短7度
(ディミニッシュ・トライアド + ルート短7度(m7))
8.ディミニッシュ・セブンス 【Cdim(7)、Cº(7)】(減七の和音):
ド、ミ♭、ソ♭、ラ / C、E♭、G♭、A / ルート+短3度+減5度+減7度
(ディミニッシュ・トライアド + ルート減7度 or 長6度)
〔三度堆積和音以外のコード〕 (例はルート音がド(C)の場合)
・三度堆積和音=ルート、3度、5度、7度、9度、11度、13度と奇数で重なっていく和音。
1.サスフォー 【Csus4】:
ド、ファ、ソ / C、F、G / ルート+完全4度+完全5度
(メジャー・トライアドの長3度を完全4度(ファ・F)に置き換えたもの)
※ふつうはメジャートライアドとあわせて使う。
2.セブンス・サスフォー 【C7sus4】:
ド、ファ、ソ、シ / C、F、G、B♭ / ルート+完全4度+完全5度+短7度
(サスフォー + ルート短7度(m7))
※セブンスの代理コード(ドミナント絡み)としてよく使われる。
3.シックス(ス) 【C6】:
ド、ミ、ソ、ラ / C、E、G、A / ルート+長3度+完全5度+長6度
(マイナー・セブンスを1オクターブ上に展開)
4.マイナー・シックス(ス) 【Cm6】:
ド、ミ♭、ソ、ラ / C、E♭、G、A / ルート+短3度+完全5度+長6度
(マイナー・トライアド + 長6度)
〔テンション・ノート〕
・ルート、3rd、5th、7thなどの基本構成音(コード・トーン)に、ルートから9th(ナインス)、11th(イレブンス)、13th(サーティーンス)などの音を加えたもの。
・ルートがCの場合、9thのレ(9)、レ♯(♯9)、レ♭(♭9)、11thのファ(11)、ファ♯(♯11)、13thのラ(13)、ラ♭(♭13)の7種類。
・主にセブンス・コードに付加されるといわれる。
■ アドナインス 【Cadd9】:
ド、ミ、ソ、レ / C、E、G、D / ルート+長3度+完全5度+長9度
(メジャー・トライアド + 長9度)
〔オンコード(分数コード)〕 【C/E、ConEなど】:
・分子はコード、分母はベース音(最低音)をさし、たとえばC/E(ConE)の場合、Cコード(ド、ミ、ソ) + ベース音E(ミ)。
・クリシェ(コードが進むごとに半音ずつベース音を上下させていく音進行)、ペダルポイント(ベース音を保持すること)、IIm7onVの形ではドミナント・セブンス(V7)の代理コード*などに使われる。
* C → Am → G7 → Cの代理として、C → Am → Dm7onG → C。
Dm7onGは G7よりもドミナント(解消したい不安定さ、C(トニック)に戻ると安心)の効きがマイルドなので、”優しいドミナント”ともいわれる。
-------------------------------
実際はこれにコード進行が加わってさらに複雑怪奇になっていくのですが、セブンス系のおサレ曲はトゥ・ファイブ・ワン・シックス(Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ-Ⅵ)進行(Dm7 - G7sus4 - Cmaj7 - Am7の循環コード進行とか)やドミナントモーション絡みの進行が多いと思う。あと、バックドアドミナント進行とか・・・。
むずかしすぎてよくわからんけど・・・(笑)
コード進行についても、もう少しおべんきょしてから書き足してみます。
■ 王道進行(未練進行)〔4536〕の代表曲といわれる「 いとしのエリー」。
コード
売れるべくして売れた? 強力なコード進行。
それと、ナインスがいいところで効きまくってる。
■ TSUNAMI - Cover by Ai Ninomiya
コード
Aメロ、Bメロ、サビでそれぞれ異なるコード進行だと思う。あと、クリシェとBメロ前の転調。
この人、やたらにうまい!
と思ったら、プロか・・・。カラバトで99.578出してる。
■ 夕陽に別れを告げて - サザンオールスターズ
コード
個人的に、なんとなく「TSUNAMI」の原曲のような気がしている曲。
情感入りまくりのメロとか、サスフォーの入れ込み方とか・・・。
『KAMAKURA』収録。サザン屈指の名曲では?
↑ 1985年の秋。就職も決まって、遊びまくった(笑)大学生活もあと半年・・・。
鎌倉や湘南は通ったので、
↓ の杏里の曲とともにリアルタイムできもちに染みていた曲だと思う。
「鎌倉の陽よさよなら・・・」とか「結んだTシャツほどく・・・」とか
絶妙なメロディラインに乗っているさりげな泣きフレーズ。
■ LONG ISLAND BEACH - ANRI
→ 杏里の名バラード20曲!
〔 コードの件で追加 〕
でも、大学生の当時、一番聴き込んでいた邦楽アーティストはやっぱり佐野元春かな。
■ 佐野元春 グッドタイムス&バッドタイムス
コード
メジャー・セブンスに、マイナー・メジャーセブンスやシックススが絶妙に絡んでる。
濡れた歩道にさざめく(G G6 Gmaj7 G6)
もう何も言わないで(F Em7-5 Dmaj7 Am7 D7)
↑ たまらん(笑)
■ NHK-FM サウンドストリート 佐野元春(ゲスト:桑田佳祐)1983.5.16
1983年の佐野元春&桑田佳祐。
貴重すぎる収録!
〔関連記事〕
■ ザ・カセットテープ・ミュージック
ふつうに歌詞がわかりやすいから刺さるのでは?
サザンに限らず、1980年代あたりの邦楽は「歌詞が刺さる」というより「風景が広がる」とか「イメージがふくらむ」とか「雰囲気をつくれる」(←これ重要)とか、そういう聴き方だったと思う。
隠喩や倒置やライムを多用する初期サザンの歌詞がストレートに「刺さる」としたら、その人はすでに詩人の域では(笑)
サウンドにしてもこんな感じか ↓ (■ 「シティ・ポップ」って?からひっぱってきました。)
多くの日本人は、根っこにヨナ抜き音階(ペンタトニック)やダウンビートが入っているので、コンスタントに洋楽を意識する局面がないと、どうしてもセブンス(四和音)やアップビートから遠ざかっていく。
それに、最近では洋楽も急速にペンタ化やダウンビート化(というか4つ打ち化)が進みつつあるし、70~80年代に洋楽の影響を受けた多才なアーティストたちも第一線を退きつつある。
ここ数年(とくにこの5年)、日本でペンタ化・4つ打ち化(ほぼフォークソング化)が進んだこと、そして海外からのシティ・ポップの評価が進んだ背景には、こんな要素もあると思う。
■『ロックの子』/桑田佳祐氏著(昭和62年(1987年)初版)

から引用させていただきます。(萩原健太氏との対談形式)
「そういう意識で来てるじゃない、ずっと。学生のころから。渋谷で友だちに会えばどこそこの輸入盤屋より・・・・ディスクなんとかよりもシスコのほうがいいもん売ってるとか、やっぱ向こうの、こう、ジェフ・ベックの海賊盤ほしいとか」
「ね。そういうふうにやってきたわけじゃない、俺たち。どれだけ向こうのディテールにくいこめるか、と」
「ディテールね」
「そういうことでしょ」
「うん」
「そういうバンドだと思うんだ、だから、俺たちも」
「宿命的に」
「そう。宿命的にね。うん」
↑
この時代、宿命的に先を走る良質な洋楽があったから、この環境が「シティ・ポップ」を生み出す大きな契機になったのだと思う。
それに「シティ・ポップ」は、音の ”ディテール” にこだわらないと創り出せないから・・・。
この”ディテール” にこだわったテイクの代表格が、サザンのセブンス曲では?
2022/10/21 UP
2022/03/04 UP
2022/01/22 UP
このところ、CMでやたらにサザンを聴く。
新型コロナ禍継続、ウクライナ侵攻、そして円安物価高と先がみえない状況だけど。
こんなときこそ、サザンのセブンス曲!
■ 海
→ 「海」のコード
イントロのフレーズ。リバーブの効いたドラムス。複雑なカウンター・メロディ。
むせぶSaxophone、そして桑田さんの色気ただようスキャット。
文句なしの名曲!
■ 素顔で踊らせて
→ コード
なかなか地上に降りてこない、メジャー・セブンスならではの浮遊感。
---------------------------------
2021/05/24 UP
さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」で「桑田さんのマイナーセブンス曲」として ↓ をとりあげてた。
■ ONE DAY - Kuwata Band
コード
中~後期のサザンでよく聴くメロ&コード展開。
とても聴きやすいけど、やっぱり個人的には ↓ のような意表をつく桑田節に惹かれます。
■ Oh! クラウディア - サザンオールスターズ
コード
いつまでも この胸に(Bm F#aug Bm/A)
オーギュメント→オンコード
■ 旅姿六人衆 - サザンオールスターズ
コード
ベースはF G Em Am(4536)の王道進行ながら、
ステキな今宵を分け合えりゃ Dm A# C (261)の切り返し(斬新)感がハンパじゃない。
神テイクすぎるにもほどがある!
いい音楽を生み出すのに、これ以上なにが要るというの?
■ シャララ - サザンオールスターズ
→ コード
不思議な 期待など もてる このごろ (Bm7 E7 Am7 E♭dim)
このごろ(E♭dim)の使い方が神ってる。
■ 涙のアベニュー - サザンオールスターズ
→ コード
ほんとにおサレじゃわ。初期のサザン。
言葉がとぎれて さめざめしい(Amaj7 G#m7 Gm7)のAmaj7のかまし。
1980年代初頭の横浜を歌ったバラッドといわれる。
-----------------------
2021/05/11 UP
このところ、初期サザンを聴く機会がけっこうあった。
初期のサザンって、どうしてこんなにお洒落だったんかな? と考えたらやっぱりセブンス系のコードしこたま使ってたりする。
そこで、初期サザンのセブンス曲と思われる(ちがうかも・・・(笑))ナンバーをいくつかあげてみました。
本来、セブンス系の曲の繊細な響きを語るには、オンコード、代理コード、テンション・ノートなどはおそらく外せないと思うのですが、やたら複雑になります。(筆者もよくわかっていない(笑))
なので、まずは三和音+7度≒セブンスとして捉えた方がわかりやすいと思います。
超安直な方法として、↓のようなコードが頻繁に入ってくると、たいていセブンス系の曲のような感じがしています。
●maj7、●7、●m7、●mM7、●M7aug、●m7-5、●dim7、●7sus4、●add9、●/●(●Con●)
↓ のコードでさがしてみてね。
01.C調言葉に御用心
→ コード
02.Just A Little Bit - cover by サザンヴィンテージーズバンド
→ コード
03.Tiny Bubbles(type-B)
いい動画がみつかりません。こっちで聴いてね。
→ コード
04.ふたりだけのパーティー - cover by サザンヴィンテージーズバンド
→ コード
05.海 ~ 栞のテーマ - サザンオールスターズ
→ 「栞のテーマ」のコード
↓ とりあえずまとめてみました。トーシロなんで間違いあるかも(笑)
〔三和音/トライアド〕
・三和音には4種類。(例はルート音がド(C)の場合)
1.メジャー・トライアド 【C】(長三和音):
ド、ミ、ソ / C、E、G / ルート+長3度+完全5度
2.マイナー・トライアド 【Cm】(短三和音):
ド、ミ♭、ソ /C、E♭、G / ルート+短3度+完全5度
3.オーギュメント・トライアド 【Caug、C+】(増三和音):
ド、ミ、ソ# /C、E、G# / ルート+長3度+増5度
4.ディミニッシュ・トライアド 【Cdim、Cº】(減三和音):
ド、ミ♭、ソ♭ / C、E♭、G♭ / ルート+短3度+減5度
・3度は音の明暗を決めるので、ここに長短がつくことでメジャー・マイナーに分かれる。
・5度は音の安定度を決めるので、ここに増減がつくことで不安定感が出る。(だからaug(増5)やdim(減5)は不安定感のあるコードとされる。)
・完全系の音程は1、4、5、8度でふつう完全、増、減であらわす。長短系の音程は2、3、6、7度で、ふつう長、短であらわす。(減7度など例外あり)
・絶対協和音程は完全1度と完全8度。協和音程は完全5度と完全4度。不完全協和音程は長3度、短3度、長6度、短6度。それ以外は不協和音程。
〔四和音/セブンス〕 (例はルート音がド(C)の場合)
・三和音(1度(ルート)、3度、5度/トライアド)+1音(7度の音)=四和音(1度(ルート)、3度、5度、7度)≒セブンス
1.メジャー・セブンス 【Cmaj7、CM7、C△7】(長七の和音):
ド、ミ、ソ、シ / C、E、G、B / ルート+長3度+完全5度+長7度
(メジャー・トライアド + ルートの半音下の音(長7度(M7)))
2.(ドミナント・)セブンス 【C7】(属七の和音):
ド、ミ、ソ、シ♭ / C、E、G、B♭ / ルート+長3度+完全5度+短7度
(メジャー・トライアド + ルート短7度(m7))
3.マイナー・メジャーセブンス 【CmM7、Cm△7】:
ド、ミ♭、ソ、シ / C、E♭、G、B / ルート+短3度+完全5度+長7度
(マイナー・トライアド + ルート長7度(M7))※ラインクリシェに重用
4.マイナー・セブンス 【Cm7】(短七の和音):
ド、ミ♭、ソ、シ♭ / C、E♭、G、B♭ / ルート+短3度+完全5度+短7度
(マイナー・トライアド + ルート短7度(m7)、)
5.メジャーセブンス・オーギュメント 【CM7aug、C△7+】:
ド、ミ、ソ#、シ / C、E、G#、B / ルート+長3度+増5度+長7度
(オーギュメント・トライアド + ルート長7度(M7))
6.セブンス・オーギュメント 【C7aug、C7+】:
ド、ミ、ソ#、シ♭ / C、E、G#、B♭ / ルート+長3度+増5度+短7度
(オーギュメント・トライアド + ルート短7度(m7))
7.マイナー・セブンス・フラット・ファイブ/ハーフディミニッシュ 【Cm7(b5)、Cm7-5】(減五短七の和音)
ド、ミ♭、ソ♭、シ♭ / C、E♭、G♭、B♭ / ルート+短3度+減5度+短7度
(ディミニッシュ・トライアド + ルート短7度(m7))
8.ディミニッシュ・セブンス 【Cdim(7)、Cº(7)】(減七の和音):
ド、ミ♭、ソ♭、ラ / C、E♭、G♭、A / ルート+短3度+減5度+減7度
(ディミニッシュ・トライアド + ルート減7度 or 長6度)
〔三度堆積和音以外のコード〕 (例はルート音がド(C)の場合)
・三度堆積和音=ルート、3度、5度、7度、9度、11度、13度と奇数で重なっていく和音。
1.サスフォー 【Csus4】:
ド、ファ、ソ / C、F、G / ルート+完全4度+完全5度
(メジャー・トライアドの長3度を完全4度(ファ・F)に置き換えたもの)
※ふつうはメジャートライアドとあわせて使う。
2.セブンス・サスフォー 【C7sus4】:
ド、ファ、ソ、シ / C、F、G、B♭ / ルート+完全4度+完全5度+短7度
(サスフォー + ルート短7度(m7))
※セブンスの代理コード(ドミナント絡み)としてよく使われる。
3.シックス(ス) 【C6】:
ド、ミ、ソ、ラ / C、E、G、A / ルート+長3度+完全5度+長6度
(マイナー・セブンスを1オクターブ上に展開)
4.マイナー・シックス(ス) 【Cm6】:
ド、ミ♭、ソ、ラ / C、E♭、G、A / ルート+短3度+完全5度+長6度
(マイナー・トライアド + 長6度)
〔テンション・ノート〕
・ルート、3rd、5th、7thなどの基本構成音(コード・トーン)に、ルートから9th(ナインス)、11th(イレブンス)、13th(サーティーンス)などの音を加えたもの。
・ルートがCの場合、9thのレ(9)、レ♯(♯9)、レ♭(♭9)、11thのファ(11)、ファ♯(♯11)、13thのラ(13)、ラ♭(♭13)の7種類。
・主にセブンス・コードに付加されるといわれる。
■ アドナインス 【Cadd9】:
ド、ミ、ソ、レ / C、E、G、D / ルート+長3度+完全5度+長9度
(メジャー・トライアド + 長9度)
〔オンコード(分数コード)〕 【C/E、ConEなど】:
・分子はコード、分母はベース音(最低音)をさし、たとえばC/E(ConE)の場合、Cコード(ド、ミ、ソ) + ベース音E(ミ)。
・クリシェ(コードが進むごとに半音ずつベース音を上下させていく音進行)、ペダルポイント(ベース音を保持すること)、IIm7onVの形ではドミナント・セブンス(V7)の代理コード*などに使われる。
* C → Am → G7 → Cの代理として、C → Am → Dm7onG → C。
Dm7onGは G7よりもドミナント(解消したい不安定さ、C(トニック)に戻ると安心)の効きがマイルドなので、”優しいドミナント”ともいわれる。
-------------------------------
実際はこれにコード進行が加わってさらに複雑怪奇になっていくのですが、セブンス系のおサレ曲はトゥ・ファイブ・ワン・シックス(Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ-Ⅵ)進行(Dm7 - G7sus4 - Cmaj7 - Am7の循環コード進行とか)やドミナントモーション絡みの進行が多いと思う。あと、バックドアドミナント進行とか・・・。
むずかしすぎてよくわからんけど・・・(笑)
コード進行についても、もう少しおべんきょしてから書き足してみます。
■ 王道進行(未練進行)〔4536〕の代表曲といわれる「 いとしのエリー」。
コード
売れるべくして売れた? 強力なコード進行。
それと、ナインスがいいところで効きまくってる。
■ TSUNAMI - Cover by Ai Ninomiya
コード
Aメロ、Bメロ、サビでそれぞれ異なるコード進行だと思う。あと、クリシェとBメロ前の転調。
この人、やたらにうまい!
と思ったら、プロか・・・。カラバトで99.578出してる。
■ 夕陽に別れを告げて - サザンオールスターズ
コード
個人的に、なんとなく「TSUNAMI」の原曲のような気がしている曲。
情感入りまくりのメロとか、サスフォーの入れ込み方とか・・・。
『KAMAKURA』収録。サザン屈指の名曲では?
↑ 1985年の秋。就職も決まって、遊びまくった(笑)大学生活もあと半年・・・。
鎌倉や湘南は通ったので、
↓ の杏里の曲とともにリアルタイムできもちに染みていた曲だと思う。
「鎌倉の陽よさよなら・・・」とか「結んだTシャツほどく・・・」とか
絶妙なメロディラインに乗っているさりげな泣きフレーズ。
■ LONG ISLAND BEACH - ANRI
→ 杏里の名バラード20曲!
〔 コードの件で追加 〕
でも、大学生の当時、一番聴き込んでいた邦楽アーティストはやっぱり佐野元春かな。
■ 佐野元春 グッドタイムス&バッドタイムス
コード
メジャー・セブンスに、マイナー・メジャーセブンスやシックススが絶妙に絡んでる。
濡れた歩道にさざめく(G G6 Gmaj7 G6)
もう何も言わないで(F Em7-5 Dmaj7 Am7 D7)
↑ たまらん(笑)
■ NHK-FM サウンドストリート 佐野元春(ゲスト:桑田佳祐)1983.5.16
1983年の佐野元春&桑田佳祐。
貴重すぎる収録!
〔関連記事〕
■ ザ・カセットテープ・ミュージック
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】
※ 女神系歌姫とは? → こちら
以前別ブログにUPした「女神系歌姫」たち100人以上の動画を、リンクつなぎなおしコメントを補足してUPしていきます。
リストした曲は個人的に好みのテイクで、かならずしも代表曲というワケではありません。
掲載順は順不同ですが、元ブログの掲載順を踏襲し適宜追加しています。
50人(曲)1セットで構成します。
アマチュアの歌い手さんも入ってますが、敬称略としています。あしからず。
■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】
■ 女神系歌姫-2 【 Angel Voice列伝 51-100 】
**************
01.癒月(ゆづき) - you 【ひぐらしのなく頃に】
奈良県出身のArtist&Creator。2007年頃から活動開始。
dai作曲の名作「you」の初代Vo.および作詞を担当。
Yukiと共にユニット「雪月」を結成。
メリハリがありながらヒーリング感を備えたすぐれた声質をもつ。
02.織田かおり - Yume no Tsubasa/FictionJunction Yuki Kajiura LIVE vol.#4 PART II
神奈川県出身のVocalist。2007年ソロデビュー。
2013年頃から活動を本格化させアニメやゲームのテーマ曲に参画。
梶浦由記のFictionJunctionや“Revo”のSound Horizonの主要メンバーでもある。
表現力とパワーを備えたVocalで、その実力は逸材揃いのFictionJunctionのLIVEでも際立っている。
03.池田綾子 - 心の糸 【Flower PS3 game】
神奈川県出身のシンガーソングライター。2002年2月メジャーデビュー。
武蔵野音大声楽科卒の本格派でその幅広い音楽性とエモーショナルな歌唱力には定評がある。
自然保護活動や伝統文化系ライブなど多彩なステージで活躍。
04.MARlNA - One love ~恋におちて~
プロフィール不詳。
微妙にビブラートがかった艶のある声質をもち、エモーショナルな存在感がある実力派Artist。声量もあると思う。→「夢にみる明日」feat SHUNNAY (from ONE)
05.中村舞子 - 桜 (Covered)
フィリピン生まれでのちに埼玉県で育つ。
2011年メジャーデビューを果たし、セツナ系の代表格とされるR&B系Artist。
すこぶる伸びのよいフェミニンなハイトーンヴォイスをもち、表現力も抜群の逸材。featやコラボ多数で佳曲も多い。
→ セツナ系の代表曲「Because」(LGYankees Feat.)
→ ■ 中村舞子の名バラード20曲
06.茶太 - 夏影 ~Airness~
福島県出身のVocalist。2003年に初の自主制作CDを発表し、主に同人音楽やゲーム・アニメの主題歌の歌い手として知られる。音系同人サークル「ウサギキノコ」を主催。
片霧烈火・霜月はるかと3人で組む「しもちゃみん」は、美声ユニットとして知られる。
かわいい感じのやわらかな声質で癒し系。
07.Hitomi(黒石ひとみ) - PLANETES
石川県金沢市出身のシンガーソングライター。1989年頃からメジャー活動開始。
シンガーとしての活動時は”Hitomi”名義となる。
藤原麻紀・山本由紀とDolce Triade(ドルチェ トリアデ)という音楽制作ユニットを組んでいたこともある。
幅広い音楽性をもち、浮遊感とヒーリング感覚あふれるたおやかな声質は「エンジェル・フェザー・ボイス」とも呼ばれる。
これはアニメ『プラネテス』のテーマソングで声質を活かしたスケール感のある佳曲に仕上がっている。
08.Sachi Tainaka(タイナカ彩智) - Saikou no Kataomoi (最高の片想い) 【彩雲国物語ED】 - Live 2007 Concert
兵庫県出身のシンガソングライター。2006年「タイナカサチ」名義でメジャーデビュー。
2010年から「タイナカ彩智」表記。
姉は東京芸大学声楽科卒・同大学院オペラ科修了の声楽家、田井中悠美でコラボコンサートも開催。
3オクターブ半ともいわれる広い声域と透明感&伸びのある優れた声質をもつ。
ライブハウスでの実績豊富な実力派で、LIVEパフォーマンスに定評がある模様。
09.戸松遥 - secret base ~君がくれたもの~ (10-yrs-after ver) w / 茅野愛衣・早見沙織
愛知県出身の声優、女優、シンガー。
2005-2006年「ミュージックレイン スーパー声優オーディション」選抜。
2009年1stALBUMリリース。
同年2009年に寿美菜子・高垣彩陽・豊崎愛生とともに声優ユニット「スフィア/sphere」を結成している。
歌唱力のある声優との競演が多く、声優シンガーのレベルの高さを示す名演多し。
声質は素直でUPチューンも多い。
10.志方あきこ - Erato
東京都出身のシンガーソングライター。
2001年同人音楽サークル「VAGRANCY」からミニアルバム第1盤をリリース。
作風と同様ナゾの多い?Artist。
どちらかというとシリアスな作風だが、ときおり創り出すヒーリング系楽曲では天才的な切れ味と圧倒的な完成度をみせ、希有の才能をもっているとみられる。
透明感&浮遊感あふれるハイトーンヴォイスも魅力。
→ 葉加瀬太郎との競演「Ave Maria」 名テイクです。
11.くゆり - 君の知らない物語 (歌ってみた)
2010年からWebをメインに活動するシンガー。プロフィール詳細は不明。
これまで聴いたなかでは、(いまだに)個人的にベストと思われる「君の知らない物語」。
抜群の透明感とブレスどり。
小刻みにかましてくるヒーカップと、立ち上がりの速いビブラートがキレッキレ。
この難曲を最後まで破綻することなく見事に歌い切っている。
12.西野カナ - 君って
三重県松阪市のメジャーシンガー。2008年2月メジャー・デビュー。
安定したハイトーンヴォイスをもつ実力派で、抜群のメロディラインのヒット曲多数。
とくに2009年から2015年にかけての怒濤のヒット曲連打とファッションリーダーとしての存在感は、同世代の女性に大きな影響を与えたといわれる。
いわゆる「セツナ系」に入ると思うが、クラブ系やR&B系など、それだけには括り切れない幅広い音楽性をもつ。
2019年2月3日から惜しくも無期限活動休止に入ったが、自身の公式YouTubeアカウントで多くのLIVE動画が公開され、その卓越したLIVEパフォーマンスが再評価されている。
13.霜月はるか - Ruri no Tori (2020 Birthday and 15th Anniversary Live)
宮城県出身、東京都育ちの女性シンガーソングライター。
2001年同人サークル「Maple Leaf」、「tieLeaf」名義で同人音楽活動を開始。
同人系のマルチArtistで作詞・作曲、編曲も多才にこなし、ゲーム・アニメ作品の主題歌も多数手掛ける。
Revoと親交があり、Sound Horizonにゲスト参加も。
とくにPCゲーム系の作品が多く、プログレ的な複雑な曲調にフェミニンで透明感のあるヴォーカルを乗せる。
14.富金原佑菜 - 流星群 (Covered) 2018/09/17 あべのAステージ
愛知県出身の若手シンガーソングライター。
2017年頃からテレビ東京「カラオケバトル」、テレビ朝日「音楽チャンプ」などに複数回出演して好演。
2021年秋~TVアニメ『境界戦機』EDテーマも担当し、活動を活発化させている。
声の成分が多彩だし響きが強い。やっぱりきっと倍音もってる。
細かな音符や休符を散りばめたような粒立ちとキレ。そして、わき上がってくるエモーション。
こういうスケールの大きい曲を、キレ味するどく歌いあげられる才能、そうはいないと思う。
→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク
15.KOKIA - 孤独な生きもの (KOKIA CONCERT TOUR 2010)
東京都出身のシンガーソングライターで、国際的に幅広い分野で活動する個性派Artist。
大学在学中の1998年にすでにメジャーデビュー。
桐朋学園大学音楽学部卒でクラシックをベースにもち、クラシカルかつメッセージ性の高い佳曲を多数もつ。
安定感&説得力のあるヒーリングヴォイスで、J-POPのレベルの高さを世界に発信できる逸材。
音楽で人を救うことができる希有のアーティストだと思う。
→ KOKIAの名バラード12曲
16.藤田麻衣子 - Shunkan (瞬間)
名古屋出身のシンガソングライターで、2006年9月CDデビュー。
以降作品リリースを重ね、ゲーム・アニメ主題歌も多数手がける。
作曲・アレンジに天才的なキレをもち、小柄な体型からは想像できない歌唱力も。
ドラマティックかつエモーショナルな佳曲多数で「泣き歌の女王」の異名をもつ。
17.吉岡亜衣加 - 消えない虹 【薄桜鬼 黎明録ED】
静岡県出身の女性シンガーソングライターで2009年デビューアルバムをリリース。
PCゲーム系のテーマソングも多数手がける。
高い声域と透明感あふれるすぐれた声質をもつ。
18.熊田このは - 手と手(オリジナル曲) 2019-12-30 大坂ESAKA MUSE
福島県郡山市出身のシンガー。2017/03/29OAの「カラオケバトル」初出場でいきなり優勝し、以降「カラオケバトル」の常連となる。
現在、大学で音楽を専攻しLIVEなどの音楽活動は休止している。
比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎは絶対セラピー効果あると思う。
高音の美しさと空に舞い上がるような透明感&高揚感。
せつなさを湛えながら、聴き手のきもちを前向きにさせるその歌唱は唯一無二のもの。
書き始めるとキリがなくなるので→こちら(熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2)をみてね。
19.川田まみ - For our days
札幌市出身のシンガーで、2001年から札幌の音楽制作集団「I've」のメインヴォーカリストとして活躍。
2005年2月メジャーデビューし、自身の作品のほかPCゲームやアニメなどのテーマ曲など多くの作品を残す。
2016年2月、年内をもって歌手活動引退を発表している。
独特のビブラートとヒーカップが織りなす、聴き応えのあるハイトーンは定評があった。
20.花たん 「栞」天野月 feat.YURiCa/花たん
名古屋市出身のシンガー。2008年2月に「ハジメテノオト」を投稿し”歌い手”デビュー。
その個性あるビブラートと美しいハイトーン、そして難曲をエモーショナルにこなす高度なテクニックで人気を博し、オリジナルアルバムやカバーアルバムもリリースしている。
”歌い手”では「花たん」、同人活動では「YURiCa」(ユリカ)を用いるが、「YURiCa/花たん」名義のものも多い。
はじめて聴いたとき何かの間違いかと思ったくらい音のつかみが巧い。
天性の「難曲キラー」ぶりは、天野月の難曲「栞」でもあますところなく発揮されている。
→ ■ 花たんの名テイク
21.みにゅ - 1/6 (歌ってみた)
2009年9月初投稿の歌い手。
投稿数が少なく、ガラス細工のように繊細な声質&唱法でちょっと曲を選ぶような気もするけど、はまったときのヒーリング感&感情の入り方はハンパじゃない。
個人的には歌い手のなかでも屈指の才能をもっていると思う。
→ 逸材!(みにゅさん特集)
22.山本千夏 - Cloe 【地球少女アルジュナ】
才人、菅野よう子の作品を何曲か歌っているが詳細不明。
クラシカルながらインパクトある菅野よう子の旋律を透明感あるハイトーンで歌いこなしている。
23.May J. - Destiny feat.STEVIE HOANG
東京都生まれ、神奈川県横浜市育ちのハーフのシンガーソングライター。
2006年12月1stシングルリリース。
声質、声量、テクとも申し分ないが、カバー曲が多くあまりに器用すぎてソツがないからか「無思想」的なコメントを受けてしまう場面も。
たしかにそういうテイクもなきにしもあらずだが、心に響くテイクだってしっかり残している。
24.みとせのりこ - 君のいる場所へ
東京都出身。主にPCゲームの主題歌を歌うマルチアーティスト。
1994年プログレ系(?)ユニット、kirche(キルシェ)にヴォーカルとして参画。
以降、ナルキとのユニットORITAなどコラボ活動も目立つ。
繊細かつ難解な曲調を澄んだ美声で唱いこなす独特な個性。
25.荒牧陽子 - 炎/LiSA を色んな人で 【歌ってみたらこんな感じ!⑧】
岡山県出身のシンガーソングライター。愛称マキタソ。
高校卒業後上京しメジャーデビューを狙うも叶わず、スタジオミュージシャンやコーラス、カラオケのガイドボーカルなどで場数を踏む。
2010年1月アルバムをリリースしているが、R&B色の強いものだった。
並はずれた力量からして、R&Bカテゴリーで勝負をかけたかったのかも知れぬ。
2011年7月19日放送の『スター☆ドラフト会議』でものまねデビュー、圧倒的な歌唱力で一躍人気ものまねシンガーとなる。
一時期紆余曲折はあったものの、これほどの才能を世間が埋もれさせておく筈はなく、近年TV出演も増えてきている。
ハスキーな低音からバイオリンのような艶のあるハイトーンまで、その声域・声質はきわめて広く、抜群の音感も兼ね備えているため、時としてオリジナルシンガーの最盛期を凌駕すると思われるパフォーマンスを展開する。
「ヴォーカル界の職人」というものがあるとすれば、この人が第一人者だと思う。
→ ■ おそるべし! マキタソ(荒牧陽子)
26.Lia - Aozora
東京都出身のシンガー。
アニソン、ゲームソングのハイトーン系シンガーの先駆けのひとり。
2000年、PCゲーム、テレビアニメ『AIR』のテーマソングを歌い、一躍人気シンガーとなる。
正直、ハイトーンの声質でLiaを凌ぐシンガーは何人も思いつくが、「鳥の詩」や「夏影」で、ヒーリング系アニソンの存在感を一気に高めた功績は計り知れない。
現在は香港に在住して活動。
27.やなぎなぎ - さよならメモリーズ
大阪府出身のシンガーソングライター。
2008年からSupercellのゲストボーカルとしてnagi名義で参画。Supercellの名曲の数々をものする。
はかなさと情感を感じさせるハイトーンヴォーカルで多くの支持を得、歌い手系フォロワー多数出現。
さすが本家だけに、ブレスどりや繊細なニュアンスの出し方がとても巧いと思う。
28.ユーズ(RAM WIRE) - きぼうのうた
千葉出身の男女3人組新鋭ユニットRAM WIREのリードVo.ユーズ。
綺麗な声質かつエモーショナルな歌いまわしでRAM WIREの楽曲にはまっていた。
2001年に活動を開始したRAM WIREは、すこぶる質の高い楽曲と繊細なアレンジが魅力でブレークの可能性もあったが、残念ながら2016年4月活動休止を発表し、ユーズはソロ活動を継続している模様。
29.Lily.- 遠く離れた場所で feat. C
2010年夏Venus-B(キングレコード)よりデビューしたセツナ系Artistでファルセット気味に抜ける高音に個性。
同レーベルに所属のLily.μとは別人と思われ、最近の動向は不明。
これは2010年7月On Saleの1st-Single。2nd-Single「気づいてよ... I Love You」もなかなかの出来。
30.新妻聖子 - NEVER ENOUGH (Covered)
※ 公式Webはリンク不可
愛知県出身のシンガー&女優。
11歳から約7年間タイで過ごし、2003年ミュージカル『レ・ミゼラブル』にオーディションで抜擢され初舞台を踏む。以降、主にミュージカル界で活動。
すこぶる綺麗で伸びのある声質と独特の情感をもち、ロングトーンとビブラートのこなしはもはや芸術。
あの葉加瀬太郎氏をして「あなたの歌は感動を与えてくれる」といわしめた逸材。
個人的にはミュージカルだけでなく、POPミュージックの世界でも幅広く活動してほしい。
→ ■ あなたの歌は感動を与えてくれる / 新妻聖子
31.riya(eufonius) - メトロクローム
eufonius(ユーフォニアス)は菊地創とriyaの音楽ユニットでアニメ、ゲームソングを中心にリリース。
ヴォーカルのriyaは透明感&ヒーリング感覚あふれるハイトーンヴォイスをもつ。
楽曲のレベルの高さも魅力。
32.川嶋あい - compass
福岡市出身のシンガーソングライター。
2002年路上ライブを開始、以降複数のヒットを出し安定した音楽活動を継続。
澄んだ声質とエモーショナルな唱法が魅力のArtistでメロディ抜群の佳曲を多数もつ。
1,000回にも及ぶ路上ライブで鍛えられた高い歌唱力にも定評あり。
33.MiKA(Daisy×Daisy) - 永久のキズナ
Daisy×Daisy(デイジーデイジー)は、2005年頃から活動を開始し現在はヴォーカルのMiKAのみのソロ・ユニット。
優れた声質とビブラートと滑舌を活かしたキレッキレの唱法をもち、この曲はじめてきいたときマキタソ(荒牧陽子)かと思った(^^)
「永遠に10歳」キャラを前面で打ち出しているが、じつはさりげに美形で天は二物を与えたか・・・。
愛媛県出身の超メジャー声優系Artistの妹という情報あり。
34.多田葵 - Brave Song 【Angel Beats!】
声優系のArtistで2005年あたりからシンガー活動を本格化。アニメ、ゲーム系への提供曲が多い。
ヒーリング感あるエンジェルヴォイス系で、これはアニメ「Angel Beats!」のエンディングテーマ。
35.堀優衣 - アイノカタチ (Covered)
往年のカラオケバトルの王者。
音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。
しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。
現在大学在学中で、音楽活動も精力的に展開している。
→ ■ 堀優衣さんコンサート 2022 "illuminate!"
→ ■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
36.夏川りみ - 月のかほり
夏川りみの声をはじめて聴いたのはたしか、水戸黄門の合間に流れていた松下グループのCM Song「この星を感じて」だったと思う。
ハイトーンが綺麗に伸びるそのボーカルは強烈なインパクトがあり、画面の下に出ていた”夏川りみ”というクレジットを頼りにCDをさがしたが、その当時はまったくのマイナーで、ごく一部の大手CDショップでシングルが見つけられただけだった。
メジャーデビューからの「南風」(2002/3)、「てぃだ~太陽・風ぬ想い~」(2002/9)、「空の風景」(2003/3)初期3枚のALBUMのできは抜群だった。
沖縄独特の音階や歌いまわしはそれほど強く出ておらず、さらりと明るい曲調に彼女の伸びやかなハイトーンが乗る内容は、まさに「ヒーリング・ミュージック」そのものだった。
この頃まではLIVEにも何度か行った。
だが、「風の道」(2004/9)あたりから次第に作風が変わり、初期のさらっと明るい曲風は姿を消して重厚なバラード主体の楽曲が増えた。
振り返ってみると、2007年9月に↑の変化についてのブログ記事を書いているので、やはり相当気に入っていたのだと思う。
これは2002年9月リリースの『てぃだ~太陽・風ぬ想い~』収録で、夏川りみの透明感あふれるハイトーンが堪能できる名曲。
37.愛美(Poppin'Party) - キズナミュージック♪
Poppin'Partyはメディアミックス作品「BanG_Dream!」に関連する声優音楽ユニット。
楽器の演奏力がさりげに高く、個人的には大橋彩香の手数の多いドラムスが好み。
ヴォーカル担当の愛美は、最近ソロ活動を再開している。
安定感のある美声で、アップテンポ曲や変拍子のこなしが巧い。
38.平野綾 - For You
名古屋市出身。アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の涼宮ハルヒの声役として知られる。
2003年、吉田有希などとともにユニット「ユニット名未定」(のちにSprings)に参画。
歌うまでルックスばっちりな声優アイドルの好例。
近年はミュージカルメインで活動中。
39.鹿乃(かの) - ハロ/ハワユ (歌ってみた)
“ロリ声”とも評されるかわいい系の歌い手(バーチャルシンガー)で、2015年5月メジャーデビュー。
公式WebのBioに「アジア圏特に中国では絶大な人気を誇る。」とあるが、たしかにこういうヴォーカル&キャラは日本ならではでは?
ハロ/ハワユは定番のボカロ曲で投稿多数だが、ここまでニュアンスの出たテイクは聴いたことがない。
40.milet - One Reason 【鹿の王 ユナと約束の旅】
思春期をカナダで過ごしたというグローバルなシンガーソングライター。
2018年頃から音楽活動を活発化。すでに複数のヒット曲をもち、東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演している。
広がりのあるメロと弾むエスニックなリズムが絡む曲調は、これまでのJ-POPにはなかったフォーマットでは。
個人的には好物の曲調。逸材だと思う。
41.春奈るな - Overfly
東京都出身のシンガーで2012年メジャーデビュー。
やや不安定な感じもあるが、高音がよく伸びビブラートのかかりも綺麗。
これは2012年11月On Saleの2nd_Single。
42.栗林みな実 - Kimi no Naka no eiyuu
静岡県出身の声優系Artistでアニソン参画多数。2002年に1stALBUMリリース。
甘さのあるハイトーンヴォイスは安定感充分で、繊細なビブラートとヒーカップのコントラストは絶品。
アップテンポ曲のキレに定評があり、この曲でもビブラート&ヒーカップがばりばりに効いている。
43.May'n(シェリル・ノーム starring May'n) - ダイアモンドクレバス
名古屋市出身。2007年中林芽依名義でデビューし、2008年May'n(メイン)に変更。
ホリプロ系だが才人、菅野よう子の作品を多数歌うなどArtist志向を強める。
透明感あふれる綺麗なハイトーンで含蓄ある優れた歌唱力も。
これは、シェリル・ノーム starring May'n名義(マクロスF)で出された人気の高い名曲。
44.@ゆいこんぬ - bouquet (歌ってみた)
2011年1月ニコ動初投稿の歌い手。
声優系の甘くやわらかなハイトーンヴォイス。微妙にゆらぐ歌声がエモーショナルで表現力高い。
doriko氏作の名ボカロ曲「bouquet」は投稿多数だが、声質を活かして華麗に仕上がったこれはベストテイクでは?
45.持田香織(Every Little Thing) - Over and Over
元子役としてテレビCMや雑誌モデルなどで活動していた持田かおりが1995年、五十嵐充、伊藤一朗と組んでEvery Little Thingを結成。
かならずしも美声とはいえないかもしれないが、声に切なさがこもって聴き手を惹きつける。
これは1999年1月27日、大ヒット曲「Time goes by」から間を置かずのシングルリリースだったが、オリコン最高位4位と大きなヒットにはいたらず「隠れた名曲」ともいわれる。
David Fosterを思わせる綺麗なメロ展開で、おそらくD~Eメロまである。
この当時の五十嵐氏のメロディメイカーぶりがよくわかる好作品。
46.KOTOKO - Imaginary Affair 【こなたよりかなたまでOP】
札幌市出身で、札幌の音楽制作集団「I've」のヴォーカリストとして活躍。
アニメやゲーム曲を多数手掛け、この分野での代表的なArtistの一人に数えられる。
ビブラートやヒーカップに頼らず、独特のブレスどりでインパクトをつくっていく独特の唱法は、アニソンのひとつのフォーマットとしてフォロワーを生んだ。
2003年12月ゲーム『こなたよりかなたまで』のOPとしてリリースされたI'veの高瀬一矢氏作曲のこの曲は、抜群のメロディラインをもつ名曲としていまだに一部で人気が高い。
KOTOKOのヴォーカル(ブレス)なくしてこの仕上がりにはならなかったと思う。
47.bakiko - ただ泣きたくなるの (歌ってみた)
声質がやたらによく、ビブラートと声の伸びが心地よい歌い手さん。
聴いていて抜けられなくなるヤミツキ感はそうとうなもの。
中山美穂のこのヒット曲は微妙なロングトーンが多くカバーが難しい難曲として知られているが、持ち味のたおやかでフェミニンな声質を活かして見事な仕上がりとなっている。
48.森恵 - 茜色の約束 (Covered)
広島県出身のシンガーソングライターで、2005年頃からストリート(路上)ライブ活動を本格化。
路上ライブで鍛え上げられた実力派で、きわめて高い歌唱力&表現力をもつ逸材。
とくにビブラートと高音の伸びが秀逸。
これは、いきものがかりのカバーでほんとうにきもちよさそに歌っている。
49.杏里/Anri - 千年の恋
1980年代初頭、飽きるほど聴き込んだ名シンガー。
杏里の歌声ってシンプルに聴こえるけど、じつは異様なフックがある。
そしてバラードでも感じるグルーヴ感。
こういう時代を超えるワン&オンリーの才能が、昨今の再評価をうみだしているのでは?
個人的には1980年代前半の楽曲に思い入れが深いが、2000年リリースのこのアルバム曲もシングルカットしてもいいくらいの素晴らしいメロディラインの名曲だった。
ピアノ&ストリングスで幕を開け、一拍置いてからのボーカルパートの入りが秀逸。
→ ■ 杏里の名バラード20曲!
50.アンジェラ・アキ(Angela Aki) - This Love
徳島県出身のシンガーソングライター。
個人的にはこれまで日本が生んだシンガーソングライターのなかで、トップの実力ではないかと思っている。
15歳で渡米し米国の音楽シーンに触れたことが、このスケール感やエモーションにつながっているのかも。
いまの米国のPOPSが失ってしまった音楽本来の魅力を、彼女はリアタイで吸収しJ-POPというかたちで昇華したのだと思う。
2005年名曲「HOME」でメジャーデビュー。以降も数々の名曲・名演を残す。
2014年8月無期限活動停止に入り渡米。
2022年1月リリースの鈴木瑛美子の配信曲に「カナリアの歌」を提供しているが、彼女自身の歌声は依然としてリリースされていない。
→ ■ アンジェラ・アキ なう!
2022年の貴重な生アンジー。
お元気そうなので、新たなセルフテイクでふたたび伝説を築いてほしい。
以下、まだまだつづきます。
以前別ブログにUPした「女神系歌姫」たち100人以上の動画を、リンクつなぎなおしコメントを補足してUPしていきます。
リストした曲は個人的に好みのテイクで、かならずしも代表曲というワケではありません。
掲載順は順不同ですが、元ブログの掲載順を踏襲し適宜追加しています。
50人(曲)1セットで構成します。
アマチュアの歌い手さんも入ってますが、敬称略としています。あしからず。
■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】
■ 女神系歌姫-2 【 Angel Voice列伝 51-100 】
**************
01.癒月(ゆづき) - you 【ひぐらしのなく頃に】
奈良県出身のArtist&Creator。2007年頃から活動開始。
dai作曲の名作「you」の初代Vo.および作詞を担当。
Yukiと共にユニット「雪月」を結成。
メリハリがありながらヒーリング感を備えたすぐれた声質をもつ。
02.織田かおり - Yume no Tsubasa/FictionJunction Yuki Kajiura LIVE vol.#4 PART II
神奈川県出身のVocalist。2007年ソロデビュー。
2013年頃から活動を本格化させアニメやゲームのテーマ曲に参画。
梶浦由記のFictionJunctionや“Revo”のSound Horizonの主要メンバーでもある。
表現力とパワーを備えたVocalで、その実力は逸材揃いのFictionJunctionのLIVEでも際立っている。
03.池田綾子 - 心の糸 【Flower PS3 game】
神奈川県出身のシンガーソングライター。2002年2月メジャーデビュー。
武蔵野音大声楽科卒の本格派でその幅広い音楽性とエモーショナルな歌唱力には定評がある。
自然保護活動や伝統文化系ライブなど多彩なステージで活躍。
04.MARlNA - One love ~恋におちて~
プロフィール不詳。
微妙にビブラートがかった艶のある声質をもち、エモーショナルな存在感がある実力派Artist。声量もあると思う。→「夢にみる明日」feat SHUNNAY (from ONE)
05.中村舞子 - 桜 (Covered)
フィリピン生まれでのちに埼玉県で育つ。
2011年メジャーデビューを果たし、セツナ系の代表格とされるR&B系Artist。
すこぶる伸びのよいフェミニンなハイトーンヴォイスをもち、表現力も抜群の逸材。featやコラボ多数で佳曲も多い。
→ セツナ系の代表曲「Because」(LGYankees Feat.)
→ ■ 中村舞子の名バラード20曲
06.茶太 - 夏影 ~Airness~
福島県出身のVocalist。2003年に初の自主制作CDを発表し、主に同人音楽やゲーム・アニメの主題歌の歌い手として知られる。音系同人サークル「ウサギキノコ」を主催。
片霧烈火・霜月はるかと3人で組む「しもちゃみん」は、美声ユニットとして知られる。
かわいい感じのやわらかな声質で癒し系。
07.Hitomi(黒石ひとみ) - PLANETES
石川県金沢市出身のシンガーソングライター。1989年頃からメジャー活動開始。
シンガーとしての活動時は”Hitomi”名義となる。
藤原麻紀・山本由紀とDolce Triade(ドルチェ トリアデ)という音楽制作ユニットを組んでいたこともある。
幅広い音楽性をもち、浮遊感とヒーリング感覚あふれるたおやかな声質は「エンジェル・フェザー・ボイス」とも呼ばれる。
これはアニメ『プラネテス』のテーマソングで声質を活かしたスケール感のある佳曲に仕上がっている。
08.Sachi Tainaka(タイナカ彩智) - Saikou no Kataomoi (最高の片想い) 【彩雲国物語ED】 - Live 2007 Concert
兵庫県出身のシンガソングライター。2006年「タイナカサチ」名義でメジャーデビュー。
2010年から「タイナカ彩智」表記。
姉は東京芸大学声楽科卒・同大学院オペラ科修了の声楽家、田井中悠美でコラボコンサートも開催。
3オクターブ半ともいわれる広い声域と透明感&伸びのある優れた声質をもつ。
ライブハウスでの実績豊富な実力派で、LIVEパフォーマンスに定評がある模様。
09.戸松遥 - secret base ~君がくれたもの~ (10-yrs-after ver) w / 茅野愛衣・早見沙織
愛知県出身の声優、女優、シンガー。
2005-2006年「ミュージックレイン スーパー声優オーディション」選抜。
2009年1stALBUMリリース。
同年2009年に寿美菜子・高垣彩陽・豊崎愛生とともに声優ユニット「スフィア/sphere」を結成している。
歌唱力のある声優との競演が多く、声優シンガーのレベルの高さを示す名演多し。
声質は素直でUPチューンも多い。
10.志方あきこ - Erato
東京都出身のシンガーソングライター。
2001年同人音楽サークル「VAGRANCY」からミニアルバム第1盤をリリース。
作風と同様ナゾの多い?Artist。
どちらかというとシリアスな作風だが、ときおり創り出すヒーリング系楽曲では天才的な切れ味と圧倒的な完成度をみせ、希有の才能をもっているとみられる。
透明感&浮遊感あふれるハイトーンヴォイスも魅力。
→ 葉加瀬太郎との競演「Ave Maria」 名テイクです。
11.くゆり - 君の知らない物語 (歌ってみた)
2010年からWebをメインに活動するシンガー。プロフィール詳細は不明。
これまで聴いたなかでは、(いまだに)個人的にベストと思われる「君の知らない物語」。
抜群の透明感とブレスどり。
小刻みにかましてくるヒーカップと、立ち上がりの速いビブラートがキレッキレ。
この難曲を最後まで破綻することなく見事に歌い切っている。
12.西野カナ - 君って
三重県松阪市のメジャーシンガー。2008年2月メジャー・デビュー。
安定したハイトーンヴォイスをもつ実力派で、抜群のメロディラインのヒット曲多数。
とくに2009年から2015年にかけての怒濤のヒット曲連打とファッションリーダーとしての存在感は、同世代の女性に大きな影響を与えたといわれる。
いわゆる「セツナ系」に入ると思うが、クラブ系やR&B系など、それだけには括り切れない幅広い音楽性をもつ。
2019年2月3日から惜しくも無期限活動休止に入ったが、自身の公式YouTubeアカウントで多くのLIVE動画が公開され、その卓越したLIVEパフォーマンスが再評価されている。
13.霜月はるか - Ruri no Tori (2020 Birthday and 15th Anniversary Live)
宮城県出身、東京都育ちの女性シンガーソングライター。
2001年同人サークル「Maple Leaf」、「tieLeaf」名義で同人音楽活動を開始。
同人系のマルチArtistで作詞・作曲、編曲も多才にこなし、ゲーム・アニメ作品の主題歌も多数手掛ける。
Revoと親交があり、Sound Horizonにゲスト参加も。
とくにPCゲーム系の作品が多く、プログレ的な複雑な曲調にフェミニンで透明感のあるヴォーカルを乗せる。
14.富金原佑菜 - 流星群 (Covered) 2018/09/17 あべのAステージ
愛知県出身の若手シンガーソングライター。
2017年頃からテレビ東京「カラオケバトル」、テレビ朝日「音楽チャンプ」などに複数回出演して好演。
2021年秋~TVアニメ『境界戦機』EDテーマも担当し、活動を活発化させている。
声の成分が多彩だし響きが強い。やっぱりきっと倍音もってる。
細かな音符や休符を散りばめたような粒立ちとキレ。そして、わき上がってくるエモーション。
こういうスケールの大きい曲を、キレ味するどく歌いあげられる才能、そうはいないと思う。
→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク
15.KOKIA - 孤独な生きもの (KOKIA CONCERT TOUR 2010)
東京都出身のシンガーソングライターで、国際的に幅広い分野で活動する個性派Artist。
大学在学中の1998年にすでにメジャーデビュー。
桐朋学園大学音楽学部卒でクラシックをベースにもち、クラシカルかつメッセージ性の高い佳曲を多数もつ。
安定感&説得力のあるヒーリングヴォイスで、J-POPのレベルの高さを世界に発信できる逸材。
音楽で人を救うことができる希有のアーティストだと思う。
→ KOKIAの名バラード12曲
16.藤田麻衣子 - Shunkan (瞬間)
名古屋出身のシンガソングライターで、2006年9月CDデビュー。
以降作品リリースを重ね、ゲーム・アニメ主題歌も多数手がける。
作曲・アレンジに天才的なキレをもち、小柄な体型からは想像できない歌唱力も。
ドラマティックかつエモーショナルな佳曲多数で「泣き歌の女王」の異名をもつ。
17.吉岡亜衣加 - 消えない虹 【薄桜鬼 黎明録ED】
静岡県出身の女性シンガーソングライターで2009年デビューアルバムをリリース。
PCゲーム系のテーマソングも多数手がける。
高い声域と透明感あふれるすぐれた声質をもつ。
18.熊田このは - 手と手(オリジナル曲) 2019-12-30 大坂ESAKA MUSE
福島県郡山市出身のシンガー。2017/03/29OAの「カラオケバトル」初出場でいきなり優勝し、以降「カラオケバトル」の常連となる。
現在、大学で音楽を専攻しLIVEなどの音楽活動は休止している。
比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎは絶対セラピー効果あると思う。
高音の美しさと空に舞い上がるような透明感&高揚感。
せつなさを湛えながら、聴き手のきもちを前向きにさせるその歌唱は唯一無二のもの。
書き始めるとキリがなくなるので→こちら(熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2)をみてね。
19.川田まみ - For our days
札幌市出身のシンガーで、2001年から札幌の音楽制作集団「I've」のメインヴォーカリストとして活躍。
2005年2月メジャーデビューし、自身の作品のほかPCゲームやアニメなどのテーマ曲など多くの作品を残す。
2016年2月、年内をもって歌手活動引退を発表している。
独特のビブラートとヒーカップが織りなす、聴き応えのあるハイトーンは定評があった。
20.花たん 「栞」天野月 feat.YURiCa/花たん
名古屋市出身のシンガー。2008年2月に「ハジメテノオト」を投稿し”歌い手”デビュー。
その個性あるビブラートと美しいハイトーン、そして難曲をエモーショナルにこなす高度なテクニックで人気を博し、オリジナルアルバムやカバーアルバムもリリースしている。
”歌い手”では「花たん」、同人活動では「YURiCa」(ユリカ)を用いるが、「YURiCa/花たん」名義のものも多い。
はじめて聴いたとき何かの間違いかと思ったくらい音のつかみが巧い。
天性の「難曲キラー」ぶりは、天野月の難曲「栞」でもあますところなく発揮されている。
→ ■ 花たんの名テイク
21.みにゅ - 1/6 (歌ってみた)
2009年9月初投稿の歌い手。
投稿数が少なく、ガラス細工のように繊細な声質&唱法でちょっと曲を選ぶような気もするけど、はまったときのヒーリング感&感情の入り方はハンパじゃない。
個人的には歌い手のなかでも屈指の才能をもっていると思う。
→ 逸材!(みにゅさん特集)
22.山本千夏 - Cloe 【地球少女アルジュナ】
才人、菅野よう子の作品を何曲か歌っているが詳細不明。
クラシカルながらインパクトある菅野よう子の旋律を透明感あるハイトーンで歌いこなしている。
23.May J. - Destiny feat.STEVIE HOANG
東京都生まれ、神奈川県横浜市育ちのハーフのシンガーソングライター。
2006年12月1stシングルリリース。
声質、声量、テクとも申し分ないが、カバー曲が多くあまりに器用すぎてソツがないからか「無思想」的なコメントを受けてしまう場面も。
たしかにそういうテイクもなきにしもあらずだが、心に響くテイクだってしっかり残している。
24.みとせのりこ - 君のいる場所へ
東京都出身。主にPCゲームの主題歌を歌うマルチアーティスト。
1994年プログレ系(?)ユニット、kirche(キルシェ)にヴォーカルとして参画。
以降、ナルキとのユニットORITAなどコラボ活動も目立つ。
繊細かつ難解な曲調を澄んだ美声で唱いこなす独特な個性。
25.荒牧陽子 - 炎/LiSA を色んな人で 【歌ってみたらこんな感じ!⑧】
岡山県出身のシンガーソングライター。愛称マキタソ。
高校卒業後上京しメジャーデビューを狙うも叶わず、スタジオミュージシャンやコーラス、カラオケのガイドボーカルなどで場数を踏む。
2010年1月アルバムをリリースしているが、R&B色の強いものだった。
並はずれた力量からして、R&Bカテゴリーで勝負をかけたかったのかも知れぬ。
2011年7月19日放送の『スター☆ドラフト会議』でものまねデビュー、圧倒的な歌唱力で一躍人気ものまねシンガーとなる。
一時期紆余曲折はあったものの、これほどの才能を世間が埋もれさせておく筈はなく、近年TV出演も増えてきている。
ハスキーな低音からバイオリンのような艶のあるハイトーンまで、その声域・声質はきわめて広く、抜群の音感も兼ね備えているため、時としてオリジナルシンガーの最盛期を凌駕すると思われるパフォーマンスを展開する。
「ヴォーカル界の職人」というものがあるとすれば、この人が第一人者だと思う。
→ ■ おそるべし! マキタソ(荒牧陽子)
26.Lia - Aozora
東京都出身のシンガー。
アニソン、ゲームソングのハイトーン系シンガーの先駆けのひとり。
2000年、PCゲーム、テレビアニメ『AIR』のテーマソングを歌い、一躍人気シンガーとなる。
正直、ハイトーンの声質でLiaを凌ぐシンガーは何人も思いつくが、「鳥の詩」や「夏影」で、ヒーリング系アニソンの存在感を一気に高めた功績は計り知れない。
現在は香港に在住して活動。
27.やなぎなぎ - さよならメモリーズ
大阪府出身のシンガーソングライター。
2008年からSupercellのゲストボーカルとしてnagi名義で参画。Supercellの名曲の数々をものする。
はかなさと情感を感じさせるハイトーンヴォーカルで多くの支持を得、歌い手系フォロワー多数出現。
さすが本家だけに、ブレスどりや繊細なニュアンスの出し方がとても巧いと思う。
28.ユーズ(RAM WIRE) - きぼうのうた
千葉出身の男女3人組新鋭ユニットRAM WIREのリードVo.ユーズ。
綺麗な声質かつエモーショナルな歌いまわしでRAM WIREの楽曲にはまっていた。
2001年に活動を開始したRAM WIREは、すこぶる質の高い楽曲と繊細なアレンジが魅力でブレークの可能性もあったが、残念ながら2016年4月活動休止を発表し、ユーズはソロ活動を継続している模様。
29.Lily.- 遠く離れた場所で feat. C
2010年夏Venus-B(キングレコード)よりデビューしたセツナ系Artistでファルセット気味に抜ける高音に個性。
同レーベルに所属のLily.μとは別人と思われ、最近の動向は不明。
これは2010年7月On Saleの1st-Single。2nd-Single「気づいてよ... I Love You」もなかなかの出来。
30.新妻聖子 - NEVER ENOUGH (Covered)
※ 公式Webはリンク不可
愛知県出身のシンガー&女優。
11歳から約7年間タイで過ごし、2003年ミュージカル『レ・ミゼラブル』にオーディションで抜擢され初舞台を踏む。以降、主にミュージカル界で活動。
すこぶる綺麗で伸びのある声質と独特の情感をもち、ロングトーンとビブラートのこなしはもはや芸術。
あの葉加瀬太郎氏をして「あなたの歌は感動を与えてくれる」といわしめた逸材。
個人的にはミュージカルだけでなく、POPミュージックの世界でも幅広く活動してほしい。
→ ■ あなたの歌は感動を与えてくれる / 新妻聖子
31.riya(eufonius) - メトロクローム
eufonius(ユーフォニアス)は菊地創とriyaの音楽ユニットでアニメ、ゲームソングを中心にリリース。
ヴォーカルのriyaは透明感&ヒーリング感覚あふれるハイトーンヴォイスをもつ。
楽曲のレベルの高さも魅力。
32.川嶋あい - compass
福岡市出身のシンガーソングライター。
2002年路上ライブを開始、以降複数のヒットを出し安定した音楽活動を継続。
澄んだ声質とエモーショナルな唱法が魅力のArtistでメロディ抜群の佳曲を多数もつ。
1,000回にも及ぶ路上ライブで鍛えられた高い歌唱力にも定評あり。
33.MiKA(Daisy×Daisy) - 永久のキズナ
Daisy×Daisy(デイジーデイジー)は、2005年頃から活動を開始し現在はヴォーカルのMiKAのみのソロ・ユニット。
優れた声質とビブラートと滑舌を活かしたキレッキレの唱法をもち、この曲はじめてきいたときマキタソ(荒牧陽子)かと思った(^^)
「永遠に10歳」キャラを前面で打ち出しているが、じつはさりげに美形で天は二物を与えたか・・・。
愛媛県出身の超メジャー声優系Artistの妹という情報あり。
34.多田葵 - Brave Song 【Angel Beats!】
声優系のArtistで2005年あたりからシンガー活動を本格化。アニメ、ゲーム系への提供曲が多い。
ヒーリング感あるエンジェルヴォイス系で、これはアニメ「Angel Beats!」のエンディングテーマ。
35.堀優衣 - アイノカタチ (Covered)
往年のカラオケバトルの王者。
音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。
しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。
現在大学在学中で、音楽活動も精力的に展開している。
→ ■ 堀優衣さんコンサート 2022 "illuminate!"
→ ■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
36.夏川りみ - 月のかほり
夏川りみの声をはじめて聴いたのはたしか、水戸黄門の合間に流れていた松下グループのCM Song「この星を感じて」だったと思う。
ハイトーンが綺麗に伸びるそのボーカルは強烈なインパクトがあり、画面の下に出ていた”夏川りみ”というクレジットを頼りにCDをさがしたが、その当時はまったくのマイナーで、ごく一部の大手CDショップでシングルが見つけられただけだった。
メジャーデビューからの「南風」(2002/3)、「てぃだ~太陽・風ぬ想い~」(2002/9)、「空の風景」(2003/3)初期3枚のALBUMのできは抜群だった。
沖縄独特の音階や歌いまわしはそれほど強く出ておらず、さらりと明るい曲調に彼女の伸びやかなハイトーンが乗る内容は、まさに「ヒーリング・ミュージック」そのものだった。
この頃まではLIVEにも何度か行った。
だが、「風の道」(2004/9)あたりから次第に作風が変わり、初期のさらっと明るい曲風は姿を消して重厚なバラード主体の楽曲が増えた。
振り返ってみると、2007年9月に↑の変化についてのブログ記事を書いているので、やはり相当気に入っていたのだと思う。
これは2002年9月リリースの『てぃだ~太陽・風ぬ想い~』収録で、夏川りみの透明感あふれるハイトーンが堪能できる名曲。
37.愛美(Poppin'Party) - キズナミュージック♪
Poppin'Partyはメディアミックス作品「BanG_Dream!」に関連する声優音楽ユニット。
楽器の演奏力がさりげに高く、個人的には大橋彩香の手数の多いドラムスが好み。
ヴォーカル担当の愛美は、最近ソロ活動を再開している。
安定感のある美声で、アップテンポ曲や変拍子のこなしが巧い。
38.平野綾 - For You
名古屋市出身。アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の涼宮ハルヒの声役として知られる。
2003年、吉田有希などとともにユニット「ユニット名未定」(のちにSprings)に参画。
歌うまでルックスばっちりな声優アイドルの好例。
近年はミュージカルメインで活動中。
39.鹿乃(かの) - ハロ/ハワユ (歌ってみた)
“ロリ声”とも評されるかわいい系の歌い手(バーチャルシンガー)で、2015年5月メジャーデビュー。
公式WebのBioに「アジア圏特に中国では絶大な人気を誇る。」とあるが、たしかにこういうヴォーカル&キャラは日本ならではでは?
ハロ/ハワユは定番のボカロ曲で投稿多数だが、ここまでニュアンスの出たテイクは聴いたことがない。
40.milet - One Reason 【鹿の王 ユナと約束の旅】
思春期をカナダで過ごしたというグローバルなシンガーソングライター。
2018年頃から音楽活動を活発化。すでに複数のヒット曲をもち、東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演している。
広がりのあるメロと弾むエスニックなリズムが絡む曲調は、これまでのJ-POPにはなかったフォーマットでは。
個人的には好物の曲調。逸材だと思う。
41.春奈るな - Overfly
東京都出身のシンガーで2012年メジャーデビュー。
やや不安定な感じもあるが、高音がよく伸びビブラートのかかりも綺麗。
これは2012年11月On Saleの2nd_Single。
42.栗林みな実 - Kimi no Naka no eiyuu
静岡県出身の声優系Artistでアニソン参画多数。2002年に1stALBUMリリース。
甘さのあるハイトーンヴォイスは安定感充分で、繊細なビブラートとヒーカップのコントラストは絶品。
アップテンポ曲のキレに定評があり、この曲でもビブラート&ヒーカップがばりばりに効いている。
43.May'n(シェリル・ノーム starring May'n) - ダイアモンドクレバス
名古屋市出身。2007年中林芽依名義でデビューし、2008年May'n(メイン)に変更。
ホリプロ系だが才人、菅野よう子の作品を多数歌うなどArtist志向を強める。
透明感あふれる綺麗なハイトーンで含蓄ある優れた歌唱力も。
これは、シェリル・ノーム starring May'n名義(マクロスF)で出された人気の高い名曲。
44.@ゆいこんぬ - bouquet (歌ってみた)
2011年1月ニコ動初投稿の歌い手。
声優系の甘くやわらかなハイトーンヴォイス。微妙にゆらぐ歌声がエモーショナルで表現力高い。
doriko氏作の名ボカロ曲「bouquet」は投稿多数だが、声質を活かして華麗に仕上がったこれはベストテイクでは?
45.持田香織(Every Little Thing) - Over and Over
元子役としてテレビCMや雑誌モデルなどで活動していた持田かおりが1995年、五十嵐充、伊藤一朗と組んでEvery Little Thingを結成。
かならずしも美声とはいえないかもしれないが、声に切なさがこもって聴き手を惹きつける。
これは1999年1月27日、大ヒット曲「Time goes by」から間を置かずのシングルリリースだったが、オリコン最高位4位と大きなヒットにはいたらず「隠れた名曲」ともいわれる。
David Fosterを思わせる綺麗なメロ展開で、おそらくD~Eメロまである。
この当時の五十嵐氏のメロディメイカーぶりがよくわかる好作品。
46.KOTOKO - Imaginary Affair 【こなたよりかなたまでOP】
札幌市出身で、札幌の音楽制作集団「I've」のヴォーカリストとして活躍。
アニメやゲーム曲を多数手掛け、この分野での代表的なArtistの一人に数えられる。
ビブラートやヒーカップに頼らず、独特のブレスどりでインパクトをつくっていく独特の唱法は、アニソンのひとつのフォーマットとしてフォロワーを生んだ。
2003年12月ゲーム『こなたよりかなたまで』のOPとしてリリースされたI'veの高瀬一矢氏作曲のこの曲は、抜群のメロディラインをもつ名曲としていまだに一部で人気が高い。
KOTOKOのヴォーカル(ブレス)なくしてこの仕上がりにはならなかったと思う。
47.bakiko - ただ泣きたくなるの (歌ってみた)
声質がやたらによく、ビブラートと声の伸びが心地よい歌い手さん。
聴いていて抜けられなくなるヤミツキ感はそうとうなもの。
中山美穂のこのヒット曲は微妙なロングトーンが多くカバーが難しい難曲として知られているが、持ち味のたおやかでフェミニンな声質を活かして見事な仕上がりとなっている。
48.森恵 - 茜色の約束 (Covered)
広島県出身のシンガーソングライターで、2005年頃からストリート(路上)ライブ活動を本格化。
路上ライブで鍛え上げられた実力派で、きわめて高い歌唱力&表現力をもつ逸材。
とくにビブラートと高音の伸びが秀逸。
これは、いきものがかりのカバーでほんとうにきもちよさそに歌っている。
49.杏里/Anri - 千年の恋
1980年代初頭、飽きるほど聴き込んだ名シンガー。
杏里の歌声ってシンプルに聴こえるけど、じつは異様なフックがある。
そしてバラードでも感じるグルーヴ感。
こういう時代を超えるワン&オンリーの才能が、昨今の再評価をうみだしているのでは?
個人的には1980年代前半の楽曲に思い入れが深いが、2000年リリースのこのアルバム曲もシングルカットしてもいいくらいの素晴らしいメロディラインの名曲だった。
ピアノ&ストリングスで幕を開け、一拍置いてからのボーカルパートの入りが秀逸。
→ ■ 杏里の名バラード20曲!
50.アンジェラ・アキ(Angela Aki) - This Love
徳島県出身のシンガーソングライター。
個人的にはこれまで日本が生んだシンガーソングライターのなかで、トップの実力ではないかと思っている。
15歳で渡米し米国の音楽シーンに触れたことが、このスケール感やエモーションにつながっているのかも。
いまの米国のPOPSが失ってしまった音楽本来の魅力を、彼女はリアタイで吸収しJ-POPというかたちで昇華したのだと思う。
2005年名曲「HOME」でメジャーデビュー。以降も数々の名曲・名演を残す。
2014年8月無期限活動停止に入り渡米。
2022年1月リリースの鈴木瑛美子の配信曲に「カナリアの歌」を提供しているが、彼女自身の歌声は依然としてリリースされていない。
→ ■ アンジェラ・アキ なう!
2022年の貴重な生アンジー。
お元気そうなので、新たなセルフテイクでふたたび伝説を築いてほしい。
以下、まだまだつづきます。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 堀優衣さんコンサート 2022 "illuminate!"
堀優衣さんのコンサート情報です。
■ 堀優衣コンサート2022 "illuminate!"
2022/11/3(木・祝)
Veats Shibuya(渋谷区宇田川町)
14:00~ 18:00~ の2部構成
ワンマンライブで生バンドが入ります。
詳細は→こちら。
チケット購入方法はこちら ↓
めちゃくちゃわかりやすいんですけど・・・。
やっぱり優衣ちゃん賢いわ。
アナウンスも聴きとりやすいし。
リクルート、引く手あまただったのでは?
当日、所用があって行けないけど、動画配信・アーカイブないのかな?
あったら当然購入するけど。
■ 最新の動画
果てなく続くストーリー / MISIA (Covered by 堀優衣) 《NHK ソルトレークシティオリンピックテーマ曲》【歌ってみた】Full Cover フルカバー
つやつやした声がさらに磨かれて、フェミニン・ヴォイス全開!
→ ■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
■ 堀優衣コンサート2022 "illuminate!"
2022/11/3(木・祝)
Veats Shibuya(渋谷区宇田川町)
14:00~ 18:00~ の2部構成
ワンマンライブで生バンドが入ります。
詳細は→こちら。
チケット購入方法はこちら ↓
めちゃくちゃわかりやすいんですけど・・・。
やっぱり優衣ちゃん賢いわ。
アナウンスも聴きとりやすいし。
リクルート、引く手あまただったのでは?
当日、所用があって行けないけど、動画配信・アーカイブないのかな?
あったら当然購入するけど。
■ 最新の動画
果てなく続くストーリー / MISIA (Covered by 堀優衣) 《NHK ソルトレークシティオリンピックテーマ曲》【歌ってみた】Full Cover フルカバー
つやつやした声がさらに磨かれて、フェミニン・ヴォイス全開!
→ ■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へ。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第58番 稲荷山 正眼寺(しょうげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町石廊崎18
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第29番
授与所:庫裡
山内由緒書&『こころの旅』によると、観應二年(1351年)真際によって開かれた臨済宗の寺院。
(由緒書では開山は高厳。)
すぐ下の長津呂港は良港で江戸時代に賑わい、享保年間(1716-1735年)には停泊する船は八十余隻に及び、戸数も七十五を数えたといいます。
正眼寺は一時衰退したものの、享保十八年(1733年)僧獲麟によって再興。
海事を司り、一時は正眼寺を凌ぐ繁栄をみせたという石廊崎の守源寺は、明治23年(1890年)の災害によって廃寺となり正眼寺に併合されています。
当山の左手の山腹にある般若堂は稲荷神を祀り厄除けの霊験あらたかで、広く信仰を集めるとのことです。
『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 開山無象和尚(徳治元年(1306年)示寂) 享保十八年(1733年)僧獲麟中興ス 般若堂稲荷祠倶寺域」とあります。
また、長津山守眼寺について、『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 今作守眼寺 開山蔵海和尚(應永十八年(1411年)取滅) 寺内有天神祠 明治廿三年廃寺トナリ 本尊ハ同村正眼寺ニ併ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山内
県道16号下田石廊松崎線で石廊トンネルを抜けてすこし行ったところ、県道沿いに駐車スペースがあります。
石段を登り切ると正面に本堂、右手が庫裡です。
木々生い茂る山内ですが、どことなく明るい雰囲気があるのは陽光ゆたかな南伊豆の風土ゆえでしょうか。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺の妻入りながら、左右に建物が付設されていてちょっと変わった構造になっています。
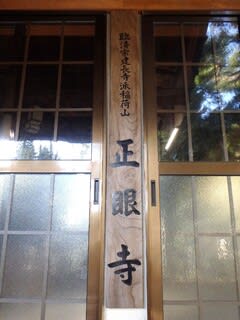

【写真 上(左)】 寺号板
【写真 下(右)】 大棟妻部
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
正面妻部には整った経の巻獅子口を備えています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 天井絵
本堂天井は折上げ天井様になっていて、中央には龍の天井絵。
御内陣中央にお厨子が一座で、こちらに御本尊の聖観世音菩薩が御座とみられます。
『豆州志稿』によると、旧守眼寺の御本尊・釈迦如来は当寺に遷られているので、本堂内のいずこに御座されているのかもしれません。
また、伊豆横道三十三観音霊場第29番の札所でもありますが、札所本尊は御本尊と思われます。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
無住ではないようですが、ご不在の場合でも書置が用意されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
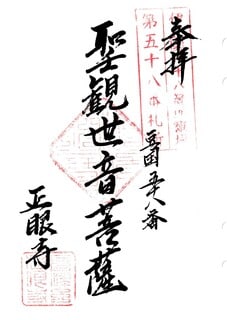
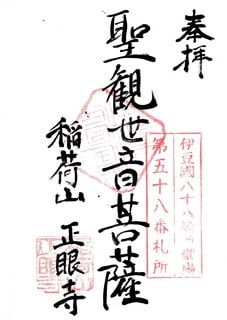
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
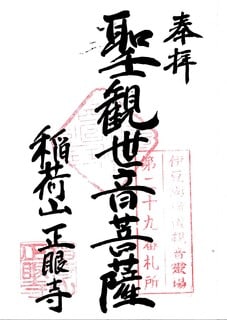
すぐそばには名勝、石廊崎があり石室神社(いろうじんじゃ)が御鎮座です。
数々の伝説に彩られるすばらしい神社なので、次回は寄り道してこちらをご紹介します。
■ 石室神社(いろうじんじゃ)
南伊豆町観光協会Web
南伊豆町石廊崎125
主祭神:伊波例命
旧社格:延喜式内社論社(伊波例命神社)
授与所:社務所
伊豆半島最南端にある石廊崎には石廊埼灯台、さらにその先には石室神社が御鎮座で南伊豆有数の観光スポットとなっています。
石室神社は当初観音像と第六天神を奉安していたところ、役小角(634年伝-701年伝)が神託を受け伊波例命を祀ったとも伝わりますが、創祀は定かでないようです。
古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれ、のちに石廊権現、石室神社と称されています。
拝殿内掲示の『石廊山金剛院縁起』および『豆州志稿』によると、御由緒は以下のとおりです。
役小角が伊豆大島へ流された(699-701年)とき、十一面施無畏(十一面観世音菩薩)のお導きにてこの霊地に至りました。
文武天皇4年(700年)の大地震の際には、龍と白鳥が群れ集まってこの霊地を守り、海中から宝殿が浮んで岬の中腹の岩窟に座す夢をみた村人が現地に行ってみると、確かに宝殿が出現し、なかには十一面観世音菩薩が御座されていたといいます。
そののち、当地の阿摩陀という人が役小角を長津呂の南岸に祀り、「イラウ権現」と号しました。
天平年間(729-749年)に至り、阿摩陀は仏像を陶鋳し第六天神を配祀したといいます。(両尊配祀は行基菩薩とも伝わります。)
南伊豆町観光協会Webでは「秦の始皇帝5世の孫と伝わる『弓月君』(ゆつきのきみ)を、『物忌奈之命』(ものいみなのみこと)として、後にその子孫と称した『秦』氏がこれを祀りお堂を建立した」という説も紹介されています。、
延長五年(927年)の編纂とされる『延喜式神名帳』の巻九神祇九 伊豆国 賀茂郡には「伊波例命神社」が記載され、当社に比定する説があります。
延喜式記載の社号からすると、927年時点での御祭神は伊波例命ともみられます。
上記の時系列から、当初この地には十一面観世音菩薩と第六天神が祀られていたが、その後に役小角が神託を受けて伊波例命を祀った、という説も提起されています。
以降、神仏習合して金剛山石室権現と呼ばれ、海上安全や商売繁盛、学業成就の神様として人々の崇敬を集め、江戸時代には韮山代官所を通じ徳川幕府から毎年米俵の寄進を受けていたとされます。
『豆州志稿』には「石廊権現 長津呂村 無格社石室神社 祭神伊波例命ナル可シ 式内伊波例命神社ナル可シ 石廊崎ノ南極ニ鎮座ス 本村ヨリ十三町 石廊ハ伊波例(イハレ)ノ転訛ナラム 初山上ニ在リシヲ 此ニ遷スト云 祠長樯ヲ海崖ノ岩窟ニ架シテ基礎ニ代フ 甚奇ナリ 遊豆紀勝ニ曰 相伝フ 播州商舶 洋ヲ過クセハ颱風忽起リ、船●●葉ノ如シ 衆哀号 石廊崎権現ニ祷リ ●シ謂フ 当厄ヲ脱セシ樯ヲ以テ報賽ス 少頃風息ミ 波平カニシテ 遂ニ得脱スルヲ乃 樯ヲ沈テ而去ル 是夜樯自海ヲ出テ ●窟中ニ横踞ス 土人●異因ヲ以テ祠ヲ構フト云フト」
「諸者手檻ニ(手繰)リ 匍匐シ祠ニ達ス 危険想フ可シ 下臨スレハ石壁峭立 高サ数百丈波浪淘涌慄然トシテ股栗ス 石廊ノ記ニ曰 日文(支)武帝ノ時 阿摩陀ト云者アリ 何ノ許ノ人ナルヲ知ラス 役小角大島ニ謫セラレシ時 阿摩陀、小角ヲ津呂ノ南岸ニ祀ラシメ イラウ権現ト号ス 天平(729-749年)ニ至リ佛像ヲ陶鋳シ 第六天神ヲ配祀ス 又マイラウト云者 ●摩ノ人也 此ニ幽棲スル事年アリ 能ク飢寒ニ耐ヘ経ヲ誦シテ懈ラス 性慈仁里人疾アレハ則樹葉ヲ執テ 之病者即癒ユ 偶郷人ト相遇フ乃作ニテ 和歌曰ク『見セバヤナ ●摩ノモノニ 此景ヲ 波ノ入間ニ 月ノイラウヲ』ト今地名ニ阿摩陀ノ窪、マイラウナトアリ 神主小澤氏ニ 慶長(1596-1615年)中 大久保岩見守、神職宅地ヲ免租ス 元禄元年(1688年)代官江川太郎左衛門 祈祷料トシテ毎年玄米壹俵ヲ寄進シ 爾来恒例トセシヲ 明治維新後廃止ス」とあります。
南北朝時代の編纂とされる伊豆國神階帳には賀茂郡37所のなかに従四位上として「いわし姫の明神」の記載があり、Wikipediaによれば、こちらが「伊波例命神社」に比定されているようです。
また、『伊豆国神階帳』(群書類従 : 新校. 第一巻) の「伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」に比定。」という説もあります。(→Wikipedia)
天保七年(1836年)起稿、明治三年(1870年)完成とされる『神社覈録』にも賀茂郡四十八座の内に「伊波例命神社」がみえます。
社殿は海岸の岩窟上に立てられた帆柱の上に造営され、「伊豆の七不思議」のひとつとされています。
こちらについては、『石廊権現の帆柱』という不思議な伝説が伝わります。
南伊豆町観光協会Webの記事をメインに各種資料を加えてまとめてみます。
その昔、播磨国濱田港から江戸へ塩を回漕していた帆船(千石船)が、石廊崎沖で時化に遭いあわや難破しそうになったとき、船人たちは石廊崎の断崖に見える石廊権現に向かって『ご加護によって無事嵐を切り抜け江戸に着けたときは、この船の帆柱を奉納いたします」と一心に祈りました。
すると不思議なことに時化はおさまり、船は無事に江戸に着くことができました。
江戸から播磨への帰途、船がこの場所にさしかかったところ、突如前に進まなくなり加えてたいへんな時化となりました。船人たちは往路に捧げた石廊権現への誓願を思い出し、ただちに船の帆柱を斧で切り倒し荒れ狂う海に投ずると、帆柱は荒波に乗ってまっしぐらに石廊権現に向かい、海面から30mもあるその直下の崖に打ち上げられると同時に時化はぴたりとおさまりました。
船人たちは石廊権現を神威を畏れつつも航海をつづけ、無事播州に帰還したそうです。
現在も石室神社拝殿の床下に見られる帆柱は、このときの帆柱であると伝わります。
石室神社のさらに岬寄り(というかほぼ岬の突端)には、境内社とみられる熊野神社が祀られています。
こちらの熊野神社にも伝説が伝わります。(Wikipedia等より)
石廊崎のそば、長津呂の名主の娘、お静は漁師の幸吉と恋に落ちましたが、身分の違いから婚姻は許されず、幸吉は神子元島に流されてしまいました。
幸吉を忘れられないお静は、石廊崎の先端で毎夜火を焚き、おなじく神子元島で火を焚く幸吉と愛を確かめ合いました。
(神子元島(みこもとしま)とは、石廊崎から東南東へ約9キロの沖合にある島。灯台がある海路上の要衝です。)
ある晩、神子元島の火が見えず、これを心配したお静は小船で神子元島に向かいましたが強風高波で難破寸前となり、お静は一心不乱に神に祈りました。
その甲斐あってかお静は神子元島にたどり着き、二人は再開を果たしました。
お静の意思の強さを認めた両親はついに幸吉との関係を許し、二人は末長く幸せに暮らしたといいます。
お静が火を焚いたところには熊野権現の祠が祀られ、縁結びの神として知られるようになり、明治の神仏分離以降は熊野神社と称しています。
------------------------------


【写真 上(左)】 石廊崎港
【写真 下(右)】 石廊崎参道入口(石廊崎港)


【写真 上(左)】 石廊崎オーシャンパーク
【写真 下(右)】 石廊崎オーシャンパークからの遊歩道
石室神社の正式な参道は「石廊崎岬めぐり」のクルーズ船が発着する石廊崎港とみられますが、かなりの距離があるのでふつうは石廊崎灯台そばにある「石廊崎オーシャンパーク」のPに停めてのアプローチとなる模様。
石廊崎周辺は強風で有名で、荒天時は立ち入り禁止となり当然御朱印授与も休止となるので、天気のいい日に参拝したいところです。


【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 遊歩道
【写真 下(右)】 ツワブキ
オーシャンパークから尾根道の遊歩道を歩いていくと、気象観測所、ついで石廊崎灯台に着きます。
途中、狛犬一対と扁額つきの石造明神鳥居。
石廊崎灯台は明治4年(1871年)、日本で8番目の灯台として建てられたものです。


【写真 上(左)】 灯台近く
【写真 下(右)】 石廊崎灯台


【写真 上(左)】 灯台の説明板
【写真 下(右)】 灯台~石室神社
ここから先は強風のためか高木はほとんどなく、青い海を見晴らすきもちのいい道行きとなります。
このあたりの黒味を帯びた凹凸の激しい岩肌は、もともと海底火山の噴火で噴出した溶岩が海水で冷やされ、それが隆起して地上に出てきたものとみられています。


【写真 上(左)】 拝殿への降り階段
【写真 下(右)】 拝殿


【写真 上(左)】 拝殿のロケーション-1
【写真 下(右)】 拝殿のロケーション-2
灯台からの道は険しく要注意。階段を降ると崖下に張り付くように建てられた拝殿です。
明治34年再建の拝殿は銅板葺。狭いスペースを活かすように切妻造の妻入りで、手前が社務所、おくが拝所です。


【写真 上(左)】 拝殿内
【写真 下(右)】 奥側からの拝殿内


【写真 上(左)】 帆柱の説明
【写真 下(右)】 帆柱
床の一部が硝子窓になっており、床下の帆柱を見ることができます。
長さ六間約12メートルとのことです。
拝所は岬とは直角の西向きに設けられています。岬の突端を御神体とするならば、本来南向き(岬に向かっての)の拝殿となるはずで、拝殿直上のひときわ高い岩が御神体、ないしは依代なのかもしれません。


【写真 上(左)】 役行者の奉納額
【写真 下(右)】 拝所


【写真 上(左)】 拝殿~熊野神社
【写真 下(右)】 岬方向からの拝殿
そこから岬の突端に向かってさらに険しい参道がつづきます。
突端には熊野神社が祀られているので確かに参道です。


【写真 上(左)】 熊野神社参道-1
【写真 下(右)】 熊野神社参道-2


【写真 上(左)】 東側の眺望-1
【写真 下(右)】 東側の眺望-2
木々はまったくない吹きさらしの岩上の小路で、荒天時は参拝不可となるのもなるほどうなずけます。
『豆州志稿』には「熊野権現 石廊ノ祠ノ向ノ岩頭ニ在リ 此所ニ至レハ益々危険 目眩シテ久ク留マル可ラス」とあり、往時からその参道の険しさはよく知られていたようです。


【写真 上(左)】 突端-1
【写真 下(右)】 突端-2
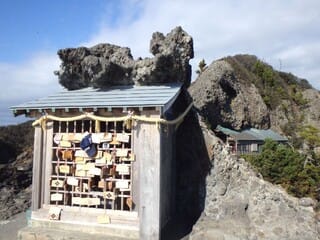

【写真 上(左)】 熊野神社-1
【写真 下(右)】 熊野神社-2
岩を回り込んだところに小祠があり、こちらが熊野神社です。
岩肌に埋め込まれるように建つ銅板葺流造の祠で、縁結びの神様らしく、たくさんの絵馬が奉納されています。


【写真 上(左)】 南側の眺望-1
【写真 下(右)】 南側の眺望-2
振り返れば石廊崎突端。陽射しを受けて青く輝く海原のむこうに伊豆七島が見えています。
ここからは、南、東、西の三方の海を見渡せ、伊豆半島の最南端に来たことを実感できます。


【写真 上(左)】 クルーズ船
【写真 下(右)】 北側の眺望


【写真 上(左)】 西側の眺望-1
【写真 下(右)】 西側の眺望-2
御朱印は社務所内授与所にて授与されていますが、荒天時は不可、好天時でも15:00には終了となってしまうようなので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。


【写真 上(左)】 拝殿と社号標
【写真 下(右)】 授与所
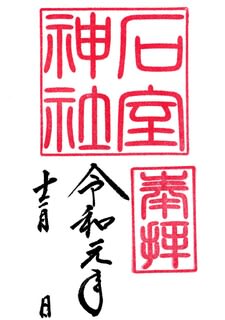
石室神社の御朱印
なお、筆者の手元には見当たらないのですが、Web上でみつかる御由緒(御朱印とともに授与?)には以下のとおりあるようです。
--------------------
・五世紀頃に物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立(伝)。その後役行者が十一面観音を合祀し、大寶元年(701年)現在の場所に建立。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社。
御祭神 伊波例命・物忌奈命
合祀 十一面観音・大六天神・大國主神・■■天皇・事代主神・梵釈四天王・住吉天神・海神自在青龍王
境内社 熊野神社(須佐之男命)
※ 『続日本後紀』によると、物忌奈命は三嶋神(三嶋大社祭神とその本后の阿波咩命の間の御子神とのことです。
■ 第59番 瑞雲山 海蔵寺(かいぞうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町入間949
臨済宗建長寺派
御本尊:弥勒菩薩
札所本尊:弥勒菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)
授与所:庫裡
第59番からはしばらく石廊崎から西伊豆・松崎までの行程となります。
東京からの観光客の多くは、南伊豆は石廊崎まで、西伊豆は松崎までなので、このエリアは「伊豆の深南部」ともいえるなじみの薄いエリアです。
集落もぐっと少なくなり、無住の札所も多くなってきます。
無住の寺院の多くは「寺役管理」で、御朱印の拝受は堂前に掲示されている当番の方の自宅をお尋ねするか、札所までおいでいただくかになります。
ご不在も多く、おいでいただく場合は時間がかかるので御朱印拝受難易度は高く、拝受に要する時間も覚悟しなければなりません。
第59番の海蔵寺は入間の集落にあります。
入間港から徒歩約40分の「千畳敷」は伊豆の秘境ともいわれ、海底に降り積もった火山灰や軽石からなる美しい風景が広がります。
千畳敷では、かつて伊豆石(軟石)の採石が行われており、火山灰の地層を人工的に切り出した跡も残るそうです。
開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、もと中木地区にあった天台宗寺院で、天文中(1532-1555年)に本村(入間)に移され、英仲和尚を開山として臨済宗建長寺派寺院として再興。
明治7年(1874年)3月20日、フランスのマルセーユ港が母校の郵便船ニール号は、香港から横浜へ航海中、風浪に遭い入間沖で座礁転覆、乗組員89名のうち生存者わずか4名という多数の犠牲者を出しました。
海蔵寺の境内には、この海難事故の犠牲者の招魂碑(十字架塔)が建立されています。
『豆州志稿』には「入間村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊弥勒 舊天台宗ニシテ中木(当村属里)ニ在リ 其場所ヲ山ノ寺ト云 古墓多シ 天文中(1532-1555年)英仲和尚ノ時 本村ニ移シテ改宗ス」とあります。
このエリアに寺院は少なくしかも比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。
-------------------


【写真 上(左)】 あたりの海岸-1
【写真 下(右)】 あたりの海岸-2

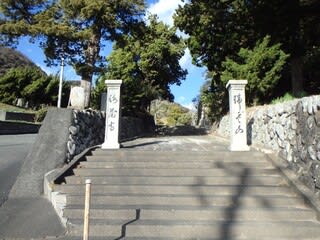
【写真 上(左)】 入間集落入口のサイン
【写真 下(右)】 参道入口
南伊豆の集落の多くは港まわりにあり、山側を走る主要道から枝道を海に向かって降りていくアプローチで、ここ入間も例外ではありません。
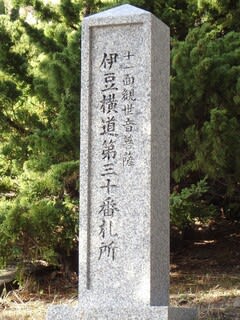

【写真 上(左)】 横道三十三観音の札所標
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
参道入り口に立派な門柱を構え、この地域の中核寺院の趣き。
伊豆横道三十三観音第三十番の札所碑も建っています。
山門はがっしりとした切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げに寺号扁額。
門柱掛札には「中風厄除観音霊場●●病消除明王霊場」とあるので、とくに中風除けに御利益のあるお寺さんのようです。


【写真 上(左)】 おたふくの石像
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 十二支守り本尊
【写真 下(右)】 六地蔵
境内各所に「おたふく」の石像が据え置かれ、「おたふく寺」とも呼ばれるとの由。
参道右手に十二支守り本尊、左手に六地蔵が並びます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の簡素な木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁。中備は左右笈形ですが中央は瓶子状の大瓶束(たいへいづか)ではなく、木柱となっています。
向拝正面の扉は下欄に格狭間、上欄が格子と縦長の花頭窓の風変わりな意匠。
御本尊は行基菩薩の御作と伝わる弥勒菩薩坐像、伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。
御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。
天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。
「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。


【写真 上(左)】 堂内山号扁額
【写真 下(右)】 布袋尊
なお、三嶋観光バスのWebによると「本堂に本尊・弥勒菩薩坐像、脇立に達磨大師、大権修理菩薩像が安置されている。本尊・弥勒菩薩坐像は行基作。脇室の厨子内の秘仏十一面観音立像は頭上に十一面を配し、奥行き豊かな一木彫りの平安後期の古仏」とのことです。
ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。
詳細はこちらのブログでご紹介されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
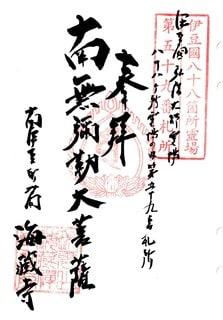

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※御朱印帳書入の揮毫は「十一面観世音菩薩」となっています。
(御寶印はいずれも弥勒菩薩のお種子「ユ」です。)
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
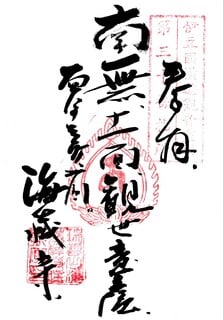
〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の御朱印 〕
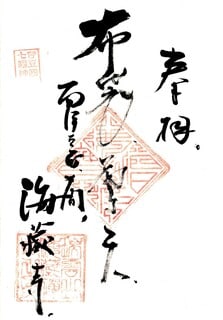
■ 第60番 龍燈山 善福寺(ぜんぷくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町妻良809
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)
授与所:庫裡
第59番から第61番を通り過ぎ、妻良の第60番の当寺に進みます。
妻良は第70番のある子浦にほど近いところですが、ここから順路は東に向きを変え一旦下賀茂あたりまで戻るかたちとなります。
妻良(めら)という地名について「三嶋大神の后神にちなむといい、妻良は三嶋大神の「妻」のこと。妻良は妻浦ともいい、「めうら」が「めら」となった可能性もある。」というWeb記事がありました。
「南伊豆最大の良港」ともいわれる妻良港を擁する港町です。
周辺の海岸は柱状節理が発達し、多くの景勝地があります。
第60番の海蔵寺は妻良の集落にあります。
三島神社にもほど近く、元別当かとも思いましたがよくわかりません。
なお、妻良の三島神社は大津往命神社、阿米都加多比咩命神社の式内社二社の論社と比定される古社です。
詳細については、こちらのWeb(shrine-heritager様)にてご紹介されています。
善福寺の開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、寛永五年(1628年)に入寂した了快が中興の祖と伝わります。
天保年間(1830-1844年)心運により本堂・庫裏が再建されました。
妻良港は風待ち港として知られ、安政二年(1855年)9月、 勝海舟ら十一人が江戸幕府の軍船・昇平丸で長崎に向かう途中、風待ちのために約一週間滞在の記録が残っています。
『豆州志稿』には「妻浦村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊大日 創立不詳 中興了快(寛永五年寂ス) 伊豆山派下ニシテ納符ノ所ナリ」とあります。
このエリアも寺院は少なく比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。
-------------------


【写真 上(左)】 妻良港
【写真 下(右)】 妻良の町並みと参道


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道階段
妻良の集落の西側山ぎわにあります。
路地に面して石段の参道。手摺の親柱向かって右には胎蔵大日如来のお種子「ア」、左には不動明王のお種子「カーン」が刻まれています。
階段うえの山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その手前に寺号標。

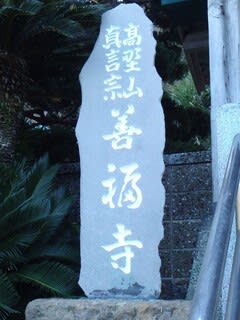
【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
本堂は入母屋造銅板葺で向拝柱はなく、密寺としてはすっきりとしたつくりです。
向拝正面は幾何学紋様の開戸と格狭間&花頭窓を配した脇戸の構成で、意匠的に渋い仕上がり。
見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂宮殿の登り龍、降り龍等の彫刻は、松崎町江奈の名工・石田半兵衛の作。
御本尊は大日如来で、行基菩薩の御作と伝わる不動明王、薬師如来も合祀されています。
伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。
御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。
天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。
「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。
ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。
詳細はこちらのブログでご紹介されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
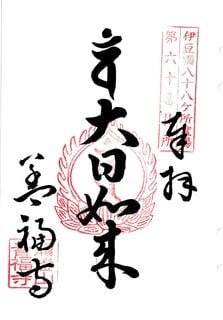
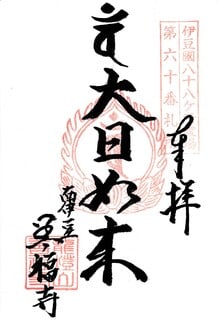
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
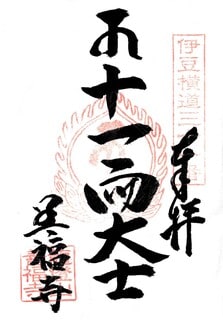
※伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の御朱印は拝受しておりませんが、授与されている模様です。
■ 第61番 臥龍山 法泉寺(ほうせんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町妻良1213
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:寺役管理
妻良(港)の集落から下賀茂に向かう途中にあります。
国道136号から枝道を少し入ったところ。
住所は妻良ですが、このあたりはすでに南伊豆の山中。この霊場巡拝がなければおそらく来る機会のないところだと思います。
この霊場でもっとも情報の少ない札所のひつとで開創も不明ですが、『豆州志稿』によると寛文二年(1662年)最福寺の宝山順和尚が(再興)開基し、最福寺三世の僧・傳心を開山とあります。
『豆州志稿』には「妻浦村 曹洞宗 上賀茂最福寺末 本尊大日 寛文二年(1662年)僧寶山開基 最福寺三世心傳ヲ開山トス」とあります。
『伊豆88遍路の紹介ページ』には「かつては真言宗の小庵でした。 1662(寛文2)年に最福寺の宝山順和尚が再興して曹洞宗の寺院となりました。」とあり、御本尊が大日如来であることの説明がつきます。
現況無住につき、納経等は寺役管理となっています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 札所標


【写真 上(左)】 新四国霊場の札所標
【写真 下(右)】 六地蔵
枝道に面して参道入口。寺号標兼札所標が建っています。
その横に「新四國八(?)拾番 観音寺」の札所標がありましたが詳細不明。
参道は立派な舗装道で、本堂前まで車で上がれます。
思いのほか広く、堂前は砂利敷で明るく開けた山内。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
本堂は入母屋造桟瓦葺で向拝柱はなく、向かって右手に庫裡(?)を付設しています。
向拝正面サッシュ扉。山号寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
御朱印は手持ちしていた寺役さんの電話番号に連絡すると、寺役さんがおいでになられ無事拝受できました。(専用納経帳捺印のみです。)
現況『伊豆88遍路の紹介ページ』記載のものが最新の連絡先と思われます。
なお、第68番東林寺(南伊豆町下小野414-1)の御朱印もこちらの寺役さんからいただきましたので、先に東林寺を回った方がいいかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

専用納経帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へつづく。
--------------------
【 BGM 】
■ Just Be Yourself - 杏里/Anri
■ Never Let Me Go - 中村舞子
■ LONESOME MERMAID - 今井美樹
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。
----------------------------------------
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7から。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へ。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
■ 第58番 稲荷山 正眼寺(しょうげんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町石廊崎18
臨済宗建長寺派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第29番
授与所:庫裡
山内由緒書&『こころの旅』によると、観應二年(1351年)真際によって開かれた臨済宗の寺院。
(由緒書では開山は高厳。)
すぐ下の長津呂港は良港で江戸時代に賑わい、享保年間(1716-1735年)には停泊する船は八十余隻に及び、戸数も七十五を数えたといいます。
正眼寺は一時衰退したものの、享保十八年(1733年)僧獲麟によって再興。
海事を司り、一時は正眼寺を凌ぐ繁栄をみせたという石廊崎の守源寺は、明治23年(1890年)の災害によって廃寺となり正眼寺に併合されています。
当山の左手の山腹にある般若堂は稲荷神を祀り厄除けの霊験あらたかで、広く信仰を集めるとのことです。
『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 開山無象和尚(徳治元年(1306年)示寂) 享保十八年(1733年)僧獲麟中興ス 般若堂稲荷祠倶寺域」とあります。
また、長津山守眼寺について、『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 今作守眼寺 開山蔵海和尚(應永十八年(1411年)取滅) 寺内有天神祠 明治廿三年廃寺トナリ 本尊ハ同村正眼寺ニ併ス」とあります。
-------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山内
県道16号下田石廊松崎線で石廊トンネルを抜けてすこし行ったところ、県道沿いに駐車スペースがあります。
石段を登り切ると正面に本堂、右手が庫裡です。
木々生い茂る山内ですが、どことなく明るい雰囲気があるのは陽光ゆたかな南伊豆の風土ゆえでしょうか。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺の妻入りながら、左右に建物が付設されていてちょっと変わった構造になっています。
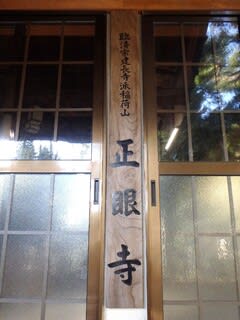

【写真 上(左)】 寺号板
【写真 下(右)】 大棟妻部
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
正面妻部には整った経の巻獅子口を備えています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 天井絵
本堂天井は折上げ天井様になっていて、中央には龍の天井絵。
御内陣中央にお厨子が一座で、こちらに御本尊の聖観世音菩薩が御座とみられます。
『豆州志稿』によると、旧守眼寺の御本尊・釈迦如来は当寺に遷られているので、本堂内のいずこに御座されているのかもしれません。
また、伊豆横道三十三観音霊場第29番の札所でもありますが、札所本尊は御本尊と思われます。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
無住ではないようですが、ご不在の場合でも書置が用意されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
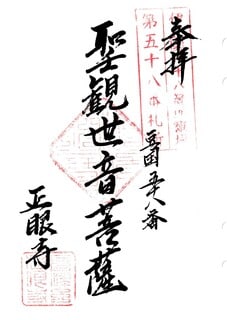
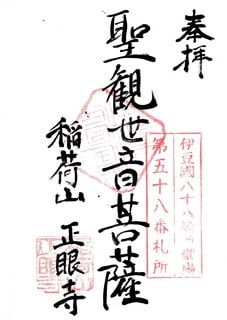
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
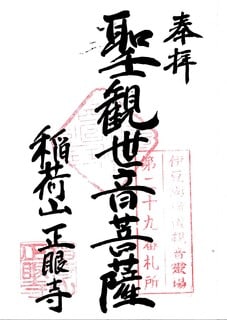
すぐそばには名勝、石廊崎があり石室神社(いろうじんじゃ)が御鎮座です。
数々の伝説に彩られるすばらしい神社なので、次回は寄り道してこちらをご紹介します。
■ 石室神社(いろうじんじゃ)
南伊豆町観光協会Web
南伊豆町石廊崎125
主祭神:伊波例命
旧社格:延喜式内社論社(伊波例命神社)
授与所:社務所
伊豆半島最南端にある石廊崎には石廊埼灯台、さらにその先には石室神社が御鎮座で南伊豆有数の観光スポットとなっています。
石室神社は当初観音像と第六天神を奉安していたところ、役小角(634年伝-701年伝)が神託を受け伊波例命を祀ったとも伝わりますが、創祀は定かでないようです。
古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれ、のちに石廊権現、石室神社と称されています。
拝殿内掲示の『石廊山金剛院縁起』および『豆州志稿』によると、御由緒は以下のとおりです。
役小角が伊豆大島へ流された(699-701年)とき、十一面施無畏(十一面観世音菩薩)のお導きにてこの霊地に至りました。
文武天皇4年(700年)の大地震の際には、龍と白鳥が群れ集まってこの霊地を守り、海中から宝殿が浮んで岬の中腹の岩窟に座す夢をみた村人が現地に行ってみると、確かに宝殿が出現し、なかには十一面観世音菩薩が御座されていたといいます。
そののち、当地の阿摩陀という人が役小角を長津呂の南岸に祀り、「イラウ権現」と号しました。
天平年間(729-749年)に至り、阿摩陀は仏像を陶鋳し第六天神を配祀したといいます。(両尊配祀は行基菩薩とも伝わります。)
南伊豆町観光協会Webでは「秦の始皇帝5世の孫と伝わる『弓月君』(ゆつきのきみ)を、『物忌奈之命』(ものいみなのみこと)として、後にその子孫と称した『秦』氏がこれを祀りお堂を建立した」という説も紹介されています。、
延長五年(927年)の編纂とされる『延喜式神名帳』の巻九神祇九 伊豆国 賀茂郡には「伊波例命神社」が記載され、当社に比定する説があります。
延喜式記載の社号からすると、927年時点での御祭神は伊波例命ともみられます。
上記の時系列から、当初この地には十一面観世音菩薩と第六天神が祀られていたが、その後に役小角が神託を受けて伊波例命を祀った、という説も提起されています。
以降、神仏習合して金剛山石室権現と呼ばれ、海上安全や商売繁盛、学業成就の神様として人々の崇敬を集め、江戸時代には韮山代官所を通じ徳川幕府から毎年米俵の寄進を受けていたとされます。
『豆州志稿』には「石廊権現 長津呂村 無格社石室神社 祭神伊波例命ナル可シ 式内伊波例命神社ナル可シ 石廊崎ノ南極ニ鎮座ス 本村ヨリ十三町 石廊ハ伊波例(イハレ)ノ転訛ナラム 初山上ニ在リシヲ 此ニ遷スト云 祠長樯ヲ海崖ノ岩窟ニ架シテ基礎ニ代フ 甚奇ナリ 遊豆紀勝ニ曰 相伝フ 播州商舶 洋ヲ過クセハ颱風忽起リ、船●●葉ノ如シ 衆哀号 石廊崎権現ニ祷リ ●シ謂フ 当厄ヲ脱セシ樯ヲ以テ報賽ス 少頃風息ミ 波平カニシテ 遂ニ得脱スルヲ乃 樯ヲ沈テ而去ル 是夜樯自海ヲ出テ ●窟中ニ横踞ス 土人●異因ヲ以テ祠ヲ構フト云フト」
「諸者手檻ニ(手繰)リ 匍匐シ祠ニ達ス 危険想フ可シ 下臨スレハ石壁峭立 高サ数百丈波浪淘涌慄然トシテ股栗ス 石廊ノ記ニ曰 日文(支)武帝ノ時 阿摩陀ト云者アリ 何ノ許ノ人ナルヲ知ラス 役小角大島ニ謫セラレシ時 阿摩陀、小角ヲ津呂ノ南岸ニ祀ラシメ イラウ権現ト号ス 天平(729-749年)ニ至リ佛像ヲ陶鋳シ 第六天神ヲ配祀ス 又マイラウト云者 ●摩ノ人也 此ニ幽棲スル事年アリ 能ク飢寒ニ耐ヘ経ヲ誦シテ懈ラス 性慈仁里人疾アレハ則樹葉ヲ執テ 之病者即癒ユ 偶郷人ト相遇フ乃作ニテ 和歌曰ク『見セバヤナ ●摩ノモノニ 此景ヲ 波ノ入間ニ 月ノイラウヲ』ト今地名ニ阿摩陀ノ窪、マイラウナトアリ 神主小澤氏ニ 慶長(1596-1615年)中 大久保岩見守、神職宅地ヲ免租ス 元禄元年(1688年)代官江川太郎左衛門 祈祷料トシテ毎年玄米壹俵ヲ寄進シ 爾来恒例トセシヲ 明治維新後廃止ス」とあります。
南北朝時代の編纂とされる伊豆國神階帳には賀茂郡37所のなかに従四位上として「いわし姫の明神」の記載があり、Wikipediaによれば、こちらが「伊波例命神社」に比定されているようです。
また、『伊豆国神階帳』(群書類従 : 新校. 第一巻) の「伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」に比定。」という説もあります。(→Wikipedia)
天保七年(1836年)起稿、明治三年(1870年)完成とされる『神社覈録』にも賀茂郡四十八座の内に「伊波例命神社」がみえます。
社殿は海岸の岩窟上に立てられた帆柱の上に造営され、「伊豆の七不思議」のひとつとされています。
こちらについては、『石廊権現の帆柱』という不思議な伝説が伝わります。
南伊豆町観光協会Webの記事をメインに各種資料を加えてまとめてみます。
その昔、播磨国濱田港から江戸へ塩を回漕していた帆船(千石船)が、石廊崎沖で時化に遭いあわや難破しそうになったとき、船人たちは石廊崎の断崖に見える石廊権現に向かって『ご加護によって無事嵐を切り抜け江戸に着けたときは、この船の帆柱を奉納いたします」と一心に祈りました。
すると不思議なことに時化はおさまり、船は無事に江戸に着くことができました。
江戸から播磨への帰途、船がこの場所にさしかかったところ、突如前に進まなくなり加えてたいへんな時化となりました。船人たちは往路に捧げた石廊権現への誓願を思い出し、ただちに船の帆柱を斧で切り倒し荒れ狂う海に投ずると、帆柱は荒波に乗ってまっしぐらに石廊権現に向かい、海面から30mもあるその直下の崖に打ち上げられると同時に時化はぴたりとおさまりました。
船人たちは石廊権現を神威を畏れつつも航海をつづけ、無事播州に帰還したそうです。
現在も石室神社拝殿の床下に見られる帆柱は、このときの帆柱であると伝わります。
石室神社のさらに岬寄り(というかほぼ岬の突端)には、境内社とみられる熊野神社が祀られています。
こちらの熊野神社にも伝説が伝わります。(Wikipedia等より)
石廊崎のそば、長津呂の名主の娘、お静は漁師の幸吉と恋に落ちましたが、身分の違いから婚姻は許されず、幸吉は神子元島に流されてしまいました。
幸吉を忘れられないお静は、石廊崎の先端で毎夜火を焚き、おなじく神子元島で火を焚く幸吉と愛を確かめ合いました。
(神子元島(みこもとしま)とは、石廊崎から東南東へ約9キロの沖合にある島。灯台がある海路上の要衝です。)
ある晩、神子元島の火が見えず、これを心配したお静は小船で神子元島に向かいましたが強風高波で難破寸前となり、お静は一心不乱に神に祈りました。
その甲斐あってかお静は神子元島にたどり着き、二人は再開を果たしました。
お静の意思の強さを認めた両親はついに幸吉との関係を許し、二人は末長く幸せに暮らしたといいます。
お静が火を焚いたところには熊野権現の祠が祀られ、縁結びの神として知られるようになり、明治の神仏分離以降は熊野神社と称しています。
------------------------------


【写真 上(左)】 石廊崎港
【写真 下(右)】 石廊崎参道入口(石廊崎港)


【写真 上(左)】 石廊崎オーシャンパーク
【写真 下(右)】 石廊崎オーシャンパークからの遊歩道
石室神社の正式な参道は「石廊崎岬めぐり」のクルーズ船が発着する石廊崎港とみられますが、かなりの距離があるのでふつうは石廊崎灯台そばにある「石廊崎オーシャンパーク」のPに停めてのアプローチとなる模様。
石廊崎周辺は強風で有名で、荒天時は立ち入り禁止となり当然御朱印授与も休止となるので、天気のいい日に参拝したいところです。


【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 鳥居扁額


【写真 上(左)】 遊歩道
【写真 下(右)】 ツワブキ
オーシャンパークから尾根道の遊歩道を歩いていくと、気象観測所、ついで石廊崎灯台に着きます。
途中、狛犬一対と扁額つきの石造明神鳥居。
石廊崎灯台は明治4年(1871年)、日本で8番目の灯台として建てられたものです。


【写真 上(左)】 灯台近く
【写真 下(右)】 石廊崎灯台


【写真 上(左)】 灯台の説明板
【写真 下(右)】 灯台~石室神社
ここから先は強風のためか高木はほとんどなく、青い海を見晴らすきもちのいい道行きとなります。
このあたりの黒味を帯びた凹凸の激しい岩肌は、もともと海底火山の噴火で噴出した溶岩が海水で冷やされ、それが隆起して地上に出てきたものとみられています。


【写真 上(左)】 拝殿への降り階段
【写真 下(右)】 拝殿


【写真 上(左)】 拝殿のロケーション-1
【写真 下(右)】 拝殿のロケーション-2
灯台からの道は険しく要注意。階段を降ると崖下に張り付くように建てられた拝殿です。
明治34年再建の拝殿は銅板葺。狭いスペースを活かすように切妻造の妻入りで、手前が社務所、おくが拝所です。


【写真 上(左)】 拝殿内
【写真 下(右)】 奥側からの拝殿内


【写真 上(左)】 帆柱の説明
【写真 下(右)】 帆柱
床の一部が硝子窓になっており、床下の帆柱を見ることができます。
長さ六間約12メートルとのことです。
拝所は岬とは直角の西向きに設けられています。岬の突端を御神体とするならば、本来南向き(岬に向かっての)の拝殿となるはずで、拝殿直上のひときわ高い岩が御神体、ないしは依代なのかもしれません。


【写真 上(左)】 役行者の奉納額
【写真 下(右)】 拝所


【写真 上(左)】 拝殿~熊野神社
【写真 下(右)】 岬方向からの拝殿
そこから岬の突端に向かってさらに険しい参道がつづきます。
突端には熊野神社が祀られているので確かに参道です。


【写真 上(左)】 熊野神社参道-1
【写真 下(右)】 熊野神社参道-2


【写真 上(左)】 東側の眺望-1
【写真 下(右)】 東側の眺望-2
木々はまったくない吹きさらしの岩上の小路で、荒天時は参拝不可となるのもなるほどうなずけます。
『豆州志稿』には「熊野権現 石廊ノ祠ノ向ノ岩頭ニ在リ 此所ニ至レハ益々危険 目眩シテ久ク留マル可ラス」とあり、往時からその参道の険しさはよく知られていたようです。


【写真 上(左)】 突端-1
【写真 下(右)】 突端-2
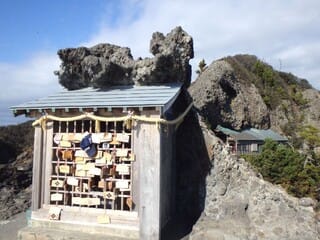

【写真 上(左)】 熊野神社-1
【写真 下(右)】 熊野神社-2
岩を回り込んだところに小祠があり、こちらが熊野神社です。
岩肌に埋め込まれるように建つ銅板葺流造の祠で、縁結びの神様らしく、たくさんの絵馬が奉納されています。


【写真 上(左)】 南側の眺望-1
【写真 下(右)】 南側の眺望-2
振り返れば石廊崎突端。陽射しを受けて青く輝く海原のむこうに伊豆七島が見えています。
ここからは、南、東、西の三方の海を見渡せ、伊豆半島の最南端に来たことを実感できます。


【写真 上(左)】 クルーズ船
【写真 下(右)】 北側の眺望


【写真 上(左)】 西側の眺望-1
【写真 下(右)】 西側の眺望-2
御朱印は社務所内授与所にて授与されていますが、荒天時は不可、好天時でも15:00には終了となってしまうようなので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。


【写真 上(左)】 拝殿と社号標
【写真 下(右)】 授与所
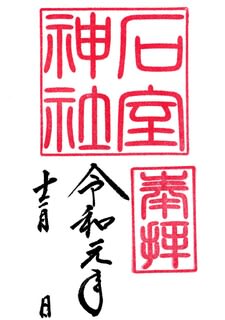
石室神社の御朱印
なお、筆者の手元には見当たらないのですが、Web上でみつかる御由緒(御朱印とともに授与?)には以下のとおりあるようです。
--------------------
・五世紀頃に物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立(伝)。その後役行者が十一面観音を合祀し、大寶元年(701年)現在の場所に建立。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社。
御祭神 伊波例命・物忌奈命
合祀 十一面観音・大六天神・大國主神・■■天皇・事代主神・梵釈四天王・住吉天神・海神自在青龍王
境内社 熊野神社(須佐之男命)
※ 『続日本後紀』によると、物忌奈命は三嶋神(三嶋大社祭神とその本后の阿波咩命の間の御子神とのことです。
■ 第59番 瑞雲山 海蔵寺(かいぞうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町入間949
臨済宗建長寺派
御本尊:弥勒菩薩
札所本尊:弥勒菩薩
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)
授与所:庫裡
第59番からはしばらく石廊崎から西伊豆・松崎までの行程となります。
東京からの観光客の多くは、南伊豆は石廊崎まで、西伊豆は松崎までなので、このエリアは「伊豆の深南部」ともいえるなじみの薄いエリアです。
集落もぐっと少なくなり、無住の札所も多くなってきます。
無住の寺院の多くは「寺役管理」で、御朱印の拝受は堂前に掲示されている当番の方の自宅をお尋ねするか、札所までおいでいただくかになります。
ご不在も多く、おいでいただく場合は時間がかかるので御朱印拝受難易度は高く、拝受に要する時間も覚悟しなければなりません。
第59番の海蔵寺は入間の集落にあります。
入間港から徒歩約40分の「千畳敷」は伊豆の秘境ともいわれ、海底に降り積もった火山灰や軽石からなる美しい風景が広がります。
千畳敷では、かつて伊豆石(軟石)の採石が行われており、火山灰の地層を人工的に切り出した跡も残るそうです。
開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、もと中木地区にあった天台宗寺院で、天文中(1532-1555年)に本村(入間)に移され、英仲和尚を開山として臨済宗建長寺派寺院として再興。
明治7年(1874年)3月20日、フランスのマルセーユ港が母校の郵便船ニール号は、香港から横浜へ航海中、風浪に遭い入間沖で座礁転覆、乗組員89名のうち生存者わずか4名という多数の犠牲者を出しました。
海蔵寺の境内には、この海難事故の犠牲者の招魂碑(十字架塔)が建立されています。
『豆州志稿』には「入間村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊弥勒 舊天台宗ニシテ中木(当村属里)ニ在リ 其場所ヲ山ノ寺ト云 古墓多シ 天文中(1532-1555年)英仲和尚ノ時 本村ニ移シテ改宗ス」とあります。
このエリアに寺院は少なくしかも比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。
-------------------


【写真 上(左)】 あたりの海岸-1
【写真 下(右)】 あたりの海岸-2

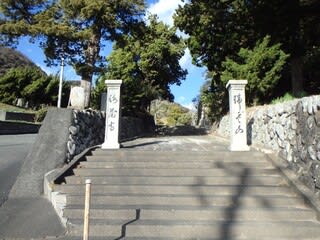
【写真 上(左)】 入間集落入口のサイン
【写真 下(右)】 参道入口
南伊豆の集落の多くは港まわりにあり、山側を走る主要道から枝道を海に向かって降りていくアプローチで、ここ入間も例外ではありません。
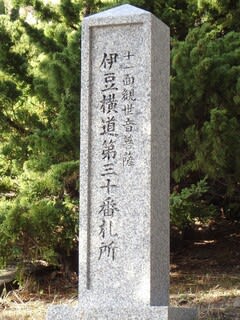

【写真 上(左)】 横道三十三観音の札所標
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
参道入り口に立派な門柱を構え、この地域の中核寺院の趣き。
伊豆横道三十三観音第三十番の札所碑も建っています。
山門はがっしりとした切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げに寺号扁額。
門柱掛札には「中風厄除観音霊場●●病消除明王霊場」とあるので、とくに中風除けに御利益のあるお寺さんのようです。


【写真 上(左)】 おたふくの石像
【写真 下(右)】 鐘楼


【写真 上(左)】 十二支守り本尊
【写真 下(右)】 六地蔵
境内各所に「おたふく」の石像が据え置かれ、「おたふく寺」とも呼ばれるとの由。
参道右手に十二支守り本尊、左手に六地蔵が並びます。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の簡素な木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁。中備は左右笈形ですが中央は瓶子状の大瓶束(たいへいづか)ではなく、木柱となっています。
向拝正面の扉は下欄に格狭間、上欄が格子と縦長の花頭窓の風変わりな意匠。
御本尊は行基菩薩の御作と伝わる弥勒菩薩坐像、伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。
御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。
天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。
「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。


【写真 上(左)】 堂内山号扁額
【写真 下(右)】 布袋尊
なお、三嶋観光バスのWebによると「本堂に本尊・弥勒菩薩坐像、脇立に達磨大師、大権修理菩薩像が安置されている。本尊・弥勒菩薩坐像は行基作。脇室の厨子内の秘仏十一面観音立像は頭上に十一面を配し、奥行き豊かな一木彫りの平安後期の古仏」とのことです。
ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。
詳細はこちらのブログでご紹介されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
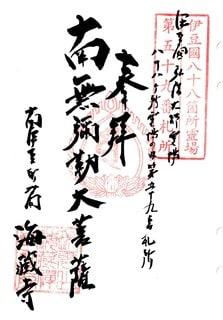

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
※御朱印帳書入の揮毫は「十一面観世音菩薩」となっています。
(御寶印はいずれも弥勒菩薩のお種子「ユ」です。)
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
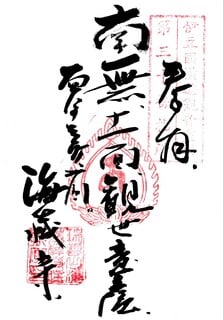
〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の御朱印 〕
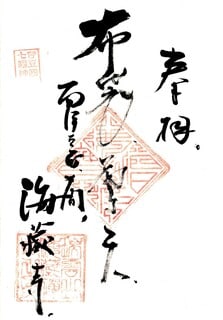
■ 第60番 龍燈山 善福寺(ぜんぷくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町妻良809
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)
授与所:庫裡
第59番から第61番を通り過ぎ、妻良の第60番の当寺に進みます。
妻良は第70番のある子浦にほど近いところですが、ここから順路は東に向きを変え一旦下賀茂あたりまで戻るかたちとなります。
妻良(めら)という地名について「三嶋大神の后神にちなむといい、妻良は三嶋大神の「妻」のこと。妻良は妻浦ともいい、「めうら」が「めら」となった可能性もある。」というWeb記事がありました。
「南伊豆最大の良港」ともいわれる妻良港を擁する港町です。
周辺の海岸は柱状節理が発達し、多くの景勝地があります。
第60番の海蔵寺は妻良の集落にあります。
三島神社にもほど近く、元別当かとも思いましたがよくわかりません。
なお、妻良の三島神社は大津往命神社、阿米都加多比咩命神社の式内社二社の論社と比定される古社です。
詳細については、こちらのWeb(shrine-heritager様)にてご紹介されています。
善福寺の開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、寛永五年(1628年)に入寂した了快が中興の祖と伝わります。
天保年間(1830-1844年)心運により本堂・庫裏が再建されました。
妻良港は風待ち港として知られ、安政二年(1855年)9月、 勝海舟ら十一人が江戸幕府の軍船・昇平丸で長崎に向かう途中、風待ちのために約一週間滞在の記録が残っています。
『豆州志稿』には「妻浦村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊大日 創立不詳 中興了快(寛永五年寂ス) 伊豆山派下ニシテ納符ノ所ナリ」とあります。
このエリアも寺院は少なく比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。
-------------------


【写真 上(左)】 妻良港
【写真 下(右)】 妻良の町並みと参道


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道階段
妻良の集落の西側山ぎわにあります。
路地に面して石段の参道。手摺の親柱向かって右には胎蔵大日如来のお種子「ア」、左には不動明王のお種子「カーン」が刻まれています。
階段うえの山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その手前に寺号標。

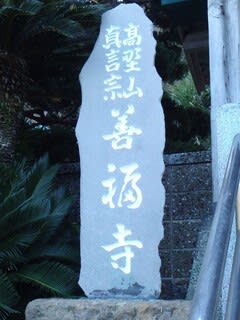
【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標
本堂は入母屋造銅板葺で向拝柱はなく、密寺としてはすっきりとしたつくりです。
向拝正面は幾何学紋様の開戸と格狭間&花頭窓を配した脇戸の構成で、意匠的に渋い仕上がり。
見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂宮殿の登り龍、降り龍等の彫刻は、松崎町江奈の名工・石田半兵衛の作。
御本尊は大日如来で、行基菩薩の御作と伝わる不動明王、薬師如来も合祀されています。
伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。
御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。
天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。
「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。
ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。
詳細はこちらのブログでご紹介されています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
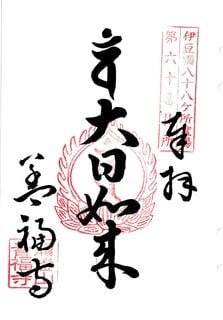
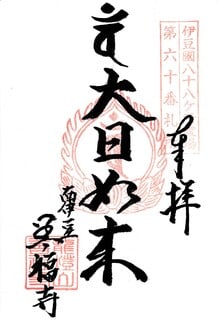
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕
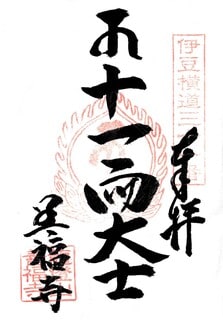
※伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の御朱印は拝受しておりませんが、授与されている模様です。
■ 第61番 臥龍山 法泉寺(ほうせんじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
南伊豆町妻良1213
曹洞宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:寺役管理
妻良(港)の集落から下賀茂に向かう途中にあります。
国道136号から枝道を少し入ったところ。
住所は妻良ですが、このあたりはすでに南伊豆の山中。この霊場巡拝がなければおそらく来る機会のないところだと思います。
この霊場でもっとも情報の少ない札所のひつとで開創も不明ですが、『豆州志稿』によると寛文二年(1662年)最福寺の宝山順和尚が(再興)開基し、最福寺三世の僧・傳心を開山とあります。
『豆州志稿』には「妻浦村 曹洞宗 上賀茂最福寺末 本尊大日 寛文二年(1662年)僧寶山開基 最福寺三世心傳ヲ開山トス」とあります。
『伊豆88遍路の紹介ページ』には「かつては真言宗の小庵でした。 1662(寛文2)年に最福寺の宝山順和尚が再興して曹洞宗の寺院となりました。」とあり、御本尊が大日如来であることの説明がつきます。
現況無住につき、納経等は寺役管理となっています。
-------------------


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 札所標


【写真 上(左)】 新四国霊場の札所標
【写真 下(右)】 六地蔵
枝道に面して参道入口。寺号標兼札所標が建っています。
その横に「新四國八(?)拾番 観音寺」の札所標がありましたが詳細不明。
参道は立派な舗装道で、本堂前まで車で上がれます。
思いのほか広く、堂前は砂利敷で明るく開けた山内。


【写真 上(左)】 本堂-1
【写真 下(右)】 本堂-2
本堂は入母屋造桟瓦葺で向拝柱はなく、向かって右手に庫裡(?)を付設しています。
向拝正面サッシュ扉。山号寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
御朱印は手持ちしていた寺役さんの電話番号に連絡すると、寺役さんがおいでになられ無事拝受できました。(専用納経帳捺印のみです。)
現況『伊豆88遍路の紹介ページ』記載のものが最新の連絡先と思われます。
なお、第68番東林寺(南伊豆町下小野414-1)の御朱印もこちらの寺役さんからいただきましたので、先に東林寺を回った方がいいかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

専用納経帳
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へつづく。
--------------------
【 BGM 】
■ Just Be Yourself - 杏里/Anri
■ Never Let Me Go - 中村舞子
■ LONESOME MERMAID - 今井美樹
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 女神系歌姫 (ハイトーンJ-POPの担い手たち)【リニューアル】
このところ、久しぶりに「歌い手」や声優・ゲーム系の女性ヴォーカルをかため聴きしました。
やっぱりこの分野のレベル異様に高いわ。
そこで、以前別ブログにUPした「女神系歌姫」たち100人以上の動画を、リンクつなぎなおしコメントを補足してUPしていきます。
リストした曲は個人的に好みのテイクで、かならずしも代表曲というワケではありません。
掲載順は順不同ですが、元ブログの掲載順を踏襲しています。
まずは、こちら(女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-10 】)からはじめます。
--------------------
2021/12/24 UP
この記事は筆者の別ブログ(ameblo)に2014/08/09にUPしたものですが、リンクつなぎ直してこちらのブログにリニューアルUPします。
(文章やリンク曲は手を入れていないので、2014年夏時点のものです。)
--------------------------------
【女神系歌姫】とは
エンヤのブレークをきっかけに一気に盛り上がった「ケルティック・ウーマン」ブーム。
ハイトーンのヒーリングヴォイスをその特徴とするアイルランドのPOPSは、全世界で高い支持を集めています。
でも、いまの日本の女性ヴォーカルのレベルは、それに勝るとも劣らないものがあるのでは。
■ Little Glee Monster - HARMONY(PV)
マスコミで注目度上昇中の激ウマグループLittle Glee Monster。
歌の巧さがますます求められる時代に入ったか?
(個人的に)女性ヴォーカルのメインになっていると思われる「女神系歌姫」について、これまでいくつかの記事に書き散らした内容を、整理してみたいと思います。
■ 上野洋子 - 協和発酵 焼酎「かのか」CM (曲名:「風と花と光と」)
女神系歌姫の走り?
【女神系歌姫とは】
1990年代中盤頃から、少しづつ邦楽の、とくに新世代の女性Artistの質感が変わってきた。
この流れは2000年代中盤から決定的になってくるのだが、まずはその特徴について考えてみた。
1.ハイトーン・ヴォイス
とにかくオクターブが高くなり、音階も広がった。
これは安室奈美恵、華原朋美、観月ありさ、globeなど、「小室ファミリー」といわれた一連の女性Vocalistの影響があると思う。
彼女らの超ハイトーン曲をふつうにカラオケで唄っていた次世代層が育ってきたということか・・・。
■ 歌ってみた Can You Celebrate
■ 歌ってみた I'm proud
■ 歌ってみた 月光
※ すべてリンク切れ
たとえば安室奈美恵の『CAN YOU CELEBRATE?』。
曲の構成はPOPというよりむしろプログレ的な大作で、音域も広くてどうみてもトーシロの手に負える曲じゃない・・・。
にもかかわらず、その曲は売り上げ、カラオケランキングともに数々の記録を打ち立て、紅白ではダントツの瞬間最高視聴率を記録した。
こんなシンガー泣かせの難曲が、当時カラオケでバリバリに歌われていたというのはある意味驚異だ。(1997年オリコン年間カラオケリクエスト回数1位)
■ m-flo(feat.加藤ミリヤ) - ONE DAY
広い声域を縦横無尽に活かした例
2000年代後半からのボカロの普及により楽曲は大きくハイトーンサイドに振れたが、最近ではカラオケでボカロ系の曲がふつうに歌われるようになってきた。
小室サウンド以上にハイトーンを多用し難易度が高いとみられるボカロ曲を、唱いこなすアマチュアも増えてきているのではないか。(ハイトーンは歌い込むほどに身についていくという説がある。)
カラオケだけでなく、Web上に「歌ってみた」というテーマで投稿する人(「歌い手」と呼ばれる)も続々とあらわれ、独自のシーンを形成。そのメインストリームもやはりハイトーン系だ。
〔ハイトーン歌い手の例〕
■ 佳仙 - Last Night,Good Night(歌ってみた)
■ ちょうちょ - メルト(歌ってみた)
J-POP界でも、「ハイトーン曲の方が売れる(というかハイトーンじゃないと売れない)」という傾向がたしかにあるようで、ハイトーン化は時代の大きな流れになっているのではないか。
2.声の艶
これはハイトーンと連動しているが、高音でも声の艶や力感を失わないアーティストが増えてきた。
地声でハイトーンまでもっていくと、どうしても無理が感じられるが、ミックス(ミドル)ヴォイスなどの技法を身につけていると、力強い(息漏れのない)裏声でハイトーンをクリアすることができる。
最近のヴォーカルスクールはこのミックス(ミドル)ヴォイスの習得を売りにしているところも多く、それだけ艶(力感)のあるハイトーンが求められていることがわかる。
■ 橋本みゆき - 未来ノスタルジア
■ 荒牧陽子 - Only Love
3.ビブラート
歌に趣や変化を与えるとされる技法。プロがプロらしくきこえるのは、このビブラートの扱いによるところが大きいと思う。
J-POPでは演歌系のこぶし(波長の長い音程のビブラートをサビで強く効かせる)より、やや波長を短くした繊細なビブラートを流していくほうが受けがいいように感じる。
ビブラートはある程度レッスンを受ければ身につけられるともいわれているが、声の艶とあいまって真価を発揮する感がつよく、やはり天性の声質や発声スタイルが求められるのだと思う。
どこのパートでどこまでビブラートを聴かせるか、これは最近の女性ヴォーカルの大きな聴きどころだ。
■ 鹿子 - glow(歌ってみた)
■ 奏夢 - さよならメモリーズ(歌ってみた)
個人的には↑の1-3までを「女神系歌姫3種の神器」と考えていて、これが最近の女性ヴォーカリスト大きな特徴になっていると思う。
最近の曲構成は、RapやTranceの影響もあって、イントロ~Aサビ~Bサビ~ブリッヂ~A'サビ~エンド、つうよ~な従来型の構成じゃなく、「サビがあるのかないのかわからないが、なんとなくずーっとサビにきこえる」といった、ひねった曲が多いが、これは声の艶や繊細なビブラートがないとたちまちお経になってしまうので、曲調からも声の艶やビブラートが求められているのだと思う。
↑の例
■ Lisa Halim - いつまでも... feat.中村舞子
■ MARINA. - One love ~恋におちて~
4.声質がフェミニンで癒し系 (ヒーリングヴォイス・エンジェルヴォイス)
女性ならではの甘い声質のヴォーカルが増えてきた。
声優系のアーティストには、この系譜に連なるタイプがとくに多い。
また、Rapにはたおやかな女性Vocalが意外に合うが、そういう背景もあるのだと思う。
YouTubeなどの動画系サイトで「作業用」と称して編集されたコンテンツがある。
ふつうPCなどの机上作業をしつつきき流すものと思われるが、これなどもやわらかで心地よい声質のヴォーカルがフューチャーされているものが多い。
サウンド探しのキーワードでも、「癒し、ヒーリング、エンジェルボイス、透明感」などを目にすることが増えてきた。
もともと日本人は圧倒的歌唱力で押しまくるより、繊細なテクや微妙な感情表現を得意とするアーティストが多いので、このような流れに乗りやすいのではないか。
■ リツカ - ハロ/ハワユ(歌ってみた)
■ ばきこ(bakiko) - ただ泣きたくなるの(カバー)
■ 志方あきこ - Erato
作風と同様ナゾの多い?Artist。どちらかというとシリアスな作風だが、ときおりつくるヒーリング系楽曲では天才的な切れ味と圧倒的な完成度をみせ、希有の才能をもっているとみられる。
透明感&浮遊感あふれるハイトーンヴォイスも魅力。
5.音数、というかことば数が多い (滑舌)
'80年代だったら「わすれかけてた~」が、「わあすれかけてえた~」となって、ひとつの音にのることばの数が圧倒的に多い。
これは絶対、Rapの影響があると思う。じっさい、彼女らとRapのコラボ(ふつうfeat.~~とされる)はやたらに多くて、MC(韻を踏んだRap)なんぞもふつうに入ってくる。
小室哲哉氏は「デジカメの画素数と同じように、”音符のサイズ”も変わってきてるんですよ。昔は4分音符1個は小さい単位だった。今はすごく巨大。2万~3万円の機材を使えば4分音符1個を128分割ぐらいまでできます。」(出典:「R25」2014.5.15_No.350㈱リクルートホールディングス刊)と語っているが、そのような背景もたしかにあると思う。
滑舌(かつぜつ)とは、せりふをはっきりと聴き取りやすく発音するための舌や口の動きの技法をさし、どちらかというとアナウンスや舞台の世界で使われてきたことばだが、最近では音楽の世界でもよくつかわれる。
これは滑舌のよさが問われる声優系の存在が大きいと思う。
また、ボカロ系の歌には、滑舌の技法なしでは唱いこなし不可能なものも多く存在し、すぐれたテクニックを披露してくれる歌い手もすくなくない。
■ Daisy×Daisy(MiKA) - 永久のキズナ
■ ヲタみん - 地球最後の告白を(歌ってみた)
6.セツナ系
メロディや歌詞が「せつなさ」や「はかなさ」を感じさせるもので、リスナーのパーソナルな感情に訴えかけるフォーマット(というか曲調)が人気を集めている。
「セツナ系」は西野カナ、加藤ミリヤ、JUJU、中村舞子などの「女神系歌姫」が代表格とされ、hip hop/Rap系ユニットとのコラボ(ふつうfeat.とされる)による名曲が多いのも特徴で、中村舞子のように自身のメジャーデビューよりも先にfeat.曲で人気を集める例もすくなくない。
日本のアニメは各国で高い評価を得ているが、それはストーリー展開やキャラクタ-設定の巧みさ、緻密なグラフィック技術とともにアニソンの果たす役割も大きいのではないか・・・。
アニソンはその性格上、ストーリー性や情緒感をもつものが多く、それがリスナーの感情に訴えやすいということもあると思う。(日本独自の繊細な風土や思想などをモチーフにするものも増えてきた。)
また、声優がアニソンを歌う例も多い。声優はもともと声質や表現力に優れているので、ハンパな歌手など軽く凌ぐ歌いぶりを聴かせてくれることも少なくない。
また、ボカロ系でも情感に訴えるフックをもったメロディをもつ曲が多いものの、たいていが難曲なのでヴォーカルが途中で破綻するリスク大。それだけに、破綻せずに歌いきったときのインパクトは強烈で、一部で伝説化するテイクも・・・。
★ボカロ系難曲の例
■ ここにあること - @うさ(歌ってみた)
難音階&難譜割り&バリバリ転調で一般人はふつうに迷子になりそ~(笑)。コード進行も凄い(→chordwiki)
これらの曲はかつてのニューミュージックや演歌などの「マイナーコードを多用してしっとりと歌い上げる」というものより、むしろメジャー系コードやRap、ブレイクビーツなどをつかいつつこれを醸成していくものが目立つ。 (淡々と流れながらも泣ける・・・ ^^)
「メジャー系コードやブレイクビーツをつかいつつ、繊細な情感を出していく」というのはできそうでなかなかできないので、ここでもJ-POPのレベルの高さがうかがわれるのでは・・・。
★夏系ソングの比較
【むかし】
■ 松田聖子 - P・R・E・S・E・N・T(1982)
どこまでもすこ~んと抜けててブライト。
【女神系】
■ KOTOKO - allegretto -そらときみ
メジャー系音階ながらどこかせつなげ。
★セツナ系の例
■ 癒月 - you / thanks (ひぐらしのなく頃に)
ゲーム・アニメ系のストーリー性高い曲の例。
同人系のArtistで声優としても活動。メリハリがありながらヒーリング感の高いすぐれた声質をもつ。「雪月」名義でユニット活動も。
これはゲーム「ひぐらしのなく頃に」の名曲とされるBGM。
■ Because... feat. 中村舞子 LGYankees (2008)
feat.型「セツナ系」の代表曲
■ 花たん - 心做し(歌ってみた)
歌い手系の絶品「セツナ系」、楽曲、ヴォーカルともに文句のつけようなし。
------------------------------------------
こうしてみると、女神系歌姫のポイントは「優れた声質」「高いテクニック」と「繊細な情緒感」ではないかと思われる。
そんなのはそうはいないと思いきや、どうしてどうしてだれもかれもが相当な完成度!!
でもって、ルックスばっちりの歌姫系(^^)
■ YUUKI(吉田有希)/Sound Horizon - 美しきもの(Roman~僕達が繋がる物語~)
■ 平野綾 - For You
■ Silent Siren - I×U
そんなわけで、彼女たちを”女神系歌姫”、創り出す音楽を”ハイトーンJ-POP”と銘打ってみたわけです。
どうして、日本でこのような”女神系歌姫”が輩出されるようになったのか、たぶんおそらくいろいろな要素や時代的背景が複合していると思うのですが(女神系歌姫は難曲とカラオケとボカロが育てた?)、これについては別に書くことにします。
↑ これに関連した記事をこちら(黄金の世代?(カラバトU-18が強い件))で書いていますので、よろしければご覧くださいませ。
■ 熊田このは「明日への手紙 (手嶌葵)」2016/05/21 HEP前 路上ライブ
〔関連記事〕
■ My Favorites 25 (from 女神系歌姫)
■ 女神系歌姫 【Angel Voice列伝 】のリスト
やっぱりこの分野のレベル異様に高いわ。
そこで、以前別ブログにUPした「女神系歌姫」たち100人以上の動画を、リンクつなぎなおしコメントを補足してUPしていきます。
リストした曲は個人的に好みのテイクで、かならずしも代表曲というワケではありません。
掲載順は順不同ですが、元ブログの掲載順を踏襲しています。
まずは、こちら(女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-10 】)からはじめます。
--------------------
2021/12/24 UP
この記事は筆者の別ブログ(ameblo)に2014/08/09にUPしたものですが、リンクつなぎ直してこちらのブログにリニューアルUPします。
(文章やリンク曲は手を入れていないので、2014年夏時点のものです。)
--------------------------------
【女神系歌姫】とは
エンヤのブレークをきっかけに一気に盛り上がった「ケルティック・ウーマン」ブーム。
ハイトーンのヒーリングヴォイスをその特徴とするアイルランドのPOPSは、全世界で高い支持を集めています。
でも、いまの日本の女性ヴォーカルのレベルは、それに勝るとも劣らないものがあるのでは。
■ Little Glee Monster - HARMONY(PV)
マスコミで注目度上昇中の激ウマグループLittle Glee Monster。
歌の巧さがますます求められる時代に入ったか?
(個人的に)女性ヴォーカルのメインになっていると思われる「女神系歌姫」について、これまでいくつかの記事に書き散らした内容を、整理してみたいと思います。
■ 上野洋子 - 協和発酵 焼酎「かのか」CM (曲名:「風と花と光と」)
女神系歌姫の走り?
【女神系歌姫とは】
1990年代中盤頃から、少しづつ邦楽の、とくに新世代の女性Artistの質感が変わってきた。
この流れは2000年代中盤から決定的になってくるのだが、まずはその特徴について考えてみた。
1.ハイトーン・ヴォイス
とにかくオクターブが高くなり、音階も広がった。
これは安室奈美恵、華原朋美、観月ありさ、globeなど、「小室ファミリー」といわれた一連の女性Vocalistの影響があると思う。
彼女らの超ハイトーン曲をふつうにカラオケで唄っていた次世代層が育ってきたということか・・・。
■ 歌ってみた Can You Celebrate
■ 歌ってみた I'm proud
■ 歌ってみた 月光
※ すべてリンク切れ
たとえば安室奈美恵の『CAN YOU CELEBRATE?』。
曲の構成はPOPというよりむしろプログレ的な大作で、音域も広くてどうみてもトーシロの手に負える曲じゃない・・・。
にもかかわらず、その曲は売り上げ、カラオケランキングともに数々の記録を打ち立て、紅白ではダントツの瞬間最高視聴率を記録した。
こんなシンガー泣かせの難曲が、当時カラオケでバリバリに歌われていたというのはある意味驚異だ。(1997年オリコン年間カラオケリクエスト回数1位)
■ m-flo(feat.加藤ミリヤ) - ONE DAY
広い声域を縦横無尽に活かした例
2000年代後半からのボカロの普及により楽曲は大きくハイトーンサイドに振れたが、最近ではカラオケでボカロ系の曲がふつうに歌われるようになってきた。
小室サウンド以上にハイトーンを多用し難易度が高いとみられるボカロ曲を、唱いこなすアマチュアも増えてきているのではないか。(ハイトーンは歌い込むほどに身についていくという説がある。)
カラオケだけでなく、Web上に「歌ってみた」というテーマで投稿する人(「歌い手」と呼ばれる)も続々とあらわれ、独自のシーンを形成。そのメインストリームもやはりハイトーン系だ。
〔ハイトーン歌い手の例〕
■ 佳仙 - Last Night,Good Night(歌ってみた)
■ ちょうちょ - メルト(歌ってみた)
J-POP界でも、「ハイトーン曲の方が売れる(というかハイトーンじゃないと売れない)」という傾向がたしかにあるようで、ハイトーン化は時代の大きな流れになっているのではないか。
2.声の艶
これはハイトーンと連動しているが、高音でも声の艶や力感を失わないアーティストが増えてきた。
地声でハイトーンまでもっていくと、どうしても無理が感じられるが、ミックス(ミドル)ヴォイスなどの技法を身につけていると、力強い(息漏れのない)裏声でハイトーンをクリアすることができる。
最近のヴォーカルスクールはこのミックス(ミドル)ヴォイスの習得を売りにしているところも多く、それだけ艶(力感)のあるハイトーンが求められていることがわかる。
■ 橋本みゆき - 未来ノスタルジア
■ 荒牧陽子 - Only Love
3.ビブラート
歌に趣や変化を与えるとされる技法。プロがプロらしくきこえるのは、このビブラートの扱いによるところが大きいと思う。
J-POPでは演歌系のこぶし(波長の長い音程のビブラートをサビで強く効かせる)より、やや波長を短くした繊細なビブラートを流していくほうが受けがいいように感じる。
ビブラートはある程度レッスンを受ければ身につけられるともいわれているが、声の艶とあいまって真価を発揮する感がつよく、やはり天性の声質や発声スタイルが求められるのだと思う。
どこのパートでどこまでビブラートを聴かせるか、これは最近の女性ヴォーカルの大きな聴きどころだ。
■ 鹿子 - glow(歌ってみた)
■ 奏夢 - さよならメモリーズ(歌ってみた)
個人的には↑の1-3までを「女神系歌姫3種の神器」と考えていて、これが最近の女性ヴォーカリスト大きな特徴になっていると思う。
最近の曲構成は、RapやTranceの影響もあって、イントロ~Aサビ~Bサビ~ブリッヂ~A'サビ~エンド、つうよ~な従来型の構成じゃなく、「サビがあるのかないのかわからないが、なんとなくずーっとサビにきこえる」といった、ひねった曲が多いが、これは声の艶や繊細なビブラートがないとたちまちお経になってしまうので、曲調からも声の艶やビブラートが求められているのだと思う。
↑の例
■ Lisa Halim - いつまでも... feat.中村舞子
■ MARINA. - One love ~恋におちて~
4.声質がフェミニンで癒し系 (ヒーリングヴォイス・エンジェルヴォイス)
女性ならではの甘い声質のヴォーカルが増えてきた。
声優系のアーティストには、この系譜に連なるタイプがとくに多い。
また、Rapにはたおやかな女性Vocalが意外に合うが、そういう背景もあるのだと思う。
YouTubeなどの動画系サイトで「作業用」と称して編集されたコンテンツがある。
ふつうPCなどの机上作業をしつつきき流すものと思われるが、これなどもやわらかで心地よい声質のヴォーカルがフューチャーされているものが多い。
サウンド探しのキーワードでも、「癒し、ヒーリング、エンジェルボイス、透明感」などを目にすることが増えてきた。
もともと日本人は圧倒的歌唱力で押しまくるより、繊細なテクや微妙な感情表現を得意とするアーティストが多いので、このような流れに乗りやすいのではないか。
■ リツカ - ハロ/ハワユ(歌ってみた)
■ ばきこ(bakiko) - ただ泣きたくなるの(カバー)
■ 志方あきこ - Erato
作風と同様ナゾの多い?Artist。どちらかというとシリアスな作風だが、ときおりつくるヒーリング系楽曲では天才的な切れ味と圧倒的な完成度をみせ、希有の才能をもっているとみられる。
透明感&浮遊感あふれるハイトーンヴォイスも魅力。
5.音数、というかことば数が多い (滑舌)
'80年代だったら「わすれかけてた~」が、「わあすれかけてえた~」となって、ひとつの音にのることばの数が圧倒的に多い。
これは絶対、Rapの影響があると思う。じっさい、彼女らとRapのコラボ(ふつうfeat.~~とされる)はやたらに多くて、MC(韻を踏んだRap)なんぞもふつうに入ってくる。
小室哲哉氏は「デジカメの画素数と同じように、”音符のサイズ”も変わってきてるんですよ。昔は4分音符1個は小さい単位だった。今はすごく巨大。2万~3万円の機材を使えば4分音符1個を128分割ぐらいまでできます。」(出典:「R25」2014.5.15_No.350㈱リクルートホールディングス刊)と語っているが、そのような背景もたしかにあると思う。
滑舌(かつぜつ)とは、せりふをはっきりと聴き取りやすく発音するための舌や口の動きの技法をさし、どちらかというとアナウンスや舞台の世界で使われてきたことばだが、最近では音楽の世界でもよくつかわれる。
これは滑舌のよさが問われる声優系の存在が大きいと思う。
また、ボカロ系の歌には、滑舌の技法なしでは唱いこなし不可能なものも多く存在し、すぐれたテクニックを披露してくれる歌い手もすくなくない。
■ Daisy×Daisy(MiKA) - 永久のキズナ
■ ヲタみん - 地球最後の告白を(歌ってみた)
6.セツナ系
メロディや歌詞が「せつなさ」や「はかなさ」を感じさせるもので、リスナーのパーソナルな感情に訴えかけるフォーマット(というか曲調)が人気を集めている。
「セツナ系」は西野カナ、加藤ミリヤ、JUJU、中村舞子などの「女神系歌姫」が代表格とされ、hip hop/Rap系ユニットとのコラボ(ふつうfeat.とされる)による名曲が多いのも特徴で、中村舞子のように自身のメジャーデビューよりも先にfeat.曲で人気を集める例もすくなくない。
日本のアニメは各国で高い評価を得ているが、それはストーリー展開やキャラクタ-設定の巧みさ、緻密なグラフィック技術とともにアニソンの果たす役割も大きいのではないか・・・。
アニソンはその性格上、ストーリー性や情緒感をもつものが多く、それがリスナーの感情に訴えやすいということもあると思う。(日本独自の繊細な風土や思想などをモチーフにするものも増えてきた。)
また、声優がアニソンを歌う例も多い。声優はもともと声質や表現力に優れているので、ハンパな歌手など軽く凌ぐ歌いぶりを聴かせてくれることも少なくない。
また、ボカロ系でも情感に訴えるフックをもったメロディをもつ曲が多いものの、たいていが難曲なのでヴォーカルが途中で破綻するリスク大。それだけに、破綻せずに歌いきったときのインパクトは強烈で、一部で伝説化するテイクも・・・。
★ボカロ系難曲の例
■ ここにあること - @うさ(歌ってみた)
難音階&難譜割り&バリバリ転調で一般人はふつうに迷子になりそ~(笑)。コード進行も凄い(→chordwiki)
これらの曲はかつてのニューミュージックや演歌などの「マイナーコードを多用してしっとりと歌い上げる」というものより、むしろメジャー系コードやRap、ブレイクビーツなどをつかいつつこれを醸成していくものが目立つ。 (淡々と流れながらも泣ける・・・ ^^)
「メジャー系コードやブレイクビーツをつかいつつ、繊細な情感を出していく」というのはできそうでなかなかできないので、ここでもJ-POPのレベルの高さがうかがわれるのでは・・・。
★夏系ソングの比較
【むかし】
■ 松田聖子 - P・R・E・S・E・N・T(1982)
どこまでもすこ~んと抜けててブライト。
【女神系】
■ KOTOKO - allegretto -そらときみ
メジャー系音階ながらどこかせつなげ。
★セツナ系の例
■ 癒月 - you / thanks (ひぐらしのなく頃に)
ゲーム・アニメ系のストーリー性高い曲の例。
同人系のArtistで声優としても活動。メリハリがありながらヒーリング感の高いすぐれた声質をもつ。「雪月」名義でユニット活動も。
これはゲーム「ひぐらしのなく頃に」の名曲とされるBGM。
■ Because... feat. 中村舞子 LGYankees (2008)
feat.型「セツナ系」の代表曲
■ 花たん - 心做し(歌ってみた)
歌い手系の絶品「セツナ系」、楽曲、ヴォーカルともに文句のつけようなし。
------------------------------------------
こうしてみると、女神系歌姫のポイントは「優れた声質」「高いテクニック」と「繊細な情緒感」ではないかと思われる。
そんなのはそうはいないと思いきや、どうしてどうしてだれもかれもが相当な完成度!!
でもって、ルックスばっちりの歌姫系(^^)
■ YUUKI(吉田有希)/Sound Horizon - 美しきもの(Roman~僕達が繋がる物語~)
■ 平野綾 - For You
■ Silent Siren - I×U
そんなわけで、彼女たちを”女神系歌姫”、創り出す音楽を”ハイトーンJ-POP”と銘打ってみたわけです。
どうして、日本でこのような”女神系歌姫”が輩出されるようになったのか、たぶんおそらくいろいろな要素や時代的背景が複合していると思うのですが(女神系歌姫は難曲とカラオケとボカロが育てた?)、これについては別に書くことにします。
↑ これに関連した記事をこちら(黄金の世代?(カラバトU-18が強い件))で書いていますので、よろしければご覧くださいませ。
■ 熊田このは「明日への手紙 (手嶌葵)」2016/05/21 HEP前 路上ライブ
〔関連記事〕
■ My Favorites 25 (from 女神系歌姫)
■ 女神系歌姫 【Angel Voice列伝 】のリスト
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 柴原温泉 「菅沼館」 【閉館】
この施設は2010年秋に閉館しています。
秩父屈指の名湯といわれた柴原鉱泉「菅沼館」は、2010年10月に閉館しています。
筆者は温泉仲間とともに閉館1ヶ月前の2010年9月に宿泊していますが、ネタが多すぎるためついつい放置プレーとなり(笑)、気がついたら12年が経過してしまいました。
一念発起して、記録の意味でレポをUPします。
 柴原温泉 「菅沼館」
柴原温泉 「菅沼館」
住 所 :埼玉県秩父市荒川贄川2050
電 話 :日帰り入浴不可/2010年10月閉館
時 間 :同上
料 金 :同上
秩父には、江戸時代から「秩父七湯」と呼ばれるいで湯がありました。
1.新木の湯 (新木鉱泉)
2.鳩の湯 (鳩の湯温泉、温泉施設は閉館)
3.柴原の湯 (柴原温泉)
4.千鹿谷の湯(千鹿谷温泉、温泉施設は閉館)
5.鹿の湯 (白久温泉、温泉施設は閉館)
6.梁場の湯 (現存せず)
7.大指の湯 (現存せず)
うち、5.6.7は早くに廃湯となり、2.4は近年閉館して温泉施設の営業はありません。
「菅沼館」は3.柴原の湯 (柴原温泉)の湯治宿でしたが、2010年10月に閉館しています。
柴原の湯 (柴原温泉)は旧小野原村と旧贄川村の境にあって、『新編武蔵風土記稿』の小野原村の項には「温泉 小名芝原ニアリ 村の北方ニシテ贄川村界の谷間ニテ 両岸ニ湯潭一ヶ所ツゝアリ 共ニ大サ五尺ニ二尺五六寸ハカリ 石モテ積立シ潭ナリ 其由来ヲ尋ヌルニ イツノ頃ヨリ湧出ルコトニヤ知モノナシ 慶安五年(1652年)村ノ水帳ニモ此邊ヲ湯本ト記セシヨシ 其古キ●ヲシテ知ヘシナレト 諸方ヘ聞ヘテ賑ヒシハ近世ノ事ナリト云 今ニ年々三四六七ノ四ヶ月ハ分テ賑ヒ群集スト云リ 此湯ノ効験ハ打身疝気或ハ虚分●気其外 諸病ニ益シト云 瘡毒癩瘡ノ如キニ至リテハ 甚タコレヲ禁ストナリ 両村ノ地ニ跨リ民家六戸アリ イツレモ病客ノ往来スルヲ以テ業トセリ」とあります。
谷間に湯つぼがあり、慶安五年(1652年)の村の資料にも記載され、近世には大いに賑わい湯治宿が6軒あったことなどが記されています。
『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)の(小野原鎮座)稲荷神社の項には「柴原は古くから鉱泉で有名であり、その湯本には昭和36年に焼失した本社(稲荷神社)の社殿建築と同じ宮大工が造ったという、見事な彫刻が施された湯権現社が祀られている。なお、同社の建築年代は江戸中期と思われる。」とあり、すでに江戸中期には湯本守護神としての湯権現社が祀られていたことがわかります。

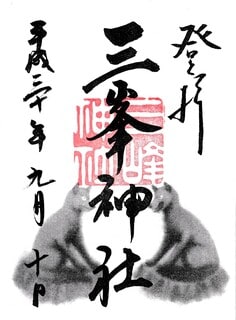
【写真 上(左)】 三峯神社
【写真 下(右)】 三峯神社の御朱印
Web上には出所不明ながら「柴原温泉は三峯神社の登拝口として賑わった」という記事がいくつかみつかります。
気になったので少し調べてみました。
『荒川村贄川における集落機能と生業形態の変化』(河野敬一氏・平野哲也氏/1991年)には「(贄川は)甲州、信州への交通路、三峰山への参詣路、荒川渡船など、交通の要衝に存在」、「昭和5年(1930年)には対岸の白久に秩父鉄道の三峰口駅が開設された。(中略)秩父参詣者は秩父鉄道を利用し、三峰口駅から白川橋を渡り贄川宿を通らずに参詣できるようになった。」とあります。
また、「三峰山は修験の山で、江戸時代中期以降、農業や火伏せ盗賊除けの神として庶民の間で信仰が盛んになり参詣客が増加した。(中略)参詣を終えるとすぐに下山し、贄川の宿屋を利用するものも多かった。明治期の贄川には『角屋』『角六』『丸太』『逸忠館』『小櫃屋』『油屋』という6軒の旅館が存在した。」
「近世期以来、(贄川の)町分の東の入口には三峰神社の一の鳥居が存在し、三峰神域の入口とされていた。贄川から三峰神社までの約10㎞は、険しい山越えのルートだったため、参詣の前夜に贄川で一泊し、翌朝早く発って三峰神社へ参拝し、夕方再び贄川へ戻り、さらに一泊して帰郷するという行程が一般的であった。」という記載もあり、昭和5年の秩父鉄道開通以前、三峯神社参詣者は贄川経由の登拝がメインであったことを示唆しています。
『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)の(贄川鎮座)八幡大神社の項に「贄川の宿は、三峰山への登拝路における最後の宿場としても大きい役割を担ってきた。当時、登拝日の決まっていた(三峰)講社に対して、神社からの使者がこの贄川の宿まで講社の人々を出迎え、道中の労をねぎらった。帰路に当たっても、使者が講社の人々を贄川まで送り、別れの盃を交わし、道中の無事を祈るとともに、翌年の参拝が約束された。こうした贄川の宿を中心とした三峰神社と講社との結びつきが、三峰講を支える大きな柱の一つとなっていた」とあります。
また、同書の(白久鎮座)熊野神社の項に「三峰詣の登拝順路にあたる当地は、三峰山の信仰と関連するところが多い。なお、この登拝路は、紀州熊野詣の形に類似しているともいわれ、彼地九十九王子に、猪鼻王子が現在でも残っている。」とあります。
いまの地理感から考えると三峰神社からかなり離れた麓の贄川に、登拝口や一の鳥居があったのは不思議な感じもしますが、『江戸における三峰信仰の展開とその社会的背景』(三木一彦氏/2001年)によると、江戸小日向(現・文京区)からの三峰詣ではじつに9泊10日の行程を要していたそうですから、贄川(柴原)~三峰間の10㎞強程度は「すぐ下の麓」という感覚だったのでしょう。
また、三峰山麓には熊野信仰の影響を受けて九十九王子が奉安されていたようで、神域内に(九十九王子を奉安するための)ある程度の距離が必要だったのでは。
贄川と柴原は、道筋こそことなるものの距離的にはさほど離れていません。
上記のとおり三峰講と贄川の宿の結びつきが強かったとすれば、表立って柴原の湯宿に泊まることは憚られたのかもしれませんが、帰途であれば精進落としの意味もあって、温泉で疲れを癒すニーズもあったであろうことは容易に想像できます。
実際『(埼玉県)宮代町史』には、三峰講による三峰神社への代参は毎年4月、川崎市資料にも「多摩区生田の土淵では、4月に代参者2名を(三峰講として)秩父の三峰神社に送った。」とあり、『新編武蔵風土記稿』の「(柴原温泉は)年々三四六七ノ四ヶ月ハ分テ賑ヒ群集ス」という記事と符合しています。
ただし、柴原の湯の本分は湯治であったこと、また、三峰講と贄川宿の強固な関係からして、柴原の湯で参詣客の利用があっても大っぴらにできなかったため、三峰講絡みの記録が少ないのかもしれません。
三峰講は関東平野を中心に多くの代参講が組織されており、(参考:関東平野における三峰信仰の展開(三木一彦氏/2005年))そのほとんどは徒歩による参詣だったので、三峰山麓の宿泊需要は旺盛だったと思われます。
田植え期間をのぞく春~初夏の三峯参詣繁忙期には、贄川の6軒の宿では足りず柴原の湯の宿に送客したこともあったのでは?
ただし、三峰講の旅程はおそらく地元の講元で管理されており、贄川が満杯で柴原の湯に泊まったとしても記録としては贄川泊になったと思われます。
こうした点からも三峰講と柴原の湯のつながりが残りにくかったのかもしれません。
秩父札所三十四ヶ所観音霊場との関係も考えられます。
秩父札所三十四ヶ所観音霊場は文暦元年(1234年)開創と伝わる古い霊場で、長享二年(1488年)の秩父札所番付が実在することから、室町時代後期には定着していたとされます。
西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所とともに日本百番観音に数えられるメジャー霊場で、江戸時代に入るといよいよ盛んに巡拝されました。


【写真 上(左)】 第30番 法雲寺
【写真 下(右)】 第30番 法雲寺の御朱印

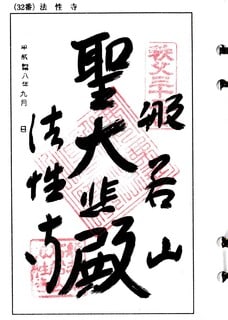
【写真 上(左)】 第32番 法性寺
【写真 下(右)】 第32番 法性寺の御朱印
柴原は第30番瑞龍山 法雲寺と第32番般若山 法性寺を結ぶ道筋にあり、秩父札所の巡拝者が泊まりに利用した可能性があります。
(直接関係ないですが、秩父札所に曹洞宗寺院が多い理由を考察した興味ぶかい論文がみつかりましたのでご紹介します。→こちら(『武蔵国秩父札所三十四観音霊場の形成にみる中世後期禅宗の地方展開』(小野澤眞氏/2012年))
以上からすると、柴原の湯 (柴原温泉)は江戸時代から、湯治客、三峰講、秩父札所という集客3チャネルを持っていた可能性があり、これが山あいの湯場ながら6軒の湯宿を支えた背景なのかもしれません。
大正14年刊の『埼玉県秩父郡誌』にも柴原鉱泉は以下のとおり記載されています。
「柴原鉱泉は其の発見江戸時代初期にあり。現今浴客を収容するの設備漸く完全ならんとす。」
明治維新後も大正くらいまではかなりの浴客を迎えていたことがわかります。
*************
前置きが長くなりました。


【写真 上(左)】 柴原温泉
【写真 下(右)】 右手おくが「菅沼館」
柴原温泉には、2010年時点で「かやの家」(旧称:白百合莊)「柳屋」「菅沼館」の3軒の湯宿がありました。(「きくや」もまだ営業中だったかもしれませんが詳細不明。)
かつての6軒の湯宿は3軒になっているものの、「かやの家」は”日本秘湯を守る会会員宿”、「柳屋」は名物の手打ち蕎麦と日帰り入浴、「菅沼館」は湯治宿とうまく棲み分けしていました。
わけても「菅沼館」のお湯はコアな温泉マニアのあいだで定評があり、日帰り入浴不可ということもあってナゾ多きお湯となっていました。
(じつは、筆者はダメもとで突入し日帰り入浴を乞うたことがあるのですが、「ここは湯治宿なので・・・」とやんわりお断りされた過去があります。)
この温泉マニア垂涎の「菅沼館」が廃業するという情報が出たのはたしか2010年春頃。
これを受けて温泉仲間が廃業直前に貸し切りのオフ会を設定してくださり、これに参戦するかたちでついに初入湯を果たしました。
湯治宿ですが、1泊2食付での宿泊としました。


【写真 上(左)】 庭内エントランス
【写真 下(右)】 庭先のサイン


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 帳場棟
「かやの家」「柳屋」は湯宿としてわかりやすい外観ですが、沢にかかる小橋を渡った最奥の「菅沼館」は湯治宿だけあって民家的な構え。
「柳屋」の裏手的な立地でややわかりにくいですが、庭先に「菅沼館」の看板が出ているので迷うことはありません。


【写真 上(左)】 玄関扁額
【写真 下(右)】 客室棟から帳場棟


【写真 上(左)】 客室棟-1
【写真 下(右)】 客室棟-2
正面が切妻屋根一層の帳場棟。そこから手前に向かってL字型に2層の客室棟が伸びています。築300年の歴史をもつようです。
玄関にはきっちりと宿名扁額を掲げて好ましげなたたずまい。
1階の帳場まわりもいい意味で年季が入って風格さえ帯びています。


【写真 上(左)】 帳場まわり-1
【写真 下(右)】 帳場まわり-2


【写真 上(左)】 1階
【写真 下(右)】 1階廊下
泊まったのは2階。湯治宿らしい開放感あふれる外廊下。
山あいの9月の涼やかな風が、網戸ごしに心地よく吹き込んできます。
窓からは手前に「柳屋」、すこし離れて「かやの家」が望めます。


【写真 上(左)】 階段
【写真 下(右)】 2階廊下


【写真 上(左)】 2階客室-1
【写真 下(右)】 2階客室-2
部屋数はすみませぬ覚えていません。
貸し切りだったので、ふすま開け放しで広々とつかいました。


【写真 上(左)】 館内の扁額
【写真 下(右)】 湯治宿の趣
湯治宿ですが部屋のつくりはよく、床の間に掛け軸も。
すみずみまで清掃が行き届いてきもちがいいです。


【写真 上(左)】 格言の扁額
【写真 下(右)】 句碑


【写真 上(左)】 スリッパ
【写真 下(右)】 室番
館内各所に格言や句、趣味のいい風景画などが掲げられ、ご主人は相当な風流人では?
スリッパの文字は館名ではなく「ゆもと」。湯元宿としての矜持が感じられます。
写真の撮影時間からすると、入浴は早朝から20時まで。
夕食は18時、朝食は7時半からだったと思います。
入浴20時まで、朝食7時半からは、さすがに保守本流の正統派湯治宿。なんちゃって系ではありません(笑)


【写真 上(左)】 夕食
【写真 下(右)】 朝食
食事は家庭料理的メニューでしたが、素材と味つけがよく、予想以上に満足いくものでした。
浴室は広くなく宿泊人数がそれなりにいたので忙しい入浴となりましたが、それでも夕・朝ともにこの名湯を満喫できました。
*************
入湯レポの前に、すこしく柴原温泉の泉源について触れてみます。
柴原温泉の泉源地は、沢沿いに建つ「柳屋」の玄関向かって左手のパイプが引かれた小径を沢沿いに遡ったところにあります。


【写真 上(左)】 柳屋
【写真 下(右)】 柳屋の脇の道です


【写真 上(左)】 淵
【写真 下(右)】 湯大権現宮入口
9月の頃合いでは草木が生い茂り、よほどの好き者でない限り探る気にはならないかと。
「柳屋」脇の小径をしばらく登ると「湯大権現宮入口」の標柱と祠?があらわれます。
このあたりの沢は淵となっていて小滝が流れ込んでいます。


【写真 上(左)】 登ります
【写真 下(右)】 乗っ越した先の沢と林相
ここから急な登りとなりますが、道沿いにパイプが数本引かれているので泉源に向かっていることがわかります。
小さな高みをひとつ乗っ越すと、再び沢沿いとなりここにも数本のパイプが見えます。
ここまで基本は沢沿いの道で徒渉はないですが、ところどころ苔で滑りやすいので要注意。
あたりはうっそうと木々が茂り、沢音だけが響きます。


【写真 上(左)】 湯大権現宮が見えてきます
【写真 下(右)】 湯大権現宮
ひとしきり沢を遡上すると切妻造妻入木造一部ブロック造トタン覆の建物が見えてきます。
こちらが「湯大権現宮」の覆屋です。
よこに説明板がありましたので転記します。
---------------------
荒川村指定有形文化財 湯大権現宮 平成二年四月九日指定
この社は江戸時代の嘉永年間(1848-1854年)に磐若村(現在の小鹿野町磐若)の神田雄七郎という大工棟梁によって建立されたもので、彫刻なども見事であるが一部欠けたりしており、聞く所によると盗難にあったといわれている。
社のわきに掘られている井戸は、柴原温泉に使われる湯がわき出している。
この湯は、弱アルカリ性硫化水素がふくまれており、ゆで玉子に似たにおいがする。
この井戸がいつ頃掘られたかは、湯元・菅沼館に口伝されている所によると、鎌倉時代とも藤原時代ともいわれているという。
以前、菅沼館では湯治客が自炊をしていたので、その火のために何度か火災に会い(ママ)、文書は焼失し口伝だけが残っているのだという。
この社には大己貴神(大国主命)と少彦名命の二神が祭られている。
荒川村教育委員会
---------------------


【写真 上(左)】 湯大権現宮社殿
【写真 下(右)】 湯大権現宮と手前が菅沼館泉源
「湯大権現宮」の覆屋には「●有者菅沼館」の木板が掲げられていました。
覆屋内には神田雄七郎作と伝わる社殿が安置され、市指定有形文化財に指定されています。
市の公式Webには「社の脇にある井戸からは、鉱泉が湧き出ており、温泉郷の湯元となっている。現在の社は、嘉永・安政年間(1848~1860)、般若村(現小鹿野町)の棟梁神田雄七郎の手によるもので、規模は小さいが、重厚で格調の高い風格を備えている。」とあります。
小ぶりながら千鳥破風、軒唐破風を備え、水引虹梁まわりに精緻な彫刻が施されたすばらしい社殿です。


【写真 上(左)】 菅沼館泉源
【写真 下(右)】 菅沼館泉源の内部
この「湯大権現宮」のすぐ脇にある井戸が、おそらく菅沼館の泉源と思われます。
内部は暗くよく見えませんが、フラッシュ撮影すると壁面は白い硫黄の湯花に覆われ、ほぼ透明の源泉がたまり、そこにホースが挿し込まれていることがわかります。
見た目からするとかなり強めのイオウ臭(甘たまご臭)が香り立ちそうですが、不思議なことにイオウ臭はさほど感じませんでした。


【写真 上(左)】 最大の泉源
【写真 下(右)】 最大の泉源の内部
「菅沼館泉源」のひとつ上の井戸はもっとも大規模で横穴式。
こちらの内部は見やすく、やや白濁気味で金属のパイプが延びていました。
こちらでは「菅沼館泉源」より明瞭なイオウ臭を感じました。


【写真 上(左)】 ナメ状の沢
【写真 下(右)】 泉源井戸がいくつも見えます
ここから奥の沢沿いにもいくつかの井戸が見えます。
そこまでは河床いっぱいの流れなのでナメ状の河床を徒渉しないとたどり着けませんが、せっかくの機会なので突入してみました。(滑りやすいのでおすすめしません。)


【写真 上(左)】 上部の泉源-1
【写真 下(右)】 上部の泉源-2


【写真 上(左)】 上部の泉源-3
【写真 下(右)】 上部の泉源の内部
上部の泉源井戸にもパイプが挿入されています。
位置関係からして、いずれの井戸も河床より低いレベルまで掘り下げ、石積みできっちり組み上げられています。
探索時にモーター音はしませんでしたが形状からすると自然流下はむずかしそうなので、間欠的なポンプ送湯はあるかと。
メモには「徒渉先に泉源5or4+タンク」とあるので、徒渉前の2つと併せると計7の泉源ないし、6の泉源+貯湯槽(タンク)があることになります。
江戸時代の湯宿の軒数は6軒と伝わるので、湯宿毎に自家井戸をもっていたのでは。
また、メモには「パイプ出ているのと出ていないのあり、一番おくがかやの家、手前が柳屋」とあるので、写真には残っていませんが所有を示す何かがあったのかも。
パイプを合流しているものもあるので、複数の泉源を併せて使っている宿もあるかもしれません。
また、もったいなくも漏れているパイプもありました。
*************
さて、いよいよ入湯です。
浴場は1階に1箇所。広くはないのでおそらく時間を譲りあっての入浴となります。
浴場に近づくにつれイオウ臭が強まり、期待が高まります。


【写真 上(左)】 浴場入口
【写真 下(右)】 浴場のサイン
脱衣所は木棚にプラかご。狭く簡素ながら使い勝手のいい脱衣所です。

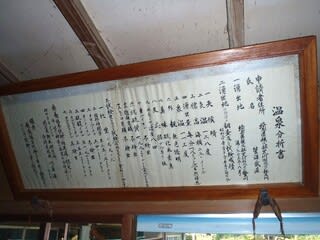
【写真 上(左)】 脱衣所
【写真 下(右)】 温泉分析書


【写真 上(左)】 浴室
【写真 下(右)】 浴槽から脱衣所
浴室は崖下に位置し、昼間でも薄暗いですがそれだけに落ち着いた空間になっています。
天高はさほどないものの、浴槽よこに開け放ちの窓があるのでこもりは感じられません。
黒い石の内床と白&ピンクのタイル壁が不思議なコントラストを見せています。


【写真 上(左)】 浴槽-1
【写真 下(右)】 浴槽-2
浴槽は扇型で、伊豆石or三波石の枠に青いタイル貼浴槽が嵌め込まれています。
2人も入ればいっぱいでしょうか。


【写真 上(左)】 湯溜め槽
【写真 下(右)】 湯溜め槽の湯口
浴槽手前に鉄平石造の湯溜め槽があり、壁から突き出た塩ビパイプから冷たい源泉が数L/minほど(変動あり)常時投入され、槽内の源泉には白い湯の花を浮かべていました。
この湯溜め槽から浴槽への直接投入はなく、上部スリットから排湯されてそれを青いバケツで受けています。
バケツは3つあり、順に満杯にしていきます。
湯溜め槽はかなり深く、相当量の源泉を溜めることができます。


【写真 上(左)】 バケツに溜められる源泉
【写真 下(右)】 バケツからの源泉投入
泉温は低く、湯溜め槽から浴槽にそのまま落とし込むと浴槽の湯温が下がってしまうので、バケツに溜め、必要に応じてバケツの源泉を浴槽に注ぎ込む方式になっているのだと思います。
槽内壁面からの熱湯注入はあるものの槽内吸湯口は見当たらず。
湯溜め槽のなかに吸湯口があるか、別系統で源泉を引きそれをボイラー加温して浴内注入しているのかもしれません。
じっさい、ボイラーとみられる施設に外から引かれたパイプ(源泉ライン?)が接続されていました。


【写真 上(左)】 ボイラーよこの源泉ライン?
【写真 下(右)】 硫化したカラン
なので、湯づかいは源泉加温かけ流しということになります。
泉温11.3℃、湧出量1.8L/minのスペックでは、このようにするしか方法はないのかもしれません。
真っ黒に硫化したカラン×4。石鹸はおいてありました。
保温用の樹脂パネルの蓋3枚を外していよいよ入ります。
お湯はかなりぬるめ。これは温泉好きがつづけて入っていたので、冷たい源泉をバケツでばりばり投入し、オーバーフローさせていたためと思います。(湯溜め槽がかなり減っていた(笑))


【写真 上(左)】 湯色
【写真 下(右)】 オーバーフロー時の湯色
浴槽のお湯はうすく黄緑がかって、うす茶の浮遊物を浮かべています。
浴槽のお湯は秩父らしい甘いたまご系のイオウ臭がメインですが、湯溜め槽の湯口では明瞭なしぶ焦げイオウ臭が香ります。
秩父の硫黄泉はほとんど甘たまご系イオウ臭なので、このしぶ焦げイオウ臭はめずらしいもの。
しぶ焦げイオウ臭なので、浴後肌にイオウ臭が残りそうな感じもしますが、水硫イオン(HS^-)系の硫黄泉のためかほとんど残りませんでした。
それでも浴中はイオウ臭のバリエーションが楽しめるので、イオウ臭中毒者(笑)にはたまらんお湯かと。
湯溜め槽の湯口は重曹味+たまご味+微苦味で、典型的な重曹硫黄泉のそれ。
かなりつよいツルすべと、肌にまとわりつくようなとろみ、そしてイオウ泉特有のスルスルとした湯ざわりは秩父のお湯でもイオウ分強めの「新木鉱泉」の源泉槽を軽く凌駕しています。
あたたまりはさほど強くないですが、入るほどにあとを曳くような絶妙な浴感があり強く記憶に残ります。
なるほどこれは文句なく秩父一の名湯かと。
基本の湯づかいはさすがに安定していて、夕・朝ともに湯質の大きな変化はありませんでした。
*************
最後に宿主さんにお伺いしたメモが残っているので、記録のためにアップしておきます。
・信じられないでしょうが昔は本当に賑わっていて、1間6畳に9人までも泊めた。
・繁忙期は部屋数が足りず、布団部屋にもお客を泊めた。
・泊まり客は近在のお百姓さんたちがメインだったが、遠来の客もおり、そのようなお客は予約なしでも泊めた。
・繁忙期はさながらお祭りのようで、庭で旅芸人の興業が催されることも。
(たしかに宿の前庭は興業も開けそうな広がりがありました。)
・宿泊客たちは湯治を終えると、秩父音頭を謡いながら帰っていった。
・300年の歴史を閉じるのは残念だが、これもいたしかたないこと。
などなど・・・。
■ 秩父音頭(小沢千月)
時代の変遷とともに客層が先細り、閉館を余儀なくされたということでしょうか。
それにしても噂に違わぬ良泉。
閉館目前のこの宿泊は、温泉好きとして会心の一湯となりました。
〔 源泉名:不明 湧出地:荒川村大字贄川湯ノ入2の35の8号 〕 <S30.3.9分析>
単純硫黄冷鉱泉(Na-HCO3型) 11.3℃、pH=8.4、1.8L/min自然湧出、固形物総量=335.05/kg
Na^+=不明、Ca^2+=3.55、Cl^-=3.40、SO_4^2-=51.91、HCO_3^-=不明
総硫黄=7.99mg/kg
療養適不試験の結果適と認定する 但し以上の検査は温泉小分析法による
主要成分が一部不明なので全体の成分バランスがわかりませんが、総硫黄=7.99mg/kgなので堂々たる「硫黄泉」であることがわかります。
(「温泉法」規定では総硫黄=1mg/kg以上で温泉、「鉱泉分析法指針」では総硫黄=2mg/kg以上で「硫黄泉」です。)
くわしくは→こちら(温泉分析書の見方 (うつぼ流・初級編))
〔 2022/10/13UP (2010/09入湯) 〕
【 BGM 】
■ 月ひとつ - See-Saw
■ This Love - Angela Aki
秩父屈指の名湯といわれた柴原鉱泉「菅沼館」は、2010年10月に閉館しています。
筆者は温泉仲間とともに閉館1ヶ月前の2010年9月に宿泊していますが、ネタが多すぎるためついつい放置プレーとなり(笑)、気がついたら12年が経過してしまいました。
一念発起して、記録の意味でレポをUPします。
 柴原温泉 「菅沼館」
柴原温泉 「菅沼館」住 所 :埼玉県秩父市荒川贄川2050
電 話 :日帰り入浴不可/2010年10月閉館
時 間 :同上
料 金 :同上
秩父には、江戸時代から「秩父七湯」と呼ばれるいで湯がありました。
1.新木の湯 (新木鉱泉)
2.鳩の湯 (鳩の湯温泉、温泉施設は閉館)
3.柴原の湯 (柴原温泉)
4.千鹿谷の湯(千鹿谷温泉、温泉施設は閉館)
5.鹿の湯 (白久温泉、温泉施設は閉館)
6.梁場の湯 (現存せず)
7.大指の湯 (現存せず)
うち、5.6.7は早くに廃湯となり、2.4は近年閉館して温泉施設の営業はありません。
「菅沼館」は3.柴原の湯 (柴原温泉)の湯治宿でしたが、2010年10月に閉館しています。
柴原の湯 (柴原温泉)は旧小野原村と旧贄川村の境にあって、『新編武蔵風土記稿』の小野原村の項には「温泉 小名芝原ニアリ 村の北方ニシテ贄川村界の谷間ニテ 両岸ニ湯潭一ヶ所ツゝアリ 共ニ大サ五尺ニ二尺五六寸ハカリ 石モテ積立シ潭ナリ 其由来ヲ尋ヌルニ イツノ頃ヨリ湧出ルコトニヤ知モノナシ 慶安五年(1652年)村ノ水帳ニモ此邊ヲ湯本ト記セシヨシ 其古キ●ヲシテ知ヘシナレト 諸方ヘ聞ヘテ賑ヒシハ近世ノ事ナリト云 今ニ年々三四六七ノ四ヶ月ハ分テ賑ヒ群集スト云リ 此湯ノ効験ハ打身疝気或ハ虚分●気其外 諸病ニ益シト云 瘡毒癩瘡ノ如キニ至リテハ 甚タコレヲ禁ストナリ 両村ノ地ニ跨リ民家六戸アリ イツレモ病客ノ往来スルヲ以テ業トセリ」とあります。
谷間に湯つぼがあり、慶安五年(1652年)の村の資料にも記載され、近世には大いに賑わい湯治宿が6軒あったことなどが記されています。
『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)の(小野原鎮座)稲荷神社の項には「柴原は古くから鉱泉で有名であり、その湯本には昭和36年に焼失した本社(稲荷神社)の社殿建築と同じ宮大工が造ったという、見事な彫刻が施された湯権現社が祀られている。なお、同社の建築年代は江戸中期と思われる。」とあり、すでに江戸中期には湯本守護神としての湯権現社が祀られていたことがわかります。

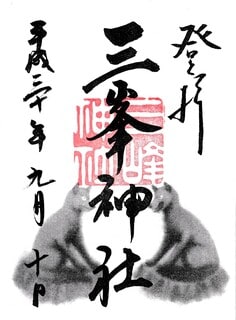
【写真 上(左)】 三峯神社
【写真 下(右)】 三峯神社の御朱印
Web上には出所不明ながら「柴原温泉は三峯神社の登拝口として賑わった」という記事がいくつかみつかります。
気になったので少し調べてみました。
『荒川村贄川における集落機能と生業形態の変化』(河野敬一氏・平野哲也氏/1991年)には「(贄川は)甲州、信州への交通路、三峰山への参詣路、荒川渡船など、交通の要衝に存在」、「昭和5年(1930年)には対岸の白久に秩父鉄道の三峰口駅が開設された。(中略)秩父参詣者は秩父鉄道を利用し、三峰口駅から白川橋を渡り贄川宿を通らずに参詣できるようになった。」とあります。
また、「三峰山は修験の山で、江戸時代中期以降、農業や火伏せ盗賊除けの神として庶民の間で信仰が盛んになり参詣客が増加した。(中略)参詣を終えるとすぐに下山し、贄川の宿屋を利用するものも多かった。明治期の贄川には『角屋』『角六』『丸太』『逸忠館』『小櫃屋』『油屋』という6軒の旅館が存在した。」
「近世期以来、(贄川の)町分の東の入口には三峰神社の一の鳥居が存在し、三峰神域の入口とされていた。贄川から三峰神社までの約10㎞は、険しい山越えのルートだったため、参詣の前夜に贄川で一泊し、翌朝早く発って三峰神社へ参拝し、夕方再び贄川へ戻り、さらに一泊して帰郷するという行程が一般的であった。」という記載もあり、昭和5年の秩父鉄道開通以前、三峯神社参詣者は贄川経由の登拝がメインであったことを示唆しています。
『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)の(贄川鎮座)八幡大神社の項に「贄川の宿は、三峰山への登拝路における最後の宿場としても大きい役割を担ってきた。当時、登拝日の決まっていた(三峰)講社に対して、神社からの使者がこの贄川の宿まで講社の人々を出迎え、道中の労をねぎらった。帰路に当たっても、使者が講社の人々を贄川まで送り、別れの盃を交わし、道中の無事を祈るとともに、翌年の参拝が約束された。こうした贄川の宿を中心とした三峰神社と講社との結びつきが、三峰講を支える大きな柱の一つとなっていた」とあります。
また、同書の(白久鎮座)熊野神社の項に「三峰詣の登拝順路にあたる当地は、三峰山の信仰と関連するところが多い。なお、この登拝路は、紀州熊野詣の形に類似しているともいわれ、彼地九十九王子に、猪鼻王子が現在でも残っている。」とあります。
いまの地理感から考えると三峰神社からかなり離れた麓の贄川に、登拝口や一の鳥居があったのは不思議な感じもしますが、『江戸における三峰信仰の展開とその社会的背景』(三木一彦氏/2001年)によると、江戸小日向(現・文京区)からの三峰詣ではじつに9泊10日の行程を要していたそうですから、贄川(柴原)~三峰間の10㎞強程度は「すぐ下の麓」という感覚だったのでしょう。
また、三峰山麓には熊野信仰の影響を受けて九十九王子が奉安されていたようで、神域内に(九十九王子を奉安するための)ある程度の距離が必要だったのでは。
贄川と柴原は、道筋こそことなるものの距離的にはさほど離れていません。
上記のとおり三峰講と贄川の宿の結びつきが強かったとすれば、表立って柴原の湯宿に泊まることは憚られたのかもしれませんが、帰途であれば精進落としの意味もあって、温泉で疲れを癒すニーズもあったであろうことは容易に想像できます。
実際『(埼玉県)宮代町史』には、三峰講による三峰神社への代参は毎年4月、川崎市資料にも「多摩区生田の土淵では、4月に代参者2名を(三峰講として)秩父の三峰神社に送った。」とあり、『新編武蔵風土記稿』の「(柴原温泉は)年々三四六七ノ四ヶ月ハ分テ賑ヒ群集ス」という記事と符合しています。
ただし、柴原の湯の本分は湯治であったこと、また、三峰講と贄川宿の強固な関係からして、柴原の湯で参詣客の利用があっても大っぴらにできなかったため、三峰講絡みの記録が少ないのかもしれません。
三峰講は関東平野を中心に多くの代参講が組織されており、(参考:関東平野における三峰信仰の展開(三木一彦氏/2005年))そのほとんどは徒歩による参詣だったので、三峰山麓の宿泊需要は旺盛だったと思われます。
田植え期間をのぞく春~初夏の三峯参詣繁忙期には、贄川の6軒の宿では足りず柴原の湯の宿に送客したこともあったのでは?
ただし、三峰講の旅程はおそらく地元の講元で管理されており、贄川が満杯で柴原の湯に泊まったとしても記録としては贄川泊になったと思われます。
こうした点からも三峰講と柴原の湯のつながりが残りにくかったのかもしれません。
秩父札所三十四ヶ所観音霊場との関係も考えられます。
秩父札所三十四ヶ所観音霊場は文暦元年(1234年)開創と伝わる古い霊場で、長享二年(1488年)の秩父札所番付が実在することから、室町時代後期には定着していたとされます。
西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所とともに日本百番観音に数えられるメジャー霊場で、江戸時代に入るといよいよ盛んに巡拝されました。


【写真 上(左)】 第30番 法雲寺
【写真 下(右)】 第30番 法雲寺の御朱印

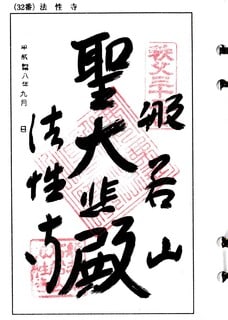
【写真 上(左)】 第32番 法性寺
【写真 下(右)】 第32番 法性寺の御朱印
柴原は第30番瑞龍山 法雲寺と第32番般若山 法性寺を結ぶ道筋にあり、秩父札所の巡拝者が泊まりに利用した可能性があります。
(直接関係ないですが、秩父札所に曹洞宗寺院が多い理由を考察した興味ぶかい論文がみつかりましたのでご紹介します。→こちら(『武蔵国秩父札所三十四観音霊場の形成にみる中世後期禅宗の地方展開』(小野澤眞氏/2012年))
以上からすると、柴原の湯 (柴原温泉)は江戸時代から、湯治客、三峰講、秩父札所という集客3チャネルを持っていた可能性があり、これが山あいの湯場ながら6軒の湯宿を支えた背景なのかもしれません。
大正14年刊の『埼玉県秩父郡誌』にも柴原鉱泉は以下のとおり記載されています。
「柴原鉱泉は其の発見江戸時代初期にあり。現今浴客を収容するの設備漸く完全ならんとす。」
明治維新後も大正くらいまではかなりの浴客を迎えていたことがわかります。
*************
前置きが長くなりました。


【写真 上(左)】 柴原温泉
【写真 下(右)】 右手おくが「菅沼館」
柴原温泉には、2010年時点で「かやの家」(旧称:白百合莊)「柳屋」「菅沼館」の3軒の湯宿がありました。(「きくや」もまだ営業中だったかもしれませんが詳細不明。)
かつての6軒の湯宿は3軒になっているものの、「かやの家」は”日本秘湯を守る会会員宿”、「柳屋」は名物の手打ち蕎麦と日帰り入浴、「菅沼館」は湯治宿とうまく棲み分けしていました。
わけても「菅沼館」のお湯はコアな温泉マニアのあいだで定評があり、日帰り入浴不可ということもあってナゾ多きお湯となっていました。
(じつは、筆者はダメもとで突入し日帰り入浴を乞うたことがあるのですが、「ここは湯治宿なので・・・」とやんわりお断りされた過去があります。)
この温泉マニア垂涎の「菅沼館」が廃業するという情報が出たのはたしか2010年春頃。
これを受けて温泉仲間が廃業直前に貸し切りのオフ会を設定してくださり、これに参戦するかたちでついに初入湯を果たしました。
湯治宿ですが、1泊2食付での宿泊としました。


【写真 上(左)】 庭内エントランス
【写真 下(右)】 庭先のサイン


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 帳場棟
「かやの家」「柳屋」は湯宿としてわかりやすい外観ですが、沢にかかる小橋を渡った最奥の「菅沼館」は湯治宿だけあって民家的な構え。
「柳屋」の裏手的な立地でややわかりにくいですが、庭先に「菅沼館」の看板が出ているので迷うことはありません。


【写真 上(左)】 玄関扁額
【写真 下(右)】 客室棟から帳場棟


【写真 上(左)】 客室棟-1
【写真 下(右)】 客室棟-2
正面が切妻屋根一層の帳場棟。そこから手前に向かってL字型に2層の客室棟が伸びています。築300年の歴史をもつようです。
玄関にはきっちりと宿名扁額を掲げて好ましげなたたずまい。
1階の帳場まわりもいい意味で年季が入って風格さえ帯びています。


【写真 上(左)】 帳場まわり-1
【写真 下(右)】 帳場まわり-2


【写真 上(左)】 1階
【写真 下(右)】 1階廊下
泊まったのは2階。湯治宿らしい開放感あふれる外廊下。
山あいの9月の涼やかな風が、網戸ごしに心地よく吹き込んできます。
窓からは手前に「柳屋」、すこし離れて「かやの家」が望めます。


【写真 上(左)】 階段
【写真 下(右)】 2階廊下


【写真 上(左)】 2階客室-1
【写真 下(右)】 2階客室-2
部屋数はすみませぬ覚えていません。
貸し切りだったので、ふすま開け放しで広々とつかいました。


【写真 上(左)】 館内の扁額
【写真 下(右)】 湯治宿の趣
湯治宿ですが部屋のつくりはよく、床の間に掛け軸も。
すみずみまで清掃が行き届いてきもちがいいです。


【写真 上(左)】 格言の扁額
【写真 下(右)】 句碑


【写真 上(左)】 スリッパ
【写真 下(右)】 室番
館内各所に格言や句、趣味のいい風景画などが掲げられ、ご主人は相当な風流人では?
スリッパの文字は館名ではなく「ゆもと」。湯元宿としての矜持が感じられます。
写真の撮影時間からすると、入浴は早朝から20時まで。
夕食は18時、朝食は7時半からだったと思います。
入浴20時まで、朝食7時半からは、さすがに保守本流の正統派湯治宿。なんちゃって系ではありません(笑)


【写真 上(左)】 夕食
【写真 下(右)】 朝食
食事は家庭料理的メニューでしたが、素材と味つけがよく、予想以上に満足いくものでした。
浴室は広くなく宿泊人数がそれなりにいたので忙しい入浴となりましたが、それでも夕・朝ともにこの名湯を満喫できました。
*************
入湯レポの前に、すこしく柴原温泉の泉源について触れてみます。
柴原温泉の泉源地は、沢沿いに建つ「柳屋」の玄関向かって左手のパイプが引かれた小径を沢沿いに遡ったところにあります。


【写真 上(左)】 柳屋
【写真 下(右)】 柳屋の脇の道です


【写真 上(左)】 淵
【写真 下(右)】 湯大権現宮入口
9月の頃合いでは草木が生い茂り、よほどの好き者でない限り探る気にはならないかと。
「柳屋」脇の小径をしばらく登ると「湯大権現宮入口」の標柱と祠?があらわれます。
このあたりの沢は淵となっていて小滝が流れ込んでいます。


【写真 上(左)】 登ります
【写真 下(右)】 乗っ越した先の沢と林相
ここから急な登りとなりますが、道沿いにパイプが数本引かれているので泉源に向かっていることがわかります。
小さな高みをひとつ乗っ越すと、再び沢沿いとなりここにも数本のパイプが見えます。
ここまで基本は沢沿いの道で徒渉はないですが、ところどころ苔で滑りやすいので要注意。
あたりはうっそうと木々が茂り、沢音だけが響きます。


【写真 上(左)】 湯大権現宮が見えてきます
【写真 下(右)】 湯大権現宮
ひとしきり沢を遡上すると切妻造妻入木造一部ブロック造トタン覆の建物が見えてきます。
こちらが「湯大権現宮」の覆屋です。
よこに説明板がありましたので転記します。
---------------------
荒川村指定有形文化財 湯大権現宮 平成二年四月九日指定
この社は江戸時代の嘉永年間(1848-1854年)に磐若村(現在の小鹿野町磐若)の神田雄七郎という大工棟梁によって建立されたもので、彫刻なども見事であるが一部欠けたりしており、聞く所によると盗難にあったといわれている。
社のわきに掘られている井戸は、柴原温泉に使われる湯がわき出している。
この湯は、弱アルカリ性硫化水素がふくまれており、ゆで玉子に似たにおいがする。
この井戸がいつ頃掘られたかは、湯元・菅沼館に口伝されている所によると、鎌倉時代とも藤原時代ともいわれているという。
以前、菅沼館では湯治客が自炊をしていたので、その火のために何度か火災に会い(ママ)、文書は焼失し口伝だけが残っているのだという。
この社には大己貴神(大国主命)と少彦名命の二神が祭られている。
荒川村教育委員会
---------------------


【写真 上(左)】 湯大権現宮社殿
【写真 下(右)】 湯大権現宮と手前が菅沼館泉源
「湯大権現宮」の覆屋には「●有者菅沼館」の木板が掲げられていました。
覆屋内には神田雄七郎作と伝わる社殿が安置され、市指定有形文化財に指定されています。
市の公式Webには「社の脇にある井戸からは、鉱泉が湧き出ており、温泉郷の湯元となっている。現在の社は、嘉永・安政年間(1848~1860)、般若村(現小鹿野町)の棟梁神田雄七郎の手によるもので、規模は小さいが、重厚で格調の高い風格を備えている。」とあります。
小ぶりながら千鳥破風、軒唐破風を備え、水引虹梁まわりに精緻な彫刻が施されたすばらしい社殿です。


【写真 上(左)】 菅沼館泉源
【写真 下(右)】 菅沼館泉源の内部
この「湯大権現宮」のすぐ脇にある井戸が、おそらく菅沼館の泉源と思われます。
内部は暗くよく見えませんが、フラッシュ撮影すると壁面は白い硫黄の湯花に覆われ、ほぼ透明の源泉がたまり、そこにホースが挿し込まれていることがわかります。
見た目からするとかなり強めのイオウ臭(甘たまご臭)が香り立ちそうですが、不思議なことにイオウ臭はさほど感じませんでした。


【写真 上(左)】 最大の泉源
【写真 下(右)】 最大の泉源の内部
「菅沼館泉源」のひとつ上の井戸はもっとも大規模で横穴式。
こちらの内部は見やすく、やや白濁気味で金属のパイプが延びていました。
こちらでは「菅沼館泉源」より明瞭なイオウ臭を感じました。


【写真 上(左)】 ナメ状の沢
【写真 下(右)】 泉源井戸がいくつも見えます
ここから奥の沢沿いにもいくつかの井戸が見えます。
そこまでは河床いっぱいの流れなのでナメ状の河床を徒渉しないとたどり着けませんが、せっかくの機会なので突入してみました。(滑りやすいのでおすすめしません。)


【写真 上(左)】 上部の泉源-1
【写真 下(右)】 上部の泉源-2


【写真 上(左)】 上部の泉源-3
【写真 下(右)】 上部の泉源の内部
上部の泉源井戸にもパイプが挿入されています。
位置関係からして、いずれの井戸も河床より低いレベルまで掘り下げ、石積みできっちり組み上げられています。
探索時にモーター音はしませんでしたが形状からすると自然流下はむずかしそうなので、間欠的なポンプ送湯はあるかと。
メモには「徒渉先に泉源5or4+タンク」とあるので、徒渉前の2つと併せると計7の泉源ないし、6の泉源+貯湯槽(タンク)があることになります。
江戸時代の湯宿の軒数は6軒と伝わるので、湯宿毎に自家井戸をもっていたのでは。
また、メモには「パイプ出ているのと出ていないのあり、一番おくがかやの家、手前が柳屋」とあるので、写真には残っていませんが所有を示す何かがあったのかも。
パイプを合流しているものもあるので、複数の泉源を併せて使っている宿もあるかもしれません。
また、もったいなくも漏れているパイプもありました。
*************
さて、いよいよ入湯です。
浴場は1階に1箇所。広くはないのでおそらく時間を譲りあっての入浴となります。
浴場に近づくにつれイオウ臭が強まり、期待が高まります。


【写真 上(左)】 浴場入口
【写真 下(右)】 浴場のサイン
脱衣所は木棚にプラかご。狭く簡素ながら使い勝手のいい脱衣所です。

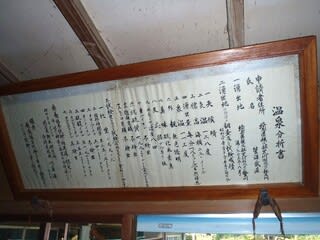
【写真 上(左)】 脱衣所
【写真 下(右)】 温泉分析書


【写真 上(左)】 浴室
【写真 下(右)】 浴槽から脱衣所
浴室は崖下に位置し、昼間でも薄暗いですがそれだけに落ち着いた空間になっています。
天高はさほどないものの、浴槽よこに開け放ちの窓があるのでこもりは感じられません。
黒い石の内床と白&ピンクのタイル壁が不思議なコントラストを見せています。


【写真 上(左)】 浴槽-1
【写真 下(右)】 浴槽-2
浴槽は扇型で、伊豆石or三波石の枠に青いタイル貼浴槽が嵌め込まれています。
2人も入ればいっぱいでしょうか。


【写真 上(左)】 湯溜め槽
【写真 下(右)】 湯溜め槽の湯口
浴槽手前に鉄平石造の湯溜め槽があり、壁から突き出た塩ビパイプから冷たい源泉が数L/minほど(変動あり)常時投入され、槽内の源泉には白い湯の花を浮かべていました。
この湯溜め槽から浴槽への直接投入はなく、上部スリットから排湯されてそれを青いバケツで受けています。
バケツは3つあり、順に満杯にしていきます。
湯溜め槽はかなり深く、相当量の源泉を溜めることができます。


【写真 上(左)】 バケツに溜められる源泉
【写真 下(右)】 バケツからの源泉投入
泉温は低く、湯溜め槽から浴槽にそのまま落とし込むと浴槽の湯温が下がってしまうので、バケツに溜め、必要に応じてバケツの源泉を浴槽に注ぎ込む方式になっているのだと思います。
槽内壁面からの熱湯注入はあるものの槽内吸湯口は見当たらず。
湯溜め槽のなかに吸湯口があるか、別系統で源泉を引きそれをボイラー加温して浴内注入しているのかもしれません。
じっさい、ボイラーとみられる施設に外から引かれたパイプ(源泉ライン?)が接続されていました。


【写真 上(左)】 ボイラーよこの源泉ライン?
【写真 下(右)】 硫化したカラン
なので、湯づかいは源泉加温かけ流しということになります。
泉温11.3℃、湧出量1.8L/minのスペックでは、このようにするしか方法はないのかもしれません。
真っ黒に硫化したカラン×4。石鹸はおいてありました。
保温用の樹脂パネルの蓋3枚を外していよいよ入ります。
お湯はかなりぬるめ。これは温泉好きがつづけて入っていたので、冷たい源泉をバケツでばりばり投入し、オーバーフローさせていたためと思います。(湯溜め槽がかなり減っていた(笑))


【写真 上(左)】 湯色
【写真 下(右)】 オーバーフロー時の湯色
浴槽のお湯はうすく黄緑がかって、うす茶の浮遊物を浮かべています。
浴槽のお湯は秩父らしい甘いたまご系のイオウ臭がメインですが、湯溜め槽の湯口では明瞭なしぶ焦げイオウ臭が香ります。
秩父の硫黄泉はほとんど甘たまご系イオウ臭なので、このしぶ焦げイオウ臭はめずらしいもの。
しぶ焦げイオウ臭なので、浴後肌にイオウ臭が残りそうな感じもしますが、水硫イオン(HS^-)系の硫黄泉のためかほとんど残りませんでした。
それでも浴中はイオウ臭のバリエーションが楽しめるので、イオウ臭中毒者(笑)にはたまらんお湯かと。
湯溜め槽の湯口は重曹味+たまご味+微苦味で、典型的な重曹硫黄泉のそれ。
かなりつよいツルすべと、肌にまとわりつくようなとろみ、そしてイオウ泉特有のスルスルとした湯ざわりは秩父のお湯でもイオウ分強めの「新木鉱泉」の源泉槽を軽く凌駕しています。
あたたまりはさほど強くないですが、入るほどにあとを曳くような絶妙な浴感があり強く記憶に残ります。
なるほどこれは文句なく秩父一の名湯かと。
基本の湯づかいはさすがに安定していて、夕・朝ともに湯質の大きな変化はありませんでした。
*************
最後に宿主さんにお伺いしたメモが残っているので、記録のためにアップしておきます。
・信じられないでしょうが昔は本当に賑わっていて、1間6畳に9人までも泊めた。
・繁忙期は部屋数が足りず、布団部屋にもお客を泊めた。
・泊まり客は近在のお百姓さんたちがメインだったが、遠来の客もおり、そのようなお客は予約なしでも泊めた。
・繁忙期はさながらお祭りのようで、庭で旅芸人の興業が催されることも。
(たしかに宿の前庭は興業も開けそうな広がりがありました。)
・宿泊客たちは湯治を終えると、秩父音頭を謡いながら帰っていった。
・300年の歴史を閉じるのは残念だが、これもいたしかたないこと。
などなど・・・。
■ 秩父音頭(小沢千月)
時代の変遷とともに客層が先細り、閉館を余儀なくされたということでしょうか。
それにしても噂に違わぬ良泉。
閉館目前のこの宿泊は、温泉好きとして会心の一湯となりました。
〔 源泉名:不明 湧出地:荒川村大字贄川湯ノ入2の35の8号 〕 <S30.3.9分析>
単純硫黄冷鉱泉(Na-HCO3型) 11.3℃、pH=8.4、1.8L/min自然湧出、固形物総量=335.05/kg
Na^+=不明、Ca^2+=3.55、Cl^-=3.40、SO_4^2-=51.91、HCO_3^-=不明
総硫黄=7.99mg/kg
療養適不試験の結果適と認定する 但し以上の検査は温泉小分析法による
主要成分が一部不明なので全体の成分バランスがわかりませんが、総硫黄=7.99mg/kgなので堂々たる「硫黄泉」であることがわかります。
(「温泉法」規定では総硫黄=1mg/kg以上で温泉、「鉱泉分析法指針」では総硫黄=2mg/kg以上で「硫黄泉」です。)
くわしくは→こちら(温泉分析書の見方 (うつぼ流・初級編))
〔 2022/10/13UP (2010/09入湯) 〕
【 BGM 】
■ 月ひとつ - See-Saw
■ This Love - Angela Aki
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伝説的ミュージシャンの50年 〜ユーミンの名曲〜
昨日(2022/10/06)放映のSONGSのユーミン特集、視てみました。
「パーソナルなところを掘り進んでいくと、あるところから急に一般性(普遍性)を帯びる」
↑ これがユーミンの歌詞の魅力の本質かもしれぬ。
一般性(普遍性)を帯びた歌詞は、時代を超えて残るから。
■ 卒業写真 - 荒井由実(松任谷由実)(cover)
---------------------------
2022/09/26 UP
先ほどの『関ジャム』のユーミン特集、視応えあった。
ユーミンへの質問って、質問者の才能や見識が透けて見えてしまうから、ある意味こわいと思う。
「カウンターメロディから曲をつくることもある」
↑ なるほど、ユーミンの名曲ってたいていカウンターメロが強力だし・・・。
納得すること多々あり。
■ 松任谷由実 - ガールフレンズ (from「日本の恋と、ユーミンと。」)
Vaundy氏が ↑ この曲のベースラインの凄さを指摘していたけど、なるほどさすがの見識じゃわ。
このベース、カウンターメロディでは?
(『VOYAGER』(1983年)収録。)
前回、
「せっかくなので、ユーミンの名曲をいくつかリストしてみます。(カバーVers.もあり)」として下記の曲をUPしていますが、やっぱりこのあたりが個人的にはユーミン屈指の名曲だと思うので、改めて上にあげてみました。
■ ベルベット・イースター
『ひこうき雲』(1973年)収録の隠れた名曲!
信じられないクリシェ。そしてメジャーセブンス。
1973年の時点でこの曲調って、いまからみると時代の先を行きすぎた感あり。
■ 瞳を閉じて
『MISSLIM』(1974年)収録。
なんということもない曲にも聴こえるが、初期のユーミンならではの透明な空気感が感じられる。
■ 翳りゆく部屋
1976年、荒井由実名義最後のシングルカット曲で、B面はなんと「ベルベット・イースター」。
イントロのインパクトが、アウトロまで緩むことなく継続する神曲。
数十年のキャリアがあっても、何曲も生みだせる曲ではないと思う。
■ 守ってあげたい
『昨晩お会いしましょう』(1981年)収録のヒットシングル。
1991.07以前、日本経済がまだ元気だった頃の時代の空気を感じる貴重なLIVE。
■ ずっとそばに
『REINCARNATION』(1983年)収録のミディアム曲。
ミディアムながらリズムセクションがキレっキレで、リリース当時から文句なく名曲だと思ってた。
■ ロッヂで待つクリスマス
『流線形'80』(1978年)収録のウィンター・バラード。
個人的には、曲のできは「恋人がサンタクロース」よりぜんぜん上だと思う。
■ 静かなまぼろし
『流線形'80』(1978年)収録。
沢田研二も歌ってるけど、この珠玉の歌詞はやっぱり女性が歌って活きる。
■ ノーサイド
『NO SIDE』(1984年)収録。
ユーミンの魅力のひとつ「母性」を感じる名曲。
■ Hello,my friend
『THE DANCING SUN』(1994年)収録。
ゲストさんの誰やらかが、↑ この曲を簡単なメロ、簡単なコードとコメントしてたけど、そうなのかな???
それを言うなら ↓ この曲では?
■ ANNIVERSARY 〜無限にCALLING YOU〜
『LOVE WARS』(1989年)収録。
いまから想うと、これから始まる「失われた数十年」を暗示していた曲のひとつかと。
こういうメロディを創り出せる才能が、”天才”。
難しい曲調をポップに聴かせる。
シンプルな曲調に含蓄をもたせて聴かせる。
こういうのが本当の才能だと思う。
難しい曲調をさも難しそうに聴かせるのは、たいした才能とは思えず。
誰とは言わないけど・・・(笑)
---------------------------
2021/09/20 UP
さきほど放送の、NHK MUSIC SPECIAL「伝説的ミュージシャンの50年 〜ユーミン・尾崎亜美そしてSKYEへ〜」、面白かった。
ゲストはユーミンとSKYEの4人、そして尾崎亜美。
スタジオで3曲演奏。これは超貴重。
【SKYE】
鈴木茂(g)
小原礼(b)
林立夫(ds)
松任谷正隆(key)
これはスーパーバンドじゃわ。
それにしても全員?70歳というのに素晴らしいパフォーマンス。
その実力をあらためて実感。
尾崎亜美の「マイピュアレディ」、グルーヴ感がハンパなかった。
とくに、尾崎亜美のフェンダー・ローズと鈴木茂のギターフレーズは涙なくして聴けず・・・
■ 中央フリーウェイ - Arai Yumi
3:04~のスキャット、尾崎亜美だそうです。知らんかった。
「パーソナルなところを掘り進んでいくと、あるところから急に一般性(普遍性)を帯びる」
↑ これがユーミンの歌詞の魅力の本質かもしれぬ。
一般性(普遍性)を帯びた歌詞は、時代を超えて残るから。
■ 卒業写真 - 荒井由実(松任谷由実)(cover)
---------------------------
2022/09/26 UP
先ほどの『関ジャム』のユーミン特集、視応えあった。
ユーミンへの質問って、質問者の才能や見識が透けて見えてしまうから、ある意味こわいと思う。
「カウンターメロディから曲をつくることもある」
↑ なるほど、ユーミンの名曲ってたいていカウンターメロが強力だし・・・。
納得すること多々あり。
■ 松任谷由実 - ガールフレンズ (from「日本の恋と、ユーミンと。」)
Vaundy氏が ↑ この曲のベースラインの凄さを指摘していたけど、なるほどさすがの見識じゃわ。
このベース、カウンターメロディでは?
(『VOYAGER』(1983年)収録。)
前回、
「せっかくなので、ユーミンの名曲をいくつかリストしてみます。(カバーVers.もあり)」として下記の曲をUPしていますが、やっぱりこのあたりが個人的にはユーミン屈指の名曲だと思うので、改めて上にあげてみました。
■ ベルベット・イースター
『ひこうき雲』(1973年)収録の隠れた名曲!
信じられないクリシェ。そしてメジャーセブンス。
1973年の時点でこの曲調って、いまからみると時代の先を行きすぎた感あり。
■ 瞳を閉じて
『MISSLIM』(1974年)収録。
なんということもない曲にも聴こえるが、初期のユーミンならではの透明な空気感が感じられる。
■ 翳りゆく部屋
1976年、荒井由実名義最後のシングルカット曲で、B面はなんと「ベルベット・イースター」。
イントロのインパクトが、アウトロまで緩むことなく継続する神曲。
数十年のキャリアがあっても、何曲も生みだせる曲ではないと思う。
■ 守ってあげたい
『昨晩お会いしましょう』(1981年)収録のヒットシングル。
1991.07以前、日本経済がまだ元気だった頃の時代の空気を感じる貴重なLIVE。
■ ずっとそばに
『REINCARNATION』(1983年)収録のミディアム曲。
ミディアムながらリズムセクションがキレっキレで、リリース当時から文句なく名曲だと思ってた。
■ ロッヂで待つクリスマス
『流線形'80』(1978年)収録のウィンター・バラード。
個人的には、曲のできは「恋人がサンタクロース」よりぜんぜん上だと思う。
■ 静かなまぼろし
『流線形'80』(1978年)収録。
沢田研二も歌ってるけど、この珠玉の歌詞はやっぱり女性が歌って活きる。
■ ノーサイド
『NO SIDE』(1984年)収録。
ユーミンの魅力のひとつ「母性」を感じる名曲。
■ Hello,my friend
『THE DANCING SUN』(1994年)収録。
ゲストさんの誰やらかが、↑ この曲を簡単なメロ、簡単なコードとコメントしてたけど、そうなのかな???
それを言うなら ↓ この曲では?
■ ANNIVERSARY 〜無限にCALLING YOU〜
『LOVE WARS』(1989年)収録。
いまから想うと、これから始まる「失われた数十年」を暗示していた曲のひとつかと。
こういうメロディを創り出せる才能が、”天才”。
難しい曲調をポップに聴かせる。
シンプルな曲調に含蓄をもたせて聴かせる。
こういうのが本当の才能だと思う。
難しい曲調をさも難しそうに聴かせるのは、たいした才能とは思えず。
誰とは言わないけど・・・(笑)
---------------------------
2021/09/20 UP
さきほど放送の、NHK MUSIC SPECIAL「伝説的ミュージシャンの50年 〜ユーミン・尾崎亜美そしてSKYEへ〜」、面白かった。
ゲストはユーミンとSKYEの4人、そして尾崎亜美。
スタジオで3曲演奏。これは超貴重。
【SKYE】
鈴木茂(g)
小原礼(b)
林立夫(ds)
松任谷正隆(key)
これはスーパーバンドじゃわ。
それにしても全員?70歳というのに素晴らしいパフォーマンス。
その実力をあらためて実感。
尾崎亜美の「マイピュアレディ」、グルーヴ感がハンパなかった。
とくに、尾崎亜美のフェンダー・ローズと鈴木茂のギターフレーズは涙なくして聴けず・・・
■ 中央フリーウェイ - Arai Yumi
3:04~のスキャット、尾崎亜美だそうです。知らんかった。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ ハイトーンヴォーカル15曲
5曲追加して15曲にしました。
----------------------
2020/10/05 UP
なんの脈略もなく、10曲集めてみました。
あとでとりまとめてみます。
それにしても、アニソンやゲーム曲って名曲の宝庫だって改めて思う。
■【MV】誇り高きアイドル/mona(CV:夏川椎菜)【HoneyWorks】
■【ライブ盤PV】Cross bouquet(歌:霜月はるか・中恵光城)【しちごさん。×ABSOLUTE CASTAWAY】
■ 大図書館の羊飼い -Dreaming Sheep- ED Nishizawa Hagumi 「サクラメント」
■ TrySail『Lapis』(TVアニメ『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd SEASON –覚醒前夜-』)Music Video
■ 恋泥棒。 / 『ユイカ』【MV】
■ Tainaka Sachi - 最高の片想い (LIVE)
■ ダイアモンド クレバス (Diamond Crevasse) - シェリル・ノーム starring May'n // covered by 凪原涼菜
■ 東山奈央「OVER!!」Music Video(作詞/作曲:東山奈央 編曲:堀江晶太)
■【小春六花】さユり / 花の塔 を歌ってもらった【リコリス・リコイル】【Synthesizer V AI】
■ KOTOKO「Imaginary affair」(LIVE)
■ 川田まみ 風と君を抱いて(kaze to kimiwo daite) LIVE
■ Hero - 安室奈美恵 // covered by 皇 美緒奈
『BanG Dream! バンドリ』つながりのユニットは、どれもかなりの演奏力↓
オリンピックの開会式でバンドリタイムつくったら、たぶん受けたと思う。
■【公式ライブ映像】Morfonica「ブルームブルーム」(RAISE A SUILEN×Morfonica「Mythology Chapter 2」より)【期間限定】
プログレバンドかと思った(笑)
■【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」
大橋彩香の手数の多いドラムス、個人的に好物なんですけど。
■【公式ライブ映像】Roselia「Blessing Chord」(「Rausch und/and Craziness Ⅱ」より)
メンバー全員リードVoとれると思う。
↑ 櫻川(桜川)めぐ ↓ が、ヴォーカルじゃなくてドラムスに回ってる時点でただごとじゃない。
■ どっちのiが好きですか? OP「僕らのWatercolor」歌:桜川 めぐ
■ ✿ 「栞」天野月 feat.YURiCa/花たん
これは名曲。
■【鬼頭明里】「君の花を祈ろう」ライブ映像【1st LIVE TOUR Colorful Closet】
PAがいいのか、声質なのか、ヴォーカルがもの凄く前に出てきてる。
----------------------
2020/10/05 UP
なんの脈略もなく、10曲集めてみました。
あとでとりまとめてみます。
それにしても、アニソンやゲーム曲って名曲の宝庫だって改めて思う。
■【MV】誇り高きアイドル/mona(CV:夏川椎菜)【HoneyWorks】
■【ライブ盤PV】Cross bouquet(歌:霜月はるか・中恵光城)【しちごさん。×ABSOLUTE CASTAWAY】
■ 大図書館の羊飼い -Dreaming Sheep- ED Nishizawa Hagumi 「サクラメント」
■ TrySail『Lapis』(TVアニメ『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd SEASON –覚醒前夜-』)Music Video
■ 恋泥棒。 / 『ユイカ』【MV】
■ Tainaka Sachi - 最高の片想い (LIVE)
■ ダイアモンド クレバス (Diamond Crevasse) - シェリル・ノーム starring May'n // covered by 凪原涼菜
■ 東山奈央「OVER!!」Music Video(作詞/作曲:東山奈央 編曲:堀江晶太)
■【小春六花】さユり / 花の塔 を歌ってもらった【リコリス・リコイル】【Synthesizer V AI】
■ KOTOKO「Imaginary affair」(LIVE)
■ 川田まみ 風と君を抱いて(kaze to kimiwo daite) LIVE
■ Hero - 安室奈美恵 // covered by 皇 美緒奈
『BanG Dream! バンドリ』つながりのユニットは、どれもかなりの演奏力↓
オリンピックの開会式でバンドリタイムつくったら、たぶん受けたと思う。
■【公式ライブ映像】Morfonica「ブルームブルーム」(RAISE A SUILEN×Morfonica「Mythology Chapter 2」より)【期間限定】
プログレバンドかと思った(笑)
■【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」
大橋彩香の手数の多いドラムス、個人的に好物なんですけど。
■【公式ライブ映像】Roselia「Blessing Chord」(「Rausch und/and Craziness Ⅱ」より)
メンバー全員リードVoとれると思う。
↑ 櫻川(桜川)めぐ ↓ が、ヴォーカルじゃなくてドラムスに回ってる時点でただごとじゃない。
■ どっちのiが好きですか? OP「僕らのWatercolor」歌:桜川 めぐ
■ ✿ 「栞」天野月 feat.YURiCa/花たん
これは名曲。
■【鬼頭明里】「君の花を祈ろう」ライブ映像【1st LIVE TOUR Colorful Closet】
PAがいいのか、声質なのか、ヴォーカルがもの凄く前に出てきてる。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)から。
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづく。
26.多福山 一乗院 大寳寺(だいほうじ)
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
大町にある日蓮宗寺院。
新羅三郎義光公や佐竹氏とのゆかりをもち、歴史好きは見逃せないお寺です。
現地掲示、鎌倉市Webなどによると、この一帯は佐竹氏の祖先である新羅三郎源義光公が兄の義家公とともに永保三年(1083年)の後三年の役に出陣し、戦捷ののちに館をかまえ以降佐竹氏の屋敷になったといいます。
應永六年(1399年)佐竹義盛が出家して多福寺を開基建立した後、文安元年(1444年)日蓮宗の高僧一乗院日出上人が再興開山となり、号を改め多福山大寶寺となりました。
源義光公は戦捷は日頃から信仰されていた多福大明神の御加護によるものとし、この地に多福明神社を建てられたと伝わります。
山内掲示には以下のとおりあります。(抜粋)
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
山内の多福明神社(大多福稲荷大明神)はもともと義光公が信仰され、多福寺が一旦廃寺になったときに大町の八雲神社に合祀されて、明應八年(1499年)に松葉ヶ谷妙法寺の日證上人によって八雲神社から大寶寺に再勧請とあります。
ちなみに、義光公の子孫は武家として栄え、嫡男・義業からは佐竹氏(常陸源氏)、義清からは武田、小笠原、南部、三好などの甲斐源氏、盛義からは平賀、大内などの信濃源氏が出ています。
『新編鎌倉志』『鎌倉攬勝考』ともに、大寳寺についての記載はみあたりませんでした。
佐竹氏屋敷跡の記載はありましたので引用します。
『新編鎌倉志』
「佐竹屋敷は、名越道の北、妙本寺の東の山に、五本骨扇の如なる山のウネあり。其下を佐竹秀義が舊宅と云。【東鑑】に、文治五年(1189年)七月廿六日、頼朝、奥州退治の時、宇都宮を立給時、無紋白旗也。二品頼朝是を咎給、仍月を出の御扇を佐竹に賜り、旗の上に付べきの由仰せらる。御旗と等しかるべからずの故也。佐竹、御旨にしたがひ、是を付るとあり。今に佐竹の家これを以て紋とす。此山のウネも、家の紋をかたどり作りたるならん。」
『鎌倉攬勝考』
「佐竹四郎秀義第跡 名越往来の北の方、妙本寺の東の山に五本骨の扇のごとくなる山のウネあり。其下を佐竹冠者秀義が舊跡といふ。此秀義扇の紋を賜ひしは、文治五年(1189年)、右大将家奥州征伐の時なり。山の谷を穿ち、五本骨に造りしは後世の事なり。足利家の代となりても、此所に佐竹氏住居の事にや、公方持氏朝臣、應永廿九年(1422年)十月三日、家督の事に依て、佐竹上総介入道を上杉憲直に討しむ。」
ともに佐竹氏定紋の「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)を奥州討伐の際に頼朝公から給い、これにちなんで屋敷の周辺を「五本骨扇」のかたちに整えたという内容です。
佐竹隆義・秀義は、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げの際に参陣せず、同年秋の富士川の戦いでは平家方につきました。
富士川の敗戦の後、本拠の常陸へ逃れた秀義は頼朝勢に追撃され(金砂城の戦い)、奥州・花園へと落ち延びました。
しかし文治五年(1189年)以前に秀義は頼朝公に帰順、奥州合戦で武功を上げて御家人の地位を確保しています。
富士川の戦い、金砂城の戦いと頼朝公に敵対した佐竹氏が滅ぼされることなく御家人の座を確保したのは不思議な感じもします。
佐竹氏は清和源氏義光流で、新羅三郎義光公の嫡男・義業ないしその子・昌義を祖とする常陸の名族。
しかも義光公の室(義業の母)は桓武平氏の平(吉田)清幹の息女で、佐竹氏は桓武平氏の流れもひいています。
秋霜烈日な頼朝公も、名族・佐竹氏を滅ぼすことにはためらいがあったということでしょうか。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり大寳寺の記載がありました。
「佐竹山ニアリ。多福山一乗院ト号ス(妙本寺末)。寺伝ハ文安元年(1444年)開山日出(長禄三年(1459年)四月九日寂ス)起立シ、此地ニ新羅三郎義光ノ霊廟アルガ故、其法名多福院ト云フヲ執テ山号トスト云ヘリ。サレド義光ノ法名ト云フモノ信用シ難シ。恐ラクハ訛ナルベシ。土人ノ伝ニ此地ハ佐竹常陸介秀義以後数世居住ノ地ニテ。今猶当所ヲ佐竹屋鋪ト字スルハ此故ナリト云フ。是ニ『諸家系図纂』ヲ参考スルニ秀義ノ後裔右馬頭義盛。應永六年(1399年)鎌倉ニ多福寺ヲ建トアリ 是ニ拠レバ其先義盛当所ノ邸宅ヲ転ジテ一寺創建アリシガ、蚤ク廢寺トナリシヲ文安(1444-1449年)ニ至リ。日出其舊趾ニ就テ当寺ヲ営ミ舊寺号ヲ執テ山ニ名ヅケ。今ノ寺院号ヲ称セシナルベシ。本尊三寶諸尊及ビ祖師ノ像ヲ安ス。」
「祖師堂。日蓮及ビ開山日出ノ像ヲ安ス。鬼子母神ノ像ヲモ置ケリ。」
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
名族、佐竹氏は室町時代も勢力を保ち、関東管領上杉家ともふかい関係をもちました。
應永十四年(1407年)第11代当主佐竹義盛が実子を残さず没したため、鎌倉公方足利満兼の裁可により、関東管領上杉憲定の次男・義人が義盛の娘源姫の婿として入り家督を継承しました。
足利満兼の子で第4代鎌倉公方の足利持氏も義人を後見・支持しました。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流はこれに反発し、山入(佐竹)与義(上総介入道常元)をかつぎました。
与義は京都扶持衆(将軍家直属の扶持衆)に任ぜられ、鎌倉府の支配外という強みもあったようです。
應永廿三年(1416年)の上杉禅秀の乱では義人・持氏派と与義・禅秀派が対立、与義は降伏するものの以降も抵抗をつづけました。
これに対して應永廿九年(1422年)、ついに持氏は側近の上杉憲直(宅間上杉)に対し佐竹屋敷に拠る与義の討伐を命じ、憲直に攻められた与義は裏山を伝って比企ヶ谷妙本寺に遁れ、法華堂(新釈迦堂)にて自刃したと伝わります。
上記から、1400年代中盤までは佐竹氏ないし庶流の山入氏が佐竹屋敷に拠っていたことがわかります。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流がここまで頑強に宗主の義人に反抗したのは、義人が清和源氏の出ではなく、藤原北家流の上杉氏の出であったことも大きいとする説があります。
應永六年(1399年)、鎌倉公方足利満兼が旧来の名族として定めた「関東八屋形」に、佐竹氏は、宇都宮氏、小田氏、小山氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏とともに列格しています。
「関東八屋形」のうち清和源氏は佐竹氏のみで、新羅三郎義光公嫡流としての矜持はすこぶる高かったのでは。
佐竹氏は伝統的に反与党の立ち位置が目立ちましたが、中世の戦乱をくぐり抜け、先祖伝来の常陸国から秋田(久保田)に転封されたものの二十万石強(実高40万石ともいわれる)の石高を保ち、明治まで大名家として存続しました。
新羅三郎義光公の流れを汲むとされる江戸期の大名家は、小笠原家、南部家、溝口家、柳沢家、蠣崎家(松前家)などがありますがいずれも甲斐源氏(義清流)で、嫡流系(義業流)の佐竹氏は、その点でも格別のポジションにあったのでは。
義光公の墓所は、調べのついたところでは滋賀県大津市園城寺町(新羅善神堂のそば)とここ大寳寺にしかありません。
その点からも清和源氏にとって大切な寺院とみられます。
---------------------


【写真 上(左)】 道標
【写真 下(右)】 山内入口
大町大路から北東、釈迦堂切通しに向かう小路沿いは著名寺院がなく、切通しも現在通行止めとなっているので観光客の姿はほとんどみられず閑静な住宅地となっています。
大寳寺は、この小路からさらに左手山側に入ったところにあります。
位置的にいうと、ちょうど名越の妙法寺と比企谷の妙本寺の中間あたりです。


【写真 上(左)】 「佐竹屋敷跡」の石碑
【写真 下(右)】 寺号標
山内入口に「佐竹屋敷跡」の石碑と寺号標、曲がり参道でここからは本堂は見えません。
参道を進むと、右手に大多福稲荷大明神。左手正面が本堂です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 お題目塔
本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺の妻入り。妻部の千鳥破風の下に向拝が設けられています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に朱雀(?)の彫刻。
正面サッシュ窓のうえには寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 天水鉢
本堂には三宝祖師のほか、新羅三郎源義光公像、子育鬼子母神、出世大黒天神、日出上人像などが祀られているそうです。
こちらの「子育鬼子母神」は子育てに霊験あらたかとして知られ、毎年5月9日には子育鬼子母神祭が催されています。
本堂手前の天水鉢には、「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)の紋が見えます。


【写真 上(左)】 大多福稲荷大明神
【写真 下(右)】 大多福稲荷大明神の鳥居扁額
山内右手の大多福稲荷大明神は石像の稲荷鳥居(台輪鳥居)で「多福稲荷」の扁額。
拝殿は石造の一間社流造りで、全体に真新しい感じです。
新羅三郎義光公の墓所についてはよくわかりませんでしたが、いくつかある宝篋印塔のひとつが墓所ないし供養塔かもしれません。(墓所は裏山という情報もあり)
御首題、御朱印ともに庫裡にて拝受しました。
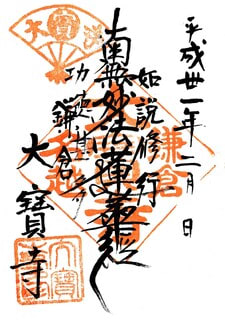
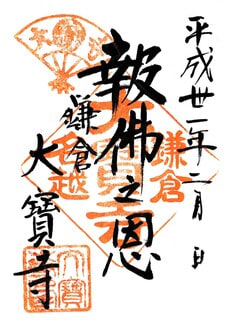
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
27.八雲神社(やくもじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市大町1-11-22
御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
永保三年(1083年)新羅三郎源義光公の勧請とされる、鎌倉を代表する古社で大町の鎮守です。
神奈川県神社庁Web、『鎌倉市史』などによる創祀は以下のとおりです。
永保三年(1083年)、義光公は奥州討伐「後三年の役」で苦戦している兄・八幡太郎源義家公の助勢に赴く途中、鎌倉に立ちよられました。
この地に悪疫が流行し郷民が苦しんでいるのをみた義光公は、「厄除神」として霊験あらたかな京の祇園社を勧請して祈願されたところ悪疫は退散し郷民は救われました
以後郷民はこのお社を”祇園さま”と崇め奉り、篤く信仰してきました。
應永年間(1394-1428年)には、当社東側の佐竹屋敷に祀られていた祠が合祀されて「佐竹天王」と称し、また御輿一座を「佐竹天王」と呼びならわすともいいます。
文安六年(1449年)、当社の神興が足利成氏の管領屋敷に渡御し奉幣の式が催されています。(『鎌倉年中行事』)
天正十四年(1586年)、北条氏直治世の時には「当社祭礼に際し不敬不礼の者は権門といえでも厳科に処す」という禁制守護状が下賜され、当社の神威がきわめて高かったことがうかがわれます。
徳川家康公も当社への尊崇の念篤く、朱印地(神領)を下賜されています。
社号は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社とも称していましたが、明治維新に際して八雲神社と改号しています。
大町総鎮守として明治6年村社に列格、明治40年神饌幣帛料供進神社に昇格。
明治44年には村内の上諏訪神社(名越)、下諏訪神社(米町)、神明社(米町)、古八幡社(中座町)の4社を合併しています。
いまも厄除開運の神社として地元では「八雲さん」や「お天王さん」などと呼ばれて親しまれ、毎年7月の神幸祭(大町まつり)の「神興渡御」や「神輿くぐり」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり祇園天王社の記載があります。
「松殿町ニアリ。永保年中(1081-1084年)新羅三郎義光ノ勧請ニテ。神体ハ秘像ト云伝フ。氏成管領ノ頃ハ。毎年六月七日。公方屋敷ニ御輿ヲ渡シテ。神楽ヲ奏シ奉幣ノ式アリ。又十四日ノ祇園会モ是ト同シ。築地ノ上桟敷ヲ構ヘ。舞練物等見物アリ。又應永年中(1394-1428年)佐竹四郎義秀ノ霊ヲ祀シ社。其屋鋪蹟ニアリシカ。後年大破ニ及シヨリ玆ニ合祀スト云フ。其年代詳ラナス。故ニ土俗佐竹天王ト称ス。按スルニ。義秀ハ頼朝ニ属セシ人ニテ時代違ヘリ。應永(1394-1428年)ノ末ニ。其末葉佐竹上総介義顕入道。管領持氏ノ不審ヲ蒙リ討手ヲ引請。終ニ比企谷ノ法華堂(今ノ妙本寺也)ニテ自害ス。其霊祟アリトテ。一社ニ祀リシ事アリ。是今相殿ノ舊社ニテ。義秀ト云フハ義顕ノ誤ナルベシ。例祭舊ニ因テ。六月七日ヨリ十四日迄行ハル。本日当村乱橋村ノ二所ニ。仮屋ヲ設。前ノ二村。小町村。又雪ノ下村ノ内。大蔵町ノ四所ニ。四座ノ神輿。巡行アルヲ例トス。天正十四年(1586年)六月小田原北條氏ヨリ祭礼ノ時ノ制札ヲ出セリ。」
御祭神として須佐之男命(スサノヲ)、配偶神である稲田姫命、スサノヲの御子神とされる八王子命、そして佐竹氏霊が祀られています。
『新編相模國風土記稿』の大寳寺(多福明神社)の項には下記の記載があります。
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
大寳寺(多福明神社)には佐竹氏の霊廟があり、こちらは佐竹天王祭禮で彼神渡御を行っていたので、八雲神社の御祭神の一座「佐竹氏霊」とゆかりがあるのかも。
また「彼祇園ノ相殿」とは八雲神社の相殿をさすのかもしれません。
大寳寺の山内掲示(抜粋)には以下のとおりあるので、やはり八雲神社に合祀ののち、大多福稲荷大明神として大寳寺に再勧請という流れとみられます。
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
スサノヲは神仏習合のもとで牛頭天王と習合し、「祇園信仰」のもと各地で祀られています。
「祇園信仰」にはいくつかの流れがあり、社号によってそのおおよその流れがわかるともいわれますが、例外も多くあります。
・京都祇園の八坂神社からの勧請系では、八坂神社、弥栄神社、祇園神社、八雲神社、八剣神社など。
・播磨・姫路の広峯神社からの勧請系では、広峯神社、素盞嗚神社など。
・須佐神社(紀伊有田ないし出雲国)からの勧請系では、須佐神社、八雲神社など。
・須賀神社からの勧請系では、須賀神社、素鵞神社、須我神社など。
・愛知の津島神社からの勧請系では、津島神社、天王(神)社など
当社は京祇園の八坂神社からの勧請系で当初は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社を号し、明治以降は八雲神社を号されています。
なお、関東地方でスサノヲを祀る神社として氷川神社がありますが、こちらは「氷川(簸川)信仰」にもとづくもので「祇園信仰」とは別の系統という説があります。
鎌倉の祇園信仰関連社として当社を含む4つの八雲神社(大町、西御門、山ノ内、常盤)が数えられ、うち御朱印授与は当社のみの模様です。
---------------------


【写真 上(左)】 案内看板
【写真 下(右)】 社頭
小町大路を蛭子神社の北から東に別れ、滑川にかかる琴弾橋を渡って妙本寺総門、常栄寺、八雲神社と辿って南下する小路(名称不明)は、東に山肌が迫り古都らしい落ち着いた住宅地がつづく風情ある道行きです。
八雲神社の社頭はこの小路に面しています。
この小路は狭く駐車場もないので、1本西の小町大路沿いのコインパーキングへの駐車がベター。近年リーズナブル料金のPが増えてきました。


【写真 上(左)】 一の鳥居
【写真 下(右)】 二の鳥居
社頭は石垣で数段高く、裏山づたいの緑がうっそうと茂っています。
石造の神明鳥居(一の鳥居)をくぐると空気感が変わります。
参道を行くと左手に手水舎。
その先に朱塗り灯籠一対、玉垣&石段の左右に阿吽の狛犬一対、さらに金属造の神明鳥居(二の鳥居)と、地域の中核社らしくきっちりまとまった印象。


【写真 上(左)】 境内-1
【写真 下(右)】 境内-2
山肌迫る境内の正面に本社拝殿、左右に境内社、左手手前に「新羅三郎手玉石」、左手脇に宝物殿。
本殿左右の社叢は生い茂ってほの暗く、パワスポ的雰囲気をまとっています。
本殿向かって右手は祇園山ハイキングコースの登り口です。


【写真 上(左)】 手玉石
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿は入母屋造桟瓦葺で、手前に軒唐破風の向拝を付設しています。
鬼板に御神紋。兎毛通部に鳥の彫刻。
水引虹梁両端には見返りの獅子、頭貫上に大がかりな斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に豪壮な龍?の彫刻を配して見応えのある意匠です。
こちらは、鎌倉・逗子・葉山エリアの十数社の神社の本務社で、それぞれ御朱印を授与されているので幾度となくお伺いしていますが、どんな季節でも天気でも、この神さびた雰囲気は変わりませんでした。
御朱印は向かって右の社務所にて授与されていますが、12時から13時半は避けた方がいいかもしれません。
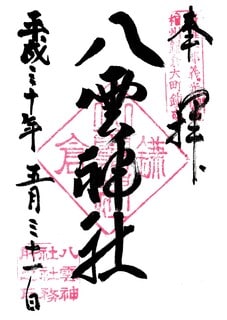
御朱印
28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-12-11
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
「ぼたもち寺」として親しまれる日蓮宗寺院です。
「龍ノ口法難」の際、片瀬の処刑場に引かれていく日蓮聖人にこの地に住む尼が胡麻のぼたもちを献上、その直後に片瀬龍ノ口で日蓮聖人を救う奇跡が起こったため、このぼたもちは「頸つぎのぼたもち」といわれ、「ぼたもち寺」として名が広がりました。
龍口寺の公式Webによると「龍ノ口法難」は以下のような内容です。
鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病など災厄に見舞われていました。
これを憂えた日蓮聖人は『立正安国論』を著されて幕府に奏上しました。
しかし、幕府はこれを政策への中傷と捉え、文永八年(1272年)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえて斬首するために鎌倉から片瀬の刑場龍ノ口へ連行し土牢へと押し込めました。
(御内人・平頼綱の独断で連行という説もあり。)
翌13日の未明、土牢から引き出された日蓮聖人は敷皮石に坐らされあわや斬首になるというそのとき、「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。
この法難は後世「龍ノ口法難」と呼ばれ、日蓮聖人の四大法難(松葉谷・伊豆・小松原・龍ノ口)に数えられています。
「龍ノ口法難」の地である龍ノ口には、日蓮聖人直弟子の日法上人が延元二年(1337年)一堂を建立され、その後本山(霊跡寺院)として高い寺格を有しています。
毎年9月11~13日「龍口法難会」として大法要が営まれ、ぼたもちが御宝前にお供ええされ、高所から撒かれて参詣者にも振る舞われます。
これが龍口寺の「難除けのぼたもち」で、「龍ノ口法難」における”ぼたもち”の存在の大きさがうかがわれます。
常栄寺にも資料類の掲示がありましたので、こちらをベースに縁起等をまとめてみます。
源頼朝公は由比ヶ浜での千羽鶴の放鳥を遠望するため、当山の裏山に桟敷(展望台)を設けたといわれます。
この地には鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王(在任1252-1266年)の近臣、印東次郎左衛門尉祐信夫妻が住んでおり、理縁尼ないし桟敷の尼(法名:妙常日栄)と称したその妻がくだんのぼたもちの尼であったといいます。
当山資料には「七百年後の今日においてもなお毎年九月十二日御法難会に際し、当寺より住職、信徒威儀を正して唱題のうちに片瀬龍口寺の祖師像に胡麻の餅を供えるのを古来よりの例としている。」とあります。
印東夫妻の法華経信仰を褒めたたえる日蓮聖人の書簡が伝わっているので、すでにこの地で草庵が結ばれていたとみられますが、寺院としての創立は比企谷・池上両山十四世自証院日証上人(日祐上人とも)により慶長十一年(1606年)と伝わります。
創立時に宝篋堂壇林(僧侶養成所)も開かれ、元禄二年(1689年)池上に移されて南谷壇林となりました。
開山の際、桟敷の尼の法名から常栄寺と号し、夫妻の墓を桟敷大明神として勧請されたようです。
桟敷の尼がぼたもちづくりに使われた木鉢とおはぐろ壺は当山に、お盆替わりに使われた鍋蓋は龍口寺にいまも所蔵されるといいます。
---------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山門
八雲神社の並びに山を背にしてあります。
朱塗りで屋根つきの冠木門といった風の変わった山門で、門柱には「ぼたもち寺」とあります。
左の門柱には「たつのくち 首の御座をふし拝む 老婆のまごころ ぼたもち 常栄寺」の句。


【写真 上(左)】 山門からの山内
【写真 下(右)】 山内のあしらい
山門左右には立派なお題目塔。
本堂に向かってまっすぐのびる参道の両脇には草花が植えられ、野趣あふれる山内です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂

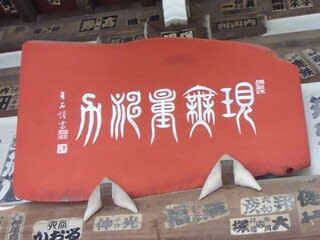
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝で、屋根中央に大がかりな千鳥破風を興して見応えがあります。
破風上には経の巻獅子口、下には猪の目懸魚、板蟇股の左右に端正な斗栱を備えています。
水引虹梁両端は貫がなく木鼻もありません。頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
全体に鎌倉の古寺らしい風雅な趣きを備えています。
向拝見上げには扁額がかかっていますが、不勉強につき読解不能です。


【写真 上(左)】 縁起
【写真 下(右)】 ぼたもちの句
御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受できますが。受付は下記の通りで要注意です。
11:00~12:00、13:00~15:00
御首題は御首題帳限定授与かもしれませんが未確認。
御朱印は句と御詠歌の2種あるようですが、混雑時には1人1種となることもあるようです。

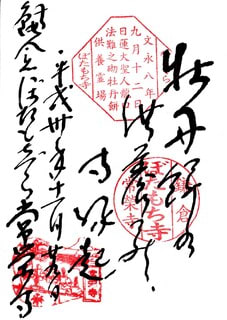
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印(句)
29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
大聖寺殿東陽岱公(北條左京大夫氏康/1515-1571年)が開基となり、知阿上人が開山と伝わる時宗寺院です。
当初は光明寺山内の北の山際にありましたが、延寶六年(1678年)現在地へ移転。
現在地にはもともと光明寺末の善昌寺があり、廃寺となったため移転と伝わります。
大町の街なかにひっそりと佇む比較的地味なお寺ですが、平家の公達にかかわる哀しい寺伝をもちます。
『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。
「寶海山と号す。米町の内にあり。時宗、藤澤道場の末寺なり。里老の伝、本は光明寺の境内、北の山ぎわに有しを、延寶六年(1678年)に、貴譽上人此地に移す。元此地に善昌寺と云て光明寺の末寺あり。廃亡したる故に、教恩寺を此に移し。元教恩寺の跡を、所化寮とせり。本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ、平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像。打ちうなづきけるとなん。寺寶 盃壱個 平重衡、千壽前と酒宴の時の盃なりと言伝ふ。」
また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり教恩寺の記載があります。
「中座町ニアリ。中座山(鎌倉志に寶海山トアリ。貞享已後改シニヤ。)大聖院ト号ス。藤澤清浄光寺末。開山ハ知阿開基ハ俗称ヲ傳ヘズ。大聖院東陽岱公トノミ伝フ。是北條左京大夫氏康ノ法名ニテ。今大住郡栗原村萬松寺ニ其碑アリ。鎌倉志。里老ノ言ヲ引テ。舊ハ光明寺ノ境内。北ノ山際ニ在シヲ。延寶六年(1678年)僧貴譽此地ニ移ス。元此地ニ善昌寺ト云フ光明寺ノ末寺アリ。其寺廃無セシガ故当寺ヲ爰ニ移シ。元ノ当寺蹟ヲ所化寮トスト記セリ。三尊ノ彌陀(運慶作)ヲ本尊トス。寺伝ニ是ハ元暦元年(1184年)平家沒落ノ時。三位中将重衡囚レテ。鎌倉ニ在シ程。賴朝ガ授与ノ靈像ニテ重衡ガ帰依佛ナリト伝フ。当安置ノ来由伝ハラズ。寺寶 盃三口 共ニ重衡ノ盃ト伝フ。」
御本尊の阿弥陀三尊像は、一ノ谷の戦いで敗れて捕虜になり鎌倉へ護送された三位中将平重衡に、「平家一族の冥福を祈るように」と源頼朝公が贈ったお像と伝わります。
重衡はこの阿弥陀像に篤く帰依し、臨終正念(極楽成仏?)を祈ったところ、この阿弥陀像は「打ちうなづきけるとなん。」と伝わります。(『新編鎌倉志』)
また、当山寺宝として重衡の盃が伝わり、これは重衡が愛した”千手の前”との酒宴で使われたものとの由。
平重衡(たいらのしげひら)は、平清盛公の五男で母は清盛の継室・平時子(二位尼)。
妻は大納言藤原邦綱の息女・藤原輔子。
若くして正三位左近衛権中将に進み、三位中将と称された平家の公達です。
弱冠ながら平家の大将として各地を転戦し、源平合戦の墨俣川の戦い、水島の戦いで源氏方を破るなど活躍したものの一ノ谷の戦いで捕虜になり、寿永三年(1184年)3月、伊豆を経て鎌倉へと護送されました。
平氏滅亡後、重衡による南都焼討を恨んだ南都衆徒の要求で引き渡され、木津川畔で斬首されました。
その優れた将器は「武勇の器量に堪ふる」(『玉葉』)と賞されるとともに、その容姿は牡丹の花に例えられるほどだったといいます。
また、『玉葉和歌集』に撰ばれた勅撰歌人でもあります。
いわば文武兼ね備えたイケメン公達で、他人への心づかいがあり、話術にも長けていたため宮中の女性にすこぶる人気があったらしく、『平家公達草紙』によると都落ちの際、御所に別れの挨拶に訪れた折には大勢の女房たちが涙にくれたといいます。
こういう清々しい人物はどこにいっても大事にされるものですが、じっさい鎌倉に送られたあとも風雅な逸話を残しています。
『吾妻鏡』には、重衡がはじめて頼朝公に対面した折、「囚人の身となったからには、もはやあれこれ言う事もない。弓馬の者が敵方の(武功の)ために捕虜になり命を落とすことは恥ではない。早く斬罪にされよ。」ときっぱり答えて周囲を感歎させたとあります。
頼朝公は重衡の度量に感心して彼を狩野宗茂に預け、北条政子は重衡の世話役として侍女の千手の前をつけました。
頼朝公が重衡を慰めるため設けた宴では、工藤祐経が鼓を打って今様を謡い、千手の前は琵琶を弾き、重衡がこれにあわせて横笛を吹き、朗詠を吟じてその風雅なありさまは『平家物語』にも描かれています。
千手の前は駿河国手越長者の娘で、温和な性格の女性だったと伝わります。(実在については諸説あり。)
ほどなく重衡に惹かれるようになり、重衡と千手の前は恋におちて結ばれたといいます。
元暦二年(1185年)6月、南都焼討を恨む南都衆徒の要求により、重衡はやむなく南都へ引き渡されることになり、源頼兼の護送のもとで鎌倉を出立。
東大寺の使者に引き渡されてほどなく木津川畔にて斬首されました。
享年29と伝わります。
なお、重衡は生前の元暦元年(1184年)に法然と対面し、受戒しているとされます。(→「平重衡の問に念仏往生を示す御詞」/浄土宗大辞典Web)
重衡の妻の輔子は重衡の南都護送の途中、伏見の日野で最期の対面を果たし、『平家物語』の名場面のひとつに数えられています。
輔子は重衡の遺骸を引き取り、日野に墓を建て法界寺(日野薬師)の僧に供養を託しました。
輔子はその後出家して、大原寂光院に隠棲した建礼門院に仕えたといいます。
『平家物語』の”大原御幸の巻”で登場し、”六道の巻”では建礼門院が極楽往生を遂げる際に阿波内侍とともにこれを看取った様が描かれています。
千手の前は重衡の死のわずか三年後に24歳でこの世を去り、鎌倉の人々は千手が重衡を朝夕恋慕し、それが積み重なっての憂死と噂したといいます。(『吾妻鏡』)
『平家物語』では、千手は出家して信濃の善光寺に入り、重衡の菩提を弔ったとあります。
重衡と千手とのかかわりは能の『千手』で演じられ、仏都・南都を焼き討ちした身と敬虔な仏徒としての葛藤を描いた修羅能『重衡』も能の演目として知られています。
- 住みなれし 古き都の 恋しさは 神もむかしに 思ひしるらむ -
(『玉葉和歌集』(勅撰)巻第8 旅歌 平重衡)
---------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門からの山内
大町大路と小町大路が交差する「大町四ツ角」の北西の路地のおくにひっそりと佇みます。
鎌倉観光ではエアポケット的な立地で、鎌倉三十三観音霊場の巡拝者のほかは拝観者は少ない模様です。


【写真 上(左)】 紫陽花と本堂
【写真 下(右)】 本堂
山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、前面中備の十六羅漢と裏面の牡丹の彫刻がみどころとされます。
すこぶる手入れのいきとどいた山内で、小枝ひとつ落ちていません。


【写真 上(左)】 天水鉢
【写真 下(右)】 向拝-1
石畳の参道正面に(おそらく)入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
いずれもすばらしい仕上がりで見応えがあります。


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
向拝正面桟唐戸のうえに山号扁額で、ムダがなくバランスのよい向拝まわりです。


【写真 上(左)】 御朱印所
【写真 下(右)】 寺号板
御本尊の阿弥陀如来像と両脇侍立像は鎌倉時代前期の作とみられ、一説では運慶の作ともいわれる名作で県重要文化財に指定されています。
鎌倉三十三観音第12番の札所本尊、聖観世音菩薩も本堂内の御座です。
御朱印は本堂脇の御朱印所にて拝受しました。
〔 御本尊・阿弥陀如来の御朱印 〕
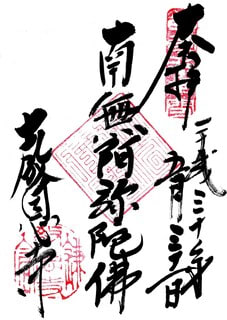
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

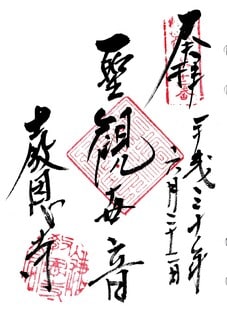
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は三寶印です。
■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづきます。
【 BGM 】
■ New Frontier - Donald Fagen
■ On And On - Angela Bofill
■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin
■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)
■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)から。
■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)
■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづく。
26.多福山 一乗院 大寳寺(だいほうじ)
鎌倉市Web資料
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町3-6-22
日蓮宗
御本尊:三宝諸尊(『鎌倉市史 社寺編』)
大町にある日蓮宗寺院。
新羅三郎義光公や佐竹氏とのゆかりをもち、歴史好きは見逃せないお寺です。
現地掲示、鎌倉市Webなどによると、この一帯は佐竹氏の祖先である新羅三郎源義光公が兄の義家公とともに永保三年(1083年)の後三年の役に出陣し、戦捷ののちに館をかまえ以降佐竹氏の屋敷になったといいます。
應永六年(1399年)佐竹義盛が出家して多福寺を開基建立した後、文安元年(1444年)日蓮宗の高僧一乗院日出上人が再興開山となり、号を改め多福山大寶寺となりました。
源義光公は戦捷は日頃から信仰されていた多福大明神の御加護によるものとし、この地に多福明神社を建てられたと伝わります。
山内掲示には以下のとおりあります。(抜粋)
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
山内の多福明神社(大多福稲荷大明神)はもともと義光公が信仰され、多福寺が一旦廃寺になったときに大町の八雲神社に合祀されて、明應八年(1499年)に松葉ヶ谷妙法寺の日證上人によって八雲神社から大寶寺に再勧請とあります。
ちなみに、義光公の子孫は武家として栄え、嫡男・義業からは佐竹氏(常陸源氏)、義清からは武田、小笠原、南部、三好などの甲斐源氏、盛義からは平賀、大内などの信濃源氏が出ています。
『新編鎌倉志』『鎌倉攬勝考』ともに、大寳寺についての記載はみあたりませんでした。
佐竹氏屋敷跡の記載はありましたので引用します。
『新編鎌倉志』
「佐竹屋敷は、名越道の北、妙本寺の東の山に、五本骨扇の如なる山のウネあり。其下を佐竹秀義が舊宅と云。【東鑑】に、文治五年(1189年)七月廿六日、頼朝、奥州退治の時、宇都宮を立給時、無紋白旗也。二品頼朝是を咎給、仍月を出の御扇を佐竹に賜り、旗の上に付べきの由仰せらる。御旗と等しかるべからずの故也。佐竹、御旨にしたがひ、是を付るとあり。今に佐竹の家これを以て紋とす。此山のウネも、家の紋をかたどり作りたるならん。」
『鎌倉攬勝考』
「佐竹四郎秀義第跡 名越往来の北の方、妙本寺の東の山に五本骨の扇のごとくなる山のウネあり。其下を佐竹冠者秀義が舊跡といふ。此秀義扇の紋を賜ひしは、文治五年(1189年)、右大将家奥州征伐の時なり。山の谷を穿ち、五本骨に造りしは後世の事なり。足利家の代となりても、此所に佐竹氏住居の事にや、公方持氏朝臣、應永廿九年(1422年)十月三日、家督の事に依て、佐竹上総介入道を上杉憲直に討しむ。」
ともに佐竹氏定紋の「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)を奥州討伐の際に頼朝公から給い、これにちなんで屋敷の周辺を「五本骨扇」のかたちに整えたという内容です。
佐竹隆義・秀義は、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げの際に参陣せず、同年秋の富士川の戦いでは平家方につきました。
富士川の敗戦の後、本拠の常陸へ逃れた秀義は頼朝勢に追撃され(金砂城の戦い)、奥州・花園へと落ち延びました。
しかし文治五年(1189年)以前に秀義は頼朝公に帰順、奥州合戦で武功を上げて御家人の地位を確保しています。
富士川の戦い、金砂城の戦いと頼朝公に敵対した佐竹氏が滅ぼされることなく御家人の座を確保したのは不思議な感じもします。
佐竹氏は清和源氏義光流で、新羅三郎義光公の嫡男・義業ないしその子・昌義を祖とする常陸の名族。
しかも義光公の室(義業の母)は桓武平氏の平(吉田)清幹の息女で、佐竹氏は桓武平氏の流れもひいています。
秋霜烈日な頼朝公も、名族・佐竹氏を滅ぼすことにはためらいがあったということでしょうか。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり大寳寺の記載がありました。
「佐竹山ニアリ。多福山一乗院ト号ス(妙本寺末)。寺伝ハ文安元年(1444年)開山日出(長禄三年(1459年)四月九日寂ス)起立シ、此地ニ新羅三郎義光ノ霊廟アルガ故、其法名多福院ト云フヲ執テ山号トスト云ヘリ。サレド義光ノ法名ト云フモノ信用シ難シ。恐ラクハ訛ナルベシ。土人ノ伝ニ此地ハ佐竹常陸介秀義以後数世居住ノ地ニテ。今猶当所ヲ佐竹屋鋪ト字スルハ此故ナリト云フ。是ニ『諸家系図纂』ヲ参考スルニ秀義ノ後裔右馬頭義盛。應永六年(1399年)鎌倉ニ多福寺ヲ建トアリ 是ニ拠レバ其先義盛当所ノ邸宅ヲ転ジテ一寺創建アリシガ、蚤ク廢寺トナリシヲ文安(1444-1449年)ニ至リ。日出其舊趾ニ就テ当寺ヲ営ミ舊寺号ヲ執テ山ニ名ヅケ。今ノ寺院号ヲ称セシナルベシ。本尊三寶諸尊及ビ祖師ノ像ヲ安ス。」
「祖師堂。日蓮及ビ開山日出ノ像ヲ安ス。鬼子母神ノ像ヲモ置ケリ。」
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
名族、佐竹氏は室町時代も勢力を保ち、関東管領上杉家ともふかい関係をもちました。
應永十四年(1407年)第11代当主佐竹義盛が実子を残さず没したため、鎌倉公方足利満兼の裁可により、関東管領上杉憲定の次男・義人が義盛の娘源姫の婿として入り家督を継承しました。
足利満兼の子で第4代鎌倉公方の足利持氏も義人を後見・支持しました。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流はこれに反発し、山入(佐竹)与義(上総介入道常元)をかつぎました。
与義は京都扶持衆(将軍家直属の扶持衆)に任ぜられ、鎌倉府の支配外という強みもあったようです。
應永廿三年(1416年)の上杉禅秀の乱では義人・持氏派と与義・禅秀派が対立、与義は降伏するものの以降も抵抗をつづけました。
これに対して應永廿九年(1422年)、ついに持氏は側近の上杉憲直(宅間上杉)に対し佐竹屋敷に拠る与義の討伐を命じ、憲直に攻められた与義は裏山を伝って比企ヶ谷妙本寺に遁れ、法華堂(新釈迦堂)にて自刃したと伝わります。
上記から、1400年代中盤までは佐竹氏ないし庶流の山入氏が佐竹屋敷に拠っていたことがわかります。
山入氏をはじめとする佐竹氏庶流がここまで頑強に宗主の義人に反抗したのは、義人が清和源氏の出ではなく、藤原北家流の上杉氏の出であったことも大きいとする説があります。
應永六年(1399年)、鎌倉公方足利満兼が旧来の名族として定めた「関東八屋形」に、佐竹氏は、宇都宮氏、小田氏、小山氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏とともに列格しています。
「関東八屋形」のうち清和源氏は佐竹氏のみで、新羅三郎義光公嫡流としての矜持はすこぶる高かったのでは。
佐竹氏は伝統的に反与党の立ち位置が目立ちましたが、中世の戦乱をくぐり抜け、先祖伝来の常陸国から秋田(久保田)に転封されたものの二十万石強(実高40万石ともいわれる)の石高を保ち、明治まで大名家として存続しました。
新羅三郎義光公の流れを汲むとされる江戸期の大名家は、小笠原家、南部家、溝口家、柳沢家、蠣崎家(松前家)などがありますがいずれも甲斐源氏(義清流)で、嫡流系(義業流)の佐竹氏は、その点でも格別のポジションにあったのでは。
義光公の墓所は、調べのついたところでは滋賀県大津市園城寺町(新羅善神堂のそば)とここ大寳寺にしかありません。
その点からも清和源氏にとって大切な寺院とみられます。
---------------------


【写真 上(左)】 道標
【写真 下(右)】 山内入口
大町大路から北東、釈迦堂切通しに向かう小路沿いは著名寺院がなく、切通しも現在通行止めとなっているので観光客の姿はほとんどみられず閑静な住宅地となっています。
大寳寺は、この小路からさらに左手山側に入ったところにあります。
位置的にいうと、ちょうど名越の妙法寺と比企谷の妙本寺の中間あたりです。


【写真 上(左)】 「佐竹屋敷跡」の石碑
【写真 下(右)】 寺号標
山内入口に「佐竹屋敷跡」の石碑と寺号標、曲がり参道でここからは本堂は見えません。
参道を進むと、右手に大多福稲荷大明神。左手正面が本堂です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 お題目塔
本堂はおそらく入母屋造桟瓦葺の妻入り。妻部の千鳥破風の下に向拝が設けられています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に朱雀(?)の彫刻。
正面サッシュ窓のうえには寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 天水鉢
本堂には三宝祖師のほか、新羅三郎源義光公像、子育鬼子母神、出世大黒天神、日出上人像などが祀られているそうです。
こちらの「子育鬼子母神」は子育てに霊験あらたかとして知られ、毎年5月9日には子育鬼子母神祭が催されています。
本堂手前の天水鉢には、「扇に月」(日の丸扇・佐竹扇)の紋が見えます。


【写真 上(左)】 大多福稲荷大明神
【写真 下(右)】 大多福稲荷大明神の鳥居扁額
山内右手の大多福稲荷大明神は石像の稲荷鳥居(台輪鳥居)で「多福稲荷」の扁額。
拝殿は石造の一間社流造りで、全体に真新しい感じです。
新羅三郎義光公の墓所についてはよくわかりませんでしたが、いくつかある宝篋印塔のひとつが墓所ないし供養塔かもしれません。(墓所は裏山という情報もあり)
御首題、御朱印ともに庫裡にて拝受しました。
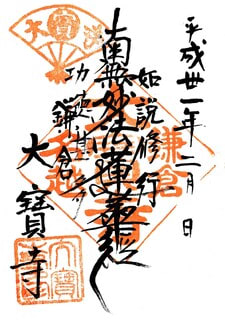
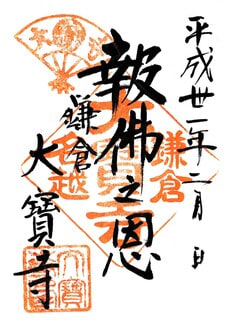
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
27.八雲神社(やくもじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市大町1-11-22
御祭神:須佐之男命、稲田姫命、八王子命、佐竹氏霊
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
永保三年(1083年)新羅三郎源義光公の勧請とされる、鎌倉を代表する古社で大町の鎮守です。
神奈川県神社庁Web、『鎌倉市史』などによる創祀は以下のとおりです。
永保三年(1083年)、義光公は奥州討伐「後三年の役」で苦戦している兄・八幡太郎源義家公の助勢に赴く途中、鎌倉に立ちよられました。
この地に悪疫が流行し郷民が苦しんでいるのをみた義光公は、「厄除神」として霊験あらたかな京の祇園社を勧請して祈願されたところ悪疫は退散し郷民は救われました
以後郷民はこのお社を”祇園さま”と崇め奉り、篤く信仰してきました。
應永年間(1394-1428年)には、当社東側の佐竹屋敷に祀られていた祠が合祀されて「佐竹天王」と称し、また御輿一座を「佐竹天王」と呼びならわすともいいます。
文安六年(1449年)、当社の神興が足利成氏の管領屋敷に渡御し奉幣の式が催されています。(『鎌倉年中行事』)
天正十四年(1586年)、北条氏直治世の時には「当社祭礼に際し不敬不礼の者は権門といえでも厳科に処す」という禁制守護状が下賜され、当社の神威がきわめて高かったことがうかがわれます。
徳川家康公も当社への尊崇の念篤く、朱印地(神領)を下賜されています。
社号は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社とも称していましたが、明治維新に際して八雲神社と改号しています。
大町総鎮守として明治6年村社に列格、明治40年神饌幣帛料供進神社に昇格。
明治44年には村内の上諏訪神社(名越)、下諏訪神社(米町)、神明社(米町)、古八幡社(中座町)の4社を合併しています。
いまも厄除開運の神社として地元では「八雲さん」や「お天王さん」などと呼ばれて親しまれ、毎年7月の神幸祭(大町まつり)の「神興渡御」や「神輿くぐり」は鎌倉の夏の風物詩として知られています。
『新編相模國風土記稿』には以下のとおり祇園天王社の記載があります。
「松殿町ニアリ。永保年中(1081-1084年)新羅三郎義光ノ勧請ニテ。神体ハ秘像ト云伝フ。氏成管領ノ頃ハ。毎年六月七日。公方屋敷ニ御輿ヲ渡シテ。神楽ヲ奏シ奉幣ノ式アリ。又十四日ノ祇園会モ是ト同シ。築地ノ上桟敷ヲ構ヘ。舞練物等見物アリ。又應永年中(1394-1428年)佐竹四郎義秀ノ霊ヲ祀シ社。其屋鋪蹟ニアリシカ。後年大破ニ及シヨリ玆ニ合祀スト云フ。其年代詳ラナス。故ニ土俗佐竹天王ト称ス。按スルニ。義秀ハ頼朝ニ属セシ人ニテ時代違ヘリ。應永(1394-1428年)ノ末ニ。其末葉佐竹上総介義顕入道。管領持氏ノ不審ヲ蒙リ討手ヲ引請。終ニ比企谷ノ法華堂(今ノ妙本寺也)ニテ自害ス。其霊祟アリトテ。一社ニ祀リシ事アリ。是今相殿ノ舊社ニテ。義秀ト云フハ義顕ノ誤ナルベシ。例祭舊ニ因テ。六月七日ヨリ十四日迄行ハル。本日当村乱橋村ノ二所ニ。仮屋ヲ設。前ノ二村。小町村。又雪ノ下村ノ内。大蔵町ノ四所ニ。四座ノ神輿。巡行アルヲ例トス。天正十四年(1586年)六月小田原北條氏ヨリ祭礼ノ時ノ制札ヲ出セリ。」
御祭神として須佐之男命(スサノヲ)、配偶神である稲田姫命、スサノヲの御子神とされる八王子命、そして佐竹氏霊が祀られています。
『新編相模國風土記稿』の大寳寺(多福明神社)の項には下記の記載があります。
「多福明神社。新羅三郎義光ノ霊廟ト云フ。明應八年(1499年)權大僧都日證(本山九世)一社ニ勧請シ其法号ヲ神号トスト伝フ。恐ラクハ佐竹義盛ノ霊廟ヲ義光ト訛リ伝フルナルベシ。毎年六月七日佐竹天王祭禮ノ時。爰ニ彼神輿ヲ渡シ神事ヲ行フ。其式舊例ニ随フト云フ。前ノ天王社伝ニ昔此地ニ佐竹秀義ノ霊社アリシガ破壊ノ後。彼祇園ノ相殿ニ祀ルト云フ。是ニ拠レバ当社モ義盛ガ霊社ト云ンニ論ナカルベシ。」
大寳寺(多福明神社)には佐竹氏の霊廟があり、こちらは佐竹天王祭禮で彼神渡御を行っていたので、八雲神社の御祭神の一座「佐竹氏霊」とゆかりがあるのかも。
また「彼祇園ノ相殿」とは八雲神社の相殿をさすのかもしれません。
大寳寺の山内掲示(抜粋)には以下のとおりあるので、やはり八雲神社に合祀ののち、大多福稲荷大明神として大寳寺に再勧請という流れとみられます。
「後三年の役の間日頃(義光公が)信仰していた御守護神の霊顕あらたかで 或る時は雁の伏兵を知らせ時には御神火となって奇瑞を顕す 御義光は甲斐守となり長男義業は常陸に住する 義光は鎌倉館(現大宝寺域)に居住し御守護神を勧請する 其の後八雲神社に合祀した(中略)明應八年(1499年)松葉谷日證上人の霊夢により本地たる現地に再勧請し大多福稲荷大明神と称する。」
スサノヲは神仏習合のもとで牛頭天王と習合し、「祇園信仰」のもと各地で祀られています。
「祇園信仰」にはいくつかの流れがあり、社号によってそのおおよその流れがわかるともいわれますが、例外も多くあります。
・京都祇園の八坂神社からの勧請系では、八坂神社、弥栄神社、祇園神社、八雲神社、八剣神社など。
・播磨・姫路の広峯神社からの勧請系では、広峯神社、素盞嗚神社など。
・須佐神社(紀伊有田ないし出雲国)からの勧請系では、須佐神社、八雲神社など。
・須賀神社からの勧請系では、須賀神社、素鵞神社、須我神社など。
・愛知の津島神社からの勧請系では、津島神社、天王(神)社など
当社は京祇園の八坂神社からの勧請系で当初は鎌倉(松堂)祇園社、祇園天王社を号し、明治以降は八雲神社を号されています。
なお、関東地方でスサノヲを祀る神社として氷川神社がありますが、こちらは「氷川(簸川)信仰」にもとづくもので「祇園信仰」とは別の系統という説があります。
鎌倉の祇園信仰関連社として当社を含む4つの八雲神社(大町、西御門、山ノ内、常盤)が数えられ、うち御朱印授与は当社のみの模様です。
---------------------


【写真 上(左)】 案内看板
【写真 下(右)】 社頭
小町大路を蛭子神社の北から東に別れ、滑川にかかる琴弾橋を渡って妙本寺総門、常栄寺、八雲神社と辿って南下する小路(名称不明)は、東に山肌が迫り古都らしい落ち着いた住宅地がつづく風情ある道行きです。
八雲神社の社頭はこの小路に面しています。
この小路は狭く駐車場もないので、1本西の小町大路沿いのコインパーキングへの駐車がベター。近年リーズナブル料金のPが増えてきました。


【写真 上(左)】 一の鳥居
【写真 下(右)】 二の鳥居
社頭は石垣で数段高く、裏山づたいの緑がうっそうと茂っています。
石造の神明鳥居(一の鳥居)をくぐると空気感が変わります。
参道を行くと左手に手水舎。
その先に朱塗り灯籠一対、玉垣&石段の左右に阿吽の狛犬一対、さらに金属造の神明鳥居(二の鳥居)と、地域の中核社らしくきっちりまとまった印象。


【写真 上(左)】 境内-1
【写真 下(右)】 境内-2
山肌迫る境内の正面に本社拝殿、左右に境内社、左手手前に「新羅三郎手玉石」、左手脇に宝物殿。
本殿左右の社叢は生い茂ってほの暗く、パワスポ的雰囲気をまとっています。
本殿向かって右手は祇園山ハイキングコースの登り口です。


【写真 上(左)】 手玉石
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿は入母屋造桟瓦葺で、手前に軒唐破風の向拝を付設しています。
鬼板に御神紋。兎毛通部に鳥の彫刻。
水引虹梁両端には見返りの獅子、頭貫上に大がかりな斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に豪壮な龍?の彫刻を配して見応えのある意匠です。
こちらは、鎌倉・逗子・葉山エリアの十数社の神社の本務社で、それぞれ御朱印を授与されているので幾度となくお伺いしていますが、どんな季節でも天気でも、この神さびた雰囲気は変わりませんでした。
御朱印は向かって右の社務所にて授与されていますが、12時から13時半は避けた方がいいかもしれません。
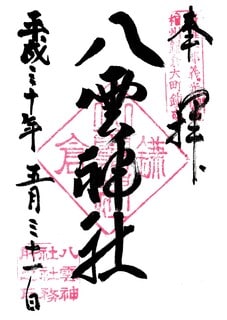
御朱印
28.慧雲山 常栄寺(じょうえいじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-12-11
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
「ぼたもち寺」として親しまれる日蓮宗寺院です。
「龍ノ口法難」の際、片瀬の処刑場に引かれていく日蓮聖人にこの地に住む尼が胡麻のぼたもちを献上、その直後に片瀬龍ノ口で日蓮聖人を救う奇跡が起こったため、このぼたもちは「頸つぎのぼたもち」といわれ、「ぼたもち寺」として名が広がりました。
龍口寺の公式Webによると「龍ノ口法難」は以下のような内容です。
鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病など災厄に見舞われていました。
これを憂えた日蓮聖人は『立正安国論』を著されて幕府に奏上しました。
しかし、幕府はこれを政策への中傷と捉え、文永八年(1272年)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえて斬首するために鎌倉から片瀬の刑場龍ノ口へ連行し土牢へと押し込めました。
(御内人・平頼綱の独断で連行という説もあり。)
翌13日の未明、土牢から引き出された日蓮聖人は敷皮石に坐らされあわや斬首になるというそのとき、「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。
この法難は後世「龍ノ口法難」と呼ばれ、日蓮聖人の四大法難(松葉谷・伊豆・小松原・龍ノ口)に数えられています。
「龍ノ口法難」の地である龍ノ口には、日蓮聖人直弟子の日法上人が延元二年(1337年)一堂を建立され、その後本山(霊跡寺院)として高い寺格を有しています。
毎年9月11~13日「龍口法難会」として大法要が営まれ、ぼたもちが御宝前にお供ええされ、高所から撒かれて参詣者にも振る舞われます。
これが龍口寺の「難除けのぼたもち」で、「龍ノ口法難」における”ぼたもち”の存在の大きさがうかがわれます。
常栄寺にも資料類の掲示がありましたので、こちらをベースに縁起等をまとめてみます。
源頼朝公は由比ヶ浜での千羽鶴の放鳥を遠望するため、当山の裏山に桟敷(展望台)を設けたといわれます。
この地には鎌倉幕府6代将軍・宗尊親王(在任1252-1266年)の近臣、印東次郎左衛門尉祐信夫妻が住んでおり、理縁尼ないし桟敷の尼(法名:妙常日栄)と称したその妻がくだんのぼたもちの尼であったといいます。
当山資料には「七百年後の今日においてもなお毎年九月十二日御法難会に際し、当寺より住職、信徒威儀を正して唱題のうちに片瀬龍口寺の祖師像に胡麻の餅を供えるのを古来よりの例としている。」とあります。
印東夫妻の法華経信仰を褒めたたえる日蓮聖人の書簡が伝わっているので、すでにこの地で草庵が結ばれていたとみられますが、寺院としての創立は比企谷・池上両山十四世自証院日証上人(日祐上人とも)により慶長十一年(1606年)と伝わります。
創立時に宝篋堂壇林(僧侶養成所)も開かれ、元禄二年(1689年)池上に移されて南谷壇林となりました。
開山の際、桟敷の尼の法名から常栄寺と号し、夫妻の墓を桟敷大明神として勧請されたようです。
桟敷の尼がぼたもちづくりに使われた木鉢とおはぐろ壺は当山に、お盆替わりに使われた鍋蓋は龍口寺にいまも所蔵されるといいます。
---------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山門
八雲神社の並びに山を背にしてあります。
朱塗りで屋根つきの冠木門といった風の変わった山門で、門柱には「ぼたもち寺」とあります。
左の門柱には「たつのくち 首の御座をふし拝む 老婆のまごころ ぼたもち 常栄寺」の句。


【写真 上(左)】 山門からの山内
【写真 下(右)】 山内のあしらい
山門左右には立派なお題目塔。
本堂に向かってまっすぐのびる参道の両脇には草花が植えられ、野趣あふれる山内です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂

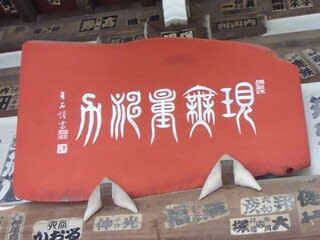
【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝で、屋根中央に大がかりな千鳥破風を興して見応えがあります。
破風上には経の巻獅子口、下には猪の目懸魚、板蟇股の左右に端正な斗栱を備えています。
水引虹梁両端は貫がなく木鼻もありません。頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
全体に鎌倉の古寺らしい風雅な趣きを備えています。
向拝見上げには扁額がかかっていますが、不勉強につき読解不能です。


【写真 上(左)】 縁起
【写真 下(右)】 ぼたもちの句
御朱印は本堂向かって右手の授与所にて拝受できますが。受付は下記の通りで要注意です。
11:00~12:00、13:00~15:00
御首題は御首題帳限定授与かもしれませんが未確認。
御朱印は句と御詠歌の2種あるようですが、混雑時には1人1種となることもあるようです。

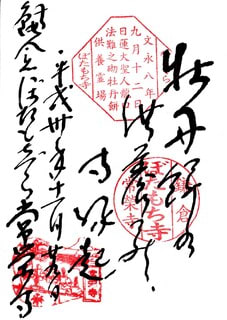
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印(句)
29.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市大町1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀如来三尊
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
大聖寺殿東陽岱公(北條左京大夫氏康/1515-1571年)が開基となり、知阿上人が開山と伝わる時宗寺院です。
当初は光明寺山内の北の山際にありましたが、延寶六年(1678年)現在地へ移転。
現在地にはもともと光明寺末の善昌寺があり、廃寺となったため移転と伝わります。
大町の街なかにひっそりと佇む比較的地味なお寺ですが、平家の公達にかかわる哀しい寺伝をもちます。
『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。
「寶海山と号す。米町の内にあり。時宗、藤澤道場の末寺なり。里老の伝、本は光明寺の境内、北の山ぎわに有しを、延寶六年(1678年)に、貴譽上人此地に移す。元此地に善昌寺と云て光明寺の末寺あり。廃亡したる故に、教恩寺を此に移し。元教恩寺の跡を、所化寮とせり。本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ、平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像。打ちうなづきけるとなん。寺寶 盃壱個 平重衡、千壽前と酒宴の時の盃なりと言伝ふ。」
また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり教恩寺の記載があります。
「中座町ニアリ。中座山(鎌倉志に寶海山トアリ。貞享已後改シニヤ。)大聖院ト号ス。藤澤清浄光寺末。開山ハ知阿開基ハ俗称ヲ傳ヘズ。大聖院東陽岱公トノミ伝フ。是北條左京大夫氏康ノ法名ニテ。今大住郡栗原村萬松寺ニ其碑アリ。鎌倉志。里老ノ言ヲ引テ。舊ハ光明寺ノ境内。北ノ山際ニ在シヲ。延寶六年(1678年)僧貴譽此地ニ移ス。元此地ニ善昌寺ト云フ光明寺ノ末寺アリ。其寺廃無セシガ故当寺ヲ爰ニ移シ。元ノ当寺蹟ヲ所化寮トスト記セリ。三尊ノ彌陀(運慶作)ヲ本尊トス。寺伝ニ是ハ元暦元年(1184年)平家沒落ノ時。三位中将重衡囚レテ。鎌倉ニ在シ程。賴朝ガ授与ノ靈像ニテ重衡ガ帰依佛ナリト伝フ。当安置ノ来由伝ハラズ。寺寶 盃三口 共ニ重衡ノ盃ト伝フ。」
御本尊の阿弥陀三尊像は、一ノ谷の戦いで敗れて捕虜になり鎌倉へ護送された三位中将平重衡に、「平家一族の冥福を祈るように」と源頼朝公が贈ったお像と伝わります。
重衡はこの阿弥陀像に篤く帰依し、臨終正念(極楽成仏?)を祈ったところ、この阿弥陀像は「打ちうなづきけるとなん。」と伝わります。(『新編鎌倉志』)
また、当山寺宝として重衡の盃が伝わり、これは重衡が愛した”千手の前”との酒宴で使われたものとの由。
平重衡(たいらのしげひら)は、平清盛公の五男で母は清盛の継室・平時子(二位尼)。
妻は大納言藤原邦綱の息女・藤原輔子。
若くして正三位左近衛権中将に進み、三位中将と称された平家の公達です。
弱冠ながら平家の大将として各地を転戦し、源平合戦の墨俣川の戦い、水島の戦いで源氏方を破るなど活躍したものの一ノ谷の戦いで捕虜になり、寿永三年(1184年)3月、伊豆を経て鎌倉へと護送されました。
平氏滅亡後、重衡による南都焼討を恨んだ南都衆徒の要求で引き渡され、木津川畔で斬首されました。
その優れた将器は「武勇の器量に堪ふる」(『玉葉』)と賞されるとともに、その容姿は牡丹の花に例えられるほどだったといいます。
また、『玉葉和歌集』に撰ばれた勅撰歌人でもあります。
いわば文武兼ね備えたイケメン公達で、他人への心づかいがあり、話術にも長けていたため宮中の女性にすこぶる人気があったらしく、『平家公達草紙』によると都落ちの際、御所に別れの挨拶に訪れた折には大勢の女房たちが涙にくれたといいます。
こういう清々しい人物はどこにいっても大事にされるものですが、じっさい鎌倉に送られたあとも風雅な逸話を残しています。
『吾妻鏡』には、重衡がはじめて頼朝公に対面した折、「囚人の身となったからには、もはやあれこれ言う事もない。弓馬の者が敵方の(武功の)ために捕虜になり命を落とすことは恥ではない。早く斬罪にされよ。」ときっぱり答えて周囲を感歎させたとあります。
頼朝公は重衡の度量に感心して彼を狩野宗茂に預け、北条政子は重衡の世話役として侍女の千手の前をつけました。
頼朝公が重衡を慰めるため設けた宴では、工藤祐経が鼓を打って今様を謡い、千手の前は琵琶を弾き、重衡がこれにあわせて横笛を吹き、朗詠を吟じてその風雅なありさまは『平家物語』にも描かれています。
千手の前は駿河国手越長者の娘で、温和な性格の女性だったと伝わります。(実在については諸説あり。)
ほどなく重衡に惹かれるようになり、重衡と千手の前は恋におちて結ばれたといいます。
元暦二年(1185年)6月、南都焼討を恨む南都衆徒の要求により、重衡はやむなく南都へ引き渡されることになり、源頼兼の護送のもとで鎌倉を出立。
東大寺の使者に引き渡されてほどなく木津川畔にて斬首されました。
享年29と伝わります。
なお、重衡は生前の元暦元年(1184年)に法然と対面し、受戒しているとされます。(→「平重衡の問に念仏往生を示す御詞」/浄土宗大辞典Web)
重衡の妻の輔子は重衡の南都護送の途中、伏見の日野で最期の対面を果たし、『平家物語』の名場面のひとつに数えられています。
輔子は重衡の遺骸を引き取り、日野に墓を建て法界寺(日野薬師)の僧に供養を託しました。
輔子はその後出家して、大原寂光院に隠棲した建礼門院に仕えたといいます。
『平家物語』の”大原御幸の巻”で登場し、”六道の巻”では建礼門院が極楽往生を遂げる際に阿波内侍とともにこれを看取った様が描かれています。
千手の前は重衡の死のわずか三年後に24歳でこの世を去り、鎌倉の人々は千手が重衡を朝夕恋慕し、それが積み重なっての憂死と噂したといいます。(『吾妻鏡』)
『平家物語』では、千手は出家して信濃の善光寺に入り、重衡の菩提を弔ったとあります。
重衡と千手とのかかわりは能の『千手』で演じられ、仏都・南都を焼き討ちした身と敬虔な仏徒としての葛藤を描いた修羅能『重衡』も能の演目として知られています。
- 住みなれし 古き都の 恋しさは 神もむかしに 思ひしるらむ -
(『玉葉和歌集』(勅撰)巻第8 旅歌 平重衡)
---------------------


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門からの山内
大町大路と小町大路が交差する「大町四ツ角」の北西の路地のおくにひっそりと佇みます。
鎌倉観光ではエアポケット的な立地で、鎌倉三十三観音霊場の巡拝者のほかは拝観者は少ない模様です。


【写真 上(左)】 紫陽花と本堂
【写真 下(右)】 本堂
山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、前面中備の十六羅漢と裏面の牡丹の彫刻がみどころとされます。
すこぶる手入れのいきとどいた山内で、小枝ひとつ落ちていません。


【写真 上(左)】 天水鉢
【写真 下(右)】 向拝-1
石畳の参道正面に(おそらく)入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。
いずれもすばらしい仕上がりで見応えがあります。


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
向拝正面桟唐戸のうえに山号扁額で、ムダがなくバランスのよい向拝まわりです。


【写真 上(左)】 御朱印所
【写真 下(右)】 寺号板
御本尊の阿弥陀如来像と両脇侍立像は鎌倉時代前期の作とみられ、一説では運慶の作ともいわれる名作で県重要文化財に指定されています。
鎌倉三十三観音第12番の札所本尊、聖観世音菩薩も本堂内の御座です。
御朱印は本堂脇の御朱印所にて拝受しました。
〔 御本尊・阿弥陀如来の御朱印 〕
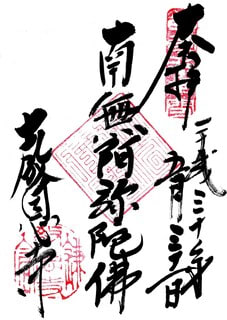
〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

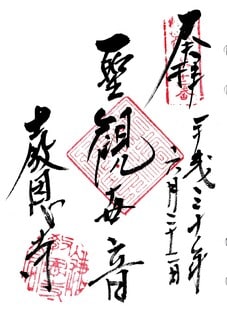
【写真 上(左)】 御朱印帳書入
【写真 下(右)】 専用納経帳書入
●主印は三寶印です。
■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)へつづきます。
【 BGM 】
■ New Frontier - Donald Fagen
■ On And On - Angela Bofill
■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )





