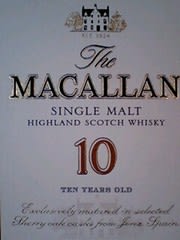宛名のない真っ白な封筒を受け取った。
朝、事務所に着くと、玄関を入る前に郵便受けの新聞を取り出す。新聞の後ろからガサッと地に落ちた封筒。拾って裏返すと、見覚えのある字で『つぼみ』と封がされていた。何の変哲もない真っ白な封筒に、宛名もなければ差出人の名もない。ただ、ほんの少し青みがかった黒いインクで『つぼみ』とだけ、ひらがなで封字されていた。女性だけが使うことができる、そのひらがなの優しげな文 . . . 本文を読む
私はこの空間が好きだ。街中から少しだけ外れた、私設の小さな美術館。受付からは奥まったワンフロアーの展示場は見えない。
もっとも平日の昼間、ここを訪れる人は日に何人あるのだろうか?受付の女性は、受付の衝立の奥のデスクにいる時のほうが多い。来る時は、幅の広い絨毯引きの階段を上がる人を知らせる何かがあるのだろうか、受付で『お待ちしていました』とばかりににこやかに迎えてくれる女性も、帰るときにはその姿をみ . . . 本文を読む
『ミズヲエタサカナ』
ネオンのように頭の中に突然点滅し始めた文字。数回繰り返されるまで、その点滅するカタカナの文字が意図することが分からなかった。
『ミズヲエタサカナ』
『みずをえたさかな』
・・・
『水を得た魚』
なんだ、水を得た魚か。そう思った瞬間に、布団を跳ね除けてベットの上に起き上がった。
ベットにやっと潜り込んだのは何時だっただろう。最後のお客さまが帰って、アルコールで重くなった体を、騙 . . . 本文を読む
誰もいない店に一人佇む。今、夢がひとつ叶おうとしている。絶対に負けるものか、そう思い続けてきた。
ドロップアウトした12年前を思い出す。先が見えない不安と、あいつは・・そう影で言われる声が悔しかった。夢を追いかけようとしただけだった。夢を掴めると信じていた。夢を叶えるために、何を捨てたのだろう。学歴、友情、仲間、そして夢を追いかけることだけに夢中になった。必死に受験勉強に勤しむ学友。そんな中、たっ . . . 本文を読む
少しの待ち時間時間合わせに、暫く顔を出していなかったbarの扉を押した。
「いらっしゃいませ。今日はお一人ですか?」
「ちょっと時間合わせ。マスターに顔を忘れられちゃうんじゃないかと心配になって。」
ドリンクメニューを広げながら、マスターの笑顔にほっとする。
「忘れませんよ。暫くぶりでしたね。」
「そう、少しおとなしくしていたのよ。」
店の奥、ミーティングスペースで数人のグループが楽しそうに宴を . . . 本文を読む
植物園の一番奥に、小さな遊具のスペースがあった。その一角、ペンキの剥げかかった青いブランコが一対、風に小さく揺れていた。
心の隅に引っかかる魚の小骨のような想いが、チクチクといつまでも刺さっている。それはこの繋いでいる手を通して、彼も同じように感じているはずだった。
「ブランコに乗ろう。」
繋いでいる手をひっぱるように、ブランコに向かって歩き出す彼。少し小走りになりながら、私は黙って彼について行っ . . . 本文を読む
「どうした?」
それ以上の言葉がでなかった。彼女の目からあふれ出た涙は、今この瞬間まで堪えてきた想いそのままだった。彼女をゆっくりと抱き寄せ、パーマを当ててないそのままのショートボブに切りそろえた髪を優しく撫ぜた。堰を切ったように、泣き出したその震える肩を、包むことしか今はできそうにもなかった。そして、彼女を胸の中に抱き寄せ、彼女が泣き止むまで車にも戻らず、ボックスの外で彼女の髪をなぜながら抱きし . . . 本文を読む
「マスター代わりましょうか?」
滅多にしないことをすると、傍で見ているとどうやら危なっかしく見えるらしい。
「嫌、いいよ。ゆっくりやるさ。まだ、時間は早いし。」
ロックアイスをそのままゆっくりグラスに合わせて、球状にけずり続けた。
店をあけるか開けないかそんな時間。この店の開店時間に合わせて入ってくるお客さまは滅多ない。遅い時間になり、やっとその日が始まり始めるのが常だ。
いつもは製氷機が落とすア . . . 本文を読む
「間違ってしまったの」
そう、彼女はつぶやいた。それが何のことなのか、その後に彼女が言葉を続けるまでわからなかった。
「私の肌には合わない色をのせてしまったの。一刷毛塗った時に、『あっいけない。』と思ったのだけど、そこから剥がして塗りなおしはできなかった。」
彼女はカップを持つ自分の指先を見ながら、言葉を続けた。彼女の指先を見ながら、そんなことはないのに、と思ったがそれを言葉にすることはまだしなか . . . 本文を読む
今夜はどんな夜になるのだろう、ネクタイの結び目を整えながら、そんなコトを考える。ピンクのワイシャツの襟を直し、スーツの上着を羽織る。
さぁ、一日が始まる。クローゼットの中を片付け、もう一度鏡の中の自分を確認する。店の一番奥にあるクローゼットの扉を閉め、ゆっくりと店の中を見渡しながら、カウンターへと向かう。店、全体のトーンを落とし、背筋を伸ばしてカンウターの中に立つ。
店が一目で見渡せるいつもの場所 . . . 本文を読む
『流水子(るみこ)!』
波の中から私を呼ぶ声がする。真っ暗な闇、打ち寄せる波の音以外何も見えない。腰を下ろしているベンチのような流木は、いつからここにあったのだろうか。こんなにも大きなものを、波は、海は、知らない遠いところから運び、打ち寄せ、ここに置いた。波はその力で、何でも運んでくるのだろうか。それとも何もかもを飲み込んでいくのだろうか。知らない場所から、知らない場所へ、何もかもを運んでいくとい . . . 本文を読む
オーク材の傷だらけのカウンター、手前の丸みを手の腹で包み込むようにしながら、小さく行ったり来たりゆっくりと撫でる。塗り重ねられたニスの剥れが、そのまま色を落ち着かせている。
目の前に置かれた皮のコースター、テイスティンググラスの古びた琥珀色は、その色が褪せる事はない。チェイサーのグラスは、アイスで冷やされカウンター上の止まりかけた時間を含む空気は、そのグラスの肌にぷつぷつと含んだ水分をはじき出させ . . . 本文を読む
乱れていないベットにもたれかかり、カーペットの上でブランケットに包まっていた。体温をブランケットが保護し、自分自身の体温で急に冷え込んできた夜を、そのままやり過ごそうとしていた。ベットに入り込んだら、夢を見そうな気がした。夢の中で、あの人に逢いそうな、逢えそうな気がした。それが怖くて、この冬一番の冷え込みなのに、ベットの中には入り込めないでいた。夢の中でも、もしも逢ってしまったとしたら、今の私は身 . . . 本文を読む
私はいつでも、その人に話かけている。朝起きると、
「おはよう、今日に良い日になるといいわね。お天気はどうかしら?」
食事をしていても、
「このお野菜はとても美味しいわ。何を使っているのかしら?今度まねしてみよう。」
そう、一日に何度も何度も、その人に話かけている。決して返事は返ってこない。
車の中、一人になれる時間。最近気に入っている女性のJAZZボーカリストのCDをかけながら、ふと気が緩みかける . . . 本文を読む
5階から見下ろす夜も更けた街。繁華街からは少しだけずれた、通りに面した古いビル。角に建つビルの作りを活かし、二面の硝子からは、通りの疎らな灯りが、グラスキャンドルを灯したかのように、優しくゆれて見える。室内のトーンを低く落としてある。ガラスを背に設えてあるカウンターからは、振り向かなければ見えないが、数席しかおかれていないテーブルからは、フレームを縁取った、一枚づつのポートレートを掲げているかのよ . . . 本文を読む