
最近の日本の政治家をみると、どうも居直りの感が拭えない。
失言を批判されたり、無知でミスをしても、なぜ悪いのだと居直る。
諸派の事情をよく考え、長い経験から紡ぎ出される発言には、もっと重みがあるものだ。
本当の識者は、軽々に世界一とは言わない。
徒に他者を批判したり罵倒することもしない。
私が以前に書いた文章に次のような段落がある。
何かの参考になれば幸いである。
できれば、今の政治家諸氏に読んでいただきたい。
***
紀元前(きげんぜん)五百年ごろに中国で活躍した、孔子(こうし)という人の教えをまとめた書物がある。その本の名を「論語(ろんご)」という。この本の中に、「知者(ちしゃ)は水を楽しみ、仁者(じんしゃ)は山を楽しむ」という一節がある。知識の豊富な人は、刻々と変わる水のように世の中で機敏に生きることを楽しいと感じる。一方、徳の高い人は、山のようにゆったりとして生きることを好む、という教えである。どちらがよい生き方なのかについて、孔子は答えていないが、どちらかを選ぶという問題ではない気もする。
(中略)
知識は「知る」ことから始まる。知らないから、知ろうとするのである。このことから知恵(ちえ)の源(データベース)ができる。科学の基本も、実はここにある。科学とは、自然の法則を知ろうとすることであり、その得られた知識を活用して人間の暮らしを便利にしていくものが技術である。知識を得た人(知者)が、それを利用したいと思うのは、自然の流れだ。およそ五百万年まえに地球上に誕生した人類にとって、知識こそ進化と生存を可能にした最大の武器であった。
一方、知識を得たことで失ったものもたくさんあった。農林水産業の発達は、自然の動植物を改変させてきた。鉱工業の発展は、自然環境に大きな影響を与えてきた。「変える」ということは「得る」ということだが、その結果、古きよきものを「失う」ことにもなった。現在問題になっている、地球(ちきゅう)温暖化(おんだんか)もそのひとつである。石炭や石油という化石燃料の利用を覚えた人類は、大気中に多大な二酸化炭素を排出してきた。このような、温暖化ガスといわれる気体の増加によって、地球の平均気温は過去百年間に1℃上昇した。二十一世紀中には、最大で4℃上昇するといわれている。「変えた」事に対する、自然の反応である。
人類の進化は、自然との闘いでもあったが、一方、人類は自然の恵みの中で生かされてもきた。それは、「変わらないもの」に対する順応でもある。私たちは自然を可能な限り破壊したくないと思っている。この「変えないこと」は仁者の道である。仁者は、仁徳という教えでもって人や自然と向き合ってきた。仁徳とは、他人に対する思いやりである。思いやりがあれば他人が嫌がることをすることはない。これは相手が自然でも同じである。
(中略)
知ることから始めたいと思う。仁者の心を以(も)って、知者としてふるまおう。知らなければ、目前に迫る危機を回避することはできない。可能な限り多くの情報を得て、最善の方法を考えよう。改めるべきところは改めて、残すべきところは残そう。知ったかぶりはやめよう。目で見て、手で触って、心で感じよう。そういう姿勢が環境問題の解決につながる。
(後略)
***
どういうわけか、この文章が高校生の受験問題集に掲載されている。
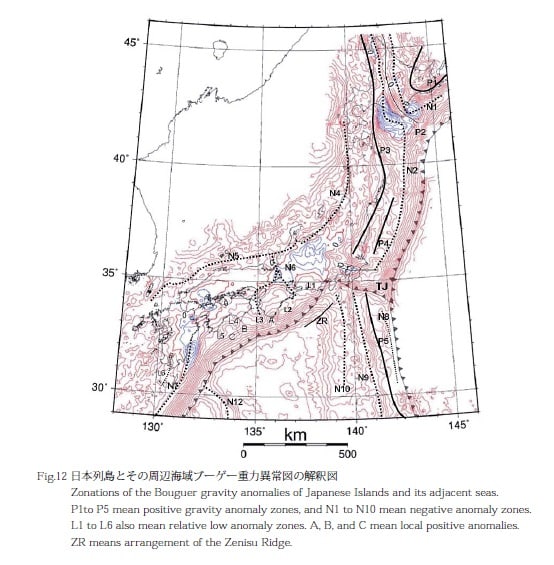












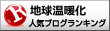


 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken








