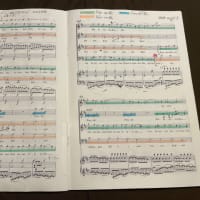●さよなら公演
といってもここから、あと8か月はあるのでしょう 国立劇場
しかし、そもそも、そうはめったに、足を運べる場所でもないですね。
昨日がその、日本最初らしい?国立劇場に入る 最後となるかもしれません。
なのでメモをのこしておきましょう。
お誘いいただいた、れいこちゃん あらためてありがとうございます。
お題目は文楽 国姓爺合戦
でした、 wikipedia でいえば、二段目の途中から三段目のところ
千里が竹虎狩りの段
楼門の段
甘輝館の段
紅流しより獅子が城の段
でした。
すみません、ここまできっちり書いておかないと、絶対にわすれてしまうでしょうから。
これで、文楽鑑賞は何回目でしょうか?
生まれて初めての文楽鑑賞はやはり、中学校時代(いやひょっとしたら高校時代)かと思います。
その程度の記憶ですけどね
やはり、#公教育に感謝 です。
わけもわからずただ騒ぐか、寝てるだけの学生全員に、わざわざ鑑賞教室を開いてくれるのですから
ああ、これは 西宮市 か 兵庫県に感謝でしょうか?
でも、いまとなっては、あのとき
お題目もなにもまったく覚えていませんが、観させてもらえてよかったと思います。
で、今回
そうですね、(古典芸能への)物心がついて、とは
といってもここから、あと8か月はあるのでしょう 国立劇場
しかし、そもそも、そうはめったに、足を運べる場所でもないですね。
昨日がその、日本最初らしい?国立劇場に入る 最後となるかもしれません。
なのでメモをのこしておきましょう。
お誘いいただいた、れいこちゃん あらためてありがとうございます。
お題目は文楽 国姓爺合戦
でした、 wikipedia でいえば、二段目の途中から三段目のところ
千里が竹虎狩りの段
楼門の段
甘輝館の段
紅流しより獅子が城の段
でした。
すみません、ここまできっちり書いておかないと、絶対にわすれてしまうでしょうから。
これで、文楽鑑賞は何回目でしょうか?
生まれて初めての文楽鑑賞はやはり、中学校時代(いやひょっとしたら高校時代)かと思います。
その程度の記憶ですけどね
やはり、#公教育に感謝 です。
わけもわからずただ騒ぐか、寝てるだけの学生全員に、わざわざ鑑賞教室を開いてくれるのですから
ああ、これは 西宮市 か 兵庫県に感謝でしょうか?
でも、いまとなっては、あのとき
お題目もなにもまったく覚えていませんが、観させてもらえてよかったと思います。
で、今回
そうですね、(古典芸能への)物心がついて、とは
いい歳こいて、ですが
ここ5年ぐらいの間では、3回目でしょうか
昨日はうーむ、ちょっと 人間国宝の三味線の音色に
途中で舟をこぎそうになりましたが
結構目を凝らして、演技者の所作を観れたような気がいたします。
しっかり、イヤホンガイドは左耳につけましたけどね。
で、ガイドによる
演技者紹介では、やはり 人間国宝の・・・氏となったら、その方凝視ですけどね
でもまぁせっかくなので、ネタバレ(もなにもないでしょうが)印象にのこる演技者を書き残しておきますわ
人形役割は 鄭芝龍老一官の妻 吉田和生さん
なんでしょう・・・もう 吉田さんそのものが 妻というか母に見えました
切語りは 六代目竹本錣太夫さん
長い・・・甘輝館の段 すごいエネルギー 脇にお弟子さん?がいらしたけれど、大丈夫だったのでしょうか?
三味線 鶴澤清治さん
聴きほれて寝ている場合ではありませんな・・・もう少し見ておくべきでした・・・
という感じです
そうそう 竹本織太夫 のあの 甘輝の高笑いの長々は あれはああいうものなのでしょうか?
んん? 結構真剣にみていたでしょう?
なんでしょうかね
やはり、年相応というものがあるのでしょうか?
それとも 祖母や父が お謡い をやっていたというのも影響があるのでしょうか?
これからもう少し、文楽の世界も勉強したいと思いました。
うーむ、やりたいこといっぱいあるな・・・ 仕事じゃなくて・・・笑
ここ5年ぐらいの間では、3回目でしょうか
昨日はうーむ、ちょっと 人間国宝の三味線の音色に
途中で舟をこぎそうになりましたが
結構目を凝らして、演技者の所作を観れたような気がいたします。
しっかり、イヤホンガイドは左耳につけましたけどね。
で、ガイドによる
演技者紹介では、やはり 人間国宝の・・・氏となったら、その方凝視ですけどね
でもまぁせっかくなので、ネタバレ(もなにもないでしょうが)印象にのこる演技者を書き残しておきますわ
人形役割は 鄭芝龍老一官の妻 吉田和生さん
なんでしょう・・・もう 吉田さんそのものが 妻というか母に見えました
切語りは 六代目竹本錣太夫さん
長い・・・甘輝館の段 すごいエネルギー 脇にお弟子さん?がいらしたけれど、大丈夫だったのでしょうか?
三味線 鶴澤清治さん
聴きほれて寝ている場合ではありませんな・・・もう少し見ておくべきでした・・・
という感じです
そうそう 竹本織太夫 のあの 甘輝の高笑いの長々は あれはああいうものなのでしょうか?
んん? 結構真剣にみていたでしょう?
なんでしょうかね
やはり、年相応というものがあるのでしょうか?
それとも 祖母や父が お謡い をやっていたというのも影響があるのでしょうか?
これからもう少し、文楽の世界も勉強したいと思いました。
うーむ、やりたいこといっぱいあるな・・・ 仕事じゃなくて・・・笑