朝から☂、昼食を丸亀製麺で食べていると電話があり
捕れたての小エビと舌平目3匹を頂けるという事で、さっそくもらいに行き
たくさんある小エビは近所さんたちに分けました。
我が家の夕食は舌平目のムニエルと、エビのかき揚げでした。
から揚げにしても香ばしくて美味しかったのですが、主人は天ぷら希望でした。
新鮮でとても美味しかったです。ありがとございました。

ショーの着付け依頼がきっかけで久しぶりに
引き抜き結びの角出しや袋帯の銀座結びを練習しました。
何時も帯は、すべて折り上げの仮紐で行なっていますので
引き抜きの角出しで久しぶりに帯を結びましたわ(^-^;
普段結び慣れていないので、ちょっぴり緊張いたしました。
普通は角だしは、昼夜帯や踊り帯、全通でするとやり易いのですが
情報は袋帯とお聞きしているので、六通の袋帯で行いました。
ですから手先の長さは、柄止まりが中心より10センチほど右になるようにして結びました。(軽く結びます)
引き抜き結びをすると、六通柄の帯は垂は裏になりますが
ひっくり返して表が出る様に引き抜きます。
垂が綺麗に出たら、もう一度締めます。

手先と垂れ元で結びます。
帯びによって手先の柄が長いものは、結ぶと蝶々なって、左右とも輪になります。

垂を表にすると、お太鼓の所は裏になるので
もう一度ここで綺麗にひっくり返し、表が出るようにします。

お太鼓の所の布目を通し、ガーゼに薄いタオルを折ったものを枕にして背中に付けます。


帯び締めを使わない角出しの出来上がりです。
お太鼓の決め線がすこーし▽になります。
時代劇によく出てきますよね。
引き抜きにすると、上下のあるものは、お太鼓部分が逆さまになるのがデメリットですね。


下の写真は、六通柄の銀座結び(角だし)です。
帯び締めを使うので、垂に決め線が綺麗ですね。

昼夜帯を使った、袋帯の銀座結び(角だし)です。
折り上げ方式です。
仮紐で押さえたところに手先を折り返して乗せます。(そこを仮紐で押さえても結構です。)
次は垂を先に決めて仮紐で押させても結構ですが、私はお太鼓の山と垂を同時に決めます。
垂の長さは、ヒップの一番高いところに合わせます。
お太鼓の位置は、仮紐の位置から広げて、二重にし
約16・7センチぐらいの所で山を作ります。
年齢によって下に膨らみを出したいときは、約20センチぐらいのところを山にします。


帯び締めを輪の中に入れ
お太鼓の決め線より、6,7センチ長めにし帯締めを置きます。

残りを畳んでいきます。
垂れ先も長めに決めます。


何時もの位置までたくし上げると、ふくらみが出来ます。
体型によってお太鼓の大きさは調整します。


帯び締めを使う銀座結びにした方が、格好いいような気がしますわ。
本日も訪問ありがとうございます
応援クリックもよろしくお願い致します













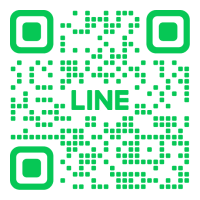













(*^^*)
タレの余りは、前結びの時も、折りたたんでいます(*^^*)
折りたたみは、調整がし易いのでラクですネ♪
ぜひ折り上げで試してくださいね。
私は殆ど、折り上げ方式です。
結ばないから結構、楽です。(^_-)-☆