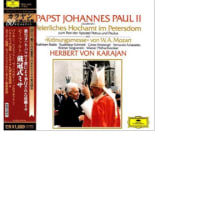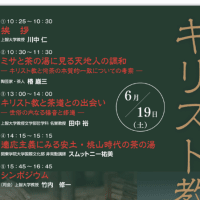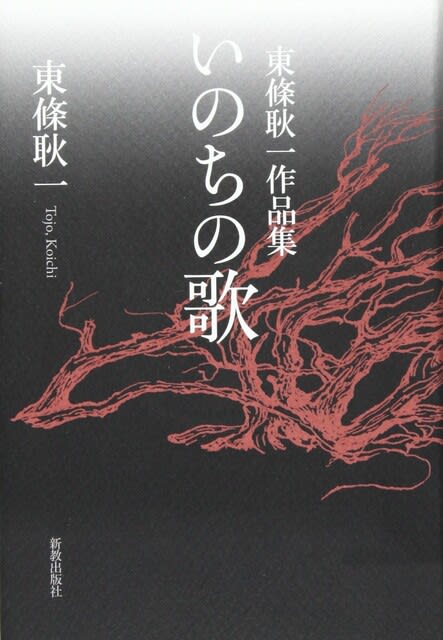
自己物語りと救済ー明石海人、北條民雄、東條耿一の生と死ー
(そのⅠ)
以下の文は、『彼方からの声』(シリーズ物語り論』(東京大学出版会、2007年)に寄稿した『復生の文学』および『東條耿一作品集 いのちの歌』(新教出版社、2009年)の解題に書いたことの再録である。内容は15年以上前に書かれたものであるが、現在の私から見た、いくつか新しい感想も追加した。東條耿一と岩下荘一の関係など、その後あきらかになったこともあるので、適当な機会にそれについても書く予定である。
明石海人と北條民雄の名前は戦前の「療養所文学」の代表的作家としてよく知られているが、東條耿一についてはよく知らないという人が多いかもしれない。
東條耿一は、戦前のハンセン病療養所、多磨全生園の文芸誌「山桜」に数々の優れた詩を発表していた詩人である。その彼が、晩年にみずからの生涯を回想しつ つ カトリックのキリスト者としての心境を綴った手記を書き残していたことを知ったのは平成十六年の春のことであった。 四谷の聖三木図書館の書棚の奥にあった「聲」の昭和一六年のバックナンバ ーに「癩者の父」に始まる東條耿一の一連の手記が掲載されていたのである。
私は、その内容に深く突き動かされた。それは、戦後間もない 頃に書かれた「長崎の鐘」 や「亡びぬものを」のような永井隆博士の手記が、すこしも古びることのない 時代の人の証言であるのと同じように、 ハンセン病が「不治の病」として恐怖されてい た苦難の時代を生きた一詩人の回心の記録であったからである。
それから五年の間、 東條の詩作品の素晴らしさを教えて頂いた俳人の村井澄枝氏とともに、 私は、東條耿一の全著作の編集に取りかかった。途中から、戦後の全生園の園誌「多磨」の編集長を務められ、北条民雄について優れた評論を書かれた野谷寛三氏にも加わって頂き、平成二十一年九月四日に東條耿一作品集「いのちの歌」 の出版を果たすことが出来たのである。
ハンセン病については、隔離政策の持つ 差別と人権侵害の問題が、国賠法訴訟で問題となっ た。これについては多くの人が語ってきた。それは、たしかに重大な社会的・ 政治的問題であるが、差別の撤廃も人権の回復も、我々が生き延びること、我々の「生」を前提としている。 しかし、 生きる希望が全く奪われ、苦痛と死が不可避であるような極限的な状況というものがある。 そういう場合、人は、人権の問題を問う以前に、そうい う苦しみに満ちた現実をどのように受容し、 その苦しみの果てにある不可避の「死」 をどのように迎えるかという、より根本的な問題に直面せざるを得ないのである。
ここで論じた明石海人、北條民雄、東條格一の生涯とその作品を理解するためには、 その日本各地にハンセン病の療養所が置かれていた時代の背景、当時の療養所の実態、 当時のカトリッ ク教会と療養所との関わりなどについて、 ある程度の予備知識を持つ ことが必要ではある。 しかし、筆者は、彼らをいわゆる「療養所文学」 ないしは「ハンセン病文学」の作者として論じるつもりはない 。その理由は、 こういう名称は、それ自身差別的であるし、 彼等の書いたものは、そういう特殊なカテゴリーを越える普遍性を持っていると信じてい るからである。ハンセン病が治癒可能な普通の病気になった現在に於いても、 治癒不可能な他の難病は存在するし、 今後もそういう難病に苦しむ人は絶えないであろう。不幸にして、 そういう病に自己自身が、あるいは自分の家族、ないし自分に親しい人が罹患したとき、ひとはどうするのか。
それは、 いつの時代にも人間が直面しなければならない問題である。 明石海人の短歌集「白描」とその序文、北條民雄の『いのちの初夜』や川端康成との往復書簡、東條耿一の詩集と晩年の手記などは、すべての人に通じる「いのち」 の根柢にある苦しみ、 死に至る病の苦しみの現実と格闘し、そこからの救済を求めた魂の記録である。彼らは、文藝の創作活動によって、あるいはキリスト教の信仰によって、古き自己を乗り越えようとした。闇の中に光明を、 絶望の中に希望を見出した明石海人や東條耿一の自己物語りは、それを読む者自身が、他人事ではなく自己自身の問題として生と死の問題を自覚する手がかりになるだろう。すくなくとも私は、若くして帰天したこれ等の作家から、古稀を過ぎた現在の私自身が学ぶことができることを有り難く思っている。
(1)短歌―明石海人「白描」について
昭和十二年に改造社が明治・大正・昭和三代にわたる新万葉集全十一巻を企画したときに、一人二十首以内で公募があった。昭和十三年に出版されたその第一巻に、ハンセン病療養所長島愛生園の明石海人の歌が十一首入選している。
皇太后陛下、癩患者御慰めの御歌並びにお手許金御下賜記念の日、遙かに大宮御所を拝して
そのかみの悲田施薬のおん后今も坐すかとをろがみまつる
みめぐみは言はまくかしこ日の本の癩者に生れて我が悔ゆるなし
父の訃、子の訃共に事過ぎて月余の後に来る。帰り葬はむよすがもなくて
送りこし父がかたみの綿衣さながら我に合ふがすべなさ
童わが茅花ぬきてし墓どころその草丘に吾子はねむらむ
世の常の父子なりせばこころゆく嘆きもあらむかかる際にも
たまたまに逢ひ見る兄や在りし日の父さながらのものの言ひさま(面会)
梨の実の青き野径に遊びてしその翌の日を別れきにけり
子を守りて終らむといふ妻が言身には沁みつつなぐさまなくに
監房に狂ひののしる人のこゑ夜深く覚めて聞くその声を (病友)
眼神経痛頻りに至る。旬日の後眼帯をはづせば視力すでになし
拭へども拭へども去らぬ眼のくもり物言ひかけて声を呑みたり
更へなずむ盗汗の衣やこの真夜を恋へばはてなしははそはの母よ
この第一首と第二首は、救癩事業を推進した皇太后の御恩に感謝する歌で、当時の療養所の短歌会では毎年のように兼題として出されていた。貞明皇太后は、昭和7年11月10日、大宮御所の歌会で、「癩患者をなぐさめて」という兼題をだし、自ら
つれづれの友となりても慰めよ ゆくこと難きわれにかはりて
という歌を詠んでいた。海人の歌は、この皇太后の歌に対する返歌であると見て良い。
この歌は発表当時評判となり、のちに長島愛生園の歌碑にも刻まれ、また当時の国の救癩政策の柱であった「皇室の仁慈」にいかに療養所の人々が感謝しているかを示すために縷々利用されることとなった。戦後は、その反動であろうか、「幻の明石海人」という評論を書いた光岡良二も「慟哭の歌人」を書いた松村好之も、ともに、晩年の海人の歌を代筆した伊郷芳紀の証言を引用しつつ、この歌の「儀礼的性格」を強調し、海人の代表作とは見なしていない。たしかに、海人自身が編集した「白描」では、この歌は療養所の生活を綴った多くの歌の中の一つとして扱われ、特別に巻頭に於かれているわけではない。
しかしながら、戦前戦後のイデオロギーや価値観の劇的変化なるものを括弧に入れて、この歌自体を眺めてみると、単なる「儀礼の歌」として片づけられないものがある。皇太后からの「御恵み」を感謝する返歌は療養所の歌人達によって数多く詠まれているが、海人のように「癩者に生れて我が悔ゆるなし」と力強い「万葉調」で堂々と言い切った歌は殆ど無い。これは皇室の恩恵をひたすら受動的に有難がっているような感謝の歌では決してない。この下の句は、返歌という儀礼を超えて、海人自身が自分の運命を積極的に受容した宣言のように思われる。海人は、のちに、歌集「白描」の序文で、
癩は天刑である。
加はる笞(しもと)の一つ一つに、嗚咽し慟哭しあるひは呻吟しながら、私は苦患の闇をかき捜って一縷の光を渇き求めた。
― 深海に生きる魚族のように、自らが燃えなければ何處にも光はない ―
さう感じ得たのは病がすでに膏肓に入ってからであった。
齢三十を超えて短歌を学び、あらためて己れを見、人を見、山川草木を見るに及んで、己が棲む大地の如何に美しく、また厳しいかを身をもって感じ、積年の苦渋をその一首一首に放射して時には流涕し時には抃舞(べんぶ)しながら、肉身に生きる己れを祝福した。人の世を脱れて人の世を知り、骨肉と離れて愛を信じ、明を失っては内にひらく青山白雲をも見た。
癩はまた天啓でもあった。
と書いたが、「癩者に生れて我が悔ゆるなし」という大胆な言葉を海人に言わせたものは、皇室であれ誰であれ、他者から与えられた恩恵への感謝という以前に、それに絶対的に先行していた、「自らが燃えなければ何處にも光はない」という海人自身の魂の奥底からの叫びであったろう。
昭和一二年に改造社によって企画され、昭和一三年に第一巻が出版された新万葉集は、明治大正昭和の代表的な短歌を収録している。審査員と当時まだ活躍していた著名な歌人には新たに五〇首以内の自薦歌の投稿が求められ、物故した歌人のよく知られた歌も縁故者によって提出された。
明石海人の歌は、第一巻に収録されている。この巻に収録された他の歌人の歌をあげると、石川啄木は、「東海の小島の磯の白砂に我なきぬれて蟹とたはむる」をはじめとする五十首、伊藤左千夫は「牛飼が歌よむときに世の中の新しき歌大いに起こる」をはじめとする五十首がある。また、歌人とは言えないが、芥川龍之介の短歌も収録されているなど、プロの歌人に留まらず、様々な職業や背景を持った人が、それぞれの自己の世界を表現している。この歌集の特徴は、作者ごとに複数の短歌が収録されているので、新万葉集という大宇宙の中に、一人一人の作者の小宇宙があるというような印象を受ける。
ただし、いわゆる有名歌人の歌の織りなす小宇宙は、かならずしも生彩があるとは言えない。たしかに一首一首は人口に膾炙した歌であるが、五〇首を並べてみても、そのあいだに作者の人格から放射するような統一性を必ずしも感じない。これは、とくに新作を投稿した有名歌人の連作についていえる。
新万葉集の聊か精彩を欠く職業歌人の歌群のなかにあって、海人の連作短歌のなかには、はるかに切実にして緊密な統一がある。これは、海人が最晩年に出版した歌集「白描」の場合は、さらにはっきりと言えることであるが、何度も推敲し磨き上げられた作品のみが持つ統一が、作者の個の一貫性がつよくでている。海人の短歌には叙事詩的な情念のうねりがあり、それが読むものに地底から響くような情念のカタルシスを与える。これまで、日本の歌人で、このような、すぐれた悲劇作品のみが持ちうるようなカタルシスと存在の真実を詠い得た歌人、「白描」序文に見られるような自己自身への思索と詩的世界を統一した歌人がどれほどいたであろうか。 「白描」は、次の歌から始められている。
医師の眼の穏(おだし)きを趁(お)ふ窓の空消え光りつつ花の散り交ふ
春たけなわの頃、自然が生命力に満ちあふれ、桜の花の美しさに惹かれて大勢の人が行楽にくりだす季節に、海人は東大病院で診察を受け、医者の穏やかな眼を追いながら診断の結果を聴く、そのつかの間を捉えた歌である。この歌が「白描」の巻頭。そして、この歌を口述筆記した伊郷芳紀の回想に寄れば、この歌の姿を定めるのを海人は最後まで引き延ばしていたとのこと。「歌集」の最初におかれた歌は、実は、最後にそのかたちを与えられたのである。
「不治の病」という宣告を受けたとき、これから自分はどのようにすればよいのか。どうしようもないではないか。海人の短歌に頻出する「すべなさ」(どうしようもなさ)ということばに象徴される運命的な事実がはっきりと告げられる、その直前の光景である。これに続く歌との関わりだけを見れば、いかにも人生の無常、不条理、真昼の花の輝きの中に突如侵入した暗黒を描くための序奏のようにもみえるが、この歌は、決してそのような側面だけから見られるべきものでない。
この巻頭の歌は、「癩者」としての彼の生の始まりを意味するだけでなく、「白描」におさめられたすべての歌を、その生の始まる直前の一点に収斂させるような働きを持っている。そういう自分自身の過去の一瞬を回想において遡りつつ描き出そうとしている海人自身は、どういう状況にあったか。彼を診断し、喉の切開手術を担当した内田守医師の言葉によれば、「およそ癩者が死ぬまでに経験しなければならない一切の苦しみを引き受けている」凄絶な状態にあったとのこと。カニューレ(呼吸補助のため喉につっこんで使用する器具)をとおしてかすかに判別されるような嗄れた声で、最後の力を振り絞りながら、伊郷に口述していたのが、この歌である。
伊郷によると、「白描」の歌をまとめあげ、原稿の発送の間際まで、海人は巻頭歌の下の句を「消え光りつつ花の散り交ふ」にするか「さくら白花真日にかがよふ」にするか、決めかねていたが、次のように云って、前者に決定したとのことである(松村好之著「慟哭の歌人」による)。 伊郷が伝える海人の言葉は以下のようなものであった。
「さくら白花真日にかがよふ」では真日にかがよふているにしても、花がじっと停止して日光を受けている、いわば静の風景だ。「消えひかりつつ花の散り交ふ」だったら、花は生きて爛漫と咲き、やがて生命を終えて散ってゆく・・・・散り交ふ花びらに生きた感情の生動を実感する。「散り交ふ」に決めよう。
散る桜に、単なる無常ではなく、存在と生命の充足による死を彼が見ていたことがこの言葉から分かる。「花」は日本の和歌の伝統では特別の意味を持っている。西行の和歌にとってそれは日本の風土、そこにいきる人々の心のあり方の象徴でもある。本居宣長の云う大和心もしかり。海人には桜の花を詠んだ次の歌もある。
さくら花かつ散る今日の夕ぐれを幾世の底より鐘のなりくる
長島愛生園をついの住処と思い定め、ハンセン病者としてその地で生を終えることを受容しなければならない境遇にありながらも、春になれば、日本の自然の美しさを見、日本の悠久の歴史に思いを馳せることができる。そういうとき、桜の花を詠んだ幾世代もの日本人の心を自分自身のうちに実感することがあったであろう。この歌は、海人の故郷、沼津の千本松原に歌碑として刻まれている。「幾世の底より」という言葉が、この歌に日本文化の基底を流れる桜花への想いを感じさせる。幾世の「世」は、悠久の歴史を表すが、その「底」という言葉は、地底より響き渡るような日本文化の深層を感じさせる。