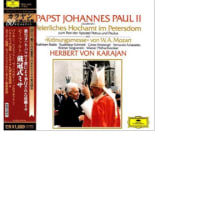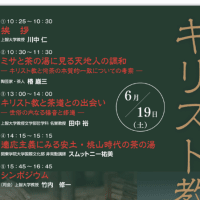鞭の下の歌これは昭和12年の「山桜」に、1936年作品集として発表されたもの。この昭和12年は東條が次から次へと詩を創作していた時期で、この作品の後では、「夕雲物語」などの散文詩が続く。「鞭の下の歌」は、旧約聖書の詩編作者やヨブ記の主人公に自己自身を重ねた歌である。不条理な苦しみにあえぐ魂の渇き、すべてを支配しているはずの全能の父にむかって、捨て身で「何故に?」と問う。
ちちよ ちちよ
いかなればかくも激しく 狂ほしく
はた切なしく われのみを打ちたまふや
飛び来る鞭のきびしきに耐え兼ね
暗き水面の只中を泳ぎ悶轉(まろ)べど
石塊(いしくれ)の重き袖は沈み 裳裾は蛇の如く足に絡みて
はや濁水はわれを呑まんとす
おお わがちちよ
なにとて おん身 われを殺さむとするぞ
死にたくはなし! 死にたくはなし!
卑しく 空しく いはれなき汚辱の下に死にたくはなし!
好みてかくも醜く 病みさらばへるにあらざるを
おん身の打ち振ふ 鞭は鳴り
鞭はとどろき
ああ 遂に--
鼻はちぎれ 額は裂けて血を噴けり
おおされどわれ死なじ 断じて死なじ!
たとへ鞭の手あらくなりまさり 濁水力を殺げど
おん身の心やはらぎ 憐情に飢ゆる時までは
おおその時までは 血を吐き 悶絶すとも
おん身の足下に われ泳がん 泳ぎて行かん。
伴侶
義足よ つれづれの孤独の伴侶(とも) 私に力を借せよかし
人生(ひとのよ)の片影 そを安らかに歩むより 私に想望(おも)ふ事もなし
いまこそ疵も癒ゆたれば お前に学び 歩きたい
向ひの病室 あちらの花芥 凧(いかのぼり)の泳ぐ芝平ら
旧約聖書ヨブ記 9:30-35に次のくだりがある。
雪解け水でからだを洗い/灰汁で手を清めても/あなたはわたしを汚物の中に沈め/着ているものさえわたしにはいとわしい。/このように、人間ともいえないような者だが/わたしはなお、あの方に言い返したい。あの方と共に裁きの座に出ることができるなら/あの方とわたしの間を調停してくれる者/仲裁する者がいるなら/わたしの上からあの方の杖を/取り払ってくれるものがあるなら/その時には、あの方の怒りに脅かされることなく/恐れることなくわたしは宣言するだろう/わたしは正当に扱われていない、と。ここには、神から受けた仕打ちが不当であると宣言するヨブの言葉が記されている。この「あの方とわたしの間を調停してくれる者 仲裁する者がいるなら わたしの上からあの方の杖を 取り払ってくれるもの」を、キリスト教徒は、子なる神=キリスト を指し示す言葉と解釈した。神自身が、アガペー(あわれみ)となって我等の間に使わされるまで、というようにヨブの「旧約の神への抗議の声」を解釈したのである。こういうヨブ記の読み方が背景にあって、はじめて、「憐れみに飢えるとき」という詩句が生きてくる。人間が苦しむとき、神も又苦しむ、高き處から慈悲をたれるのではなく、神自ら、「憐れみに飢える」時が来る、つまり、みづから人間に代わって、人間の苦しみを引き受けるはずだ、そうでなければならない。
おん身の心やはらぎ 憐情に飢ゆる時まではこの詩があからさまに詠んでいるのは「嘆き」であり、やるすべもなき「苦しみ」である。しかし、決して、そういう嘆きや苦しみそのものが主題なのではない。作者が知りたいのは、その苦しみの意味なのである。意味への問いに答えが得られるまで、決してこの世を否定せずに生き続けようと言う作者の決意がある。「伴侶」 という詩は、この「鞭の下の歌」の次に置かれた詩である。耐えがたい苦痛がしずまり、作者に平安が訪れる。そのときに、作者は、感謝を込めて「義足」にむかって「伴侶」と呼びかけている。義足はたしかに作者の歩行を助けますから、伴侶と呼ぶにふさわしい物であるが、實は義足に限らず、作者は自分の日常生活を成立させているあらゆるものに向かって、「伴侶」と呼びかけているように感じられる。盲目となり歩行も困難であっても、それを手助けしてくれる物から学び、感謝する心がうまれたことは、その直前の歌が一種のカタルシスとして働き、そのあとに作者の心に平安が与えられたことを示している。
おおその時までは 血を吐き 悶絶すとも
おん身の足下に われ泳がん 泳ぎて行かん。