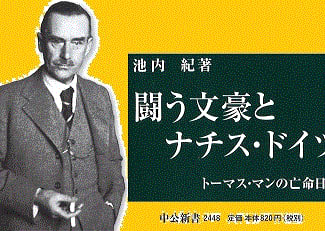
トーマス・マンはブルジョア教養人だから、すぐ、ナチスのいかがわしさにすぐ気づいた。しかし、同時代の一般のドイツ人にはむずかしかったのではと思う。
現在、ヒトラーやナチスへの非難は、かれらが自滅してから、悪口として書かれている。だから、それを読んで、ヒトラーやナチスが悪者だと思うことは容易だ。しかし、それは、たんに悪口を信じたというだけである。
ヒトラーやナチスの唱えた国民社会主義とは、国民共同体(Volksgemeinschaft)の実現を求める政治運動である。特権階級の廃止、ドイツ国民の平等化、ドイツ民族の一体化を唱えたのである。
ウィキペディアの英語版をみると、共産主義は2000年前にさかのぼり、貴族の特権の廃止、私的所有の廃止、平等社会の実現を唱えていたという。この古典的共産主義は、理念上、共同体運動とほとんど変わらないように私には思える。
エンゲルスが、『空想から科学へ』(新日本出版社)で、ユートピア共産主義と科学的共産主義との違いとして、主張したのは、生産手段の国有化であった。これでは、国民共同体運動と区別がつかない。
レーニンが、真の共産主義として持ち出したのは国際主義である。ほとんどの共同体運動の欠点は「排他的」になることである。たしかに、ナチスはユダヤ人の排除をはかった。「排他的」にならないことは大事な視点である。
しかし、レーニンは、同時に、プロレタリアート独裁という誤りの芽を持ち込んだ。
もっと大事な視点は、「自由」と「個人の尊重」ではないかと私は思う。
トラヴェルソが『全体主義』(平凡社新書)で指摘したように、古典的自由主義はブルジョアと貴族が主張したものだが、「分権、複数政党、公的機関、憲法による個人的権利の保障(表現の自由、信教の自由、居住地の自由など)」は、権力の集中を防ぐために、現実的に必要なのだ。
したがって、フロムが『自由からの逃走』(東京創元社)で示した視点を私は支持する。
「支配―服従」の人間関係を廃止するために、ヒトラーに服従するという思考はおかしいのである。救世主を求める思考はおかしいのである。天皇もいらないのである。
そのうえで、伝統的な共同体思想の「助け合い」「弱者への思いやり」を「自由」と「個人の尊重」と共存させないといけないと思う。









