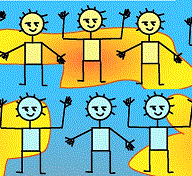
ひさしぶりに、エーリッヒ・フロムの『自由からの逃走』(東京創元社)を読む。同じ本を何度も読む場合、読み切らないといけないという強迫観念がないので、細部を楽しむことができる。著者の論旨がどうでも良くなっている自分がいる。
フロムは自己卑下する感情は、怒りを人にぶつけることができないので、怒りが自分に向かった状態であると言う。私も自己否定に反対である。
私の学生時代には学園闘争なるモノがあり、「自己否定」を唱える集団があったが、権力者でもないものが「自己否定」しても何もいいことはない。うつの人を相手にするようになって、私はそう思うようになった。
「自己否定」は自我崩壊にいたる危険がある。そこまでいたらなくても、カリスマに絶対服従するようになる危険がある。
フロムは、また、「自由」というモノは、「個人」というものが存在してはじめて問題となるものだという。
ドストエフスキーは、小説の『カラマーゾフの兄弟』のなかで、無責任にも自由という考えを民衆に吹き込んだ、と大審問官にイエスを長々と責めさせる。
「何が善で何が悪かは、自分の自由な心によって判断していかなくてはならなくなった。」
「人間にとって、良心の自由にまさる魅惑的なものはないが、しかしこれほど苦しいものもまたない。」
「人間にとっては、善悪を自由に認識できることより、安らぎや、むしろ死のほうが、大事だということを。」
「選択の自由という恐ろしい重荷におしひしがれた人間が、ついにはお前の姿もしりぞけ、おまえの真実にも異議を唱えるようになるということを。」
しかし、新約聖書に4つの福音書があるが、どれにもそんな「自由」をイエスはのべていない。
ドストエフスキーが、大審問官の姿を借りて、怒りを述べているのは、近代的自我からくるものである。この近代的自我とは、自分を個人として意識することである。自分は他人と違う、他人の判断に頼ることができない、自分で自分の未来を選択しないといけない、と思うことである。
いっぽう、社会が身分社会でも、自分の身分を越えたことを欲することがなければ、「自由」があった、とフロムは言う。16世紀のブリューゲルの絵をみると、農民が楽しそうにお祭りに酔いしれ、また、卑猥なことにふけり、ルター派やカルヴァン派の教会の教えを無視している。
萩生田光一文部科学相が10月24日、テレビ番組で「(英語民間試験は)自分の身の丈に合わせて頑張ってもらえば」と言ったのは、この考えで、他人と自分は身分が違うのだ、と思えといっているのだ。
萩生田光一の発言に同意するひとは、近代的自我を持ち合わせていない。そういう人は、権力者に絶対服従し、そうでない人を非難するようになる危険をひめている。
東京創元社の『自由からの逃走』は日高六郎の訳だが、誤訳がけっこうある。そのなかで今回、気になったのは、彼は“individuality”を「個性」と、“individuation”を「個性化」と訳していることだ。
英和辞典を引けば、たしかに、そういう訳を最初にかかげているが、本書ではそういう意味ではない。フロムは“individuality”を「個人であること」、“individuation”を「個人であると意識すること」の意味で使っている。第1章、第2章の、人間の心理と自由についての関連の分析を読めば、フロムはそういう意味で使っていることは明らかだ。
もっとはっきりするのは、第2章の“a ten-year-old child’s sudden awareness of its own individuality”である。「自分の個性に目覚める」のではなく、「自分が個人であることに気づく」である。10歳の女の子が、自分が自分であることに気づき、急に自分をいとしく、また、誇らしく感じたことを言っているのであって、何か、自分の特性に気づいたことではない。
他人が自分と違うことは、いずれ、わかることである。それでも、他人に優しくあるには、「自分をいとしく、また、誇らしく」感じられることである。
ゆめゆめ、「自己否定」をしてはいけないし、他人にそれを求めてはいけない。









