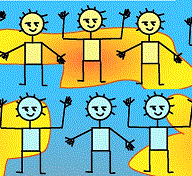
きょうの朝日新聞《オピニオン》にインタビュー記事『なぜ叱ってしまうのか』がのっていた。答えるのは臨床心理士の村中直人である。
記者は「ほめて育てたいのに、叱ってしまう。叱っているうちに、だんだん止まらなくなってしまう」と問う。
村中は「お子さんを叱るのは、どんなときですか」と聞き返す。
記者は「約束の時間になっても宿題を始めないときとか、親に口答えしたときとか……」と答える。
村中は「心の奥では、子どもが自分の言葉に反応し、思い通りに動いてほしいと思っていませんか?」と核心を突く。
人を叱るとは人を支配しようということである。人を支配しようと思わなければ叱ることもない。親子の間だけでなく、上司と部下のあいだでも起きることである。
村中は優しい人なのか、「処罰感情は生まれながらに持っている欲求です」「叱ることへの依存は心の病だと言っているのではありません」と言う。
確かに、社会事件が起きると厳しい処罰を求める声がネットをにぎやかす。しかし、私は処罰感情は生まれながらの欲求だと思わない。私にはそういう欲求はないし、昔からなかった。「叱る」という行為は伝染病のようなものだと思う。ひどく叱られたとき、それに十分な免疫(あるいはレジリエンス)がなければ、弱いものを叱ろうとする心が植え付けられる。
記者の「宿題を始めない」「親に口答えをした」は、少しも叱る理由にならない。叱らなくても、すべきことは、いずれ、なされる。しかし、宿題はしなくても良いのである。先生にそんな権威はない。私は宿題を無視したが、昔の学校の先生は私を愛すだけの寛容な心を持っていた。日本が戦争に負けて得た「民主化」のおかげである。
私は両親に叱られることはほとんどなかった。2度だけ叱られた記憶があるが。
一度目は、私が小学校に行く前のこと、幼稚園に通わなかったので、ほかの子と遊んだことがなかった。親はそれを心配して、町内の男の子たちの集まりに私を連れていった。その子たちは、私を連れて、近所の九谷焼の店に行き、石を投げた。私は何が起きたかわからず、ひとり、その場に立ち尽くした。私は、店の親父に親もとへ連れて行かれて、叱られた。ハッキリ言ってなぜ叱られるのかわからなかった。石を投げたのは通りの向かいの町会長の息子である。しかし、それ以来、町内の男の子たちと遊ばないで済んだ。
二度目は、小学校の高学年のとき、兄に命令されて、2階に上がってくる父を、物干し竿で突いた。なぜそうなったのか思い出せないが、軽い気持ちでついたのである。父親は怒って一声何か言った。その言葉は今は思い出せない。
会社にいたとき、私は会社の上下のある人間関係が理解できなかった。座り心地の良い椅子があったので、自分の椅子と交換したら、部長の座る椅子だと文句を言われた。また、だれでもできる退屈な仕事を与えられるのが、とても不満であった。そんなことがあって、入ってきた新入社員が可哀そうに思うようになり、すぐに友達になっていた。会社で叱った覚えはない。叱る必要性もない。また、私は自分に自信があったので、叱られても平気であった。
いま、「発達障害」や「うつ」の子の指導をNPOで行っているが、「叱る」必要性を感じたことはない。べつに「ほめる」ことを意識しているわけではないが、子どもをひとりの人間としてみれば、その能力に心動かされることが多くある。そのとき、「すごいね」という言葉がひとりでに出てくる。私がそうしていると周りのスタッフもそうやって子どもたちの指導するようになる。
私は、これを「愛も伝染する」とみている。カラスやサルだけでなく、人間も他の人を見て学ぶのである。だから、いずれ、叱ることない社会が来るかもしれない。



















