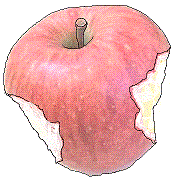ニーチェの『この人を見よ』(光文社古典新訳文庫)に続いて、『善悪の彼岸』を読んだ。岩波文庫の木場深定の訳と光文社古典新訳文庫の中山元の訳と、ネット上のドイツ語原文を合わせて読む。
理由は、最初に取り寄せた木場深定の訳が重く、わかりにくかったからだ。木場の訳は、漢字に凝り、やたらと常用外漢字を使うし、漢字を2字組み合わせ、造語する。
中山元の訳はわかりやすいが、原文にない余計な語句を追加する。かなりの頻度で、木場訳と中山訳は相反する。多くの場合は、中山の読みが正しいが、明らかに中山が間違っている場合もあった。
翻訳のむずかしさを感じる。言語は互いに翻訳可能とするのは幻想である。
しかも、ニーチェ自身が混乱しているし、現代の私たちと異なった言葉使いをしている。ニーチェは古典文献学者で、時代の世界の思想の流れにそっぽを向いている。
ニーチェは、断章14で次のように言う。
「物理学はそれなりに眼と指とをもち、それなりに明白さと平易さとをもっている。」(木場訳)
この「物理学」は、Physikの訳である。ニーチェは、「自然科学」をPhysikと呼んでいる。カントと同じ言葉使いである。
ここで、ニーチェは言葉遊びをしている。自然科学には、目(Augen)と指(Finger)があるから、直接見ること(Augenschein)ができ、直接さわること(Handgreiflichkeit)ができると言っている。すなわち、観測手段や実験手段があると言っている。ニーチェからみれば、観測や実験は労働だから、奴隷がする行為になる。自然科学をバカにしたつもりなのだろう。
ニーチェは、断章12で次のように言う。
「唯物論的原子論に関して言えば、これはあらゆるもののうちで最も完全に論駁されたものの一つである」(木場訳)
ここでの「唯物論的原子論」は、die materialistische Atomistikの訳である。ただ、この「原子論」は19世紀の原子論ではなく、古代ギリシアの「原子論」である。「たましい」も原子からできているとする、「原子論」である。
ニーチェは当時の化学や物理の原子論の進展をまったく知らなかったと思われる。
19世紀の化学では、原子の質量比や、分子を形作る原子数の構成が、実験的に求められ、1重結合、2重結合の概念もできていた。また、物理学では、イギリスのマックスウェル、オーストリアのボルツマンは気体分子運動論を提唱し、統計力学の道が開かれた。
ニーチェは、断章204で次のように言う。
科学は、哲学や神学の奴隷であったのに、いちはやく、神学から解放され、「科学は今では不遜となり無分別になって、ついには哲学に対して法則を与え、自己自らが今度は『主人』の役」を演じるに至っている。
ここでの「科学」は、Wissenschaftの訳である。ニーチェは、神学と哲学以外のすべての知識体系をWissenschaftと呼んでいる。ここでは、アリストテレス、プラトンを意識している。
ニーチェはすごく劣等感の強い男であったと思われる。時代の進展に取り残され、哲学者としても敬意を払われず、裕福だった牧師の父親にも劣等感をいだいている。
冒頭の断章1で、「真理への意志」(Der Wille zur Wahrheit)という異常な言葉をニーチェは吐く。これは「真理を探究しようとする意志」ではない。
これは、断章211の「真の哲学者は命令者であり、かつ立法者」で、「かくあるべし」と言うのだと通じる。自分の思いに世界を変えるのだと言っているのだ。
断章6で「これまでのあらゆる偉大な哲学」は、「その創設者の自己告白」であり、「一種の《覚え書き》」なのだと言う。
断章34で、「哲学者はこれまで地上において常にもっとも馬鹿にされてきた存在」として、「わるい性格」をもつ権利があると言う。
「いじけている」ニーチェとしか、言いようがない。このような男が、「自分の思いに世界を変えるのだ」と社会問題や道徳を論じるとトンデモナイことになる。