メタエンジニアの眼シリーズ(141)
TITLE: 「動的平衡」
書籍名;「動的平衡」[2009]
著者;福岡伸一 発行所;木楽舎
発行日;2009.2.25
初回作成日;R1.10.11 最終改定日;
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
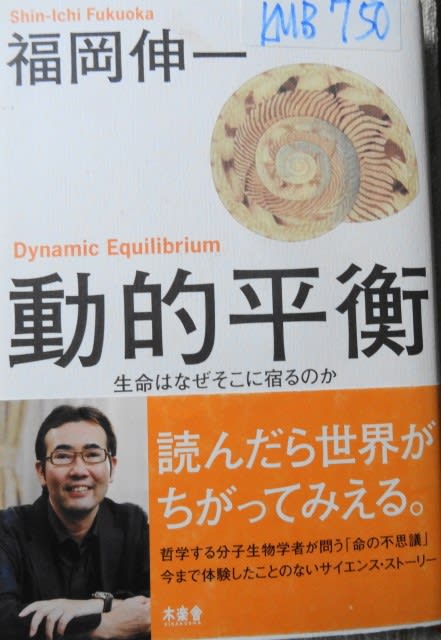
この本は、一時期話題に上ったが、その後は忘れていた。当時は、言葉の真意が良くわからずに、読むこともなかったのだが、近年(2017)小学館から新版が発行された。そこで、最初の版を読んでみることにした。その前に、「動的平衡」の意味を確かめる。色々な意味があるようで面白い。Wikipediaには次のようにある。
『動的平衡(dynamic equilibrium)とは、物理学・化学などにおいて、互いに逆向きの過程が同じ速度で進行することにより、系全体としては時間変化せず平衡に達している状態を言う。
系と外界とはやはり平衡状態にあるか、または完全に隔離されている(孤立系)かである。 なお、ミクロに見ると常に変化しているがマクロに見ると変化しない状態である、という言い方もできる。これにより他の分野でも動的平衡という言葉が拡大解釈されて使われるが、意味は正確には異なる。これについては他の意味の項を参照。』
とある。そこで、「他の意味」も引用する。
『他の意味;動的平衡という用語は、分野によっては、むしろ物理用語でいうところの「定常状態」を使うべき場合もある。定常状態とは、系が平衡状態にない外界と接している場合にのみ起こり、流れがあるが時間変化が見られない、すなわち系への出・入の速度が等しい状況をいう。
たとえば、経済において、資本のフローが一定であれば、安定した市場が成立する。また、生物の出生率と死亡率が同じ場合、個体数は変化しない。このように、経済学・生態学・人口学でも、本来とは少し異なる意味で、動的平衡という言葉が使われている。』
つまり、自然科学と人文・社会科学の両方にまたがる言葉なので、そこが面白い。ついでに、著者の福岡 伸一(日本の生物学者。青山学院大学教授。専攻は分子生物学。農学博士)についての記述もある。「福岡伸一の動的平衡」の項目がそれである。
『ルドルフ・シェーンハイマーの提唱した「生命の動的状態(dynamic state)」という概念を拡張し、生命の定義に動的平衡(dynamic equilibrium)という概念を提示し、「生命とは動的平衡にある流れである」とした。生物は動的に平衡な状態を作り出している。生物というのは平衡が崩れると、その事態に対してリアクション(反応)を起こすのである。そして福岡は、(研究者が意図的に遺伝子を欠損させた)ノックアウトマウスの(研究者の予想から見ると意外な)実験結果なども踏まえて、従来の生命の定義の設問は浅はかで見落としがある、見落としているのは時間だ、とし、生命を機械に譬えるのは無理があるとする。機械には時間が無く原理的にはどの部分から作ることもでき部品を抜き取ったり交換することもでき生物に見られる一回性というものが欠如しているが、生物には時間があり、つまり不可逆的な時間の流れがあり、その流れに沿って折りたたまれ、一度おりたたんだら二度と解くことのできないものとして生物は存在している、とした』
冒頭の「青い薔薇―はしがきにかえて」の短文が示唆に富んでいる。Fハカセが赤い薔薇をツユクサのような鮮やかな青に変えたいとして、遺伝子などをいじくりまわす。青くするための酵素群、赤くするメカニズムの除去、青を拒絶する酵素の除去、青い色素を安定化させる細胞内環境などである。
その結果、Fハカセは鮮やかな青い薔薇を咲かせた。しかし、ハカセはそれがどこから見てもツユクサだったことに気づかなかった、というわけである。この話は、生物が「動的平衡状態」でなければ成り立たないことを示しているように思う。
「プロローグ」として、「生物現象とは何か」が14ページにわたって書かれている。彼がアメリカ滞在中に実際に出会った様々な高名なバイオ学者の成功・失敗の実話だった。そして、最後にこのように結んでいる。バイオの先端研究は、とてつもない利益が期待されるベンチャーを育てるが、多くの場合それは一時的なものであった。
『しかし、それはどこまでも一時のニュースであり、多くの場合、まもなく色槌せたものとなり、次のニュースによって塗り替えられる。なぜだろうか。 それは、端的にいえば、バイオつまり生命現象が、本来的にテクノロジーの対象となり難いものだからである。工学的な操作、産業上の規格、効率よい再現性。そのようなものになじまないものとして、生命があるからだ。 では、いったい生命現象とは何なのか。それを私はいつも考える。』(pp.23)
生命体、すなわち人間はとてつもない数の細胞からできている。そして、その細胞は常に新しものと入れ替わっている。つまり、
『生命現象が絶え間ない分子の交換の上に成り立っていること、つまり動的な分子の平衡状態の上に生物が存在しうる』(pp.32)
この文がすべてを語っているように思う。そこから、「記憶とは何か」の論議が始まる。当時は、脳の中の記憶物質を突き止める研究が盛んだったのだが、それを真っ向から否定した人物がいた。それが、先に挙げた、ルドルフ・シェーンハイマーの提唱した「生命の動的状態」という概念であり、この著書は全体としてこの理論にそっている。
『すこし冷静に考えれば、常に代謝回転し続ける物質を記憶媒体にすることなどできるはずもない。だから、音楽やデータを記録する媒体として、我々は常により安定した物質を求め続けてきた。レコード、磁気テープ、CD、MD、HD……。 ほんの数日で分解されてしまう生体分子を素子として、その上にメモリーを書き込むことなど原理的に不可能だ。記憶物質は見つかっていないのではなく、存在しようがないのである。ヒトの身体を構成している分子は次々と代謝され、新しい分子と入れ替わっている。それは脳細胞といえども例外ではない。』(pp.34)
この論理からは、自分自身の「昔の記憶」について、面白い論理が展開されている。頭のどこかに記憶が刷り込まれているのではない。頭の中は、クリスマスツリーの豆電球のように考えればよいそうだ。
豆電球の回路が無数にあって、ある回路に電流を流すと、星座のような形が出てくる。それが昔の記憶だ。豆電球は古いものではなく、新しいものに取り換えられている。だから、記憶は過去のものではなく、現在の頭で新たに生成されたものということになる。
つまり、こういうことなのだと主張している。
『そこには因果関係があるのではなく、平衡状態があるにすぎない。私たちが「記憶の想起」と呼んでいるものも、実は一時点での平衡状態がもたらす効果でしかない。
大半の方がそうだと思うが、私たちは五年前や10年前の一年の過ぎ方がどうだったかなどと思い出すことすらできない。過去は恐ろしいほどにボンヤリしたものでしかないのである。 仮に「五年前にはこんなことがあり、1〇年前にはあんなことがあったなあ」と思いだすことはできても、それは日記なり写真なり記念品があるから、それを手がかりに過去の順番をかろうじて跡づけられるのであって、感覚としては、1〇年前のことが五年前のことよりも、より遠い昔のことだという実感を持つことはできない。』(pp.35)
このことが理解できると、後の章はその展開になっている。詳細は割愛する。
『汝とは「汝の食べた物」である、「消化」とは情報の解体』(pp.61)
『骨を調べれば食物がわかる』(pp.62)
『体重を増やさない食べ方』(pp.96)
人間の食物はすべて、かつては他の生物だった。その生物のたんぱく質が分解されて、新たな形に合成されて人体の細胞になる。そのことを色々な角度から述べている。このことから、『もう少し謙虚になるべきなのだ。私たちは、たとえ進化の歴史が何億年経過しようとも、中空の管でしかないのだかないのだから。』(pp.74)
そして、再び生命論に戻る。
『では、それを機械のように組み合わせれば、生命体となるだろうか。否である。合成した二万数千種の部品を混ぜ合わせても、そこには生命は立ち上がらない。それはどこまで行ってもミックス・ジュースでしかない。 ところが、私たち生命はその部品を使って現にいま生きている。ミクロな部品が組み合わさって、動き、代謝し、生殖し、思考までする。その生命現象においては、機械とは違って、全体は部分の総和以上の何ものかである。1+1は2ではなく、2プラスα。その プラスαは何か。それはどこから来るのか。』(pp.136)
『生物は死ぬと「生気」が離脱してその分、体重が軽くなるといったことが、かつでは真面目に議論されたのである。
もちろん、生気などというものはない。だが、プラスαはある。プラスαとは、端的にいえば、エネルギーと情報の出入りのことである。
生物を物質のレベルからだけ考えると、ミクロなパーツからなるプラモデルに見えてしまう。しかし、パーツとパーツの間には、エネルギーと情報がやりとりされている。それがプラスαである。』(pp.136-137)
このことは、テレビに例えられている。テレビを分解してもテレビの機能を理解することはできない。なぜならば、テレビは電気エネルギーと番組という情報が加わるからだ。
最後に「デカルトの罪」を述べている。
デカルトは、生命現象はすべて機械論的に説明可能だとした。(pp.226)
その考え方は、全世界に広がり、そこから、細胞操作や臓器売買が始まった。そして、ES細胞の激しい先陣争いが始まってしまった。
『果たして私たちの未来を幸福なものにしてくれるのだろうか。』(pp.228)
これが結論のように思えてくる。好きな区とも、人間が動物として生きられなくなることは、幸福とは思えない。
TITLE: 「動的平衡」
書籍名;「動的平衡」[2009]
著者;福岡伸一 発行所;木楽舎
発行日;2009.2.25
初回作成日;R1.10.11 最終改定日;
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
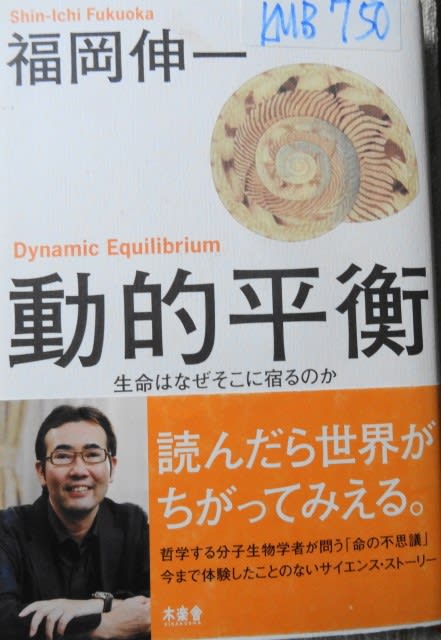
この本は、一時期話題に上ったが、その後は忘れていた。当時は、言葉の真意が良くわからずに、読むこともなかったのだが、近年(2017)小学館から新版が発行された。そこで、最初の版を読んでみることにした。その前に、「動的平衡」の意味を確かめる。色々な意味があるようで面白い。Wikipediaには次のようにある。
『動的平衡(dynamic equilibrium)とは、物理学・化学などにおいて、互いに逆向きの過程が同じ速度で進行することにより、系全体としては時間変化せず平衡に達している状態を言う。
系と外界とはやはり平衡状態にあるか、または完全に隔離されている(孤立系)かである。 なお、ミクロに見ると常に変化しているがマクロに見ると変化しない状態である、という言い方もできる。これにより他の分野でも動的平衡という言葉が拡大解釈されて使われるが、意味は正確には異なる。これについては他の意味の項を参照。』
とある。そこで、「他の意味」も引用する。
『他の意味;動的平衡という用語は、分野によっては、むしろ物理用語でいうところの「定常状態」を使うべき場合もある。定常状態とは、系が平衡状態にない外界と接している場合にのみ起こり、流れがあるが時間変化が見られない、すなわち系への出・入の速度が等しい状況をいう。
たとえば、経済において、資本のフローが一定であれば、安定した市場が成立する。また、生物の出生率と死亡率が同じ場合、個体数は変化しない。このように、経済学・生態学・人口学でも、本来とは少し異なる意味で、動的平衡という言葉が使われている。』
つまり、自然科学と人文・社会科学の両方にまたがる言葉なので、そこが面白い。ついでに、著者の福岡 伸一(日本の生物学者。青山学院大学教授。専攻は分子生物学。農学博士)についての記述もある。「福岡伸一の動的平衡」の項目がそれである。
『ルドルフ・シェーンハイマーの提唱した「生命の動的状態(dynamic state)」という概念を拡張し、生命の定義に動的平衡(dynamic equilibrium)という概念を提示し、「生命とは動的平衡にある流れである」とした。生物は動的に平衡な状態を作り出している。生物というのは平衡が崩れると、その事態に対してリアクション(反応)を起こすのである。そして福岡は、(研究者が意図的に遺伝子を欠損させた)ノックアウトマウスの(研究者の予想から見ると意外な)実験結果なども踏まえて、従来の生命の定義の設問は浅はかで見落としがある、見落としているのは時間だ、とし、生命を機械に譬えるのは無理があるとする。機械には時間が無く原理的にはどの部分から作ることもでき部品を抜き取ったり交換することもでき生物に見られる一回性というものが欠如しているが、生物には時間があり、つまり不可逆的な時間の流れがあり、その流れに沿って折りたたまれ、一度おりたたんだら二度と解くことのできないものとして生物は存在している、とした』
冒頭の「青い薔薇―はしがきにかえて」の短文が示唆に富んでいる。Fハカセが赤い薔薇をツユクサのような鮮やかな青に変えたいとして、遺伝子などをいじくりまわす。青くするための酵素群、赤くするメカニズムの除去、青を拒絶する酵素の除去、青い色素を安定化させる細胞内環境などである。
その結果、Fハカセは鮮やかな青い薔薇を咲かせた。しかし、ハカセはそれがどこから見てもツユクサだったことに気づかなかった、というわけである。この話は、生物が「動的平衡状態」でなければ成り立たないことを示しているように思う。
「プロローグ」として、「生物現象とは何か」が14ページにわたって書かれている。彼がアメリカ滞在中に実際に出会った様々な高名なバイオ学者の成功・失敗の実話だった。そして、最後にこのように結んでいる。バイオの先端研究は、とてつもない利益が期待されるベンチャーを育てるが、多くの場合それは一時的なものであった。
『しかし、それはどこまでも一時のニュースであり、多くの場合、まもなく色槌せたものとなり、次のニュースによって塗り替えられる。なぜだろうか。 それは、端的にいえば、バイオつまり生命現象が、本来的にテクノロジーの対象となり難いものだからである。工学的な操作、産業上の規格、効率よい再現性。そのようなものになじまないものとして、生命があるからだ。 では、いったい生命現象とは何なのか。それを私はいつも考える。』(pp.23)
生命体、すなわち人間はとてつもない数の細胞からできている。そして、その細胞は常に新しものと入れ替わっている。つまり、
『生命現象が絶え間ない分子の交換の上に成り立っていること、つまり動的な分子の平衡状態の上に生物が存在しうる』(pp.32)
この文がすべてを語っているように思う。そこから、「記憶とは何か」の論議が始まる。当時は、脳の中の記憶物質を突き止める研究が盛んだったのだが、それを真っ向から否定した人物がいた。それが、先に挙げた、ルドルフ・シェーンハイマーの提唱した「生命の動的状態」という概念であり、この著書は全体としてこの理論にそっている。
『すこし冷静に考えれば、常に代謝回転し続ける物質を記憶媒体にすることなどできるはずもない。だから、音楽やデータを記録する媒体として、我々は常により安定した物質を求め続けてきた。レコード、磁気テープ、CD、MD、HD……。 ほんの数日で分解されてしまう生体分子を素子として、その上にメモリーを書き込むことなど原理的に不可能だ。記憶物質は見つかっていないのではなく、存在しようがないのである。ヒトの身体を構成している分子は次々と代謝され、新しい分子と入れ替わっている。それは脳細胞といえども例外ではない。』(pp.34)
この論理からは、自分自身の「昔の記憶」について、面白い論理が展開されている。頭のどこかに記憶が刷り込まれているのではない。頭の中は、クリスマスツリーの豆電球のように考えればよいそうだ。
豆電球の回路が無数にあって、ある回路に電流を流すと、星座のような形が出てくる。それが昔の記憶だ。豆電球は古いものではなく、新しいものに取り換えられている。だから、記憶は過去のものではなく、現在の頭で新たに生成されたものということになる。
つまり、こういうことなのだと主張している。
『そこには因果関係があるのではなく、平衡状態があるにすぎない。私たちが「記憶の想起」と呼んでいるものも、実は一時点での平衡状態がもたらす効果でしかない。
大半の方がそうだと思うが、私たちは五年前や10年前の一年の過ぎ方がどうだったかなどと思い出すことすらできない。過去は恐ろしいほどにボンヤリしたものでしかないのである。 仮に「五年前にはこんなことがあり、1〇年前にはあんなことがあったなあ」と思いだすことはできても、それは日記なり写真なり記念品があるから、それを手がかりに過去の順番をかろうじて跡づけられるのであって、感覚としては、1〇年前のことが五年前のことよりも、より遠い昔のことだという実感を持つことはできない。』(pp.35)
このことが理解できると、後の章はその展開になっている。詳細は割愛する。
『汝とは「汝の食べた物」である、「消化」とは情報の解体』(pp.61)
『骨を調べれば食物がわかる』(pp.62)
『体重を増やさない食べ方』(pp.96)
人間の食物はすべて、かつては他の生物だった。その生物のたんぱく質が分解されて、新たな形に合成されて人体の細胞になる。そのことを色々な角度から述べている。このことから、『もう少し謙虚になるべきなのだ。私たちは、たとえ進化の歴史が何億年経過しようとも、中空の管でしかないのだかないのだから。』(pp.74)
そして、再び生命論に戻る。
『では、それを機械のように組み合わせれば、生命体となるだろうか。否である。合成した二万数千種の部品を混ぜ合わせても、そこには生命は立ち上がらない。それはどこまで行ってもミックス・ジュースでしかない。 ところが、私たち生命はその部品を使って現にいま生きている。ミクロな部品が組み合わさって、動き、代謝し、生殖し、思考までする。その生命現象においては、機械とは違って、全体は部分の総和以上の何ものかである。1+1は2ではなく、2プラスα。その プラスαは何か。それはどこから来るのか。』(pp.136)
『生物は死ぬと「生気」が離脱してその分、体重が軽くなるといったことが、かつでは真面目に議論されたのである。
もちろん、生気などというものはない。だが、プラスαはある。プラスαとは、端的にいえば、エネルギーと情報の出入りのことである。
生物を物質のレベルからだけ考えると、ミクロなパーツからなるプラモデルに見えてしまう。しかし、パーツとパーツの間には、エネルギーと情報がやりとりされている。それがプラスαである。』(pp.136-137)
このことは、テレビに例えられている。テレビを分解してもテレビの機能を理解することはできない。なぜならば、テレビは電気エネルギーと番組という情報が加わるからだ。
最後に「デカルトの罪」を述べている。
デカルトは、生命現象はすべて機械論的に説明可能だとした。(pp.226)
その考え方は、全世界に広がり、そこから、細胞操作や臓器売買が始まった。そして、ES細胞の激しい先陣争いが始まってしまった。
『果たして私たちの未来を幸福なものにしてくれるのだろうか。』(pp.228)
これが結論のように思えてくる。好きな区とも、人間が動物として生きられなくなることは、幸福とは思えない。









