花菖蒲の開花も終わり、来年に向けての株分け作業を紹介します。
 花は「五湖の遊」です(5号鉢)
花は「五湖の遊」です(5号鉢)


最初に花の咲いた茎を切り落とし水の中で根をほぐします。(散水ノズルをジェットにして用土を落とすと早いです)

用土を落とした状態です。

最初に切り落とした茎の部分から半分に切り分けます(この時、開花まで頑張り役目を終えた茶色の根があるはずですから取り除きます)

葉芽を一つづつ丁寧に切り離します。(作りたい数を決め大きめの葉芽(苗)にたくさん根が付くようにハサミを入れます。最初は
思うようにいかないと思いますが何度もやっている内にコツがつかめます。品種や株の状態にもよりますので経験値が必要な作業です)

新しい用土に植えつけるのですが、ここで花菖蒲の「裏と表」を意識して下さい。茎の後ろ(裏)に新しい根が見えます。つまり
新しい根は後ろ(裏)に伸びるため鉢植えの場合は、根が伸びるスペースを作って植えつけます。(苗の裏表に気を付けます)

だいたいですが根が広がるスペースを開けて植えつけた状態です。(植え付けは根が隠れるギリギリの浅植えが基本です。
私の経験では苗がグラつかないよう深植えにしても根は下や横へ伸び、上には張らず 結局用土を余分に使うことになります)

根が伸びる部分を広げて植えたつもりが苗が中心にきてしましましたが鉢の中では根のスペースは確保してあるはずです。
「五湖の遊」今回6苗できました。菖翁花の一つで貴重な品種ですが場所が狭いため2苗は廃棄しました。

今年の株分けは終了。約120種 424鉢(調子に乗って作りすぎました)

用土ですが2年の試験を経て、今年から土は使わずヤシガラピートと籾殻だけで作りましたが こちらは人柱的なところもあり
まだお勧めできません。一番簡単にできる鉢植え用用土は赤玉土の小玉と籾殻を7:3くらいで良いはずです。ピートモスは
調整ピートなら使えますが未調整のピートはpH4~4.5ですから使っちゃダメです。これは経験者としてハッキリ言えます。
よくネットで苗を購入した時、根をピートモスで固められた状態で送られてきたときは絶対にピートモスは洗い流して下さい。
私も経験ありますが、ピートモスで固めた状態のまま鉢に植えた場合 根の生育は著しく遅れ、最悪の場合根が死に枯れます。
あくまでも未調整ピートの場合ですが、調整か未調整かは酸度計測しないと分かりませんので洗い流すのがベストです。
参考までにヤシガラピートと籾殻のpHは5.5~6.0くらいでヤシガラピートは商品にもよりますが塩分(EC)がかなり高いです。


![]()










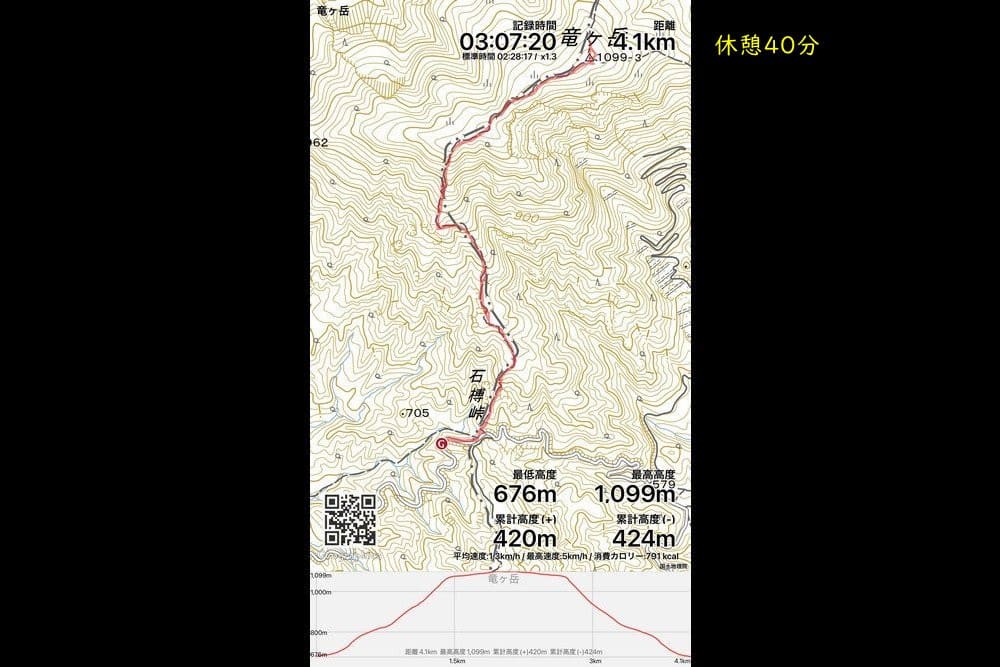















 花は「五湖の遊」です(5号鉢)
花は「五湖の遊」です(5号鉢)














