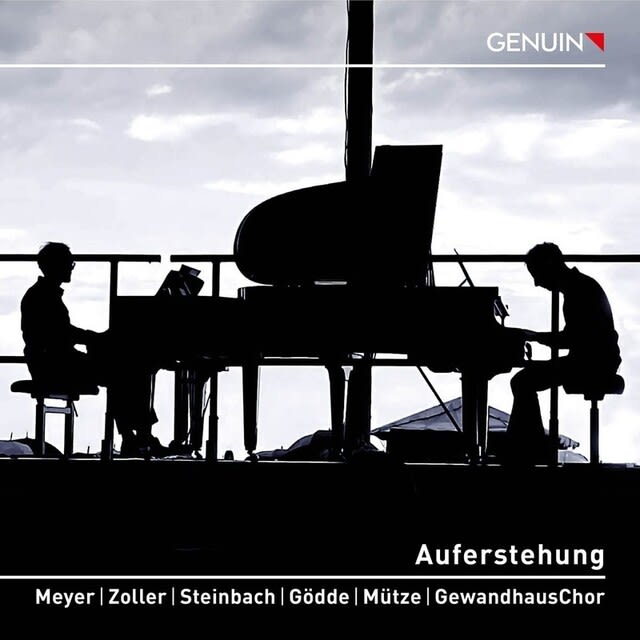チケットを頂いたので習志野フィルハーモニー管弦楽団の
第104回定期演奏会を聴きに行ってきました。

チャイコフスキー:幻想序曲『ロメオとジュリエット』
リヒャルト・シュトラウス:4つの最後の歌
チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調
指揮:湯川紘惠
独唱:中江早希(ソプラノ)
所謂アマチュアオーケストラ(市民オーケストラ)ですが、
今年創立55周年の伝統あるオーケストラで想像の10倍上手かったです。
チャイコフスキーの2曲はコンサートで何度も聴いたことがありますが
リヒャルト・シュトラウスは初めてです。
『4つの最後の歌』
第1曲:春
再2曲:9月
第3曲:眠りにつくとき
第4曲:夕映えの中で
リヒャルト・シュトラウスの『4つの最後の歌』は熱狂的ファンの多い曲です。
クラシック音楽の中でも「最も美しい歌」などと言われることがありますが
正直、独唱曲はあまり好きではないので
CDで聴いてもあまり心を動かされることはありませんでした。
ですが、生で聴いて考えが改まりました。
なんと美しい歌なんでしょう。
第1曲の途中から、涙が溢れてきました。
というよりも4曲を通して、ほぼ号泣。
何も考えず目を閉じて、只々美しい音色に酔い痴れました。
まさに天上の美しさ。
今更ながら、こんなに感動できる曲に出逢えるとは思っていませんでした。
思い出に残るいいコンサートでした。
第104回定期演奏会を聴きに行ってきました。

チャイコフスキー:幻想序曲『ロメオとジュリエット』
リヒャルト・シュトラウス:4つの最後の歌
チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調
指揮:湯川紘惠
独唱:中江早希(ソプラノ)
所謂アマチュアオーケストラ(市民オーケストラ)ですが、
今年創立55周年の伝統あるオーケストラで想像の10倍上手かったです。
チャイコフスキーの2曲はコンサートで何度も聴いたことがありますが
リヒャルト・シュトラウスは初めてです。
『4つの最後の歌』
第1曲:春
再2曲:9月
第3曲:眠りにつくとき
第4曲:夕映えの中で
リヒャルト・シュトラウスの『4つの最後の歌』は熱狂的ファンの多い曲です。
クラシック音楽の中でも「最も美しい歌」などと言われることがありますが
正直、独唱曲はあまり好きではないので
CDで聴いてもあまり心を動かされることはありませんでした。
ですが、生で聴いて考えが改まりました。
なんと美しい歌なんでしょう。
第1曲の途中から、涙が溢れてきました。
というよりも4曲を通して、ほぼ号泣。
何も考えず目を閉じて、只々美しい音色に酔い痴れました。
まさに天上の美しさ。
今更ながら、こんなに感動できる曲に出逢えるとは思っていませんでした。
思い出に残るいいコンサートでした。