ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団演奏の、
マーラー交響曲全集のDVD(11枚組)を買いました。
第1番から第9番と「大地の歌」、第10番(クック版全曲)、
それに交響詩「葬礼」が収録されています。
マーラー生誕150年/没後100年に合わせて開催された"マーラー・チクルス"
の演奏会を収録したライブ盤で、指揮者は
第1番:ダニエル・ハーディング
第2番:マリス・ヤンソンス
第3番:マリス・ヤンソンス
第4番:イヴァン・フィッシャー
第5番:ダニエレ・ガッティ
第6番:ロリン・マゼール
第7番:ピエール・ブーレーズ
第8番:マリス・ヤンソンス
第9番:ベルナルド・ハイティンク
第10番:エリアフ・インバル
「大地の歌」と「葬礼」:ファビオ・ルイージ
です。
前々から気にはなっていたのですが、中古で8,000円で売ってたので。
古い人間にとっては「ロイヤル・コンセルトヘボウ」よりも
「アムステルダム・コンセルトヘボウ」の方が馴染み深いのですか、
例の如く"物識りウィキさん"によると
1988年に創立100周年を迎え、ベアトリクス女王より「ロイヤル」の称号を下賜され、
現在の名称「ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団」に改称
とあります。
なるほど、レニングラード・フィル→サンクトペテルブルク・フィルとは
全然違うのですね。
コンセルトヘボウの演奏は、CDでは色々聴いていますが、
オケの実力は?というとどの辺に位置するのか、イマイチピンとこない。
まあ個人的には「コンセルトヘボウだから」と好んで買うことはなく・・・。
取り敢えず第1番と第5番を聴いた(観た)のですが、なんと素晴らしい演奏!
恥ずかしながら、こんなに実力のあるオケとは露知らず、ご無礼をばお許しを。
第1番指揮のダニエル・ハーディングの演奏は初めて聴きました。
CDのジャケット写真から勝手に「カッコつけタイプか?」と想像していましたが、
意外に指揮振りは激しくて、それに結構「顔で表現する」タイプ?
表情豊かで、ちょっとアーノンクールを思い出してしまいました。
第5番指揮のダニエレ・ガッティという方は全く存じ上げなかったのですが、
これまた、細部までコントロールされた素晴らしい演奏!!
演奏後の表情とかを見ると、オケもガッティ自身も会心の出来だったのでは。
マーラーの交響曲の面白さは「演奏風景込み」だと思うので、
こうやってまとめて観られる(聴ける)のは、大変嬉しいですね。
最近は比較的古い録音のCD全集とか、びっくりするような安価で売ってますが、
このDVD全集はマーラー入門編としてもうってつけだと思います。
ブルーレイ盤もありますが、もう少し安くなったらこっちも買ってしまうかも。
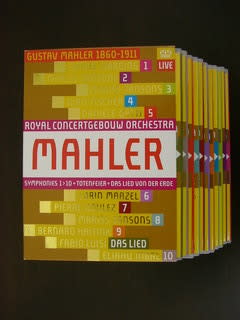
この色使い、デザインセンスもオランダぽくてイイです。
マーラー交響曲全集のDVD(11枚組)を買いました。
第1番から第9番と「大地の歌」、第10番(クック版全曲)、
それに交響詩「葬礼」が収録されています。
マーラー生誕150年/没後100年に合わせて開催された"マーラー・チクルス"
の演奏会を収録したライブ盤で、指揮者は
第1番:ダニエル・ハーディング
第2番:マリス・ヤンソンス
第3番:マリス・ヤンソンス
第4番:イヴァン・フィッシャー
第5番:ダニエレ・ガッティ
第6番:ロリン・マゼール
第7番:ピエール・ブーレーズ
第8番:マリス・ヤンソンス
第9番:ベルナルド・ハイティンク
第10番:エリアフ・インバル
「大地の歌」と「葬礼」:ファビオ・ルイージ
です。
前々から気にはなっていたのですが、中古で8,000円で売ってたので。
古い人間にとっては「ロイヤル・コンセルトヘボウ」よりも
「アムステルダム・コンセルトヘボウ」の方が馴染み深いのですか、
例の如く"物識りウィキさん"によると
1988年に創立100周年を迎え、ベアトリクス女王より「ロイヤル」の称号を下賜され、
現在の名称「ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団」に改称
とあります。
なるほど、レニングラード・フィル→サンクトペテルブルク・フィルとは
全然違うのですね。
コンセルトヘボウの演奏は、CDでは色々聴いていますが、
オケの実力は?というとどの辺に位置するのか、イマイチピンとこない。
まあ個人的には「コンセルトヘボウだから」と好んで買うことはなく・・・。
取り敢えず第1番と第5番を聴いた(観た)のですが、なんと素晴らしい演奏!
恥ずかしながら、こんなに実力のあるオケとは露知らず、ご無礼をばお許しを。
第1番指揮のダニエル・ハーディングの演奏は初めて聴きました。
CDのジャケット写真から勝手に「カッコつけタイプか?」と想像していましたが、
意外に指揮振りは激しくて、それに結構「顔で表現する」タイプ?
表情豊かで、ちょっとアーノンクールを思い出してしまいました。
第5番指揮のダニエレ・ガッティという方は全く存じ上げなかったのですが、
これまた、細部までコントロールされた素晴らしい演奏!!
演奏後の表情とかを見ると、オケもガッティ自身も会心の出来だったのでは。
マーラーの交響曲の面白さは「演奏風景込み」だと思うので、
こうやってまとめて観られる(聴ける)のは、大変嬉しいですね。
最近は比較的古い録音のCD全集とか、びっくりするような安価で売ってますが、
このDVD全集はマーラー入門編としてもうってつけだと思います。
ブルーレイ盤もありますが、もう少し安くなったらこっちも買ってしまうかも。
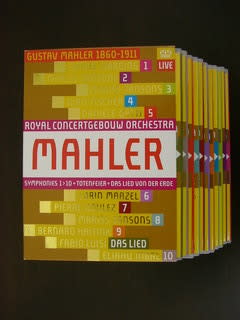
この色使い、デザインセンスもオランダぽくてイイです。
























